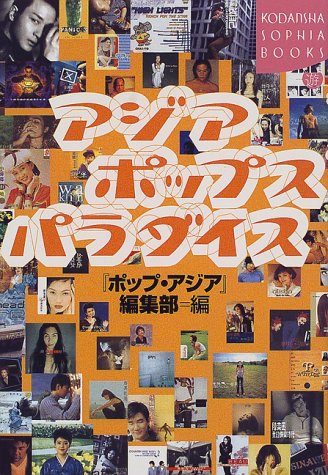1 0 0 0 OA 八戸南部家の読本収集
- 著者
- 大高 洋司
- 出版者
- 読本研究の会
- 雑誌
- 読本研究新集 (ISSN:1346874X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.137-155, 2014 (Released:2022-02-28)
1 0 0 0 OA Unpaywallを利用した日本におけるオープンアクセス状況の調査
- 著者
- 西岡 千文 佐藤 翔
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.31-50, 2021-02-28 (Released:2021-03-26)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 3 1
本稿は Unpaywall を利用して日本と世界のオープンアクセス(OA)状況を調査した.日本の調査では Unpaywall と Scopus に収録されている日本の著者による雑誌論文約 200 万件,世界の調査では Unpaywall に収録されている雑誌論文約 8,000 万件を対象とした.結果,日本と世界の OA の割合はそれぞれ 41.83%, 29.77%であることがわかった.日本の割合の高さの要因は,過去に出版された論文の多くがブロンズであ ることである.近年の傾向としてゴールドの割合の上昇が観察された.機関リポジトリで公開されている論 文の割合は 2000 年から 2010 年にかけて増加しているものの,2010 年以降は横ばいで約 5%である.2010 年以降の機関リポジトリのみで OA である論文の割合は約 1.5%である.グリーン OA を効率よく推進するためにも,各機関がそれぞれの OA の状況を継続的に把握できるような仕組みが必要である.
1 0 0 0 OA 歯科における再生医療 : 現状と将来の展望
- 著者
- 春日井 昇平
- 出版者
- 日本再生歯科医学会
- 雑誌
- 日本再生歯科医学会誌 (ISSN:13489615)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.3-11, 2003 (Released:2005-06-03)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
歯科では口腔組織の欠損部を材料により補填し, 機能を回復する治療法がおこなわれている. 一方, 喪失あるいは機能の低下した組織や臓器を再生する再生医療が注目されている. 1920年にHermannが水酸化カルシウムを断髄面に使用したのが歯科領域での再生医療の始まりとされている. その後, 1980年代になってGTR法とGBR法が報告され, 1990年代に入って仮骨延長法の口腔領域での適用がおこなわれた. 1990年代の後半には, Emdogainによる歯周組織の再生, rhBMPによる骨増加法, PRPによる骨増加法についての臨床報告がなされた. 現在FGF2の歯周組織の再生への効果について臨床試験がおこなわれている. 一方, 歯科領域での細胞を用いた再生治療として, 粘膜の再生, 顎骨の再生, 歯周組織の再生が試みられており, さらに歯の再生プロジェクトも開始されている. 再生医療が社会に受け入れられるためには確実な治療効果と共に, 安全性と簡便性さらに経済的な利点も要求されると考えられる.
1 0 0 0 アジアポップスパラダイス
- 著者
- 『ポップ・アジア』編集部編
- 出版者
- 講談社
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 OA 夏秋季,海岸植生上にみられるコブノメイガ,シロオビノメイガ成虫集団
- 著者
- 宮原 義雄
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.21-27, 1990-02-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 2
コブノメイガ,シロオビノメイガについて,寄主植物の生育しない海岸植生上に休止する成虫を,捕虫網で採集し,雌雄別個体数と雌成虫は交尾率を調べた。両種とも夏秋季を通じて採集され,採集虫の性比は,雌雄の偏りはなく,交尾率はコブノメイガ8.0∼20.9%,シロオビノメイガ9.4∼19.6%と低く,卵巣未発育で,かつ,翅の傷みの少ない個体で占められた。両種成虫は日没後半時間で飛び立ち,翌日になると,再び同じ場所に休止する成虫がみられ,移動中の一時的着地と考えられた。次に,シロオビノメイガについて,寄主植物の豊富な畑地内で同様に調べた。野生寄主イヌビユ上の成虫は,採集日により交尾率が著しく変動したが,イネ科雑草上の成虫は,秋季を通じ81.5%の高い交尾率で産卵中の個体群と考えられた。これら移動行動にみられる共通した特徴から,シロオビノメイガもコブノメイガ同様,移動性昆虫と考えられた。
1 0 0 0 OA 2010 年のテンサイにおける飛来性害虫シロオビノメイガの多発生と効果的薬剤の検討
- 著者
- 岩崎 暁生 青木 元彦 妹尾 吉晃
- 出版者
- 北日本病害虫研究会
- 雑誌
- 北日本病害虫研究会報 (ISSN:0368623X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.62, pp.194-198, 2011-12-27 (Released:2017-12-20)
- 参考文献数
- 10
In the summer and autumn of 2010, a mass outbreak of the beet webworm Spoladea recurvalis in sugar beet occurred throughout the entire sugar beet cultivation area of Hokkaido, the northern island of Japan. Serious damage was incurred in mid-August in the southern area, in mid to late August in the central area and the Tokachi district of the eastern area, and after mid-September in the Okhotsk district of the eastern area. Through field research in the central area, the migration period of adult moths was estimated to be mid-July. The early and/or mass migration of moths in addition to the higher summer temperature suitable for the development of the pest from their immature stages might accelerate the unusual mass occurrence of the pest throughout the year. Several insecticides mainly belonging to organophosphates and synthetic pyrethroids were found to be less effective on middle-to-late instar larvae in both insect dipping and diet dipping experiments. Insect growth regulators, on the other hand, were found to be effective for the control of larvae of the pest on sugar beet fields even under such mass occurrence.
1 0 0 0 OA 森林に加入する鳥糞由来の栄養塩-質と量からの考察-
- 著者
- 藤田 素子 小池 文人
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第52回日本生態学会大会 大阪大会
- 巻号頁・発行日
- pp.728, 2005 (Released:2005-03-17)
都市の森林における,窒素(N)及びリン(P)の鳥類の排泄物によるランドスケープ内への輸送について報告する。動物(主に魚類及びそれを採餌する哺乳類、魚食性鳥類)によるランドスケープ間の物質の移動が注目されているが、鳥類は都市およびその近郊においても栄養塩の移動をもたらしていると予想される。横浜市の6つの孤立林内に5m2のメッシュシートを数個設置し、落下した鳥糞を数日後に回収し、C%、N%、P%を測定した。更に、加入する栄養塩の起源を推定するために、NとPの構成比や安定同位体比δ15N及びδ13Cを季節・場所ごとに比較した。森林に加入したP(0-11.8kg/ha/ yr)を他の主な経路と比較すると、風化によるもの(0.05-1.0kg/ha/yr)や降水起源(0.2-0.9kg/ha/yr)よりも有意に大きく、都市林に生息する鳥類、特にねぐらをつくるカラス類の貢献度が高いことが明らかになった。秋にはCが多くNPの少ない植物質の糞が多く、夏にはNの多い昆虫質の糞であった。越冬期にはPが多く、特にカラスのねぐらとなる常緑樹林ではδ15Nが最も高かった(平均4.89)ため、哺乳類・鳥類などの動物質の餌を食べていると予想された。δ15Nは落葉樹林の鳥糞で最も低い値(平均0.62)を示しため、より植物食の鳥が多かったと考えられる。繁殖期の鳥類はテリトリーをもつため、採餌する昆虫由来の栄養塩は数百m以内から運搬されたことが予想される。一方で越冬期には、カラスはねぐらから8km以上離れた餌場への移動が確認されているなど、その採食範囲は広くなっていると考えられる。カラス類によりゴミ由来の栄養塩が都市林に運ばれている可能性もある。
1 0 0 0 OA ラコサミドによる発作性心房細動及び徐脈頻脈症候群が疑われた一症例とTDMの活用
- 著者
- 相原 史子 蓑毛 翔吾
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.44-52, 2021 (Released:2021-11-05)
- 参考文献数
- 15
ラコサミド (lacosamide: LCM)は、電位依存性Naチャネルの緩徐な不活性化を選択的に促進することにより過興奮状態にある神経細胞膜を安定化させる抗けいれん薬である。治療濃度域が確立されていないとされ、TDM(Therapeutic Drug Monitoring)の施行は一般的ではない。今回、LCM 300 mg/dayで投与中、てんかん発作による意識障害を主訴に救急搬送された61歳代男性の治療経過中に、発作性心房細動・徐脈頻脈症候群が出現し、病棟担当薬剤師が血漿中LCM濃度測定を提案、結果を薬物動態の特徴から解析・報告した症例を経験したので報告する。LCMは血漿中濃度上昇に伴い有害事象の発現頻度が増加することから、腎機能低下が認められる症例には、予測されるクリアランスの低下を基にした用量調節や、血漿中濃度測定結果を基にした評価が必要である。血漿中濃度の参考値として、臨床試験結果の活用が可能である。有効性と忍容性が確認できた個々のLCM血漿中濃度の把握は、薬物動態変化時の用量調節に有用と考えられることから、積極的なTDMの活用が望まれる。
1 0 0 0 OA 家族性高コレステロール血症のリスク評価と管理
- 著者
- 小倉 正恒 斯波 真理子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本冠疾患学会
- 雑誌
- 日本冠疾患学会雑誌 (ISSN:13417703)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.42-45, 2018 (Released:2018-03-26)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 神経変性疾患と生体微量金属代謝
- 著者
- 栗田 尚佳 位田 雅俊 保住 功
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.150, no.1, pp.29-35, 2017 (Released:2017-07-07)
- 参考文献数
- 52
亜鉛(Zn),銅(Cu),鉄(Fe)などの生体内微量金属元素は,酵素をはじめとする多くのタンパク質の活性中心となるため,生命活動を行う上で必要不可欠である.それぞれの元素において,過剰症,欠乏症が存在するため,生体内外における適切な調節が必要である.脳内においても,これらの微量元素は,神経系の調節に重要な役割を果たしている.したがって,微量金属元素の生体内恒常性の破綻は,脳神経系への影響を引き起こす可能性がある.これまでにアルツハイマー病(Alzheimer’s disease),パーキンソン病(Parkinson’s disease)および筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis)などの神経変性疾患の発症と,微量金属元素の恒常性変化との関連が示唆されている.これらの知見を基に,金属キレート剤についての,疾患モデルを用いた治療研究も成されている.本総説では,神経変性疾患と金属トランスポーターをはじめとする調節因子との関わりについて,我々の知見を含めて,細胞内ストレス応答および生体内微量金属代謝異常という観点から概説する.
- 著者
- Masahito Michikura Masatsune Ogura Mika Hori Kota Matsuki Hisashi Makino Kiminori Hosoda Mariko Harada-Shiba
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.11, pp.1603-1612, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 4 10
Aims: Achilles tendon (AT) xanthomas are a specific physical finding of familial hypercholesterolemia (FH) and AT thickness has been used for its diagnosis and evaluation of its severity. Recently, we reported that the AT of FH patients was softer than that of non-FH patients and the combined use of a cut-off value for AT softness with that for AT thickness improved diagnostic accuracy. However, an association between AT softness and severity of atherosclerosis has not been reported. Accordingly, the present study aimed to investigate whether AT softness was associated with carotid atherosclerosis and presence of atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) in FH.Methods: The AT of 176 genetically diagnosed FH patients and 98 non-FH patients was examined to measure AT thickness and the elasticity index (EI) as an indicator for assessing AT softness using ultrasonography.Results: Increased age was associated with AT softness, and overweight was negatively related to AT softness. There were significant inverse correlations between EI and maximum and mean intima-media thickness (IMT) within the common carotid artery only among FH patients. In multiple linear regression analysis, although the relationship between EI and mean IMT was attenuated, the association between EI and maximum IMT remained robust. In logistic regression analysis adjusted for age, sex and traditional cardiovascular risk factors (smoking history, presence of hypertension, presence of diabetes mellitus, overweight, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, and Log triglycerides), EI was associated with presence of ASCVD (Odds ratio per 1-SD increase, 0.37; 95% CI, 0.15 – 0.86; P=0.0252).Conclusion: The degree of lipid deposition in the AT of FH patients could be assessed by its thickness as well as its softness. AT softness is not only useful in diagnosing FH but is also associated with the severity of carotid atherosclerosis and presence of ASCVD. In addition, these findings suggest that AT softness would be helpful in risk assessment for FH patients.
- 著者
- Mariko Harada-Shiba Junya Ako Atsushi Hirayama Masato Nakamura Atsushi Nohara Kayoko Sato Yoshitaka Murakami Ryusuke Koshida Asuka Ozaki Hidenori Arai
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.8, pp.1201-1212, 2022-08-01 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 3 7
Aim: Genetic testing can provide a definitive diagnosis of familial hypercholesterolemia (FH). However, accessibility of genetic testing may be limited in certain countries where it is not considered “standard of care,” including Japan. In addition, mutations responsible for FH cannot be identified in approximately 30% of patients. Methods: EXPLORE-J is a multicenter, prospective, observational study of patients presenting with acute coronary syndrome (ACS). The genetic data were analyzed and adjudicated as pathogenic, indeterminate, or nondetectable pathogenic variant.Results: Of 1,944 patients, 431 underwent genetic screening. Overall, most patients had nonpathogenic variants of LDLR, LDLRAP1, or PCSK9 (n=396, 91.9%). Of the 25 (5.8%) patients with pathogenic variants, variants of the LDLR gene and the PCSK9 gene were seen in 10 and 15 patients, respectively. Indeterminate variants were observed in 10 (2.3%) patients. Of the 431 patients, eight (1.9%) met the criteria for a diagnosis of FH using the Japanese Atherosclerosis Society (JAS) 2017 guidelines. When genetic data were incorporated, 33 (7.7%) patients met the JAS guidelines. No patients with FH pathogenic variants satisfied the JAS clinical criteria for a diagnosis of FH.Conclusions: The results revealed a higher prevalence of genetic mutations of FH among Japanese patients with ACS and a low sensitivity of the FH diagnostic criteria of the JAS 2017 guidelines. These findings highlight the difficulties of FH diagnosis in patients with ACS in the acute phase and suggest the importance of genetic testing and family history.
- 著者
- Mariko Harada-Shiba Hidenori Arai Shinichi Oikawa Takao Ohta Tomoo Okada Tomonori Okamura Atsushi Nohara Hideaki Bujo Koutaro Yokote Akihiko Wakatsuki Shun Ishibashi Shizuya Yamashita
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.12, pp.1043-1060, 2012 (Released:2012-12-20)
- 参考文献数
- 85
- 被引用文献数
- 144 146
Familial hypercholesterolemia (FH) is a highly prevalent autosomal dominant hereditary disease, generally characterized by three major signs, hyper-low-density-lipoprotein (LDL) cholesterolemia, tendon/skin xanthomas and premature coronary artery disease (CAD). Because the risk of CAD is very high in these patients, they should be identified at an early stage of their lives and started on intensive treatment to control LDL-cholesterol. We here introduce a new guideline for the management of FH patients in Japan intending to achieve better control to prevent CAD. Diagnostic criteria for heterozygous FH are 2 or more of 1) LDL-cholesterol ≥180 mg/dL, 2) tendon/skin xanthoma(s), and 3) family history of FH or premature CAD within second degree relatives, for adults; and to have both 1) LDL-cholesterol ≥140 mg/dL and 2) family history of FH or premature CAD within second degree relatives, for children. For the treatment of adult heterozygous FH, intensive lipid control with statins and other drugs is necessary. Other risks of CAD, such as smoking, diabetes mellitus, hypertension etc., should also be controlled strictly. Atherosclerosis in coronary, carotid, or peripheral arteries, the aorta and aortic valve should be screened periodically. FH in children, pregnant women, and women who wish to bear a child should be referred to specialists. For homozygotes and severe heterozygotes resistant to drug therapies, LDL apheresis should be performed. The treatment cost of homozygous FH is authorized to be covered under the program of Research on Measures against Intractable Diseases by the Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare.
1 0 0 0 OA Optimal Cut-off Points of Triglycerides for Cardiovascular Disease Prediction in Japanese Population
- 著者
- Aya Hirata
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.105-106, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA アメリカ課外活動成立過程に関する一考察 生徒の自治活動を学校内化するロジック
- 著者
- 猪股 大輝
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.2, pp.248-261, 2023 (Released:2023-09-02)
19世紀末から20世紀前半のアメリカにおいて、学校外の施設や街頭など様々な場所における遊びや仲間関係の中で普遍的に行われてきた生徒の自治活動を「学校内化」した課外活動が取り組まれるようになった。本稿は、この「学校内化」を実現したロジックを分析することで、課外活動成立過程を通貫する歴史的性格を考察し、これらの取り組みの影響下において今日も取り組まれる特別活動のあり方に対する示唆を提起した。
1 0 0 0 OA 電磁波の生体に及ぼす影響と安全基準
- 著者
- 雨宮 好文
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.831-836, 1991-07-20 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 13
電磁波は熱作用と非熱作用により生体に影響を与えるが, 熱作用を主な対象として電磁界強度を制限するための安全基準が各国で策定されている.現状では, これを越えるレベルの電磁波を放出しているデバイスもあり, 安全基準の運用に当たっては, さらにきめ細かい定め (電波を安心して使ってもらうためのマニュアル) を作っておく必要がある.
1 0 0 0 沖縄県与那国島におけるヤエヤマハシカグサ(アカネ科)の再発見
- 著者
- 内貴 章世 仲宗根 忠樹 大井・東馬 哲雄 米倉 浩司 阿部 篤志
- 出版者
- The Editorial Board of The Journal of Japanese Botany
- 雑誌
- 植物研究雑誌 (ISSN:00222062)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.3, pp.134-139, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
- 参考文献数
- 15
国内では沖縄県与那国島にのみ分布するヤエヤマハシカグサExallage auriculariaが約40年ぶりに再発見されたので報告する.近縁種を含めた分子系統解析を行ったところ,先行研究と同じく本種は単系統ではないことが示唆され,与那国のものはタイやフィジーに分布するものと近縁であることが示された.本種は形態が多型的で種内分類群が提唱されたことがあり,種内および近縁種との関係性を明らかにするためにはさらなる解析が必要である.
1 0 0 0 OA ナノ粒子化による金の触媒作用創出:現代の錬金術
- 著者
- 春田 正毅
- 出版者
- 一般社団法人 日本真空学会
- 雑誌
- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.11, pp.721-726, 2008 (Released:2009-01-15)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3 5
Gold has long been neglected as a catalyst because of its chemical inertness. However, when gold is deposited as nanoparticles on carbon and polymer materials as well as on base metal oxides and hydroxides, it exhibits unique catalytic properties for many reactions such as CO oxidation at a temperature as low as 200 K, gas phase direct epoxidation of propylene, and aerobic oxidation of glucose to gluconic acid. The structure-catalytic activity correlations are discussed with emphasis on the contact structure, support selection, and the size control of gold particles. Gold clusters with diameters smaller than 2 nm are expected to exhibit novel properties in catalysis, optics, and electronics depending on the size (number of atoms), shape, and the electronic and chemical interaction with the support materials. The above achievements and attempts can be regarded as a modern alchemy that creates valuables by means of the noblest element with little practical use.
1 0 0 0 OA 排便障害における骨盤底機能と姿勢に関する研究
- 著者
- 槌野 正裕 濱邊 玲子 山下 佳代 辻 順行 高野 正博
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0570, 2007 (Released:2007-05-09)
【はじめに】 近年,排泄障害に関する研究が進み,排泄障害における骨盤底機能障害の関与が示唆されている.また,臨床の現場では,排泄障害を有する患者において,脊椎の視診において,腰椎の生理的前彎の減少や骨盤の後傾など,姿勢制御機構の障害が示唆される症例を多く経験する.今回われわれは,排便障害を有する患者における骨盤底機能と姿勢に関して調査を行ったので報告する.【対象と方法】 2004年4月から2005年4月までの期間で,排便障害を主訴として当院を受診した70歳以下の42例(男性13例,女性29例,平均年齢54歳±16歳)を対象とした.方法は,まずDefecography(排便造影)検査を通して,骨盤底機能障害の指標となるPerineal Descent (以下PD)を,擬似便を直腸内に注入した後ポータブルトイレ上座位にて,安静時,肛門収縮時,怒責時の3動態における腰部骨盤帯部の単純X線側面像を撮影し,その画像上で恥骨下縁と尾骨下縁を結んだ線から肛門縁までの距離を測定した.更に肛門内圧を行い,左下側臥位にて,圧センサー(スターメディカル社製直腸肛門機能検査キットGMMS-200)を用いて,安静時の肛門内圧(以下静止圧)と外肛門括約筋随意収縮時の肛門内圧(以下随意圧)を測定した.姿勢に関しては,仰臥位にて安静時の腰部骨盤帯部MRIT1 saggital像を撮影し,その画像上で腰椎前彎角度と仙骨角度を計測した.診断には安静時におけるPDが50mm以上を骨盤底機能障害群(以下E群),PDが50mm未満の骨盤底機能正常群(以下C群)として統計学的に比較した.なお統計学的解析にはMann-Whitney’s U testを用い,P値<0.01は有意とした.【結果】 C群25例(男性11例、女性14例、平均年齢53±16歳),E群17例(男性2例、女性15例、平均年齢54±15歳)では,両群間で平均年齢と年齢分布に有意差はなかった.C群と比較してE群は女性に多かった.肛門内圧に関して,静止圧,随意圧は, C群では91.5±34.9,273.4±143.7,E群では62.1±33.7,140.8±108.1で,ともにC群に対してE群で有意に低下していた.姿勢に関しては,腰椎前彎角度,仙骨角度ともにC群が39.8±8.5,37.0±6.6,E群が31.4±8.5,30.9±6.3で,ともにC群に対してE群で有意に減少していた.【考察】 排便障害を有する患者のなかには骨盤底機能が障害されている症例が存在し,それらの症例において認められる肛門内圧の低下は排便障害の一因となっていることが示唆された.さらに,骨盤底機能障害を有する症例において認められる腰椎前彎角度および仙骨角度の減少は,姿勢と骨盤底機能との関連性を示唆するものであり,骨盤後傾位における骨盤底筋群への伸張負荷の増大など,姿勢制御機構の障害による骨盤底機能障害発生の可能性が考えられた.