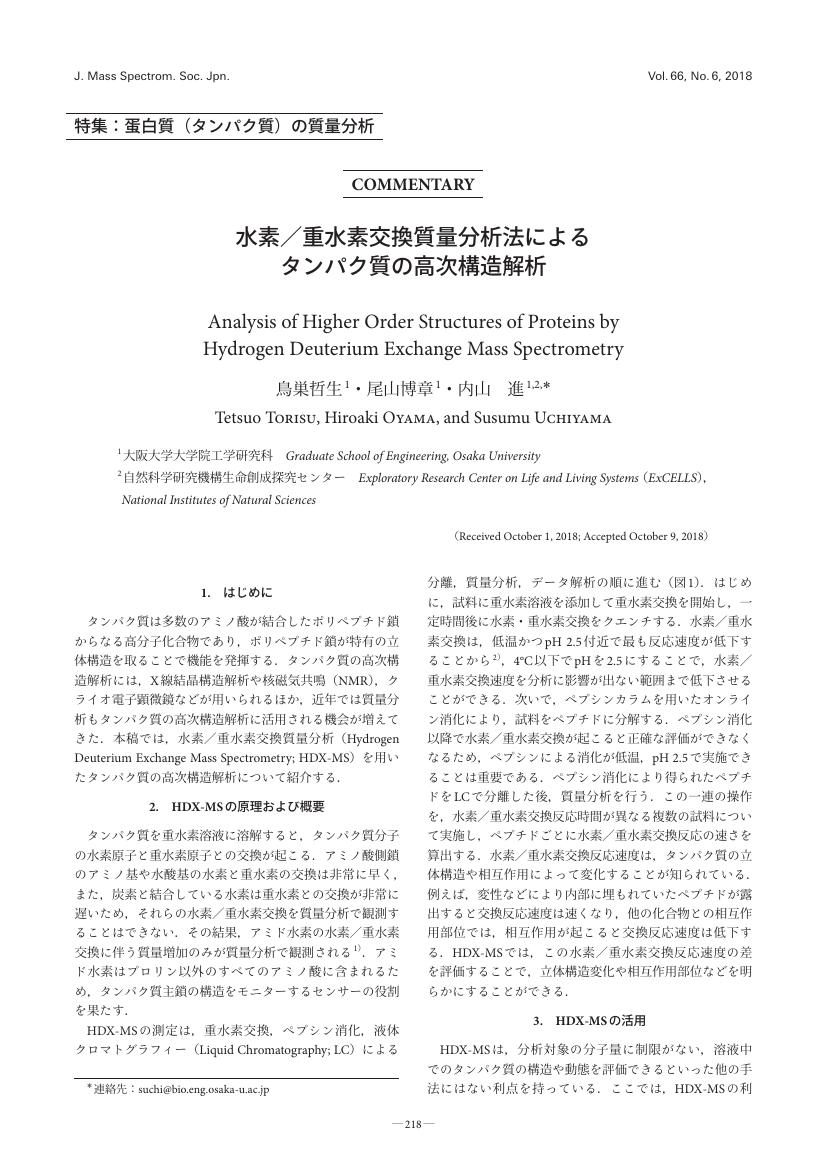- 著者
- 葛西 礼衣 福井 誠 栁沢 志津子 片岡 宏介
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.173-177, 2022 (Released:2022-08-15)
- 参考文献数
- 6
本研究では,1,450 ppmフッ化物配合歯磨剤によるブラッシング後60分間の唾液中フッ化物イオン濃度の経時測定を行い報告するものである.歯磨剤には市販1,450 ppmフッ化物配合歯磨剤を,そしてこれまで複数の報告があるが,参考として現在広く用いられている950 ppmの市販フッ化物配合歯磨剤による経時測定も行った.ブラッシング直後の洗口については,行わない場合ともしくは25 mLによる超純水による洗口を行う場合とした.ブラッシング直前およびブラッシング直後,5分,10分,15 分,30分,60分後の計7回の安静時唾液を4分間採取し,唾液中に含まれるフッ化物イオン濃度を測定した.1,450 ppmフッ化物配合歯磨剤では,洗口なしの場合,ブラッシング直前の唾液中フッ化物イオン濃度と比較してブラッシング10分後までは有意に高いフッ化物イオン濃度が認められた.また,洗口ありの場合,ブラッシング直後にのみ有意に高いフッ化物イオン濃度が認められた.また1,450 ppmと950 ppmフッ化物配合歯磨剤の比較では,洗口なしの場合,ブラッシング直後の唾液にのみ950 ppmフッ化物配合歯磨剤よりも1,450 ppmフッ化物配合歯磨剤が有意に高い唾液中フッ化物イオン濃度を認め,ブラッシング5分以後は有意な差は認められなかった.
- 著者
- 蛯原 健介
- 出版者
- 立命館大学政策科学会
- 雑誌
- 政策科学 = 政策科学 (ISSN:09194851)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.15-28, 2006-03
- 著者
- 長南 幸恵
- 出版者
- NPO法人 日本自閉症スペクトラム支援協会 日本自閉症スペクトラム学会
- 雑誌
- 自閉症スペクトラム研究 (ISSN:13475932)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.53-61, 2017-09-30 (Released:2019-04-25)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
感覚の問題は、ASD 児の半数以上にあり、DSM-5 の診断基準にも新たに加わった。しかしASD 児の感覚の特性と行動の実態は明らかではない。今回は、ASD 児の視覚、聴覚、触覚の低反応と行動の実態を明らかにすることを目的とし、知的障害および言語障害のない年長児3 例を対象に保育活動への参加観察から得たデータを基に質的記述的分析を行った。視覚では視野の狭さにより「無関心」にみえる行動に繋がり、聴覚では感覚の同時処理や言語処理の困難さから「無視」や「無反応」にみえる行動として現れると考えられた。触覚では不確かな体性感覚が見られ、情緒的発達を妨げる要因となる可能性が示唆された。感覚全般の支援として感覚刺激負荷の減少、中心視で対象を捉えられるような視覚支援、ゆっくりと短文で話す聴覚特性への配慮、伸縮性のある衣服の着用や触覚体験を重ねるなどの触覚支援等が重要である。
- 著者
- Takahiro Nakajima Shinsuke Yoshioka Senshi Fukashiro
- 出版者
- Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences
- 雑誌
- International Journal of Sport and Health Science (ISSN:13481509)
- 巻号頁・発行日
- pp.202305, (Released:2023-08-04)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
This study aims to investigate the kinetic mechanisms of controlling the whole-body linear momentum (WBLM) and whole-body angular momentum around the whole-body center of mass (WBAM) in the single-support phase after tripping during gait. Twelve young participants were made to trip during gait, and the kinematics and kinetics of their recovery responses were recorded using a 17-camera motion capture system and force platform. We found that the knee-flexion torque of the support leg dominantly contributed to the decrease in the forward WBAM increased owing to tripping, whereas this torque caused a significant forward WBLM at foot landing. The ankle-plantarflexion torque of the support leg contributed to the prevention of the body descent in the first half of this phase, although this effect decreased in the later phase, resulting in the increase in the downward WBLM at foot landing. The ankle-plantarflexion torque also contributed to the increase in the forward WBLM at foot landing. These results indicate that the ankle- and knee-joint torque exertions of the support leg are the main contributors to the change in WBLM and WBAM in the single-support phase after tripping during gait. This study also suggests that there is a trade-off relationship between the control of WBLM and WBAM, and younger adults prioritize the WBAM adjustment during this phase.
1 0 0 0 徐放性細胞増殖因子を組み込んだ生体材料
本研究の目的は、細胞の分化増殖を促す細胞増殖因子を材料とうまく組み合わせることにより、積極的に細胞を増殖させる機能を備えた生体材料を開発することである。つまり、細胞増殖因子の徐放化技術とこれまでの人工材料とを複合化することによる生体材料の創製を試みる。そのため、その第一段階としての、細胞増殖因子の徐放化の検討を行った。この徐放化技術により、増殖因子のin vivoでの安定性の向上、ならびにその作用を有効に発揮させることができる。そこで、平成6年度には、増殖因子を徐放化するための高分子ハイドロゲルの調整、ならびにハイドロゲルからのモデルタンパク質の徐放化を調べた。タンパク質はその環境の変化により容易に変性失活することから、まず、架橋ハイドロゲルを作製し、その後、タンパク質をハイドロゲル内に含浸させる方法によりタンパク質含有ハイドロゲル製剤を得た。平成7年度においてはハイドロゲル用の生体内分解吸収性の高分子としてゼラチンを取り上げ、グルタルアルデヒドにて化学架橋することによりゼラチンハイドロゲルを作製した。これらの架橋試薬ならびにゼラチンの濃度を変化させることにより、ゼラチンハイドロゲルの分解性はコントロール可能であった。ハイドロゲルからの塩基性繊維芽細胞増殖因子(bFGF)の徐放を試みたところ、ハイドロゲルの分解とともにbFGFが徐放され、その徐放パターンがハイドロゲルの含水率、つまり分解性により変化することがわかった。本年度はbFGF含浸ゼラチンハイドロゲルから徐放されるbFGFの生物活性について検討した。その一つの方法として、bFGF含浸ゲルをマウス皮下に埋入した後の血管新生効果を評価した。bFGFの水溶液投与群においては全く血管新生が認められなかったのに対して、bFGF含浸ハイドロゲルの周辺には有意な血管の新生が認められ、ハイドロゲルから徐放されたbFGFの生物活性が残存していることが確かめられた。また、微粒子状のゼラチンハイドロゲルを用いた場合にも、同様にbFGFの血管新生作用の増強が見られた。
1 0 0 0 OA 丸山眞男論を捉え直す : 国民国家の黄昏を迎えて
- 著者
- 夫 鍾閔 Jongmin Boo
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.57-84, 2021-11-30
本論文は,丸山眞男の思想をめぐる言説を取り上げて,そこにおいてどのような観点から,何が問題とされてきたかを検討するものである。まず,国民国家の問題点に積極的に取り組んで丸山を批判する議論を検討し,そこで丸山が国民国家論の思想家の代表として標的にされた理由を考察した。その後,国民国家批判の潮流と距離を置きながら丸山思想の意義を見出す諸解釈を検討したが,こうした議論が〈国民国家批判としての丸山批判〉から丸山をどのように救い出しているのかを確認した。これらの解釈は国民国家の問題性を認識しながらも,丸山と国民国家を分離させようとするが,そこには,自由主義と民主主義の対立という契機が働いている。しかし,それらの主張を丸山のテキストに即して検証したところ,その解釈には論理的な難点がある。その点,丸山のテキストの読解としては,丸山の国民国家論を一貫したものとして捉えたということで,国民国家批判論者たちによる丸山論のほうがより適切だったと結論付けると同時に,丸山の国民国家論に再解釈の余地があることも明らかにした。
1 0 0 0 トリチウムの生体への取り込みとその影響効果
本年度の研究成果を以下に述べる。1.トリチウムガス・トリチウム水の生体内代謝・排泄促進の解明研究では、(1)トリチウムガスのラットへの取り込みは、雰囲気の水蒸気濃度や軽水素濃度には殆んど影響されない。(2)トリチウムガスの酸化はラット腸内の嫌気性菌によるところが多いので、サルおよびヒトの糞便でも調べたところ、サルおよびヒトの糞便もトリチウムガスをラットと同程度に酸化することを見出した。(3)トリチウムガスをラットに投与する前に、嫌気性菌に作用スペクトラムを持つ抗菌剤や抗生物質を前もってラットに投与しておくと、トリチウムガスの体内酸化が顕著に抑制されることを見出した。(4)体内に取り込まれたトリチウムを排出促進するには、リンゲル液,グルコース液,KN補液の静脈内投与、およびリンゲル液と利尿剤の同時投与が効果的であり、組織結合型トリチウム濃度を著しく低下させることを明らかにした(以上、一政・秋田)。2.食物連鎖によるトリチウムの体内取り込み研究では、(1)トリチウムで標識したアミノ酸をラットに投与して組織の細胞核内および核外の蛋白質当りのトリチウムの比放射能を測定すると、両者とも略1に近い値である。(2)経口投与実験で確認する必要があるが、食品中のトリチウムで標識されたアミノ酸成分に関する限り、体内に取り込まれたトリチウムによる細胞内の線量は組織の平均トリチウム濃度に略比例することを明らかにした(以上、石田・斉藤)。3.ヒトのトリチウム代謝研究では、(1)人体および動物の組織を200〜300g焼却し組織中のトリチウム濃度を測定し得る前処理装置が完成した。(2)40献体の脳,肺,肝,腎,脾臓がサンプリングされ、その内の20献体の臓器の平均トリチウム濃度は76.6±78.9pC/l,2.83±2.92Bq/lであることを明らかにした(以上、上野)。飲料水のトリチウム濃度の測定用に約300サンプルが準備された(東郷)。
1 0 0 0 OA 高水敷を掘削した後に見られる河道内樹林の拡大速度
- 著者
- 川尻 啓太 森 照貴 内藤 太輔 今村 史子 徳江 義宏 中村 圭吾
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.23-32, 2023-07-31 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 56
近年,河道内の樹木が定着範囲を拡大させる「樹林化」が日本全国で生じている.治水対策として,樹木の伐採に加え高水敷を掘削する対策が実施されているが,掘削後にヤナギ類等の樹木が再び繁茂する事例が報告されている.効率的な樹木管理を実施する上で,掘削後に再び樹林化することを考慮した管理計画が求められる.しかし,どの程度の速さで再び樹林が拡がるかについての知見は乏しい.本研究では,26 箇所の掘削地を対象として,掘削後に撮影された衛星写真と空中写真から河道内における樹木の繁茂状況を判読した.そして得られた繁茂状況の年変化から,ヤナギ類を中心とした樹林の拡大速度と,河床勾配による違いについて検証した.その結果,樹林は掘削から約 5 年が経過すると拡大速度を増し,掘削から約 10 年が経過した頃には掘削した範囲の約 50 %を覆うことが明らかとなった.掘削地には,ヤナギ類の種子が多量に運ばれ,約 5 年が経過する頃には複数の個体が掘削地の一部を覆うほどに樹冠を大きくしたものと考えられる.その後も,各個体での樹冠の拡大と個体の定着範囲の拡大が続いたことで樹林面積が増加したと考えられる.さらに,河床勾配に応じて,樹林化が進行する速度が異なっていた.河床勾配が緩い区間ではより速く樹林が拡大する傾向にあり,これは流速が小さく,樹木が流亡しにくくなったためと考えられる.また,勾配が緩いことで高水敷に堆積する土砂の粒径が小さく,湿潤環境が形成されやすいために,樹木が定着・生長しやすくなったと考えられた.本研究の成果は,高水敷掘削からの経過年数に応じた樹林の繁茂状況の推定に寄与する.これにより,掘削の後にいつ樹木管理を実施するべきかの判断材料となるだろう.また,樹林化の抑制対策の効果を評価する際,対策を実施しなかった場合に想定される樹林化の速度として活用されるだろう.
1 0 0 0 OA 統計的自然言語処理と機械学習・統計学の未来(<特集>ポスト経験主義の言語処理)
- 著者
- 持橋 大地
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.284-287, 2012-05-01 (Released:2020-09-29)
1 0 0 0 OA 水素/重水素交換質量分析法によるタンパク質の高次構造解析
- 著者
- 鳥巣 哲生 尾山 博章 内山 進
- 出版者
- 一般社団法人 日本質量分析学会
- 雑誌
- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.218-221, 2018-12-01 (Released:2018-12-15)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA デュアルユース概念の科学技術社会論的検討
文献・インタビュー・質問紙調査等によって、日本におけるデュアルユース概念の特徴は以下のように概括された。1)用途両義性と軍民両用性の連続性がない。2)軍民両用研究ではなく軍事研究に着目している。3)資金出資組織によって軍事研究か否かを判断する「入口議論」に傾いている。4)「両義性がある」ことが、軍民両用研究を肯定(追認)する根拠にも、否定する論拠にもなっている。5)核兵器や化学兵器、バイオテロといったイメージが中心。これらの成果は学会・シンポジウムで10回発表し、論文6本、書籍5冊、一般記事等3本として公開した。また、一般向けイベント主催・登壇5件を行い、本件に関する議論を広く社会に発信した。
本研究ではまず当院過去10年間の両側腎臓MRIの症例を用いて3D自動セグメンテーションシステムの構築を目指す。次にこれらの過去画像群および自動化ツールで得られたsegmentation dataのセットを用いて、texture解析と深層学習を用いたCKD患者の腎機能予測モデルの構築を目指す。さらに深層学習(3D CNN)を用いた腎機能予測モデルの構築も行うことで、腎機能予後評価のさらなる向上を狙う。低侵襲なMRI検査およびtexture解析や機械・深層学習といった手法により、CKDの早期診断やリスク予測ができれば、その予防や症状改善に貢献できる可能性がある。
1 0 0 0 OA 口腔保湿剤としてのグリセリン溶液の水分保持能力の検討
- 著者
- 森 啓輔 小西 有望 坂本 典子 山田 知子 江本 晶子 小向 翔 江口 由美子 山下 佳雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.465-470, 2019-03-31 (Released:2019-04-24)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
口腔衛生状態を良好に維持するためには,適切な湿潤状態を維持することが重要である。しかし,高齢者の多くは加齢による唾液分泌能低下,内科的疾患やその治療薬の副作用のため口腔乾燥症を発症している。高齢化に伴い,この口腔乾燥症患者は年々増加しているが,その多くは対症療法として口腔保湿剤を使用している。しかし,経済的な理由から保湿剤の適正使用ができていない場合も多い。今回,安価なグリセリンを主成分とした溶液が口腔乾燥症に対して応用可能であるかどうかを,鳥ムネ肉を検体として用いて基礎実験を行った。比較溶液としては蒸留水,市販の口腔保湿剤(バトラージェルスプレー®)を用いた。水分量は口腔水分計ムーカス®を用いて測定し,水分保持能力は水分量の変化率(処置前水分量-120分後の水分量/処置前水分量×100)と定義した。結果,鳥ムネ肉における120分後のグリセリン溶液群とバトラージェルスプレー®群では同等な水分保持能力を示した。また,グリセリン溶液濃度(12・24・36%)と水分保持能力には統計学的に有意な相関関係は認められなかった。 今回の実験結果から,グリセリン溶液は市販の口腔保湿剤と同等な水分保持能力を有することが判明した。グリセリンは安価なことから,経済面からも長期使用が可能な口腔保湿剤の一つになりうると考える。
1 0 0 0 OA なぜ福島第一1-4号機が過酷事故に至ったのか――事故調の報告書を中心に――
- 著者
- 大山 耕輔
- 出版者
- 日本公共政策学会
- 雑誌
- 公共政策研究 (ISSN:21865868)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.6-23, 2014-12-20 (Released:2019-06-08)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 2
本稿は,なぜ福島第一1-4号機が過酷事故に至ったのかについて,同じく津波が襲ったが過酷事故に至らなかった5-6号機や福島第二,東北電力の女川,日本原子力発電の東海第二における津波対策と比較しながら考察する。そして,東京電力は,3.11以前に10m超の津波を試算していたが,経営上の理由で有効な津波対策を打たなかったし,副次的要因として,原子力安全委員会や原子力安全・保安院も電力会社に捕虜にされ津波対策に有効な規制を打てなかったために過酷事故に至った,という仮説を,各種の事故調査委員会の報告書を検討しながら検証している。配電盤の水密化やかさ上げなど比較的安上がりで有効な津波対策を打っていれば福島第一1-4号機は過酷事故に至らなかった可能性があるし,規制当局が電力会社から独立性・専門性・透明性を確保していれば,津波対策に有効な規制を打てた可能性がある。
- 著者
- 魏 珂楠 Kenan Wei
- 雑誌
- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)
- 巻号頁・発行日
- no.139, pp.87-99, 2022-10-31
1 0 0 0 [写真帳 : 関東大震災]
- 出版者
- [安富平太郎]
- 巻号頁・発行日
- 0000
- 著者
- 見城 道子 今福 恵子 大杉 紘徳 山下 香枝子
- 出版者
- 日本保健医療福祉連携教育学会
- 雑誌
- 日本保健医療福祉連携教育学会学術誌・保健医療福祉連携 (ISSN:18836380)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.50-60, 2011 (Released:2019-09-26)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,在宅における行動障害および精神症状(以下BPSD)を有する認知症高齢者へのケアについてIPWの観点から,看護,介護,リハビリテーションを中心に各分野のアプローチの実際を文献検討から明らかにすることを目的とした。国内で発表された日本語文献を医学中央雑誌にて検索した。検索語は「認知症」「BPSD」「連携」を組み合わせた語と「看護」または「リハビリテーション」または「介護福祉士」「ケアマネジャー」「社会福祉士」を連結させて行い,施設内のケアに関するものを除いた。 BPSDを有する在宅の認知症高齢者のケアにおける「連携」に関する論文は,看護学とリハビリテーション学分野においては,2006年から発表されており,増加傾向であった。すべての分野の論文に共通して「専門職の専門領域の確立」と「目標の共有」に関する記述が確認されたことから,多職種連携と協働による支援の必要性は認識されており,IPWの推進が重要である。
1 0 0 0 OA 質量分析による赤芽球特異的5-アミノレブリン酸合成酵素複合体タンパク質の解析
- 著者
- 鈴木 亘 Costantine Chasama Kamata 古山 和道
- 出版者
- 岩手医学会
- 雑誌
- 岩手医学雑誌 (ISSN:00213284)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.2, pp.69-79, 2023 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 28
Erythroid-specific 5-aminolevulinate synthase (ALAS2) is the rate-limiting enzyme of the heme biosynthetic pathway in erythroblasts. ALAS2 is essential for supplying heme to produce hemoglobin in developing erythroblasts. While it has been reported that the gene expression of ALAS2 is regulated at the transcriptional and the translational steps, the post-translational regulation of ALAS2 protein is not well understood. In this study, we examined the protein complex of FLAG-tagged ALAS2 (ALAS2F) using immunoprecipitation followed by mass spectrometry and identified several mitochondrial proteins in the complex of ALAS2F. We also confirmed the presence of these proteins in the complex of ALAS2F by Western blot analysis, and we speculated on the novel role of one of these identified proteins on the post-translational regulation of ALAS2 protein. Further studies on the role of these proteins in the regulation of ALAS2 protein will reveal the precise mechanisms of the post-translational regulation of ALAS2 in erythroid cells.
1 0 0 0 OA 高温ガス炉ガスタービンシステムの動力変換システム基本概念の評価
- 著者
- 皆月 功 溝上 頼賢
- 出版者
- Atomic Energy Society of Japan
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.276-288, 2007 (Released:2012-03-07)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 2
The design studies on High Temperature Gas Cooled Reactor with Gas Turbine (HTGR-GT) have been performed, which were mainly promoted by Japan Atomic Energy Agency (JAEA) and supported by fabricators in Japan. HTGR-GT plant feature is almost determined by selection of power conversion system concepts. Therefore, plant design philosophy is observed characteristically in selection of them. This paper describes the evaluation and analysis of the essential concepts of the HTGR-GT power conversion system through the investigations based on our experiences and engineering knowledge as a fabricator. As a result, the following concepts were evaluated that have advantages against other competitive one, such as the horizontal turbo machine rotor, the turbo machine in an individual vessel, the turbo machine with single shaft, the generator inside the power conversion vessel, and the power conversion system cycle with an intercooler. The results of the study can contribute as reference data when the concepts will be selected. Furthermore, we addressed reasonableness about the concept selection of the Gas Turbine High Temperature Reactor GTHTR300 power conversion system, which has been promoted by JAEA. As a conclusion, we recognized the GTHTR300 would be one of the most promising concepts for commercialization in near future.