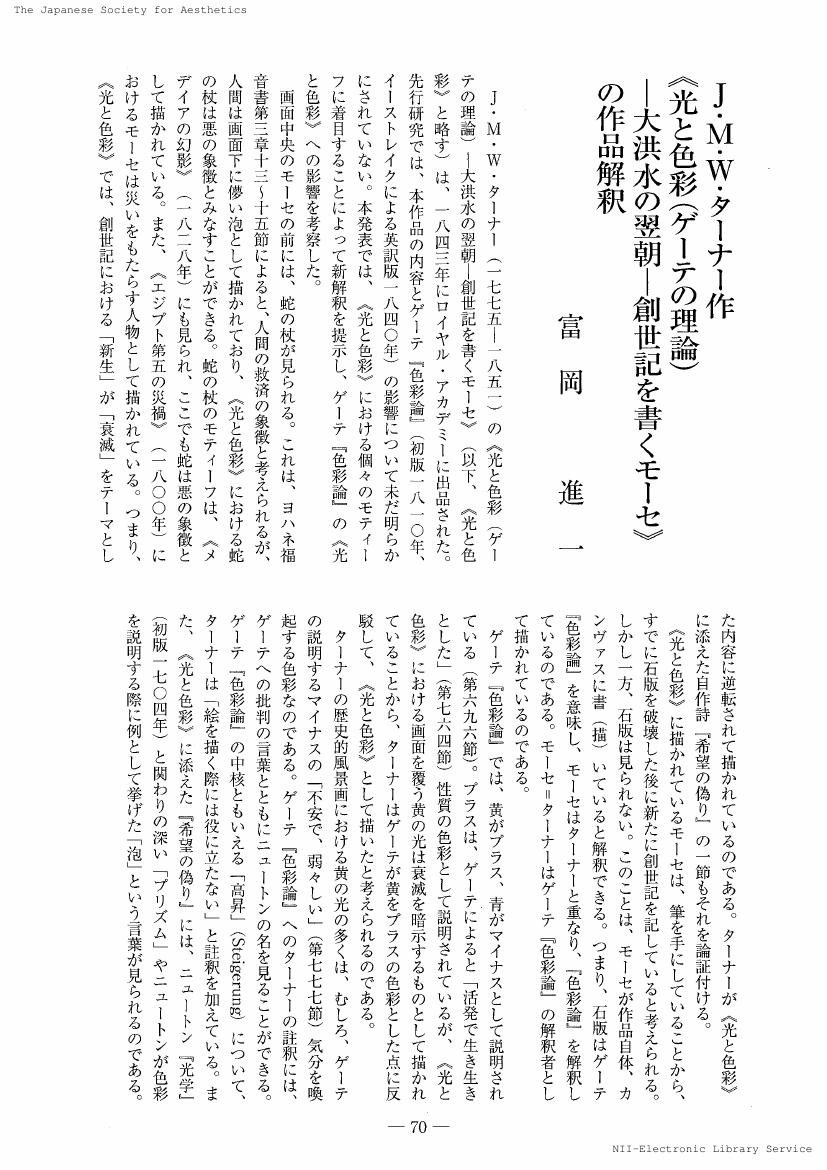1 0 0 0 OA ボイルオーバー:事故事例と最近の研究
- 著者
- 古積 博
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.253-264, 2016-08-15 (Released:2016-08-15)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 2
ボイルオーバーの事故と研究について総説した.主に原油と重油が起こすこと,地震や戦争で消防力が損なわれた時に起こっているが,日本でも1964 年の新潟地震後に起きている.ボイルオーバーの研究は,燃料層内に形成される高温層の生成機構に注目していたが,バイオデイーゼルのように高温層を形成しない場合でもボイルオーバーのように激しい燃焼がみられる薄層ボイルオーバーの研究も行われている.ボイルオーバーがいつ起こるのか,燃料層厚さとの関係が調べられた.最近では,ボイルオーバーの抑制に関する研究が進んでいる.例えば,ビーズの投入でボイルオーバーの発生が抑えられる可能性がある.
1 0 0 0 OA バロック期フランス・オペラの現代上演における問題 : 驚異の再現は可能か
- 著者
- 内藤 義博
- 出版者
- 立命館大学アート・リサーチセンター
- 雑誌
- アート・リサーチ = アート・リサーチ (ISSN:13462601)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.13-22, 2015-03
- 著者
- 白倉 正博 亀井 淳 赤坂 真奈美 中軽米 美里 小山 耕太郎
- 出版者
- 岩手医学会
- 雑誌
- 岩手医学雑誌 (ISSN:00213284)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.183-199, 2019 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 22
知的に正常な早産極低出生体重児の家庭生活状況と自尊心および親子関係について調査した.対象は2002年4月から2011年3月に当院新生児集中治療室に入院し,就学前の知能検査で正常知能が確認され,2017年4月の時点で学齢期にある108人である.自尊心はPopeの子ども用5領域自尊心尺度で評価し,結果はおおむね良好であった.自尊心評価が完遂できた96人の各尺度を従属変数とし,周産期情報およびアンケート情報の計16項目を独立変数とした重回帰分析を行った結果,出生体重,呼吸窮迫症候群,脳室周囲白質軟化症,調査時年齢と有意な関連を認めた.親子関係も対象の殆どが良好であった.自尊心尺度と親子関係は子からみた母子関係に相関する項目が多く,特に男子の家族尺度が「被拒絶感」と強い負の相関 ‹r = −0.7471, p< 0.001› があった.一方,自尊心と「心理的侵入」,「厳しいしつけ」および「達成要求」は殆ど相関しなかった.
- 著者
- 高原 光弘
- 出版者
- Okayama Medical Association
- 雑誌
- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.9-10, pp.1235-1248, 1979-10-30 (Released:2009-03-30)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1 1
Persistent juvenile T wave patterns found in mass examination and in clinical cases were studied for the purpose of clarifying their significance. Persistent juvenile T wave patterns were classified into three types. Type I had negative T waves in lead V1 only, Type II in lead V1 and V2 and Type III in V1 to lead V3 or V4. During mass examinations, persistent juvenile T wave patterns were found in 243 cases (43.5%) of 558 male subjects. Of these, 15 (6.2%) were Type II, III. On the other hand they occurred in 547 (66.5%) of 823 female subjects. Of these, 86 (15.7%) were Type II, III. The incidence of each Type of persistent juvenile T wave pattern did not vary significantly with age, but Type II, III were relatively more frequent between 35 and 49 years of age. Persistnet juvenile T wave patterns were often positive in many cases in electrocardiograms (ECG) thaken from the same subjects 8 years after the first mass examination. Standard ECG's and Frank's system vectorcardiogram (VCG)'s were analysed in 116 clinical cases showing persistent juvenile T wave patterns. Transitional zone and electrical axis deviation in ECGs were almost normal in the persistent juvenile T wave pattern. The shape of the transverse T loop was mostly normal whereas the transverse QRS loop normally varied in shape. Clockwise rotation of the transverse T loop was observed in 15 of 116 clinical cases. The maximum magnitude of the T loop in VCG was significantly smaller in Type III than in Type I, II. Changes in the persistent juvenile T wave pattern on ECG and VCG were studied in 25 cases after administration of Propranolol. The negative T wave in ECG tended to become positive and the maximal T vector tended to become larger shifting towards anterior in VCG after administration of Propranolol. The persistent juvenile T wave pattern was observed more frequently in middle aged women and usually became normal after administration of Propranolol. These results suggest that increased sympathetic tone is one of the pathological mechanisms involoved in the persistent juvenile T wave pattern.
1 0 0 0 OA 野村兼太郎編著, 『村明細帳の研究』, 昭和二十四年七月, 有斐閣發行
- 著者
- 三橋 時雄
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.141-142, 1950-04-15 (Released:2017-11-30)
1 0 0 0 沖縄沿岸域から採取した微生物群を用いた砂質土固化とその特徴
- 著者
- 屋比久 雄斗 松原 仁
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.8, pp.23-00020, 2023 (Released:2023-08-20)
- 参考文献数
- 29
微生物の代謝反応によって誘発されて析出する炭酸塩鉱物は,離散状態にある土粒子を結合し,土の強度や剛性を高める.微生物を実環境に添加する際には,周辺生態系への影響を考慮すれば,土着の微生物を利用することが好ましい.しかしながら,地盤固化に有用な土着微生物を微生物資源としてストックするための研究はあまり進んでいない現状がある.本研究では,この技術の沖縄地域での適用を指向し,当該地域の沿岸域における有用微生物を同定し,その菌叢を明らかにするために16S rRNA遺伝子解析を行った.分析の結果,試料を採取したすべての地点で有用微生物の存在が確認されたものの,固化の程度は採取地に依存することが明らかとなった.また,分子系統樹解析の結果から,地盤固化に有用な微生物は比較的近縁なDNA配列を有することが分かった.
1 0 0 0 OA 若者はどのようにして恋愛関係を成立させるのか ―ケータイ・コミュニケーションに注目して―
- 著者
- 大森 美佐
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会家族関係学部会
- 雑誌
- 家族関係学 (ISSN:09154752)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.27-39, 2014 (Released:2020-06-09)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 3
The purpose of this study is to clarify how young adults in Japan establish their romantic relationships with particular reference to mobile communications. It is said that as mobile phone use has spread among young adults, interpersonal relationships and communications have been transformed qualitatively. Moreover, the resulting decrease of interpersonal communication skills between young adults has been viewed as a problem. The increase in the number of young adults who are not dating and the reduction in the marriage rate in recent years have been attributed in part to the weakness of their “interpersonal communication skills” (Ministry of Health, Labor and Welfare, 2013). However, the “youth society” must have its own means to build relationships, therefore we should clarify in detail how they communicate with others and build romantic relationships. Qualitative research methodology was utilized in this study. The qualitative research data consisted of four discussion groups and four semi-structured interviews. Each group was divided by occupation (students or company employees) and gender, and the total number of participants in the discussion groups was 24 people, 14 of them female and 12 male. An interviewee was chosen from each group. The results of the analysis show that the communication by means of mobile phone (“ke-tai”) can be a device for measuring the distance between people. In addition, youths tend to be excessively concerned with interpersonal skills and the paradox of communication skill: the more effort that is put into developing better communication and paying attention to the attitudes and remarks of the interlocutor, the harder it is to build a romantic relationship.
1 0 0 0 OA 群れの機能と「安心」の神経内分泌学
- 著者
- 菊水 健史
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.67-75, 2018 (Released:2018-06-27)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3
Group living mammals have a distinct characteristic: when conspecific animals are together, they show a better recovery from experiences of distress. This phenomenon, termed 'social buffering', has been found in rodents, birds, non-human primates, and also in humans. This phenomenon is well-observed in bonded dyad; the mother-infant or pair-bonded dyads. Social contact, including allogrooming, appears to have a very positive influence on the psychological and physiological aspects of social animals, including human beings. These relationships depend on the neuroendocrine system, especially oxytocin. Oxytocin is released by affiliative social contact in dyads and can ameliorate stress and anxiety in both sides. This review overviews the classic finding of social buffering in animals and describe the recent findings of neuroendocrinological mechanisms for social buffering.
1 0 0 0 高炉スラグ微粉末を混合した非セメント系微粒子注入材の検討
- 著者
- 田代 怜 末政 直晃 佐々木 隆光 永尾 浩一 伊藤 和也
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.8, pp.22-00184, 2023 (Released:2023-08-20)
- 参考文献数
- 27
新たな液状化対策工法として,改良費用が安価かつ狭隘地においても施工可能な工法の開発が求められている.本研究では産業副産物を母材とする安価な微粒子を用いた微粒子注入工法の実用化を目的とし,高炉スラグ微粉末を用いた非セメント系微粒子注入材の開発を試みた.まず,ジオポリマーやドロマイトの固化原理に着目し,複数の微粒子を用いた供試体を作製し,一軸圧縮試験を行うことで強度特性から適した配合を模索した.最適な配合において水粉体比等の注入条件を変えた一次元注入実験を実施することで浸透性や改良効果を把握した.結果,半水石膏・高炉スラグ微粉末・酸化マグネシウムを用いた配合において1年以内では強度低下は起こらず,液状化対策に必要な改良強度を持つこと,水粉体比や注入流量によって改良効果が異なることを確認した.
1 0 0 0 OA 特集:スポーツ統計
- 著者
- 油谷 大樹 神野 有生
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.8, pp.22-00087, 2023 (Released:2023-08-20)
- 参考文献数
- 15
浅水底のUAV写真測量では,水面での光の屈折による水深の過小評価への対策として,推定された各点の水深に一定の係数を乗じる事後補正が行われている.しかし既往研究により,最適な係数(水深過小評価倍率)が条件により変動する問題が指摘され,その挙動の解明が課題となっている.本研究では,水深,波,水底テクスチャなどの条件を多様に設定したCGシミュレーションを行い,水深過小評価倍率が水深・波の増大とともに減少し,従来提案されていた値1.42からも大きく乖離し得ることを明らかにした.さらに,この傾向が生じるメカニズムについて検討し,水深・波の増大による投影点のエピポーラ線からの逸脱,局所的特徴の変化により,特に目標点が画像の外側に写るカメラが点群の座標推定に使われにくくなることを示して,対策を論じた.
1 0 0 0 OA 所得税制史にかんする一つの覚書 - エルツベルガーの所得税制 - (島恭彦教授記念號)
- 著者
- 廣田 司朗
- 出版者
- 京都大學經濟學會
- 雑誌
- 經濟論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.1, pp.31-47, 1974-01
1 0 0 0 OA 手話研究のパラダイム変換
- 著者
- 神田 和幸
- 出版者
- 特定非営利活動法人 手話技能検定協会
- 雑誌
- 手話コミュニケーション研究会論文集 (ISSN:27583910)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.48-56, 2019-05-01 (Released:2023-05-09)
手話の言語学的研究が始まって70年以上になる。鼻祖ストーキーの枠組みはアメリカ構造言語学であり、言語相対論に基づく「手話には独自の構造がある」というものであった。その後のアメリカ手話学者は当時流行のチョムスキーによる言語普遍論による枠組みへとパラダイムをシフトした。そのため「手話の音素」という一見、奇妙な概念を設定し、人間の言語の普遍性を強調する一方、音素の中身は音声言語とはまったく異なる構造を設定するという矛盾の中で、音韻論を構築し、統語論を展開しようとしたが、うまくいかなかった。その背景には手話学者の多くが民族主義的な政治思想をもっており、手話が聾者の言語であるという教条から抜け出ることができないまま、科学的な分析技術を拒否し、チョムスキー言語学のいう母語話者の直観にのみ証拠を求める、という思弁的な方法論に終始してきた。本論では言語学のパラダイムの歴史的変化を言語普遍論と言語相対論という対比で考察した。これは哲学的方法論として、演繹的方法論と帰納的方法論に換言できるかもしれない。トマセロの理論は方法論的には帰納法が中心だが、広範囲な諸文献の考察により演繹論も採用している。折衷的という批判もできるが、バランスをとっているという肯定的な見方もできる。あとは実際的な言語処理技術が手話学に応用できるかどうか、というべ実用的な基準もありうるので、別稿においてトマセロの議論の歴史的変化も追いながら考察してみたいと考えている。
1 0 0 0 OA 小学校における天動説の立場からの「月の満ち欠け」に関する授業の実践とその効果
- 著者
- 長谷川 恭子 吉田 歩 森藤 義孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.25-30, 2015 (Released:2018-04-07)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
平成 20 年の小学校学習指導要領の改訂により,「月の満ち欠け」に関する内容が,小学校第 6 学年において再び取り扱われるようになった。吉田らは,天動説の立場から,小学校第 6 学年「月と太陽」で取り上げる「月の満ち欠け」について,月早見板の作成活動を取り入れた授業を構想し,実践を行った。本研究では,小学校第 6 学年の「月の満ち欠け」に関する効果的な学習指導法の検討を行うため,吉田らの授業を受けた子どもを対象に,月の満ち欠けに関わる理解がどのように維持され,あるいは崩壊しているのかを明らかにした。
1 0 0 0 OA コミュニケーションの基本 「私」が「私たち」になるとき
- 著者
- 岸田 一隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.8, pp.416-420, 2020 (Released:2021-02-01)
2019年12月に開催された「再処理・リサイクル部会セミナー」における岸田の基調講演の内容を,その時の講演のスタイルとともにまとめた。コミュニケーションの基本構造から解き明かし,伝え方や心構えについて注意を払うことを解説した。大切なのは,コミュニケーションを担う双方の間に共同体意識を生むことであり,共に未来を作り出してゆくという意識を持つことである。そのためには,自らも変わる準備がなくてはならない。
1 0 0 0 OA 臨床に役立っ局所解剖 外•中耳の血管と神経(局所に対して)
- 著者
- 中野 雄一
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.9, pp.1374-1377, 1991-09-20 (Released:2008-03-19)
- 著者
- 富岡 進一
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.70, 2003-12-31 (Released:2017-05-22)
1 0 0 0 OA 印刷物セキュリティを実現する電子透かし技術
- 著者
- 阿南 泰三
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.179-184, 2012 (Released:2012-07-15)
- 参考文献数
- 10
Since May 2005, numerous laws have been enacted in Japan to protect personal information. The responsibility for protecting personal information has become a critical issue for enterprise-level businesses. Computers and networks are not the only source of sensitive information leaks. In many incidents of information leakage, printed documents are involved. It is now possible to protect confidential and private information by applying the following countermeasures during the printing of documents:·Copy control by applying a watermark to restrict copying and forgery·Watermarks for traceability and falsification detection, including background texture watermarks and font embedded watermarks·Encryption by paper encryption technologyThis paper presents an overview of some digital watermarks and paper encryption technology in order to prevent information leaks from paper documents.