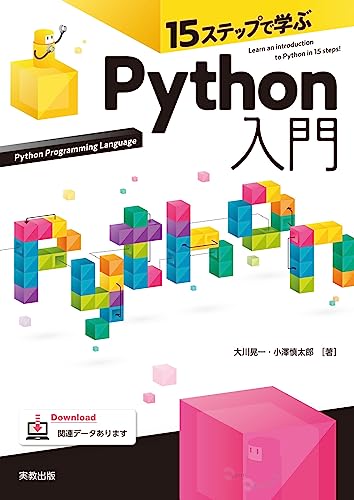- 著者
- 新藤 慶
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.39-60, 2022 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 17
1990 年の改正入管法施行により増加したブラジル人・ペルー人の状況や,その集住地域として知られる群馬県大泉町の状況を検討した結果,第1に,定住者として来日したブラジル人・ペルー人の永住者化が確認された。ここには,日本生まれの日系4世の将来的な在留資格の確保といったねらいも見いだされる。一方,第2に,ブラジル人・ペルー人の経済状況は不安定であった。共働きが中心でも世帯年収は300 万円を少し超える程度である。そのなかで,非労働者の労働者化の進行がうかがえる。また,就学援助の受給率の高さなど,子どもの教育環境への影響もみられる。さらに第3に,こうした貧困の問題と並行して,日本語能力の低さの問題も見いだされた。大人も日本語能力に不安を抱えるが,子どもについても,他の外国人に比べて,ブラジル人は日本語指導が必要なくらい日本語能力が低い者が多くなっていた。そのなかで,第4に,大泉町では在留外国人の受け入れ体制の充実がみられた。当初から,町行政も受け入れを支援していた。また,子どもの教育についても,言語面を中心に充実した指導体制を構築していた。しかし,そのことが,「日本語学級にお任せ」といった形で,「外国人教育」への教員の当事者意識を低下させていた。今後の多文化共生のためには,在留外国人の実態の変化や多様化を把握し,外国人の声を聞きつつ,ホスト住民側も当事者意識を持って関わることが重要となる。
1 0 0 0 OA 南オーストラリア州アデレードにおけるベトナム系住民の分布とその特徴
- 著者
- 筒井 由起乃 松井 圭介 堤 純 吉田 道代 葉 倩瑋
- 出版者
- 地理空間学会
- 雑誌
- 地理空間 (ISSN:18829872)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.117-129, 2015 (Released:2018-04-04)
近年,オーストラリアではアジア化が進んでいる。なかでも多いのが,中国,インド,ベトナムである。中国やインドからの移民が2000年代以降に急増したのに対し,ベトナムからの移民は1970年代後半からのインドシナ難民を中核としており,在豪年数の長さと難民としての性格を持つ点が特徴的である。ベトナム系は特にニューサウスウェールズ州とヴィクトリア州に多いが,クイーンズランド州,南オーストラリア州にも1万人以上が居住している。シドニー郊外のカブラマッタに代表されるような「ベトナム人街」も形成されている。このようなベトナム社会の形成過程とその実態を解明するのが本稿の目的である。本稿では,来豪時期によって社会経済的な背景が異なることに着目し,属性の違いが移民の職業選択や居住地選択といった意思決定や生活形態にどのような影響をおよぼしているのかについて,南オーストラリア州アデレードを対象として検討する。
- 著者
- Makoto Fukuda Naoki Sawa Daisuke Ikuma Yuki Oba Hiroki Mizuno Masayuki Yamanouchi Akinari Sekine Eiko Hasegawa Tatsuya Suwabe Junichi Hoshino Kei Kono Keiichi Kinowaki Kenichi Ohashi Hiromichi Tamaki Motoaki Miyazono Yoshifumi Ubara
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.81-85, 2023-01-01 (Released:2023-01-01)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 3
A 43-year-old Japanese woman with rheumatoid arthritis treated by infliximab and methotrexate for 11 years was admitted for proteinuria and purpura. A kidney biopsy revealed endothelial damage-dominant nephritis with IgA deposition. Infliximab and methotrexate were discontinued, and tocilizumab was started; however, proteinuria persisted. Therefore, tocilizumab was discontinued, and oral prednisolone and methylprednisolone pulse therapy were administered. After 6 months, urinary protein was less than 0.1 g/day, and purpura subsided. To our knowledge, this is the first case of endothelial damage-dominant nephritis related to IgA vasculitis involving the skin and kidney after long-term use of infliximab and methotrexate.
1 0 0 0 OA 営利的言論をめぐる判例法理の展開 : アメリカ連邦最高裁判決を中心に
- 著者
- 太田 裕之 Hiroyuki Oota
- 出版者
- 同志社法學會
- 雑誌
- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4-5, pp.90-145, 1987-01-31
研究ノート
1 0 0 0 OA 家庭内における性的虐待への対応策の検討 ―刑事政策的側面から―
- 著者
- 西山 智之
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.171, 2023 (Released:2023-04-25)
1 0 0 0 15ステップで学ぶPython入門
- 著者
- 大川晃一 小澤慎太郎著
- 出版者
- 実教出版
- 巻号頁・発行日
- 2023
1 0 0 0 位相最適化による鉄道構造物の耐震設計プロセスの提案とその有効性
- 著者
- 月岡 桂吾 坂井 公俊
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.8, pp.23-00005, 2023 (Released:2023-08-20)
- 参考文献数
- 36
鉄道構造物の耐震設計に位相最適化を導入するためのプロセスを提案した.提案手法ではまず,現在の一般的な耐震設計手法に基づいて構造物の設計を実施する.次に位相最適化によって構造物の構造形態の候補を複数作成し上述した設計結果と比較することで,コストや性能等の観点でパレート最適解の範囲を絞り込む.最後に絞り込まれた解の範囲の中から,予算,施工性および維持管理性等を踏まえて設計者が最適な構造形態を選定する.提案手法の有効性を確認するために,柱高さ6mのコンクリート橋脚を対象に手法を適用した.その結果,パレート最適解として複数の構造形態が得られることや,解の範囲から選定した構造形態は従来のものと比較して性能やコストの面で優位性を有している事等を確認した.
- 著者
- Kazuhiro Morita Erina Takeda Makoto Shimoyamada
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- pp.FSTR-D-23-00077, (Released:2023-08-22)
Raw soymilk separates into two layers upon freeze-thawing. We investigated the effects of high-temperature thawing (50–100 ℃) on the freeze-thaw fractionation of soymilk. After freezing, the samples thawed at high temperatures separated into two layers with similar fractions as observed in samples thawed at low temperatures (10 ℃). As the thawing temperature increased, the separation time of the samples thawed at high temperatures decreased by less than half, when compared to those thawed at low temperatures. The ratio of the weight of the upper layer to the total weight decreased as the thawing temperature increased. The 7S and 11S proteins in soymilk could be fractionated through high-temperature thawing, similar to that through low-temperature thawing. Protein denaturation did not occur upon fractionation at higher temperatures. These results suggest that raw soymilk can be fractionated even through high-temperature thawing and may contribute to the efficient production of freeze-thaw fractionated soymilk.
1 0 0 0 CERS法による大倉ダムの地震時物性値の推定と変動要因の考察
- 著者
- 中村 豊 佐藤 勉 齋田 淳
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.8, pp.22-00260, 2023 (Released:2023-08-20)
- 参考文献数
- 13
構造物などのヘルスモニタリング手法として,波動伝播速度や減衰定数を観測波形から直接リアルタイム計測できるCERS法がある.これをダム堤体の一部であるスラストブロックの物性値計測に適用した.対象は仙台市青葉区の大倉ダム(1961年に建設された日本唯一のダブルアーチダム)であり,竣工後50年の2011年東北地方太平洋沖地震(Mw9.0)の際にも特に被害は報告されていない.公開されたアーチ間のスラストブロック頂部および点検坑道内の強震記録により,観測点間の波動伝播速度をCERS法により直接測定し,物性の変化を検討した. その結果,Mw9.0の強震動でスラストブロックの剛性が約6割まで低下し,記録終了時には約7割に回復したことが確認されるなど,物性値の変動や減衰に及ぼす貯水位の影響等が把握できた.
1 0 0 0 上田自由大学とその周辺
- 著者
- 藤林 博明 野呂 直樹 辻 翔太 大山 理 松井 繁之
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.8, pp.22-00148, 2023 (Released:2023-08-20)
- 参考文献数
- 12
プレフレックスビーム(以下,プレビーム)は,プレストレスを導入した下フランジコンクリートと床版コンクリートを合成させた二重合成桁である.分割工法では工場で下フランジコンクリートにプレストレスを導入した桁を2~3ブロックに分割して現地に輸送する.近年,プレビームの長支間化に伴い,プレストレス導入時に下フランジコンクリートの分割位置付近でひび割れ発生が見られるようになった. 本稿では,このプレビームの分割工法における下フランジコンクリートのひび割れ発生メカニズムを究明し,ひび割れ防止対策として鋼桁フランジの側面に緩衝材を貼付する方法に加え,ずれ止めの角鋼ジベルを分割配置し,頭付きスタッドを併用する方法を提案した.これらのひび割れ防止対策に対してFE解析と静的載荷試験によって有効性を検証した.
1 0 0 0 OA 多様な「個性」を創発する脳システムの統合的理解
- 著者
- 大隅 典子
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2016-06-30
1 0 0 0 OA 放射性廃棄物の地中処分問題
- 著者
- 井上 頼輝 森沢 真輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.3-15, 1973-01-30 (Released:2010-04-19)
- 参考文献数
- 79
- 著者
- 濱名 篤 川嶋 太津夫 山田 礼子 森 利枝 塚原 修一 深堀 聡子 齊藤 貴浩 白川 優治 合田 隆史 近田 政博 芦沢 真五
- 出版者
- 関西国際大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-01
本研究では、大学設置の「入口規制」として大学設置基準が、日本の高等教育の発展にどのように貢献してきたか、を分析するとともに、今日の規制緩和の流れの中で従来型の質保証体制がどのように変容するのかについて考察を加える。設置基準と認証評価がどのように連動して質保証システムとして機能してきたか、この両者が相互補完する体制が実質的な成果を挙げているか、についても検証する。また、比較可能な諸外国の設置基準と認証評価制度の関係を調査し、国際比較研究を通じて、日本固有の課題や将来への課題を明示する。さらに、日本の現状に見合った大学設置基準と質保証体制の在り方を模索し、将来の設置審査に関する提言を行う。
1 0 0 0 OA 経腸栄養剤に使用する食物繊維および半固形化材へのフェノバルビタールの吸着の影響
- 著者
- 名徳 倫明 秋山 紗奈江 松浦 亜梨紗 面谷 幸子 長井 克仁 初田 泰敏 向井 淳治 廣谷 芳彦
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.8, pp.438-443, 2017-08-10 (Released:2018-08-10)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
In many hospitals, semi-solid enteral nutrients are administered. Dietary fibers are used as the main component of semi-solid agents, but some studies have reported that dietary fibers influence the bioavailability of drugs. In this study, we examined the influence of the adsorption of phenobarbital (PB) to dietary fibers and semi-solid agents used for the manufacturing of enteral nutrients. Five types of dietary fiber or 3 semi-solid agents were dissolved in 0.01% PB solution to prepare concentrations of 1.0, 0.5, and 0.1%, and the adsorption rate and viscosity were measured. In PB solution containing 1.0% guar gum, which was prepared with purified water, the adsorption rate of PB was 33.7%. It reduced with a decrease in the concentration of guar gum. The adsorption rate of PB to xanthan gum was also similar, although it was slightly lower than that to guar gum. There was no adsorption of PB to dextrin hydrate or cellulose under any condition. The first and second solutions established by the Japanese Pharmacopoeia also showed similar results. The results of this study indicate that the adsorption rates of PB to guar gum and xanthan gum were high. When administering drugs to patients receiving semi-solid enteral nutrients, the timing of administration at which there is no influence of adsorption must be reviewed.
1 0 0 0 OA 主として頚椎過屈曲機転により生じた頚椎棘突起骨折の6例
1 0 0 0 OA 低出生体重児と臓器障害(DOHaD説)
- 著者
- 池住 洋平
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.7, pp.1385-1390, 2018-07-10 (Released:2019-07-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
近年,胎児期及び出生後の生活環境が成人期における生活習慣病発症に関与するというdevelopmental origins of health and disease(DOHaD)仮説が提唱され,多くの疫学研究,動物実験等から,その妥当性が認識されるようになった.我々は,腎生検にて巣状分節性糸球体硬化症(focal segmental glomerulosclerosis:FSGS)と診断された患児の多くが低出生体重であることを見出し,さらに,これらの患児では,腎における糸球体肥大や密度の減少等がみられることを報告した.このような低出生体重児に生じる臓器障害機序は,腎疾患にとどまらず,さまざまな成人疾患の病態に関わると考えられ,低出生体重を成人期疾患の発症を予測する1つのパラメータとしてとらえ,低出生体重児を生じる要因の改善とともに,生活環境の改善を通じた予防策を講じる必要があると考えられる.