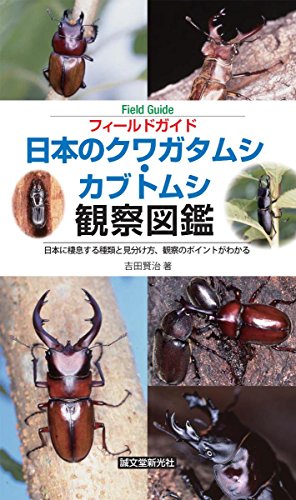1 0 0 0 OA 貴金属ナノ粒子の塗料用色材への応用
- 著者
- 小林 敏勝
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.107-111, 2005-02-10 (Released:2007-12-25)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 7 5
Highly concentrated pastes of Au and Ag nanoparticles were prepared by a novel method using a comb-shaped block copolymer and an amine as protective colloid and reducing agent, respectively. The nanoparticles were applied to paint colorants utilizing the surface plasmon light absorption. Au and Ag nanoparticles exhibited clear red and yellow colors, respectively. It was revealed that the nanoparticles possess aesthetic color properties such as transparency and color saturation as well as excellent weather durability. Further, a novel metal paint system was also developed from using the condensed Ag paste, which enables us to produce metal like coatings by a simple, dry and environmentally friendly process.
1 0 0 0 OA アーフォントステル号発見の有田産アルバレロ形壷
- 著者
- 野上 建紀
- 出版者
- 金沢大学文学部考古学研究室
- 雑誌
- 金大考古
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.19-23, 2008-04-01
1 0 0 0 OA HEART's Selection 運動療法の効果とその機序
- 著者
- 伊東 春樹
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.252-259, 2007-03-15 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 街で音を奏でること : 2005年あたりの下北沢
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.1-23, 2012-01-28 (Released:2017-04-07)
- 参考文献数
- 39
In this paper, I focused on a town, Shimokitazawa. By examining the activities of musicians there, I considered the relationship between the urban user and the place. A pop musician's occupation is singing her/his songs repeatedly. As the facilities where they play their music are scattered around the city, they move around as mobile laborers in a similar manner like nomads. Therefore, the audiences who appreciate the performance of the musicians are called mobile consumers. To understand some of these actual situations, I investigated the facilities that hold such music performances in Shimokitazawa and the behaviors of three musicians who give these performances around the town and an audience. I considered the relationship between the musicians and Shimokitazawa by focusing on the former's practices in their music performances, especially in 2005 and the musical landscape depicted in their songs. The upsurge of the redevelopment problem was observed in Shimokitazawa around 2005. As a result, it can be said that music played the significant role in the development of people's connections with the musicians, and of positive associations of the musicians with the town.
1 0 0 0 OA 鳥取砂丘の安定化に伴う海浜植生の群落構造の変化
- 著者
- 笹木 義雄 森本 幸裕
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第51回日本生態学会大会 釧路大会
- 巻号頁・発行日
- pp.414, 2004 (Released:2004-07-30)
鳥取砂丘では、防風林として植栽されたクロマツやニセアカシアが汀線に向かって砂丘内に侵入する現象が見られ、裸地面が減少し、安定化が進行している。本報告では、海浜植生を持続的に管理することを目的に、砂丘の安定化が、群落構造へ与えた影響について明らかにした。 鳥取砂丘の千代川河口付近の汀線から約500mに位置する砂丘列において、1986年に84箇所のコドラート(2.5m×2.5m)を設置した。各コドラートについて、ブラン_-_ブランケットの植物社会学的手法により、コドラート内に生育する植物種とその被度を測定するとともに、基点から各コドラートの標高を水準測量により1986年11月15日に測量した。これより16年が経過した2002年に、同地点について1986年に調査したのと同様な手法で、植生調査と測量を実施した。また、これらの調査結果をTWINSPAN法による分類、DCA法による序列化により比較した。 調査対象地域の植生は、1986年においては、コウボウムギ群落、ケカモノハシ群落、メマツヨイグサ群落の3タイプに分類されたが、2002年においては、これまでに見られた草本群落に加えて、アキグミ群落、クロマツ群落などの木本が優占する群落タイプも見られるようになった。また、種数は、1986年においては、15種であったのに対し、2002年においては、41種と増加がみられた。なかでもこれまで調査対象地域に見られなかった外来種のコバンソウ、マンテマ、ハナヌカススキなどの草本、ニセアカシアなどの木本の侵入が顕著であった。 このまま、砂丘の安定化が続くと海浜植生の優占する群落タイプが減少するとともに、樹林化が進行し、遷移が進行すると予想される。海浜植生を持続的に維持していくためには、調査対象地域周辺を攪乱することで裸地化を図り、砂丘を再流動化させることが必要と考えられる。
- 著者
- 中村 航 山田 宮土理 村本 真 畑中 久美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.60, pp.875-880, 2019-06-20 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 3
In Japan, the cob construction is often used for fences, but is rarely used for buildings. These buildings are being dismantled by aging and change of owner. We conducted measurement on the warehouse and the wall built with the cob construction method around the Yamanobe road in Nara prefecture. As a result, it is found that there is relationship between the structure of the warehouse, the area and the application. Furthermore, it was possible to estimate the construction method from the states of the mud wall.
1 0 0 0 OA 伝統土壁構法の検証 「団子積み」と「練り土積み」構法の実践と施工特性に関する研究
- 著者
- 畑中 久美子 木村 博昭 村本 真 加藤 亜矢子
- 出版者
- 一般社団法人 芸術工学会
- 雑誌
- 芸術工学会誌 (ISSN:13423061)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.113-120, 2016 (Released:2018-12-24)
本論文では、「団子積み」と「練り土積み」と呼ぶ古来から日本にある、湿った土を積み上げる土壁構法に焦点を当てる。本論文の目的は、建築における土壁構法の選択肢を増やす事や、2つの構法の活用可能性を広げることを最終目標と捉え、その第一歩として、今後の建築のための記録を残すことと、2つの構法の違いおよび、版築や2つの構法に類似する土を積み上げる土壁構法に対する位置付けを明確にすることである。「団子積み」と「練り土積み」の施工特性を把握するため、以下の方法で研究を進めた。 1)「団子積み」と「練り土積み」構法の定義 2)「団子積み」と「練り土積み」の検証実験 2つの構法のいずれか、もしくは両方を用いた3つの建築や工作物によるプロジェクトの検証実験について、計画と概要、材料、道具、施工の要領をまとめ、工程、施工日数、人数等を比較、考察する。 3)1)〜2)を総合して、「団子積み」と「練り土積み」を用いた土壁構法の施工特性をまとめる。3つのプロジェクトと使用構法は下記のとおりである。 1.「公園灰屋」における「団子積み」 2.「藁葺き泥小屋」における「練り土積み」 3.「かまど」における「団子積み」と「練り土積み」の混合 検証実験の結果 「団子積み」と「練り土積み」の施工特性をまとめると、①施工速度が「団子積み」より「練り土積み」の方が速かったこと。②土に混ぜる水の量の目安が、「団子積み」の方が「練り土積み」より多かったこと、③土を練る際の藁は、「団子積み」では加え、「練り土積み」は加えなかったこと。などが挙げられた。本研究をとおして明らかになったことは、①「団子積み」「練り土積み」共、建物平面に曲面が多用されている場合は、型枠コストと、造形のしやすさの面で、型枠を必要とする版築よりも優位である。②「団子積み」より、「練り土積み」の方が施工速度が速く、乾燥期間も短いため、総工期を短かくすることができる。③ 1 日の壁の施工可能高さは「団子積み」「練り土積み」共600㎜程度である。さらに、版築や、2つの構法に類似する湿った土を積み上げる土壁構法に対する関係性を図示した。
1 0 0 0 OA 常時微動測定による横浜市都筑区池辺町地域の軟弱地盤構造の推定
- 著者
- 年縄 巧 高浜 勉 中山 将史
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震工学会
- 雑誌
- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1_26-1_36, 2020 (Released:2020-01-31)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
2014年に不同沈下被害が発生した箇所と1923年関東地震の際に木造家屋の全壊率が80%以上であった河内集落を含む横浜市都筑区池辺町地域において高密度の常時微動測定を行い,軟弱地盤の厚さの分布と地盤震動増幅率を推定し被害との関連性を調べた.ボーリング調査地点近傍で得られた微動H/Vスペクトル比のピーク周期(Tp)とN値50深さ(D)を比較し,TpからDを推定する式を求めた.この式を用いてこの地域のDの分布を推定すると,低地部のほとんどはD=10-15 mであるが,台地際低地北端部のDは15 mを超え,局部的にはDが20 mを超す領域が存在し,2014年の不同沈下発生地点は表層地盤の厚さが大きく変化する領域に位置していることがわかった.また,微動H/Vスペクトル比のピーク値(Ap)から強震スペクトル比(As)を推定し,その面的分布と集落毎の中央値を求めた.1923年関東地震の際の木造家屋全壊率がそれぞれ80%以上,30-50%の河内・川向集落はAsの中央値が5以上,全壊率が10%未満の藪根集落はAsの中央値が3以下であり軟弱地盤の地盤震動増幅が被害を大きくした可能性を示している.しかしながら,河内集落の木造家屋全壊率が特に大きかった理由については地盤震動増幅だけから説明することはできなかった.
1 0 0 0 OA 超高齢社会における歯周病治療の役割
- 著者
- 吉成 伸夫 石原 裕一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.18-25, 2015-03-28 (Released:2015-05-13)
- 参考文献数
- 39
1 0 0 0 OA 矩形都市移動時における太陽光逆光割合
- 著者
- 髙原 勇 大澤 義明 湊 信乃介
- 出版者
- 一般社団法人 地理情報システム学会
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.105-114, 2016-12-30 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
Sun glare may be a major hazard for car drivers in the winter. This is because the sun is low in the sky during the morning and evening where the roads are at their busiest with people driving to work and to home. The purpose of this article is to analyze what to extend the sun glare disability arises in rectangular area. We derive the probability of sun glare by use of computing the number of trips driving toward the sun. In addition, we examine how the shape, the direction, the latitude of the rectangular study area affect such probability.
1 0 0 0 OA 道路地図および航空写真の特徴量を用いたドライブ風景の推定
- 著者
- 奥 健太 山西 良典 松村 耕平 川越 恭二
- 出版者
- Webインテリジェンスとインタラクション研究会
- 雑誌
- Webインテリジェンスとインタラクション研究会 予稿集 第6回研究会 (ISSN:27582922)
- 巻号頁・発行日
- pp.60-65, 2015 (Released:2022-11-07)
- 参考文献数
- 10
我々は,ドライブ風景を考慮した経路推薦システムの実現を目指している.そのためには,道路ネットワークを構成するリンクに対し,山道風景や海沿い風景,田園風景などといったドライブ風景タグを付与する必要がある.既存の道路ネットワークデータとしては,市販のものやOpenStreetMapなどがあるが,ドライブ風景タグが付与されたものは見当たらない.また,ドライブレコーダで記録された車載カメラの画像からドライブ風景を推定する方法も考えられるが,カメラ角度の微妙なずれや明るさの変化などによりノイズが多く,データの網羅性も低い.そこで,本稿では,Webから網羅的に収集が可能な道路地図画像および航空写真に着目し,ドライブ風景を推定するために有効な画像特徴量について明らかにする.具体的には,収集したドライブレコーダデータを分析し,ドライブ風景の推定に有効と考えられる画像特徴量について仮説を立案し検証した.また,有効と判断された特徴量を含めた学習モデルを構築し,テストデータを用いたドライブ風景ラベルの推定精度の評価を行った.
- 著者
- 菊池 美幸
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.2, pp.135-159, 2019 (Released:2021-02-19)
1 0 0 0 OA 舌下免疫療法の効果発現における制御性T細胞の役割
- 著者
- 松田 将也 寺田 哲也 北谷 和之 河田 了 奈邉 健
- 出版者
- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会誌 (ISSN:24357952)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.21-26, 2021 (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 44
舌下免疫療法(sublingual immunotherapy:SLIT)は,抗原を舌下に長期間投与し免疫寛容を誘導することから,アレルギー疾患に対する唯一の根治療法といえる。SLITのアレルギー性鼻炎に対する臨床的有効性は確立されており,その効果発現メカニズムには制御性T細胞(Treg細胞)の増加が関与するとされるが,その詳細は不明な点が多い。Treg細胞には,マスター転写因子としてforkhead box P3(Foxp3)を発現するCD25+ CD4+ T細胞(Foxp3+ Treg細胞),ならびに抗炎症性サイトカインであるIL-10を高産生するFoxp3– CD4+ T細胞(Tr1細胞)が存在する。SLITを行ったアレルギー性鼻炎の患者においては,Foxp3+ Treg細胞ならびにTr1細胞の顕著な増加が認められることから,これらの細胞がアレルギー症状の抑制に重要な役割を担うことが推察される。本総説においては,これまでに報告されてきたSLITによるTreg細胞の誘導機序,ならびにSLITの効果発現におけるTreg細胞の役割について概説するとともに,近年発見されたTreg細胞誘導剤の有用性について考察した。SLITにおけるTreg細胞の誘導機序の解明ならびにその誘導薬物の創出は,より効率的なSLITの創出に繋がると考えられる。
1 0 0 0 OA STN液晶ディスプレイ用色補償フイルム
- 著者
- 岡田 豊和 中村 公成
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.380, 1989-05-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2 1
1 0 0 0 OA トキの胃内容物 (佐渡1933年採取) の写真撮影者の特定および関連する二・三の知見
- 著者
- 塚本 洋三 鶴見 みや古
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.107-112, 2013-03-30 (Released:2015-03-30)
- 参考文献数
- 15
The Yamashina Institute of Ornithology owns the 11,982 photograph collection of Kenji Shimomura (1903–1967), the pioneer of wildlife photography in Japan. One of the prints in the collection (ID no.: AVSK_PM_1198, Fig.1a) depicts the stomach contents of Crested Ibis Nipponia nippon. When the computer database of the Shimomura collection was made, the photographer of this print was plausibly thought to be Shimomura, but was uncertain. Later we discovered in some publication that this photo was taken by Jicho Ishizawa (1899–1967), an insect and bird researcher at the then Wildlife Research Laboratory of the Ministry of Agriculture. Because the photo showing stomach contents of the endangered wild Crested Ibis is rarely publicized, we are of the opinion that the accurate identification of the photographer is academically important. Based on the memorandum on the backside of the print, handwriting analysis was made by Shimomura's and Ishizawa's relatives. The implications of the rubber stamps on the backside were also considered. These investigations concluded that the photo in question was almost certainly taken by Ishizawa, who also identified the stomach contents. We hope that this example will alert researchers to the possibility of incorrect citation of the photographer in earlier publications already published, and that, when detected, these be corrected in subsequent citations. Comments on related subjects that arose through the process of identifying the photographer are also given.
1 0 0 0 OA 仮説生成型の研究を論文にしていくには : 「検証」の新しい基準作りにむけて
- 著者
- 高木 和子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.43-44, 1992-09-25 (Released:2017-07-20)
1 0 0 0 OA 茨城縣一豊村におけるワイル氏病の淫浸状況について
- 著者
- 本橋 久和 本橋 久男 野田 喜代一
- 出版者
- 口腔病学会
- 雑誌
- 御茶の水學會誌 (ISSN:21857164)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.25-30, 1951-03-31 (Released:2010-10-08)
- 参考文献数
- 4
以上著者等は茨城縣一農村におけるワイル氏病について, 著者等の経驗した例の患者を対象として, その発生状況, 協床的事項について檢討考察した。以下簡単に本報告の要旨を列記する。1) 昭和12年より同24年に至る13年間に本橋病院を訪れた薪患数は約3万人ありそのうち28例がワイル氏病患者であつた。すなわち約0.1%に本病患者の発生を見た。そしてこの28例について調査檢討した成績について報告した。2) 本病の発生には特定の地域の問題があり, ここを仕事場とする入に発生し易いめ, 発生者は2例の例外を除いては農夫と漁夫に限られた。3) 感染経路はすべて創傷面より起ると考えられた。4) 著者の28例について症歌と診断についての檢討を試みた。5) 血清療法の効果は著しいが, ペニシリンの発見により治療血清が部座に入手できない場合に9も早期治療が行いうる。6) 早期治療が行き届けば死亡率は0となる。以上の本報告を終るにのぞみ, 終始御懇篤な御指導と御校閲をいただいた所長宮本先生ならびに御後援御指導をいただいた霞ケ浦分院長大淵先生に心から感謝いたします。
1 0 0 0 OA 虚構論と語り論 ――小川洋子「ハキリアリ」「トランジット」など――
- 著者
- 中村 三春
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.12-22, 2017-04-10 (Released:2022-04-28)
物語世界は物語文の原因として作られ、同時に物語文は物語世界を原因として作られたものと想定される。従って物語文が物語世界の次元に対して第二次の位置づけとなる局面が考えられる。その時、物語文は自己同一的なものではなく、媒介され引用されたものと見なされる。小川洋子の「ハキリアリ」および「トランジット」を例として、語りによる媒介の局面をとらえてみる。語りこそ、言語の〈トランジット〉(乗り継ぎ)にほかならない。
- 著者
- Keiko Wada Michiko Tsuji Kozue Nakamura Shino Oba Sakiko Nishizawa Keiko Yamamoto Kaori Watanabe Kyoko Ando Chisato Nagata
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.37-42, 2021-01-05 (Released:2021-01-05)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 7 11
Background: Few studies have examined the association between seaweed intake and blood pressure in children. We conducted an intervention study to investigate whether seaweed intake affects blood pressure.Methods: Subjects were children aged 4 to 5 years attending a preschool in Aichi Prefecture, Japan, in 2010. Among 99 students, 89 (89.9%) were enrolled in our study. Nori (dried laver), an edible seaweed widely consumed in Japan, was used as a dietary intervention. Children in the intervention group were asked to consume 1.76 grams per day of roasted nori in addition to standard meals for 10 weeks. Children in the control group consumed their usual diet. Before the intervention and at the 10th week of the intervention, children’s blood pressure was measured three times successively using an automated sphygmomanometer with subjects in a sitting position. Changes in systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were compared between 55 children in the intervention group and 26 in the control group after adjustment for SBP and DBP before the intervention.Results: Changes in SBP were −8.29 mm Hg in the intervention group and +0.50 mm Hg in the control group (P for difference in change = 0.051). Changes in DBP were −6.77 mm Hg in the intervention group and −0.05 mm Hg in the control group (P = 0.031). In girls, no difference in blood pressure changes was found between the intervention and control groups.Conclusion: Nori intake lowered DBP level in boys. Seaweed intake might have preventive effects on elevated blood pressure in childhood.