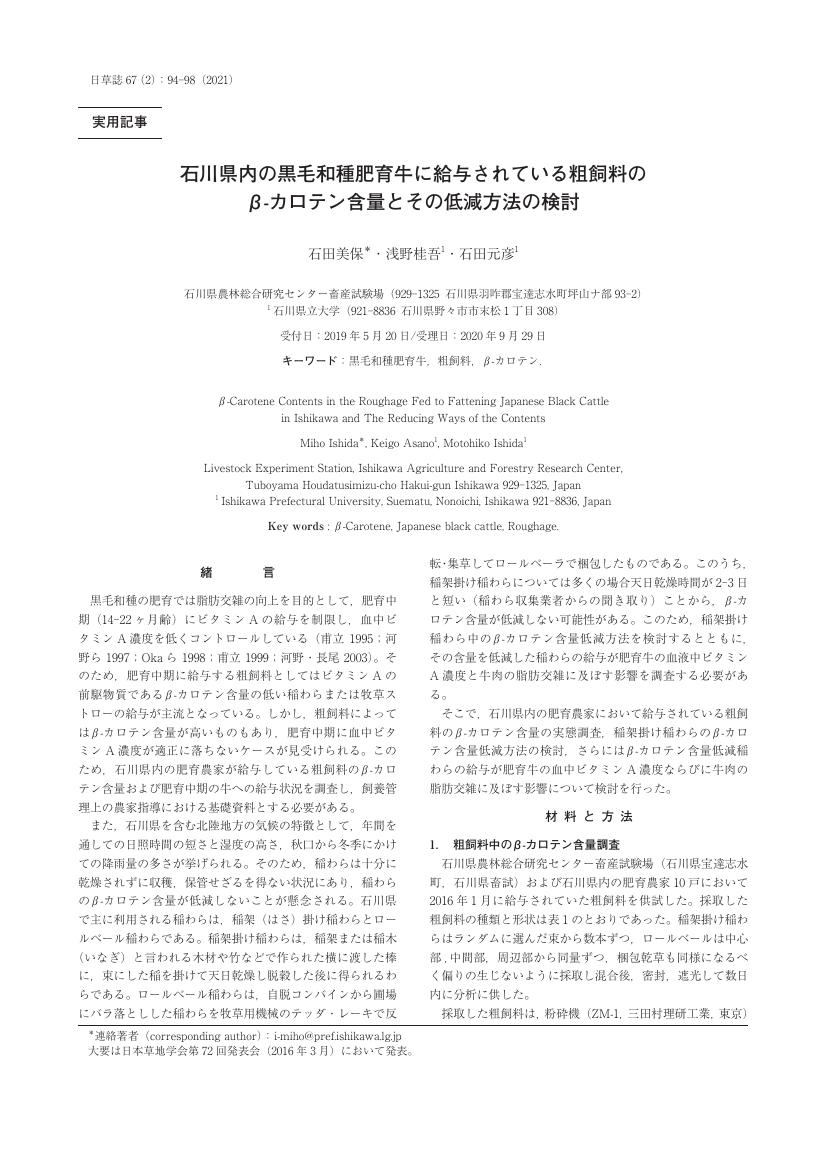1 0 0 0 OA 精子の成熟機構と受精能
- 著者
- 淨住 大慈 伊川 正人
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.18-23, 2022 (Released:2022-01-01)
- 参考文献数
- 20
「受精」という言葉は今日においても私たちに生命の神秘やロマンを感じさせてくれる.しかしそれは,不妊のような私たちの人生に直結する問題も,科学的にはまだ十分な解明に至っていないということの裏返しかもしれない.本稿では,哺乳類の精子がどのようにして受精の能力を獲得し,何が原因となって不妊となるのか,ゲノム編集技術によって近年各段に進展しつつある個体レベルでの研究をベースに,筆者らによる最新の知見も交えながら解説したい.
1 0 0 0 OA マミチャジナイ,シロハラ,アカハラ,アカコッコの翼式の差異
- 著者
- 今野 怜 今野 美和
- 出版者
- 日本鳥類標識協会
- 雑誌
- 日本鳥類標識協会誌 (ISSN:09144307)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1_2, pp.21-35, 2020-12-31 (Released:2021-10-01)
- 参考文献数
- 17
マミチャジナイTurdus obscurus 29個体,シロハラT. pallidus 39個体,アカハラT. chrysolaus 79個体,アカコッコT. celaenops 16個体の翼式の要素(初列風切最長羽,p9の位置,初列風切の間隙,外弁欠刻)を比較した.4種の各要素は有意に異なっており,渡る距離が長い種ほど翼の形状が尖っていた.初列風切の間隙の見た目はマミチャジナイ・アカコッコとシロハラ・アカハラに大別された.アカコッコは間隙を形成する羽毛が独特で外弁欠刻はより近位にあると推察されたこと,マミチャジナイの外弁欠刻はより遠位にあったこととあわせ,翼式は4種の識別に有効であった.
1 0 0 0 OA 千葉県におけるアカコッコTurdus celaenopsの記録
- 著者
- 桑原 和之 茂田 良光 野口 一誠 富谷 健三
- 出版者
- 日本鳥類標識協会
- 雑誌
- 日本鳥類標識協会誌 (ISSN:09144307)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.43-48, 2004 (Released:2015-08-20)
- 参考文献数
- 11
アカコッコTurdus celaenopsは,伊豆諸島とトカラ列島でのみ繁殖する日本固有種である.本種は,本州では房総半島と伊豆半島で稀に越冬期の記録がある.1983年12月15日から1984年5月7日まで雄成鳥が千葉県銚子市(35°44′N,140°51′E,)で越冬し,また1992年4月25日から5月2日に雄成鳥が千葉県山武郡山武町(35°39′N,140°23′E,)で観察された.この2例が千葉県における初めての確実な報告例となる.
1 0 0 0 北海道宗教大鑑 : 開道百年記念
1 0 0 0 OA 伊勢紀行についての覚え書
- 著者
- 白井 忠功
- 出版者
- 立正大学文学部
- 雑誌
- 立正大学文学部論叢 (ISSN:0485215X)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.59-73, 1978-12-01
1 0 0 0 OA 原発性肺軟骨肉腫と考えられた1例
- 著者
- 岡松 佑樹 井上 勝博 川上 覚 河口 知允 内山 明彦 笹栗 毅和
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会
- 雑誌
- 肺癌 (ISSN:03869628)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.373-378, 2016-10-20 (Released:2016-11-11)
- 参考文献数
- 15
背景.軟骨肉腫は大腿骨や骨盤から発生することが多く,肺より発生する軟骨肉腫は極めて稀であり,国内では自験例を含めて18例が報告されているのみである.症例.53歳男性.高血圧症,脂質異常症で近医通院中であった.初診1か月前より咳嗽を認め,かかりつけ医を受診した.胸部X線写真で右下肺野に腫瘤影を指摘されたため当科紹介受診となり,精査目的に入院となった.胸部CTで右中下葉にまたがる腫瘤を認め,気管支鏡検査では確定診断には至らなかった.MRI,FDG-PET検査により悪性腫瘍が疑われたため,右中下葉切除術を施行した.切除標本の病理組織所見では,硝子軟骨様の多量の基質中に大小不同の異型性を有する軟骨細胞様の腫瘍細胞が増生しており,軟骨肉腫の病理診断となった.全身検索の結果,他臓器からの肺転移は否定的であり原発性肺軟骨肉腫と考えられた.術後経過は良好で,現在も再発や他臓器の原発巣の出現なく経過している.結語.今回我々は肺原発と考えられる軟骨肉腫の1例を経験した.治療の第1選択は手術による完全切除とされ,完全切除された場合の予後は比較的良好であるが,再発例も多く自験例も慎重な経過観察が必要である.
- 著者
- 屋形 禎亮
- 出版者
- The Society for Near Eastern Studies in Japan
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.125-129, 1974-09-15 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 OA 観光地化が進む大阪市道頓堀・戎橋筋周辺街路における歩行者行動の実態
- 著者
- 木村 優輝 嘉名 光市 蕭 閎偉
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.975-982, 2019-10-25 (Released:2019-11-06)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4
観光地化が進む都市では、来訪者の増加によって、近隣の人々による利用が低下している地域がある。本研究では、大阪市道頓堀・戎橋筋周辺の街路において追跡調査を行い、街路上の歩行者の行動を把握した。それにより得られた結果を用いてクラスター分析を行うことで、対象地の街路を歩行者の行動の観点から9タイプ、歩行者の属性の観点から6タイプに類型化することができた。これらの街路類型を街路の空間特性と比較することによって、歩行者行動に影響を与える要素を把握することができた。結論として、観光地化が進む都市において、近隣の人々と旅行者が快適に共存し、調和のとれた歩行環境を実現するためには、地区内における歩行者を、地区全体で上手く分担することが求められると考えられる。
1 0 0 0 OA パリ公主と韓国仏教
- 著者
- 樋口 淳
- 出版者
- 専修大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文科学年報 (ISSN:03878708)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.241-270, 2023-03-31
1 0 0 0 OA 近代東京の名所体験 : 名所図会・案内本の分析を中心として
- 著者
- 米家 志乃布
- 出版者
- 法政大学文学部
- 雑誌
- 法政大学文学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Letters, Hosei University (ISSN:04412486)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, pp.41-53, 2023-03-03
本研究では,江戸東京の代表的な名所図会および案内本に記載された名所とその分布傾向を比較し,各史料の違いを明確にしたうえで,近代東京における人々の名所体験を論じることを目的とした。その際,東京における行政区画,山の手と下町という地形的特徴,近代交通網の整備・発展という観点から,名所体験と東京の地域性との関係について分析・考察した。その結果,近代東京における人々の名所体験は,明治・大正・昭和を経て,より高密度に,より広範囲に展開し,名所風景の近代化という側面だけでなく,名所体験として多様化したことを論じることができた。
1 0 0 0 OA 腸肝相関を介した肝免疫寛容誘導機序の解明
肝疾患における治療介入の標的として腸肝臓軸が注目されている。本研究では、腸炎と肝炎のタンデムモデルを用いて、腸管粘膜バリア破綻状態では、続発する肝炎に対してIL-10産生マクロファージによる免疫寛容が誘導されることを示した。この免疫寛容は腸管除菌により消失することから、腸内細菌叢とその代謝産物がこのプロセスに必要であることが示唆された。免疫寛容を誘導する代謝産物の候補として1-methylnicotinamide(1-MNA)を同定し、1-MNAによる肝炎抑制効果も腸管除菌により消失することを示した。本研究の成果から、腸肝臓軸を介した肝臓免疫応答のバランス調節機構に関して新たな知見が得られた。
1 0 0 0 OA 慢性関節リウマチの経過中に発症した潰瘍性大腸炎の1例
- 著者
- 森 正樹 川田 裕一 湖山 信篤 今村 洋 昆野 博臣 熊沢 健一 芳賀 陽子 矢川 裕一 芳賀 駿介 梶原 哲郎 榊原 宣 市岡 四象
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.265-270, 1985 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 1
潰瘍性大腸炎に慢性関節リウマチ様の末梢型関節炎がみられることはよく知られているが,真の慢性関節リウマチと潰瘍性大腸炎の合併はまれである.われわれは慢性関節リウマチの治療中に発症した潰瘍性大腸炎の1例を経験した.症例は37歳の女性で,昭和51年7月頃より関節症状出現,53年7月典型的慢性関節リウマチと診断された.非ステロイド性抗炎症剤の内服,ステロイド剤の関節内注入により治療されていたが,58年2月頃より消化器症状が出現した.同年8月当科入院,潰瘍性大腸炎(左側大腸炎型,活動期,重症,初回発作型)と診断された.潰瘍性大腸炎は絶食とサラゾスルファピリジン,プレドニゾロンなどの全身投与により寛解した.慢性関節リウマチにみられる潰瘍性大腸炎以外の病変についても文献的に考察した.
1 0 0 0 OA 石川県内の黒毛和種肥育牛に給与されている粗飼料のβ-カロテン含量とその低減方法の検討
1 0 0 0 OA 二つの邪馬台国観 白石説と宣長説 (昭和四十年四月十二日 会員 坂本太郎 紹介)
- 著者
- 宮崎 道生
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.67-89, 1965 (Released:2007-05-30)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- HASAN MEHRAJ
- 出版者
- 神戸大学
- 巻号頁・発行日
- 2022
1 0 0 0 OA 非営利型民間フリースクールの「経営」を考える
- 著者
- 武井 哲郎 橋本 あかね 今川 将征 櫻木 晴日 矢野 良晃 三科 元明 永田 佳之 竹中 烈
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, pp.75-76, 2021-08-16 (Released:2021-10-22)
1 0 0 0 OA 緩和医療における呼吸困難への対処法 ―がんと非がん疾患の呼吸困難へのオピオイドの役割―
- 著者
- 山口 崇
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.177-180, 2022-04-28 (Released:2022-04-28)
- 参考文献数
- 20
呼吸困難は,がん・非がんに関わらず,緩和ケア対象患者において頻度の高い重要な症状である.国内外の各種診療ガイドラインにおいて,モルヒネをはじめとするオピオイドはがん患者・非がん患者の呼吸困難に対する症状緩和薬物療法の第一選択として推奨されている.しかしながら,これらのガイドライン推奨の根拠とされている臨床研究は試験デザイン上いくつかの懸念があり,堅牢なエビデンスとは言えない現状がある.またモルヒネ以外のオピオイドについては,臨床研究自体がかなり不足しており,モルヒネの代替薬となりうるのかに関する知見は不足している.また重要な課題として,背景疾患によるオピオイドの効果差に関しても十分な知見は積み上げられていない.このような背景から,呼吸困難に対するオピオイドに関する臨床研究を今後もより一層進めていき,臨床現場の道しるべとなるようなエビデンスを創出していくことが重要である.