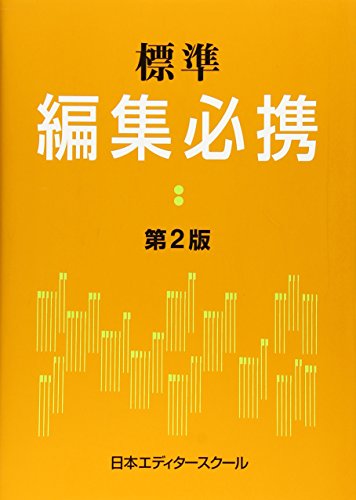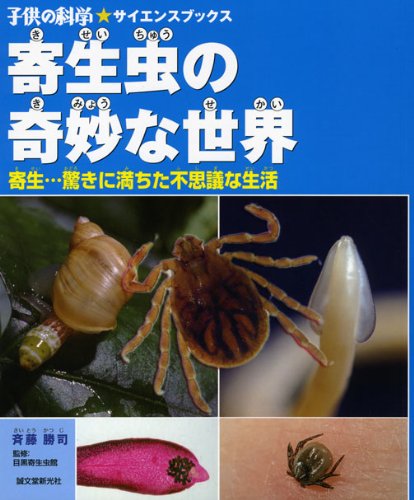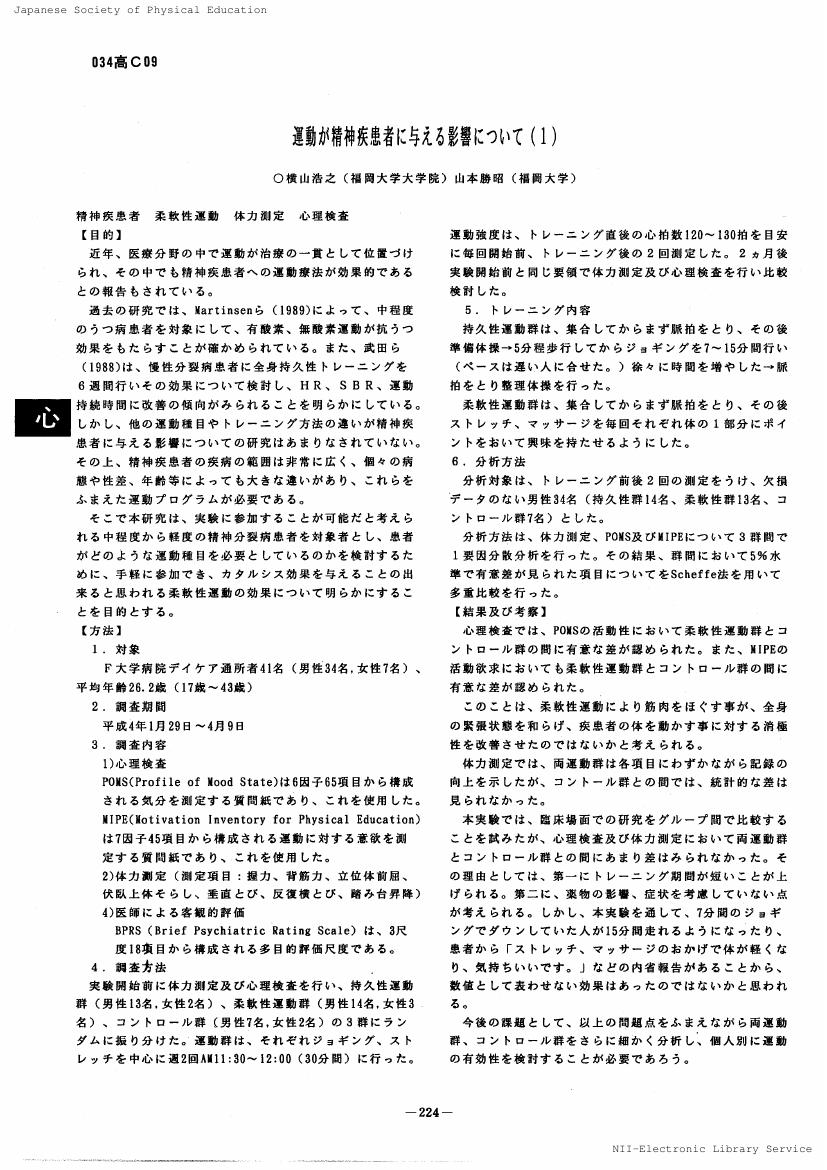1 0 0 0 OA 言語統計学入門(4) 平均値に差があるのかないのか
- 著者
- 林 直樹
- 出版者
- 計量国語学会
- 雑誌
- 計量国語学 (ISSN:04534611)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.286-299, 2022 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 33
本稿では,言語データの平均値に差があるのかどうかを確認する際の統計的手法について概説する. まず,平均値の定義や適用事例について概説した後,言語研究分野における平均値の適用事例について述べる. 続いて,統計的手法に基づく平均値の比較方法としてt検定と一元配置分散分析を取り上げ,その計算法を示すとともに,実際のデータに基づき分析していく.
- 著者
- Gyana Ratna SRAMAN
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.477-474, 2002-12-20 (Released:2010-03-09)
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 高校の生徒・進路指導におけるアイデンティティ概念に関する誤った教育とその弊害
1 0 0 0 OA 幼児の感情理解に及ぼすマスクと音声の影響 -コロナ禍の表情認知に対する試行的検討-
- 著者
- 堀 由里
- 出版者
- 桜花学園大学
- 雑誌
- 桜花学園大学保育学部研究紀要 = BULLETIN OF SCHOOL OF EARLY CHILDFOOD EDUCATION AND CARE OHKAGAKUEN UNIVERSITY (ISSN:13483641)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.173-178, 2022-03-15
コロナ禍でマスク生活が続く中、幼児はマスク有りの表情から他者の感情状態を正しく認知することができるのかを試行的に検討するため、マスクをした状態の保育者(写真)や他児(イラスト)の表情と感情音声をマッチングさせる課題を幼児に行った。その結果、8試行のうち正解は半分の4試行で、表情の種類は用意した全ての表情があてはまった。またイラスト刺激よりも写真刺激の方が高正答率であった。一方、表情刺激に対するラベリングを検討した結果、イラスト刺激には全4種の感情に正しいラベリングができていた反面、写真刺激は「怒り」のみ正答で、「喜び」「驚き」「悲しみ」は誤答であった。つまり、写真刺激は、音声刺激とのマッチングにおいては正しく回答できていたが、ラベリングにおいては難しさを感じていたようだった。子どもたちが日々の生活でコミュニケーションをとるのは、イラストで表現されたような分かりやすい表情ではない。そのため、実際の人間の表情を使用した方がより現実に近い状況でのデータを得ることができると考えられる。
1 0 0 0 標準編集必携
- 著者
- 日本エディタースクール編集
- 出版者
- 日本エディタースクール出版部
- 巻号頁・発行日
- 2002
1 0 0 0 OA スペイン刑法の最近の改正の概要 および訳語の若干の変更
- 著者
- 江藤 隆之
- 出版者
- 桃山学院大学 総合研究所
- 雑誌
- 桃山法学 (ISSN:13481312)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.129-141, 2021 (Released:2021-10-15)
- 著者
- Bibian Diway Ling Chea Yiing Mohd Effendi Wasli Yayoi Takeuchi
- 出版者
- JAPAN SOCIETY OF TROPICAL ECOLOGY
- 雑誌
- Tropics (ISSN:0917415X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.1-14, 2023-06-01 (Released:2023-06-01)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 2
In Sarawak, Malaysia, logging is conducted with a 25-year harvesting cycle; however, it remains largely unclear if this cycle length is sufficient for forest recovery. This study aims to investigate how the structure of logged forests recovered along the periods after logging. We conducted this study in the Anap-Muput Forest Management Unit (AMFMU), Sarawak. We first established permanent sample plots with different logging history; that is, from 5 years to more than 37 years after the most recent logging. Using the various sample plots, we assessed the stem density, basal area (BA), proportion of dipterocarps, growth and mortality. To compare the forest structure of the logged over forests with that of primary forests, we used our previous data of a primary forest in Batang Ai National Park. We found significant differences in the stem density, total BA, and the proportion of dipterocarp among the plots. Generally, the stem density and total BA increased with the period after logging and decreased with diameter at breast height (DBH) size classes, except of tree of ≥60 cm DBH in several plots. The growth rates and mortalities were higher in more recent logged forests. These results indicated that logged forest was recovering with periods after logging partly because of higher growth rate; however, even in a forest of 37 years after logging, the forest structure was not fully recovered compared to the primary forest. Thus, we concluded that a 25-year harvesting cycle in the selective logging system would not be sufficient for the AMFMU forest to recover. We further need other effective strategies with systematic monitoring.
1 0 0 0 OA 「記憶」し,「恐れ」,「楽しむ」-フィクションのなかの核
- 著者
- 川口 悠子
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.6, pp.299-307, 2018-12-15 (Released:2020-12-15)
- 参考文献数
- 61
1 0 0 0 寄生虫の奇妙な世界 : 寄生…驚きに満ちた不思議な生活
1 0 0 0 OA 大学におけるオンデマンド授業の改善点について
- 著者
- 串山 寿 三浦 洋子
- 出版者
- 千葉経済大学
- 雑誌
- 千葉経済論叢 = CHIBA KEIZAI RONSO (ISSN:21876320)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.147-161, 2022-06-30
オンデマンド授業は、教員は授業の資料をアップロードし、学生は受講したい時に好きな時間に受講ができるメリットがある一方、学生の自主性に任せることによる授業の理解度のバラツキが考えられる。新型コロナウイルス拡大の影響で、オンライン授業やオンデマンド授業は当たり前になってきている中、教員は試行錯誤しながら授業を運営している。その授業の中で、履修生と教員とのあいだで直接意志の疎通のツールとなるのはチャットであるが、そこで交わされる質疑応答では、質問の内容以前に、情報関連の用語等に関して、教員としては当然わかっているだろうと思われることを学生は知らず、双方のちぐはぐさが目立ち、往々にして一方通行にもなりうる事態が生じている。主な原因は履修生の情報関連の知識不足であり、教員側は授業の他にそれらの補充もしなければならない、ということになる。そこで本稿では、オンライン授業やオンデマンド授業のイントロダクションとして、情報関係の基礎知識を教えることを念頭に、教育内容を考えてみた。
1 0 0 0 OA 「ティティテイメント」による貧困
- 著者
- 李 為
- 出版者
- 京都産業大学マネジメント研究会
- 雑誌
- 京都マネジメント・レビュー = Kyoto Management Review (ISSN:13475304)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.135-151, 2023-03-01
1 0 0 0 OA 1-4 Microsoft「Teams・OneNote・Forms・Stream」を利用した歯学部5年生対象オンライン臨床実習の試み ―オンライン実習および小グループ討論に対する学生の感想―
- 著者
- 鈴木 一吉
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.531-533, 2020-10-25 (Released:2020-12-09)
- 著者
- 串山 寿 三浦 洋子
- 出版者
- 千葉経済大学
- 雑誌
- 千葉経済論叢 = CHIBA KEIZAI RONSO (ISSN:21876320)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.95-112, 2021-12-01
新型コロナウイルス拡大の影響で、本学では一定数以上の受講者がいる授業については、オンデマンド授業を実施せざるをえなくなり、さらに今後こうした授業形態は長期間継続していくと予想される。もちろん教育分野に情報化が浸透していることは数年前から顕著であったが、本学は旧態然とした授業形態を採用していて、その波に乗り切れていなかった。しかし、絶好の機会が、新型コロナウイルス拡大とともに到来した。ここで大学のオンデマンド授業をどのように展開していくべきか、教員と学生との間での様々なやりとりを通して試行錯誤を繰り返すことにより、将来、情報化を土台にした大学教育をどのように実施すればよいか、そうした課題に一つの答えを導くことができるだろう。すなわち、本稿は、大学教育の将来を見据えながら、オンデマンド授業の実施方法を、暗中模索の中で、著者らが具体的に行った記録である。 本稿では、本学学生のオンデマンド授業を開講するうえで、学生の利用環境を調査するとともに、本学学生を対象にMicrosoft Forms(以下、Forms)を利用した出席管理についてその方法を提示し、学生のアンケートデータも加味して、その有用性や課題を分析した。 さらに、Microsoft Teams(以下、Teams)を利用したオンデマンド授業を行う上で、授業資料の掲載方法について提案した。ここでは、オンデマンド授業の資料提示について、Power Automateⅲを利用して指定した時間に自動的に掲載する方法を提案する。 また、テスト方法については、Formsを利用して行うことにしたが、以前から行っていた選択式に加え、計算した値を答えさせる作問方法を紹介する。
1 0 0 0 OA パワーの変動と戦争
- 著者
- 野口 和彦
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.133, pp.124-140,L13, 2003-08-29 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 61
The purpose of this article is to analyze the impact of power shifts on war. Realists have argued that the change of the distribution of power among states is a major cause of war. Yet, they failed to explain how and why it affects state's incentive to attack another country. I propose a window theory for clarifying the causal relationship between them. I argue that the rapid change of relative power affects state's motivation to initiate a war in two ways. First, war is more likely when the window of vulnerability opens. When a state is the declining power, it tends to begin a preventive war for stopping its weakening. Second, war is more likely when the window of opportunity opens. Under the condition that the costs of an offensive war are low, a state in the rising process may want more secure position by the use of forces.I examine the cases of the opening of the Korean War and the Entry of the Chinese People's Volunteers in 1950 for testing the above hypotheses. North Korea decided to invade South Korea with the approval of the Soviet Union because it expected that the United States would not militarily intervene in the war. The Acheson's announcement of the defensive perimeter indirectly excluding South Korea gave Stalin an opportunity to permit the North's war plan against the South. Kim Il Sung also estimated that North Korea would win the war without US intervention in the short period of time because South Korea was quite weak. Chinese decision makers almost agreed to send the Chinese People's Volunteers to Korean peninsula immediately after that the US-led UN forces advanced across the 38 parallel. China expected better outcomes from the preventive war than a war started later because time would make its security worse. In short, the empirical tests confirm this window theory.
1 0 0 0 OA 口腔・咽頭梅毒
- 著者
- 余田 敬子
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.255-265, 2002-06-01 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 6
口腔咽頭梅毒のほとんどは性感染症としての第1・2期の顕症梅毒である.日本でも今後口腔咽頭梅毒の増加が危惧されている.当科で経験した23例からみた口腔咽頭梅毒の特徴は, 第1期病変で受診する症例は少なく第2期の粘膜斑“butterfly appearance”や乳白斑を呈して受診する症例が多いこと, 性器病変を伴わない例が多いこと, '98年以降HIV感染を合併している同性愛男性例が増えてきたことが挙げられる.口腔咽頭梅毒を的確に診断するため, 10代から高齢者までの患者の口腔咽頭病変に対し常に梅毒の可能性を念頭に置きながら対処し, 顔面・手掌.頭髪などの皮膚病変の有無にも着目することが有用である.
- 著者
- Masatoshi MORIMOTO Shunsuke TAMAKI Takayuki OGAWA Shutaro FUJIMOTO Kosuke SUGIURA Makoto TAKEUCHI Hiroaki MANABE Fumitake TEZUKA Kazuta YAMASHITA Junzo FUJITANI Koichi SAIRYO
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.87-92, 2023-12-31 (Released:2023-04-10)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3
Various approaches to lumbar interbody fusion have been described. The usefulness of full-endoscopic trans-Kambin's triangle lumbar interbody fusion has recently been reported. This technique has several advantages in patients with degenerative spondylolisthesis, including the ability to improve symptoms without decompression surgery. Moreover, given that the entire procedure is performed percutaneously, it can be performed without increasing the operation time or surgical invasiveness, even in obese patients. In this article, we discuss these advantages and illustrate them with representative cases.
1 0 0 0 OA Web議論における対立意見の止揚を促進するための意見の偏り解消手法の試作
- 著者
- 石塚 光 白松 俊 小野 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.1P1GS1003, 2022 (Released:2022-07-11)
2つの対立する主張があった際に,そのどちらの主張も否定せずに発展した答えを導くことを「アウフヘーベン」という.アウフヘーベンは日本語で「止揚」と訳される.この止揚の考え方は,話し合いや議論の場などで,皆の納得できる高度な結論を導くうえで重要だと考えられる. 本研究では,議論において対立意見の止揚が起こるのに必要な要素を明らかにするため,まずは止揚の度合を定量化した上で,議論実験とその分析を行った.その結果,議論中に自分の意見の根拠となる情報として投稿されたURLの数と,議論での止揚の度合いの間に弱い正の相関関係が確認された. また議論で止揚が起こるには前提として,対立する主張が存在する必要がある.しかし実際の話し合いや議論では,皆が似たような主張で対立する主張を述べる人が少ない,または存在しないことがある.このような状態は,議論の中で意見の偏りが生じていて,止揚が起こりにくい状態だといえる.そこで本研究では,議論においてbotが少数派の意見を補強する情報を投稿する,意見の偏り解消手法を提案する.
1 0 0 0 OA 034高C09 運動が精神疾患者に与える影響について(1)
- 著者
- 横山 浩之 山本 勝昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第44回(1993) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.224, 1993-10-05 (Released:2017-08-25)
1 0 0 0 OA 日本の経営機械史における組織内変化と情報技術の適応について
- 著者
- 法雲 俊栄
- 出版者
- 大阪商業大学商経学会
- 雑誌
- 大阪商業大学論集 = THE REVIEW OF OSAKA UNIVERSITY OF COMMERCE (ISSN:02870959)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.265-285, 2019-05-30