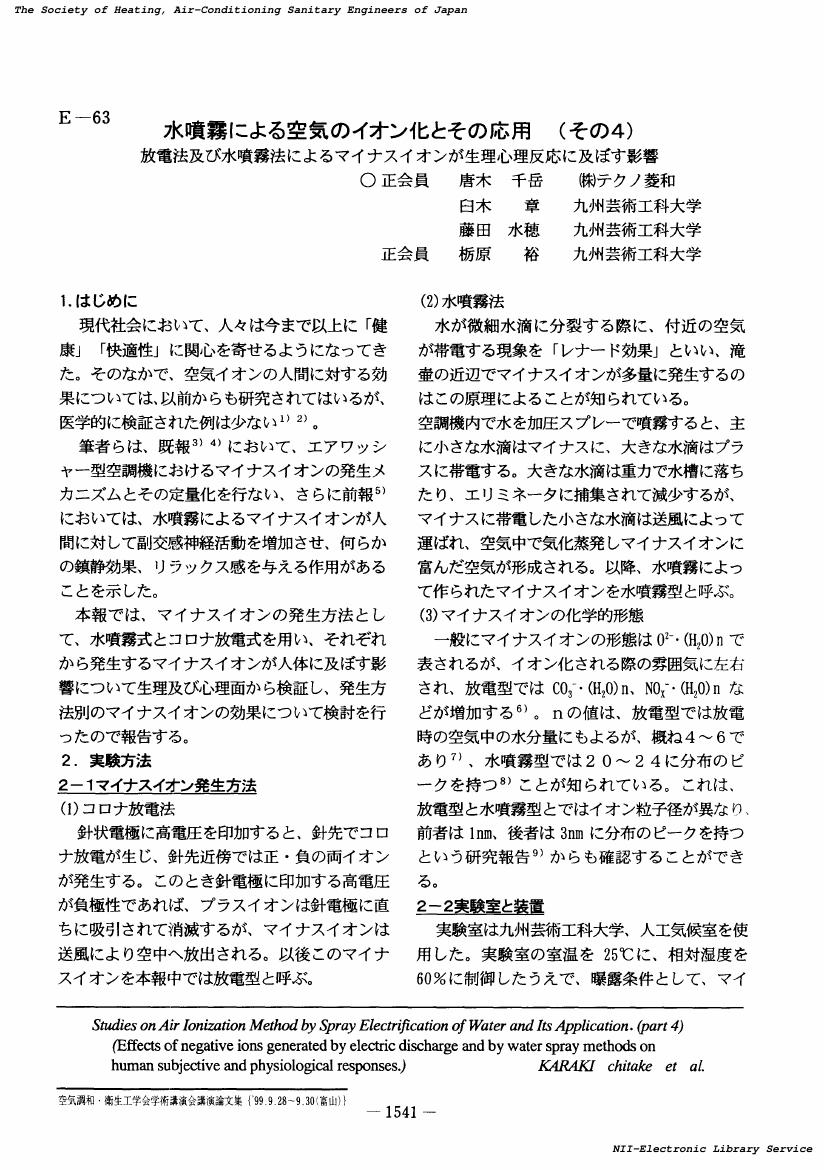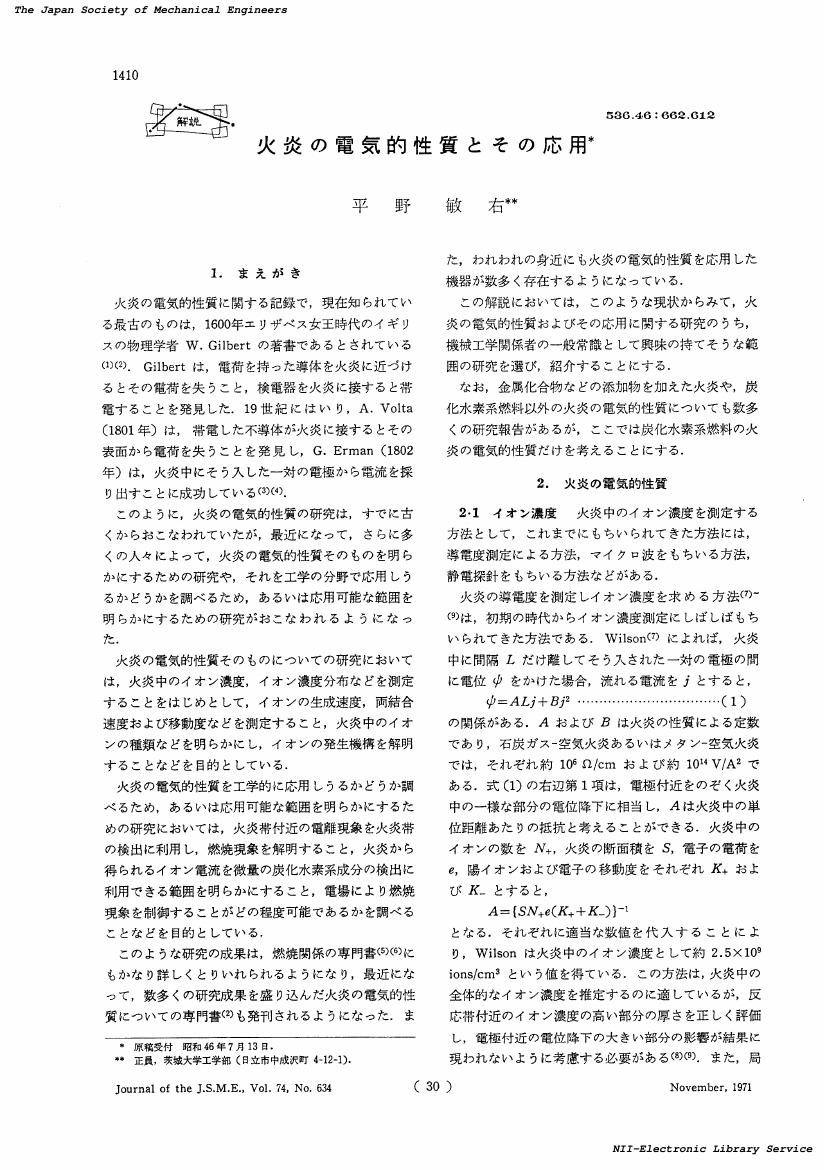1 0 0 0 OA 加納六郎先生を偲んで
- 著者
- 篠永 哲
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.i-ii, 2000-12-15 (Released:2016-08-09)
- 著者
- 大庭 潤也
- 出版者
- 全国社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科研究 (ISSN:0289856X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.41-50, 2008-03-31 (Released:2017-07-01)
- 著者
- 唐木 千岳 臼木 章 藤田 水穂 栃原 裕
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成11年 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.1541-1544, 1999-08-10 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 石原 理 太田 博明
- 出版者
- 社団法人 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.9, pp."N-163"-"N-167", 2008-09-01
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 脳脊髄液漏出症診断の最前線
- 著者
- 守山 英二
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳神経外傷学会
- 雑誌
- 神経外傷 (ISSN:24343900)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.7-17, 2014-06-20 (Released:2020-04-28)
- 参考文献数
- 21
Objective: The Cerebrospinal Fluid Hypovolemia Research Group beneficiary of a scientific research grant from the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) has concluded, that minor traumas, including motor vehicle accident, may cause spinal CSF leak. Because the first aim of MHLW research group was to confirm the occurrence of spinal CSF leak after minor trauma, very strict image diagnostic criteria were adopted. The purpose of this study is to weigh the MHLW criteria against the existing image diagnostics.Materials and Methods: Between March 2011 and January 2013, 178 patients suspected with spinal CSF leak underwent combined radioisotope cisternography (RIC) and computed tomography myelography (CTM). Serial spinal MRIs were performed before and after combined RIC ⁄ CTM studies.Results: RIC revealed overt RI leak in 47 patients (Group P), and CTM confirmed CSF leaks in 27 patients. In 52 patients with indirect RIC findings including early bladder filling and/or accelerated RI clearance (Group I), CTM confirmed CSF leaks in 7 patients. Eleven patients presented with typical clinical and radiological features of spontaneous intracranial hypotension (SIH) (Group P: 7, Group I: 4). Serial spinal MRI after combined RIC ⁄ CTM showed increased CSF leak in 33 ⁄ 47 patients (Group P), and 15 ⁄ 52 patients (Group I). In these patients, most CSF leaks were located at thoracolumbar junction.Conclusion: This study shows spinal CSF leak is a complication of minor trauma. In the diagnosis of spinal CSF leak, RIC has several advantages in addition to its inherent ability, especially when combined with CTM. Combined RIC ⁄ CTM often increases CSF leak, resulting in the enhanced sensitivity of spinal MRI.
1 0 0 0 OA 後期軍記『朝倉始末記』―伝本の分類、その性格―
- 著者
- 瀬戸 祐規
- 出版者
- 関西大学国文学会
- 雑誌
- 國文學 (ISSN:03898628)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.29-43, 2003-12-17
1 0 0 0 OA 乳酸投与がマウス骨格筋量に及ぼす影響
- 著者
- 大野 善隆 松井 佑樹 須田 陽平 伊藤 貴史 安藤 孝輝 横山 真吾 後藤 勝正
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.I-147_2, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに、目的】運動量に応じて骨格筋量は変化するが、その分子機構には不明な点が多く残されている。運動時に骨格筋は乳酸を産生し、分泌する。骨格筋には乳酸受容体が存在するため、乳酸は骨格筋にも作用すると考えられる。近年、培養骨格筋細胞を用いた実験において、乳酸によるタンパク合成シグナルの活性化ならびに筋細胞の肥大が報告されている。しかしながら、生体レベルでの骨格筋量に対する乳酸の影響は未解明である。そこで本研究では、乳酸がマウス骨格筋量に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。 【方法】実験には雄性マウス(C57BL/6J)を用い、足底筋とヒラメ筋を対象筋とした。マウスを実験1:対照群と乳酸投与群、実験2:対照群、筋萎縮群および筋萎縮+乳酸投与群、に分類した。筋萎縮群と筋萎縮+乳酸投与群のマウスには、2週間の後肢懸垂を負荷し、筋萎縮を惹起させた。乳酸投与群と筋萎縮+乳酸投与群のマウスには、乳酸ナトリウム(乳酸)の経口投与(1000mg/kg体重、5回/週)を行った。対照群と筋萎縮群には同量の水を投与した。全てのマウスは気温約23℃、明暗サイクル12時間の環境下で飼育された。なお、実験期間中マウスは自由に餌および水を摂取できるようにした。実験開始後2、3週目(実験1)および1、2週目(実験2)にマウスの体重を測定した後、足底筋とヒラメ筋を摘出した。筋重量測定後、体重あたりの筋重量を算出した。また、乳酸の経口投与が血中乳酸濃度に及ぼす影響を確認するために、乳酸の単回経口投与後にマウスの尾静脈から採血し、簡易血中乳酸測定器を用いて血中乳酸濃度を測定した。実験で得られた値の比較には、一元配置分散分析または二元配置分散分析および多重比較検定を用いた。 【結果】本研究で用いた乳酸の経口投与は、マウスの体重に影響を及ぼさなかった。また、乳酸の単回投与後に血中乳酸濃度の一過性の増加が認められた。実験1において、足底筋ならびにヒラメ筋の重量は乳酸投与により増加した。実験2では後肢懸垂により足底筋とヒラメ筋の重量は減少した。一方、乳酸投与は後肢懸垂による筋重量の減少を一部抑制した。 【考察】乳酸は筋肥大および筋萎縮予防の作用を有すると考えられた。細胞外乳酸濃度の増加が培養骨格筋細胞を肥大させることが報告されていることから、乳酸経口投与による血中乳酸濃度の増加が、筋重量の増加に関与していると考えられた。 【結論】血中乳酸濃度の増加は筋重量の増加に作用することが示唆された。本研究の一部は、日本学術振興会科学研究費(17K01762、18K10796、18H03160)、公益財団法人明治安田厚生事業団研究助成、日本私立学校振興・共済事業団「学術研究振興資金」、公益財団法人石本記念デサントスポーツ科学振興財団「助成金」、豊橋創造大学大学院健康科学研究科「先端研究」を受けて実施された。 【倫理的配慮,説明と同意】本研究の動物実験は、所属機関における実験動物飼育管理研究施設動物実験実施指針に従い、所属機関の動物実験委員会による審査・承認を経て実施された。
1 0 0 0 OA Graphene transparent antennas
- 著者
- Shinji Koh Shohei Kosuga Ryosuke Suga Shunichiro Nagata Sho Kuromatsu Takeshi Watanabe Osamu Hashimoto
- 出版者
- The Carbon Society of Japan
- 雑誌
- Carbon Reports (ISSN:24365831)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.23-30, 2023-03-01 (Released:2023-03-01)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 3
Transparent antennas have attracted much attention because they can meet the demands of the Internet of Things (IoT) and fifth generation (5G) mobile communication technologies. From this point of view, intensive research and development has been carried out to produce materials with high optical transparency and low electrical resistance. Research on graphene transparent antennas is reviewed along with our experimental demonstration. The unique features of graphene as a material for transparent antennas are introduced and compared to the characteristics of metal-based and metal-oxide transparent conductors. The challenges involved in the fabrication of transparent antennas using graphene films grown by chemical vapor deposition (CVD) are described. Fabrication techniques of transparent antennas (transfer and patterning methods) and techniques to decrease the sheet resistance of the graphene films (stacking and doping methods) are described. The performance of the CVD graphene transparent antennas we have fabricated are presented.
1 0 0 0 OA 火災の電気的性質とその応用
- 著者
- 平野 敏右
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.634, pp.1410-1417, 1971 (Released:2017-06-21)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA モンタージュの観点から小説を読む ─カテブ・ヤシン『ネジュマ』の場合─
- 著者
- 小柏 裕俊
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会関西支部
- 雑誌
- 関西フランス語フランス文学 (ISSN:24331864)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.39-49, 2015-03-31 (Released:2017-11-13)
Nedjma, roman écrit en 1956 par Kateb Yacine, est particulièrement réputé pour sa structure compositionnelle agençant plusieurs lignes d’actions menées et racontées par quatre protagonistes(Mourad, Rachid, Lakhdar et Moustapha). Plusieurs critiques y ont vu le symbole de l’Algérie de l’époque, emportée dans une quête d’identité qui ne débouche que sur le vide. Nous tentons ici de renouveler cette interprétation en appliquant une optique du montage qui privilégie, dans la composition romanesque, les « coupes » qui y sont introduites : à savoir les sauts brusques, non expliqués par les voix narratives, d’une ligne d’action à l’autre. Nous pouvons ainsi établir que la voix de Lakhdar s’approprie le récit raconté à la première personne par Mourad, par l’invasion du « je » de ce dernier. De même, les carnets de Moustapha, insérés à intervalles réguliers dans le roman, prennent le relais d’autres voix narratives pour raconter, malgré cette interruption, la suite du récit narré par les autres. Notre conclusion est qu’à travers les coupes, la voix se densifie à l’excès et se surcharge de récits des autres. Le sens de l’opération nous paraît aller à l’encontre du lieu commun de la vacuité de l’Algérie, et témoigner au contraire de la richesse d’une littérature algérienne francophone apte à faire sienne la langue qui lui a été imposée pour renouveler son fonds culturel propre.
1 0 0 0 OA 企業主導型保育事業における指導監査の課題 : 立入調査の状況分析から
- 著者
- 淡路 佳奈実
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院 教育行政学研究室・学校経営論研究室
- 雑誌
- 公教育システム研究
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.1-24, 2020-11-30
本稿は、企業主導型保育事業における立入調査の状況分析を通して、企業主導型保育事業の指導監査の実態を明らかにし、そのあり方について考察したものである。
1 0 0 0 OA 秋田県産地呼称清酒認証制度と秋田旬吟醸の開発
- 著者
- 斎藤 久一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.11, pp.769-772, 1992-11-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
本年4月に清酒の級別制度が完全に廃止され, 産地間競争, 銘柄間競争が激しくなってきている。秋田県酒造組合では秋田県産酒の差別化と品質の向上を図り, 産地イメージの高揚を推進するため「秋田県産地呼称清酒認証制度」を作り, それに基づいて統一銘柄秋田旬吟醸を開発した。本稿ではその経緯を述べていただいた。
1 0 0 0 OA 顧客志向の反復型プロセス : リーン・スタートアップとアジャイルの組織的仕組み
- 著者
- 平井 直樹 ヒライ ナオキ Naoki Hirai
- 雑誌
- 立教DBAジャーナル = Rikkyo DBA journal
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.45-58, 2020
1 0 0 0 OA 「法律上の婚姻」とは何か(3) : 日仏法の比較研究
- 著者
- 大島 梨沙
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.410-369, 2012-03-30
1 0 0 0 OA 詹糖香の基原植物
- 著者
- 指田 豊
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.203-209, 2020 (Released:2021-01-28)
目的:香の 1 種である詹糖香は「神農本草経集注」(502?536),「新修本草」(659)に初めて登場する.前書は樹の傷口から滲出する含油樹脂,後書はミカン類に似た植物の枝葉の煎じ液である.しかし,清代に至るまで基原植物の考察は行われていない.そこで,詹糖香の基原植物を明らかにする目的で研究を行った. 方法: 主として中国の本草書の調査を行った.詹糖香の基原植物と推定される植物については「新修本草」に基づいて濃縮水エキスを作った.エキスの香りは香司が評価した. 結果:唐の高僧,鑑真和上は海南島で詹糖香の樹を見ている.「唐大和上東夷伝」(779)に書かれた樹の特徴はゲッキツ Murraya paniculata(ミカン科)を思わせる.またその特徴は「新修本草」,「本草綱目」の記載と一致する.このように唐代(日本の平安時代)の詹糖香の基原植物はゲッキツである.清代の「植物名実図考」(1848)は詹糖香の基原植物をカナクギノキ Lindera erythrocarpa(クスノキ科)とした.現代の中国はこの説に従っている.しかしカナクギノキはミカン類とは似ていない.そこでゲッキツ,カナクギノのエキスが香として使えるかどうか実験を行った.「新修本草」に準じてエキスを作った.両エキスとも甘い香りがあり,香りの五味もよく似ていた.これらは香として十分使えるものであった. 結論:唐代の詹糖香の基原植物はゲッキツ,清代のそれはカナクギノキである.両植物から得たエキスの香りはよく似ており,香として使えるものであった.カナクギノキはゲッキツを産しない地域でその代用として使われたものと思われる.
1 0 0 0 OA 歯科用ユニットに潜在するレジオネラ感染のリスク
- 著者
- 伏見 華奈 齋藤 敦子 更谷 和真 土屋 憲 池ヶ谷 佳寿子 加瀬澤 友梨 徳濱 潤一 原田 晴司 柴田 洋 髙森 康次 増田 昌文
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境感染学会
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.136-142, 2018-07-25 (Released:2019-01-25)
- 参考文献数
- 25
本邦には歯科用ユニットの給水に関する水質の基準がなく,レジオネラ属菌による汚染の報告もみられず医療関係者の関心も低い.当院は1997年より院内感染対策の一環として院内給水系のレジオネラ定期環境調査を行っており,2014年から歯科用ユニットの給水を環境調査に追加した.4台の歯科用ユニットのうち1台よりLegionella sp.が60 CFU/100 mL検出され,部位別にみると,うがい水,低速ハンドピース,スリーウェイシリンジから,1,000 CFU/100 mLを超えるLegionella sp.が検出された.対策として,給水の温水器停止と回路内のフラッシング,次亜塩素酸ナトリウム希釈水の通水を行ったが,Legionella sp.は検査検出限界以下にならなかった.歯科用ユニットの構造的理由から,高温殺菌や高濃度消毒薬の使用など更なる対策の追加はできず,やむを得ず歯科用ユニットを交換した.近年,大半のレジオネラ症例は感染源が明らかではない国内単発例と報告されており,これまで認識されていない感染源の存在が示唆される.エアロゾルを発生する装置としての歯科用ユニットの給水システムはレジオネラ感染の極めて高い潜在的リスクと考える.歯科用ユニット製造業者と使用管理者,行政が連携し,歯科用ユニット給水汚染の制御法確立とレジオネラ症予防のための適切な管理基準の策定が望まれる.
1 0 0 0 OA 医療政策の価値規範
- 著者
- 堀 真奈美
- 出版者
- 日本公共政策学会
- 雑誌
- 公共政策研究 (ISSN:21865868)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.32-45, 2013-12-20 (Released:2019-06-08)
- 参考文献数
- 17
医療政策は,政治過程の産物である。他の政策と同等以上に,政治的アクターは多くかつその利害関係は非常に複雑であり,全てのアクターが満足するような医療政策を形成するのは容易ではない。政治情勢における利害調整にふりまわされ,誰のためか何のためか不明瞭なまま政策が局所的に形成されることもある。だが,我々の生命に少なからず影響を与える医療政策が利害調整を中心とした政治情勢によってすべてが決まってよいのであろうか。医療政策として何をすべきであるか(何をすべきでないのか),何を優先問題とすべきかなど,制度全体を貫く価値規範となるべき理念が必要ではないだろうか。以上を問題意識として,本稿では,1)医療政策における価値規範となるべき理念を論じる意義は何か,価値規範となる理念の論拠をどこに求めるか,2)価値規範から想定される医療政策のあり方について検討を行う。
1 0 0 0 OA 「花たちばなの香り」考
- 著者
- 田邊 留美子 Rumiko Tanabe
- 出版者
- 学習院大学文学部国語国文学会
- 雑誌
- 学習院大学国語国文学会誌 (ISSN:02864436)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.21-35, 2015-03-15
1 0 0 0 OA 経絡の研究 (第7報)
- 著者
- 藤田 六朗 岸 勤
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.12-18, 1955-03-31 (Released:2010-10-21)
Examination by means of the skin palpation technique developed by the author's co-worker Tsutomu Kishi yielded the following results. 1. A set of characteristic skin “Keiraku”(meridian) lines exists for each Keiraku. 2. As has been described by Sawada and Shirota, the “Bokokei”(VU) was found to coincide with the first, second, and third lines, and the T M 13 to be located at the seventh cervical vertebra. 3. Subcutaneous indurations belonging to “Yo-keiraku”(positive meridian) are seen as prominences, and those beloning to “In-keiraku”(negative meridian), as depressions, and those belonging to Keiraku of semi-positive, seminegative character included both types. 4. By studies on pulse diagnosis Fujita established the fact that the combination of intraand extra-vascular flow of the body fluids is helical in mode and came to the conclusion that the findings obtained by means of Kishis special technique could probably be analysed as a set of projections of mathematical curves braught about by some changes due to the heical motion of the body fluids. 5. Furthermore the cause of the undulatory change of the Keiraku is presumed to lie in the vibration of automatic movements of the twelve organs, among which the heart is of course the most important. Therefore the author considers that explanation of the undulatory character of Keiraku phenomena can be obtained by simultaneouly taking out the electric action current of each organ and measuring of its intensity in each of the Keiraku (1955, 19/II).