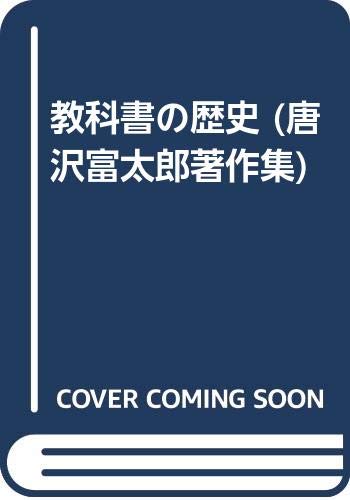1 0 0 0 教科書の歴史 : 教科書と日本人の形成
1 0 0 0 OA 明治初期、筑摩県の教育行政 : 教育県としての長野県の系譜
- 著者
- 木村 晴壽
- 出版者
- 学校法人松商学園松本大学
- 雑誌
- 教育総合研究 = Research and Studies in Education (ISSN:24336114)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-28, 2018-11-30
本論は、明治初期に開始された地方制度改革の過程で信州に設置された筑摩県を素材に、その教育行政のあり方を仔細に検討した。筑摩県は地方行政区として4年余り存続しただけの県ではあったが、その教育行政は独特であり、短期間に着々と小学校の設立が進んだだけでなく、学制施行直後の当時としては驚異的な高就学率をも達成した。これらの実績を評価した文部省は、官民ともに県全体が学制の主旨に沿った教育の充実を実現しているとして、筑摩県を賞賛した。迅速な学校設置や高就学率を実現するため筑摩県では、後に県の一部となる伊那県の時代から県の長官を務める人物が先頭に立って教育行政を牽引し、精勤賞や不就学補助金等の実効性ある施策を実施していた。さらには、長官である権令自ら県内の小学校を巡回して就学を督励するなど、むしろ特異ともいえる姿勢で教育行政と取り組んでいた。その最中、地方統治の完成を目指す政府が断行した府県統合策によって筑摩県は、発足から4年余りで旧長野県と統合された。筑摩県が消滅した後、統合長野県の教育行政からは、徐々に筑摩県色が失われていったが、就学率を含めた教育水準は、それなりに維持された。
1 0 0 0 OA 移動軌跡に着目した都市空間の歩行速度分析
- 著者
- 渡辺 美穂 羽藤 英二
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.42.3, pp.535-540, 2007-10-25 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
仕事に向かう人,お気に入りのCDショップに向かう人,恋人と手をつないで歩く人. 遅刻しそうな時,初めての場所を訪れた時,疲れている時.歩く速さはそれぞれ異なるはずだ.街には様々な人が織り成す様々な速度が溢れている.そしてそれらの速度が集まることでその場所の速度―空間速度―が生まれる.従来の都市においては空間速度の違いを考慮した空間設計はあまり為されてこなかった.また,近年の複雑・高速化し続ける交通体系において,基本交通手段である歩行の挙動解明の重要さが見直されている.そこで本研究では,GPS搭載の携帯電話を用いたプローブパーソン技術により歩行者の行動文脈の流れに沿ってデータを蓄積する,従来の歩行者研究とは異なる手法を用いて, 個人間・個人内の歩行速度を分析し,空間速度を明らかにすることにより,空間速度を考慮した空間デザインの一手法を提案する.
- 著者
- Michiko Izumi Akiyuki Uzawa Reiji Aoki Masahide Suzuki Koki Yoshizawa Yutaro Suzuki Akio Kimura Takayoshi Shimohata Satoshi Kuwabara
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.465-468, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 8
Recent studies have reported that autoantibodies against glial fibrillary acidic protein (GFAP), a major cytoskeletal protein expressed in astrocytes, can lead to GFAP astrocytopathy, an autoimmune central nervous system inflammatory disease. We herein report the unique case of a 59-year-old Japanese woman with GFAP astrocytopathy who presented with characteristic symptoms, including signs of meningeal irritation, cerebellar ataxia, and bladder/rectal dysfunction, in the absence of specific findings on initial brain magnetic resonance imaging (MRI). The patient exhibited new abnormal changes mainly in the brainstem on follow-up MRI, illustrating the need to recognize that MRI abnormalities may appear later in GFAP astrocytopathy.
1 0 0 0 OA 下限数量以下の非密封放射性同位元素の管理区域外使用の安全管理 運用の基本的考え方について
- 著者
- 松田 尚樹 吉田 正博 高尾 秀明 奥村 寛
- 出版者
- 日本放射線安全管理学会
- 雑誌
- 日本放射線安全管理学会誌 (ISSN:13471503)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.25-31, 2006 (Released:2011-03-17)
- 参考文献数
- 15
Recent amendments to the Law concerning Prevention of Radiation Hazards due to Radioisotopes, etc. and related regulations might afford the use of unsealed radioisotopes below the exemption limits outside controlled areas. This drastic change brought a great convenience to radiation workers, however, the practical management should take safety of both non-radiation workers and environments into consideration. Analysis of research activities using unsealed radioisotopes and a survey for radiation workers in Nagasaki University revealed that a number of biochemical experiments could be performed using radioisotopes below the exemption limits and that a half of respondents desired to use them in their own laboratories. Radiation safety management of those areas was also favored by most of responders, which would increase tasks of radiation safety staffs. Therefore, the rational and affordable safety management practice is required. On the basis of these results together with radiation safety managements in the U. S., Canada and the U. K., practical considerations for the use of radioisotopes outside controlled areas in Japan are discussed.
- 著者
- 松本 直也 伊藤 めぐみ 山田 一孝 豊留 孝仁
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.101-107, 2020-09-30 (Released:2020-11-30)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 4
飼育下の鳥類においてアスペルギルス症は重要な疾患であるが,その予防策や診断方法,治療法は確立されていない。アスペルギルス症の主な起因菌であるAspergillus fumigatusは自然環境中に普遍的に存在するため,ときとして飼育鳥類に感染し,死に至らしめる。登別マリンパークニクス飼育下のキングペンギン(Aptenodytes patagonicus),ジェンツーペンギン(Pygoscelis papua),ケープペンギン(Spheniscus demersus)のA. fumigatus感染を防ぐことを目的とし,本研究では飼育環境中に存在するA. fumigatus汚染源の調査を行った。エアーサンプリングおよび土壌サンプリングのデータから主な汚染源が土壌であると推定されたため,土壌とペンギンの接触を最小限とする対策を行った。その結果,アスペルギルス症の発症は認められなくなった。本研究から,A. fumigatusの感染予防において,予め飼育環境下の汚染源を推定することは有効であり,屋内での対策とともに屋外の環境への対策も重要であることが確認された。
1 0 0 0 OA チョウ成虫の季節適応と関連した毛状鱗粉形成機構の解析
チョウ成虫の翅や脚に存在する毛状鱗粉が季節的な可塑性を示すかどうかを検討するため、毛状鱗粉に及ぼす幼虫および蛹期の日長と温度の影響を調べた。短日成虫の翅あるいは脚の毛状鱗粉の本数は、長日成虫のものより非常に多かった。一方、低温条件下に曝された成虫の毛状鱗粉の平均長は、高温条件下のものより長かった。翅や脚の毛状鱗粉形成に関与するホルモン(おそらく夏型ホルモン:SMPH)が蛹の脳内に存在するかを検討するため、3種のチョウの短日蛹に投与した。いずれの種においても翅や脚の毛状鱗粉数の減少が認められた。これら結果は、夏型ホルモンが毛状鱗粉形成に関与することを示唆するものである。
1 0 0 0 OA 日本人の動物に対する態度の類型化について
- 著者
- 石田 敢 亀山 章 高柳 敦 若生 謙二
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.19-24, 1991-03-31 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 2 2
日本人の動物観をとらえるために, 動物に対する態度の類型化を行った。 動物に対する態度は, 動物に関する職業や運動についている専門家が最も極端なものをもっていると考えられることから, 専門家に対するヒアリング調査とアンケート調査を実施することによって, 日本人の動物観の極限としての輪郭の把握を試みた。この調査はS. ケラートがアメリカ人に対して行った調査と同様の方法で行ったが, 審美的態度については日本人とアメリカ人とでは内容が異なることが明らかにされた。 また, 日本の専門家は自然主義的態度と生態学的態度を強くもっている者が多いことが明らかにされた。
- 著者
- ジャン クレマン マルタン 山岸 拓郎[訳]
- 出版者
- 専修大学大学院社会知性開発研究センター/歴史学研究センター
- 雑誌
- 専修大学大学院社会知性開発研究センター・歴史学研究センター年報 : フランス革命と日本・アジアの近代化
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.94-111, 2006-03
文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業オープン・リサーチ・センター整備事業
1 0 0 0 OA 集中治療室の専任薬剤師による注射処方発行前鑑査が薬物治療の適正化に及ぼす効果
- 著者
- 上林 里絵 池村 健治 若井 恵里 杉本 浩子 平井 利典 加藤 秀雄 向原 里佳 石倉 健 今井 寛 岩本 卓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.1-9, 2023-02-28 (Released:2023-02-28)
- 参考文献数
- 20
集中治療室(intensive care unit,以下,ICU)入室患者の薬物治療は複雑であることが多く,処方の適正化には薬剤師の積極的な参画が求められる。三重大学医学部附属病院では,2019年2月よりICU専任薬剤師による翌日投与予定の注射処方発行前に処方鑑査を行う運用(注射処方発行前鑑査)を開始し,医師の指示や患者の病態に応じた薬物治療の適正化に介入してきた。本研究では,運用前後6カ月間における介入件数やその内容,注射薬の返品率に及ぼす注射処方発行前鑑査の影響について調査した。薬剤部にて注射薬の調剤・払い出しを行う薬剤師の全介入件数は,運用後に有意に減少し(p=0.030),ICU専任薬剤師の全介入件数は有意に増加した(p=0.002)。注射室と比較しICU専任薬剤師の注射オーダー反映率は運用後で有意に上昇し(p<0.001),未使用注射薬の返品率も有意に低下した(p<0.001)。以上より,ICU専任薬剤師による注射処方発行前鑑査の運用は,効率的な薬物治療の適正化に貢献したと考えられた。
1 0 0 0 OA モルヌピラビル(ラゲブリオ®)投与終了後のリバウンドが認められたCOVID-19の2例
- 著者
- 金澤 将史 竹本 正明 中野 貴明 若山 功 田井 誠悟 杉村 真美子 大野 孝則 朝比奈 謙吾 井上 幸久 伊藤 敏孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.51-54, 2023-02-28 (Released:2023-02-28)
- 参考文献数
- 5
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の第7波では,高齢者施設で多くのクラスターが発生した。高齢のCOVID-19患者に対してその使いやすさもあってモルヌピラビル(ラゲブリオ®)が投与された。今回われわれは,COVID-19罹患後にモルヌピラビルを投与され症状が改善して療養解除となった後に,呼吸困難を発症し入院した症例を2例経験した。同じ抗ウイルス薬に分類されるニルマトレルビル/リトナビル(パキロビッド®)使用例では,COVID-19から回復して2〜8日後の症状再燃または検査での陰転化後の再陽性で定義されるリバウンドの報告があり,モルヌピラビルでもリバウンドが認められた。リバウンドは療養解除後の時期に起こり得るが,その際の救急診療における感染対策や隔離解除などの対応に注意が必要である。今後の対応のため疫学調査ならびに病態解明の必要性が示唆された。
- 著者
- 小沢 直 本杉 省三
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.558, pp.121-128, 2002-08-30 (Released:2017-02-04)
- 被引用文献数
- 1
This paper investigates the singularity of the amount of work and a work schedule of a drama performance in a temporary theater. making the stage and audience seating including technical fascilities in itrequires a big amount of work and long production schedule. It brings also positive activity for all member of drama company.
1 0 0 0 OA 『フランケンシュタイン』の書簡性
- 著者
- 平倉 菜摘子
- 出版者
- イギリス・ロマン派学会
- 雑誌
- イギリス・ロマン派研究 (ISSN:13419676)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.17-29, 2019-03-30 (Released:2020-05-08)
- 参考文献数
- 23
The multilayered narrative of Frankenstein; or, The Modern Prometheus has fascinated both critics and general readers ever since the novel’s first publication in 1818. Their main interests, however, have tended to lie in the narratives of its protagonist, Victor Frankenstein, and his hideous creature, thus overlooking the significance of the outermost layer in the novel: the letters from Robert Walton to his sister, Margaret Saville. According to the British Critic’s 1818 review of Frankenstein, this “sort of introduction, which precedes the main story of the novel” has “nothing else to do with it.” In the present age, Frankenstein is often regarded as the prime example of a fictional work which “shifts from epistolary immediacy to monologic narrative, from eighteenth-century novels of letters to nineteenth-century first person narratives” (Britton 2009). These remarks seem to suggest that the epistolary form was no longer valued in the early nineteenth century. It should be pointed out, however, that Mary Shelley was deeply read in epistolary novels, especially the ones written by her own parents. This essay maintains that Shelley was keenly aware of the fact that she was born into a family of literary geniuses, and that her choice of an epistolary format for her very first work shows her desire to invigorate this slightly outdated mode. It attempts to shed light on her masterly performance of epistolarity, first by closely examining the way in which she created “Letters from the Arctic” à la Letters from Sweden (1796) by her mother, Mary Wollstonecraft. I then try to give a possible answer to the question of why these fictional letters are addressed to “a dear sister in England,” whose own voice is totally silenced. By considering the creation of Margaret Saville, I hope to shed light on the imaginative dialogue between Shelley and her own half-sister, Fanny Wollstonecraft. Lastly, I analyse the “mock epistolarity” (O’Dea 2004) in Frankenstein, hoping to clarify the innovativeness of Shelley’s narrative. I conclude with a brief examination of the voices of women skillfully embedded in this seemingly “unfeminine” epistolary novel.
1 0 0 0 OA 知の限界を問う欲望-ミシェル・フーコーによるジョルジュ・バタイユ読解-
- 著者
- 市川 崇
- 出版者
- 法政大学言語・文化センター
- 雑誌
- 言語と文化 = 言語と文化 (ISSN:13494686)
- 巻号頁・発行日
- vol.10 別冊, pp.179-194, 2013-02
1 0 0 0 時報
- 著者
- 齋藤報恩會
- 出版者
- 齋藤報恩會學術研究總務部
- 巻号頁・発行日
- 1926
1 0 0 0 OA 情報システム部の新しい役割-CEOの情報参謀
- 著者
- 松平 和也
- 出版者
- 一般社団法人 情報システム学会
- 雑誌
- 情報システム学会 全国大会論文集 第2回全国大会・研究発表大会論文集 (ISSN:24339318)
- 巻号頁・発行日
- pp.7-04, 2006 (Released:2021-01-04)
今情報システム部門は役割を見失っている。発足以来電算課から情報システム部門へとすくすく育ったが経営環境の急変に付いて行けずに旧来の機能を墨守しているに過ぎない。戦略情報システム子会社ともてはやされて分社したら、数年を経ず電算メーカに売却されてしまったなどという例もある。コストカット対象部門になって久しい。 情報の語源は敵情報知からきたという。この語源が示唆することは、この部門の本質的機能は経営者に敵、即ち競争相手および潜在的競合の情報を報告知らせることではなかったか。軍組織ではこの役割は情報参謀と言っていた。CIOはこの参謀達の主任である。本論文ではダブルキャストのCIO制と配下の参謀組織を文字通りSTAFFとして再編成して持つ新しい役割機能を提案するものである。
1 0 0 0 OA CIE図書館の女性図書館員たち
- 著者
- 大島 真理
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.224-235, 2004-11-01 (Released:2017-05-24)
戦後日本の占領軍支配下において作られたCIE図書館に,多くのアメリカ人女性図書館長を見出すことができる。CIE図書館の利用者の書いた資料から,実際的なCIE図書館の姿を分析すると同時に彼女らの業績を調査した。さらに来日の背景の分析,日本の図書館界に及ぼした影響などについて考察する。
- 著者
- American Society for Testing Materials
- 出版者
- American Society for Testing Materials
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA ハワイ州の司法制度について
- 著者
- 伊藤 博文
- 出版者
- 愛知大学法学会
- 雑誌
- 愛知大学法学部法経論集 = THE JOURNAL OF THE FACULTY OF LAW (ISSN:09165673)
- 巻号頁・発行日
- no.201, pp.159-188, 2014-12-12
1 0 0 0 博物館時報
- 著者
- 齋藤報恩會 [編]
- 出版者
- 齋藤報恩會學術研究總務部
- 巻号頁・発行日
- 1931