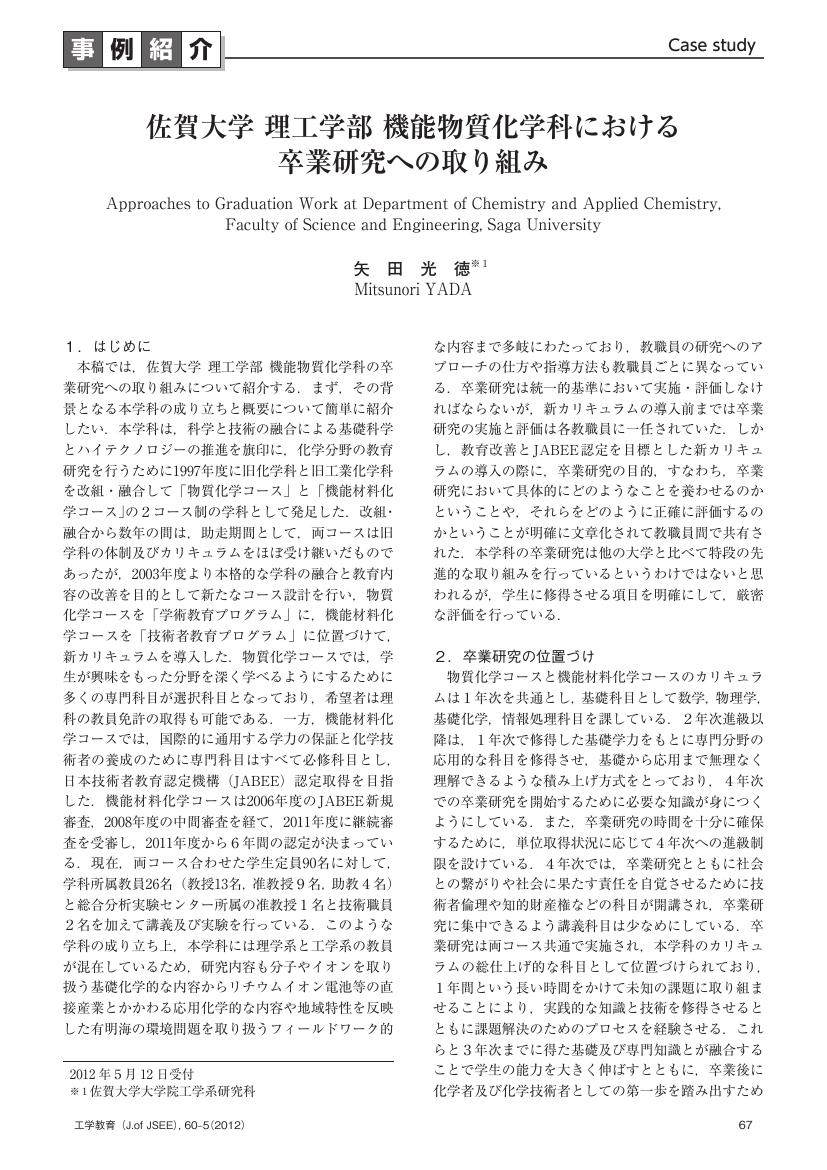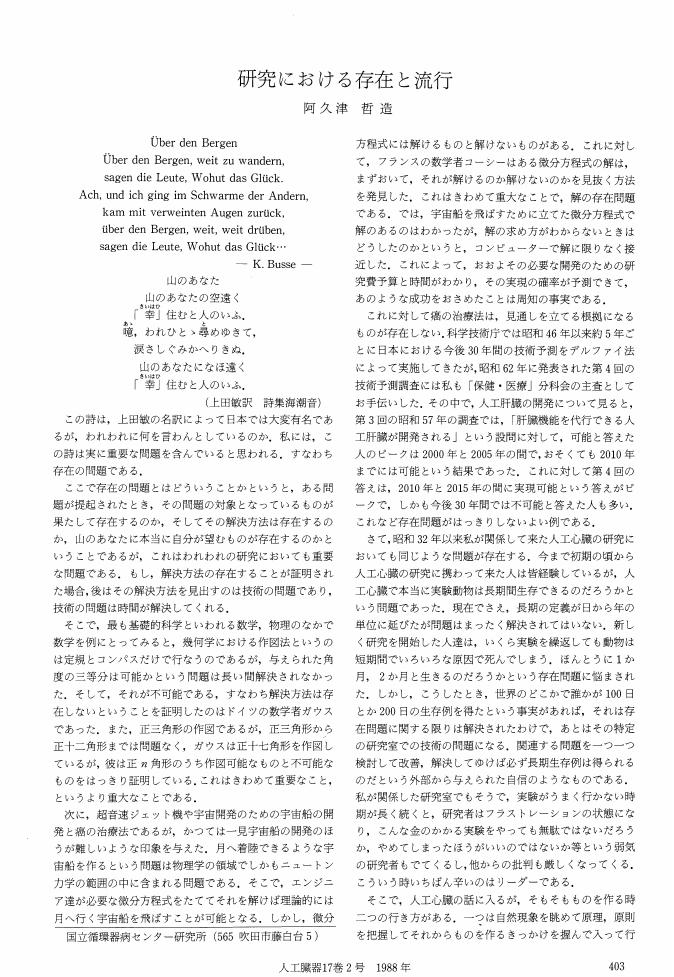1 0 0 0 車両と電気
- 著者
- 車両電気協会 [編]
- 出版者
- 車両電気協会
- 巻号頁・発行日
- vol.22(1), no.250, 1971-01
1 0 0 0 リモート対話場面におけるロボットを活用した批判的思考課題の効果
1 0 0 0 OA 私の文化財保護法研究の歩み
- 著者
- 椎名 愼太郎 シイナ シンタロウ Shintaro Shiina
- 雑誌
- 山梨学院ロー・ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-35, 2010-07-30
- 著者
- Masumi ONO Hiroyuki YAMANISHI Yuko HIJIKATA
- 出版者
- Japan Language Testing Association
- 雑誌
- 日本言語テスト学会誌 (ISSN:21895341)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.65-88, 2019 (Released:2020-02-07)
- 被引用文献数
- 1 1
Integrated writing tasks are becoming popular in the field of language testing, but it remains unclear how teachers assess integrated writing tasks holistically and/or analytically and which is more effective. This exploratory study aims to investigate teacher-raters’ holistic and analytic ratings for reliability and validity and to reveal their perceptions of grading the integrated writing task on the Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL iBT). Thirty-six university students completed a reading-listening-writing task. Seven raters scored the 36 compositions using both a holistic and an analytic scale, and completed a questionnaire about their perceptions of the scales. Results indicated that the holistic and analytic scales exhibited high inter-rater reliability and there were high correlations between the two rating methods. In analytic scoring, which contained four dimensions, namely, content, organization, language use, and verbatim source use, the dimensions of content and organization were highly correlated to the overall analytic score (i.e., the mean score of the four dimensions). However, the dimension of verbatim source use was found to be peculiar in terms of construct validity for the analytic scale. The analyses also indicated various challenges the raters faced while scoring. Their perceptions varied particularly regarding verbatim source use: Some raters tended to emphasize the intricate process of textual borrowing while others stressed the difficulty in judging multiple types and degrees of textual borrowing. Pedagogical implications for the selection and use of rubrics as well as the teaching and assessment of source text use are suggested.
1 0 0 0 OA 中島徳一郎先生(1910-96)
- 著者
- 北川 尚史
- 出版者
- 日本蘚苔類学会
- 雑誌
- 蘚苔類研究 (ISSN:13430254)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.27-28, 1997 (Released:2018-07-03)
1 0 0 0 OA 中川素子先生のご退職にあたって
- 著者
- 久保村 里正
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文教大学教育学部紀要 = Annual Report of the Faculty of Education Bunkyo University (ISSN:03882144)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.9, 2013-03-01
1 0 0 0 OA 中川素子教授 略歴・主要業績
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 文教大学教育学部紀要 = Annual Report of the Faculty of Education Bunkyo University (ISSN:03882144)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.10-11, 2013-03-01
- 著者
- 楠奥 繁則
- 出版者
- 立命館大学経営学会
- 雑誌
- 立命館経営学 = 立命館経営学 (ISSN:04852206)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.5, pp.169-185, 2006-01
本研究では、北海道の水系に定着したブラウントラウトの生活史と回遊性、また本種の食性と近縁サケ科魚類との種間競争の実態を解明し、本種による在来淡水魚類への影響を評価する目的で、北海道南部の戸切地川、および中央部の支笏湖水系において生態的・集団遺伝学的調査を行い、以下の成果を得た。1.戸切地川において、ブラウントラウトは河口から約7km上流地点に位置する上磯ダム湖で主に生育し、雌では2歳で尾叉長275mm以上に、雄では2歳で172mm以上に達すると性成熟し繁殖に加わることが示された。2.本種の一部の個体は、秋季に尾叉長210-270mmの成長すると、スモルト化し、翌春に川を下って降海型(シートラウト)になること、また降海型は沿岸域で成長・成熟した後、繁殖のために河川に遡上することが確認された。3.本種は尾叉長200-300mmの個体ではトビケラ目幼生、陸生落下動物の他にフクドジョウなどの底生魚類を主に捕食することが示された。4.本種とニジマスが定着している支笏湖水系において、流入河川の美笛川ではブラウントラウトは主に底生型動物、ニジマスは遊泳型動物を摂餌し、2種は餌資源を分割利用していることが示された。一方、支笏湖内では、ブラウントラウトは陸生落下動物が少ない時期に、イトヨ、アメマス、ヒメマスなどの魚類を捕食することが明らかになった。5.餌ニッチの幅では、ブラウントラウトはニジマスより低い傾向を示した。6.ブラウントラウトによる特定魚種への捕食圧が大きくはなかったため、在来魚類の遺伝的集団構造に変化は認められなかった。
1 0 0 0 OA 佐賀大学 理工学部 機能物質化学科における卒業研究への取り組み
- 著者
- 矢田 光徳
- 出版者
- Japanese Society for Engineering Education
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.5_67-5_70, 2012 (Released:2012-09-29)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 研究における存在と流行
- 著者
- 阿久津 哲造
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.403-406, 1988-04-15 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 図書館だよりNo.196
- 著者
- 近畿大学中央図書館
- 雑誌
- 図書館だより = Toshokan Dayori
- 巻号頁・発行日
- no.196, pp.1-2, 2022-09-01
1 0 0 0 OA eクチコミと消費者行動 情報取得・製品評価プロセスにおけるeクチコミの多様な影響
- 著者
- 杉谷 陽子
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- pp.202203.002, (Released:2022-03-07)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA インターネットにおけるリテラシー概念の展開
- 著者
- 岸谷 和広
- 出版者
- 關西大學商學會
- 雑誌
- 關西大學商學論集 (ISSN:04513401)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.69-85, 2011-12-25
本稿では,リテラシー概念をインターネット媒体へ適用することを目的とする。近年,インターネット利用に関する研究が進展すると同時に,インターネット利用自体もユーザーの経験が積み重なるにつれて利用の仕方に多様性を孕むようになった。その結果,当初考えられていた利用像とは異なりつつある。それゆえ,当初想定されていた利用像に従って今までの研究が進められているために,インターネット利用が日常化する現在において利用のあり方それ自体をあらためて検討する必要があると言えよう。同時に,スマートフォン等の新たな端末の登場は,パソコンや携帯電話など端末の相違を解消させるため,端末それ自体に依存しない,もしくは横断する理論的な概念,そしてその展開が必要とされていると言えよう。まず始めに,メディア利用研究を理解することで,ネット・リテラシー概念の必要性を確認する。その次に,リテラシー概念を理解することで,ネット・リテラシー概念への応用を検討し,ネット・コミュニケーション・リテラシー,ネット・操作リテラシー,ネット情報に対する懐疑的な態度の3つの必要性を論じる。その後,実証研究に向けて展望を論じることにする。
- 著者
- 山岸 順一 Cooper Erica
- 出版者
- 国立情報学研究所
- 雑誌
- 挑戦的研究(萌芽)
- 巻号頁・発行日
- 2021-07-09
我々は伝統話芸である落語の実演データから深層学習モデルを学習、あたかもプロの噺家の様に、噺を読み上げる落語音声合成システムを最先端音声合成技術に基づき構築した。従来の音声対話システムとは目的が全く異なり、聞き手を楽しませるAI噺家の実現を目標としている。本課題では 、長期的音響情報および非言語情報の明示的モデル化により合成音声の表現力を向上させ、 ニューラル言語モデルによる噺の自動生成に取り組む。
1 0 0 0 OA 4.転倒や出血を考慮した抗血栓薬管理
- 著者
- 杉森 宏 森 興太 矢坂 正弘 岡田 靖
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.305-311, 2022-07-25 (Released:2022-09-07)
- 参考文献数
- 14
高齢者では転倒・転落による死亡者数は不慮の事故の中で最も多い.抗血栓療法は循環器疾患をそしてそれに伴う転倒も予防するが,同時に出血を宿命的に合併する.転倒は患者側の原因と環境原因が重なって起こることを認識してリスクを評価し,転倒リスクに関連する薬剤の処方などを抑制する.また適応があるなら新規経口抗凝固薬などより安全な薬剤を処方し,極端に虚弱な患者には抗血栓療法を控えることも考慮するなど総合的な対応が重要である.
- 著者
- 尾崎 章彦
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.177-182, 2022-04-25 (Released:2022-09-07)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 税理士業の事業承継に伴い受領する対価の所得区分
- 著者
- 鎌倉 友一
- 出版者
- 愛知大学経営学会
- 雑誌
- 愛知経営論集 = THE AICHI JOURNAL OF BUSINESS (ISSN:0916569X)
- 巻号頁・発行日
- no.178, pp.13-49, 2020-02-14
1 0 0 0 OA 経済的相互依存と安全保障戦略 : 国際政治経済学(IPE)の分析概念と冷戦期の東西貿易
- 著者
- 永澤 雄治
- 出版者
- 東北文化学園大学
- 雑誌
- 総合政策論集 : 東北文化学園大学総合政策学部紀要 = Policy management studies (ISSN:13468561)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.71-90, 2002-03-30
The purpose of this article is to analyze several concepts concerning economic interdependence and the security of nations in the IPE (International Political Economy), and to apply the concepts to the case of economic sanctions used by the United States and the EC toward the Soviet Union during the "new cold war". It deals with unsolved arguments between liberalism and realism in the IPE. Liberals argue that economic interdependence lowers the likelihood of war by increasing the value of trading over the alternative of aggression : interdependent states would rather trade than invade. Realists dismiss the liberal argument, arguing that high interdependence increases rather than decreases the probability of war. In anarchy, states must constantly worry about their security. Accordingly, interdependence gives states an incentive to initiate war, if only to ensure continued access to necessary materials and goods. This paper argues that the realist's assertion is based on old notions influenced by mercantilism and imperialism. This article, then, deals with East-West trade during the "new cold war" and asserts that the EC has employed "positive economic linkage", involving the use of positive economic means in the pursuit of political goals.
1 0 0 0 OA 新しい犬猫用注射麻酔薬「アルファキサロン」
- 著者
- 山下 和人
- 出版者
- MPアグロ 株式会社
- 雑誌
- MPアグロジャーナル (ISSN:21852499)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.4-7, 2014-04