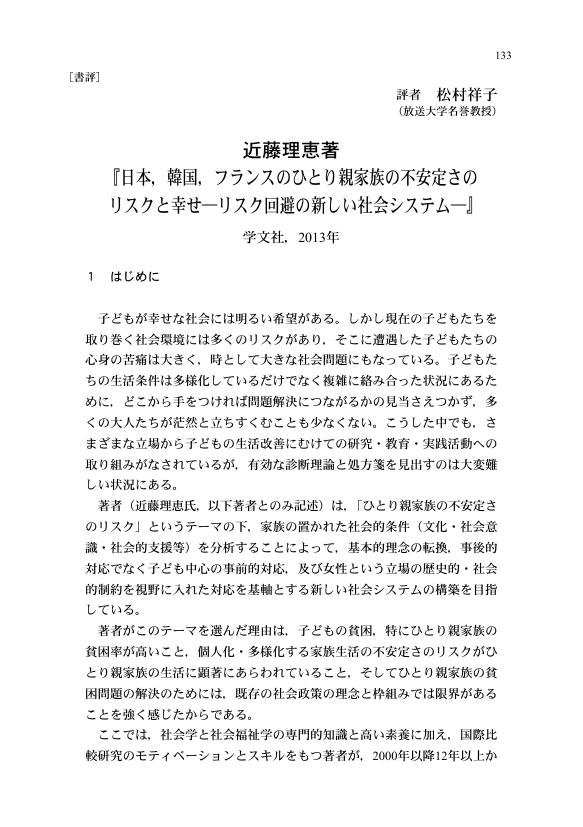1 0 0 0 OA 大規模空間における案内地図のデザインとわかりやすさに関する研究
- 著者
- 池田 千登勢
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.259-269, 2017 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 2
The purpose of this study is to find effective design elements to make maps easy to use for people with poor directional ability. We conducted comparative experiments using 12 types of existing maps. 58 subjects tried to find their ways using several maps in large spaces such as shopping malls and stations with rather complex structures. After observing their behaviors, we conducted interviews to clarify supportive design elements of maps to find ways. As a result, we found some effective design elements such as vivid color tones, the right angle of bird's-eye-view, the right degree of deformation of illustrations, readable design from upside down position when maps are rotated, for example. We also found two important requirements of map design; (1) landmarks on maps should be easily collated with real landmarks, (2) relations between different stories of the building should be clearly described.
1 0 0 0 OA 第二次世界大戦前の日系二世と 「アメリカニズム」
- 著者
- 米山 裕
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.20, pp.99-113, 1986-03-25 (Released:2010-10-28)
- 参考文献数
- 78
1 0 0 0 OA 判例データベースに見る近年の犯罪に該当する子ども虐待行為について
- 著者
- 清水 裕樹
- 出版者
- 名古屋経済大学法学会
- 雑誌
- 名経法学 = Meikei Law Review (ISSN:24337706)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.45-68, 2020-03-31
1 0 0 0 OA Parkinson病の自律神経障害:特に発汗系について
- 著者
- 山元 敏正
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.15-19, 2020 (Released:2020-04-02)
- 参考文献数
- 16
Parkinson病(PD)の発汗障害について解説する.1. 起立性低血圧を伴うPD患者の定量的軸索反射性発汗試験と心電図R-R間隔変動のスペクトル解析,MIBG心筋シンチグラフィとの比較検討では,PDの自律神経障害は,心臓交感神経や心血管系に比べ発汗系が最も軽微である.2. PDのオフ時はオン時に比較し発汗量が多かったとする報告がある.3. PD3例の発汗発作にゾニサミド25~50 mg/日が有効である可能性がある.4. レビー小体型認知症の中には,寒冷による多汗を呈する一群がある.PDでは発汗神経の障害は軽度で,発汗異常は視床下部を中心とする体温調節障害により生じている可能性がある.
1 0 0 0 OA 主体形成への歴史的省察 : 丸山眞男における道徳、権力、主体
- 著者
- 小川 史
- 出版者
- 上田女子短期大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:09114238)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.51-62, 2012-01-31
丸山眞男が1946年に発表した論文「超国家主義の論理と心理」では、道徳と権力との関係が問題となっていた。そこで想定されている主体像は、戦後日本の教育が避けて通れない重要な問いを含んでいる。本稿では同論文を検討し、丸山が道徳的に自由な主体のあり方を問うていたことをみる。
1 0 0 0 OA ブレゲーBr. 940“アンテグラル”STOL輸送機
- 著者
- 木村 秀政
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.58, pp.333-334, 1958-11-28 (Released:2009-07-09)
1 0 0 0 OA 精神障害を伴う高齢者食道義歯異物の2例
- 著者
- 大野 覚 三浦 誠 市丸 和之
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.11, pp.983-986, 2004-11-01 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 4
Two cases of denture foreign body in the esophagus were reported.A 74-year-old male with dementia due to Alzheimer's disease suddenly complained of dysphagia. A chest X-ray displayed a denture lodged in the esophagus, but the denture was not noticed at that time. Because he subsequently suffered from secondary aspiration pneumonia, he underwent tracheostomy and percutaneous endoscopic gastrostomy. After 3 years, by chance, the denture foreign body was detected by gastro-intestinal fiberscopy. His family did not consent to the removal of the foreign body.A 65-year-old male with mental retardation suddenly complained of dysphagia. A chest X-ray revealed a denture lodged in the esophagus the next day. The denture was removed under esophagoscopy with a Verda dilation laryngoscope without any complications.When the aged suddenly complain of dysphagia, presence of a foreign body in the esophagus should be ruled out, even if they are not aware of misswallowing foreign bodies.
- 著者
- Mizuki Watanabe Honoka Takahashi Kazuyoshi Uematsu Mineo Sato Takaki Masaki Dae-Ho Yoon Kenji Toda
- 出版者
- The Ceramic Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Ceramic Society of Japan (ISSN:18820743)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.7, pp.458-463, 2022-07-01 (Released:2022-07-01)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 2
All-inorganic halides exhibit excellent optical as well as luminescence properties. Among them, non-toxic copper-doped halide Cs2ZnCl4 with high stability is a promising material. However, the conventional method for preparing these materials, using the hot injection technique, is unsuitable for mass production. Therefore, herein, we suggest a simple and low-temperature (below 100 °C) method without using special equipment, regents, and treatments. Cu-doped Cs2ZnCl4 was successfully synthesized using the water-assisted solid-state reaction (WASSR) method, and the oxidation state of Cu in the samples was estimated through the iodometric titration technique. The optical and luminescence properties were investigated using the absorption and photoluminescence excitation/emission spectra. Significantly, Cu-doped Cs2ZnCl4 exhibited unique green emission centered at ∼520 nm under ultraviolet irradiation. Moreover, the oxidation of Cu in the Cs2ZnCl4 lattice was suppressed owing to the low-temperature conditions in the WASSR.
1 0 0 0 OA 不随意運動に対するDBSと凝固術
- 著者
- 山田 和慶
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.448-453, 2022 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 22
近年, 運動異常症に対する治療法は, 脳深部刺激療法 (deep brain stimulation : DBS) と凝固術がともに進歩・発展している. 2020年末に本邦においてadaptive DBS (aDBS) が臨床応用されるようになった. aDBSは, 電極周囲のフィールド電位をリアルタイムにフィードバックし, 刺激強度を変化させる画期的な治療技術である. 一方, 凝固術の新技術として集束超音波治療 (focused ultrasound : FUS) が登場したが, 従来の高周波凝固術も再評価されつつある. 特にこれまで避けるべきとされてきた両側凝固術についても一定の評価がなされつつある. 不随意運動・パーキンソン病に対するDBSと凝固術について, 新技術・新知見の理解を踏まえて, 今後の課題について検討する.
1 0 0 0 OA 聖帝と煤煙 大阪における歴史意識の転換についての覚書
- 著者
- 井上 智勝
- 出版者
- 大阪歴史博物館
- 雑誌
- 大阪歴史博物館研究紀要 (ISSN:13478443)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.0027-0034, 2007 (Released:2022-07-30)
1 0 0 0 OA オーステナイト系ステンレス鋼の磁気特性による微少領域の非破壊硬度評価
- 著者
- 青木 孝史郎 福澤 将宣
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集 2010年度精密工学会春季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.427-428, 2010 (Released:2010-09-01)
本研究はオーステナイト系ステンレス鋼の塑性加工に伴う加工硬化度を非破壊で測定する事を目的としている.これまでの調査結果から,交流磁場により試験片全体を測定する方法では誤差が大きい事が判明している.そこで高精度化を目的に測定点を縮小した上で歪,硬度,磁気特性の相関を調査することを試みた.
1 0 0 0 OA 培土処理がダイズの生育と根粒による窒素固定に及ぼす影響
- 著者
- 土田 宰 有馬 泰紘
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.20-26, 1993-02-05 (Released:2017-06-28)
- 被引用文献数
- 4
異なる培土処理をしたダイズ植物の生育および根粒形成と窒素固定についてポット試験を行い,植物の生育ステージにそって検討した.標準的な培土方法(高さ10cm)により,植物の生育と窒素集積量は,発芽後98日目でそれぞれ46%および40%の増加を示した.培土をすると多くの根粒が不定根上に形成され,定根と不定根に着生する根粒は重量も個数も増加した.固体当たりの最大の根粒活性(アセチレン還元能)は無培土の植物よりも高くなり,生育にともなう根粒活性の低下の時期も遅れた.培土部分にダイズ根粒菌を接種する方法は,標準培土処理の植物と比較して固体当たりの根粒の重量と個数を増加させた.しかし,定根と不定根に着生する根粒のサイズや重量の平均値は低く,根粒と根の間および根粒間での光合成産物の強い競合があったことを示唆していた.高く(15cm)培土をする方法は地上部と不定根,不定根根粒の生育を促進した.定根の生育およびそこに着生する根粒の量と活性は抑制されていたが,それらは不定根とそこに着生する根粒によって補われ,高く培土された植物の総窒素集積量と根粒活性は,標準培土を行った植物よりも著しく高くなった.
- 著者
- 日本集中治療医学会小児集中治療委員会日本小児集中治療連絡協議会COVID-19ワーキンググループ 日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.247-253, 2022-05-01 (Released:2022-05-01)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 OA 植物のR遺伝子によるウイルス抵抗性
- 著者
- 宮下 脩平 高橋 英樹
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.199-208, 2015-12-25 (Released:2016-10-19)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 3
植物は獲得免疫をもたない.その代替として,多数のNB-LRR型免疫レセプターによりそれぞれの病原体を特異的に認識し,抵抗性反応を誘導する機構を持っている.NB-LRR型免疫レセプターをコードする遺伝子は,これまでに植物で報告された優性抵抗性遺伝子(R遺伝子)の大半を占める.本稿では植物ウイルスの認識に関わるNB-LRR型R遺伝子について,抵抗性メカニズム・進化・農業上の利用の観点から概説するとともに,近年明らかになったmiRNAやイントロンによるNB-LRR型R遺伝子の発現調節機構について紹介する.また,NB-LRR型R遺伝子が引き起こす興味深い現象の一つにウイルス感染開始点周辺のプログラム細胞死があるが,それが植物の生存戦略にもたらす意義については明らかでない.これについて,筆者らの実験結果や生態学的見地からの推論をもとに議論する.
- 著者
- 松村 祥子
- 出版者
- 日仏社会学会
- 雑誌
- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.133-139, 2014-11-30 (Released:2017-05-29)
1 0 0 0 OA There Are Not Enough Facilities for Outpatient Cardiac Rehabilitation ― What Is the Solution? ―
- 著者
- Yuma Tamura Takanori Yasu
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-22-0375, (Released:2022-07-20)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 OA 日本語の次文字予測率からの検討
- 著者
- 横原 恭士
- 出版者
- 相愛大学
- 雑誌
- 相愛大学研究論集 = The annual report of researches of Soai University (ISSN:09103538)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.21-28, 1997-12
本研究は、西部文学・西部表象を移動・環境・女性の観点から捉え直すことを試みる。これまでの研究の多くが東部作家による西部表象の問題を扱ってきたのに対し、本研究は、西部へと流入してきた作家、あるいは、西部間を移動する作家が西部をどのように描いているのかという問いを主軸に置く。この問いを考える上で、トランスリージョナリズムという本研究独自の概念(ヒト・モノの移動が地域に及ぼす文化的諸相)を提唱する。さらに、主として男性作家に担われてきた西部文学にあって女性はどのように描かれているのか、女性作家は西部をどのように描いているのか、移動の文化と女性との関係はいかなるものか、といった問いを追究する。