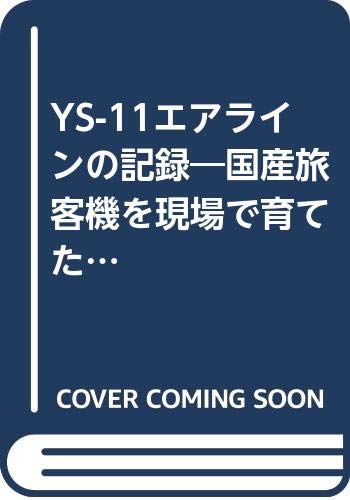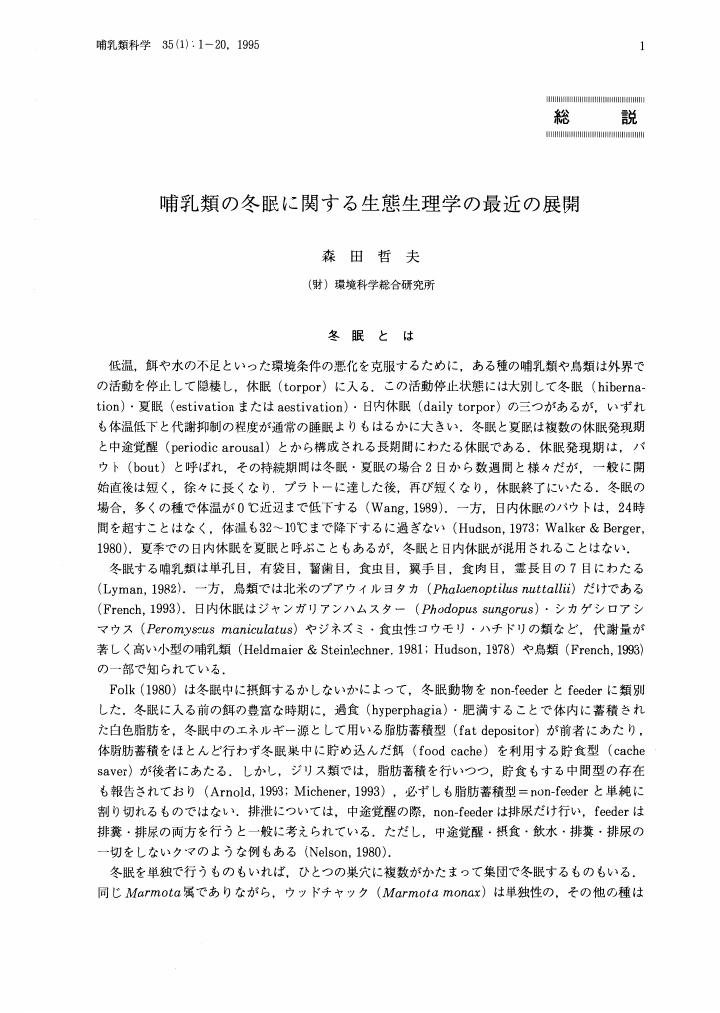9 0 0 0 OA 一休骸骨
『一休骸骨』は仮名書きの法語集で、多くの骸骨が登場して日常の営みごとを行うさまを描き、道歌を多く収めている。書名に一休とあるが仮託の書である。当該本は巻末に刊記の一部「孟春吉旦」を残した、元禄5年(1692)本の後印本。本文3丁裏に3行の増補の文がない系統の本である。先行本に室町古版とされる版本があるが、これは寛永(1624-1643)ころの整版本と判断され、これも3行の増補のない本文であるが版式は全く異なる。屋代弘賢(1758-1841)の「不忍文庫」、徳島藩の「阿波国文庫」の印記がある。(岡雅彦)(2016.2)
9 0 0 0 OA 物語的現実としての霊 他者の死と自己の死をつなぐもの
- 著者
- 堀江 宗正
- 出版者
- 宗教哲学会
- 雑誌
- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.1-13, 2019-03-30 (Released:2019-05-22)
In contemporary society, people are increasingly less likely to reject spirits on the grounds that they are not scientifically verifiable. Rather, they accept the reality of spirits if narratives about them heal the narrators. This article describes this phenomenon as the rise of a “narrative reality” of spirits. In order to understand this new attitude, I refer to psychological theories about the deceased, such as S. Freud’s theory on object loss and “mourning work,” D. Klass et al.’s notions of continuing bonds, C. G. Jung’s theories of complex and archetype, and V. Frankl’s ideas about the spiritual person. I then consider two examples of spiritualist practices called “demonstration” based on my fieldwork research in the U.K. and in Japan. I argue that stories of spirits sound realistic when they fit into a preset narrative pattern of the dead watching over the living. Stories of the deceased watching over us aid us in accepting death, of others and ourselves. At the same time, they imply that another Japanese narrative pattern in which the dead punish the living has receded into the background while an expectation that the benevolent dead watch over us has become dominant. Perceivable behind this shift is the fact that the range of sympathy toward the dead is narrowing to only include the deceased who are beloved by family, friends, or acquaintances. Inclusion of the lonely who die with no one to love them will be one of our society’s main tasks to tackle.
9 0 0 0 OA アレルゲン免疫療法の現況―皮下免疫療法から舌下免疫療法まで
- 著者
- 後藤 穣
- 出版者
- 日本鼻科学会
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.90-93, 2018 (Released:2018-04-19)
- 参考文献数
- 3
【実験Ⅰ】目標は「膀胱における尿再吸収を制御する生理的条件の検討」であった。①「尿組成の影響」:生理的浸透圧を大きく超える塩化ナトリウム溶液やブドウ糖液は、再吸収を促進しなかった、②膀胱壁伸展の影響:機能的容量以上で再吸収が始まり、約200%までは容量依存的に吸収量が増加した、③体水分の影響:検討できなかった。結果は予想通りであり、Na+イオン吸収量に依存して膀胱腔内の液量は減少した。【実験Ⅱ】目標は「膀胱に発現するclaudinサブタイプの確認」であった。生理食塩液による膀胱伸展により、claudin-3, -6, -11の発現が増加することを確認した。また、追加実験において同様の刺激により、aquaporin-2の発現が増加することを確認した。さらに、RNA干渉によりaquaporin-2の発現を抑制することで、膀胱での再吸収が抑制されることを突き止めた。【Neurourology and Urodynamics受理済み論文の詳細】ラット膀胱を生理食塩液 1.0mLで3時間伸展すると、aquaporin-2の発現が大きく促進されてNaイオンとともに水が膀胱壁より吸収される。aquaporin-2の発現を抑制すると、水およびNaイオンの吸収量が大きく減少する。aquaporin-2は主に尿路上皮に発現しており、組織学的にも再吸収に関与していると考えて矛盾しない。わずか3時間の過程で再吸収に関わる遺伝子および蛋白の発現変化は予想していなかったことであり、再吸収機構を検証する上で非常に興味深い知見である。
- 著者
- 伊藤 眞
- 出版者
- 東京都立大学人文学部
- 雑誌
- 人文学報 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.309, pp.83-109, 2000-03
9 0 0 0 OA がんゲノム研究における変異シグネチャー解析の展開
- 著者
- 松谷 太郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会
- 雑誌
- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.75-87, 2022 (Released:2022-11-01)
- 参考文献数
- 51
がん細胞のゲノムには多数の突然変異が含まれており、それらは変異プロセスと呼ばれる何らかの原因によって引き起こされたものである。一部の変異プロセスは、変異の種類(一塩基置換や構造バリアント等)や周辺の塩基情報に依存した特定の変異を引き起こしやすいことが知られており、そのような変異のパターンを変異シグネチャーと呼ぶ。個人の腫瘍に含まれる多数の突然変異は複数のシグネチャーが作用した結果と解釈することが可能であり、そのようなシグネチャー解析は変異をその原因と結びつけるという意味で発がん過程の分子的なメカニズム解明の一助となる他、個別化医療の現場におけるバイオマーカーとしての利用が期待されている。本総説では、変異シグネチャーの推定手法としてオミクスデータに対する教師なし学習を中心に概説した後に、がんゲノム研究における応用例を紹介し、今後の展望について議論する。
- 著者
- YS-11エアラインの記録編集委員会編
- 出版者
- 日本航空技術協会
- 巻号頁・発行日
- 1998
9 0 0 0 OA 尺度翻訳に関する基本指針(<特集>「行動療法研究」における研究報告に関するガイドライン)
- 著者
- 稲田 尚子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.117-125, 2015-05-31 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 11
患者報告式アウトカム尺度が翻訳されることにより、研究成果の国際比較および国際共同研究が可能となる。翻訳された尺度から得られるデータの質は、その翻訳の正確さに依存する。ISPOR(International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)タスクフォースによるガイドラインは、患者報告式アウトカム尺度の翻訳に関する質を担保し、ひいては研究報告の質を高めるうえで有用となる。本稿では、当該ガイドラインに従って、推奨される10の手続き((1)事前準備、(2)順翻訳、(3)調整、(4)逆翻訳、(5)逆翻訳のレビュー、(6)調和、(7)認知デブリーフィング、(8)認知デブリーフィング結果のレビューと翻訳終了、(9)校正、(10)最終報告)について解説した。また、当該ガイドラインに基づく具体的な記載事例の紹介を行い、尺度翻訳の際の留意事項について考察した。
9 0 0 0 OA 米海軍水上艦船の復原力および予備浮力に関する基準
- 著者
- 中島 武之
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会誌 (ISSN:03861503)
- 巻号頁・発行日
- vol.414, pp.67-78, 1964-02-25 (Released:2018-04-21)
9 0 0 0 OA 聖徳太子の人物像と千三百年御忌
- 著者
- 東野 治之
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.1, pp.1-16, 2022 (Released:2022-12-12)
Rare is such a historical figure who has been the subject of review for so many generations as Prince Shōtoku (574–622). His image alone serves as an entire research topic. This paper focuses on Prince Shōtoku Hōsankai, an honoring party founded in 1921, and examines how it impacted the modern view of Prince Shōtoku. In general, Prince Shōtoku is known as the regent and prince to Empress Suiko, suppressing tyranny of the Gōzoku (prominent clans) and striving for a central government led by the emperor. Prince Shōtoku established diplomatic relations with the Sui dynasty and promoted the civilization of Japan by proactively adopting the Chinese culture. This perception was based on the Nihon Shoki (The Chronicles of Japan, written in 720). However, modern research has denied the existence of a prince or regent during the Suiko dynasty. Additionally, Prince Shōtoku was most likely an advisor to Empress Suiko and Soga no Umako, without much involvement in government policies. (View PDF for the rest of the abstract.)
9 0 0 0 OA 国文研ニューズ No.51 SPRING 2018
- 著者
- 原 正一郎 太田 尚宏 小山 順子 黄 昱 恋田 知子 神作 研一 齋藤 真麻理 高科 真紀 有澤 知世
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文研ニューズ = NIJL News (ISSN:18831931)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.1-16, 2018-05-07
●メッセージ国文学研究資料館情報システムの今昔物語●研究ノート読書時間は森の中――尾張藩「殿山守」資料に見る山間村落のひとこま――現代における古典文学コミカライズの傾向について●トピックス平成29年度 連続講座「初めてのくずし字で読む『百人一首』」平成30年度 連続講座「多摩地域の歴史アーカイブズ(古文書)を読む」特別展示 「伊勢物語のかがやき――鉄心斎文庫の世界――」第15回日本古典籍講習会(平成29年度)国際研究ワークショップ「江戸の知と随想」2017冬パリフォーラム「東アジアにおける知の往還」第一回――書物と文化――日本古典籍セミナー国際研究交流集会「災害国におけるアーカイブズ保存のこれから――技術交流・危機管理から地方再生へ――」平成30年度 アーカイブズ・カレッジ(史料管理学研修会通算第64回)の開催閲覧室だより第4回日本語の歴史的典籍国際研究集会の開催「古典」オーロラハンター3LOD Challenge 2017の最優秀賞に当館の「日本古典籍データセット」が使用されました総合研究大学院大学日本文学研究専攻の近況●表紙絵資料紹介山東京伝書簡
9 0 0 0 OA 哺乳類の冬眠に関する生態生理学の最近の展開
- 著者
- 森田 哲夫
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.1-20, 1995 (Released:2008-07-30)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- Mayumi Watanabe Osamu Takano Chikako Tomiyama Hiroaki Matsumoto Takahiro Kobayashi Nobuatsu Urahigashi Nobuatsu Urahigashi Toru Abo
- 出版者
- Biomedical Research Press
- 雑誌
- Biomedical Research (ISSN:03886107)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.243-248, 2012 (Released:2012-09-04)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 5 7
Skin rubdown using a dry towel (SRDT) to scrub the whole body is a traditional therapy for health promotion. To investigate its mechanism, 24 healthy male volunteers were studied. Body temperature, pulse rate, red blood cells (RBCs), serum levels of catecholamines and cortisol, blood gases (PO2, sO2, PCO2 and pH), lactate and glucose, and the ratio and number of white blood cells (WBCs) were assessed before and after SRDT. After SRDT, pulse rate and body temperature were increased. PO2, sO2 and pH were also increased and there was no Rouleaux formation by RBCs. Lactate level tended to increase, whereas that of glucose did not. Adrenaline and noradrenaline levels increased, indicating sympathetic nerve (SN) dominance with increase in granulocytes. WBC number and ratio were divided into two groups according to granulocyte ratio (≤ or
9 0 0 0 OA 被害者参加人の発言および被害者参加制度への態度が量刑判断に与える影響
- 著者
- 白岩 祐子 唐沢 かおり
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.12-21, 2013 (Released:2013-09-03)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2
近年,裁判員制度や被害者参加制度が刑事裁判に導入され,一般市民の法的判断を規定する要因が注目され始めている。本研究では,被害者参加人のタイプや表出感情,被害者参加制度に対する個人の態度が,量刑判断にどのような影響を及ぼすのかを検討するため,大学生・大学院生などを対象にシナリオ実験を行なった。その結果,誰が被害者参加人を務め,どのような感情を表出するかという要因と,個人の量刑判断との間に関連はみられなかった。また,「他者は自分よりも被害者参加人の言動に影響される」という社会的影響の非対称な認知が確認され,この判断バイアスは,被害者参加制度に対する態度が否定的であるほど大きくなった。さらに,制度に対する態度は,非対称な認知のうち自己への影響認知を媒介して量刑選択に影響を及ぼしていた。具体的には,被害者参加制度に反対するほど被害者参加人の発言による自己への影響が否定され,それによって短い量刑が選択された。以上の結果を踏まえ,量刑判断の規定因研究における展望と課題が議論された。
9 0 0 0 OA 天然抗酸化物質の吸収と代謝
- 著者
- 宮澤 陽夫 仲川 清隆 浅井 明
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.104-114, 2000-02-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 6 5
9 0 0 0 OA ぺた語義:三重大学のノートPC必携制度の5年間とこれから
三重大学では,2018年度に学部入学生のノートPC必携制度が始まった.筆者は2017年から総合情報処理センターの教員として全学的な必携制度の推進に従事したのち,2021年度からは工学研究科の教員として,立場を変えながら必携制度と向き合ってきた.本稿では三重大学の必携制度の5年間とこれからについて,全学からの視点と学部教員の視点の両方から考察する.特に,ノートPCのスペック,サポート体制,必携PCの活用を念頭に開設した施設である数理・データサイエンス館(CeMDS),学部の研究室でのPC活用,そして必携制度のこれからに焦点を当てる.
9 0 0 0 OA 尾張名所図会
- 著者
- [岡田啓, 野口道直 編]
- 出版者
- 名古屋温古会
- 巻号頁・発行日
- vol.附録 巻3, 1930