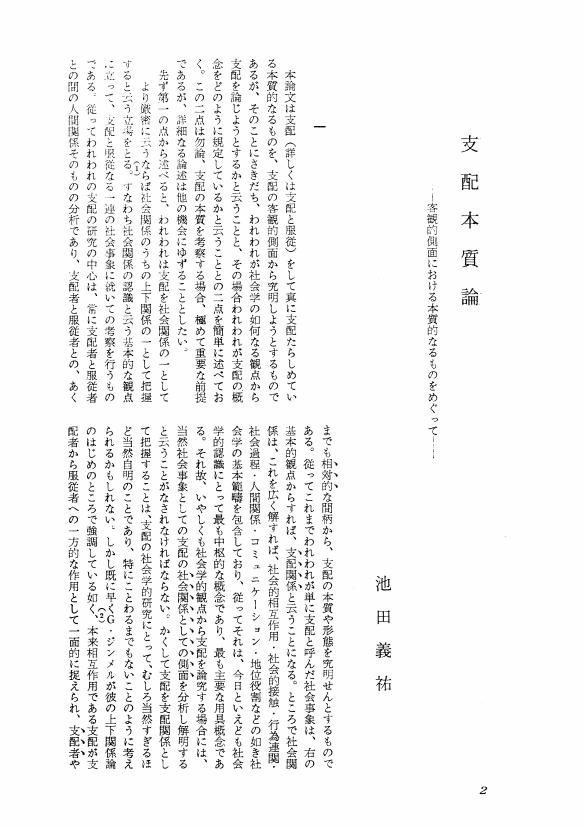- 著者
- 日野川 静枝
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究. 第II期 (ISSN:00227692)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.238, pp.81-91, 2006-06-01
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2
The World War II broke out in Europe in 1939, and the United States set up the National Defense Research Committee on June in 1940. On April 3,1940, the Meeting of Trustees of the Rockefeller Foundation decided on a grant of $1,150,000 to support the construction of a new 184-inch cyclotron at the University of California. This paper elucidates the process leading up to that decision. The decision-making process can be divided into three stages : The first, beginning in October 1939, saw initial enthusiasm for the giant cyclotron project; the second, lasting until February 1940, involved changes in the Foundation's internal circumstances and limitations on funding; the third, which began in early February 1940, saw specific steps toward the materialization of Foundation support for the project. Doubtlessly, Lawrence's supporters tangibly and intangibly influenced the Rockefeller Foundation's decision to support the construction of the giant cyclotron. The decision-making process, however, seems to shed light on the Foundation's grant-making plans or grant-making policy. That is, the Foundation was deeply involved in drawing up the plans from the start, and provided grants for carefully-selected, large-scale, and long-range projects in the fields it was interested in. The giant cyclotron project, for which single-source support was an important issue, seems to be one such case.
1 0 0 0 イネファイトアレキシンとジャスモン酸
- 著者
- 田母神 繁
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.100-103, 2001-02-20
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 肝性昏睡の臨床的研究 臨床経過ならびに予後について
- 著者
- 浮田 実
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.5, pp.341-352, 1977-05-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 32
肝性昏睡は一部の症例を除いては一般的に予後不良と言えるが,肝疾患に対する治療法の進歩により,その臨床経過ならびに予後も変化してきていることが考えられる.そこで,本稿においては最近17年間に岡山大学医学部付属病院第一内科に入院した肝性昏睡102例を対象として,臨床経過,死因,予後の時代的変遷を検討した.その結果,肝硬変では,最近5年間に肝性昏睡からの覚醒率が高くなってきており,治療法の進歩をうかがわせたが,一方では,肝癌合併例の急激な増加,肝腎症候群を呈する例の増加が顕著であり,これらの例の予後は不良であった.肝性昏睡を繰り返す,いわゆる慢性型肝性昏睡の肝硬変では,初回肝性昏睡から平均2~3年で死亡した.fulminant hepatitisでは,肝性昏睡から1週間以内に覚醒した例は完全な回復を示した.亜急性肝炎で肝性昏睡に陥った例はすべて2週間以内に死亡した.
- 著者
- 新立 義文 小郷 克敏 沢田 芳男
- 出版者
- 熊本大学体質医学研究所
- 雑誌
- 熊本大学体質医学研究所報告 (ISSN:0023530X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.p159-168, 1981-03
1 0 0 0 OA 氷晶石に就て
- 著者
- 薗部 龍一
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.351-353, 1941-08-15 (Released:2010-10-13)
- 著者
- 小巻 亜矢
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経トップリーダー = Nikkei top leader (ISSN:24354198)
- 巻号頁・発行日
- no.427, pp.3-5, 2020-04
こまき・あや1959年東京都生まれ。大学卒業後にサンリオ入社。25歳で結婚退社後、37歳で仕事復帰。2013年に東京大学大学院修士課程修了。14年サンリオエンターテイメントに顧問として入社。
- 著者
- 小巻 亜矢
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経コンピュータ = Nikkei computer (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.1021, pp.68-71, 2020-07-23
新型コロナウイルス感染拡大を受け、いち早くサンリオピューロランドを休園する決断を下した。かつてない経営危機も変革の契機と捉え、動員数至上主義からの脱却を宣言。デジタルの活用や人材育成を加速し、新たなテーマパーク像の構築を目指す。
1 0 0 0 IR 五味川純平の中国観と『人間の條件』 : 第一部・第二部を中心に
- 著者
- 高橋 啓太
- 出版者
- 花園大学文学部
- 雑誌
- 花園大学文学部研究紀要 = Annual Journal Faculty of Letters Hanazono University (ISSN:1342467X)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.27-39, 2021-03-12
1 0 0 0 国史学界の今昔(59)戦後歴史学と古代史研究のあゆみ(下)
1 0 0 0 国史学界の今昔(58)戦後歴史学と古代史研究のあゆみ(上)
1 0 0 0 OA 小規模図書室におけるオフコンを利用した図書資料管理
- 著者
- 板橋 慶造 石川 正
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- ドクメンテーション研究 (ISSN:00125180)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.33-39, 1984-01-01 (Released:2017-10-05)
日本原子力研究所技術情報部では,那珂地区核融合研究センター内に「研究情報センター」を設置するにあたり,その業務を効率的に処理するため,オフィスコンピュータによる図書館システムを導入した。このシステムは会計処理を除く窓口業務中心のトータルシステムであり,図書,レポート,雑誌,パンフレットを対象としている。その結果,OCRハンドスキャナーの導入により蔵書点検作業が大幅に軽減されただけでなく,窓口業務も利用者の手書き作業が不要になるなど省力化され,図書館のイメージアップにもつながる等の効果が見られた。
1 0 0 0 OA 「新田岩松家旧蔵粉本コレクション」について -発見・復元・図録作成・その特徴-
- 著者
- 山中 康行
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.37-44, 2003-08-31 (Released:2017-12-12)
群馬大学附属図書館は,昭和41年新田岩松家の後裔である故新田義美(よしとみ)氏から旧新田男爵家に伝来された文献資料群の寄贈を受けた。寄贈時にもたらされた資料群の中に膨大な屑状の紙片があった。それらの紙片は屑としか見えない状態であったためにかえりみられることがなかった。平成13年春,この紙片の塊が廃棄寸前になって,日本画の下絵(粉本)であることが判明した。約1年半をかけて膨大な屑状の紙片の悉皆調査を行い,総点数1,265点の反故を画帳形式に復元整備した。寄贈者の遺族も知らなかった粉本の発見であった。平成15年3月には整理が終わるとともに群馬大学附属図書館所蔵「新田岩松家旧蔵粉本図録」が完成した。
1 0 0 0 OA 中国北西部乾燥域で観測された2つの局地的シビアストーム
- 著者
- 光田 寧 林 泰一 竹見 哲也 胡 隠樵 王 介民 陳 敏連
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.1269-1284, 1995-12-25 (Released:2009-09-15)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 14 13
HEIFEプロジェクト期間中において2個のシビアストームが観測された(1992年7月19日・1993年5月5日)。ここでは乾燥地帯で発生したストームの発生機構について述べる。2つのストームは一方が数kmの積乱雲のスケール、もう一方が100kmのスコールラインのスケールであったが、ともに対流性の雲からの強い下降流で特徴づけられるという点で一致していた。これらは本質的に世界の各地で見られるストームと同じであるが、7月19日の場合では、年間雨量の3分の1に相当する30mmの雨が降り、下降流が地表に達したことで生じる発散する風速場がとらえられた。5月5日の場合では、激しい砂嵐をともない、スコールラインが狭いバンドから広いバンドに発達していくとともに、発達した状態では地表で2時間以上にもわたり強風が続いていたことが特徴的であった。
1 0 0 0 IR カタルーニャ独立問題 : それは多様性を認めないスペイン・ナショナリズムの問題(後半)カタルーニャ・スペイン問題の国際化と袋小路の要因 (広瀬恵子先生 天野知恵子先生 工藤貴正先生 退職記念号)
- 著者
- 奥野 良知
- 出版者
- 愛知県立大学外国語学部
- 雑誌
- 紀要. 地域研究・国際学編 = The Journal of the Faculty of Foreign Studies, Aichi Prefectural University. Area studies and international relations (ISSN:13420992)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.45-76, 2021
1 0 0 0 IR カタルーニャ独立問題 : それは多様性を認めないスペイン・ナショナリズムの問題(前半)
- 著者
- 奥野 良知
- 出版者
- 愛知県立大学外国語学部
- 雑誌
- 紀要. 地域研究・国際学編 = The Journal of the Faculty of Foreign Studies, Aichi Prefectural University. 愛知県立大学外国語学部 編 (ISSN:13420992)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.47-70, 2020
1 0 0 0 歴史の風 戦後の歴史家と「現在」
- 著者
- 稲葉 伸道
- 出版者
- 史学会 ; 1889-
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.37-39, 2020-01
1 0 0 0 OA 支配本質論
- 著者
- 池田 義祐
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.2-17,111, 1963-09-30 (Released:2009-11-11)
1 0 0 0 IR 近世前期の仏典注釈――光隆寺知空の講義録と出版――
- 著者
- 木村 迪子
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要 文学研究篇 = The Bulletin of The National Institure of Japanese Literature (ISSN:24363316)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.63-95, 2021-03-29
西本願寺二代目能化・光隆寺知空は承応の鬩牆を契機として西吟教学からの決別を果たし蓮如義に移行したと言われる。近年、これに反論して知空の西吟教学継承を説く動きが顕著である。まず、本稿では主にテキストから検証されてきた知空による西吟教学の継承を、これまで検討されてこなかった明暦三年に行われた知空の講義録二書に注目し、その証左とする。第一に、知空が講義に選んだ『浄土或問』ならびに『仏遺教経論疏節要』が明代の禅僧・雲棲袾宏の注釈を附した和刻本であったことを指摘し、明暦三年時点で知空による西吟教学の踏襲があったことを明らかにする。次に寛文元年刊行の『和讃首書』が当時禅籍にのみ用いられていた頭書形式を踏襲していたことを指摘する。次に、明暦三年の知空の講義録『浄土或問鉤隠』が天和三年刊頭書本『浄土或問』に利用され、またその増補再版に浄土宗西山派の学僧・諦全が補考を附した事実から、元禄期における仏典注釈の交雑化を指摘する。十七世紀における頭書本仏書の流行は重板類板の規制強化を受けて急速に衰えたが、寛文末頃から不遇を託っていた知空は元禄八年の学林再興と共に能化に返り咲き、以後、今度は大坂の書林・毛利田庄太郎らと組んでその仏典注釈板行を行った。こうした積極性、柔軟性は知空に限定されず、十七世紀仏教と宗学への積極的な評価に繋がるものである Chiku was a scholar priest belonging to Buddhism's Shin sect and this paper attempts to re-evaluate Japanese early modern Buddhism byelucidating his annotations of Buddhist commentaries and their development. Of note is that the Zen character found in Chiku's writings is a reflection of his teacher, Saigin. Chiku tried to overcome'承応の鬩牆'by using Zen perspectives derived from the Shin sect. Significantly, it has come to light that a record of Chiku's lectures was used by the annotation published in 1683. Moreover, the book reprinted in 1690 was added annotations by Taizen, a scholar of the Jodo sect. This is proof that at the end of the 17th century, the Buddhist annotations that had been communicated independently by each sect were, in fact,compendiums of various authorities. From the beginning of the 18th century, the publication of Buddhist annotations declined rapidly against the backdrop of tightening publishing regulations. But Chiku's lectures were published by his disciples from bookstores in Osaka. It can be concluded that Chiku's progressive stance also spread to other Buddhists in the early modern period, and that this can be viewed as a positive characteristic of Japanese early modern Buddhism.
1 0 0 0 十一月号特集「文学」と「サブカルチャー」の社会学
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, 2001