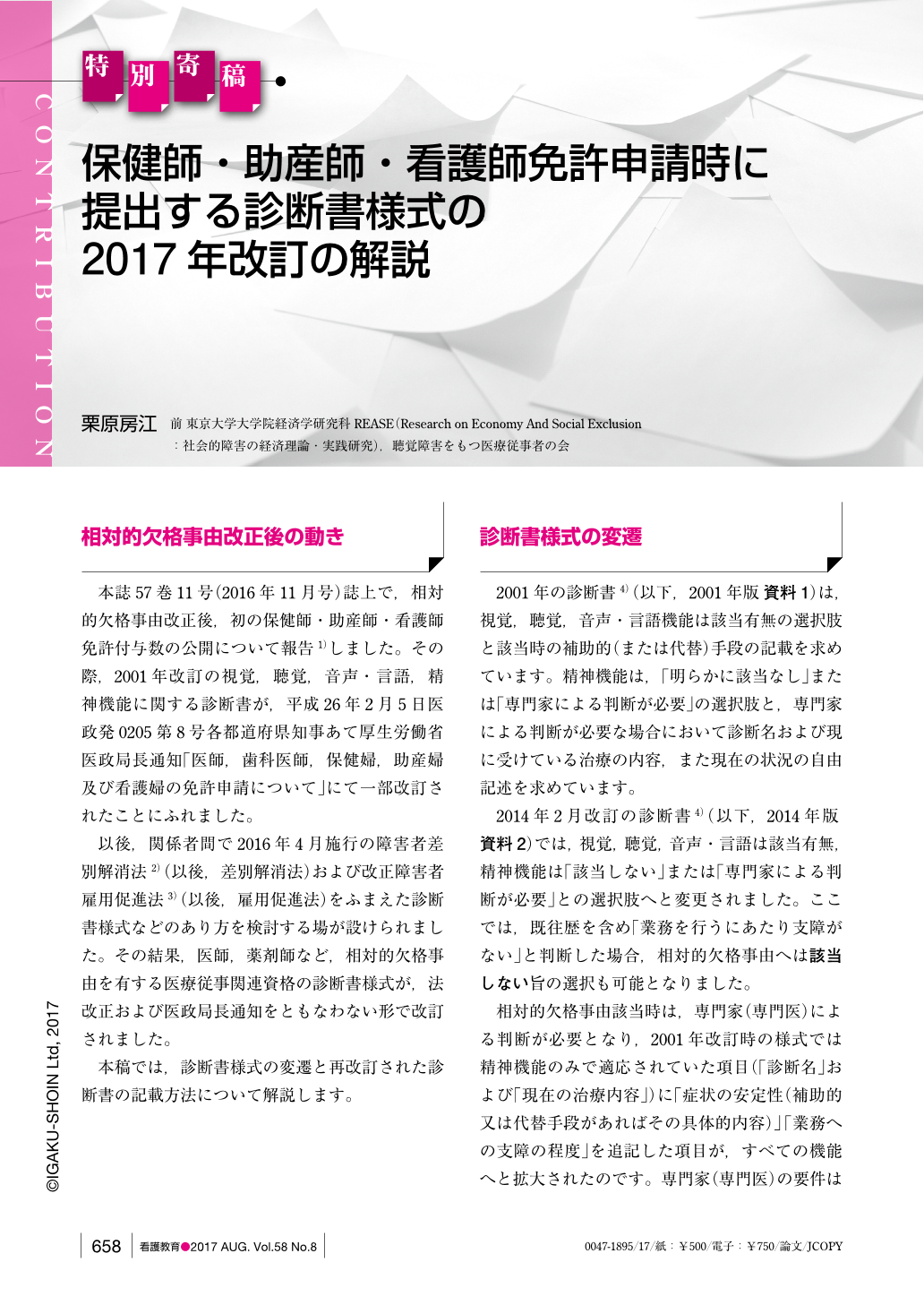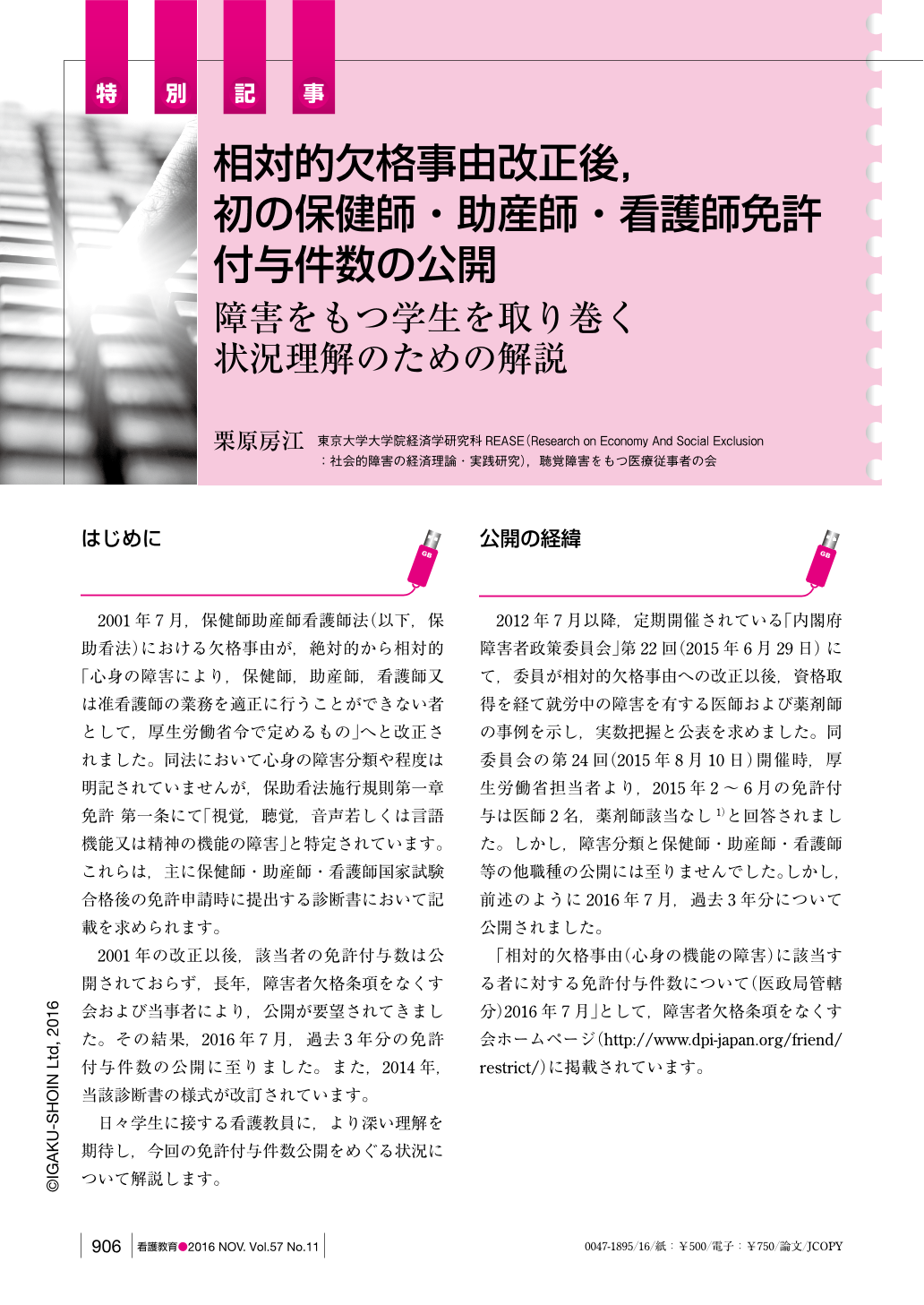- 著者
- 堀野 洋 森 信彦 松木 明好 鎌田 理之 平岡 浩一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48101509, 2013
【はじめに、目的】眼球運動時に安静にある第一背側骨間筋、小指外転筋、橈側主根伸筋の運動誘発電位(MEP)振幅が減少することが報告されている(Maioli et al. 2007)が、目と手の協調を必要とする眼球・腕運動同時実施時に眼球運動が上肢筋支配の皮質脊髄下降路に及ぼす影響は明らかでない。本研究では目と手の協調を必要とする眼球・腕同時の標的運動時に眼球運動が上腕二頭筋・三頭筋支配皮質脊髄下降路興奮性に及ぼす影響を検証した。【方法】健常成人11 名(23-35 歳)に椅子座位をとらせ、右肘関節を屈伸できるペンデュラムに右上肢を乗せた。ペンデュラム前腕部に前腕運動を壁面に投影するレーザーポインターを設置し、頭部固定装置で頭部を固定した。右上腕二頭筋と右上腕三頭筋に記録用表面電極(EMG)を取り付けた。角膜反射光法による眼球運動計測装置を取り付けた。被験者の1m前方の壁の正中線上に開始位置マークと、その20°左側に終了位置マークを設置した。開始位置マークにレーザービームを合わせて右肘関節屈曲35°の開始肢位を取らせ、警告音の1000ms後の開始音を合図に右肘関節屈曲55°の位置にある終了位置マークにレーザービームを一致させる課題を行わせた。眼球運動は、開始音(500Hz)を合図にレーザービームを眼球で追従させる条件(円滑追従眼球運動;SP)、開始音(143Hz)を合図に開始位置マークを凝視させる条件(眼球静止;EM)、開始音(84Hz)を合図に視線を終了位置マークに急速に移動させる条件(衝動性眼球運動;S)の3 条件とした。double cone coilを使用し、運動閾値の1 倍で上腕二頭筋hotspotに経頭蓋磁気刺激(TMS)を行った。TMSのタイミングは、右肘関節屈曲運動前の開始音時、開始音後200 ms、腕運動初期相・中間相・最終相)で実施した。【倫理的配慮、説明と同意】実験は大阪府立大学研究倫理委員会の承認を得て実施した。被験者には実験の目的・方法及び予想される不利益を説明し同意を得た。【結果】眼球運動のreaction time(RT)は各条件において有意差を認めなかった。上腕二頭筋EMGのRTはS条件において他の条件に対して有意に延長した。SP・S条件において眼球運動RTと上腕二頭筋EMGのRTの間で有意な相関を認めた。肘関節運動時間はSP条件において他の条件に対して有意に延長した。上腕二頭筋のbackground EMG振幅は初期相においてSP条件で他の条件と比較して有意に低下したが、それ以外の相では3 条件間で有意差を認めなかった。上腕二頭筋・上腕三頭筋のMEP振幅は3 条件間で有意差を認めなかった。開始音後200msの上腕二頭筋・上腕三頭筋の上腕二頭筋・上腕三頭筋のbackground EMG振幅は3 条件間で有意差を認めなかった。開始音後200msの上腕二頭筋・上腕三頭筋のMEP振幅は3 条件間で有意差を認めなかった。【考察】円滑追従眼球運動・衝動性眼球運動における上腕二頭筋EMGのRTに対する有意な相関は、眼球運動と腕運動が同一運動制御中枢のトリガーにより開始されることを示唆した。円滑追従眼球運動条件における腕運動時間延長と上腕二頭筋BEMG振幅低下は、眼球で追える程度の腕運動速度に低下させるためにEMG活動が減少したためであると考えられた。一方、皮質脊髄下降路興奮性は運動開始前・運動開始中とも眼球運動条件間で有意差がなかった。特に運動開始前には固有感覚や視覚フィードバックが生じないので、この相におけるMEPは腕運動および眼球運動命令の影響を純粋に反映するものと考えられる。したがって、本研究の知見は、目と手の協調を必要とする標的運動時であっても、眼球運動命令は腕筋支配皮質脊髄下降路興奮性に影響を及ぼさないものと考えられた。安静状態にある前腕・手指筋のMEP振幅は円滑追従眼球運動時に減少するが、これは眼球運動によって一部共有する眼球運動中枢からの腕・指運動命令中枢が眼球運動時に運動命令を生じて安静にもかかわらず腕・指運動が生じることを予防するために生じていると考えられている(Maioli et al. 2007)。本研究でこのようなMEP振幅減少が確認されなかった理由は、腕運動を同時に遂行したため、運動発現予防のための上腕筋支配皮質脊髄下降路興奮性抑制の必要がなかったためと考えられた。【理学療法学研究としての意義】目と手を同時に標的へ動かした時の運動制御機能について明らかにすることにより、様々な日常生活動作に関する上肢のリーチング動作やポインティング動作への理学療法アプローチに資する知見である。
1 0 0 0 OA スポーツマンシップとは何か?
- 著者
- 谷釜 尋徳 渡邊 瑛人
- 出版者
- 東洋大学スポーツ健康科学委員会
- 雑誌
- スポーツ健康科学紀要 = JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE (ISSN:13461087)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.5-11, 2020-03
1 0 0 0 技術&イノベーション 高炉いらずの新製鉄法
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1220, pp.76-78, 2003-12-08
日本初の本格的な製鉄所、官営八幡製鉄所が操業したのは1901年。モノ作りの要とも言える鉄鋼業の幕開けは、ドイツから導入した製鉄技術がもたらした。それから100年余り、"日本発"の高炉いらずの新製鉄法が実用化に向けて秒読み段階に入っている。 神戸製鋼所が開発した「ITmk3(アイティ・マークスリー、第3世代製鉄技術の意)」と呼ぶ製鉄法だ。
相対的欠格事由改正後の動き 本誌57巻11号(2016年11月号)誌上で,相対的欠格事由改正後,初の保健師・助産師・看護師免許付与数の公開について報告1)しました。その際,2001年改訂の視覚,聴覚,音声・言語,精神機能に関する診断書が,平成26年2月5日医政発0205第8号各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「医師,歯科医師,保健婦,助産婦及び看護婦の免許申請について」にて一部改訂されたことにふれました。 以後,関係者間で2016年4月施行の障害者差別解消法2)(以後,差別解消法)および改正障害者雇用促進法3)(以後,雇用促進法)をふまえた診断書様式などのあり方を検討する場が設けられました。その結果,医師,薬剤師など,相対的欠格事由を有する医療従事関連資格の診断書様式が,法改正および医政局長通知をともなわない形で改訂されました。
- 著者
- 小泉 萌香 鈴木 希 伊藤 真吾 五十嵐 里美 梅津 優子 山田 晴美 高橋 暢 山田 敬子
- 出版者
- 山形県精神保健福祉協会
- 雑誌
- やまがた精神保健福祉
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.31-33, 2019
はじめに 2001年7月,保健師助産師看護師法(以下,保助看法)における欠格事由が,絶対的から相対的「心身の障害により,保健師,助産師,看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として,厚生労働省令で定めるもの」へと改正されました。同法において心身の障害分類や程度は明記されていませんが,保助看法施行規則第一章 免許 第一条にて「視覚,聴覚,音声若しくは言語機能又は精神の機能の障害」と特定されています。これらは,主に保健師・助産師・看護師国家試験合格後の免許申請時に提出する診断書において記載を求められます。 2001年の改正以後,該当者の免許付与数は公開されておらず,長年,障害者欠格条項をなくす会および当事者により,公開が要望されてきました。その結果,2016年7月,過去3年分の免許付与件数の公開に至りました。また,2014年,当該診断書の様式が改訂されています。 日々学生に接する看護教員に,より深い理解を期待し,今回の免許付与件数公開をめぐる状況について解説します。
1 0 0 0 OA 御伽草子「はちかづき」の草双紙への展開 ―西村屋與八板を中心に―
- 著者
- 松原 秀江
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.1-15, 1982 (Released:2017-04-28)
1 0 0 0 OA 不妊治療を経験した女性たちの語り 「子どもを持たない人生」という選択
- 著者
- 竹家 一美
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.118-137, 2008 (Released:2020-07-06)
- 被引用文献数
- 1
生殖補助医療の急速な進展は,不妊に苦悩する女性たちに,希望と残酷な可能性の両方をもたらしてしまった。不妊治療は「先の見えないトンネル」ともいわれ,治療の結果,子どもを持てる確率は非常に低いのが現実である。不妊治療は妊娠・出産を迎えなければ完了せず,治療の継続・断念は当事者に一任される。本研究では,不妊治療を経験したうえで「子どもを持たない人生」を選択した女性 9 名との半構造化面接を通して,「子どもを持たない人生」を受容するプロセスを明らかにし,彼女たちの人生における不妊治療経験の意味を検討することを目的とした。対象者の語りは「不妊治療初期」「不妊治療集中期」「不妊治療終結期」の 3 つの時期に分けられたが,女性たちの心の変容プロセスは段階的,画一的なものではありえず,個別的で多様性にみちていた。また,対象者の語りにおいて不妊治療の経験は,「受容感の拡大」「価値観の転換」「治療の意味づけの変更」「生成継承性の芽生え」に繋がるものとして意味づけられていた。不妊治療終結期以降,不妊に苦悩した女性たちは,「社会化」を実現することによって不妊を乗り越えていた。生涯発達的観点からみると,彼女たちの語りには,肯定的な意味づけと発達的な一側面が示唆されていると思われた。
1 0 0 0 OA アキレス腱障害の発生機序の検討 ~ねじれの程度に着目して~
- 著者
- 江玉 睦明 久保 雅義 大西 秀明 稲井 卓真 高林 知也 横山 絵里花 渡邉 博史 梨本 智史 影山 幾男
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0563, 2015 (Released:2015-04-30)
【はじめに,目的】アキレス腱(AT)障害の発生メカニズムとしては,これまで踵骨の過回内による「whipping action(ムチ打ち)」が要因であると考えられてきた。しかし,近年では,踵骨の回内時にAT内の歪みが不均一であることが要因として重要視されてきている。この原因としては,ATの捻れ構造が関与している可能性が示唆されていが,ATの捻れの程度の違いを考慮して検討した報告はない。従って,本研究は,踵骨を回内・回外方向に動かした際にATを構成する各腱線維束に加わる伸張度(%)を捻れのタイプ別に検討することを目的とした。【方法】対象は,我々が先行研究(Edama,2014)で分類したATの3つの捻れのタイプ(I:軽度,II:中等度,III:重度の捻れ)を1側ずつ(日本人遺体3側,全て男性,平均年齢:83±18歳)使用した。方法は,下腿部から踵骨の一部と共に下腿三頭筋を採取し,腓腹筋の筋腹が付着するAT線維束とヒラメ筋の筋腹が付着するAT線維束(以下,Sol)を分離し,腓腹筋内側頭が付着するAT線維束(以下,MG)と外側頭の筋腹が付着するAT線維束(以下,LG)とに分離した。そして,各腱線維束の踵骨付着部の配列を分析して3つの捻れのタイプに分類し,各線維束を3-4mm程度にまで細かく分離を行った(MG:4~9線維,LG:3~9線維,Sol:10~14線維)。次に,下腿三頭筋を台上に動かないように十分に固定し,Microscribe装置(G2X-SYS,Revware社)を使用して,各腱線維の筋腱移行部と踵骨隆起付着部の2点,踵骨隆起の外側の4点をデジタイズして3次元構築した。最後に,任意に規定した踵骨隆起の回転中心を基準に作成した絶対座標系上で踵骨を回内(20°)・回外(20°)方向に動かした際の各腱線維の伸張度(%)をシミュレーションして算出した。解析には,SCILAB-5.5.0を使用した。統計学的検討は,Microscribe装置測定の検者内信頼性については,級内相関係数(ICC;1,1)を用いて行った。【結果】級内相関係数(ICC;1,1)は,0.98であり高い信頼性・再現性が確認できた。タイプ毎の伸張度(%)は,タイプIでは,回内(MG:-1.6±0.9%,LG:-2.2±0.2%,Sol:1.7±3.4%),回外(MG:1.3±0.7%,LG:2.0±0.3%,Sol:-1.4±3.3%),タイプIIでは,回内(MG:-1.2±0.7%,LG:-0.4±0.6%,Sol:2.4±1.4%),回外(MG:0.8±0.7%,LG:0.4±0.5%,Sol:-3.2±1.5%),タイプIIIでは回内(MG:-1.7±0.4%,LG:-0.4±1.4%,Sol:3.7±6.0%),回外(MG:1.3±0.4%,LG:0.4±1.3%,Sol:-5.4±6.2%)であった。【考察】AT障害の発生メカニズムとして,踵骨の回内時にAT内の歪みが不均一であることが要因として報告されている。また,好発部位は,踵骨隆起から近位2-6cmであり,外側よりも内側に多いことが報告されている。今回,踵骨を回内すると3つの捻れのタイプ全てにおいて,MG・LGは短縮し,Solは伸張された。特にタイプIII(重度の捻れ)では,回内時のSolの伸張度が他のタイプに比べて最も大きく,更にSolを構成する各腱線維の伸張度のばらつきが多い結果であった。従って,タイプIII(重度の捻れ)では,踵骨回内時には,ATを構成するMG,LG,Solの伸張度が異なるだけでなく,他のタイプに比べてSolの伸張度が大きく,更にSolを構成する各腱線維の伸張度も異なるため,AT障害の発生リスクが高まる可能性が示唆された。【理学療法学研究としての意義】AT障害は,重症化するケースは少ないが再発率が高く,管理の難しい疾患の一つとされている。近年,有効な治療法はいくつか報告されているが,予防法に関しては有効なものが存在していない。その原因として,発生メカニズムが十分に解明されていないことが懸念されている。本研究結果は,AT障害の発生メカニズムの解明に繋がり,有効な予防法や治療法の考案,更には捻れ構造の機能解明に繋がると考える。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ものづくり (ISSN:13492772)
- 巻号頁・発行日
- no.777, pp.50-52, 2019-06
エレクトロンは最新テクノロジーを集めて開発しており、炭素繊維強化樹脂(CFRP)製の機体構造を採用して軽量化。電動ポンプを使ってガス配管をなくすなど、機体の信頼性を高めている。 スペースXやブルーオリジンとは異なり、機体の回収・再利用によるコス…
1 0 0 0 OA 初等代数学教科書
- 著者
- 蘆野敬三郎, 坂田忠次郎 編
- 出版者
- 内田老鶴圃
- 巻号頁・発行日
- 1897
1 0 0 0 OA シャンプーに混入したPseudomonadとその防腐に関する研究
- 著者
- 安福 正憲 橋本 浩明 浜井 順三 上杉 与八
- 出版者
- THE SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTS OF JAPAN
- 雑誌
- 日本化粧品技術者連合会会報 (ISSN:1884412X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.100-105, 1969-03-01 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 12
It has been confirmed that Pseudomonas is dominant contaminant in commercial shampoo and shows an important role in initial product spoilage due to microbial activity. And then, bactericidal activity of several preservatives used in cosmetics has been tested in model shampoo using practical aging test.1) Sixty two per cent of isolated bacteria from commercial shampoos were identified as Pseudomonas species. The rest was unidentified gram-negative rods (21%) and gram-positive rods (17%), 2) Many of the Pseudomonas strains from shampoo could assimilate sodium lauryl sulphate as sulphur source and some of them could produce alkylsulphatase.3) In bactericidal activity of preservatives tested for isolated bacteria, Vancide 89 and nitrofran derivative showed pretty effect but carbanilide, bisphenol, salcylanilide and benzoate derivative showed less effect.4) Contamination by alkylsulphatase positive Pseudomonas into commercial shampoo contained alkylsulphate is an inherent problem. It is essential for us to take the practical aging test in using alkylsulphatase positive strain of Pseudomonas in order the effective bactericidal preservative may be selective.
1 0 0 0 IR 久布白落実の研究 : 廃娼運動とその周辺
- 著者
- 嶺山 敦子 Atsuko Mineyama
- 出版者
- 関西学院大学
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 OA 大島鎌吉のスポーツ思想に学ぶ(5) 理念「オリンピズム」の探究という視点において
- 著者
- 伴 義孝
- 出版者
- 人体科学会
- 雑誌
- 人体科学 (ISSN:09182489)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.23, 2018 (Released:2018-12-01)
- 参考文献数
- 40
オリンピズムは近代オリンピックの復活を提唱したクーベルタンの造語である。造語は1962年の大島邦訳書『ピエール ド クベルタン オリンピックの回想』によれば「オリンピック主義」と直訳されている。他方で2015年版の『オリンピック憲章』は今日的なオ リンピズムの解釈として二つの基本的な指標を提示している。ひとつは「肉体と意志と精神」のすべてにおいてバランスのよい結合を目ざす「生き方の哲学」であって、他は「スポーツを文化と教育へ融合させる」ために「生き方の創造」を探求するものである。ところで1936年のクーベルタンは「私のオリンピズムは、まだ、任務の半分を象徴しているのにすぎない」と書き遺している。本稿では、クーベルタンのその最後の希望に焦点を当てて、 またジャーナリストとしての大島鎌吉が関与してきた日本におけるオリンピック運動を点検することにおいて、オリンピック運動の理念「オリンピズム」における核心的な課題について検討してみる。
- 著者
- 木内 正人
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.239-246, 2017
Today, information dissemination using Web media is common. The information I personally sent was approved as a UNESCO "Memory of the World" on October 10, 2015. Personal information diffused through new media called web media and integrated with existing media such as print media and broadcasting media was uniquely developed based on the keyword "empathy."
1 0 0 0 幽霊問答 : 天下三傑
- 著者
- 大石 雄爾
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.4-9, 2008
Since the 1980s, the Japanese Gini index, both that of before income redistribution and after, has been steadily increasing and the gap between rich and poor has widened. Recently the index reached the level of 0.5 and now stands at 0.526. The index of Japan classified it as a country with high inequality, along with the USA. The last several years has seen an increase of the profit in the listed companies contributing to a personal income for high level managers and stockholders. On the other hand, there has been a dramatic increase in the number of households we class as working poor and a continual increase in the aged poor. The rise in the working poor could be seen as the core of the problem. Business bodies have actively urged the separate companies to adopt a more flexible employment method where workers are hired as non-regular employees. More than 70% of these non-regular employees work full-time hours. A recent trend of the past several years has seen regular employees replaced by non-regular workers. Because more women tend to work as non-regular employees, they are more likely to be affected by this recent trend. Another big change is that wage conditions are now determined by worker performance. In these situations, regular workers are forced to do more unpaid overtime. Because of longer working hours, the number of workers with mental disorders, the phenomena of "death-by-overworking" and work-related suicide has increased and remains high. Also the highest income tax rate has been lowered with little change in the rates of tax for lower income levels. The introduction of a consumption tax has become a bigger burden on low-income employees. As a result, income redistribution has become ineffective. The level of income to recipients of Social Security payment in Japan is amongst the lowest of OECD nations. There are many working poor who can't be on welfare because of a reluctance of social insurance agencies to help them and the poverty problem is getting serious among aged people. After World War II, Japan established its social regime as a state-monopolistic capitalist system, under which the impressive high economic growth was accomplished. However, as a result of the rapid rise of the productive powers, the intrinsic contradiction of the regime burst into a phenomenon known as stagflation. Gigantic corporations in the developed countries began at first to head overseas to the developing countries. And as a whole, they created the economic structure known as global capitalism. In that process, 'Neo-libertarian Policies' were introduced one after another by the Japanese government. Business bodies in Japan, cooperating with the government, pushed forward with the deregulation of the labor law system, which divided workers into regular employees and non-regular employees. This enabled the extension of disparities in income between these groups. In order to resolve this poverty problem, it is required to stop the increase in the number of poor workers. First of all each company should increase the number of its regular employees rather than the number of non-regular employees. On the other hand the government's role is to review the structure of the labor market. In order to promote such 're-reform', organized labor itself should try to reorganize and strengthen its labor union movement. Secondly, the government should review the Social Securities system and the tax system, which have now little income redistribution effect and rearrange the structure of the welfare-state. Various types of policies introduced for resolving the gap in income would create a substantial amount of effective demand for the companies manufacturing products for Japanese consumers. This expansion of demand should surely promote better business conditions.
1 0 0 0 日本の大学生のSNS利用と学業成績との関連性について
- 著者
- 長 広美 柳瀬 公
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.191-206, 2020
<p>本研究は,先行研究から見えた調査上の課題点を踏まえ精度の高いSNS利用状況を把握すること,各SNS利用の代替・補完性について明らかにすること,そして,SNS利用が学業成績に及ぼす影響について体系的に解明することを目的とした。SNS利用時間の測定では,調査票調査や日記式調査にみられる自己申告によるものでなく,調査対象者の大学生(<i>N</i>=153)が所持しているスマートフォンのバッテリー使用状況を用いて収集した。学業成績の測定についても,先行研究の多くが採用している自己申告GPAではなく,専門科目の学期末試験の得点を用いた。</p><p>分析の結果,LINEとInstagram,TwitterとYouTubeとの間にそれぞれ補完的な利用関係があることが明らかになった。学業成績には,LINE,Twitter,YouTubeの利用が負の影響を与えていた。つまり,これらのSNSの利用時間が増えるほど学業成績が悪くなることが示唆された。本研究結果は,SNS利用によって注意力が散漫になったり,SNSに費やす時間が学習の時間を減少させ,結果として学業成績の低下につながるという先行研究結果と整合性があるものであった。本研究では,SNS利用と学業成績との関連性の議論に実証的根拠を示すことができたとともに,当研究領域における現代社会のSNS利用行動の複雑さを解明する一つの可能性を見出した。</p>
- 著者
- 中澤 信彦
- 出版者
- 関西大学経済・政治研究所
- 雑誌
- セミナー年報 (ISSN:18822010)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.113-124, 2007
第176回公開講座
- 著者
- Guo Yu Sakurai Makoto Kameyama Hideo MATSUYAMA AKIRA KUDOH YASUSHI
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- Journal of chemical engineering of Japan (ISSN:00219592)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.12, pp.1470-1479, 2003-12-01
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 16 41
A novel metallic monolith support was prepared by anodization, HWT (hot water treatment) and calcination. A commercial aluminum plate was anodized to form porous alumina films in the outer surfaces of the aluminum plate. In contrast to the anhydrous and amorphous alumina formed after anodization, the alumina in the anodized film with HWT was boehmite. The calcination after HWT made the boehmite film lose its hydrate water and rearrange into <I>γ</I>-alumina. The HWT and calcination significantly enhanced the surface area of the support due to the formation of numerous micropores (radius <25 Å). These new micropores were superimposed on the original skeleton structure to make up a binary-pore structure.<BR>The activities of Cu-Mn-CeO<SUB>x</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al and Pt/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al alumite catalysts for the SCR-HC of NO by propene were investigated under oxygen-rich conditions. At low temperatures, Pt/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al exhibited a higher activity for NO<SUB>x</SUB> removal than Cu-Mn-CeO<SUB>x</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al. However, a higher temperature (>623 K) made the activity of Pt/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al inferior to that of Cu-Mn-CeO<SUB>x</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al. In comparison with Pt/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al, Cu-Mn-CeO<SUB>x</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al had a lower N<SUB>2</SUB>O selectivity throughout the whole temperature range. The addition of SO<SUB>2</SUB> inhibited the activity of Pt/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al, and this activity decay was reversible. On the other hand, a dramatic promotional effect of SO<SUB>2</SUB> on reducing NO<SUB>x</SUB> was observed over Cu-Mn-CeO<SUB>x</SUB>/Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>/Al, but this influence of SO<SUB>2</SUB> on the activity was irreversible.