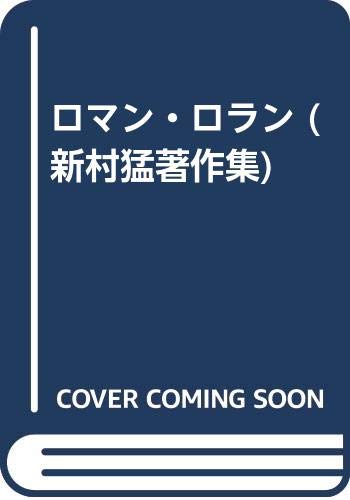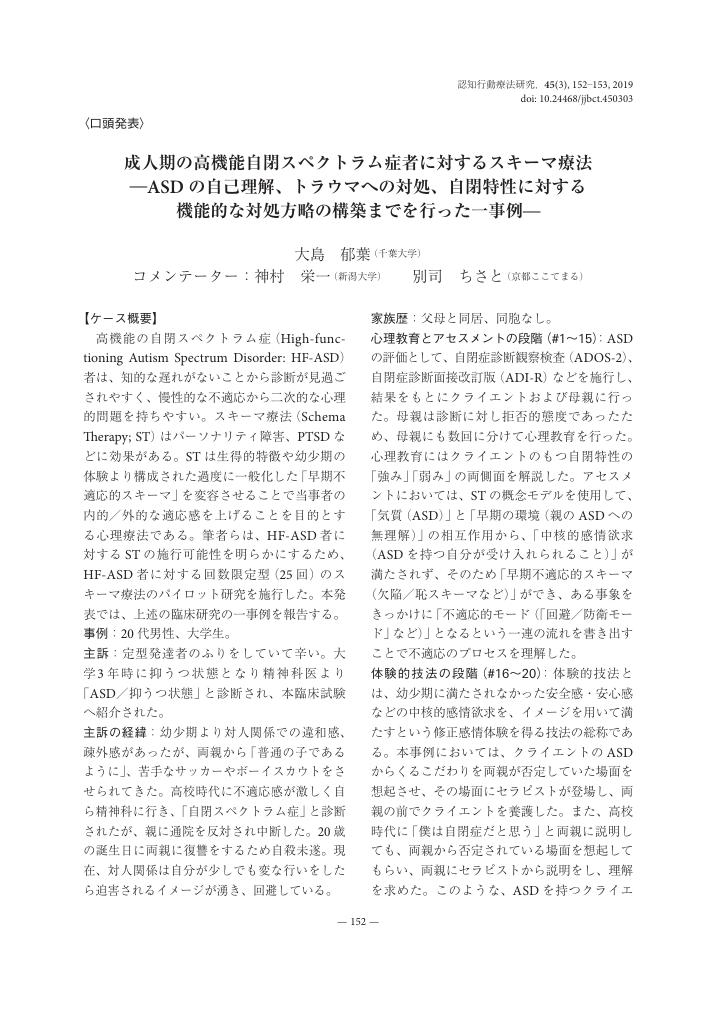1 0 0 0 ヨーロッパ文明との対話
1 0 0 0 SOX2発現の人為的抑制がブタ初期胚の発生におよぼす影響
<p>【目的】哺乳動物の初期胚は,桑実期から胚盤胞(BC)期にかけて,内部細胞塊(ICM)と栄養膜細胞(TE)への分化が起こる。SOX2はICM分化に重要な役割を担うと考えられているが,ブタ初期胚におけるSOX2発現動態と胚発生への役割については明らかではない。本研究では,ブタ胚におけるSOX2発現動態とその発現抑制が初期胚発生におよぼす影響について検討した。【方法】ブタIVM卵子および1-細胞期からBC期における<i>SOX2</i> mRNA発現量およびSOX2タンパク質の発現を解析した。次に,ブタ1-細胞期胚にSOX2発現抑制用siRNAを注入する区(SOX2 siRNA 区),Control siRNAを注入する区(Control siRNA 区),siRNAを注入しない区(無処理区)を設け,BC期までの発生率を調べ,BC期での<i>TEAD4</i>および<i>OCT-4</i> mRNA発現量を解析した。また,それら BC期胚の総細胞数およびSOX2発現陽性細胞率を調べた。【結果および考察】<i>SOX2 </i>mRNA発現量は,IVM卵子,1-細胞期,桑実期,BC期に比べ,8-~16-細胞期で有意(<i>P</i> < 0.05)に高い値を示した。SOX2タンパク質は8-細胞期以降の細胞核で発現が認められ,BC期胚においては,ICMと思われる部位に局在が認められた。Control siRNA区およびSOX2 siRNA区の4-細胞期以上への発生率は,無処理区と比較して有意(<i>P </i>< 0.05)に低い値を示したが,BC期への発生率は各処理区間に差は認められなかった。<i>TEAD4</i>および<i>OCT-4</i>発現量は,各処理区間に差は認められなかった。BC期での総細胞数およびSOX2発現陽性細胞率は無処理区に比べ,SOX2 siRNA区で有意(<i>P </i>< 0.05)に低い値を示した。SOX2 siRNA区においてはBC期ICMへのSOX2局在化が認められなかった。本結果より,SOX2はブタ初期胚におけるICM形成に関与する可能性が示された。</p>
- 著者
- 大島 郁葉
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.152-153, 2019-09-30 (Released:2020-06-25)
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.361, pp.40-45, 2004-10-08
●● 森永さんは,公共事業が日本の経済や財政に与える影響について,いろいろと発言されています。まず,社会資本整備が日本経済に与えてきた影響について,どうみていますか。森永 公共事業はダムや橋などの社会資本を造るというだけでなく,都市部から地方部に所得を移転するという側面も持っています。
- 巻号頁・発行日
- 1945
- 巻号頁・発行日
- 1945
1 0 0 0 IR 史的イエスとケーリュグマ――学問的構成と信仰への道
- 著者
- 須藤 伊知郎
- 出版者
- 西南学院大学学術研究所
- 雑誌
- 西南学院大学神学論集 (ISSN:03874109)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.199-238, 2014-09-01
親愛なる神学部長の片山さん、親愛なる同僚、学生の皆さん、そしてここにお集りの皆さん、親しくお招きを頂きまして大変有り難うございます。好意的なご紹介を頂き、心から感謝いたします。実は何とおっしゃっているか分からなかったのですけれども(笑)。そしてこの西南学院大学で講演をする機会を頂き、本当に有り難うございます。これは新約聖書神学の中心的なテーマについての講演です。すなわち、史的イエスとケーリュグマの関係、つまり、初期キリスト教のイエス・キリストについてのメッセージおよび史的な研究と信仰の関係がテーマです。キリスト者にとってイエスははるかに単なる人間以上のものです。しかし何がこの〔単なる人間以上の〕「余剰価値」なのでしょうか?どのようにして、最初のキリスト者たちは彼をそれほど〔単なる人間〕より以上のものであると看做すことが可能になったのでしょうか?どのようにして私たちは、史的イエスからケーリュグマ〔宣教〕の神の子への移行を理解することができるでしょうか?これは一つの史的な問いでもあり、また一つの神学的な問いでもあります。すなわち、史的な問いによって私たちは史的現実と触れ合うことを期待し、神学的な問いによって神と触れ合うことを期待するのです。いずれの場合も接近の仕方は、私たちがその問いに〔向かう時に最初から〕持ち込む姿勢に左右されます。私たちは自分たちの資料が、史的方法の助けを借りて読めば、史的現実への道を拓いてくれる、と信じているはずです―― 資料の向こう側に歴史を認識することが果たしてできるのかというポストモダンの懐疑があるにもかかわらず。同じように、私たちは一つの宗教的な姿勢が(たとえ私たちにとってそれが科学的な方法のようには自由にならないとしても)神的な現実との触れ合いを可能にする、と信じているはずです―― 神は人間の想像の産物かもしれないという現代の宗教批判と懐疑があるにもかかわらず。現代神学の一つの決定的な問題は疑いなく、現実に対する史的(あるいは経験的)な接近の道から神学的な接近の道への移行です。この移行は私の見るところでは、私たちの姿勢と認知的な枠組みにおける一つの変化にかかっています。しかしそもそも、私たちがイエスを史的に見る場合と彼を神学的に解釈する場合とでは、何が変わるのでしょうか?これが私たちの問題です。史的・批判的な方法論は、一方で私たちが一次資料の助けを借りて答える一連の問いと、他方で〔それらに対して〕可能な答えの〔解釈をする〕ための一連のカテゴリーで構成されています。イエス研究の中では、最近30年の間に一つの方法論の転換が起りました。1950年代に始まった研究は、真正な、イエスに遡る素材を発見する手段として「差異の基準」〔criterion of dissimilarity〕を用いて作業を遂行しました。〔そこで立てられた〕問いは、イエスが一方でユダヤ教と他方で初期キリスト教と違っているのはどの点なのか、どの伝承がユダヤ教においても初期キリスト教においても類を見ないものなのか、というものでした。類例のない伝承は史的〔に真正である〕と判断され、一貫性の基準〔criterion of coherence〕の助けを借りて補われました。この基準は、類例のないイエス伝承と調和している他のすべての伝承を史的であると看做すものでした。その結果〔史的と判断されて残ったもの〕は、比類の無い啓示の主張という観点で解釈されました。この方法によれば、史的な姿勢から神学的な姿勢への移行は問題とはなりませんでした。史的な接近方法〔自体〕がすでに〔史的な類例の有無を問うたわけですから〕、歴史を超越していると思われる伝承に焦点を当てていたのです。しかし時が経つにつれて、差異の基準は史的蓋然性の基準に取って代わられました。イエスは今やユダヤ教の歴史の枠内で、そして初期キリスト教の出発点として解釈されます。私たちが今や問うのは、何がユダヤ教の文脈における個別的な現象として理解できるものなのか(すなわち、文脈上の蓋然性〔contex-tual plausibility〕)、そして何が初期キリスト教の成立と史的イエスについての資料の多様性を説明できるものなのか(すなわち、影響史的蓋然性〔effec-tive plausibility〕)、ということです。私たちがここで探しているのは、初期キリスト教の全般的な傾向に反する孤立したモティーフに加えて、初期キリスト教のイエス伝承の様々な流れに繰り返し現れるモティーフです。史的蓋然性の二つの観点―― 一方でユダヤ教の中での文脈上の蓋然性と、他方で初期キリスト教の中での影響史的蓋然性―― は原則として独立しています。この方法論〔を採用すること〕によって私たちは、初めから人間としてのイエスに史的に接近する道を優先させます。すなわち、ユダヤ教の歴史に合わないものは、真正ではあり得ません。逆に、この〔ユダヤ教の〕歴史に合うものだけが、史的イエスに帰されることができます。イエスはユダヤ教の歴史の産物であり、同時に初期キリスト教の(必ずしも唯一のではないにせよ)一つの起源であるはずなのです。史的イエスから初期キリスト教のケーリュグマへの移行を分析する際、私たちはまず史的な問いに取り組みます。すなわち、何をイエスは自分自身について語ったのか、何を最初のキリスト者たちは彼について語ったのか、なぜ彼(女)らは、イエスが自分自身についてそもそも語ったであろうことよりはるかに多くのことを彼について語っているのか、ということです。私たちはイエスの神性についての発言を理解しようと試みているにもかかわらず、これらは史的な問いであって神学的な問いではありません。しかし、これらの史的な問題と取り組む中で、私たちは繰り返し神学的な問題に出くわすでしょう。それはすなわち、何を他の人々がかつてイエスと神について考えていたかということだけでなく、何が今日イエスと神について妥当するのかということも問う、ということです。講演の終わりに、私はこの史的な接近方法から神学的な接近方法への移行について直接考察するつもりです。私は認知宗教学に基づいて、この移行を進める一つの試みをスケッチするつもりです。これは、宗教に対する非常に世俗的な、そして非宗教的ですらあるアプローチではありますが、私たちが歴史から信仰への移行を理解することを助けてくれるでしょう。
1 0 0 0 OBITUARY Mark Blaug (1927-2011)
- 著者
- 原谷 直樹
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.122-124, 2015
1 0 0 0 OA 戦前の四日市都市計画に関する研究ノート
- 著者
- 波多野 憲男
- 出版者
- 四日市大学
- 雑誌
- 四日市大学環境情報論集 (ISSN:13444883)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.135-157, 1999-09-30 (Released:2019-12-01)
The purpose of this study is to find and investigate the urban planning in the past, which led to the formation of Yokkaichi City. I think the following three plans are important. The first is a city-planning map 1941. The second is a master plan of the war rehabilitation land readjustment project. The third is a conception picture of the Yokkaichi general development plan 1960. I investigate into the city-planning map 1941 in this paper. This map was made by Mie Local City Planning Commission. According this plan, the southern part of Yokkaichi central urban district was developed as industrial district, and Yokkaichi station of Kansai Express Railway was transferred to where present Kintetsu Yokkaichi Station is located. This map played an important part to develop Yokkaichi City as an industrial-city, just like a master plan of those days. That was the first time Yokkaichi City had something like a master plan for the development of the city.
1 0 0 0 対州層群の形成年代と堆積環境
- 著者
- 二宮 祟 市原 季彦 谷口 翔 下山 正一 宮田 雄一郎 ダニエル ダンクレイ 松田 博貴 山中 寿朗 青木 隆弘 西田 民雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.132, 2009
1 0 0 0 新第三系対州層群の堆積環境
- 著者
- 二宮 崇 市原 季彦 谷口 翔 下山 正一 宮田 雄一? ダンクレイ ダニエル 松田 博貴 山中 寿朗 青木 隆弘 西田 民雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.131, 2010
1 0 0 0 OA 「動く襖絵」に内在する錯視のメカニズム
- 著者
- 山田 憲政
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.107-112, 2005-06-01
"Moving pictures on sliding doors" date back to the Edo Era in Japan. These pictures were called moving pictures because they seem to move when they are viewed while moving. The aim of this study was to determine the mechanism underlying this illusionary phenomenon. For that purpose, photographs of a "moving picture" on sliding doors were taken using a digital camera, and the characteristic points on each image were digitized and stored in a computer. Then changes in perception of the picture with movement of the viewpoint of the observer were computed by using a coordination transformation technique. The results of calculation revealed that the picture had been painted from a bird's-eye view and that the illusionary motion is seen when the observer views the picture from an oblique angle while moving along the length of the sliding doors. When viewing the picture from an oblique angle while moving, distances from points on the picture to the observer's viewpoint change, and these changes in distances give rise to the illusionary motion of the picture. Thus, the mechanism by which the picture is perceived as moving is motion parallax.
1 0 0 0 OA 豊臣秀吉を日本国王に封ずる誥命について : わが国に現存する明代の誥勅
- 著者
- 大庭 脩
- 出版者
- 関西大学東西学術研究所
- 雑誌
- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.29-77, 1971-03-30
- 著者
- 山城 晶弘 神谷 直紀 大塚 薫 駒津 和浩 伊東 洋一 久保田 展聡 小林 正人
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.163-169, 2013-02-20 (Released:2013-03-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
In magnetic resonance imaging (MRI), the ideal phantom should have similar T1 and T2 values to those of organs of interest for measuring the change in signal intensity, contrast ratio and contrast noise ratio. There have been several reports to develop such a phantom using materials with limited availability or complex methods. In this study, we have developed a simple phantom using indigestible dextrin and soluble calcium at 1.5-tesla MRI. The T1 and T2 values have been reduced by dissolving indigestible dextrin and soluble calcium in distilled water. The similar T1 and T2 values to those of organs (i.e., kidney cortex, kidney medulla, liver, spleen, pancreas, bone marrow, uterus myometrium, uterus endometrium, uterus cervix, prostate, brain white matter, and brain gray matter) have been obtained by varying the concentration of indigestible dextrin and soluble calcium. This phantom is easy to develop and has a potential to increase the accuracy of MRI phantom experiments.
- 著者
- Minoru Murayama Sumiko Yamamoto
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- Progress in Rehabilitation Medicine (ISSN:24321354)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.20200021, 2020 (Released:2020-09-11)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 6
Objective: Previous studies have suggested that the use of an ankle–foot orthosis may cause disuse atrophy of the tibialis anterior muscle. The objective of this study was to explore gait and muscle activity changes in patients in the recovery phase of stroke with 2-month use of an ankle–foot orthosis that provided plantarflexion resistance.Methods: The participants were 19 patients in the recovery phase of stroke who were prescribed an ankle–foot orthosis that provided plantarflexion resistance. We measured ankle and shank tilt angles as well as electromyography activity of the tibialis anterior and the soleus during 10-m walk tests. Measurements were taken on three occasions. The first was 2 weeks after delivery of the orthosis, 1 and 2 months after the initial measurement, and the third 2 months later. Changes in gait parameters were analyzed between the first and second measurements and between the second and third measurements.Results: Between the second and third measurements, significant increases were observed in plantarflexion and shank forward tilt angles and the activity ratio of the tibialis anterior during loading response compared with other phases.Conclusions: Plantarflexion movement induced by an ankle–foot orthosis with plantarflexion resistance could increase the activity ratio of the tibialis anterior during loading response.
1 0 0 0 OA インターネットコミュニケーションにおける非言語情報
- 著者
- 増田 桂子
- 出版者
- 中央大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文研紀要 (ISSN:02873877)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.283-300, 2014-09-16
コミュニケーションにおいては,話し手がメッセージを伝える際に,言語そのもの以外の情報が非常に重要な役割を果たしている。対面コミュニケーションにおいては,これらの非言語情報は相手の声や表情,動きなどから読み取ることができる。しかしながら,近年急速に増えてきた,PC やスマートフォン等のデジタル機器を用いたインターネット上のコミュニケーションにおいては,相手の姿は見えず声も聞こえない。このような状況でコミュニケーションを円滑に進めるために,非言語情報を文字化して表記するという方策がとられている。声量や声質,話し方といった非言語的音声は,長音府やかな文字を非標準的な方法で組み合わせるなどして表現され,顔の表情,身体の動作といった視覚的情報は,文字や記号を組み合わせて並べ,表情や動作を図形化することで表現されている。
1 0 0 0 OA ランボー作品における花のエクリチュール : 花について詩人が「語った」こと
- 著者
- 田島 義士
- 出版者
- 関西大学フランス語フランス文学会
- 雑誌
- 仏語仏文学 (ISSN:02880067)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.181-206, 2011-03-15
伊藤誠宏教授退職記念号
1 0 0 0 OA 3Dプリント連続炭素繊維強化熱可塑複合材料の引張試験特性
- 著者
- 轟 章 大浅田 樹 水谷 義弘 鈴木 良郎 上田 政人 松崎 亮介 平野 義鎭
- 出版者
- 一般社団法人 日本複合材料学会
- 雑誌
- 日本複合材料学会誌 (ISSN:03852563)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.141-148, 2019-07-15 (Released:2020-07-29)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
Continuous carbon fiber composites can be printed with 3D printers. Many studies detailing elucidations of the mechanical properties of such 3D printed composites have been published, all of which employed a conventional tensile specimen configuration with surface resin layers. In the present study, 0º, 90º, ±45º, and lay-up direction type specimens were newly designed for 3D printed composites without surface layers. Using the 3D printer, both conventional and newly designed specimens with serpentine folded fiber bundles were fabricated and investigated experimentally. The lay-up direction specimen was fabricated using 800 layers. The specimens without the serpentine folded fiber bundles were experimentally shown to be adequate for tensile tests. The lay-up direction specimen had the lowest strength and stiffness, which seems to be related to its surface roughness.