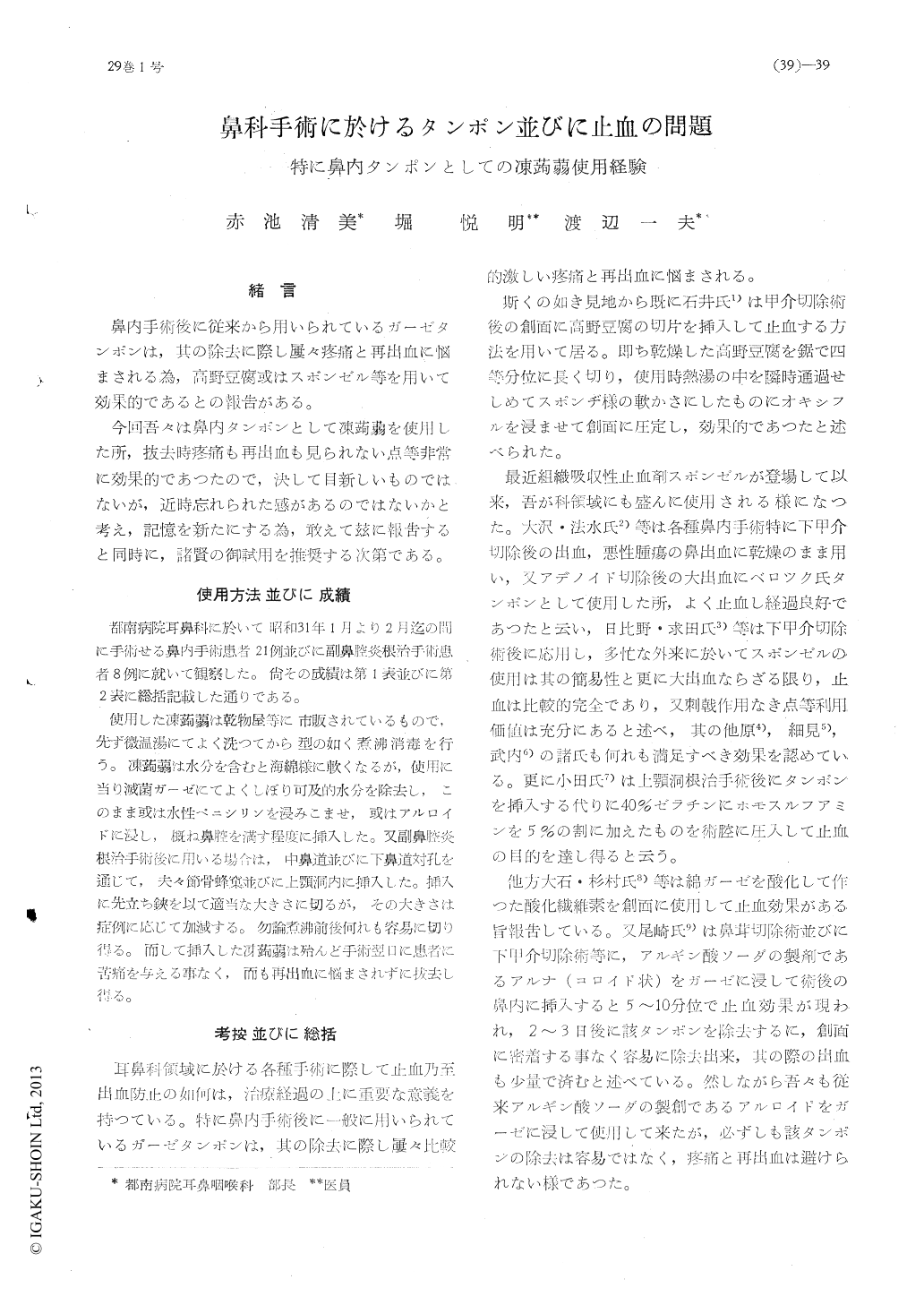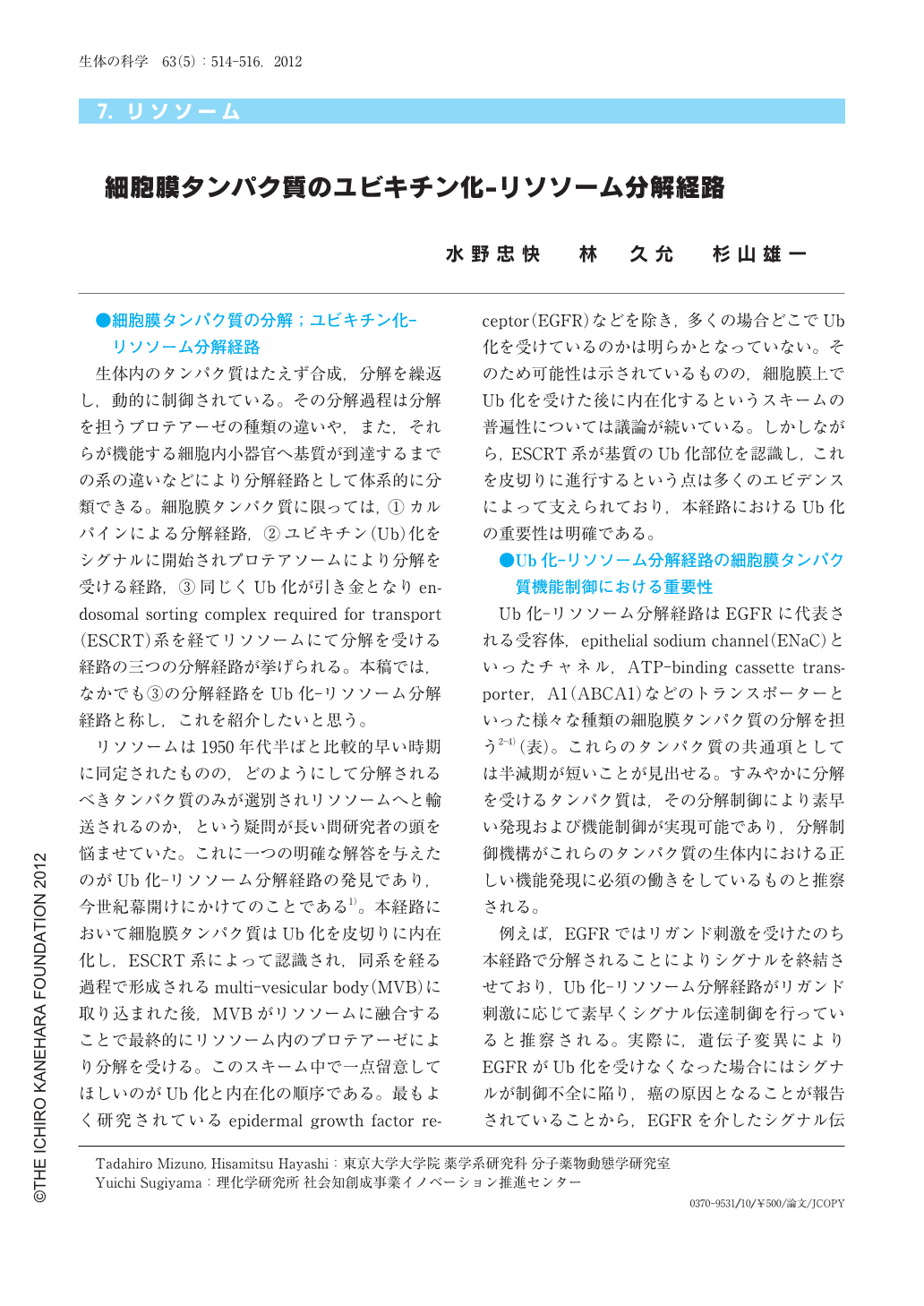- 著者
- Yoichi MIURA Yume SUZUKI Hideki KANAMARU Masato SHIBA Ryuta YASUDA Naoki TOMA Hidenori SUZUKI
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.oa.2020-0430, (Released:2021-06-01)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 7
The present study was conducted to investigate whether non-fasting serum triglyceride (TG) levels can be used to assess a risk for the progression of carotid artery stenosis. This was a single-center retrospective study. Consecutive 96 patients with ≥50% stenosis of at least unilateral cervical internal carotid artery and normal fasting serum low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels of ≤140 mg/dL were followed up for at least 1 year (mean, 3.1 years), and clinical variables were compared between patients with and without carotid stenosis progression (≥10% increases in the degree on ultrasonography). Carotid stenosis progression was shown in 21 patients, associated with less frequent treatment with calcium channel blockers (CCBs), higher non-fasting TG and glucose levels. In carotid artery-based analyses including <50% stenosis side, stenosis progression was shown in 23 of 121 arteries except for those with complete occlusion and less than 1-year follow-up period because of carotid artery stenting (CAS) or carotid endarterectomy (CEA). Stenosis progression was more frequently observed in symptomatic and/or radiation-induced lesions, and was also accompanied with less frequent treatment with CCBs, higher non-fasting TG and glucose levels in carotid artery-based analyses. The receiver operating characteristic (ROC) curve analyses revealed that a cutoff value of non-fasting TG to discriminate carotid stenosis progression was 169.5 mg/dL for carotid arteries with the baseline stenosis of <50%, and 154.5mg/dL for those of ≥50%. Non-fasting TG level was an independent risk factor of carotid stenosis progression, and more strict control of non-fasting TG may be necessary for higher degree of carotid artery stenosis.
1 0 0 0 OA 私は脳のどこにいるのか?
- 著者
- 澤口 俊之
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.298, 2000-04-20 (Released:2017-06-02)
- 著者
- 三宅 啓 福本 弘二 福澤 宏明 渡辺 健太郎 光永 眞貴 草深 純一 青葉 剛史 矢本 真也 漆原 直人
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会
- 雑誌
- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.392, 2012-05-01 (Released:2017-01-01)
1 0 0 0 OA 蓖麻子毒性蛋白リシンの化学的研究(第1報) リシンの分離法の検討
- 著者
- 船津 勝 船津 軍喜
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.6, pp.461-464, 1959 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
(1) Ricinus communis L.とRicinus sanguineus L.の2種類の箆麻子種実から結晶リシンとリシンTbとの分離を試みたが,結晶は後者から容易に得られた.この事から箆麻子の種類によりリシンの含量が異なる事を推察した. (2)結晶とTbとにつきプロテアーゼ作用と血球凝集作用とを比較した結果,両作用共Tbの方が結晶より強く,毒性とプロテアーゼ作用とは必ずしも並行していない事を確めた. (3)更に結晶リシンのプロテアーゼ作用は不純物である可能性を残しており,プロテアーゼ即リシンの考え方を再検討する必要がある事を認めた.
1 0 0 0 OA 高知県中央部の「わんぱーくこうち」におけるアリ相
- 著者
- 辻 雄介 近藤 英文
- 出版者
- 特定非営利活動法人 四国自然史科学研究センター
- 雑誌
- 四国自然史科学研究 (ISSN:13494945)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.74-82, 2021 (Released:2021-06-01)
- 参考文献数
- 26
Ant fauna was surveyed in a municipal comprehensive park, ”WANPARK KOCHI” from July to October 2020. As a result, 27 species of ants from 4 families, include 1 endangered species and 7 introduced species were collected.
1 0 0 0 OA サイバー犯罪に関する国際的対応と情報刑法の体系化
情報通信技術の進展は,めぐるましく,クラウドコンピューティングがその主流となりつつある。また,今後「モノ」のインターネットが情報通信技術の中心へとなることが予想される。こうした状況にあっては,現在の情報の保護に関して,情報の化体した媒体を財物として解釈し,その保護を図っていくという保護のあり方は,弥縫策としての限界を露呈している。こうした状況を打破するには,情報の化体する媒体という財物概念を放棄し,情報それ自体の管理・支配の侵害を直接処罰する刑事立法が必要といえる。また,児童ポルノの刑事規制は,その保護法益の理解に問題があり,児童の権利・自由を直接保護するものに改められるべきである。
1 0 0 0 OA Changes in ionized calcium concentration in the blood of dairy cows with peracute coliform mastitis
- 著者
- Keiichi HISAEDA Tomoko KOSHIISHI Ayuna SASAKI Yasunori SHINOZUKA Naoki ISOBE Kazuhiro KAWAI
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-0678, (Released:2020-02-26)
- 被引用文献数
- 1 8
We determined the clinical signs and blood ionized calcium (iCa) levels in dairy cows with peracute coliform mastitis (PCM). The clinical scores at the onset of the disease (day 0) and on day 2 and subsequent days were significantly (P<0.01) higher than those of healthy cows. We found a positive correlation (r=0.894, P<0.01) between iCa and total calcium (TCa) concentrations in the blood of healthy cows ; however there was no correlation from day 0 to day 3 in the blood of PCM cows. Multiple regression analysis revealed that the concentration of iCa was correlated with rectal temperature, hematocrit value, platelet count, and albumin level of PCM cows at the onset of disease (r=–0.804, r=0.6576, r=0.6182, r=0.284, P<0.01, respectively). There was no correlation between the TCa concentration and these parameters for PCM cows at day 0. Low blood iCa concentration at day 0 for PCM cows was related to symptoms of septic shock involving hypothermia, activation of the blood coagulation system, and dehydration.
1 0 0 0 OA 地理歴史科教員の実態と地理的知識低下の問題点
- 著者
- 碓井 照子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.10, pp.13-19, 2008-10-01 (Released:2012-02-15)
- 被引用文献数
- 3 3
- 著者
- 青木 美紗
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.87, 2018
<b>目的 </b>倫理的消費は「地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動」と消費者基本計画(2015年)において定義され、持続可能な消費を実践するために求められている。しかし、購買者の多くは倫理的消費について学習する機会がほとんどなく、倫理的消費行動を誘引する環境はそれほど整っていない。そこで、購入時に倫理的消費に関連する情報を継続的に提示することによって、倫理的消費行動をとるのかどうか明らかにすることを本研究の目的とする。<br><b>方法 </b>大阪府東大阪市におけるJA農産物直売所の利用者を対象としたアンケート調査を2017年6月実施し、回収した493のデータをクロス集計と因子分析によって分析した。調査対象とした直売所では、2009年より東大阪市産の環境に配慮して生産した農産物を継続的に購入する消費者には、その農産物を購入する意味を提示し購入特典を提供する取り組みを続けている。データ分析では、この取り組みへの参加者と非参加者の農産物に関する倫理的消費行動を比較した。<br><b>結果 </b>まず、購入する農産物の生産背景、地産地消の認知度は参加者の方が高い結果となった。また、直売所を利用する理由においても、環境に配慮したもの、地元のものが買える、地域の生産者を応援できる、地域の農地を守ることができると回答した人が参加者の方が多かった。そして、因子分析の結果、参加者の方が農産物購入時に環境や地域に配慮していることが明らかとなった。
1 0 0 0 PCS電源のみによる自立系統上での簡易事故シミュレーション
- 著者
- 姉川 高也 石亀 篤司 高山 聡志
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.6, pp.500-501, 2021-06-01 (Released:2021-06-01)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2
The isolated power system (off-grid) using only renewable energy resources (PCS supplies) is studied. On the other hand, the off-grid of the Japanese general transmission and distribution company using only PCS supplies has not been realized. To realize and clarify the safety operation of off-grid, in this paper, we simulated the fault aspect using the simple simulation.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.476, pp.197-200, 2005-02-28
対策の基本は"仕分け"/ 功を奏するか、送信者認証
1 0 0 0 マグナス効果を利用した小型風力発電機の開発
- 著者
- 佐藤 司
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:00214728)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.1076, 2008
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 2.糖尿病で感染症が増えるメカニズム
- 著者
- 嶋崎 鉄兵 本郷 偉元
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.10, pp.666-667, 2018-10-30 (Released:2018-10-30)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 IR 学業失敗場面での次への切り替えという 精神的弾力性の検討 ―性格特性や対処様式を基に―
- 著者
- 川原 誠司 鈴木 美緑 Seishi KAWAHARA Minori SUZUKI
- 出版者
- 宇都宮大学教育学部
- 雑誌
- 宇都宮大学教育学部研究紀要.第1部 = The research bulletin of the Faculty of Education, Utsunomiya University. Section 1 (ISSN:24325546)
- 巻号頁・発行日
- no.70, pp.23-33, 2020-03-25
1 0 0 0 OA 腎細胞癌に対するPDDの応用
- 著者
- 小山 政史 上野 宗久
- 出版者
- 日本泌尿器内視鏡学会
- 雑誌
- Japanese Journal of Endourology (ISSN:21861889)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.23-28, 2011 (Released:2014-02-07)
- 参考文献数
- 20
5-アミノレブリン酸(5-ALA)を用いた術中光力学的診断(PDD)は通常光では視認困難な腫瘍の同定やサージカルマージンの検索に有用である.泌尿器科領域では従来,膀胱癌に対して5-ALAを膀胱内注入してきたが,内服が可能なことより,最近では腎細胞癌に応用され5-ALAの腫瘍特異性が確認されている.また,腹腔鏡下腎部分切除術に5-ALA-PDDを併用することでサージカルマージンの蛍光発色部位に病理組織学的に癌細胞が確認されている.5-ALA-PDDが手術中リアルタイムにサージカルマージン同定に寄与する可能性が示唆された.尚,5-ALAによる有害事象は本稿で紹介した報告では認めていない.
1 0 0 0 IR 近江商人研究と「三方よし」論
- 著者
- 宇佐美 英機
- 出版者
- 滋賀大学経済学部附属史料館
- 雑誌
- 滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要 = Bulletin of Archival Museum, Faculty of Economics, Shiga University (ISSN:02866579)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.31-45, 2015-03
1 0 0 0 OA 小野道風
- 著者
- 中 圭子
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.170, pp.1-18, 1990-03-21 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 細胞膜タンパク質のユビキチン化-リソソーム分解経路
- 著者
- 水野 忠快 林 久允 杉山 雄一
- 出版者
- 金原一郎記念医学医療振興財団
- 巻号頁・発行日
- pp.514-516, 2012-10-15
●細胞膜タンパク質の分解;ユビキチン化-リソソーム分解経路 生体内のタンパク質はたえず合成,分解を繰返し,動的に制御されている。その分解過程は分解を担うプロテアーゼの種類の違いや,また,それらが機能する細胞内小器官へ基質が到達するまでの系の違いなどにより分解経路として体系的に分類できる。細胞膜タンパク質に限っては,① カルパインによる分解経路,② ユビキチン(Ub)化をシグナルに開始されプロテアソームにより分解を受ける経路,③ 同じくUb化が引き金となりendosomal sorting complex required for transport(ESCRT)系を経てリソソームにて分解を受ける経路の三つの分解経路が挙げられる。本稿では,なかでも③の分解経路をUb化-リソソーム分解経路と称し,これを紹介したいと思う。 リソソームは1950年代半ばと比較的早い時期に同定されたものの,どのようにして分解されるべきタンパク質のみが選別されリソソームへと輸送されるのか,という疑問が長い間研究者の頭を悩ませていた。これに一つの明確な解答を与えたのがUb化-リソソーム分解経路の発見であり,今世紀幕開けにかけてのことである1)。本経路において細胞膜タンパク質はUb化を皮切りに内在化し,ESCRT系によって認識され,同系を経る過程で形成されるmulti-vesicular body(MVB)に取り込まれた後,MVBがリソソームに融合することで最終的にリソソーム内のプロテアーゼにより分解を受ける。このスキーム中で一点留意してほしいのがUb化と内在化の順序である。最もよく研究されているepidermal growth factor receptor(EGFR)などを除き,多くの場合どこでUb化を受けているのかは明らかとなっていない。そのため可能性は示されているものの,細胞膜上でUb化を受けた後に内在化するというスキームの普遍性については議論が続いている。しかしながら,ESCRT系が基質のUb化部位を認識し,これを皮切りに進行するという点は多くのエビデンスによって支えられており,本経路におけるUb化の重要性は明確である。