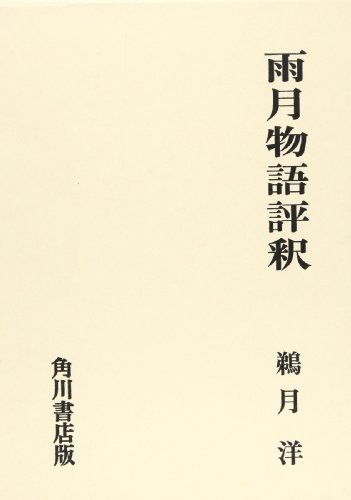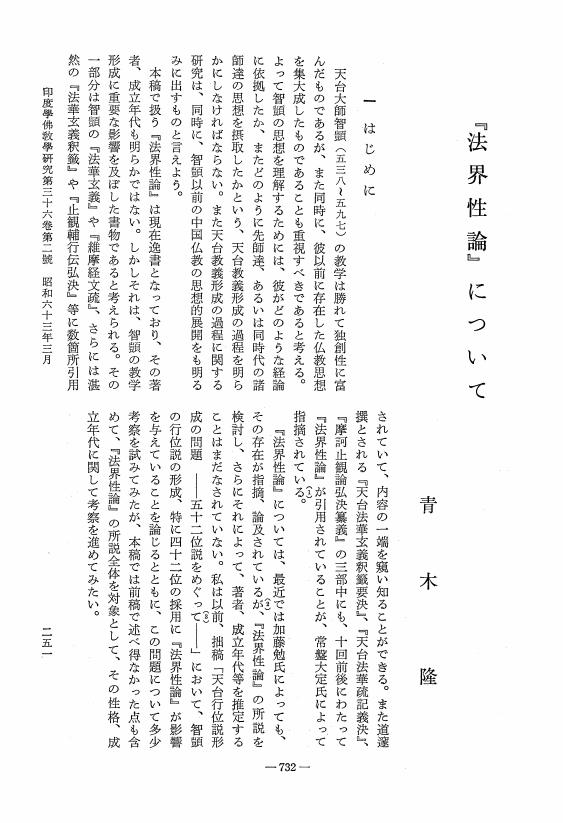- 著者
- von Johannes Ittmann bearbeitet und herausgegeben von E. Kähler-Meyer
- 出版者
- D. Reimer
- 巻号頁・発行日
- 1976
1 0 0 0 Deutsche Kolonialsprachen
- 出版者
- Kraus Reprint
- 巻号頁・発行日
- 1973
- 著者
- 吉村 輝彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.1033-1038, 2011-10-25 (Released:2011-11-01)
- 参考文献数
- 2
近年、まちづくりを進めていく上で、地域の中で、自分たちで意思決定を行い、自分たちで実行できるシステムを作っていくことの重要性が認識されてきている。行政中心の上意下達に基づく「統治(カバメント)」から「共治(ガバナンス)」を目指した多様な主体の重層的な連携、協働と共創によるまちづくりへの展開では、まちづくりの主体やマネジメントの仕組みが転換していく。ここでは、より対話と交流を基盤にしたまちづくりの展開のあり方が問われている。そんな中で、名古屋市の地域委員会制度による地域予算を決めていく取り組みは、対話や熟議に基づくまちづくりの展開やガバナンスの観点から注目される。地域委員会は、地域課題を解決するために、投票で選ばれた委員を中心に公開の場で話し合い、市の予算(税金)の一部の使途(配分)を決める「新しい住民自治の仕組み」として創設された。本研究では、地域委員会制度の実施プロセスの実態を踏まえ、地域委員会という場が、対話や熟議に基づくまちづくりを展開していく上で、どのような意義や課題があるのかについて考察する。
1 0 0 0 江戸町人文学
- 著者
- 水野稔 鵜月洋 [著]
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1958
1 0 0 0 雨月物語 : 附現代語譯
1 0 0 0 広告文の歴史 : キャッチフレーズの100年
1 0 0 0 国文古典物語文学 : 研究と鑑賞
1 0 0 0 雨月物語 : 現代語訳付き
1 0 0 0 OA 『法界性論』について
- 著者
- 青木 隆
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.732-739, 1988-03-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA ウニのエキス成分に関する研究-IV エキス構成々分の呈味性
- 著者
- 小俣 靖
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.9, pp.749-756, 1964-09-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 31 35
To elucidate the taste of “Uni”, the raw unripe gonad of sea-urchin, sensory tests were carried out on test solutions prepared by mixing L-amino acids and other authentic reagents so as to reproduce partly or wholly the natural extracts. The composition and concentration of each constituent were based on the analytical data on Bafun-uni III reported in the previous papers1) ?? 3) (Table 1). The test solution containing all constituents satisfactorily reproduced the original taste of “Uni”, showing that they cover all the essential tasting substances. Teste on the solutions from which some of the components were eliminated in a group, indicated that amino acids and nucleotides are responsible for the taste and other groups, organic bases, organic acids and glucose, make little contribution, if any. Among amino acids, only the limited members, such as glycine, alanine, valine, glutamic acid and methionine were judged to be essential for the taste and role of other amino acids was insignificant. Glycine and alanine contributed to the sweetness, valine to the characteristic bitterness, and glutamic acid, in interaction with inosinic and guanylic acids, to the meaty taste, respectively. Methionine, even though a minor component, was indispensable to development of a peculiar taste of “Uni” (Table 2), and it thickened the taste and enhanced the after-taste. This sweet-bitter amino acid was found to show a threshold value as low as 0.00125% (Table 3). Inosinic acid, together with guanylic acid, attributed to the meaty taste and hypoxanthine, the most abundunt purine base in the extracts, did not reveal any taste, as shown in Table 4. Although glycogen itself was entirely tasteless, it showed a distinct body effect by smoothing the taste of test solution.
1 0 0 0 OA 弥生時代のブタについて(Ⅴ. 生活文化史への視点)
- 著者
- 西本 豊弘
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.175-194, 1991-11-11
弥生時代の遣跡から出土する「イノシシ」について,家畜化されたブタかどうか,再検討を行った。その結果,「イノシシ」が多く出土している九州から関東までの8遺跡では,すべての遺跡でブタがかなり多く含まれていることが明らかとなった。それらのブタは,イノシシに比べて後頭部が丸く吻部が広くなっていることが特徴である。また,大小3タイプ以上は区別できるので,複数の品種があると思われる。その形質的特徴から,筆者は弥生時代のブタは日本でイノシシを家畜化したものではなく,中国大陸からの渡来人によって日本にもたらされたものと考えている。また,ブタの頭部の骨は,頭頂部から縦に割られているものが多いが,これは縄文時代には見られなかった解体方法である。さらに,下顎骨の一部に穴があけられたものが多く出土しており,そこに棒を通して儀礼的に取り扱われた例も知られている。縄文時代のイノシシの下顎骨には,穴があけられたものはまったくなく,この取り扱い方は弥生時代に特有のものである。このことから,弥生時代のブタは,食用とされただけではなく農耕儀礼にも用いられたと思われる。すなわち,稲作とその道具のみが伝わって弥生時代が始まったのではなく,ブタなどの農耕家畜を伴なう文化の全生活体系が渡来人と共に日本に伝わり,弥生時代が始まったと考えられるのである。
1 0 0 0 OA 関節柔軟性の規定因子の解明とセミテーラーメイド型肉離れ予防ストレッチング法の確立
1 0 0 0 OA 大学生における風疹ワクチン接種後の経時的抗体産生状況について
- 著者
- 丸山 典彦 伊藤 宏 内山 秀和 戸根 慶子 角野 猛 松井 清治
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.656-661, 1983-08-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 18
風疹抗体陰性の大学生50名を対象にワクチンを接種した後, 経時的に採血して抗体価ならびに免疫グロブリンの測定と同時に副反応についても検討し, 次の成績を得た.1. 大学生168名中, 風疹HI抗体の陽性率は女子で59.0%, 男子で76.3%, 全体では64.3%であった.2. ワクチン接種後, 3週から抗体産生が認められ, 5週において全例 (100%) の陽転が認められた.3. 5週における平均抗体価はHI価で68.6倍, NT価で42.4倍であり, 両抗体価の間には高い相関 (r=0.95) が認められた.4. 遠心分画法による2・ME感受性試験で接種後3週から6週目の血清の一部にIgMが検出された.5. 接種後, 副反応を呈したものは50名中6名 (12%) に認められ, そのうちわけは関節痛が2名, 発疹が1名, 発熱が1名であった.
1 0 0 0 IR 氏寺の中世的展開 : 『建内記』にみる浄蓮華院の役割を通して
- 著者
- 相川 浩昭
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 常民文化 (ISSN:03888908)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.172-157, 2006-03
1 0 0 0 OA 光マイクロトラップアレー中の冷却リュードベリ原子を用いた量子シュミレータ
The physical functionalities of various substances such as metals, uperconductings,and magnetic materials are governed by individual electrons and their interactions. However, it is difficult to exactly calculate the behavior of the quantum many–body systems containing over 50 particles with a classical computer, since the computational resource grows exponentially with the system size. Quantum simulation is an alternative approach to the many-body problems, which consists in building a well-controllable quantum system. The main objective of the quantum simulation is a deep understanding of many–body quantum phenomena ranging from dynamics of energy transport and particle localization to quantum–to–classical transition. To date, several platforms, from atoms and ions to superconducting circuits, have demonstrated the basic functionality of quantum simulation. The current challenges are not only to increase the number of particles but also to extend the versatility of the simulator. In this thesis, I describe the development of and scientifc results from a experimental platform for a versatile quantum simulation using laser-cooled Rydberg atoms. We create 2D arrays of optical microtraps using a spatial light modulator (SLM). Single87Rb atoms can be trapped in geometry-tunable and reconfigurable arrays with interatom spacings of a few micrometers. We first focused on one crucial prerequisite for the implementation of quantum simulation, i.e. detecting individual atoms with high efficiency. A fluorescence imaging yields single–atom–resolved information about the trap occupation and internal states of the trapped atoms. However, poor uniformity of trap–induced light shifts in arrays increases the detection error due to the variance of cooling efficiency and the photon scattering rate from each atom. Moreover, as each trap has a finite detection efficiency η, anN–atom system has an exponentially small detection efficiencyηN, that limits accuracy of experimental simulations. To overcome this issue, we have developed the novel optimization method to realize highly uniform holographic arrays of microtraps using in-trap fluorescence measurements. By applying this method to various arrays with up to N = 62 traps, the detection efficiency of all individual atoms, η62, can be improved from ≃ 55.0 % to ≃ 99.6 %. An optimization method such as the one presented in this work with holographic trap characteristics obtained by using in-trap atoms is useful for creation of finely optimized microtrap arrays. In order to generate strong interactions between atoms in arrays, we coherently laser–couple ground states to Rydberg states using a two–photon transition. The Hamiltonian of this system can be mapped onto spin Ising models in magnetic fields. In one experiment, we observe the collective enhancement of Rydberg excitations in the fully Rydberg blockade condition, where the interactions are much stronger than the laser–coupling. The Rydberg pair correlations we observe indicate strong correlations between nearby atoms, and blockade breaking arised from system edges. In a second experiment, we have implemented spin ising dynamics with opened– and closed–boundary conditions. We use an N = 5 1D array and an N = 6 ring array with nearest neighbor interactions, and measure the dynamics of spin densities, correlations, and all many–body states. The obtained results are in good agreement with numerical simulations for a short time and show that spatial localization of excitations appears in the 1D array, while the ring system has almost spatially homogeneous behavior. The experimental platform developed in this work has well–controllability rangingfrom atomic configurations to interactions, and pave the way for experimental investigation of synthetic or frustrated Ising magnets. 金属や超伝導素子,磁性体などの身の回りにある様々な物質の物理的特性は、物質中の個々の電子の振舞いやその相互作用により支配されている。しかしながら、このような複数の量子が相互作用しあう量子多体系は、粒子数がN = 50個でも現在のコンピュータでは厳密に解析することが難しいことが知られている。その理由は、粒子数の増加に対して系の取り得る量子状態が指数関数的に増大し、膨大な計算機リソースを要するためである。量子多体系を解析するもう一つのアプローチとして量子シミュレーションが挙げられる。量子シミュレーションは、中性原子・イオン・超伝導素子などの物理系を用いて量子多体系を記述するハミルトニアンを模擬的に再現し、個々の粒子の振舞いを実験的に解析する手法である。この手法により、未解決の物性の解明や物質の新たな機能探索が可能になるとして期待されている特に近年では粒子数の拡張だけでなく、量子シミュレータを構成する物理系の特色を生かし、粒子間の相互作用の相互作用パスや相互作用の大きさ、粒子配置などのパラメータの自由度の高い量子シミュレータの開発が着目されている。この技術により、多種多様な物質に対応させるだけでなく、対応物が存在しない系を実現することも可能になると期待されている。 本研究の目的は、冷却中性原子とリュードベリ状態間の大きな相互作用を用いて様々な量子多体系を再現可能な量子シミュレータの開発である。この手法の特徴は、リュードベリ状態間の大きな相互作用により各原子間距離を数μm以上離すことが可能となるゆえ、容易に単一サイトごとの観測・操作が実現できる点にある。さらに、空間光位相変調器(Spatial Light Modulator: SLM)によって生成された光マイクロトラップアレーを用いることで、プログラマブルに原子配置を制御することが可能となる。 本量子シミュレータの開発にあたり、我々はまず単一原子の観測効率に着目した。蛍光観測を行うことによって、原子配置や各原子に刻まれたスピンの状態を読み取ることができる。しかしながら、各サイトの光シフトの不均一性が生じると、原子の冷却効率や蛍光散乱レートにバラつきが生じ、単一原子の観測効率の悪化をもたらす。例えば単一原子あたりの観測効率がη= 0.99であっても、N= 50個の原子では指数関数的に観測効率が減少し、η50≃0.61となることが推測される。本研究では、実際のトラップ平面におけるをピーク強度のバラつきを単一原子から得られる蛍光を用いて均一化する手法を開発し、N= 62個のトラップ数においても全原子の検出効率η62を≃55 %から≃0.996 %まで向上できることを実証した。 数μm間隔のアレー状に並べられた単一原子間に強い相互作用を生成するために、我々は二光子遷移を用いて基底状態の原子をリュードベリ状態へのコヒーレント励起を行った。このようなリュードベリ原子系は磁場印加中のイジングスピンモデルにマッピング可能となる。一つ目の実験では、我々はリュードベリ原子間の相互作用が支配的な条件化において、リュードベリ状態への励起のダイナミクス測定を行った。ここでは、最大リュードベリ原子数が原子数Nに依存せず1個に制限されるリュードベリブロッケード効果や、N原子系のラビ振動が√Nに比例して増大する集団励起効果を観測した。二つ目の実験では、開境界条件および閉境界条件を有するスピン系のダイナミクスの実験シミュレーションを行った。ここでは、N= 5個の単一原子を一次元状に並べたアレーおよびN= 6個の単一原子をリング状に並べたアレーを用いて、スピンの密度分布やスピンスピン相関、多体状態のダイナミクスの測定を行った。得られた実験結果は、短時間領域においてイジングモデルの計算結果と良く一致するだけでなく、システムの境界の有無によってスピンの密度分布の局在化など系全体にもたらす効果を示す。 本研究で開発した実験プラットフォームは、個々の単一原子の高い制御性・観測効率だけでなく原子配置や相互作用領域の自由度を有し、幾何学的にフラストレートしたスピン系などの複雑なスピン系への応用が期待される。
1 0 0 0 IR ルーマニアにおけるEU加盟後のヒツジの移牧
- 著者
- 漆原 和子
- 出版者
- 法政大学文学部
- 雑誌
- 法政大学文学部紀要 (ISSN:04412486)
- 巻号頁・発行日
- no.64, pp.37-49, 2011
ルーマニアにおいて,EU加盟後5年を経過した2011年におけるヒツジの移牧の実態の把握を試みた。1989年12月の革命よりも前のヒツジの移牧の実態は,聞き取り調査によって正確に明らかにすることが困難であった。その後の市場経済体制下とEU加盟後の今日のヒツジの移牧は,2003年から2011年までの現地調査によってその実態が明確になった。調査地域は第2次世界大戦後の社会主義体制下において,生産性の上がらない場所として集団化をまぬがれたチンドレル山地の山麓である。ジーナ村とその周辺の海抜約1000mを基地として移牧を行う人々に限定して,調査を実施した。その結果,現在ジーナ村で登録されているヒツジの群は,冬の宿営地であるバナート平原で冬を越し,また春にはジーナ村に引き返す。夏は海抜1800m まで移動する。その際は,若羊のみ山頂の2200m 付近へ移動させる。一方,バナート平原に定住し,そこで飼われたヒツジは肉として売られるか,又はチーズの生産にむけられている。この数は年々大型化していて,その総数は不明である。しかし,1戸が1,000~1,500頭を超えるヒツジ飼育農家が増加している。その他にドナウ河畔まで南下し,冬を過ごすグループもあり,1 グループが600~800頭である。彼等は,夏はチンドレル山頂で過ごし,秋にはジーナ村にもどる。基地のジーナ村には秋の市場が開かれる時のみ戻る。もう一つはドナウ川下流域,又はデルタまで移動した移牧のグループである。彼等はEU 加盟後は移動をやめて定住している。その数は,今回の聞き取り範囲の推定頭数でも15,000頭に達することがわかった。ドナウデルタ全域では,定住しているヒツジの総数はきわめて多数にのぼると推定される。EU加盟後5年を経た今日のヒツジの移牧の実態から,今後のヒツジの畜産業の方向には次の二つが考えられる。一つは,バナート平原やドナウデルタのように冬も宿営地として飼育できる場で定住をし,大型化をはかる方向である。この方向は今後ますます飼育頭数が増加していくであろう。二つ目は,チンドレル山地の山頂まで移牧をし,良質の草を食べさせて,良質の若羊を飼育する方向である。これは,伝統的なこれまでの方法であるが,質の良い肉の需要がある限り,この移牧は消滅することはないであろう。しかし,伝統的移牧で扱うヒツジの頭数は年々減少すると思われる。
1 0 0 0 ルーマニアにおける社会体制の変革にともなうヒツジの移牧
- 著者
- 漆原 和子 白坂 蕃 バルテアヌ ダン
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, 2012
ルーマニアにおけるヒツジの移牧が社会体制の変革とともにどのように変化したかについて研究結果を述べる。とりわけ2007年EU加盟後の移牧が変質してきた。夏の宿営地(2100mの準平原面)へのヒツジの移牧頭数は激減し、冬の宿営地(バナート平原)へは移動手段を貨車、トラックに頼るようになった。また、バナート平原に定住化したヒツジの移牧の頭数が増え、大型化している。1000mの準平原面の上の基地では土地荒廃は改善されつつある。またドナウデルタではヒツジは定住化し、移牧は全くおこなわれなくなった。