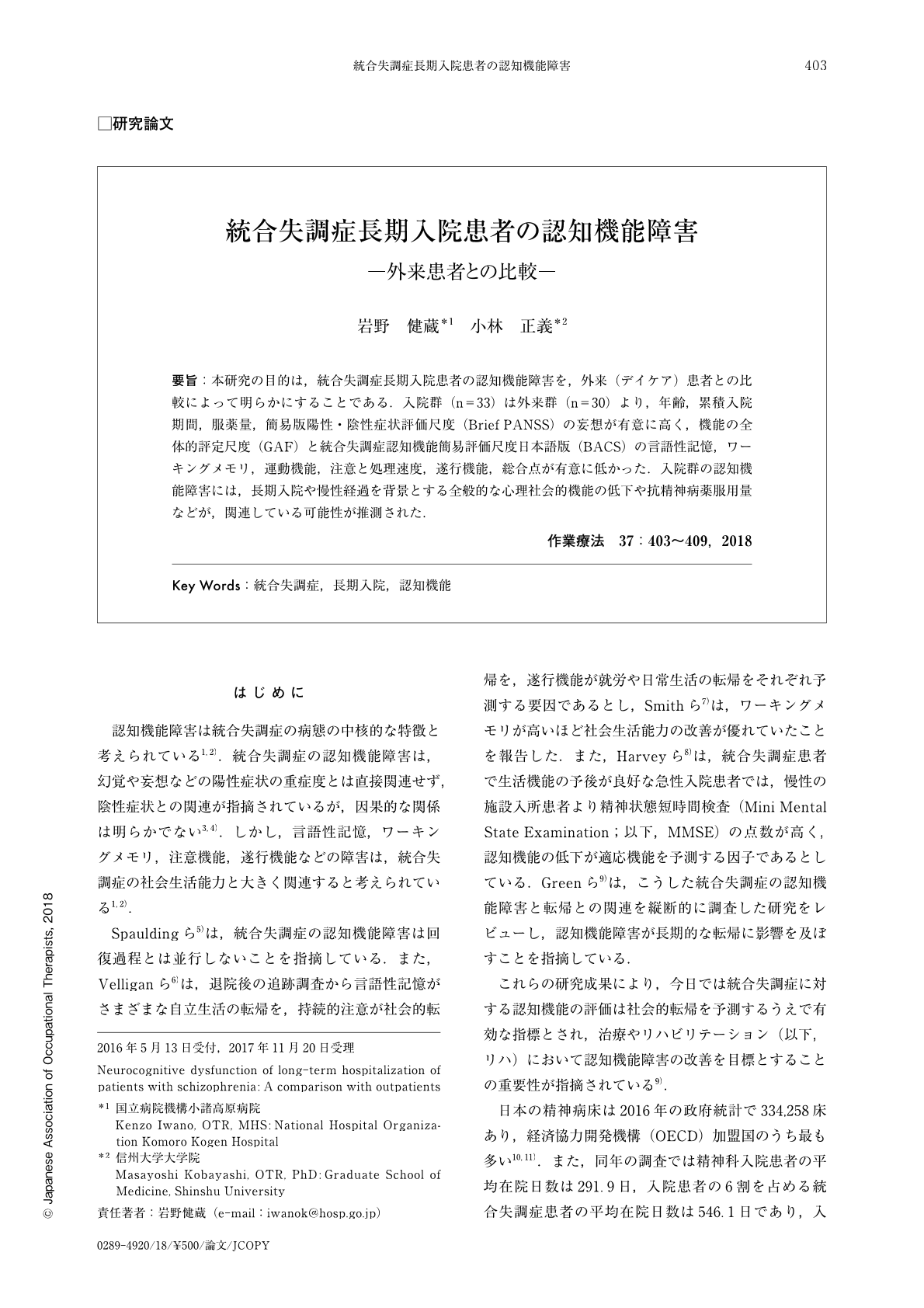1 0 0 0 OA 重度障害児の排泄実態と排泄環境整備
- 著者
- 植田 瑞昌 八藤後 猛
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.750, pp.1447-1457, 2018 (Released:2018-08-30)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 2
Independent excretion requires disabled children to acquire communication ability and the ability to maintain posture throughout the process of growth. These efforts require a combination of medical care, rehabilitation and education. However, under the current circumstances, teaching and training for excretion are provided at hospitals, rehabilitation facilities or schools when they are not given under home conditions. Further, the need for the development of changing excretion environments along with the growth of disabled children is not referred to. No studies have been found that address these issues as well as appropriate excretion environments based on the stages of growth or development of disabled children from the perspective of architectural planning studies. Consequently, the objective of our studies is to highlight the current situations and environments of excretion among disabled children and the actual conditions of the development of excretion environments based on the stages of growth or development of disabled children (physical/intellectual ability). We conducted a survey using a questionnaire and obtained responses from 729 disabled children. We classified the disabled children based on the physical or excretion conditions into groups that share similar difficulties in terms of excretion environments and analyzed them group by group. Our survey revealed the following: 1. Some disabled children use diapers in spite of no excretion disability. If children have difficulties going to the toilet owing to reason of physical functions, housing environments need to be developed from the perspective of caregivers who assist disabled children with moving. 2. The development of excretion environments would enable disabled children to excrete or change diapers at the toilet. Even though disabled children use diapers at their houses, they would be able to excrete at the toilet using assistance tools or toilet bowls of various shapes at rehabilitation facilities or schools. The development of excretion environments at houses which allow disabled children to excrete without help is needed. 3. Few houses have sufficient excretion environments. Information on how to develop environments at houses or subsidy housing is lacking. 4. Excretion environments at public toilets away from home are highly unsuitable. That they have no table for adults to change children's diapers suggests they do not assume use by disabled children. 5. Children with severe intellectual disability such as sound hypersensitivity, allotriophagy or coprophilia have different issues from physically disabled children with respect to the development of excretion environments.
1 0 0 0 OA 臨床能力とは何か
- 著者
- 鶴岡 賀雄 ツルオカ ヨシオ Yoshio Tsuruoka
- 出版者
- 立教大学史学会
- 雑誌
- 史苑 (ISSN:03869318)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.242-247, 2015-01
1 0 0 0 OA 若年女性におけるブラジャーのサイズ選択の実態
- 著者
- 高橋 美登梨 佐藤 百恵 川端 博子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.411-418, 2020 (Released:2020-07-18)
- 参考文献数
- 13
本研究では, 若年女性におけるブラジャーのサイズ選択の実態を検証した. 56名 (平均21.7歳) を被験者とし, 基本身体寸法に基づくサイズ, 被験者が日常的に着用しているサイズ, 販売員の資格を持つ者 (評価者) が選定したサイズの比較をするとともに, サイズ選択に関わる要因についてつけ心地と外観より考察した. 得られた結果を以下に示す. (1) 被験者の基本身体寸法によるサイズは, 被験者が着用しているサイズおよび評価者が選定したサイズと一致する割合が低く, サイズの選択にはつけ心地や外観といったフィット性が影響するといえる. 基本身体寸法からは乳房の左右差, 形状等の推定が難しいため, フィット性を重視したサイズと差異が生じることが示唆された. (2) 被験者が着用しているサイズと評価者が選定したサイズは, 約40%が一致とみなせた. 一致していない場合, 被験者はカップ体型を小さく認識していることが示された. (3) 被験者が日常的に着用しているサイズに対して, 評価者はブラジャーのカップ上部や脇が身体に食い込んでいると評価していた. また, 評価者が適切なフィット性であると評価したサイズは, 被験者にとってカップ上部の浮きを感じさせることが示された.
1 0 0 0 長明と琵琶--「胡琴教録」と「手習」と
- 著者
- 今村 みえ子
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国語と国文学 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.p28-40, 1992-03
1 0 0 0 日本音楽の学習指導の基礎--雅楽における学習過程の考察を通して
- 著者
- 伊藤 佐保美
- 出版者
- 日本音楽教育学会
- 雑誌
- 音楽教育学 (ISSN:02896907)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.p3-12, 1992
1 0 0 0 OA コロナ禍における静岡文化芸術大学の学生支援について
- 著者
- 佐々木 哲也 ササキ テツヤ
- 雑誌
- 静岡文化芸術大学研究紀要 = Shizuoka University of Art and Culture Bulletin
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.193-206, 2021-03-31
2020年の新型コロナウイルス感染症(以下 、COVID-19と略記)の感染拡大を受けて、静岡文化芸術大学(以下、本学と略記)では、学内の感染拡大防止と構成員の安全確保のため、大学構内への立入制限、遠隔授業の実施、諸行事の変更等の対応をとった。学生支援の分野では「全学生に対して漏れなく学修機会を提供すること」を最重要課題とし、SNSやWEB会議システムを活用した学生支援や窓口業務の遠隔化・電子化等に取り組み、平常時の業務の改善や非常時の対応能力の向上に繋がる経験を得た一方で、非常時の学生支援に関する脆弱性や課題が明らかとなった。本稿では、COVID-19に関する対応を開始した2020年1月から、大学構内への立入制限を解除した同年9月までの間の本学の学生支援の取り組みを報告し、同年7月に実施した緊急学生生活調査の結果等からコロナ禍が学生にもたらした影響を論述する。さらに、OVID-19に関する対応の経験を踏まえ、非常時における学生支援の課題として「大学IRと統合的な危機管理体制の構築」「組織と情報環境のレジリエンスの向上」「学生の危機管理能力の育成」の3点を提示する。
1 0 0 0 OA 高速原型炉“もんじゅ”のNaもれ事故の教訓
- 著者
- 住田 健二
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.63-67, 1997-01-01 (Released:2009-12-21)
1 0 0 0 OA Dynamic Influence of Propellant Sloshing Estimation Using Hybrid: Mechanical Analogy and CFD
- 著者
- Kai DONG Naiming QI Xianlu WANG Jiabao CHEN
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES
- 雑誌
- TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES (ISSN:05493811)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.177, pp.144-151, 2009 (Released:2009-11-02)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3 5
Liquid propellant sloshing, which induces perturbations to dynamic behavior of spacecraft, is a serious problem. This paper proposes an approach based on equivalent mechanics theory and Computational Fluid Dynamics (CFD) technology to estimate the dynamic influence of propellant sloshing on spacecraft. A mechanical model was built by CFD technique and packed as a “sloshing” block utilized in the spacecraft Guidance Navigation and Control (GNC) simulation loop. The block takes the motion characteristics of the spacecraft as inputs and outputs perturbative force and torques induced by propellant sloshing. It is more convenient to utilize in analysis of the coupling effect between propellant sloshing dynamics and spacecraft GNC than CFD packages directly. A validation case is taken to validate the accuracy and the superiority of the approach. The deducing process is applied to practical cases, and the simulation results are presented to demonstrate the proposed approach is efficient in identifying the problems induced by sloshing and evaluating effectiveness of several typical schemes for suppressing sloshing.
1 0 0 0 統合失調症長期入院患者の認知機能障害—外来患者との比較
要旨:本研究の目的は,統合失調症長期入院患者の認知機能障害を,外来(デイケア)患者との比較によって明らかにすることである.入院群(n=33)は外来群(n=30)より,年齢,累積入院期間,服薬量,簡易版陽性・陰性症状評価尺度(Brief PANSS)の妄想が有意に高く,機能の全体的評定尺度(GAF)と統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版(BACS)の言語性記憶,ワーキングメモリ,運動機能,注意と処理速度,遂行機能,総合点が有意に低かった.入院群の認知機能障害には,長期入院や慢性経過を背景とする全般的な心理社会的機能の低下や抗精神病薬服用量などが,関連している可能性が推測された.
1 0 0 0 OA 坂井利之先生のご逝去を悼む
- 著者
- 中川 聖一
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.6-7, 2018-12-25 (Released:2018-07-01)
1 0 0 0 有田磁器への新加飾法の提案 -発光性結晶釉の開発-
本研究では亜鉛結晶釉 (Willemite結晶 (Zn2SiO4)) において, 平成30年度の議論を基に磁器素地に穴をあけずに、シード材(ZnO+陶土)を表面に塗布する方法による結晶成長に成功した。結晶の成長温度が成長速度及び結晶形態に及ぼす影響を調べた。また、Mn発光結晶の形成について、シードより釉薬への添加が良いことが分かった。結晶成長温度を1050~1200℃まで50℃刻みで変化させ、結晶の大きさ及び形状を調べた。1100℃及び1150℃で最も大きく成長し(3時間で16mm)、前者では円盤状結晶と針状結晶が混在した組織、後者では針状組織となった。これは高温ほど結晶がガラスへ融解し易いためと考えられる。各保持温度で得られた結晶の配向性を調べた処、1050℃では粒状結晶からなっていたため配向性は認められなかったが、1100℃及び1150℃では(hk0)面の強い配向が認められた。これまではシード材である(ZnO+陶土)へのみMnOを添加していたが、この場合には発光強度が中央で最も強く、結晶周辺では殆ど認められなかった。そこで、今回の実験ではこれ以外にMnOを釉薬へ配合した実験も行った。254nmの紫外線照射下で、Willemite結晶自身も薄い緑色の発光を示した。ただし、装飾には利用できない。シード材に混合した場合には昨年と同様に結晶内で発光強度が低下した。一方、釉薬にMnOを乳鉢混合した場合には結晶が2~3mmしか成長せず、添加MnOが成長阻害材となっていることが分かった。なお、この結晶は緑色発行を示した。ただし、(釉薬+MnO粒子)混合物をボール見る粉砕・混合すると成長阻害効果は認められず、16mmの結晶が得られた。MnO添加量は0.3mol%が適切で、多くすると結晶成長阻害が認められた。この結晶は均一に強い緑色発光を示し、実用へ一歩近づいたと考えられる。
1 0 0 0 IR 海の妖精と人魚男--贖罪1000年のエピソ-ド
- 著者
- 松浦 暢
- 出版者
- 成城大学文芸学部
- 雑誌
- 成城文芸 (ISSN:02865718)
- 巻号頁・発行日
- no.134, pp.p55-74, 1991-03
- 著者
- 松尾 学
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.887, pp.109-112, 1997-04-21
日本歯科医師会会長選で,買収工作疑惑の現職候補にまさかの敗北。地域医療に邁進してきた開業医の挑戦は退けられた。"カネまみれ"体質を改めない限り,国民の信頼は得られないという。3月13日の日本歯科医師会会長選挙は,現職の会長で参議院議員(自由民主党)も務める中原爽氏が,全国139人の代議員から87票を獲得して当選した。
1 0 0 0 OA 自然脱落毛からの STR 型検出のための判断基準
- 著者
- 廣重 優二 山本 敏充 吉本 高士 石井 晃
- 出版者
- 日本法科学技術学会
- 雑誌
- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.97-111, 2013 (Released:2013-07-30)
- 参考文献数
- 26
In general, the attachment of human hair sheath is considered as one of the most important factors in detecting STR genotypes from single hair samples. Thus, it is difficult to genotype STRs from naturally shed human hair samples using AmpFℓSTR Identifiler PCR Amplification Kit. In this study, we examined the conditions involved in determining STR genotypes from a single hair root of naturally shed human hair focusing on two kinds of commercially available DNA extraction kits; a QIAamp DNA Micro kit (Micro kit) and an ISOHAIR kit (ISOHAIR kit), and the relationship between the concentration of extracted DNA and the numbers of STR loci genotyped. As a result, based on the protocol of DNA quantification adopted in the police labs in Japan, the DNA amounts were sufficient to quantify in approximately 28% or 36% of 72 naturally shed human hair samples using a Micro or an ISOHAIR kit, respectively. There was no significant difference in genotyping STRs between the two extraction methods. If a quantitative value was estimated based on a Ct (cycle threshold)-value, the extracted DNA was duplicated to amplify by 28 PCR cycles. Alternatively, if a quantitative value showed “ND (not detected)”, the extracted DNA was performed by duplicate PCR amplification for 32 cycles. Consequently, in the case of a 28 cycle-amplification, when a quantitative value was more than 0.04 ng/μl, the genotyping result was obtained accurately at almost all loci by both extraction methods. On the other hand, in the case of a 32 cycle-amplification, there was a tendency that more accurate genotypes are obtained by a smaller size of an amplicon except a few loci. It indicated that the accurate genotyping rate should not depend only on the size of PCR products. Therefore, when a DNA sample shows “ND” as an estimated value, more careful interpretation should be necessary to genotype by increasing PCR cycles to 32, or more strict making decision not to proceed to any PCR amplification should be performed.
1 0 0 0 長柱強力の圖式的計算法
- 著者
- 菱田 唯蔵
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- no.334, pp.11-23, 1914-10
1 0 0 0 OA 自閉スペクトラム症を持つ人の自己モニタリング機能の活性化を促す看護介入プログラムの効果
- 著者
- 関根 正 森 千鶴
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.70-85, 2018-02-01 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 41
青年期以降の自閉スペクトラム症を持つ人が治療を受けるきっかけは二次障害であり,根底には自分に対する意識が希薄という特徴がある。治療として,二次障害に対する薬物療法だけでは長期的な社会適応やQOLの改善は見込めず,心理社会的介入は必須である。しかし,看護師による確立された心理社会的介入は認められず,自閉スペクトラム症を持つ人の特徴を踏まえて実践できる介入プログラムが必要と考えた。そこで,リフレクション支援,自己説明支援,外化支援を介入技法とし,認知的介入と行動的介入から構造化した全10回の個人面接とする看護介入プログラムを作成し,有用性の検討を目的とした。評価は,認知行動的セルフモニタリング尺度,私的自意識尺度,SRS-Ⅱ(self-report),SRS-Ⅱ(others-report)を使用し,実施前後の比較をWilcoxon符号付順位検定,尺度の関連の検討を重回帰分析で行った。また,自分に対する意識の変化を質的帰納的に分析した。自閉スペクトラム症を持つ人16名に実施した結果,認知行動的セルフモニタリング尺度,私的自意識尺度は実施後の方が高く,SRS-Ⅱ(others-report)で実施後の方が低かった。また,行動モニタリングが私的自意識尺度に影響を与えていた。自分に対する認識の変化から,【自分の内面を意識できるようになった】,【対人関係を意識できるようになった】のカテゴリが生成された。これらの結果から,自分に対する意識が高まったと考えられ,看護介入プログラムは自閉スペクトラム症を持つ人に有用と考えられた。
1 0 0 0 OA 統語的逆成 : 日本語の受身文の場合
- 著者
- 赤楚 治之
- 出版者
- 名古屋学院大学総合研究所
- 雑誌
- 名古屋学院大学論集 言語・文化篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; LANGUAGE and CULTURE (ISSN:1344364X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1-13, 2008-10-31