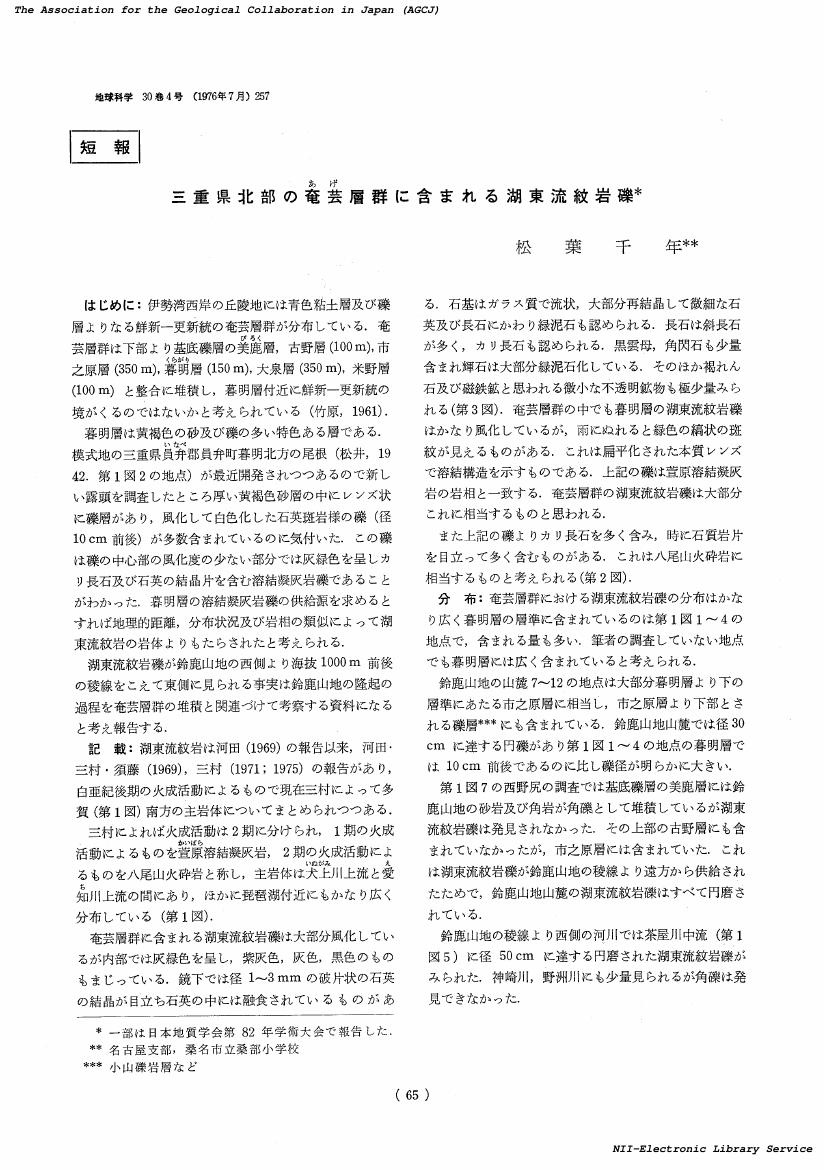1 0 0 0 OA 精神科長期入院患者の生活世界
- 著者
- 田中 浩二
- 出版者
- 日本精神保健看護学会
- 雑誌
- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.33-42, 2011-01-30 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 16
本研究は,精神科病院に長期入院を余儀なくされた患者が体験している生活世界を明らかにすることを目的とした質的記述的研究である.研究参加者は,精神科病院に10年以上入院している患者12名であり,参加観察と半構造的面接によりデータを収集し,質的帰納的に分析した.その結果,長期入院患者は【失ってしまったものが多く自らの存在が危うくなるような体験をしている】が,【入院前の自分らしい体験に支えられた生活】や【入院生活のなかでみつけた小さな幸せ】【病棟内から社会とのつながりを見いだそうとする工夫】【生きていくうえでの夢や希望】を拠り所に生活していることが明らかになった.長期入院患者の看護では,喪失体験に対する共感的理解とともに,その入らしい生活を送ることができるような場や人とのつながりを探求していくことが重要である.
1 0 0 0 IR 清拭タオルB.cereus汚染に対するICTの取り組み
- 著者
- 原 理加 永島 哲郎 小林 義明
- 出版者
- 日本赤十字社医学会
- 雑誌
- 日赤医学 = The Japanese Red Cross Medical Journal (ISSN:03871215)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, 2010-10-01
1 0 0 0 OA 近見反応痙攣の二症例
- 著者
- 伊藤 幸江 石川 均 西本 浩之 向野 和雄 石川 哲 佐藤 喜一郎
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.211-216, 1990-12-31 (Released:2009-10-29)
- 参考文献数
- 12
今回,輻湊痙攣による内斜視,調節痙攣,縮瞳の3症状が同時にみられる近見反応痙攣の2症例を経験した.症例1は18歳女子高校生,3歳半頃,頭部打撲後より内斜視に気づいた.両外転神経麻痺がみられたが徐々に改善した.ところが,15歳頃,全身運動した後に頭痛と複視を自覚し,近見反応痙攣が出現した.症例2は28歳女性,26歳頃より症状が出現し,現在も恒常的に近見反応痙攣が続いている.この痙攣に対して上原らが用いたアモバルビタールの静注を我々も行ってみた.症例1は静注前と著明な変化はみられなかった.症例2は3時間程持続効果がみられ以前の状態に戻ってしまった.近見反応痙攣の発作は,皮質中枢の異常興奮・輻湊の中間中枢,動眼神経核,EW核への抑制の障害などが考えられ,アモバルビタールの有効性からも推定できる.
1 0 0 0 OA 琵琶湖底掘削研究
- 著者
- 堀江 正治
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.4, pp.213-236, 1980-08-25 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 6
Lake Biwa is the third oldest lake in the world next to Lake Baikal and C aspian and Aral Seas. Its peculiar position in the Japanese Archipelago, Deep Seated Earthquake zone, striking by negative gravity anomaly, and many endemic species of animals and plants indicate its extremely long limnetic history. In other words, if we succeed in obtaining whole sediments columns by deep boring, we can clarify many unknown facts such as glacial and interglacial features, geomagnetic events, cosmic ray variations, sedimentological phenomena, chemical composition, biological evolutions…cand so on.On the basis of this idea, the writers and their collaborators undertook deep coring operations of 200 meters at the water depth of 65 m at the center of the lake in 1971 and of 1, 000 meters at the shore in 1975-1976. This paper summarizes these results together with a discussion of our future project of extremely deep drilling in order to introduce our pioneering work of human beings.
1 0 0 0 OA 舌潰瘍を契機に第一期梅毒と診断した未受診妊婦の1例
- 著者
- 品川 翔太 渡部 幸央 井比 陽佳 小池 将人 関川 翔一 神山 勲
- 出版者
- 社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.11, pp.559-564, 2020-11-20 (Released:2021-01-20)
- 参考文献数
- 19
The prevalence of syphilis has increased in Japan since 2010. Its rapid increase among women in their 20s is of particular concern because it is associated with an increase in the prevalence of congenital syphilis. We report a case of primary syphilis diagnosed from a tongue ulcer in a pregnant woman who did not receive antenatal care. A 29-year-old pregnant woman, who did not receive antenatal care, presented with a tongue ulcer at our hospital. She had a history of being a commercial sex worker. Laboratory tests revealed elevated C-reactive protein levels (5.56 mg/dL) and positive TPLA and RPR. We referred the patient to the department of infectious diseases as well as to the department of obstetrics and gynecology. She was treated with benzylpenicillin potassium (24 MU/day) for 14 days. Later, the tongue ulcer disappeared and RPR showed negative results. She gave birth to a boy who did not have congenital syphilis. The number of patients with syphilis presenting with oral symptoms is increasing, and it is expected that more of such cases will be examined by dentists. Therefore, it is crucial to consider syphilis as a differential diagnosis of oral mucosal disease and establish coordination among specialists who can be consulted and referred to when syphilis is initially suspected.
1 0 0 0 OA 三重県北部の奄芸層群に含まれる湖東流紋岩礫
- 著者
- 松葉 千年
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.257-259, 1976-07-20 (Released:2017-07-26)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 乳酸菌HOKKAIDO株を用いた機能性を有する食品等の開発と技術普及
- 著者
- 中川 良二
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.6, pp.283-289, 2018-06-15 (Released:2018-06-21)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
We have isolated a new strain of Lactobacillus plantarum from Japanese pickles produced by a farmer in Hokkaido, and have named the strain HOKKAIDO. Our investigation of HOKKAIDO strain revealed several characteristics. The strain exhibits digestive juice tolerance and can survive in the intestine. The strain strongly adheres to human enterocyte-like Caco-2 cells, and cells of HOKKAIDO strain competed with E. coli O-157 cells for adhesion to Caco-2 cells. From several examinations with human dendritic cells, this strain may act to improve immune function. It was found that HOKKAIDO strain is superior in the fermentation of vegetables, fruits, and cereals. These characteristics were exploited to produce foods such as fermented soybean milk, alcoholic beverages using sake lees, and fermented carrot drink. In addition, HOKKAIDO strain as a probiotic was contained in commercial products such as yogurt and a milk substitute for calves.
1 0 0 0 鰹の魚群態と漁況
- 著者
- 宇田 道隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.107-111, 1933
- 被引用文献数
- 5
The shoal of “Katuwo” [<i>Euthynnus vagans</i> (Lesson)] is often found associated with either sea-birds, drifting timbers, whales, sharks, or what not. The association with sea-birds or whales is almost clcaracteristic to the shoals of this fish found in the districts south to Prov. Bosyu, whereas the shoals associated with sharks are mostly distributed in the northern districts. Such difference of the distribution corresponds to that of oceanographical conditions, particularly of salinity (Figs. 1, 2 and Tab. 1).<br> The denseness of crowd and the degree of biting are represented quantitatively with the index-numbers <i>k</i> and <i>q</i> respectively (Tabs. 2 and 3), viz., <i>k</i>=<i>m</i>+0.1<i>n</i>/<i>m</i>+<i>n</i>, where m and n are the number of records of dense and thin crowds respectively, and <i>q</i>=3<i>p</i><sub>2</sub>+2<i>p</i><sub>1</sub>+<i>p</i><sub>0</sub>+0.5<i>p</i><sub>-1</sub>+0.1<i>p</i><sub>-2</sub>/<i>p</i><sub>2</sub>+<i>p</i><sub>1</sub>+<i>p</i><sub>0</sub>+<i>p</i><sub>-1</sub>+<i>p</i><sub>-2</sub>, where <i>p</i><sub>2</sub>, <i>p</i><sub>1</sub>, <i>p</i><sub>0</sub>, <i>p</i><sub>-1</sub> and <i>p</i><sub>-2</sub> are the mumber of records of very good, good, medium, poor and very poor biting respectively. The index-number of fishing value of a shoal defined by <i>N'</i>/<i>lt</i>. where <i>N'</i>, <i>l</i> and <i>t</i> are the total number of fishes angled, the numberof rods used and the duration of angling respectively, varies with the product <i>Kq</i> (Tab. 6). But, since <i>N'</i> is not exactly proportional to <i>t</i> (Tab. 5), the above-mentioned index number is only an approximate one.<br> The relation between the degree of biting of “Katuwo” and the quantity of the contents of their stomach (Tab. 4) seems to be explained by taking the time required for digestion into account.
1 0 0 0 IR オカルト科学とストリンドベリの生物理論
- 著者
- 林田 愛
- 出版者
- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会
- 雑誌
- 慶応義塾大学日吉紀要. フランス語フランス文学 (ISSN:09117199)
- 巻号頁・発行日
- no.69, pp.49-71, 2019
Ⅰ : 「科学的オカルティズム」時代のストリンドベリⅡ : 「生」物体の心理Ⅲ : 「生物」の擬態と輪廻Ⅳ : オカルト的概念から宗教性へ
1 0 0 0 OA マスト細胞放出亜鉛の創傷治癒における役割解明
マスト細胞の顆粒中には亜鉛が豊富に含まれていることが報告されており、脱顆粒に伴って細胞外に放出されることが知られている。しかし、その役割とメカニズムについては明らかにされていなかった。そこで、マスト細胞顆粒中へ亜鉛を取り込む機構、そして細胞外に放出された亜鉛の役割解明を目的とした。本研究においてマスト細胞における顆粒内への亜鉛取り込みに関与している分子として亜鉛トランスポーターZnT2の同定に成功した。ZnT2欠損マスト細胞では刺激依存的な放出亜鉛が観察されず、またZnT2KOマウスでは皮膚創傷治癒の遅延が生じた。以上、本研究によりマスト細胞から放出される亜鉛の生理的意義を初めて示した。
1 0 0 0 OA がん患者における自立歩行を維持するための膝伸展筋力の検討
- 著者
- 會田 萌美 武井 圭一 岩田 一輝 山本 満
- 出版者
- 公益社団法人 埼玉県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.78-81, 2018 (Released:2018-04-03)
- 参考文献数
- 12
【目的】本研究では,がん患者の歩行自立度と下肢筋力の関連を明らかにし,自立歩行を維持するための下肢筋力の目標値を検討することを目的とした。【方法】がん患者48例で繰り返し測定した値を含む延べ 68例を対象とし,Barthel Indexの移動の項目から15点を自立群(49例),10点以下を非自立群(19例)とし2群に分類した。ロコモスキャンにて膝伸展筋力を測定し,2群間を比較した後に,ROC曲線からcut off値を求めた。【結果】膝伸展筋力は,自立群が0.53 ± 0.15 kgf/kg,非自立群が0.35 ± 0.10 kgf/kgであり,2群間に有意差を認めた。ROC曲線からcut off値は0.42 kgf/kgであった。【結論】全病期のがん患者を対象にした場合,自立歩行を維持するための膝伸展筋力として, 0.4 kgf/kgを一つの目安と考えられた。
1 0 0 0 OA ソーシャルメディアにおける単語の一般的ではない用法の検出
- 著者
- 青木 竜哉 笹野 遼平 高村 大也 奥村 学
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.381-406, 2019-06-15 (Released:2019-09-15)
- 参考文献数
- 35
ソーシャルメディアにおいては,辞書に掲載されているような用法とは全く異なる使われ方がされている単語が存在する.本論文では,ソーシャルメディアにおける単語の一般的ではない用法を検出する手法を提案する.提案手法では,ある単語が一般的ではない使われ方がされていた場合,その周辺単語は一般的な用法として使われた場合の周辺単語と異なるという仮説に基づいて,着目単語とその周辺単語の単語ベクトルを利用し,注目している単語の周辺単語が均衡コーパスにおける一般的な用法の場合の周辺単語とどの程度異なっているかを評価することにより,一般的ではない用法の検出を行う.ソーシャルメディアにおいて一般的ではない用法を持つ40単語を対象に行った実験の結果,均衡コーパスと周辺単語ベクトルを用いる提案手法の有効性を確認できた.また,一般的でない用法の検出においては,単語ベクトルの学習手法,学習された単語ベクトルの扱い方,学習コーパスを適切に選択することが重要であることがわかった.
- 著者
- 佐藤 容子 Yoko Sato
- 出版者
- 東京音楽大学
- 雑誌
- 東京音楽大学大学院論文集 = Bulletin of the doctoral programs, Tokyo College of Music (ISSN:21895767)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.69-85, 2018-03-01
- 著者
- 稲村 裕
- 出版者
- The Chemical Society of Japan
- 雑誌
- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.7, pp.734-736,A39, 1966
- 被引用文献数
- 1
1,2-ジベンゾイルエチレンや1,2-ジベンゾイルエタン,さらに3-ベンゾイル-1-フェニル-1-プロパノールの還元はすでに行なわれているが,その生成物の一つとして得られる1,4-ジフェニルブタン-1,4-ジオールには一対の立体異性体,aおよびbがあり,いずれがメソ型,いずれがラセミ型であるかが明確でなかった。著者は1,2-ジベンゾイルエタンと3-ベンゾイル-1-フェニル-1-プロパノールのラネーニッケル触媒による接触還元を行ない,後者からは上記異性体のジオールaおよびbを得,前者からはジオールa,bのほかに3-ベンゾイル-1-フェニル-1-プロパノールを得た。また水素化ホウ素ナトリウムによる還元では1,2-ジベンゾイルエタン,3-ベンゾイル-1-フェニル-1-プロパノールのどちらからも上記ジオールa,bのみを得た。これらの還元においては生成物の収率のうちジオールbのそれが圧倒的に高かった。またtrans-1,4-ジフェニル-2-ブテン-1,4-ジオールのラネーニッケル触媒による接触還元ではその生成物としてジオールaのみが得られた。以上の還元の結果とすでに行なわれている上記被還元物質のアルミニウムイソプロポキシドによる還元の結果からこれらの還元の機構について考察し,そこから上記2種の異性体の立体構造について推論した。
1 0 0 0 OA 海のよろずや : 玉野事業所
- 著者
- 横田 浩明
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)
- 巻号頁・発行日
- vol.866, pp.111-114, 2002-03-10 (Released:2018-03-28)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 健康問題からみた子どもの遊びの変遷に関する一考察
- 著者
- 棚橋 昌子
- 出版者
- 愛知淑徳大学文化創造学部
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集. 文化創造学部篇 (ISSN:13463330)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.113-126, 2002-03-05
1 0 0 0 房州産ツチクヂラに就て
The Northern Porpoise Whales visit the coastal waters of Sirohama, Tiba Prefecture in the months extending from June to October every year and are caught in numbers by small whale-boats in the period above-mentioned. Males and females show no significant difference in length, but on the average the females grow rather larger than the males, the fact is quite different from what is known on the most toothed whales, where the males are far greater than the females. As is known on the most whalebone whales and sperm whales, this whale also leaves a pormanent records of all ovulations in the ovaries as a form of corpus luteum. The females reach the sexual maturity at the approximate length 10.0m.
- 著者
- Tomoko YAESHIMA Sachiko TAKAHASHI Nobuko MATSUMOTO Norioi ISHIBASHI Hirotoshi HAYASAWA Hisakazu IINO
- 出版者
- JAPAN BIFIDUS FOUNDATION
- 雑誌
- Bioscience and Microflora (ISSN:13421441)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.73-77, 1997 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 32 42
Yogurt containing Bifidobacterium longum BB536 (designated as Bifidus yogurt) was administered to adult volunteers and its effects on the intestinal environment with reference to fecal microflora, ammonia levels, fecal characteristics (color, consistency) and defecation frequency were examined. Bifidus yogurt was manufactured by fermenting milk with B. longum BB536, Streptococcus thermophilus STH-450 and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus LBU-108. Standard yogurt manufactured using only S. thermophilus STH-450 and L. delbrueckii subsp. bulgaricus LBU-108 was used as the control diet. Eleven women volunteers were assigned as subjects to test the effects of Bifidus yogurt on the intestinal environment. Thirty-nine women volunteers were assigned as subjects to test the effects on fecal characteristics and defecation frequency. The volunteers were each administered 100 g of standard yogurt per day for two weeks. After a two-week interval period, each subject was administered 100 g of Bifidus yogurt per day for the subsequent test period. The period of administration of Bifidus yogurt was 2 weeks for testing effects on the intestinal environment and 3 weeks for testing effects on fecal characteristics and defecation frequency. The administration of Bifidus yogurt was effective to increase the number and relative percentage of fecal bifidobacteria significantly. The fecal ammonia concentration tended to decrease and fecal organic acid content tended to increase. The defecation frequency was significantly increased by Bifidus yogurt. The color of the feces changed to yellow and the consistency changed to soft. The administration of Bifidus yogurt was effective to improve the intestinal environment, fecal characteristics and defecation frequency.