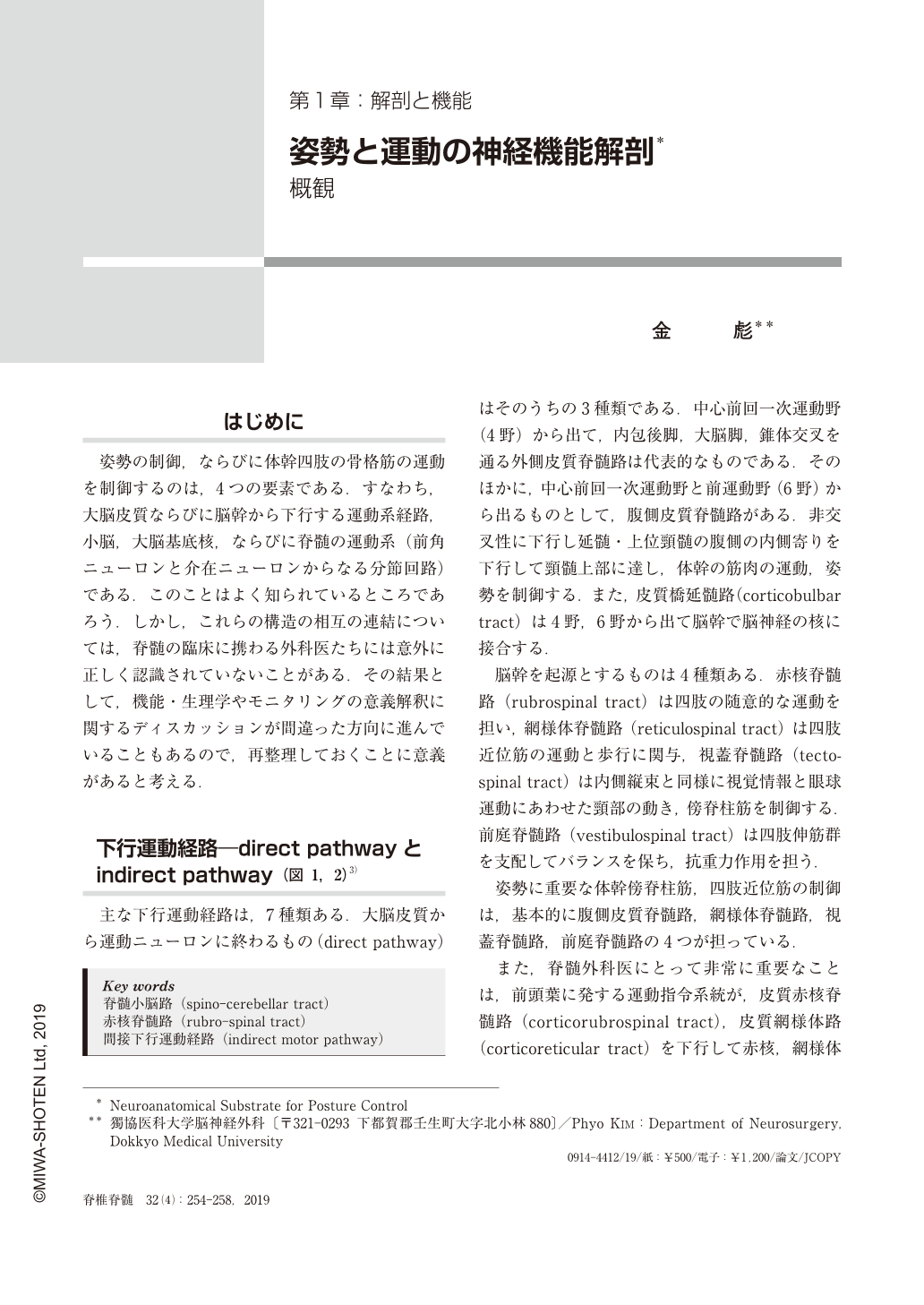1 0 0 0 OA 指回し体操を用いる健康法の多様な効果
- 著者
- 栗田 昌裕
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.26, 2020 (Released:2020-04-01)
- 参考文献数
- 29
指回し体操は、空間認知兼姿勢制御運動を特徴とする簡便な健康法として筆者が創案した方法である。それは1992年に拙著により一般社会に紹介された。その生体に及ぼす効果は多彩であり、運動系、自律系、感情・情緒系、感覚系、認知・言語系、代謝系に亘る。指回しは運動系では柔軟度や筋力に影響があり、自律系では皮膚血流や瞳孔対光反射に影響が生じ、感情・情緒では主観的な元気度が増す。指回しは脳波への影響が観察され、認知・言語系では、迷路抜け速度、計算速度、読書速度、数字記憶力、数字認知速度などが改善し、代謝系では体重変動が生ずる。また、交番磁場に対する感受性の亢進も生ずることが分かった。このように多彩な影響が生ずる理由は、指が知的機能の拠点であり、空間認知を支える視覚と連動しながら、姿勢制御系とも密接に関わり、しかも食べる動作を通じて内臓諸機能とも連携しているからである。指回し体操を活用した指回し健康法は、心身を総合的に高めて、健康を促進する上で有用と思われる。特に高齢者の健康寿命を促進する手法としても有意義である。
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ビジネス = Nikkei business (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.2009, pp.68-70, 2019-09-23
17年、中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)の日本法人が、初任給40万円で新卒エンジニアを募集した。これを契機にIT各社を中心に、初任給を上げる動きが広がった。 対話アプリのLINEでは19年卒の新卒採用から、エンジニアの最低年俸を528万円とそれま…
- 著者
- Aritada YOSHIMURA Takahiro OHMORI Kokoro ITOU Ryo ISHI Yuri MATSUMURA Yuhei WADA Miori KISHIMOTO Tomoko IWANAGA Naoki MIURA Kazuhiko SUZUKI Ryuji FUKUSHIMA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-0409, (Released:2021-03-15)
- 被引用文献数
- 2
In dogs, pancreatic acinar cell injury is thought to be caused by decreased pancreatic blood flow due to heart failure. In previous our report, it demonstrated that decreased heart function causes a significant decrease in pancreatic blood flow in heart failure dog model caused by rapid ventricular pacing (RVP). However, the types of histopathological changes remain unclear. We aimed to verify the types of histopathological changes occurring in the pancreatic tissue due to decreased heart function. After RVP for 4 weeks, atrophy of pancreatic acinar cells, characterized by a decrease in zymogen granules, was observed in all areas of the pancreas. In conclusion, the result of this study suggests that attention should be paid to ischemia/hypoperfusion injury in the pancreas.
1 0 0 0 開発された鶏卵皮蛋の製造後貯蔵過程における品質特性の変化
- 著者
- 工藤 美奈子 小泉 昌子 峯木 眞知子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.12, pp.823-832, 2019
<p> 日本製の安全・安心な鶏卵皮蛋が製造, 流通されるために, 鶏卵皮蛋の貯蔵過程における品質の変化を明らかにすることを目的とした. またそれらの変化について, 台湾産皮蛋と比較した.</p><p> 白色レグホーン種鶏卵を加工した鶏卵皮蛋を入手した. 入手後1, 7, 14, 21, 28, 58, 118, 180, 360日間貯蔵した鶏卵皮蛋の成分, 外観の観察, 重量, pH, 色度, 塩分, 卵白の水分含有率, 卵白の破断特性, 卵黄のテクスチャー特性およびにおい識別装置によるにおいの測定を行った.</p><p> 鶏卵皮蛋は28日間で卵黄が軟らかい溏心タイプの様になった. 鶏卵皮蛋の構成比について, 貯蔵日数とともに卵白の割合が低下し, 卵黄の割合が上昇していき, 360日間で卵白と卵黄の構成比が逆転した. 鶏卵皮蛋の卵白は, 貯蔵日数とともにかたくなる傾向が見られ, 台湾産皮蛋と比較すると, 卵白が軟らかく, 卵黄はかたさと付着性が低かった. 卵白のにおいの類似度は, 硫黄系, アルデヒド系ガスのにおいが高く, 皮蛋独特のアンモニア臭が低かった. これより鶏卵皮蛋は, 皮蛋独特のアンモニア臭が少なく食べやすいと考える.</p><p> 製造後貯蔵中の品質の変化より, 鶏卵皮蛋が一定の品質の製品になったのは, 貯蔵28日間以降半年程度であった.</p>
1 0 0 0 自動車車室内のにおい・空気質
- 著者
- 岩下 剛
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.391, 2011
自動車に乗る際,車室内の空気質を気にする時は,どんな時だろうか?昔は新車のにおいが顕著で,それを好ましく感じる人もいれば不快に感じる人もいた.空気質を考慮した自動車内装材の選定により,新車のにおいは以前に比べ顕著ではなくなった.排気ガスのにおいとともに小さい頃自動車に乗った記憶を甦らす人もいるだろう.喫煙者の所有する自動車の内装材およびエアコンのにおいに閉口した経験がある人も多そうだ.しかし,普段,運転をしていない方にとっては,車室内のにおいや空気質に対し,現実的なイメージをお持ちでない場合が多いと思われる.<BR>日常的に自動車を運転する方にとっては,もっと現実的な考えをお持ちだろう. 「幹線道路を運転する時は,大型車からの排気ガスが車室内に侵入するのを嫌い,外気を取り入れない換気モードを選択する」という行動を取られる方は少なくないだろう.夏季に冷房の効率を上げるために,外気を取り入れないという行動もあるだろう.そして,不快な外気を取り入れないため,室内空気(内気)を循環させる換気のモードを選択すると,換気量が減り,車室内発生の汚染物質の濃度が上昇することを知覚することは少ない.それは自動車に乗っている間に嗅覚疲労,嗅覚順応が生じてしまっているからかもしれない.<BR>建築の室内空気質については,シックビル・シックハウス・シックスクール問題が顕著になって以降,多くの研究がなされてきた.一方,居室と同等の居住性が要求されるようになってきている自動車車室内のにおい・空気質に関する研究例は少ない.そこで,今回の特集では「自動車車室内のにおい・空気質」と題し,様々な立場から,最近の動向を記述いただくことにした.<BR>株式会社ヴァレオジャパンの原氏には,自動車の車外,車内からのにおい発生源について解説いただき,その対策技術についても記述いただいた.<BR>日産自動車株式会社の吉浪氏には,自動車用の香り発生装置を組み込んだ車室内空調システムについて解説いただき,その目的,性能,運転方法などを記述いただいた.<BR>株式会社いすゞ中央研究所の達氏には,自動車部品から放散する VOCs(揮発性有機化合物)の評価方法について詳細に解説いただいた.<BR>最後に,筆者(東京都市大学・岩下)が車室内空気質の実測例を報告した.これら様々な視点から捉えた自動車車室内のにおい・空気質の現状が読者の方々にご理解いただければ幸いである.<BR>建築では室内環境が作業効率・知的生産性に及ぼす影響が注目されている.不快な環境による作業効率の低下が,企業生産性や安全性の低下につながるとしたら,それは由々しき問題である.2003年に建築基準法が改正される以前は居住空間に換気設備設置の義務はなく,住宅,学校などでは換気が不十分な箇所が少なくなかった.ビル衛生管理法では室内 CO<sub>2</sub>濃度は 1000ppm以下,学校環境衛生基準では教室内 CO<sub>2</sub>濃度は 1500ppm以下にすることが定められているが,換気量の少ない教室では 1500ppmを上回る測定例がしばしば見受けられた.60m<sup>2</sup>程の面積の教室に 40名もの生徒が一日中在室している在室密度の高さが高 CO<sub>2</sub>濃度の主要因となっている.在室密度の高さから言えば,普通乗用車も例外ではない.3〜10m<sup>3</sup>の車室内に 1〜8名の乗員がいるのである.コンパクトカーに4名の成人が乗車していれば換気が少なければ車室内 CO<sub>2</sub>濃度はかなり高くなるであろう.人体由来のVOCsはもちろん,人体由来以外のVOCsも内気循環の換気モードでは濃度が高くなる.換気状態の悪化が運転者の運転パフォーマンスに影響を及ぼすことがあってはいけない.安全性の視点からも車室内のにおい・空気質について考えてみたい.
1 0 0 0 OA Japanese Companies in the United States
- 著者
- David E. Jio
- 出版者
- The Japanese Association of Administrative Science
- 雑誌
- 経営行動科学 (ISSN:09145206)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.13-22, 1992-06-10 (Released:2011-01-27)
- 参考文献数
- 15
The purpose of this paper is to explain the current issues associated with an ever growing controversy in the United States: Whether Japanese companies in the United States discriminate against U. S. citizens, in favor of their own expatriates. The first half of the paper will discuss some theories on why Japanese companies are singled out more so than other foreign or U. S. companies when employment discrimination is alleged. The second half of the paper will discuss the current U. S. discrimination laws that are applicable to foreign companies operating in the United States. The major issue surrounding these laws is the vagueness and uncertainty they have on the issue of whether a Japanese company can legally discriminate and hire a Japanese expatriate over a U. S. citizen. A conflict exists between Title VII of the Civil Rights Act of 1964 which prohibits discrimination and the U. S.-Japan Friendly Cooperation and Navigation treaty which permits Japanese companies to discriminate for certain executive and specialist positions. Unfortunately the U. S. courts have not resolve this conflict. The Japanese companies do not know what constitutes discrimination and what is legally allowed. As long as the discrimination laws that are applicable to Japanese companies are not clarified, these companies will be exposed to the risk of possibly violating U. S. discrimination laws. The consequences of these uncertainty can only result in more litigation cost for the Japanese companies and more importantly, an increase in anti-Japanese sentiments. Thus, it is important for the Japanese companies to avoid employment discrimination allegations. Unfortunately, the U. S. courts have not helped to further clarify what type of discrimination practice is acceptable.
- 著者
- 東海 義仁
- 出版者
- 富山大学国語教育学会
- 雑誌
- 富山大学国語教育 (ISSN:03853632)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.32-39, 2019-11
1 0 0 0 オンリー•イエスタデイ:1950年代•回想
- 著者
- 渡辺 雅夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.7, pp.475-477, 1996
- 著者
- 高畑 由起夫
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.181-189, 1994
- 被引用文献数
- 3
In this article, I review and discuss the present problems of Japanese primatology by looking back at the trends of the 1980s. The main themes are (1) the significance of the research on great apes, (2) the theories concerning the social structure of primates, (3) cooperation among the field sites of the great apes, and (4) recruitment of “good students”.
- 著者
- Tanaka Takanobu
- 雑誌
- 人文研究 (ISSN:04913329)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.431-447, 1999-12
I Introduction : Martin Chuzzlewit (1843-44) has an overall "design," a grand unifying theme. This is the theme of selfishness and all its fruits and is loudly enunciated by old Martin and the narrator at the end of the first monthly number. Many critics such as J. Hillis Miller and Steven Marcus read the novel as centered around this theme, and regard old Martin as a sort of "human providence." Stuart Curran, arguing that the myth of the loss of Eden is central to the whole idea of the novel, identifies him with the "stern Deity of the Old Testament, the God of Truth." Old Martin restores justice and order, and brings a happy ending. This reading can be reviewed from a different perspective, that is, the father-son relationship when we notice old Martin is a patriarch. In fact, the theme is itself developed as centered around such relationships as old Martin and his grandson young Martin, Anthony Chuzzlewit and his son Jonas, Tom Pinch and his "father" Pecksniff, and Tom and his new father-figure old Martin after he knows Pecksniff's true character. ……
1 0 0 0 映画の映像理論に基づく対面会議シーンの自動撮影手法
- 著者
- 井上 亮文 吉田 竜二 平石 絢子 重野 寛 岡田 謙一 松下 温
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.212-221, 2004-01-15
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 8
本研究では,映画の映像理論に基づく対面会議シーンの自動撮影方式を提案する.対面会議シーンの撮影には複数のカメラを用いる必要があるが,位置的に離れたカメラの映像でスイッチングを行うと急激な変化が生じ,視聴者が参加者の位置関係の認識に混乱を来たす.提案手法では,人物の位置関係を明確にする映像理論であるイマジナリーラインを設定および解除する方法と,参加者の対話シーンを強調する三角形配置に従った撮影用カメラの決定方法を定義している.実験では正確なイマジナリーラインを冗長な部分があるものの70¥%の確率で設定でき,映像表現に影響を与えるような検出ロスは少なかった.アンケートによる比較実験では,人手でスイッチングしたものと比べて位置関係の見やすい映像を自動生成できたことが確認された.In this paper,an automatic shooting method for face-to-face meeting scene based on grammar of the film language is proposed.Shooting a meeting scene requires multiple video cam- eras,however,viewers may get confused in case of switching shot between spatially distant cameras.To shoot participants effectively,we introduce two filming theory into automatic shooting method.The dectection of the メimaginary line モmakes spatial relationships of the participants clear.The determination of the メcamera triangle モfigures out the conversation of the participants.Although there remains some redundancies,the detection ratio of the ideal imaginary line was 70%,the loss of which had less effects on the video image.The comparative experimental result indicated the availability.
1 0 0 0 OA 人工衛星帯電
- 著者
- 趙 孟佑
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.673, pp.53, 2010-02-05 (Released:2019-04-19)
- 著者
- 小池 敏夫
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- Transactions and proceedings of the Palaeontological Society of Japan. New series = 日本古生物学会報告・紀事. 新篇 (ISSN:00310204)
- 巻号頁・発行日
- no.173, pp.366-383, 1994-04-30
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 5
愛媛県東宇和郡城川町田穂上組に分布する, 田穂石灰岩から産するEllisonia dinodoides (Tatge)を検討したところ, M, Sa, Sb, Scの4つの構成エレメントからなり, それらは2 : 1 : 2 : 6の割合の数で存在することが判明した。しかしSaエレメントがノリアンでは極めて少ないか, 失われるようである。各エレメントは, スミシアンからアニシアンまで大きさが減少するが, アニシアンからノリアンにかけてはほぼ一定の大きさを保つ。エレメントの大きさと歯の数の相関係数は0.09から0.75で, 標本ごとにかなりのばらつきを示す。この相関係数について, 時代的な傾向は認められない。三畳紀において, 個体の大きさが時代とともに減少するのは, 比較的生存期間の長い複歯状コノドントに見られる一般的な傾向である。
1 0 0 0 OA 硬膜動静脈瘻の病態把握 (判断) と治療 (行動)
- 著者
- 里見 淳一郎 永廣 信治
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.42-51, 2016 (Released:2016-01-25)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2 3
硬膜動静脈瘻 (以下DAVF) は後天性疾患であり, 多くの症例が血管内治療の対象となる疾患である. 本疾患の病態把握と治療適応, 適切な治療方法についてレビューする. DAVFの自然歴は, これまで静脈還流異常 (静脈洞閉塞, 皮質静脈逆流, 静脈うっ滞) が悪化に関与する因子として長く認識されてきたが, 近年, DAVFの発症形式が自然歴に大きく影響するとした報告が相次いでいる. また, 自然消失に関して, DAVFは静脈還流路の閉塞性変化を伴いつつ消失に向かう症例も多い. 治療適応に関して, 治療によるメリットが自然経過, 周術期合併症によるデメリットを上回るためには, 発症形式, 血管撮影所見, 罹患部位等, さまざまな因子を総合的に判断することが重要である. 治療方法に関して, 血管内治療は, 短絡部位より近位の動脈側の塞栓はシャント量減弱に一定の効果を有するが, 根治に至らないことが多い. 一方で, 経静脈的塞栓は, 短絡部位の流出側を閉塞する手技であり, 根治の率が高いものの, 治療遂行にあたっては, 皮質静脈逆流を残さないよう努める必要があり, また, 正常静脈還流に関与する部位の塞栓は避けなければならない. 前頭蓋窩, 頭蓋頚椎移行部など, 外科的治療が血管内治療より容易で適切と考えられる部位もあるが, 今後, 液体塞栓物質 (NBCA, Onyx) を用い経動脈的シャント閉塞を目指した根治療法の発展が期待されている.
- 著者
- 松下 元則
- 出版者
- 地域公共政策学会
- 雑誌
- 地域公共政策研究 = Public policy in local governments (ISSN:13463411)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.55-72, 2020-11
1 0 0 0 OA 漢籍國字解全書 : 先哲遺著追補
- 著者
- 藤原 瑞穂
- 出版者
- 日本養護実践学会
- 雑誌
- 養護実践学研究 (ISSN:24336076)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.19-28, 2020 (Released:2021-01-20)
1 0 0 0 姿勢と運動の神経機能解剖—概観
はじめに 姿勢の制御,ならびに体幹四肢の骨格筋の運動を制御するのは,4つの要素である.すなわち,大脳皮質ならびに脳幹から下行する運動系経路,小脳,大脳基底核,ならびに脊髄の運動系(前角ニューロンと介在ニューロンからなる分節回路)である.このことはよく知られているところであろう.しかし,これらの構造の相互の連結については,脊髄の臨床に携わる外科医たちには意外に正しく認識されていないことがある.その結果として,機能・生理学やモニタリングの意義解釈に関するディスカッションが間違った方向に進んでいることもあるので,再整理しておくことに意義があると考える.
1 0 0 0 OA 弾性体の逆問題
- 著者
- 中村 玄
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.113-124, 2001-04-26 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 39
1 0 0 0 IR 初期文法学派のダルマ論序 : 日常世界と祭式世界における知行
- 著者
- 川村 悠人
- 出版者
- 広島大学比較論理学プロジェクト研究センター
- 雑誌
- 比較論理学研究 : 広島大学比較論理学プロジェクト研究センター研究成果報告書 : the annals of the Research Project Center for the Comparative Study of Logic (ISSN:18806376)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.103-121, 2016
Kātyāyana's Vārttika begins with the following statement:vt. 1 (Paspaśā): siddhe śabdārthasambandhe lokato 'rthaprayukte śabdaprayoge śāstreṇa dharmaniyamo yathā laukikavaidikeṣu ||Let me cite here Cardona's lucid explanation of this statement and Patañjali's Bhāṣya thereon:It is given from every day communication in the world that there is an established relation between words and meanings; it is also given that the use of a word is prompted by a meaning in that one uses words in order to convey meanings. This being so, a restriction intended for merit (dharmaniyamaḥ) is established by the grammar. Kātyāyana says such a restriction has parallels in every day life and in practices based on Vedic lore. Two examples that Patañjali gives will suffice to illustrate. Smṛti texts provide that certain animals may be eaten and that others may not be eaten. It is forbidden, for example, to eat a domestic fowl or pig. Now, one consumes something in order to do away with hunger, and this can be done by eating anything, including dog meat. A restriction is set down, then: such and such may be eaten, such and such may not be eaten. In ritual practice, a sacrificial pole is used; an animal being offered is tied to this pole. The animal may be tied to any piece of wood, which one may set erect or not. A restriction is established, whereby the sacrificial pole is not only to be erected but is to be made of Bilva or Khadira wood . . . . Patañjali goes on to show how the same situation obtains with respect to language use. Both a correct speech form (śabdena) and an incorrect speech form (apaśabdena) serve to produce the same understanding of a meaning (samānāyām arthagatau). A restriction intended for merit is made in the grammar: The meaning in question should be conveyed only by a correct speech form, not by an incorrect one. And usage in conformity with this restriction produces felicity, prosperity. (Cardona 1997: paragraph 830)In vārttikā 9 of the Paspaśā: śāstrapūrvake prayoge 'bhyudayas tat tulyaṃ vedaśabdena, Kātyāyana sets forth that the use of correct speech forms, preceded by a knowledge of grammar (śāstrapūrvake prayoge), results in prosperity (abhyudaya). In his Bhāṣya on the vārttika Patañjali elaborates on this theme, comparing śāstrapūrvaka-prayoga to Vedic norms (MBh on vt. 9 [Paspaśā] [1.10.22–26]).In Kātyāyana's and Patañjali's discussions the following causal sequence is assumed:śāstrapūrvaka-prayoga → dharma is produced → abhyudaya (in heaven)They propose śāstrapūrvaka-prayoga in the everyday world as a means of gaining merit and, through this, as a means of achieving prosperity; they intend this means to serve as an alternative to ritual activities (tat tulyaṃ vedaśabdena). This idea is a close reflection of the linguistic situation of their time, in which Middle Indic vernacular forms are observed to be used. It goes without saying that in their views such forms are to be regarded as incorrect (asādhu).広島大学比較論理学プロジェクト研究センター研究成果報告書(2016年度)本稿はJSPS科研費15J06976の助成を受けたものである。