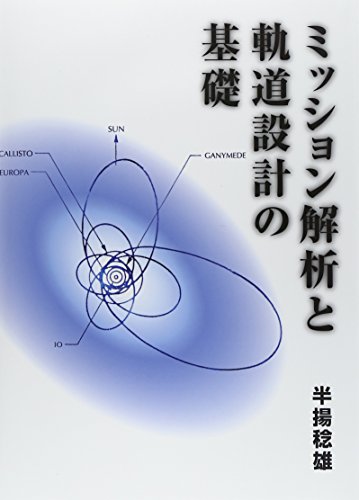1 0 0 0 OA インタラクティブマルチメディアコンテンツに対する感性品質の評価手法の提案
- 著者
- 阿部 周平 Shuhei Abe
- 出版者
- 電気通信大学
- 巻号頁・発行日
- 2013-03-25
現在、世の中には数多くのゲームが存在している。これらゲームはインタラクティブ性、マルチメディア性、コンテンツ性という3つの特性をもっている。以上の特性をもつものを本研究ではインタラクティブマルチメディアコンテンツ(以下IMC)と呼ぶ。IMCの典型例であるゲームには様々なジャンルがあり、例えば恋愛アドベンチャーゲーム(以下恋愛ADV)がある。IMCの品質においては、面白さのような感性品質が重要となる。感性品質はユーザーの感性によって決定される品質である。感性品質を高めるためには感性品質を評価する必要がある。感性品質に関する既存研究は棟近らの「感性品質の調査に用いる評価用語選定の指針」と阿部の「インタラクティブマルチメディアコンテンツに対する感性品質の評価手法の提案」の2つがある。しかし、棟近らの手法は物理特性があるものの評価を対象としているため、IMCの評価は行えない。阿部の手法はIMCの評価は行える。しかし、阿部の手法では静的な印象が得られる感性品質の評価しか行えず、「ヒロインの態度が素っ気ないから可愛らしいへ変化する」のような変化する感性品質の評価は行えない。本研究ではIMCに対する変化する感性品質の評価手法を提案する。本研究では変化する感性品質をTS感性品質と呼び、TS感性品質を評価するためにモデル化を行う。提案するのは時間経過による変化をモデル化したタイムストリーム図と変化の種類をモデル化した変化パターンである。タイムストリーム図はTS感性品質の元となる感性品質とTS感性品質の関係などをモデル化した図である。変化パターンは変化の種類をモデル化したもので、ギャップパターンと増加パターンの2つを提案している。提案したタイムストリーム図と変化パターンを用いてIMCに対する感性品質の評価手法を提案する。評価手法を被験者に使用してもらい、TS感性品質を抽出することができるかという点と、抽出したTS感性品質がIMCの感性品質の評価に有用なものであるかという点について検証を行い、本研究の有用性を示す。
1 0 0 0 ビデオゲームの目録作成とメタデータモデルを巡る研究動向
- 著者
- 福田 一史
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- カレントアウェアネス (ISSN:03878007)
- 巻号頁・発行日
- no.336, pp.23-27, 2018-06-20
1 0 0 0 OA 小麦の文化史 : イタリア小麦の現状とセナトーレ・カッペッリ小麦
- 著者
- 牧 みぎわ
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 人間文化研究 = Journal of Humanities Research St. Andrew's University (ISSN:21889031)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.213-240, 2017-03-10
The safety of food is a matter of great concern in the world today. In Italy,the homeland of pasta, the safety of wheat is a focus of attention and arousingan intense controversy. However, a thorough check of its quality is very difficultbecause of the enormous quantity of imported wheat which is goingaround. Under these circumstances, ancient types of wheat like Spelt andCamut are attracting an increasing interest for their primitiveness and, therefore,safety.In the same way, a wheat cultivar Senatore Cappelli is being reevaluated. Itwas created in 1915 by an Italian agricultural geneticist Nazareno Strampelli,as the first cultivar of hard wheat (Durum). It is the ancestor of almost all ofthe hard types of wheat existing and circulating now. The Senatore Cappellialso contributed to the “Green Revolution” and turned Southern Italy into afertile land, but after the World War Ⅱ, it went driven away by new cultivars.Only recently the Senatore Cappelli is regaining its reputation, especiallyamong professionals of the food market. In this paper I try to examine thevalue of this species of wheat and show its significance in today’s Italy.
1 0 0 0 OA ホツケー選手の体力, 動作分析所要熱量に関する調査報告
- 著者
- 横堀 栄 中村 常弘
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.123-129, 1962-11-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA インシデントレポートからみた当院RSTの活動成果
- 著者
- 手間本 真 佐藤 伸之 佐藤 照樹 上田 歩 逢坂 みなみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.162-166, 2020-08-31 (Released:2020-09-02)
- 参考文献数
- 4
【目的】これまでのRST活動をまとめ,その成果をインシデントレポートの変遷から考察する.【方法】2014-17年の人工呼吸器関連のインシデントを抽出し,内容と変遷についてRST活動との関連を検討した.当院RSTの主たる活動は週1回の病棟ラウンドで,安全管理,離脱,合併症予防などの観点から評価,提案を行なっている.また院内研修会やセミナーを開催している.【結果】人工呼吸器関連のインシデントは全体の2-3%程度であった.項目別では呼吸器本体とチューブ関連が多かった.チューブ関連では当初予定外抜管が多く見られたが2017年には全インシデントに対する割合は有意に低下していた.【考察】インシデントの内容は多岐にわたるが,予定外抜管に関しては低下していた.チューブ固定や鎮静に関するラウンドでの指導や研修会の開催,体位変換時のチューブ固定に関するマニュアル作成などのRST活動が寄与したと考えられた.
1 0 0 0 ミッション解析と軌道設計の基礎
- 著者
- 中北 浩爾
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.11, pp.2007-2015, 2001
1 0 0 0 OA イチジクの抗アレルギー作用に関する研究
- 著者
- 鳥居 貴佳 近藤 徹弥 半谷 朗 三井 俊
- 出版者
- 愛知県産業技術研究所
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.82-83, 2011 (Released:2013-10-08)
イチジクが有する抗アレルギー作用を効果的に利用するため、培養細胞を用いたβ‐ヘキソサミニダーゼ遊離阻害率を脱顆粒反応の指標として抗アレルギー作用を示す成分の特性を検討した。イチジク果汁をHP-20樹脂に添加して、80%メタノールで溶出することにより抗アレルギー成分を粗精製した。これをポリビニルポリピロリドンに接触させたところ、β‐ヘキソサミニダーゼ(β‐HEX)遊離阻害率が低下した。このことからポリフェノールがβ‐HEXの遊離に関与していることが考えられた。また、沸騰水中で加熱処理したところ、β‐HEX遊離阻害率が未処理の試験区と比較して高くなった。
1 0 0 0 OA 宮沢賢治とエマーソン ―詩人の誕生―
- 著者
- 信時 哲郎
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.139-150, 1992-03-31 (Released:2017-06-17)
Miyazawa Kenji read Emerson’s Essays First and Second Series, which was translated into Japanese by Togawa Shūkotsu in 1911-1912,in his junior high school days. As Ōsawa Masayoshi has pointed out, Miyazawa’s belief in Hokke may have been influenced by Emerson. However, in this essay, I would like to focus my attention on another aspect of Emerson’s influence upon Miyazawa Kenji. Miyazawa is considered a unique poet in Japan; especially his poetic theory is said to be unique in the history of Japanese literature. I would like to show that Miyazawa’s poetic theory was influenced by Emerson’s essay “The Poet.” The fundamentals of Miyazawa’s theory can be summarized as follows. The main part of the poet’s work is to listen to the voice of nature carefully. The poet is a representative of human beings, for he can describe the truth that nobody has ever discovered. Therefore, a good poem may seem inconsistent and difficult to understand. These characteristics correspond to Emerson's attitude to poetry as described in "The Poet." Although Miyazawa insisted that his works were not poems but mental sketches, if we consider the strong influence of Emerson’s poetic theory on him, we should regard his mental sketches as poems and Miyazawa Kenji as a poet. The poet Miyazawa Kenji was born when he read Emerson's essays.
1 0 0 0 人間社会への価値創造と技術開発:―強い意志と柔らかい心―
- 著者
- 遠藤 信博
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:18844863)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.214-223, 2017
1 0 0 0 基調講演「武道教育の昔と今」
- 著者
- 佐伯 弘治
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.35-41, 2007
1 0 0 0 OA コミュニケーションにおけるあいまいな感情表現の有用性のロボットを用いた検証
- 著者
- 高橋 英之
- 出版者
- 玉川大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2009
コミュニケーションは人間の社会性の基盤となるものである.コミュニケーションは情報交換であり,一般的にはそこに曖昧さは必要が無いと考えられる.本研究では,人間のコミュニケーションに含まれる曖昧さが,特に大きな規模の社会集団では非常に重要な機能を持つという仮説を提起し,それを検討するためのシミュレーションと心理実験を行った.その結果,曖昧な顔表情を用いることで他者とのコミュニケーションが円滑になることを示すデータを得た.
1 0 0 0 考古学からみた現代琉球人の形成
- 著者
- 安里 進
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地學雜誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.3, pp.364-371, 1996-06-25
- 参考文献数
- 33
Is it possible that modern Ryukyuans are the descendants of Palaeolithic Minatogawa Man, and the people of the Shellmound Period, which is partially equivalentto the Jomon Period ? There is a blank period of about 10, 000 years between the Minatogawa population and the population of the Okinawan Shellmound Period. Sakishima prehistoric culture was one of the Southeast Asian prehistoric cultures until the beginning of the Heian Period. A dramatic cultural change occurred in Okinawa after the Shellmound Period, in the Gusuku Period, which began in the 10th to 11th centuries as a result of culturalinfluence from the Mediaeval Period of Kyushu. Darling 13th to 14th centuries the culture of the Gusuku Period also expanded into the Ryukyu Islands from Amami Islands to the Sakishima Islands, and there was a general rapid population increase. Modern Ryukyuans are descended from the populations of the Gusuku Period. Some geneticists and anthropologists insists that modern Ryukyuans possess hereditary blood factors found in northern Asian populations. It is suggested that those factors flowed into the Ryukyuan population in the Gusuku Period.
1 0 0 0 OA 実測値に基づいたヒト胃液のpHと滴定酸度の関係
- 著者
- 瀬川 昂生 有沢 富康 丹羽 康正 加藤 忠 塚本 純久 後藤 秀実 早川 哲夫 中澤 三郎
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.4, pp.849-853, 1994 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 9
入院および外来の患者,延べ387名より胃管にて空腹時に有管法にて分画採取した基礎およびテトラガストリン刺激後のpH0.95からpH6.9までの標本,3206検体を用いて胃液のpHと滴定酸度(mEq/l)との関係について検討した.一定のpHに対応する滴定酸度は一定した値ではなく,かつその変動幅はpHが高いほど大であったが,pHが高くなるとともに酸度は全体として低下し,pH(X)と滴定酸度(Y)との関係の近似式(Y=369.19-424.09X+203.66X2-48.29X3+5.57X4-0.25X5)を求めることができた.また,これにより計算したヒト胃液のpHから酸度(mEq/l)を求める換算表を日常臨床のために呈示した.
1 0 0 0 OA 腎機能と生理
- 著者
- 中西 祥子 杉野 信博
- 出版者
- 一般社団法人 日本体外循環技術医学会
- 雑誌
- 体外循環技術 (ISSN:09122664)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.74-81, 1979-09-10 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 市販飲料のう蝕誘発性リスク
- 著者
- 佐藤 節子 水枝谷 幸恵 日野 陽一 於保 孝彦
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.117-125, 2007-04-30 (Released:2018-03-23)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
容易に入手できるペットボトルや缶入り飲料の種類は多岐にわたる.われわれはう蝕予防の観点から62種類の飲料のう蝕誘発性に関する4つの要因,すなわち飲料のpH,中和に要するアルカリ量,う蝕細菌Streptococcus sobrinusによる酸産生および接着性不溶性グルカン合成を評価した.その後,4つの評価で得られたスコアを統合してう蝕誘発性リスクのレーダーチャートを作成した.その結果,炭酸飲料,スポーツドリンク,果・野菜汁および乳飲料のpHは,エナメル質脱灰の臨界値5.5より低かった.それらの飲料の中和には多量のアルカリが必要であり,特に果・野菜汁の中和には最も多くのアルカリを必要とした.また, S. sobrinusとの反応の結果,天然水飲料,無糖茶飲料および無糖コーヒー以外の飲料は, 5.5以下のpHを示した.さらに調査した飲料の半数が,接着性不溶性グルカンを産生した.レーダーチャートの評価により,全飲料は4つの特徴的なパターンに分類された.このレーダーテャートを用いて,茶飲料や天然水飲料等の低う蝕誘発性飲料とその他の高う蝕誘発性飲料を容易に区別することが可能であった.以上の結果から,われわれは飲料の潜在的なう蝕誘発性について認識する必要があること,そしてそのリスクについてのレーダーチャートは飲料の特徴を認識するのに有用であることが示唆された.
1 0 0 0 ワインの味とにおい(2)
- 著者
- 横塚 弘毅
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.94-101, 1989
1 0 0 0 ワインの味とにおい(1)
- 著者
- 横塚 弘毅
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.29-36, 1989
- 著者
- 岡坂 桜子
- 出版者
- 東京芸術大学
- 雑誌
- Aspects of problems in Western art history (ISSN:13485644)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.127-137, 2012