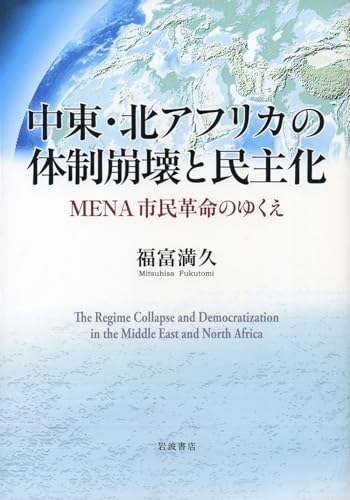7 0 0 0 OA 40周年を迎えた半導体電力変換技術委員会の過去・現在・未来
- 著者
- 船渡 寛人
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.1, pp.NL1_1, 2020-01-01 (Released:2020-01-01)
7 0 0 0 OA 福岡県小呂島漁業コミュニティーにおける世帯再生産メカニズム
- 著者
- 山内 昌和
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.12, pp.835-854, 2000-12-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 3
本稿では,縁辺部における人口や世帯の再生産が行われている例として,漁業が基幹産業となっている小離島の中から小呂島を取り上げ,戦後の世帯再生産のメカニズムを明らかにした.小呂島における世帯再生産は,漁業労働力の確保という経営体の戦略と,世帯維持に対する規範意識に代表される社会的な制約の双方が深く絡み合いながら行われていた.その際,イノベーション導入による漁業生産の拡大は経済的な保証を与え,一方で社会的制約は小呂島出身者に対し大きな影響力を有し,世帯再生産を支える要因の一つとなっていた.今後は,婚姻形態の変化などの社会的理由から若干の世帯数の減少が予想される.しかしながら,他地域た比べて漁業資源獲得に際しての相対的優位性が続くと想定されるため,今後とも一定の世帯数が再生産されていくであろう.
7 0 0 0 IR 親鸞を讃仰した超国家主義者たち(1)原理日本社の三井甲之の思想
- 著者
- 石井 公成
- 出版者
- 駒澤短期大学仏教科
- 雑誌
- 駒沢短期大学仏教論集 (ISSN:1342789X)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.45-70, 2002-10
7 0 0 0 OA 奔放な詩魂に導かれて 前田和泉著『マリーナ・ツヴェターエワ』未知谷,2006年
- 著者
- 竹内 恵子
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室
- 雑誌
- Slavistika : 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室年報
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.241-243, 2007-07-31
書評
- 著者
- 難波 知子
- 出版者
- お茶の水女子大学大学院人間文化研究科
- 雑誌
- 人間文化論叢 (ISSN:13448013)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.41-50, 2006
This article aims at reconsidering the history of women's school uniforms from the viewpoints of the educational system, students, and uniform production in modern Japan. Though the historical studies of school uniforms have focused on the control of students' bodies and clothing by schools, this article moreover notices the significance that women students realized in their uniforms, and the situation that their uniforms were made in the transition from Kimono style to Western style. The composition of this article is as follows. First, it gives an outline of the history of women's school uniforms from the Meiji era to the early Showa era. Second, it elaborates the process of wearing HAKAMA which women students longed to put on in the 30's of the Meiji era. And third, it considers the practical situation that the school uniforms were made, worn by students and controlled by schools. To conclude, in modern Japan women's school uniforms were formed as a culture by interrelationship among schools, students, and uniform production. Schools instituted uniforms for the realization of educational policy and the regu\lation of clothing. On the other hand, women students created their original meanings and dressing in their school uniforms. And the school uniforms as a culture prevailed involving the changes of styles of living in clothing, for example, from Kimono style to Western style and from sewing at home to buying products in stores.
7 0 0 0 OA GISの標準コアカリキュラムと知識体系を踏まえた実習用オープン教材の開発と評価
- 著者
- 山内 啓之 小口 高 早川 裕弌 瀬戸 寿一
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.288-295, 2019 (Released:2019-08-28)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
筆者らは,大学の学部や大学院のGISの実習授業を充実させるための教材を開発し,オープンな活用ができるコンテンツとして広く公開するためのプロジェクトを実施している.教材は,既存プロジェクトの成果である書籍『地理情報科学GISスタンダード』と対応するように構成した.GISを用いたデータの処理には,フリーかつオープンソースのソフトウェアを利用した.これらの教材は,GIS実習の課題や使用するソフトウェアの特性を考慮し,二次利用しやすいようにオープンライセンスのパッケージとして整備し,GitHubを用いて試験公開を行っている.本稿では,開発中の教材の設計と初期の構築の経緯をまとめ,既存のGIS教材との比較を行い,本教材の有用性について評価した結果を解説する.
- 著者
- 長谷川 直子 三上 岳彦 平野 淳平
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2019年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.116, 2019 (Released:2019-09-24)
1. はじめに/研究目的・方法 長野県諏訪湖では冬季に湖水が結氷しその氷が鞍状に隆起する御神渡りと呼ばれる現象が見られる。これが信仰されてきたことにより、その記録が575年にわたり現存している(石黒2001)。この記録には湖の結氷期日も含まれており、藤原・荒川によってデータベース化され(Arakawa1954)それらが長期的な日本中部の冬季の気候を復元できる資料として世界的にも注目されてきた(Gray1974)。 しかしこれらのデータは複数の出典に分かれており、出典ごとに記載されている内容が異なるものであり(表1)、統一的なデータベースとして使用するには注意が必要である。また一部の期間についてはデータのまとめ違いがあることもわかっており(Ishiguro・Touchart 2001)、このデータを均質的なデータとしてそのまま使用することは問題と考えている。そこで演者らはこのたび、諏訪湖の結氷記録をもう一度改めて検証し直し、出典ごとに記載されている内容がどのように違うのかを丁寧に検討し、それらのデータの違いを明らかにしていく。 2.諏訪湖の結氷記録の詳細 写真1:現地調査で確認した原本の例 諏訪湖の結氷記録は出典が様々であり、大きく分けると表1のようになっている。出典毎にそれぞれ、観測・記録した団体が別々のものであったり、観測者が記載したものから情報が追加されて保管されているものもある。表1に示した出典のうち一部は諏訪史料叢書に活字化されて残されているが、そこに掲載されていない資料もある。活字化されていないものについては原本に当たる必要があるが、現在ではその原本が所在不明なものもある。演者らは、活字化されていない資料を中心に、原本の所在を確認しているところである(写真1)。また世界的に広く使われている期日表は藤原・荒川のものであるが、田中阿歌麿が「諏訪湖の研究」(田中1916)の中ですでに期日表をまとめており、これと藤原・荒川期日表との照合も必要であると考えている。 3. 近年の気候変動と諏訪湖の結氷 近年、諏訪湖の結氷が稀になっていることは気候温暖化との関連も考えられ、図1に示すように気候ジャンプとの関連もみられる。これについては諏訪湖を含めた北半球での報告もされており(Sharma et al. 2016)、最近数十年に限定した詳細な検討も必要だと考えている。
7 0 0 0 OA 日本書紀古訓の形容詞語彙に関する研究
7 0 0 0 OA アトランタオリンピック爆弾テロ
- 著者
- 永田 高志 長谷川 学 石井 正三 橋爪 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本外傷学会
- 雑誌
- 日本外傷学会雑誌 (ISSN:13406264)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.47-51, 2017-01-20 (Released:2017-01-20)
- 参考文献数
- 11
アトランタオリンピックは,1996年7月19日から8月4日までアメリカのアトランタで行われた第26回夏季オリンピックであり,近代オリンピック開催100周年記念大会であった.爆弾テロ事件の概要は,大会7日目の7月27日午前1時20分頃にセンテニアル公園の屋外コンサート会場でパイプ爆弾による爆破事件が発生し,死者2名,負傷者111名の多数傷病者事案となった.死者2名のうち1名は爆発物の釘による頭部外傷によるものであり,もう1名は心不全であった.111名の傷病者のうち96名は事件発生後30分以内に爆発地点から半径5km以内の4つの病院に搬送された.外傷センターに搬送された35名中10名に対して緊急手術が行われ,市中病院に搬送された61名のうち4名に対して手術が実施され,すべて救命することができた.2020年東京オリンピックを控える日本にとってアトランタオリンピック爆弾テロから3つの教訓,事前の医療公衆衛生体制の構築,多数傷病者対応のための医療機関の準備,緊急時における情報伝達・コミュニケーションの難しさ,があげられる.2020年東京オリンピックでは爆弾テロを含めた様々な事案が起こるという最悪の想定のもとで,限られた時間と予算,資源の中で準備を進める必要がある.
7 0 0 0 中東・北アフリカの体制崩壊と民主化 : MENA市民革命のゆくえ
7 0 0 0 OA 北海道における海鳥類繁殖地の現状
- 著者
- 長 雄一 綿貫 豊
- 出版者
- Yamashina Institute for Ornitology
- 雑誌
- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.107-141, 2002-03-20 (Released:2008-11-10)
- 参考文献数
- 102
- 被引用文献数
- 26 33
北海道の海鳥類の保護及び研究を進めるために,既存の調査報告書を収集して,飛来数あるいは繁殖つがい数といった繁殖地サイズの動向と海鳥類の繁殖に対する人為的攪乱及び自然界での攪乱について分析を行った。北海道では少なくとも12種の海鳥類が繁殖している。繁殖規模の概数は,ウミガラス(Uriaaalge),10つがい以下;エトピリカ(Lunda cirrhata),15つがい;ケイマフリ(Cepphus carbo),100つがい;ウミスズメ(Synthliboramphus antiquus),20つがい以下;ウトウ(Cerorhinca monocerata),300,000つがい;オオセグロカモメ(Larus schistisagus),10,000つがい;ウミネコ(Larus crassirostris),30,000つがい;チシマウガラス(Phalacrocorax urile),25つがい;ウミウ(Phalacrocorax capillatus),3,000つがい;ヒメウ(Phalacrocorax pelagicus),10つがい;オオミズナギドリ(Calonectris leucomelas),120つがい;コシジロウミツバメ(Oceanodroma leucorhoa),900,000つがいであった。その他にマダラウミスズメ(Brachyramphus perdix)の繁殖については不明である。天売島のウミガラス繁殖地にいた成鳥数は,1938年から1980年の間に年平均で12.2%ずつ減少しており,1981年から1994年の間には年平均で26.6%ずつ減少し,1998年には7つがいが確認されたに過ぎない。モユルリ島のウミガラスについて,その繁殖地にいた成鳥数は1965年から1985年までに年平均で24.8%ずつ減少したが,1985年以来飛来個体が確認されておらず,繁殖地が消失したと考える。さらにモユルリ島エトピリカ繁殖地周辺にいた成鳥数は1960年から1995年の間に年平均で10.0%ずつ減少しており,現在ではユルリ•モユルリ島を中心に15つがい前後が繁殖していると考えられる。ケイマフリでは,天売島において年平均8.8%ずつ,ユルリ島においては14.4%ずつ減少しており,北海道全体の生息数も100つがい程度と考えられることから,この減少傾向が続くと繁殖地の消失も考えられる。その一方で,モユルリ島のウトウ繁殖地サイズは1960年から1996年の間で年平均14.2%ずつ増加していた。過去30年間の間にオオセグロカモメは増加傾向にあると考えられたが,モユルリ島の繁殖地サイズは1982年から減少に転じ,1996年までで年平均7.0%ずつ減少していた。天売島のウミネコは,1980年代には3万つがいが営巣していたが,ネコ等の捕食により1990年代に半減した。その一方で利尻島のウミネコは1987年に新たな繁殖地が形成されて以来,年平均19.5%ずつ増加し,現在では1万つがい以上が営巣するに至っている。調査報告書に攪乱の記述のある繁殖地は14箇所であった。カモメ類あるいはカラス類による攪乱の記述があったのは12箇所,死因が漁網への混獲との記述があったのは8箇所,人為導入されたドブネズミ類あるいはネコによる攪乱の記述があったのは5箇所であった。日本の海鳥類繁殖地の多くは,鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律等によって保護されている。しかしながら,繁殖地周辺の採餌域あるいは越冬域といった場所は保護の対象となっていない。そのため,海鳥が混獲しにくい漁具を開発することや,繁殖地周辺での漁業活動を見直すこと,あるいは石油流出事故に対応するたあの体制構築の必要があろう。また,人間によって繁殖地に導入された,あるいは人間の出すゴミによって増加したドブネズミ,ネコ,カモメ類,カラス類等の影響について考える必要があろう。
- 著者
- 羽山 伸一
- 出版者
- 獣医疫学会
- 雑誌
- 獣医疫学雑誌 (ISSN:13432583)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.22-23, 2009-07-20 (Released:2010-09-10)
The Tsushima leopard cat (Prionailurus bengalensis euptilura) is indigenous to the island of Tsushima in Nagasaki prefecture, Japan, and was declared as a critically endangered species by Species Conservation Act of Japan. In 1996, one of the wild Tsushima leopard cats was found to positive for FIV (feline immunodeficiency virus) that was original in domestic cats. Many captive or feral domestic cats can be found all over the island, and they might carry the FIV to the Tsushima leopard cat. According to the result of this survey, FIV infection rates in captive domestic cats were 13.6% (38/280) in Kami-shima (Northern Island) distributed the population of Tsushima leopard cats, and 10.6%(46/433) in Shimo-shima (Southern island) not confirmed the population. It was found through the GIS analysis that there are some specific areas where the FIV infection risks for the Tsushima leopard cat are much higher than other areas. It was recommended that it should be intensively done the action for prevention the Tsushima leopard cat from the FIV infection in this high risk area.
7 0 0 0 OA 人狼ゲームにおけるエージェント存在の開示度に対する看破への影響
- 著者
- 高田 和磨 杉原 太郎 五福 明夫
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18840833)
- 巻号頁・発行日
- pp.TJSKE-D-17-00028, (Released:2017-07-20)
- 参考文献数
- 14
This study analyzes the factors for detecting agents to implement a human-like agent in werewolf games, which are new themes in game studies of artificial intelligence. A comparative experiment was conducted to reveal the influences regarding the degree of disclosure of the agent existence; seven players and an agent participated in four games. Communication logs were collected from the game logs. Impressions for each player was reported in questionnaires with five-point scales and detection of the agent were reported in a free writing. Although the most players, who did not know that an agent played the games, did not be aware of the true character of the agent, the most players who knew the existence could detect the agent. The statements of detected agents differed from them of other players. This study concludes that the technical requirement for agents is to adapt to statements of other players.
7 0 0 0 OA 鼠よめ入 2巻
- 出版者
- [鶴屋喜右衛門]
- 巻号頁・発行日
- 1700
赤本2冊(合1冊、全10丁)。題簽欠のため元の題名は不明。覆表紙に「赤本鼠嫁入」、帙に「鼠のよめ入 赤本」とあるのは後に付けた題名。「鼠よめ入」は本文の版心にある題名。本文第1・6丁に「鶴の丸」の商標があり、鶴屋の版。画作者は不明。赤本の「嫁入りもの」は異類を擬人化して婚礼の次第を絵解きする作品で、鼠や狐や鳥などの異類が一種のものや十二支のように混在するものがある。中でも「鼠」による「嫁入もの」は何種類かあり、本作も「鼠の嫁入」ものの1つ。9場面から成り、各場面が絵と会話で展開し、会話におかしみや時代性が多分に盛り込まれている。
7 0 0 0 OA 近世上方における連用形命令の成立 : 敬語から第三の命令形へ
- 著者
- 森 勇太
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.1-16, 2013-07-01
現代語では,動詞の連用形に相当する形式で命令を行う"連用形命令"が西日本を中心に見られる。この連用形命令は宝暦頃から見られはじめるものであるが,本稿では,この連用形命令の成立過程を考察した。近世前期には,すでに敬語助動詞「やる」の命令形「やれ」が「や」と形態変化を起こし,待遇価値も低くなっている。また,終助詞「や」も近世上方に存在していた。このことから連用形命令は近世上方において,敬語助動詞命令形「や」が終助詞と再分析され,「や」の前部要素が命令形相当の形式として独立し,成立したと考える。この連用形命令が成立したのは,待遇価値の下がった命令形命令を避けながらも,聞き手に対して強い拘束力のもと行為指示を行うという発話意図があったためである。また,各地で敬語由来の命令形相当の形式(第三の命令形)が成立しており,連用形命令の成立も"敬語から第三の命令形へ"という一般性のある変化として位置づけられる。
7 0 0 0 共感性形成要因の検討 : 遺伝-環境交互作用モデルを用いて
- 著者
- 敷島 千鶴 平石 界 山形 伸二 安藤 寿康
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.188-201, 2011
Factors contributing to individual differences of empathy were examined using behavioral genetics methodology. Data related to individual levels of empathy and parental warmth received during childhood were collected from approximately 450 pairs of twins (ages 14-33). A bivariate model analysis clarified that shared family environmental factors did not contribute to the formation of empathy. No common shared environmental factors were detected between empathy and parental warmth, either. The positive correlation between the two variables was mediated principally by genetics. The result does not support socialization theory, which holds that warm parenting nurtures children's empathy. However, the subsequent gene-environment interaction model analysis revealed that shared family environmental factors significantly affected the formation of empathy for those with high or very low parental warmth. The results imply that individuals with a strong or very weak attachment to their parents were more influenced by the shared family environment.
7 0 0 0 IR 横浜・寿町における自立支援と地域再生 : 多様性を包摂するまちづくり
- 著者
- 西山 志保
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- グローバル都市研究 (ISSN:18838006)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.81-97, 2011-03-31