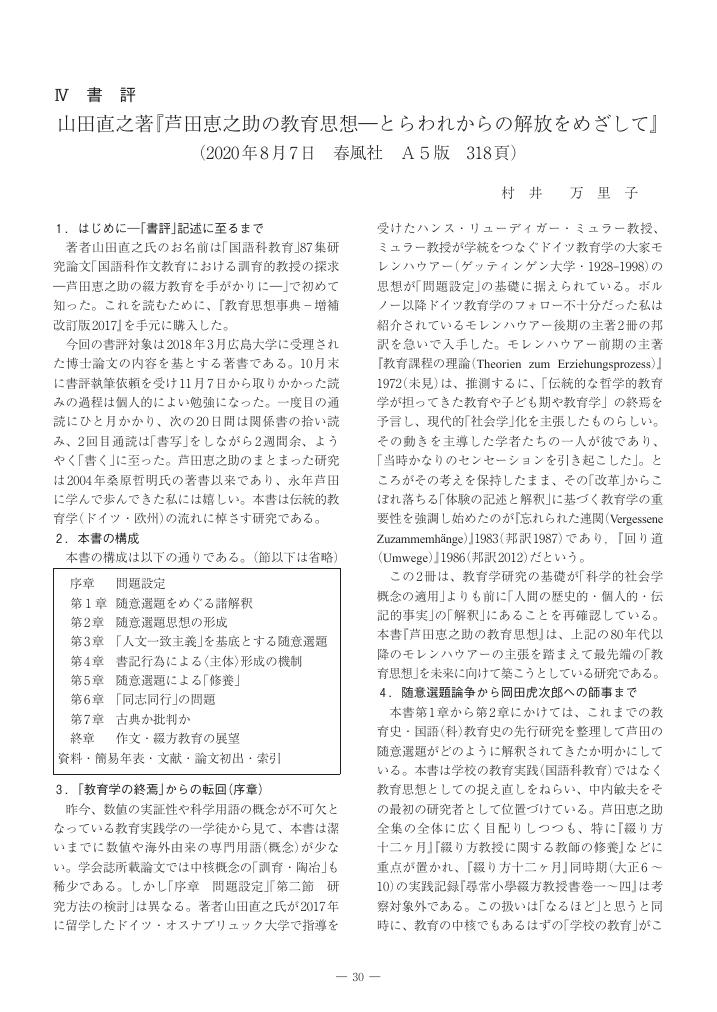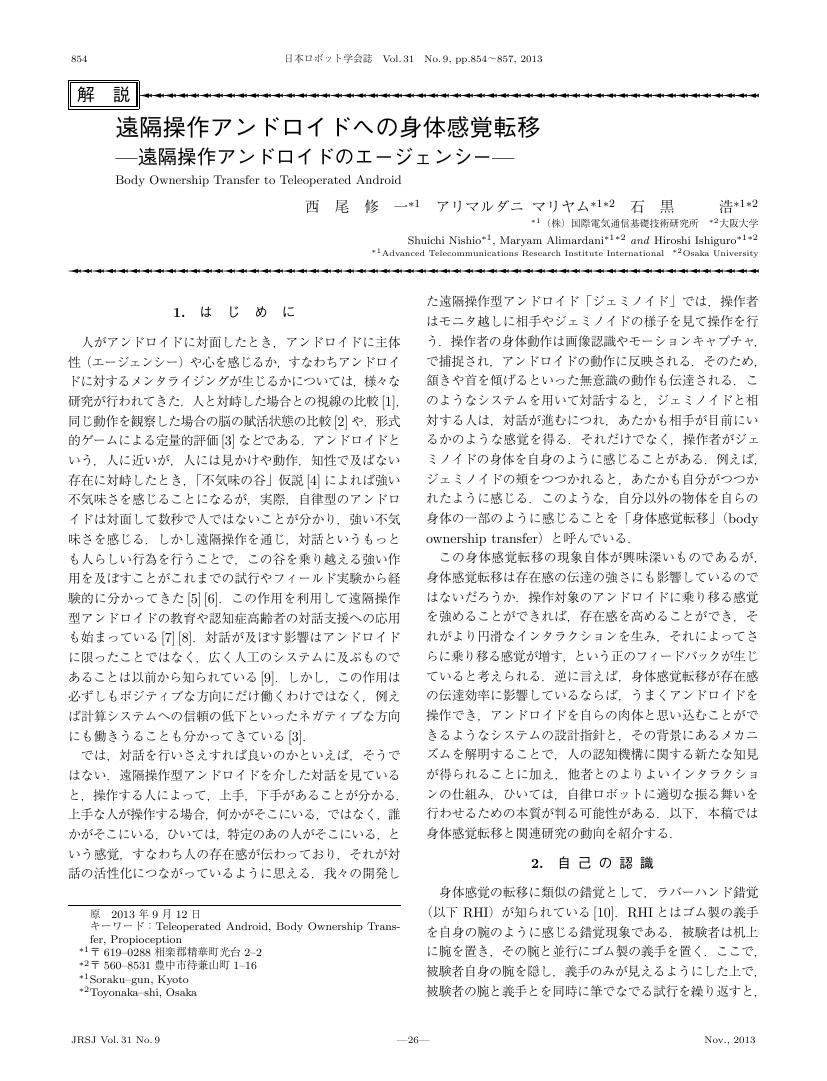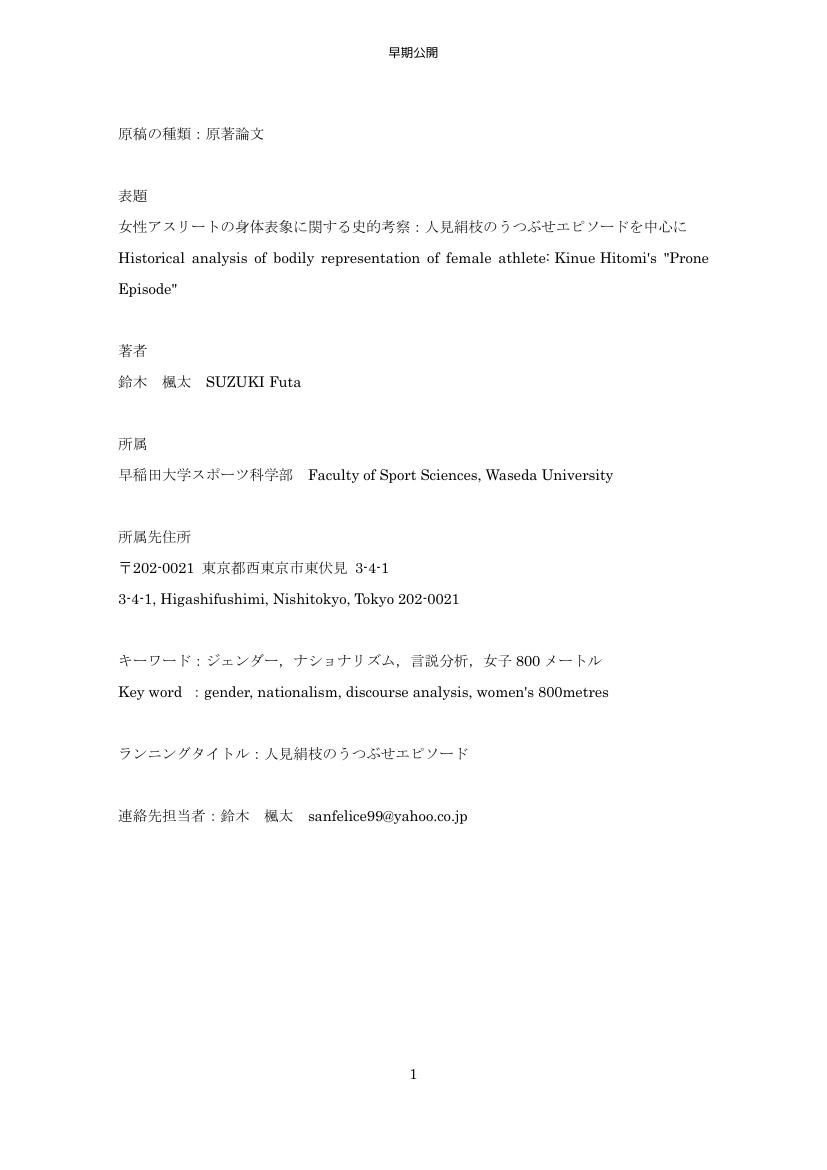3 0 0 0 OA 山田直之著『芦田恵之助の教育思想―とらわれからの解放をめざして』
- 著者
- 村井 万里子
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.30-32, 2021-03-30 (Released:2021-04-01)
3 0 0 0 OA 遠隔操作アンドロイドへの身体感覚転移 —遠隔操作アンドロイドのエージェンシー—
- 著者
- 西尾 修一 アリマルダニ マリヤム 石黒 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.9, pp.854-857, 2013 (Released:2013-12-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
3 0 0 0 OA LE-7エンジンターボポンプと8号機失敗の原因
- 著者
- 今野 彰 坂爪 則夫
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.139-146, 2001-03-10 (Released:2011-07-11)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 機械学習による全反射蛍光X線分析の高感度化
- 著者
- 菊田 真也 山上 基行 河野 浩 堂井 真
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.9, pp.463-470, 2020-09-05 (Released:2020-11-11)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
全反射蛍光X線(TXRF)分析はX線を極めて低角度で試料に入射させることで試料表面の微量元素を高感度に分析する手法である.TXRFは半導体製造工程管理に広く用いられており,Siウェーハ上の汚染評価を行うことができる.半導体デバイスの微細化,高性能化の要求から半導体製造工程は年々複雑になっており,汚染評価の重要性が高まるのに伴い,TXRF測定装置の高感度化,高機能化に向けた装置開発を行っている.本稿では,データ分析の観点からTXRF分析に機械学習を応用した取り組みについて紹介する.TXRF測定で得られた約9000個のデータを教師データとして,畳み込み層が1層,隠れ層が4層のニューラルネットワークモデルに投入し,波形プロファイルと含まれる元素,含有量の関係を学習させた.その後,波形プロファイルのみを投入することで含まれる元素と含有量を推定させた.その結果,短時間測定において従来のピークフィットによる手法では見逃していた元素を検出することができ,長時間測定と同等の結果が得られた.本稿ではTXRFにおける機械学習による高感度化の可能性について論じた.
3 0 0 0 OA 東北・北海道における最終氷期以降のブナ林の拡大
- 著者
- 紀藤 典夫
- 出版者
- 森林立地学会
- 雑誌
- 森林立地 (ISSN:03888673)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.69-74, 2015-12-25 (Released:2016-04-15)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
最近の研究成果に基づき,東北地方から北海道における最終氷期以降のブナの地史的変遷についてレビューした。花粉分析の結果に基づけば,東北地方北部においても晩氷期以降ブナ属花粉が有意に出現する地点があり,また針葉樹の減少と同時にコナラ属と同調してブナ属花粉が増加する地点は,最終氷期末期にはブナが存在したと考察した。北海道におけるブナの北上は,最近記載された分布北限域の外側の孤立したブナ林の研究や生育適地の研究から,半島脊梁地域を中心に北上した可能性を指摘した。また,北海道に最終氷期の逃避地が存在したとすると日本海側南部(松前半島)であったに違いない。
3 0 0 0 OA 視覚の奥行距離情報とその奥行感度
- 著者
- 長田 昌次郎
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン (ISSN:18849644)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.8, pp.649-655, 1977-08-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3 13
本論文は奥行知覚をもたらす多くの視覚要因の効果を定量的に評価することを目的とする.まず, 評価量として各視距離とその距離における奥行弁別閾との比を奥行感度と定めた.つぎに静止状態での観察および体を左右に動かした状態での観察を4種の視距離について行い, 奥行弁別閾を測定した.その結果より各要因の奥行感度を求め, 距離10m以内では両眼視差がもっとも有効であり, 遠距離では運動速度が最適であれば運動視差が有効であることを確かめた.
3 0 0 0 OA 黒川紀章設計のカプセルと茶室に関する考察 「壺中」の世界観
- 著者
- 和田 菜穂子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.781, pp.1167-1176, 2021 (Released:2021-03-30)
“Nakagin Capsule Tower Building” established in 1972 is a world well-known architecture as a symbol of Metabolism architecture designed by Kisho Kurokawa. The architect regards capsule as living cell which have to be replaced every 25 years in order to realize the recycle system of Metabolism architecture, but never exchanged. “Nakagin Capsule Tower Building” is apartment house for single man. Total 140 capsules are attached to the core shaft. At the same time, he designed his summer cottage “Capsule K” in Karuizawa consisted by 4 capsules as an experimental house. One of them is a tea room, because tea ceremony is his hobby. However, the metabolism movement came to be ended in the late 1970’s, he has continued to design tea room since he built traditional Sukiya Architecture “Kyoju-so” and tea house “Ritsumei-an” in 1979. Kurokawa put the new word “Hana-Suki” for the concept of new Sukiya architecture. Then, he built his own tea room “Yuishiki-an” in 1984 which named from the philosophy of Buddhism. Finally, his last tea room “Takiminoseki” was completed in 2000 collaborate with Japanese painter Hiroshi Senju which is into a concrete box. The author researched his capsule architecture, tea rooms and his texts to clarify his view of capsule and tea room and concluded the following fourpoints: 1. The expression of spoken and written words by Kisho Kurokawa are equal to the expression of architecture. He often created new words for showing his new concept of architecture and published over 100 books and had lectures. It was necessary for him to spread his new philosophy. 2. The fundamental philosophy of the architect was formed by the experience of young ages in Kanie city of Aichi prefecture during the World War II. He learned the Buddhism at junior and high school. For example, not only the name of his tea room “Yuishiki-an” but his main philosophy “Kyosei” is also inspired from Buddhism. He spent his young ages at tea room “Yoshitsu-an” in Kanie. His grandfather was “Sukisha” which is cultural person and Sukiya collector. His grandfather gave a great impact to young Kurokawa and he got the aesthetic eyes at small tea room of traditional Skiya architecture. It led to the concept of Capsule architecture to spend at the minimum space alone. 3. Japanese tradition gave him the inspiration for his new creation. Especially, tea room was regarded as the symbol of Japanese original culture. The concept of Japanese tradition was translated by Kurokawa and got reborn as contemporary architecture. 4. He prefer to use the word “Kochuu” for the minimum space in his late years around 2000. He designed “Takiminoseki” into the concrete box in 2000 which was similar to Capsule architecture. Although the material was different, the concept was the same as tea room at “Capsule K”. For him, the worldview of “Kochuu” which means to feel universe at minimum space, is important to express his concept. He realized the world view of “Kochuu” was unvarying concept and has continued from the beginning of his carrier since “Capsule K” was completed in 1973.
3 0 0 0 OA 嘘と虚構とVR パーキングエリアとテーマパークから
- 著者
- 宮本 道人 青山 一真
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.50-51, 2020-06-30 (Released:2021-03-04)
3 0 0 0 OA 昆虫脱皮とキチン分解酵素
- 著者
- 古賀 大三
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.8, pp.506-512, 1986-08-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 36
3 0 0 0 OA 2017年の香港特別行政区 返還20周年,新長官の就任と新たな政治課題
- 著者
- 倉田 徹
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア動向年報 (ISSN:09151109)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, pp.155-174, 2018 (Released:2019-03-27)
3 0 0 0 OA ファンタジーにAI を読み取る
- 著者
- 宮本 道人
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.329, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)
3 0 0 0 OA 教育委員会制度改革とその課題
- 著者
- 林 紀行
- 出版者
- 関西法政治研究会
- 雑誌
- 法政治研究 (ISSN:21894124)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1, 2017 (Released:2017-05-26)
3 0 0 0 OA シェーンベルクにおける無調音楽の構成原理 : 表現主義的側面を中心に
- 著者
- 浅井 佑太
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.133-144, 2014-06-30 (Released:2017-05-22)
Dieser Beitrag beschaftigt sich mit der freien Atonalitat Schonbergs. Seine zwischen 1908 und 1916 komponierten Werke wurden bisher immer wieder als expressionistisch bezeichnet und nehmen eine besondere Stellung in seinem Oeuvre ein. Dennoch wurden in dieser Hinsicht Spezifika in Schonbergs freier Atonalitat bis jetzt kaum in konkreten Analysen nachgewiesen. Manche Untersuchungen betrachten sogar die freie Atonalitat ohne Rucksicht auf diese Aspekte lediglich als Vorstufe der Zwolftonmusik. Dieser Aufsatz ist ein Versuch, Momente in Schonbergs freier Atonalitat zu beleuchten, durch die sie sich von der Zwolftonmusik unterscheiden lasst. In der Periode, in der er Stiicke in freier Atonalitat komponierte, hatte er eigentumliche Gedanken uber Musik, die eng mit dem Expressionismus verwandt waren und sich von jenen nach der Zwolftonmusik klar unterschieden. Hierzu werden Schonbergs Werke unter Berucksichtigung seiner musik-asthetischen Gedanken analysiert, und schliesslich wird die Beziehungen zwischen den kompositorischen Techniken und seinen Gedanken zu erlautern versucht.
- 著者
- 岩崎 直子
- 出版者
- 日本精神衛生学会
- 雑誌
- こころの健康 (ISSN:09126945)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.52-61, 2000-11-30 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
性的被害の実態と, 被害者および周囲の人々へのサポートに関するニーズを調べるため, 大学生を中心とした男女学生277名を対象に, 質問紙調査を実施した。さまざまな性的被害に関して具体的な行為を提示し, 調査実施時点までの被害経験率を調べたところ, 女性の74.0%および男性の25.0%が何らかの被害経験を持ち「レイプ既遂」の被害率は3.4%であった。そのすべてが「友人・知人」「恋人」などの「顔見知り」から被害を受けた“date/acquaintance rape (DAR)”の被害者であり, 社会に蔓延する“real”rape像にはあてはまらないことがわかった。一方, 被害者を身近でサポートする重要な他者 (=SOs) は, 時に自らも被害の影響を受けることが知られているが, 回答者の約3割は, 自分の身近な人が性的被害経験を持つSOsであった。そのうちの7割以上が自分自身のためにも「何らかのサポートが必要である」と感じていた。これらの結果から, 今後の調査研究と被害者支援の方向性について考察した。
3 0 0 0 OA うがい効果の検討
- 著者
- 河野 えみ子 福井 順子 今井 玲 寺村 重郎 井野 千代徳 山下 敏夫
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.199-207, 2003-02-28 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 2
うがい効果を十分に得るためには, 含嗽剤の殺菌作用と機械的除菌作用を有効に活用することにある.また, 咽頭炎などの感染症には “咽頭型” のうがいを, 口内乾燥症には “口蓋型” のうがいと疾患別のうがい方法を考案して作成したパンフレットを用いてうがいの指導にあたってきた.うがい教室に参加した症例を対象として, うがい効果を検討した.口内乾燥症は「口がかわく場合」のうがい方法を6ヵ月実施後, 40%に自覚的に効果があった.手術を勧められた習慣性扁桃炎患者に「のどが痛い場合」のうがいを6ヵ月実施後, 53%が扁桃炎の発症が減少して改善がみられ, 今回手術を見送った.掌蹠膿疱症14例は「のどが痛い場合」のうがいを6ヵ月実施後, 10例に改善がみられ今回手術を見送った.
- 著者
- 宇都木 昭 田 允實 金 熹成
- 出版者
- The Phonetic Society of Japan
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.30-42, 2008-08-30 (Released:2017-08-31)
日本語(東京方言)におけるダウンステップの存在が古くから指摘されている一方で,近年では韓国語(ソウル方言)にもそれに類する現象が存在するという指摘がある。これらの現象は,フォーカスによってリセットされるという点て共通する。本稿は,これらの現象とそれがリセットされた場合との間の離散性の有無について,それを解明することの理論的重要性を指摘するとともに,範躊知覚実験による解明の試みを報告するものである。実験の結果,どちらの言語に関しても典型的な範躊知覚の特徴は見出されなかった。これにはアクセントの影響や刺激音の自然度の影響という想定外の要因が混入したと考えられるため,離散性の有無に関して現時点で結論を下すのは困難であり,今後方法論の改善を要する。一方で,実験の主目的とは別の点て,いくつかの興味深い結果が得られた。これには,上述のアクセントや刺激音の自然度の実験結果への影響に加え,刺激音提示順の効果,および,F0ピークの役割に関する日本語と韓国語の差異が含まれる。
3 0 0 0 OA ロボットに対する愛着行動の解析
- 著者
- 棟方 渚
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.8, pp.696-699, 2014 (Released:2014-11-15)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 女性アスリートの身体表象に関する史的考察: 人見絹枝のうつぶせエピソードを中心に
- 著者
- 鈴木 楓太
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.19012, (Released:2020-02-10)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 人はなぜ老いるのか-個体老化·寿命のメカニズム-
- 著者
- 石井 直明
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.2, pp.143-148, 2006 (Released:2006-02-06)
- 参考文献数
- 5
近年飛躍的に進んでいる老化研究の結果から,老化のメカニズムがインスリン·シグナル伝達経路やカロリー制限が関係する「エネルギー代謝」と,ヘリケースやテロメアが関係し,細胞老化やガン化につながる「細胞分裂」に集約されてきた.この両者は一見,つながりがないように思えるが,エネルギー代謝の副産物として産生される活性酸素による傷害が細胞分裂の停止や細胞死,ガン化に関与することや,インスリン·シグナル伝達経路が細胞分裂を制御しているという報告があることから,老化の基本的なメカニズムが1つのネットワークの中に描かれる日が近いことを感じさせる.
3 0 0 0 OA 経絡・経穴の解剖学的並びに臨床的検討
- 著者
- 山田 鑑照 尾崎 朋文 松岡 憲二 坂口 俊二 王 財源 森川 和宥 森 俊豪 吉田 篤 北村 清一郎 米山 榮 谷口 和久
- 出版者
- 社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.27-56, 2006-02-01 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 43
経穴研究委員会 (前経穴委員会) は福岡で開催された第54回全日本鍼灸学会学術大会ワークショップIIにおいて、経絡・経穴について3つの検討テーマを6名の委員により報告した。第1テーマ : 経絡・経穴の解剖学的検討1) 経絡と類似走行を示す解剖構造について (松岡憲二) : 遺体解剖による経絡の走行と神経・血管の走行との類似性についての研究。2) 上肢経絡・経穴の肉眼解剖学的研究 (山田鑑照) : 豊田勝良元名古屋市立大学医学部研究員の学位研究である上肢経絡・経穴の解剖学的研究紹介並びに山田の研究として皮下における皮神経・血管の走行と経穴・経絡との関係についての報告。第2テーマ : 日中における刺鍼安全深度の研究1) 中国における刺鍼安全深度の研究と進展状況 (王財源) : 中国刺鍼安全深度研究で権威のある上海中医薬大学解剖学教室厳振国教授のデータの紹介と最近の中国における刺鍼安全深度研究の進展状況報告。2) 経穴の刺鍼安全深度の研究を顧みて (尾崎朋文) : 尾崎が今まで発表してきた経穴部位の刺鍼安全深度の研究並びに厳振国教授のデータと同じ経穴との比較研究。第3テーマ : 少数経穴の臨床効果の検討1) 少数穴使用による鍼灸の臨床効果 (坂口俊二) : 1~4穴使用による鍼灸臨床効果ついての医学中央雑誌文献の検索・分析。2) 合谷-穴への各種鍼刺激が皮膚通電電流量に及ぼす影響 (森川和宥) : 合谷穴-穴への置鍼刺激、直流電気鍼刺激、鍼通電刺激が皮膚通電電流量に及ぼす影響についての研究。