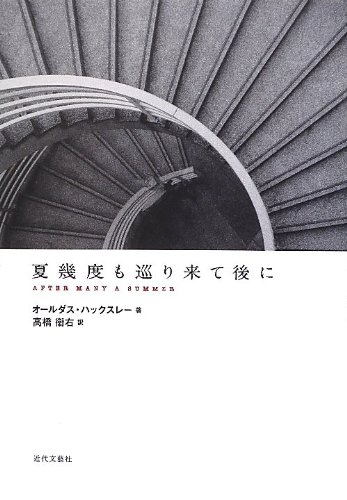1 0 0 0 OA 権力分立(三権分立)論をめぐる研究と問題の整理
- 著者
- 鈴木 陽子
- 出版者
- 東洋大学法学会
- 雑誌
- 東洋法学 = Toyohogaku (ISSN:05640245)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.107-119, 2014-01-15
1 0 0 0 OA 文化財の寿命を延ばすために
- 著者
- 松田 泰典
- 出版者
- マテリアルライフ学会
- 雑誌
- マテリアルライフ学会誌 (ISSN:13460633)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.1-11, 2002-01-31 (Released:2011-04-19)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 「計算過程の部分評価」再び
- 著者
- 二村 良彦
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.340-342, 2004-09-28 (Released:2009-04-27)
1 0 0 0 OA IPWにおける薬剤師-看護師連携のあり方—看護師の立場から
- 著者
- 中島 美津子 孫 大輔 川村 和美 内海 美保
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, no.1, pp.117-121, 2015-01-01 (Released:2015-01-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 2
The concept of interprofessional work (IPW) is becoming increasingly important recently and the role of nurses in IPW seems critical. In Japan, the problem of burnout and turnover of nurses has been recognized, and the solution seems embedded in the scheme of IPW, because it appears to improve their job satisfaction and recognition as health professionals. However, many obstacles lie ahead, such as “tribal conflict” between health professionals including between pharmacists and nurses. Although failure to understand the roles of other professionals or competencies may seem to hamper with the promotion of collaboration, we must realize that even a lack of understanding among nurses exists. The authors believe that the solution is to understand and respect not only other professionals but also colleagues of the same profession.
1 0 0 0 日本心理学会大会発表論文集
- 出版者
- 日本心理学会大会準備委員会
- 巻号頁・発行日
- 1958
1 0 0 0 OA 神戸第2高炉(3次)の吹き止め操業及びN2冷却保存
- 著者
- 西田 功 田中 孝三 上原 輝久 矢場田 武 高野 成
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.189-196, 1985-02-01 (Released:2009-06-19)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
No. 2 blast furnace in Kobe Works was blown in on February 4, 1981 and because of the economic conditions it was blown out on April 22, 1983. Since its working period was very short (about 2.2 years), it was banked with the expectation of blowing in after several years.The methods employed were :(1) to lower the stock line down to just above the level of the SiC brick lining (lower shaft) with the burden being replaced by coke, (2) to cool the furnace by N2 gas, (3) to preserve the furnace brick under N2 atmosphere.Two samples of SiC brick at lower shaft part were collected just after and at 8 months after blowing out, and then they were investigated. It was found that there was no impairment in the SiC brick during this 8-month period.Hot stoves were cooled by the natural cooling method with keeping airtight and their cooling periods were about 3 months. After cooling them, the observations inside them were done and it was confirmed that the damage of the brick was very little, so the reoperation of them would be of no trouble.
1 0 0 0 ウイルス的戦略を用いた生体高分子の適応設計
1.進化分子工学において、ウイルス粒子は、遺伝子型と表現型が一つの結合体になっているので、表現型の評価が即遺伝子型の選択に結びつくため、クローニング操作なしに人為淘汰が行える。これを模擬する試験管無いプロセスとして、無細胞翻訳系でmRNAと新生タンパク分子が結合体となるような系(これを以下in vitroウイルスと呼ぶ)を開発しつつある。in vitroウイルスは、逆転写、PCR増幅、転写という、レトロウイルス様のライフサイクルで増殖する。mRNAと新生蛋白の結合法として、2つの方法を試みた。一つは、その蛋白に組み込まれたビオチン様ペプチドと、mRNAに付加されたアビジンとの結合による。もう一つは、mRNAをtRNAとみなすことができるように改変する方法である。このmRNAの3'末端CCAにシンテターゼを用いて、アミノ酸をチャージする事には成功した。2.進化分子工学は生命の起源のモデルと表裏一体をなす。われわれは、進化分子工学において、遺伝子型と表現型を対応づける戦略としてのウイルス型戦略が、細胞型戦略よりも進化速度の点で有利であることに着目した。RNAワールドから、蛋白質合成系が進化してくる機構として、in vitroウイルス様の生命体があったとするモデルを構築することに成功した。すなわち、RNAワールドに登場する最初のコード化された蛋白質はRNAレプリカーゼ(当然リボザイムである)の補因子に違いないが、その蛋白質補因子はそれがコードされているリボザイムRNAに結合していたとする。すると、RNA複製系と翻訳系が、速やかに安定に漸進的に共進化してくることが、コンピュータシミュレーションで明らかにされた。それは、ウイルス型メンバーを持つハイパーサイクルである。
- 著者
- 髙橋 康汰 小林 稔
- 雑誌
- ワークショップ2019 (GN Workshop 2019) 論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, pp.20-25, 2019-11-07
Twitter や LINE などの SNS を日常的に利用する人が増え,SNS をきっかけとしてコミュニケーションをとる機会が増えている.SNS で食事や遊びなどに誘うメッセージを送信する際,送信者は受信者からの応答を期待するため,応答が得られないとストレスを感じてしまうことがある.そこで,我々はメッセージを送る負担を減らすこと ・送信相手を曖昧にすることの 2 点によって,利用者が感じる期待を減らすことができると考えた.本稿では,これを実現するための非言語呼びかけ方法を提案する.
1 0 0 0 OA アメリカの図書館におけるファンドレイジング
- 著者
- 福田 都代
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.274-292, 2005-01-01 (Released:2017-05-24)
- 被引用文献数
- 2
現在,日本もアメリカ合衆国(以下,アメリカとする)も財政難の折から人件費や資料費の削減が図書館界における大きな問題となっている。日本の公共図書館は公的財源に依存し,代替的な財源を求めるような活動に積極的に取り組んでいない。しかし,アメリカの図書館では館種を問わず,財政危機を乗り越えるため,非営利団体が従来行ってきた資金調達活動(ファンドレイジング)の手法にならい,さまざまなアイデアや手法を考案してきた。本稿ではアメリカの公共図書館と大学図書館における具体的な事例をとりあげ,ファンドレイジングの手法と新たな傾向について概説する。
1 0 0 0 OA 滑空模型による横及び方向安定釣合実験
- 著者
- 山名 正夫 山本 晴之 堀内 武夫 笹島 豊之介
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空學會誌 (ISSN:18835422)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.40, pp.771-778, 1938-08-05 (Released:2009-07-09)
1 0 0 0 夏幾度も巡り来て後に
- 著者
- オールダス・ハックスレー著 高橋衞右訳
- 出版者
- 近代文藝社
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 涙の文化学 : 人はなぜ泣くのか
1 0 0 0 IR オートクチュールの存在理由と展望
- 著者
- 横井 由利
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = Journal of Atomi University, Faculty of Management (ISSN:13481118)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.69-92, 2019-01
壮麗なヴェルサイユ宮殿を作り太陽王と称されフランスに君臨したルイ14世の時代、お洒落の達人としてヨーロッパからロシアまで名を馳せたマリー・アントワネットの時代を経て、「モードの都」パリのイメージは確立していった。19世紀に入ると、イギリスより移り住んだシャルル・フレデリック・ウォルトは現在のオートクチュールのシステムを考案し、その後登場するデザイナーによってオートクチュールビジネスは多様化し発展するが、70年代以降は、時代の変化に伴い衰退と再生を繰り返すことになる。本稿では、オートクチュールのビジネスシステムと文化的な側面を紐解き、スピードと量が問われるデジタル時代にあって、多くの職人の手と時間をかけて完成するオートクチュールの服は、モード界に必要か否か、またそのあり方について論じていく。
1 0 0 0 OA 緘黙症Y子(17歳)のプレイセラピィ ―転移性恋愛について―
- 著者
- 神野 秀雄
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 治療教育学研究 (ISSN:09104690)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-11, 1992-03-29
1 0 0 0 OA 都市における社会性ハチの生態と防除(5)
- 著者
- 松浦 誠
- 出版者
- 玉川大学ミツバチ科学研究所
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.63-75, 2004 (Released:2011-03-05)
- 著者
- 雜賀 玲衣 岡本 健 松居 辰則
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第81回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.3B-017, 2017-09-20 (Released:2020-03-27)
1 0 0 0 OA 自動思考と否定的内容の自己開示との関連
- 著者
- 髙橋 真悠 伊藤 宗親
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.3AM-039, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)