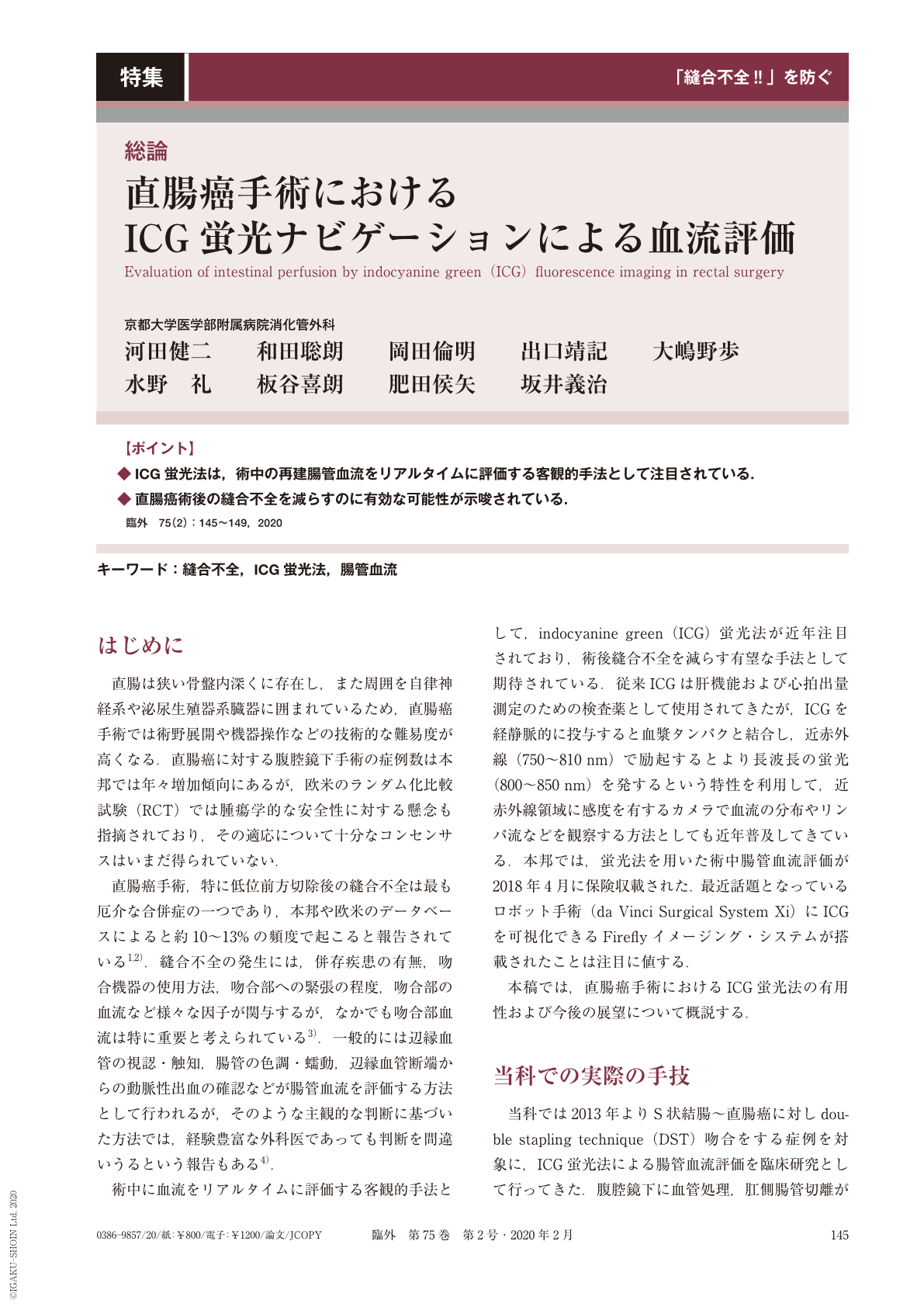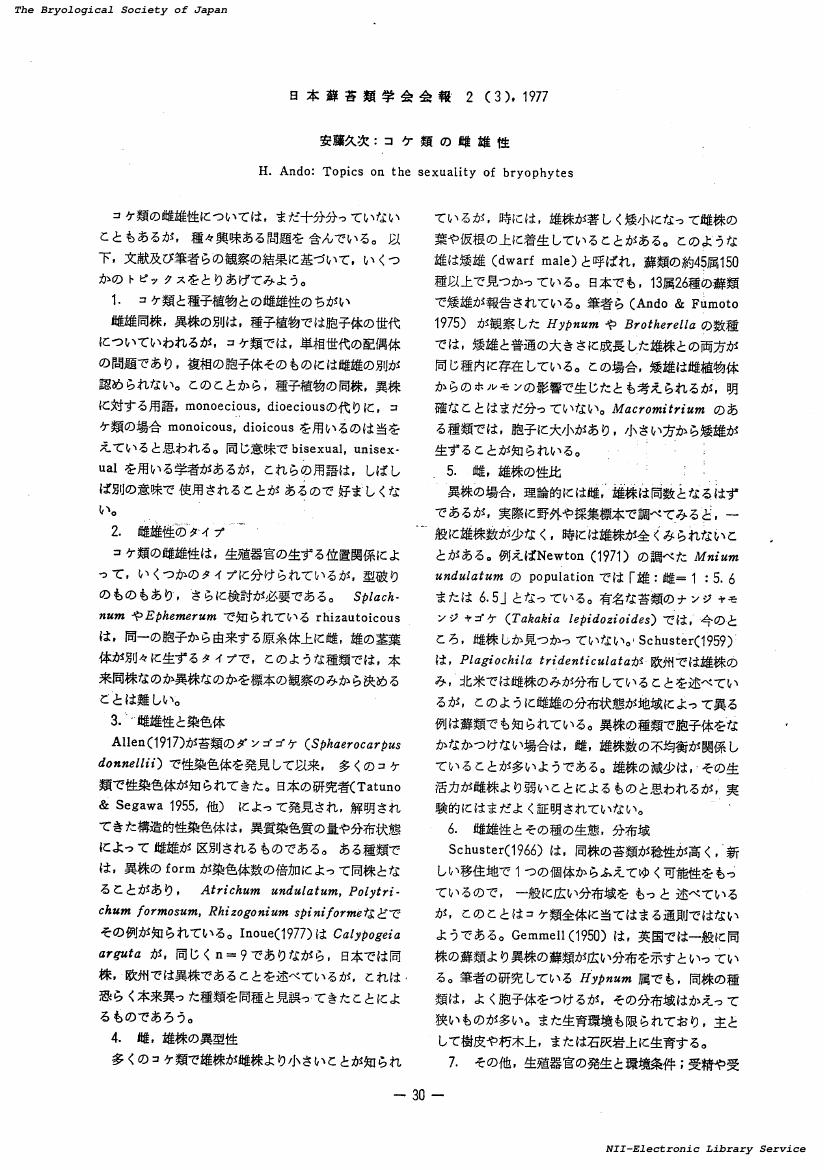1 0 0 0 直腸癌手術におけるICG蛍光ナビゲーションによる血流評価
1 0 0 0 外科医の矜持
- 著者
- 中川 国利
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床外科 (ISSN:03869857)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.2, pp.185, 2020-02-20
急性胆囊炎例に対して即手術をすべきか否か,外科医によって治療方針は異なる. 初期研修時代のボスは痛いと訴えている患者には,「即しかも根治手術をしてあげるのが外科医の責務である」との信念を持っていた.そこで急性虫垂炎例を始め,急性胆囊炎例に対しても手術を即施行した.そこで初期研修後に入局した母校医局で「急性胆囊炎例でも即手術をすべきです」と発言したら大いにしらけ,教授からも非難を受けた.当時の医局は,急性胆囊炎例に対しては保存的治療を行うことが掟であった.
1 0 0 0 OA 協会だより/編集後記
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.108-110, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
1 0 0 0 OA 「本の索引の作り方」藤田節子著
- 著者
- 岩本 登志雄
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.107, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
1 0 0 0 OA INFOSTA-SIG-パテントドクメンテーション部会の活動紹介
- 著者
- 桐山 勉
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.102-106, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
1 0 0 0 メンタルヘルスケア領域における新規サービスの提案
- 著者
- 長谷部 雅彦 杉山 典正 高石 静代 中村 幸子 西田 彩子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.90-95, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
本研究では,特許/非特許,Web,SNS分析などからヘルスケア関連のニーズ・シーズを読み取り,既存技術やセンシング技術を組み合わせた新しいサービスを提案する。サービス提案においては,世代ごとのヘルスケアに関する課題整理から,青年期から壮年期の現役世代で問題となるメンタルヘルスに注目した。また特許・論文調査から,精神状態測定に関連する特許出願や文献が増えていることが分かった。提案では,オフィスにおける生産性向上を実現しつつ,スタッフの「ウェルネス」を高めることを目的とした。また,診断において極力個人を特定しない,プライバシーに配慮したシステムとしてAI技術を用いた新規サービスを提案した。
1 0 0 0 図書館における快適な読書をサポートする家具の研究:椅子
- 著者
- 根来 貴成
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.77-82, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
2016年度から2018年度までの3年間,金沢海みらい図書館で「図書館で過ごす時間を豊かにする椅子」をテーマに,学生デザイン教育に重点をおいたワークショップを通して約60脚の椅子のプロトタイプ制作を行った。研究方法としては,図書館を利用する様々な人の所作と動線を観察し,そこからの気付きを元に図書館における読書を快適にサポートする椅子のプロトタイプ制作を行った。実際に図書館に展示し座ってもらい人気投票の上位に選ばれた椅子の特徴としては,読書環境に着目した椅子,読書の所作や姿勢を考慮した椅子,図書館での一連の行動の流れを重視した椅子が挙げられる。これらの椅子のデザインは,‘みらい’の図書館に新しい読書体験をもたらしてくれると考えられる。
1 0 0 0 図書館が抱える課題と保管什器による解決
- 著者
- 日下 有紀 三木 すずか
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.64-70, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
図書館に設置される書架は「移動棚」と「自立棚」の二つに分けられる。主に閉架で利用されることの多い移動棚だが,移動棚と一口でいっても丸ハンドル式,電動式,アンカーレスなどの種類があり,それぞれがさまざまな図書館事情に起因して開発されている。自立棚も同じように多くの種類が存在する。地震対策を施した自立棚など,棚にはデザイン以外にもそれぞれ個性を持っている。本稿では当社で取り扱う図書館製品(主に移動棚や自立棚,またそれらに取り付けるアイテム)の開発経緯と構造を紹介しながら,図書館が抱える課題と,それに対する保管什器による解決について紹介していく。
1 0 0 0 特集:「家具 ―図書館を支える脇役たち―」の編集にあたって
- 著者
- 久松 薫子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.51, 2020-02-01 (Released:2020-02-01)
資料を並べる書架,それらを見るための机や椅子,こうした家具がなければ図書館は成り立ちません。また,ゆったりと寛ぎながら資料を見る場,活発なコミュニケーションを行う場など,その場の機能を表現し構成するツールとしても家具は重要な役割を果たしています。図書館サービスや運営の向上を考えるとき,資料や利用者に注目し家具は「脇役」として考えがちですが,その重要性を改めて見つめ,本号ではこの脇役たちに焦点を当て,いわば「主役」にして特集を組みました。図書館施設の改装や新築の際に出てくる疑問,例えばどのような機能に特に配慮して家具を選ぶべきなのか,場の機能を表現する家具をどうやって探せば良いのかなど,建築分野の非専門家にとっては難しい課題であり,こうしたことに悩まれたご経験のある読者もおられるのではないでしょうか。この特集では,図書館員が建築分野の専門家とスムーズなコミュニケーションをとるのに必要な知識の紹介のほか,図書館の家具に持たせるべき機能,作り上げたいイメージや機能を家具として具現化させて行った事例を紹介して,新たに施設を作り上げる時の参考となるような内容を目指しました。また,企画段階で大きなテーマとして浮かび上がったのは「地震対策」です。利用者と資料の安全を守るために国内のあらゆる図書館で備えるべき課題であり,ここ数年だけでも大きな地震と被害を受けた図書館の事例をいくつも思い浮かべることができます。こうした経験から得た貴重な知見が数多くあり,今回掲載した原稿のうち多くがこの点に触れて解説をいただきました。植松貞夫氏(筑波大学)には冒頭で,性能・工事・備えるべき家具の種類など基本的知識の解説のほか,家具を選ぶ際に配慮すべき点を概括していただきました。施設について考えるとき図書館員が理解しておくべき内容であり,サイズなど細かな点にも触れていただいていますので,すぐに参考にできる内容です。そしてその原稿の中でも言及されている地震対策について,柳瀬寛夫氏(岡田新一設計事務所)に詳細にご紹介いただきました。この中で,家具そのものだけでなく建物の構造的な配慮といった大きな視点が必要であることを解説いただいています。続いて,図書館家具メーカーの視点から,地震対策その他の図書館の課題に応える家具の紹介と解説を日下有紀・三木すずか氏(金剛株式会社)にお願いしました。主に書架についての解説ですが,そのほかのユーザー目線から新規開発された家具についてもご紹介いただきました。次に事例紹介を二つお願いしました。一つは,複数のプロジェクトにおいて建築側と図書館の運用側の意見を調整するコーディネーターを務められた太田剛氏(図書館と地域をむすぶ協議会)に,もう一つは図書館家具として欠かせない椅子に着目し,「図書館で過ごす時間を豊かにする椅子」を学生・利用者と共に考え作成したプロジェクトを根来貴成氏(金沢美術工芸大学)にご報告いただきました。「図書館施設をより良いものにしたい」その思いを形にする際のご参考になりましたら幸いです。(会誌編集担当委員:久松薫子(主査),稲垣理美,大橋拓真,南山泰之)
1 0 0 0 OA ダランベール著『ラモー氏による理論的・実践的音楽の基礎原理』に関する考察
- 著者
- 片山 千佳子 関本 菜穂子 安川 智子
- 出版者
- 東京藝術大学音楽学部
- 雑誌
- 東京藝術大学音楽学部紀要 (ISSN:09148787)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.17-38, 2008
- 著者
- 福永 奈穂子 佐藤 愼二
- 出版者
- 学校法人 植草学園短期大学
- 雑誌
- 植草学園短期大学紀要 (ISSN:18847811)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.81-89, 2016 (Released:2018-04-13)
1 0 0 0 OA 減資規制・配当規制と合併シナジーの分配
- 著者
- 原 秀六
- 出版者
- 滋賀大学経済学部
- 雑誌
- 滋賀大学経済学部研究年報 (ISSN:13411608)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.107-122, 1997
- 著者
- 西山 啓太 向井 孝夫
- 出版者
- 日本乳酸菌学会
- 雑誌
- 日本乳酸菌学会誌 (ISSN:1343327X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.176-186, 2016-11-18 (Released:2017-12-02)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 1
Lactobacillus 属や Bifidobacterium 属は、哺乳類の消化管に生息する共生細菌である。非運動性のこれらの細菌にとって、宿主腸粘膜への付着は、流動的な腸内環境で定着を有利にする生存戦略のひとつであると考えられる。近年、 Lactobacillus 属や Bifidobacterium 属の遺伝子ツールや解析技術が確かなものとなり、菌体表層のアドヘシンを介した宿主腸粘膜との相互作用が分子レベルで明らかにされてきた。本総説では、近年研究が進んでいる Sortase 依存性の表層タンパク質である Mucus-binding proteins(MucBPs)と線毛に着目し、これらを介した Lactobacillus 属や Bifidobacterium 属の腸粘膜への付着性に関わる分子機構について、我々の研究成果を交えながら述べたい。さらに、 Lactobacillus 属の付着特性を利用した病原細菌の感染予防に関する取り組みについても紹介したい。
1 0 0 0 OA 甲状腺疾患に対する超音波を用いた診断法に関する研究
- 著者
- 東野 英利子 Tono Eriko
- 巻号頁・発行日
- 1989
筑波大学医学博士学位論文・平成元年3月25日授与 (乙第517号)
1 0 0 0 OA 診療事故と新しい判例
- 著者
- 寺畑 喜朔
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.11, pp.865-866, 1971-11-20 (Released:2011-10-19)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 教育におけるICT活用について( 1 )
- 著者
- 片山 雅男
- 出版者
- 学校法人 夙川学院 夙川学院短期大学
- 雑誌
- 夙川学院短期大学研究紀要 (ISSN:02853744)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.46, pp.3-15, 2019 (Released:2019-10-31)
- 著者
- 辰野 誠次
- 出版者
- 公益社団法人 日本植物学会
- 雑誌
- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.585, pp.628-635, 1935 (Released:2007-05-24)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 2
1. 予ハうろこごけ目19種ノ Heterochromosomen ニ就テ觀察ヲ行ツタ。此等ノ中 Madotheca 屬ノ4種ハ1個ヅツノ Heteroechromosom Hノミヲ有スルガ, 他ノ15種ハ何レモ2個ヅツノ Heterochromosomen H, hヲ合セ有ス。2. 苔類ノ Heterochromosomen ハ屡ゝ性染色體トシテ分化シテヰル。此等性染色體ハ二系統ニ大別サレ, H-染色體カラ分化シタモノトh-染色體カラ分化シタモノトガアル。而シテH,hハ互ニ起源ヲ異ニスルモノデアルカラ, 從ツテ苔類ノ性染色體ハ二種ノ起源ヲ有スルコトガ明デアル。3. Calobryum rotundifolium ハH, hヲ合セ有スルガ, 兩者ノ中Hノミガ分化シテ雌雄ノ間ニ性染色體トナツテヰル。
1 0 0 0 マルクス主義とフェミニズムの接点
- 著者
- 原口 剛
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, 2019
<p><b>1.はじめに—寄せ場研究からの問い</b></p><p></p><p> 地理学における寄せ場研究の先駆である丹羽弘一は、1990年代初頭に、寄せ場のジェンダー問題という困難な問いに取り組んだ(丹羽 1992, 1993)。すなわち、釜ヶ崎で起きた性差別事件や糾弾を受け止め、研究者のアイデンティティと立場性を問うたのである。その自己批判と学界制度への批判は、いまなお際立った重要性をもつ。他方で、丹羽の問いを継承しつつ乗り越えることは、現在の私たちの責務であろう。たとえば丹羽は、自らの内なる権威主義を振り払うべく、生身の人間として他者と「ぶつかりあう」よう訴える(丹羽 2002)。だがそれでも、私たちはフィールドの他者から研究者として視られるだろうし、その立場を隠すわけにはいかないだろう。とするなら、私たちがフィールドの他者に関わり、社会的現実と切り結ぶには、研究という活動によるしかない。</p><p></p><p>このような問題意識にもとづき本報告では、かつて丹羽が成したように、路上の運動の声や実践に応答しうる理論の視角を模索したい。具体的には、野宿者運動の状況と、地理学の理論的動向という2つの地平を取り上げる。それぞれの地平において、フェミニズムの視角はいっそう重要なものとなりつつある。かつ、フェミニズムからの問いは、90年代とは異なる射程を有している。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>2.運動の状況—寄せ場から野宿者運動へ</b></p><p></p><p> 1990年代以降の寄せ場では、日雇労働者の大量失業がもたらされ、都市の公共空間に野宿生活が広がった。この現実に直面して、運動の姿勢は2つに分岐した。既存の労働運動は、野宿を非本来的な生活として捉え、そこからの脱却と労働市場への復帰を最優先課題とした。これに対し野宿者運動は、彼らの実存を肯定し、公共空間においてその労働・生活を守ろうとした。</p><p></p><p>後者の野宿者運動は、90年代末に現れた潮流である。この新たな運動は、既存の運動の枠を超えた実践を志向した。第1に、寄せ場の運動における労働者主体の把握は、あまりに狭く限定的だった。なぜなら、野宿生活者は下層労働市場からも排除されており、彼らが従事するのはアルミ缶集めなどの都市雑業である。第2に、公園などの占拠や反排除闘争は、最も重要な実践であった。ゆえにこの運動は、世界各地のスクウォット闘争を参照し、公共空間とはなにかを問うた。そして第3に、この潮流において、フェミニズムの声や実践は無視し得ないものとなった。その異議申し立ての声は、性差別の問題はもちろん、それを下支えする国家と資本主義への対抗へと向かっている。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>3.理論の動向—マルクス主義とフェミニズム</b></p><p></p><p>路上の運動が変転を遂げているならば、理論も同じ場所にとどまるわけにはいかない。丹羽が議論を展開していた90年代においては、文マルクス主義とアイデンティティの政治は鋭く対立し、フェミニズムもまた後者の陣営に数えられていた。だが2000年代に入ると、マルクス主義とフェミニズム双方のなかで、重大な転換が生じたように思われる。</p><p></p><p>一方のマルクス主義地理学において、その代表的論者であるD・ハーヴェイ(2013)は、本源的蓄積の再読を通じて「略奪による蓄積」という概念を提起した。そしてこの概念にもとづきつつ、「労働の概念は、労働の工業的形態に結びつけられた狭い定義から……日常生活の生産と再生産に包含されるはるかに広い労働領域へとシフトしなければならない」と明言する(p. 239)。このように再生産領域を重視することでハーヴェイは、潜在的にであれ、フェミニズムとの交流可能性を開いた。</p><p></p><p>他方のフェミニズム研究においても、おなじく本源的蓄積がキー概念として浮上しつつある。たとえばS・フェデリーチ(2015)は、女性の身体をめぐる抗争が、資本主義の形成史において決定的な戦略の場であったことを論じた。そのことによりフェデリーチは、賃労働や労働市場を自明の前提とするのではなく、労働市場が形成される過程のうちに見出される抗争こそ、階級闘争の根底的な次元であることを看破した。</p><p></p><p></p><p></p><p><b>4.おわりに</b></p><p></p><p>運動における新たな志向性と、研究における理論の動向とは、別々の局面でありながら、同じ方向へと進んでいるように思われる。そして双方の地平において、フェミニズムの声や理論は欠かせない契機となっている。そこから、いくつかの命題や課題が見出される。第1に、本報告でみたフェミニズムの実践や理論は、アイデンティティの政治を超え出て、資本主義と階級に対する批判的視角を打ち出している。よって、ジェンダーの視点と階級の視点とを、互いに切り離すことはできない。第2に、この理論的地平において、労働の概念を問い直しは中心的課題の一つである。つまり、労働市場の内側だけでなく、その外側に広がる搾取や略奪の機制を捉える視点が求められている。</p>
1 0 0 0 OA コケ類の雌雄性(第6回大会講演要旨)
- 著者
- 安藤 久次
- 出版者
- 日本蘚苔類学会
- 雑誌
- 日本蘚苔類学会会報 (ISSN:02850869)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.30-31, 1977-12-15 (Released:2018-07-03)
1 0 0 0 極限寿命生物の活動的長寿の分子基盤
なぜ生物は老いるのか?この問いに答えることは、至近要因的にも進化的・究極要因的にも生物学の最重要課題である。近年の分子生物学的手法の発展により、老化や生理寿命の分子基盤に対する理解は急速に進んできている。しかし、主要な研究は線虫・ショウジョウバエ・マウスといった短命なモデル生物を用いて行われてきた。本研究では、70年以上の寿命をもつと推定されるヤマトシロアリの王に着目し、従来の短命なモデル生物の研究では到達しえない寿命研究の全く新しい領域を開拓するものである。最新の研究により、孵化した幼虫がワーカーとして発育するか、羽アリとして発育するかのカースト決定に、フェロモンだけでなく、ゲノムインプリンティング(精子・卵特異的なエピジェネティック修飾)が影響することが明らかになった。カースト分化に対するインプリンティングの効果を検証するため、まず若い王に対してDNAメチル基転移酵素(DNMT1、 DNMT3)をターゲットとしたRNAiを行い、精子のエピジェネティック修飾を操作し、コロニーを創設させた。現在、子のカースト分化への影響を評価している。王の代謝活性は全体として年齢とともに変化するのか、また、どの代謝経路が駆動しているのかを判別するために水同位体比アナライザー(PICARRO社 L2140-i)を用いた二重標識水法により、代謝フラックス解析を行っている。現在、標識水投与による生存への影響評価を完了し、本試験の実施中である。ヤマトシロアリのワーカーは王と女王に対して特殊な餌(以後、ロイヤルフードと呼ぶ)を給餌している。このロイヤルフードの成分を特定し、その機能を明らかにするため、ワーカーから王と女王への口移し給餌物の直接採取、および解剖によって中腸内容物を回収した。現在、MALDI-IT-TOF 型顕微質量分析装置を用いて成分を分析中である。