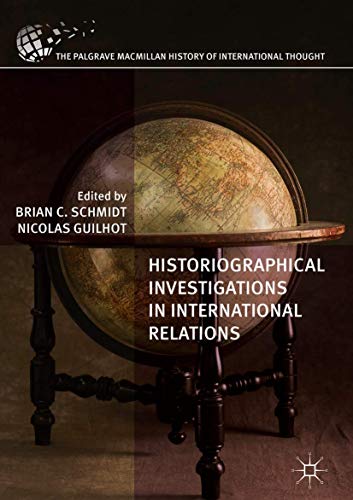1 0 0 0 フォークランド諸島の防衛をめぐるイギリスの政策
- 著者
- 篠﨑 正郎
- 出版者
- 国際安全保障学会 ; 2001-
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.97-115, 2017-06
1 0 0 0 OA 磁気緩和現象
- 著者
- 富田 和久
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.1-10, 1958-01-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 60
1 0 0 0 243年貯蔵酒の性状と成分について
- 著者
- 江村 隆幸 岡崎 直人 石川 雄章
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.9, pp.726-732, 1999
243年前 (宝暦6年, 1756年) に仕込んだ古酒が新潟県関川村, 渡邉家で発見され, 官能評価及び成分分析を行った結果, 以下のことが明らかになった。<BR>1.官能評価の結果, 外観等の性状は濃暗褐色で濁りはなく粘度が高く, 強い酸味と甘味及び若干の苦みを有し, 香りは強い老香様を呈していた。<BR>2.現在の清酒に比較して, 酸度およびグルコース濃度は高く, pHは低く, また, 酸度の割にアミノ酸度は低かった。<BR>3.有機酸は, コハク酸及びクエン酸を除き測定した全ての成分において多かった。また, リン含量が多かったがその理由として, 当時の製法が玄米または低精白米を使用したことが推察された。<BR>4.アミノ酸含量は, 測定した20アミノ酸全てについて現在の清酒に比較して少なく, 特に塩基性アミノ酸及び含硫アミノ酸が少なかった。<BR>5.酢酸エチル, 酢酸イソアミル, イソアミルアルコール, イソブチルアルコール及びn-プロピルアルコールの香気成分が同定された。<BR>6.アルコール濃度は約2%と低く, 貯蔵開始時の容積の約35%が蒸発したためと考察した。<BR>7.以上の結果から, 当初詰められた酒は糖分と酸の多い現在の酒母に近い酒であったことが推察された。<BR>最後に, 243年古酒を提供していただいた渡邉家保存会理事長渡邉和彦氏に厚く御礼申し上げます。また, 本報告にあたりご協力賜りました大洋酒造 (株) 平田大六氏に深謝いたします。
1 0 0 0 OA 反PDCA論
- 著者
- 吉澤 剛
- 出版者
- 研究・技術計画学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.347-350, 2011-10-15
一般講演要旨
- 著者
- 遠藤 由香
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.8, pp.733-740, 2010
- 参考文献数
- 27
目的:思春期過敏性腸症候群(IBS)の疫学的特徴を明らかにする.方法および対象:中学3年生にアンケート調査を施行した.質問紙にはRIIMQ,SIBSQ,GSES,SF-36v2を用い,さらに睡眠やストレスなど生活に関する質問を付加した.結果:男子106名(12.7%),女子145名(16.3%)がIBSと診断された.全員IBSの治療歴はなく,有症状率に地域差はなかった.IBSの腹部症状に大きな男女差はなく,ストレスによる症状増悪は女子に多かった(p<0.05).IBS群は対照群に比して,睡眠障害,ストレスやトラウマ(各p<0.01)をより多く訴えた.IBS群では,女子のほうが男子よりストレス,トラウマを多く訴えた(各p<0.05).IBS群は対照群よりGSESとSF-36v2の全下位尺度で得点が低かった(各p<0.01).結論:思春期IBSでは性差の面で成人とは異なる傾向が認められた.
1 0 0 0 OA 大東亞戰爭完遂 國民總力結集大演説會に於ける講演(一)
- 著者
- 内閣總理大臣 東條 英機
- 出版者
- コロムビア
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA 複視を呈した症例に対する眼球運動課題の考案
- 著者
- 田村 正樹 中 優希 久保 有紀 渕上 健
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1149, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】複視とは,脳血管障害などが原因で物体が二重に見える症状である。物体の見えにくさから日常生活動作(以下,ADL)に支障をきたすが,具体的なリハビリテーション介入に関する知見は少ない。今回,複視を呈した症例に対して,自動車運転の獲得を目標にレーザーポインターやミラーを用いた眼球運動課題を考案し介入したことで退院後に目標達成に至ったため,報告する。【方法】症例は59歳,男性。診断名はクモ膜下出血と右視床梗塞。発症2週後の眼科受診で右外転神経麻痺と診断された。発症4週目に当院入院となり,入院当初から運動麻痺や感覚障害は認められず,ADLは歩行で自立していた。その他の所見として,Berg Balance Scaleは56/56点,Mini Mental State Examinationは30/30点,Trail Making TestはPart-A36秒,Part-B81秒であった。職業は内装業であり,復職と自動車運転の獲得を希望されていた。発症9週目で内装業に必要な動作が獲得できたため,眼球運動課題を開始した。このときの眼球運動所見は,peripersonal spaceの物体を正中から右側に20cm以上,左側に30cm以上追視した際に複視が出現し,10分程度で眼精疲労が確認された。さらに,personal spaceからextrapersonal spaceへの切り替えを多方向に行うと,複視により3分程度で気分不良が確認された。複視は右側のextrapersonal spaceへの追視の際に著明であった。眼球運動課題はレーザーポインターを用いたポインティング課題,ミラーを用いた識別課題を方向や距離,速度,実施時間を考慮して行った。レーザーポインターを用いたポインティング課題では前方と側方の安全確認と信号の認識を想定し,頭頸部回旋運動を取り入れてレーザーの照射部位を追視するように教示して実施した。ミラーを用いた識別課題ではバックミラーとサイドミラーに映った自動車の認識を想定し,各3方向のミラーに映った対象の詳細や距離について正答を尋ねた。【結果】発症11週後には,peripersonal spaceにある物体の追視では正中から左右ともに35cmまで複視が出現せず可能となった。peripersonal spaceでの眼球運動は40分程度,personal spaceからextrapersonal spaceへの切り替えを多方向に行う眼球運動では30分程度問題なく行えるようになった。発症12週目に自宅退院となり,最終的には自動車運転の獲得に至った。【結論】本症例は右外転神経麻痺による両眼球の共同運動障害により複視が生じていた。personal spaceからextrapersonal spaceへの切り替えを多方向に行うレーザーポインターやミラーを用いた眼球運動課題を組み合わせることにより,複視の改善に至ったと考える。
1 0 0 0 ハイネとマルクス--「貧しき織工」をめぐって
- 著者
- 井上 正蔵
- 出版者
- 東京都立大学人文学部
- 雑誌
- 人文学報 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.36-73, 1966-05
1 0 0 0 OA 無形文化遺産の記録保存における歴史と課題 ―無形民俗文化遺産を中心に―
- 著者
- 山路 興造
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.135-141, 2016 (Released:2016-05-15)
- 参考文献数
- 5
Since the Law for the Protection of Cultural Properties was established in 1950, our country has been producing a record of intangible cultural properties, which are characterized as non-physical objects to be protected, as well as tangible cultural properties. The details of the movement of intangible cultural properties could not be recorded because papers were mainly used for recording. Videotapes or DVDs have recently become popular, thus enabling the recording of intangible cultural properties. The method of recording the on-stage performances of professionals in national theaters is applied to the recording of intangible cultural properties. However, as for the intangible cultural properties succeeded by local festivals, discussions on how they should be preserved have just begun, and there are as yet only a few places to store and exhibit them.
1 0 0 0 OA 馬琴と小津桂窓の交流
- 著者
- 菱岡 憲司
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, pp.16-29, 2009 (Released:2017-04-28)
1 0 0 0 OA 大腿四頭筋機能と歩行能力の関係
- 著者
- 伊東 元 橋詰 謙 齋藤 宏 中村 隆一
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.164-165, 1985-05-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 11 3
健常男性20名に最大速度で歩行を行わせ,速度,歩幅,歩行率と大腿四頭筋の最大等尺性収縮トルク(MVC)およびMotor time(MT,急速膝伸展時の筋活動開始から運動開始までの潜時)との連関を検討した.速度の有意な決定因は体重,MVCで,体重が軽くMVCが大きいと速度が速かった.速度は歩幅,歩行率と正の相関を示すが,歩幅と歩行率との間には負の相関があった.この歩幅と歩行率の両者にとって有意な決定因はMTで,MTが短いと歩幅は大きくなり,MTが長いと歩行率は大きくなった.
1 0 0 0 OA ブックレビュー : 浅見克彦・山本ひろ子編『島の想像力-神話・民俗・社会』
- 著者
- 塩崎文雄
- 出版者
- 和光大学
- 雑誌
- 東西南北 : 和光大学総合文化研究所年報
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, 2011
1 0 0 0 OA N95マスク装着における集団実技指導の効果
- 著者
- 小川 謙 横岡 真由美 石角 鈴華 斉藤 容子
- 出版者
- Japanese Society of Environmental Infections
- 雑誌
- 環境感染 (ISSN:09183337)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.91-95, 2006-06-30 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 9
N95マスクの装着に際し, フィットテスト, フィットチェックによるトレーニングが重要であると言われている. 今回, 我々は自己流で装着した場合, どの程度正しくマスクがフィットしているのかの実態調査を行い, また集団指導でもフィットチェック及びフィットテストを含む実技指導は効果があるかを検証した. その結果, S病院に勤務する職員79名の内61%が, 自己流ではマスクがフィットしていなかった. さらに, フィットしなかった職員を「指導群」「非指導群」の2群に分け, 集団実技指導の効果を検討したところ,「指導群」において有意にN95マスクがフィットするようになつた (P<0.05). このことから, 指導の重要性が明らかとなり, 方法は個別指導でなくとも, 集団指導でも効果があることが示唆された. 一方, 指導した群においても36%がフィットしなかった. これらの職員に対しては, 個別指導を加え, さらに密着性が得られない場合は, フィットするマスクの選択ができるよう, 数種類の常備が必須である.
- 著者
- ローレンス・カーニアック著 円城寺敬子〔ほか〕訳
- 出版者
- 第三書館
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 叡山点の成立について
- 著者
- 宇都宮 啓吾
- 出版者
- 訓点語学会 ; 1954-
- 雑誌
- 訓点語と訓点資料 = Diacritical language and diacritical materials (ISSN:04546652)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, pp.38-49, 2018-03
1 0 0 0 OA 感染予防対策におけるN95マスク装着効果について
- 著者
- 栁澤 千香子 押見 雅義 鈴木 昭弘 齋藤 康人 高橋 光美 鹿倉 稚紗子 洲川 明久
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1117, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに】当センターは高度専門医療を担っており一般病棟268床の他,第二種感染症指定医療機関として51床の結核病床を有する。結核患者に対してのリハビリ介入も行っており,理学療法部の24年度新規依頼件数1223件のうち結核患者27件であり,全件数の2.2%を占めている。結核患者の理学療法実施にあたり,N95マスクを装着し他患者との接触を避けるため隔離病棟でのベッドサイド対応で感染予防を行っている。N95マスクの使用頻度は高いが,装着方法についてはマニュアルに記載されている程度で十分教育されてはいない。N95はフィルターの性能を示すものであり,装着後のマスクと顔の密着性は保証されていないため,米国では最低年1回のフィッティングテスト実施を勧告している。感染リスク抵減のため,N95マスクの正しい装着方法をマスターする事・自分の顔に合うマスクを見つけることを目的として,フィッティングテストを行う事が必要である。今回リハビリ部門において,N95マスクを使用しての定量的フィッティングテストを施行し教育効果の検証を行った。【方法】対象は当センターのリハビリスタッフ7名(PT6名・リハ医1名)。N95マスクは2種類使用した(マスクA:3M三つ折りマスク,マスクB:KOKENハイラック350型)。定量的測定は,労研式マスクフィッティングテスターMT-03型を使用(大気じんを使用してマスク内外の粉じん量の測定により漏れ率を測定)した。漏れ率5%以下で適合すると判定した。1回目の測定は,全員にマスクAを通常使用している方法で装着してもらい行った。2回目の測定は非適合の者に対し装着の方法・息の漏れがないか確認するためのユーザーシールチェック方法の指導後行った。3回目の測定は全員にマスクBを使用して行った。1回目の測定の際,装着方法が正しいか・ユーザーシールチェックを行えているか観察した。また,アンケートを行い基本的な装着方法を知っていたか・N95マスクの交換頻度等について調査した。【説明と同意】対象者には施行内容について主旨の説明後,同意を得て実施した。またアンケートは個人情報に配慮した。【結果】1.マスクAでは7名中3名が適合した。適合者平均0.88%(0.7~1.11%)・不適合者平均7.97%(5.02~9.99%)であった。不適合者の指導後の再測定では全員適合であった(全体平均1.52%)。2.マスクBでは全員適合した。全体平均0.54%(0.38~0.88%)。3.観察にて装着そのものができていなかったのは2名・装着やユーザーシールチェックまでできていたのは4名であった。できていた4名のうち不適合は2名であった。4.アンケートでは,N95マスクの装着方法を知っているは2名・だいたい知っている4名・知らない1名であった。ユーザーシールチェックまで意識して行っているのは1名・行っていない(知らない)3名であった。N95マスクの交換頻度は毎日5名・1週間ごと2名であった。【考察】マスクAでの適合者は,ユーザーシールチェックを意識して行えていた者・無意識で行っていた者・装着もできていなかったが偶然顔の形で適合した者が1名ずつであった。マスクBでは,装着方法の指導後の結果であったため適合者が増えた結果となった。ユーザーシールチェックに関しては,4名が行えていた。意識して行っているのは1名で他は無意識で行っていた。無意識で行っていたうち適合したのは1名であり,しっかり意識付けして行う事が必要である。N95マスクの交換頻度は,使い捨てが原則であるが実際にはばらつきがあった。衛生面でも統一した知識の共有が必要である。当センターでは,N95マスクを3種類採用しているが装着感のみで自己選択している現状である。しかし1種類のもので検証した結果,適合の割合は個々の顔の形や大きさにより8~9割程度のみとの報告もある。自分にフィットする製品を知っておくことも必要である。アンケートより今回定量的測定を行った事で,漏れを数値で確認でき客観的にわかりやすかった・結果が良かったので安心した・ユーザーシールチェックを行うことで,漏れる場所のポイントが分かり漏れが改善した等の反応があった。国内での結核罹患率は欧米諸国と比べると依然として高く,未だ年間2万1千人以上が新規に登録されている。また結核病床を有する病院での医療従事者の結核罹患率は,一般の発生率の3倍とされている。感染予防のためにも正しいN95マスクの装着方法について継続的な教育が大切である。【理学療法学研究としての意義】N95マスクの装着に関して定量的なフィッティングテストを行う事で,視覚的に正しい装着方法を学習できる。感染リスク軽減のために正しいマスクの装着についての教育・啓発は必要なことであると考えられる。
- 著者
- Brian C. Schmidt Nicolas Guilhot editors
- 出版者
- Palgrave Macmillan
- 巻号頁・発行日
- 2019
- 著者
- 武藤 拓之 水原 啓太 入戸野 宏
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第17回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.2, 2019 (Released:2019-10-28)
複数の選択肢の中から1つを素早く自由に選択する課題において,自分がどれを選択したかについての意識体験が後付け的に決定されるという現象が知られている。このポストディクション現象は,視覚情報が無意識的に処理されてから意識に上るまでの時間差に起因すると考えられてきた。しかし,従来のモデルは現象の言語的な記述に留まっており,数理的妥当性の検証は不十分であった。そこで本研究は,先行研究の理論的考察を踏まえた仮定から,自由選択の認知過程を表現するシンプルな確率モデルを導出し,このモデルでポストディクション現象が説明できるか否かを検証した。水原・武藤・入戸野 (2019) の2つの実験課題から得られたデータにモデルを適用した結果,全てのデータをこのモデルでよく説明できることが確認された。また,無意識的な処理が意識に上るまでの時間差や選択に要する時間の分布といった有意味な情報を推定できることも示された。
1 0 0 0 OA 鳥類における生活史研究の最新動向と課題
- 著者
- 堀江 明香
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.197-233, 2014 (Released:2015-04-28)
- 参考文献数
- 351
- 被引用文献数
- 3
鳥類は生活史進化の研究において最も古い研究対象であるが,今なおその進化機構の解明には議論が続いている.Ricklefs(2000a)は生活史進化の研究史を2つに分けた.第1期はLackを初めとする鳥類学者が生活史を自然選択の枠組みで捉え,その進化について議論を開始した時期,第2期は生活史理論が成熟してその進化機構を実証しようと研究が進められてきた時期である.この第2期の流れは現在も続いているが,2000年前後を境に生活史進化の分野には新たな視点が加わり,研究は次のステージに入ったと考えられる.つまり,一腹卵数以外の生活史形質への研究拡大,餌資源の制約や捕食以外の新たな選択圧の探索,そして生活史を規定する内的機構の解明といった視点である.これらの研究によって,生活史進化を複合的・総合的に説明する土台が築かれつつある.本稿では,このような研究の転換から10-15年経った現時点において,新旧の選択圧が生活史に与える影響はどの程度検証されているか整理した.それぞれの選択圧についての検討には,個体や個体群内での影響を評価した可塑的なものと,種間比較や個体群間比較などから進化的な影響を推察したものがあったが,後者については検証が不十分なものが多かった.これらの問題点を含めて鳥類における生活史進化の現状と課題を議論し,日本における生活史研究の方向性について述べる.