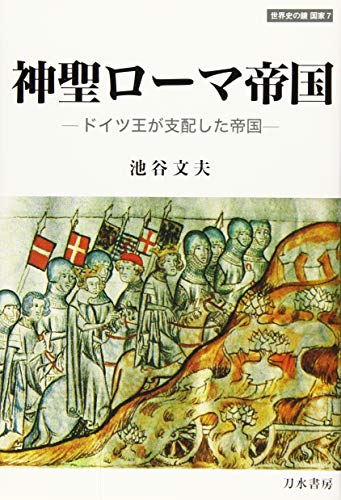1 0 0 0 OA サファヴィー朝年代記とトルコ暦(十二支)の導入
- 著者
- 後藤 裕加子
- 出版者
- 東洋史研究会
- 雑誌
- 東洋史研究 (ISSN:03869059)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.663-631, 2008-03
In Islamic historical writing the canonical Hijra calendar was ordinarily used to date historical events. In the area where Persian was the main written language of the inhabitants, historians began to write in Persian, but the Hijra calendar remained in use. After the Mongol invasion, the cyclical Chinese-Uighur calendar, in which the years were represented by a series of twelve animals, was introduced and used in parallel with the Hijra calendar in Persian historical writing and in dating the issuance of farmans (royal decrees). After the fall of the Il-Khanid dynasty in the first half of the 14th century, the use of the solar animal calendar in Persian historiography became rare, even though it was still in use in administrative affairs. The Safavid dynasty, which had taken control of Persia in 1501, revived the use of the animal calendar, in the form of the Turkish calendar, sal-i turki. A special characteristic of this calendar is the conformity of New Year's Day with nauruz (New Year's Day) of Persian origin. Then in the later reign of Shah Tahmasb I and that of Shah Sultan Muhammad Hudabandah, most of the farmans that were issued between the late 960's (the early 1560's) and the late 990's (the late 1580's) had a corresponding animaldesignated year in addition to a Hijra date. This period corresponds to the period when the Turkish calendar was given precedence over the Hijra dates in the Safavid chronicles, and both calendars were used in tandem. In the reign of 'Abbas I, dates based on the coronation of the shahs were added to supplement the dates from the Turkish and Hijra calendars. These chronicles were written by munsis (secretaries) who were in charge of drawing up farmans with animal-designated years. From this period onward the nauruz festival began to be celebrated in the Chihil-Sutun palace in the capital Qazwin and was established as an important ceremony of the royal court. The Safavids had struggled up to this point to escape the influence of the Qizilbas tribes and construct a centralized government. The introduction of the Turkish calendar and the nauruz festival are aspects of a policy that sought to establish a strong Safavid kingship.
1 0 0 0 地学辞典
- 著者
- 竹内均 [ほか] 編
- 出版者
- 古今書院
- 巻号頁・発行日
- 1970
1 0 0 0 OA 航空機の設計・整備におけるリスク評価
- 著者
- 遠藤 信介
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.406-414, 2002-12-15 (Released:2017-01-31)
- 被引用文献数
- 1
航空機は,運航中に遭遇するさまざまな事態の下でも安全に飛行できるよう,システムごとに,故障解析,信頼性解析を行い,一定の安全目標が達成されていることを確認することが要求されているが,設計時に想定された安全性,信頼性を長期問維持するには,適切な検査,修復,交換などの整備を行う必要がある.本稿は,航空輸送の安全性について過去の実績とほかの社会’活動との比較を紹介し,設計における安全の目標の設定方法,設計・製造時に想定された安全性,信頼性を維持するための整備方式 などについて概説する.
- 著者
- 松村 和歌子
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, pp.501-513, 2008-03-31
1 0 0 0 OA 境界領域における化学結合
- 著者
- 井口 洋夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.1-5, 1970-01-05 (Released:2011-09-02)
1 0 0 0 十字架への献身 ; 精霊たち ; 夏
- 著者
- 安藤元雄 [ほか] 訳
- 出版者
- 新潮社
- 巻号頁・発行日
- 1973
1 0 0 0 遺伝相談の実態
- 著者
- 藤木 典生 中井 哲郎 金沢 弘 渡辺 稔夫 柿坂 紀武 和田 泰三 岡田 喜篤 津田 克也 細川 計明 山本 学 阿部 達生 近藤 元治 斉藤 隆治 渋谷 幸雄
- 出版者
- 日本先天異常学会
- 雑誌
- 日本先天異常学会会報 (ISSN:00372285)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.101-112, 1972
最近10年間に先天異常ことに心身障害児に対する一般の関心が大いに高まってきて、染色体分析や生化学的な代謝異常のスクリーニングの改善によって、早期診断、保因者の検索、適切た治療が進められてきた。こうした染色体異常や代謝異常でたくても、一般の人々が家系の中に発生した先天異常が遺伝性のものであるか、従って結婚や出産にあたってその再発の危険率などについて、しばしば尋ねられることが多い。我カは既に過去10年間にわたって遺伝相談を行ってきたが、今回これら二機関のデーターについて集計した結果について報告する。京都では、研究室で染色体分析や生化学的なスクリーニングことにアミノ酸分析を行っているためもあって、精薄が最も多く、近親婚の可否、精神病の遺伝性、先天性聾唖の再発率、兎唇、その他遺伝性疾患の遺伝的予後だとが主なものである。実施にあたっては、予約来院した相談者は人類遺候学の専門の知識をもったその日の担当医によって家族歴、既往歴など約2時間にわたる詳細な問診と診察の後に、その遺伝的予後についての資料が説明され、パンチカードに記入ファイルされるが、夫々臨床各科の専門医の診察の必要な場合には、その科の相談医の日が指定されて、専門的な診療指示が与えられる。愛知では、昨年末までの8ケ月間の一般外来忠児約900名について集計分類してみると、精薄が31.5%を占め、次いで脳性まひ、てんかん、自閉症、タウソ症候群、先天性奇形を含む新生児疾患、小頭症、情緒障害児、水頭症、脊椎異常、フェニールケトン尿症、脳形成異常、その他となっており、また、これらの心身障害児の合併症として骨折その他の外傷、上気道感染、胃腸障害が約30%に認められた。臨床診断にあたっては、臨床各科の医師と、理療士、心理判定士、ケースワーカーなどのパラメディカルスタッフからなる綜合診断チームが新来愚老の診察にあたって、綜合的な診断と専門的な指示が与えられるように考慮されている。心身障害児の成因分析をパイロット・スタディーとして試みたが、大半の症舳こ妊娠分娩或いは新生児期に何等かの異常を認めた。このことは、このような不幸な子供を生まないようにするためには、妊娠分娩時の母子の健康管理が遺伝の問題と共にいかに大切であるかを示すものである。今后、この方面の基礎的研究が各機関で進められると同時に、患者・保因老の早期発見、結婚出産に対する適切な指導を行うために、各地にこのような心身障害児のためのセンターが作られるように切望すると同時に、人類遺缶学が基礎医学のみでなく、臨床医学の一部としても、卒後研修の中にとり入れられることを切望する。
- 著者
- 杉本 浩司
- 出版者
- 中央法規出版
- 雑誌
- おはよう21 : 介護専門職の総合情報誌
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.9, pp.66-69, 2018-08
1 0 0 0 OA 日本のコミュニティにおける獅子舞伝承の今日的意義
- 著者
- 平島 朱美
- 出版者
- 法政大学大学院 国際日本学インスティテュート専攻委員会
- 雑誌
- 国際日本学論叢 = 国際日本学論叢 (ISSN:13491954)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.92-121, 2016-03-07
Shishimai is a traditional performing art employing a lion mask. It is explained as a lion dance because shishi means lion and mai means dancing. Shishimai is one of the biggest and the most enjoyable events inJapanese communities. The performers try to make contact with the supernatural world through dancing rhythmically with the mask on. Most shishimai in Japan are performed at Shinto festivals or on the New Year by people in the community and transmitted among them from elders to younger people, while those in some Asian societies are performed at the opening ceremony of a company or on the Lunar New Year by professional groups and transmitted from master to pupil there. Shishimai in Japanese communities are a religious symbol for thepeople there. Shishimai give them hope, satisfaction, power to live, identity and good relationship in a community not only in case of peace but also in case of emergency. Shishimai show people’s decision to form asense of identity and maintain their community.
- 著者
- ウセレル アントニ
- 出版者
- 日本カトリック教育学会
- 雑誌
- カトリック教育研究 (ISSN:09103716)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.25-34, 2017
1 0 0 0 OA 介護福祉士養成課程を持つ専門学校における学生の学習継続の困難に関する調査研究
- 著者
- 松永 繁
- 出版者
- 学校法人 敬心学園 職業教育研究開発センター
- 雑誌
- 敬心・研究ジャーナル (ISSN:24326240)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.35-43, 2019 (Released:2019-07-16)
- 参考文献数
- 13
専門学校における従来の学習継続困難、中途退学に関する研究では、経済的な側面や「学力」の側面から検討されてきた。本研究では、非認知能力の人間関係形成能力をキーワードにして、介護福祉士養成専門学校で学ぶ学生の学習継続困難要因、背景、教員の対応に焦点を当て検討した。結果、課題としては、【構成員からの離脱】【自己中心的な世界観】【孤立させる行動】の概念を生成し、背景では、【理想の子ども像】【スキル形成機会の剥奪】の概念を生成した。教員の具体的支援については、≪個別面談≫≪個別指導≫≪他の教員との情報共有≫≪家族への連絡≫の4つのカテゴリーを生成した。 結論として、人間関係形成能力の発達途上に学習継続困難となる課題が生じていることが示唆された。
1 0 0 0 OA 当法人職員における上司からの思いやりとサービス受益者に対する思いやりの関連
- 著者
- 中山 陽平 喜多 一馬 小島 一範
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.D-39, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに】日本は2040 年までに医療福祉職の人材が200 万人超の増加が必要と経済財政諮問会議で発表された。その中で,数だけでなく質の確保が急務とされている。そして,質の確保のためには思いやりを持つ重要性が示唆されており(福間2012),これからの医療福祉職には思いやりを育む教育や環境の整備が課題になる。これは在宅分野の理学療法士でも同様である。しかし,思いやりの育み方については,教育関連における報告は多いが(山村2012,三浦2013),医療福祉職における報告は見当たらない。他方,思いやりは様々な人間関係の中で育まれるものであり(植村1999),職員と上司の関係性はその一つとして重要と考えられる。本研究の目的は,職員が上司から感じている思いやりと,職員が利用者に意識している思いやりとの関係性を明らかにすることである。【方法】対象は,本法人のうちデイサービス(3 施設)と老人ホーム,居宅介護支援事業所のいずれかに所属する職員33 名(男性7 名,女性26 名,年齢47+12.4 歳)とした。なお,職員の職種は,ヘルパー,介護福祉士,看護師,柔道整復師,理学療法士であった。対象者には,紙面によるアンケート調査を実施した。アンケート項目は,上司から感じている思いやりについて「上司はあなたが困っている状況を話すと理解してくれる」など4 つの設問を設定した。利用者に意識している思いやりについては「あなたは利用者が困っている状況を理解しようと意識している」など4 つの設問を設定した。各設問に対し,①そう思う(1 点)から,⑤そう思わない(5 点)の5 件法にて回答を得ることとした。分析方法は,回答を点数化し,上司からの思いやりの合計点と利用者への思いやりの合計点との関連を,スピアマンの順位相関係数を用いて検討した。【倫理】本研究はヘルシンキ宣言に基づき,研究の趣旨,目的,内容,方法などの説明を行い,対象者の同意を得た上で実施した。なお,対象者の個人情報が特定されぬよう,アンケートの回答は無記名にする等の配慮を行った。【結果】上司からの思いやりの合計点の中央値は6(5 ‒ 8),利用者への思いやりの合計点の中央値は6(5 ‒ 7)であった。スピアマンの相関係数が中等度の正の相関(r = 0.478, p < 0.05)を認めた。【考察】結果より,職員が上司から感じている思いやりと,職員が利用者に意識している思いやりには,関係性があることが示唆された。これは,思いやりを感じる力と思いやりを持つ力は共感する能力に起因して生じた可能性がある。上司からの思いやりを感じるには,前提条件として,上司が思いやりを持っていることに対する共感が必要となる。また,他者への思いやりは共感から生じるものであり(満野ら2010),利用者への思いやりも共感をもつことが前提となる。つまり,2 つの質問の性質は両方とも他者への共感に基づくものであったといえる。よって,思いやりを感じる力を育むことは,他者に思いやりを持つ力を育むことと同意となる。思いやりは後天的な遺伝的要因以外の部分のほうが影響するといった報告がある(Varun Warrier 2018)。また,米グーグル社は2012 年から始めた研究(プロジェクトアリストテレス)でも思いやりに近似する心理的安全性がサービスの質を向上させると結論づけ,その形成に効果が証明されているマインドフルネスなど内観的プログラムを開始している。このような報告を応用し,在宅分野の理学療法士を含む医療福祉職における思いやりを育む教育を実践し,その効果を検証することが今後の課題である。【結論】職員が上司から感じている思いやりと,職員が利用者に意識している思いやりには,関係性を認めた。
- 著者
- 升 佑二郎
- 出版者
- The Japan Journal of Coaching Studies
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.219-230, 2018-03-20 (Released:2019-09-02)
- 参考文献数
- 12
This study compared the patterns of upper limb motion when delivering forehand (the hand holding the racket) straight/cross-court clear, drop, and smash shots from the backcourt in badminton. Seven male badminton players, belonging to a team that was third in the All Japan Intercollegiate Badminton Championships, delivered these shots to record the pattern of motion in each case using MAC 3D System Cameras. On comparison between straight and cross-court shots, the velocity of the wrist was significantly higher in the latter in all cases (p<0.05). The shoulder horizontal flexion angle was also markedly greater in the latter in all cases (p<0.05). On wrist motion trajectory analysis, the lateral (X-Z) plane at impact was shifted forward in the latter in all cases. Similarly, the frontal (Y-Z) plane was displaced inwards in the latter, while it was displaced outwards in the former from immediately before impact in all cases. Based on the results, the velocity of the wrist may be higher at a greater shoulder horizontal flexion angle when delivering cross-court compared with straight shots. Furthermore, during the phase immediately before impact, the probabilities of straight and cross-court shots being delivered are high when the wrist moves out- (the distance from the trunk increases) and inwards (it decreases), respectively.
1 0 0 0 OA プロフェッション理論の展開 -会計プロフェッションの場合
- 著者
- 平野 由美子
- 出版者
- 立命館大学経営学会
- 雑誌
- 立命館経営学 = 立命館経営学 (ISSN:04852206)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.231-251, 2010-05
1 0 0 0 OA アルコール性肝障害の長期予後
- 著者
- 加藤 活大 西村 大作 佐野 博 片田 直幸 杉本 吉行 野場 広子 芳野 充比古 佐守 友康 三谷 幸生 武市 政之
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.9, pp.1829-1836, 1990 (Released:2007-12-26)
- 参考文献数
- 25
アルコール性肝障害271例の長期予後を検討した. 生命予後は肝硬変が最も悪かつた (10年生存率: 23.8%). とくに多飲酒を続けた肝硬変は消化管出血死が多いことを反映して, 予後不良であつた. 肝細胞癌発生は肝硬変にほぼ限られ, その5年発生率は16.3%であり, 禁酒群の方が高い発生率を示した. 多飲酒継続の非硬変66例には反復肝生検を行い, 平均4年弱の経過で肝硬変移行率は30.3%であつた. 以上より, 多飲酒継続はアルコール性肝障害を進展させ, 生命予後の悪化をもたらすといえる. 肝硬変のみの検討でも禁酒は生命予後を全体的に改善したが, 肝細胞癌発生の危険性も高めるので, 肝硬変に移行する前に禁酒に導くことが大切である.
1 0 0 0 OA 白石平野における基盤整備の進展とクリーク水質の変化
- 著者
- 大串 和紀 中野 芳輔
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.137-140,a2, 2006-02-01 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 16
白石平野のクリークは, かつて農業用水のみならず生活用水源としても利用され, 地域の生活全般に密接に関係する存在であったため, クリークは住民の手によって清浄に保たれていた。しかし, 1960年代以降の水田およびクリークの整備と営農形態の変化に加えて, 生活水準の向上等によりクリークと住民との関わりが希薄になったこと等により, クリークの維持管理が疎かになるとともにその水質が悪化している。本報では, クリークの生い立ちおよび1960年代の農業や維持管理の状況をレビューし, さらにその後のクリークを取り巻く環境の変化を明らかにして, 今日の水質悪化を招いた要因を考察した。
1 0 0 0 OA 鳥(新型)インフルエンザに関する不安要因の構造
- 著者
- 山崎 瑞紀 吉川 肇子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.6, pp.476-484, 2010 (Released:2012-03-20)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 4
This study examined the structure of anxiety associated with highly pathogenic avian influenza and pandemic influenza among lay people, using data from a survey of 1 016 adults in the Tokyo Metropolitan area. Confirmative factor analyses demonstrated that anxieties associated with infection and its effects are comprised of three factors: health threats, concern about economics, and anxiety about unknown risks. Anxieties related to management of influenza consisted of factors of distrust of administrative organizations, distrust of grocery stores, industry, and farmers, distrust of medical services, and lack of self-confidence in coping. The means of these factors significantly differed for age groups. Respondents aged 60-81 years were more anxious about infection and its effects, while those aged 18-39 years were more concerned about how to cope with the flu than the other age groups. The importance of using different communications considering the types of anxieties of the target audience was discussed.
1 0 0 0 神聖ローマ帝国 : ドイツ王が支配した帝国
1 0 0 0 OA サファイア基板上GaNの成長に関する研究
- 著者
- 名古屋工業大学極微構造デバイス研究センター
- 出版者
- 名古屋工業大学極微構造デバイス研究センター
- 雑誌
- 極微構造デバイス研究センター報告書 = Technical report at Research Center for Micro-Structure Devices
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-112, 1998-03
- 著者
- 田中 圭二
- 出版者
- 高岡法科大学法学会
- 雑誌
- 高岡法学 (ISSN:09159339)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1-2, pp.43-80, 1994-03-24 (Released:2019-05-09)