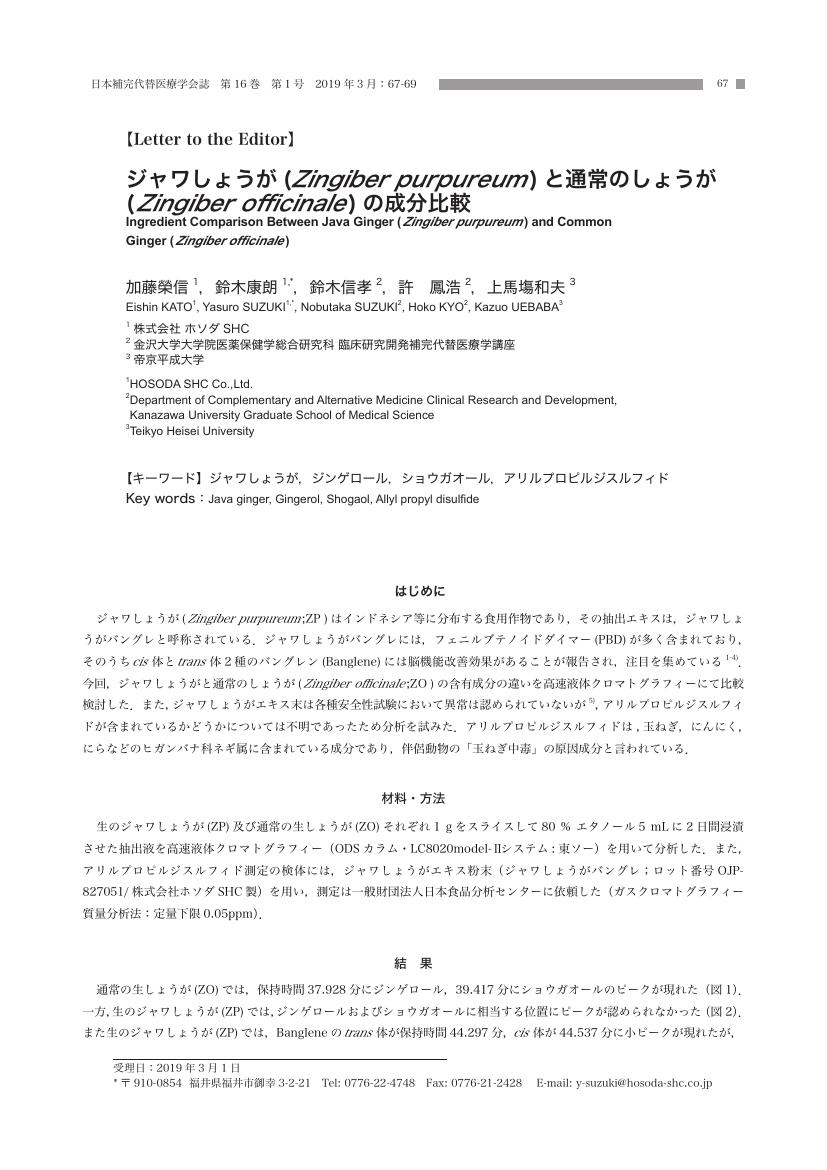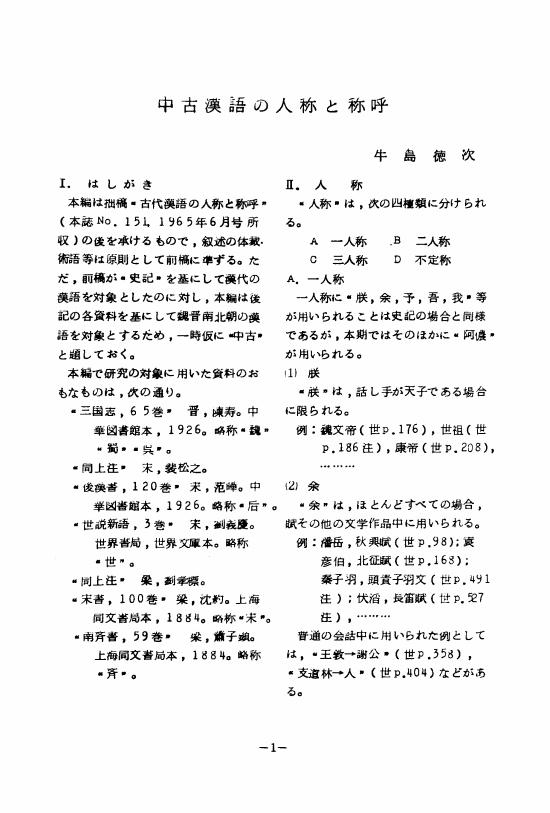- 著者
- Ryosuke Nakamura Michiko Nakagawa Kaoru Kitajima
- 出版者
- 日本熱帯生態学会
- 雑誌
- Tropics (ISSN:0917415X)
- 巻号頁・発行日
- pp.MS19-09, (Released:2020-03-20)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
Tropical forest trees take up silicon (Si) and return it to the forest floor via leaf litterfall. Our objective was to explore to what extent litter Si flux and Si availability from the soil are spatially coupled. We examined these relationships within a 4-ha area of lowland mixed dipterocarp forest of Lambir Hills National Park in Borneo. Using leaf litter samples collected with litter traps, we found that Si concentration and flux of leaf litter ranged 2-23mgSig-1 and 0.8-13.1gSim-2 yr-1, respectively, whereas water-extractable Si from 0-10cm deep soil ranged from 5.9 to 24.5mg kg-1 (0.7 to 3.0gSim-2) at 80 litter trap locations. There was no significant correlation among these three aspects of Si cycling via trees. Water-extractable soil Si from three 95cm deep cores showed no significant change with depth, whereas in-situ measurements with six tension lysimeters showed higher soil-water Si concentration in the upper soil layer (0-5cm depth). These results suggest that spatial variations of Si concentration and flux in leaf litter do not reflect those of soil Si availability, but are modulated by distribution of tree species that differ in Si uptake. Si returned to the soil via leaf litter did not show strong spatial signals probably because solubility of Si from dead leaves differs among species. At the stand level, our results are consistent with the perspective that litter Si input enriches plant-available Si pool in the upper soil horizons in tropical forests.
3 0 0 0 OA 日本におけるインストラクショナルデザイン研究の動向(2003-2018)
- 著者
- 高橋 暁子 杉浦 真由美 甲斐 晶子 冨永 敦子
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.253-265, 2019-12-31 (Released:2020-02-14)
- 参考文献数
- 46
本研究では,日本におけるインストラクショナルデザイン(ID)の先行研究をレビューし,研究動向を整理した.2003年から2018年までの教育工学領域の論文から72編のID 研究論文が抽出され,ここ10年の論文数は横ばいであった.そのうち61編が実践系の論文に位置づけられ,とくに「教育実践の改善および学習環境づくり」での活用が顕著であることが示された.教育現場における実践報告が多くの割合を占める一方で,実践研究と基盤的研究との往還やID 本来の趣旨である教育設計時の活用に関しての課題が明らかになった.
3 0 0 0 OA 海外子会社マネジメントにおける組織社会化のジレンマ
- 著者
- 中川 充 中川 功一 多田 和美
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.38-48, 2015 (Released:2017-03-23)
This study aims to reconsider about the negative impact of organizational socialization on subsidiary companies of multinational corporations (MNCs). International research has repeatedly demonstrated that the process of organizational socialization when adopted in a foreign subsidiary setting has positive effects on various areas of its organizational performance. Hence, organizational socialization is largely used by a parent company as one of the tools for controlling a subsidiary. An analysis of six Japanese MNCs in the emerging markets reveals that organizational socialization has both negative as well as positive impact. Subsidiaries encounter difficulties in implementing strategies when they experience intensive promotion of the organizational culture of their parent companies. Considering the significant cultural and economic differences between the headquarters and the subsidiary, the subsidiary personnel cannot easily adapt the parent company’s culture to their local workplace environment. From these considerations, we add a new understanding about the influence of organizational socialization and give a proposition that organizational socialization brings a tradeoff between knowledge transfer and subsidiary innovativeness.
3 0 0 0 OA X線位相イメージングとX線位相CT
- 著者
- 百生 敦
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.6, pp.513-517, 2016-06-05 (Released:2016-06-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 2
3 0 0 0 OA リハビリテーション分野のWeb サイトにおける医療広告ガイドラインの遵守割合
- 著者
- 藤本 修平 小林 資英 小向 佳奈子 杉田 翔
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.196-200, 2019 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 28
【目的】リハビリがかかわる医療機関Web サイトにおける医療広告ガイドラインの遵守実態を検証することとした。【方法】リハビリがかかわる医療機関のWeb サイトを抽出するため,国土数値情報(国土交通省)から東京都23 区内の医療機関を抽出し,医療機関名と住所を組み合わせWeb サイトの検索を行った(database: Google)。Web サイトの質を評価するために,医療広告ガイドラインを参考に6 項目評価した。【結果】診療科目で本来使用すべき「リハビリテーション科」という標榜以外の記載をしているWeb サイトは993 件中461 件(46.4%)であった。医療機関の名称の語尾に“センター”と標榜するもののうち,名称として認められていないものは47 件中38 件(80.9%)であった。【結論】本来医療機関の名称として認められていない標榜を採用している医療機関が多く,情報提供者は,医療機関に関する情報をより正確に説明する必要がある。
3 0 0 0 OA アルツハイマー病アミロイドβタンパク質の凝集における 生体膜の役割
- 著者
- 松﨑 勝巳
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.185-189, 2007 (Released:2015-06-27)
The conversion of soluble, nontoxic amyloid β-protein (Aβ) to aggregated, toxic Aβ rich in β-sheet structures by seeded polymerization is considered to be the key step in the development of Alzheimer’s disease. Accumulating evidence suggests that lipid rafts (microdomains) in membranes mainly composed of sphingolipids (gangliosides and sphingomyelin) and cholesterol play a pivotal role in this process. Our model membrane studies revealed the following mechanism. Soluble Aβ with unordered structures specifically binds to raft-like membranes containing a ganglioside cluster, the formation of which is facilitated by cholesterol. The membrane-bound Aβ forms an α-helix-rich structure at lower densities. At higher densities, Aβ undergoes a conformational transition to a β-sheet-rich structure that can serve as a seed for amyloid fibril formation. This model was confirmed in cellar level using rat pheochromocytoma PC12 cells. Fourier-transform infrared spectroscopic and electron micrographic studies revealed that the structures of Aβ fibrils formed in solution and lipid rafts are different. The fibrilization can be inhibited by small organic compounds and biocompatible nanogels.
3 0 0 0 OA 絶滅した生物“首長竜”:講演録
- 著者
- 佐藤 たまき
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物教育学会
- 雑誌
- 生物教育 (ISSN:0287119X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.130-137, 2017 (Released:2018-10-29)
- 参考文献数
- 15
本稿では古生物学という学問と,絶滅した中生代の化石海生爬虫類である首長竜について解説した.化石の研究は古生物学と呼ばれ,考古学と間違われやすいが,地学と生物学の境界に位置しており,博物館との関わりも深い.古生物学に関連するトピックは小学校から高等学校までの様々な学年の理科教科書に登場し,高校教科書では地学と生物学の両方にまたがっている.首長竜は恐竜であると思われがちであるが,系統学的な定義でも骨の形態でも異なる別個の分類群である.また,福島県で発見された首長竜フタバスズキリュウを用いて,学名や記載論文の意義についても解説した.
3 0 0 0 OA ヒトにおけるホルモン依存性発癌
- 著者
- 笹野 公伸
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第41回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.W4-4, 2014 (Released:2014-08-26)
ホルモン、特にステロイドホルモンは種々の標的組織における細胞増殖他に密接に関与している事から、腫瘍/癌化に大きく関与する。 中でもエストロゲン、アンドロゲンを中心とした性ステロイドは男性では前立腺癌、女性では子宮内膜癌、卵巣癌そして乳癌の発生に密接に関与する事はよく知られている。 こられのいわば古典的な性ステロイド依存性腫瘍に加えて最近では肺癌、大腸癌、胸腺腫等の一部でもこれら性ステロイドホルモンが癌化他に深く関与している事が示されてきている。 この性ステロイドが関与する発癌機構で動物実験と異なる事として、腫瘍組織局所での性ステロイド代謝による影響があげられる。 すなわち性ステロイド作用は通常血中のホルモン濃度と標的細胞における受容体の有無で規範される事が原則であるが、例えばヒトの場合エストロゲン依存性乳癌が発症してくるのはむしろ血中のエストロゲン濃度が極めて低下する閉経期以降が多い。この現象は受容体が発現している標的組織中で、閉経前後でその血中濃度があまり変わらない副腎皮質網状層由来の生物学的活性の低い男性ホルモンがアロマターゼ他の酵素によりエストロゲンに転換され作用する事に起因している。 このように血中のホルモン濃度に関係なく標的組織でホルモンを代謝/産生して作用する機序は従来の“Endocrinology”に比べて“Intracrinology”とも呼ばれ、多くの性ステロイド依存性腫瘍の発生/進展に際し大きな役割を果たしている事が明らかにされてきている。 このIntraccine機構はサイトカイン、成長因子等種々の要素による局所でホルモンを活性化、あるいは非活性化する酵素群の発現動態が影響され、これらのホルモン依存性は発癌機構も単に血中のホルモン濃度と標的細胞の受容体の発現量だけで規範されない。このようにホルモン、特に性ステロイドが関与するヒト発癌/腫瘍発生機構は非常に複雑であり、全身/組織/細胞レベルの総合的な解析が欠かせない。
3 0 0 0 OA 戦後民主主義と象徴天皇制
- 著者
- 舟越 耿一
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, pp.59-75, 1999-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 18
3 0 0 0 OA CKY に基づく畳み込みアテンション構造を用いたニューラル機械翻訳
- 著者
- 渡邊 大貴 田村 晃裕 二宮 崇 Teguh Bharata Adji
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.207-230, 2019-03-15 (Released:2019-06-15)
- 参考文献数
- 40
本論文では,ニューラル機械翻訳 (NMT) の性能を改善するため,CKY アルゴリズムから着想を得た,畳み込みニューラルネットワーク (CNN) に基づく新しいアテンション構造を提案する.提案のアテンション構造は,CKY テーブルを模倣した CNN を使って,原言語文中の隣接する単語/句の全ての可能な組み合わせを表現する.提案のアテンション構造を組み込んだ NMT は,CKY テーブルの各セルに対応する CNN の隠れ状態に対するアテンションスコア(言い換えると,原言語文中の単語の組み合わせに対するアテンションスコア)に基づき目的言語の文を生成する.従来の文構造に基づく NMT は予め構文解析器で解析した文構造を活用するが,提案のアテンション構造を用いる NMT は,原言語文の構文解析を予め行うことなく,原言語の文に潜む構造に対するアライメントを考慮した翻訳を行うことができる.Asian Scientific Paper Excerpt Corpus (ASPEC) 英日翻訳タスクの評価実験により,提案のアテンション構造を用いることで,従来のアテンション構造付きのエンコーダデコーダモデルと比較して,1.43 ポイント BLEU スコアが上昇することを示す.さらに,FBIS コーパスにおける中英翻訳タスクにおいて,提案手法は,従来のアテンション構造付きのエンコーダデコーダモデルと同等かそれ以上の精度を達成できることを示す.
3 0 0 0 OA 特大変圧器輸送用貨車“シキ” の活躍と保存
- 著者
- 西村 怜馬 永海 俊治 矢代 大祐
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.7, pp.439-442, 2008-07-01 (Released:2008-07-01)
- 参考文献数
- 2
本記事に「抄録」はありません。
- 著者
- 加藤 榮信 鈴木 康朗 鈴木 信孝 許 鳳浩 上馬塲 和夫
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.67-69, 2019-03-31 (Released:2019-04-10)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 今村 隆寿
- 出版者
- 日本細菌学会
- 雑誌
- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.499-516, 2000-08-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 103
- 被引用文献数
- 1 1
細菌プロテアーゼとして, 新たな構造と機能が見い出された歯周病の主要な原因菌 Porphyromonas gingivalis のトリプシン様システインプロテアーゼ gingipains を紹介する。Gingipains は3種の遺伝子 (rgpA, rgpB, Kgp) から産生される variants であり, そのペプチド結合切断特異性からは Arg-Xaa を切断する gingipains R (rgpAとrgpB由来) とLys-Xaaを切断する gingipain K (kgp 由来) に分類される。HRgpAとKgpは触媒ドメインと赤血球凝集/接着活性ドメインとの複合体である。他に, gingipains Rには触媒ドメインのみの型とこれに多糖体が結合した膜型がある。Gingipains は P. gingivalis のハウスキーピングだけでなく宿主への感染や宿主防御機構からの回避にも重要な役割を果たす。Gingipains は P. gingivalis の病原性と密接に関連し歯周病の発症・進展に関与しているので, 歯周病予防・治療法開発のターゲットとして有用である。
3 0 0 0 OA 生徒指導上の問題発生頻度および携帯電話に対する規制と高校生の携帯電話依存傾向の関連
- 著者
- 三島 浩路 黒川 雅幸 大西 彩子 吉武 久美 本庄 勝 橋本 真幸 吉田 俊和
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.518-530, 2016 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 5 5
高校ごとの生徒指導上の問題の発生頻度認知や携帯電話に対する規制と, 携帯電話に対する生徒の依存傾向等との関連を検討した。13の高校に所属する教師約500人と生徒約1,700人を対象に調査を行った。その結果, 生徒指導上の問題の発生頻度認知が高い高校に在籍している生徒ほど, 携帯電話に対する重要度認知が高く, 携帯電話に対する依存傾向が強いことが示唆された。生徒指導上の問題の発生頻度認知が低い高校に関しては, 携帯電話に対する規制の強弱により, 生徒の携帯電話に対する依存傾向が異なることが示唆された。具体的には, 生徒指導上の問題の発生頻度認知が低い高校の中では, 携帯電話に対する規制が強い高校に在籍している生徒の方が, 規制が緩やかな高校に在籍している生徒に比べて, 携帯電話に対する依存傾向が強いことを示唆する結果が得られた。
3 0 0 0 OA 中古漢語の人称と称呼
- 著者
- 牛島 徳次
- 出版者
- 日本中国語学会
- 雑誌
- 中国語学 (ISSN:05780969)
- 巻号頁・発行日
- vol.1966, no.159, pp.1-13, 1966-04-15 (Released:2010-11-26)
3 0 0 0 OA 改訂された「参照文献の書き方」
- 著者
- 古谷 実
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.155-161, 2007 (Released:2007-06-01)
- 参考文献数
- 4
「SIST 02-1997参照文献の書き方」と「SIST 02 suppl.-2003参照文献の書き方(補遺)電子文献参照の書き方」の双方を併せて改訂して1冊にまとめた新版『SIST 02-2007』が公刊された。記述ルールをできるだけ単純にすることを目指し,印刷媒体,電子媒体いずれの参照にも対応できるようにした。旧版からの主要な変更点とその考え方について説明し,参照すべき文献種類の多様化に対応して記述例を80に増やした。また,ある主題分野や一部学会で多年にわたり慣用されてきた参照ルールにも目を向け,残された課題や今後必要な作業について述べた。公刊する前にパブリック・コメントを徴し,それを取り入れたことも今回の改訂の特徴である。
3 0 0 0 OA 『デジタルアーカイブ・ベーシックス1 権利処理と法の実務』
- 著者
- 足立 昌聰
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.359, 2019-06-24 (Released:2019-08-30)
3 0 0 0 OA 震災後の買い溜め,買い控え行動の消費者の心理プロセスの検討
- 著者
- 大友 章司 広瀬 幸雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.6, pp.557-565, 2014-02-25 (Released:2014-04-15)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4 4
This study examined psychological processes of consumers that had determined hoarding and avoidant purchasing behaviors after the Tohoku earthquake within a dual-process model. The model hypothesized that both intentional motivation based on reflective decision and reactive motivation based on non-reflective decision predicted the behaviors. This study assumed that attitude, subjective norm and descriptive norm in relation to hoarding and avoidant purchasing were determinants of motivations. Residents in the Tokyo metropolitan area (n=667) completed internet longitudinal surveys at three times (April, June, and November, 2011). The results indicated that intentional and reactive motivation determined avoidant purchasing behaviors in June; only intentional motivation determined the behaviors in November. Attitude was a main determinant of the motivations each time. Moreover, previous behaviors predicted future behaviors. In conclusion, purchasing behaviors were intentional rather than reactive behaviors. Furthermore, attitude and previous behaviors were important determinants in the dual-process model. Attitude and behaviors formed in April continued to strengthen the subsequent decisions of purchasing behavior.
3 0 0 0 OA 有毒植物による食中毒の最近の動向と今後の課題
- 著者
- 笠原 義正
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.311-318, 2010-12-25 (Released:2011-01-07)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 8
3 0 0 0 OA 新自由主義時代の社会政策と社会統合―オーストラリアにおける福祉給付の所得管理をめぐって―
- 著者
- 藤田 智子
- 出版者
- オーストラリア学会
- 雑誌
- オーストラリア研究 (ISSN:09198911)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.16-31, 2016 (Released:2017-04-28)
- 参考文献数
- 50
The Australian Government has repeatedly restructured its social policy since the 1980s, making welfare payments conditional and increasing work incentives. This welfare reform, influenced heavily by neoliberalism, has been legitimised by the problematisation of“ welfare dependency,” emphasising the obligations and the responsibilities of welfare recipients. The Howard Coalition Government in particular promoted an insistent neoliberal turn in social policies, asserting the importance of a social welfare system encouraging“ responsible behaviour.” In 2007, the Government introduced a measure called“ income management” or“ welfare quarantining” which linked welfare payments to the“ socially responsible behaviour” of parents. Income management was taken over by the Rudd-Gillard Labor Government, and eventually by the Abbott Coalition Government, and has been a prominent feature of welfare reform, indicating the importance of analysing income management in the context of welfare reform from the perspective of parenthood. This paper analyses the policy process of income management and the logic that has supported it to consider the issue of neoliberal welfare reform and social inclusion/exclusion. Income management, introduced by the Howard Government as a part of the Northern Territory Emergency Response (NTER), was actually a scheme to advance welfare reforms based on the principle of“ mutual obligation” by urging parents to show responsibility for the care and education of their children. While supporting the NTER and echoing the Howard Government’s arguments on parental responsibility, the Rudd and Gillard Governments more obviously referred to income management as a significant welfare reform scheme and broadened its application. In that whole process, welfare dependency and its intergenerational cycle have been problematised, and individuals“ depending on welfare” have been referred to as“ bad parents” who behave“ against normal community standards.” Parenthood has been the core element of this welfare reform by connecting normative parental behaviour with provision of welfare payments and thus making parents subject to intervention. Furthermore, attributes such as Aboriginality, class, age and family type have had a close relationship with representation of welfare recipients as“ bad parents.” Whereas income management intends to encourage welfare recipients to achieve social inclusion, this very process excludes them from social citizenship by referring to vague norms of parenthood.