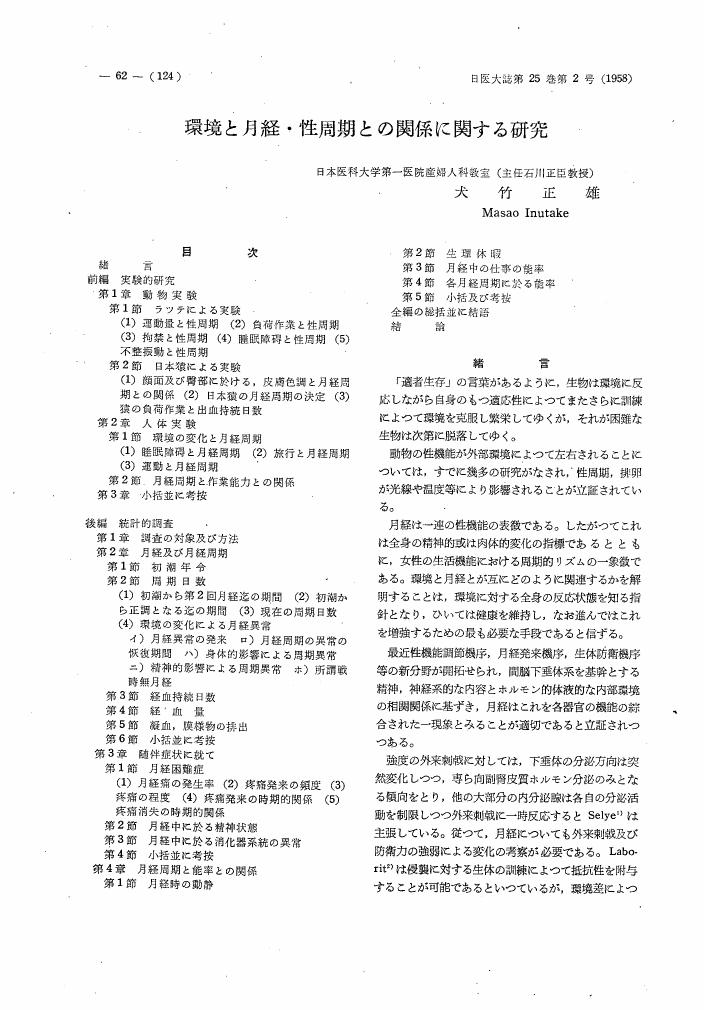1 0 0 0 IR 映画の「戦後総力戦体制」
- 著者
- 赤上 裕幸
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科生涯教育学講座
- 雑誌
- 京都大学生涯教育学・図書館情報学研究 (ISSN:13471562)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.43-52, 2007-03
GHQ(General Headquarters、連合国総司令部)による占領期から特にその終結期にかけて「戦後反戦映画」が多数作られ、興行的にも大きな成功を収めている。1950年の『また逢う目まで』、『暁の脱走』、『きけわだつみの声』、1953年の『ひめゆりの塔』、『君の名は(第1・2部)』、1954年の『二十四の瞳』、『君の名は(第3部)』などがそれにあたる。 これらの反戦映画が、戦時中の映画体制との関わりの中で語られることはほとんどない。しかし、戦意高揚映画が多数作られ戦争に邁進していった戦中と、反戦映画が多数作られ平和国家建設に邁進していった戦後と、一体どれほどの違いがあるというのだろうか。近年のメディア史研究においては、戦前戦後の間に「断絶」ではなく「連続性」が存在すること、すなわち戦後のマス・コミュニケーション学のパラダイムが、戦中の総力戦体制に由来するということが指摘されている。 本論文では、この「総力戦の継続」という視点に着目し、占領期を中心とした時期(1945年~54年)を「戦後総力戦体制」と定義し、戦中も含めたメディア史の流れの中で、いかに「戦後反戦映画」を位置付けることができるかに重点をおいて分析していく。
1 0 0 0 OA 貝尽浦の錦 2巻
- 著者
- 大枝流芳
- 出版者
- 伊和惣兵衛[ほか2名]
- 巻号頁・発行日
- vol.[1], 1751
1 0 0 0 IR イケモテュッベからドゥームへ--「求愛」、「正義」、「紅葉」再読
- 著者
- 白川 泰旭
- 出版者
- 近畿大学語学教育部
- 雑誌
- 近畿大学語学教育部紀要 (ISSN:13469134)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.15-28, 2008
1 0 0 0 IR シフトする視点 : 「紅葉」試論
- 著者
- 白川 泰旭
- 出版者
- 近畿大学
- 雑誌
- 近畿大学語学教育部紀要 (ISSN:13469134)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.87-101, 2007
W.フォークナーは1930年7月、彼自身としては初めてのインディアンに纏わる物語「紅葉」を『サタデイ・イブニング・ポスト』誌に送付し、10月発行の同誌に掲載される。その後、章の構成に改訂が加えられて、フォークナーにとっての最初の短編集『これら13編』(1931)に、続いて十数年の年月を経てマルカム・カウリー編纂の『ポータブル・フォークナー』(1946)、そして最終的に『ウィリアム・フォークナー短編集』(1950)に収録されることになる。さらに、フォークナーはその数章を改訂し、短編集『大森林』(1955)の中の一つの物語「昔の人々」の序章として組み込んでいる。フォークナーの短編作品で、雑誌に掲載された後にあらためて短編集などに再録されたものはかなりの数にのぼる。しかし、「紅葉」が以上のように繰り返し収録された跡をたどると、この作品がフォークナーの数多くの短編作品の中でもきわめて重要な意味を持っていることが窺える。また、批評家J.ファーガソンがこの作品に含まれているさまざまな要素を挙げて、「フォークナーの最もすぐれた短編作品の一つ」と評しているのも十分首肯できる。「紅葉」は、チカソー族の酋長イセティッベハの死に伴い、部族のしきたりに則って彼とともに生きたまま埋葬されるはずの「側仕え」の黒人奴隷が、イセティッベハの死ぬ直前に逃げ出したために、部族の者たちが彼を追跡し、捕えるまでの6日間の様子を描いた物語で、展開されるストーリー自体は単純である。しかし、物語の焦点は追跡それ自体ではなく、その背後に横たわっているこのインディアン部族が抱えるさまざまな問題、言い換えればこの部族の過去および現在の「暗部」に当てられている。ドゥームからイセティッベハへ、そしてモケチュッベへと親子三代にわたって酋長の座が引き継がれていく間に、部族を取り巻く状況はますます悪くなっていくのであるが、その背景には、ドゥームが酋長の座を手に入れた経緯、ドゥームの死後、酋長の座を引き継いだイセティッベハの行動、さらにはその息子モケテュッベとの「赤い踵の上靴」をめぐる父子の相剋などが複雑に絡み合っている。しかし、こうした「暗部」の核心や部族の歴史に暗い影を投げかける隠された事実については曖昧さを残したままである。一方、そのようなインディアンの世界を呈示しながら、それと並行して、逃亡する黒人に焦点が当てられ、彼の生命力にあふれた姿も描き出される。彼は死と向かい合った自分を突き放して冷笑的に見ながら、ただ死から逃れようと走り続けるうちに、生きることに必死だった過去の自分を思い出し、自分の中に生きたいという気持ちが湧き起こってくるのに気づく。その描写は生き生きとして、インディアンたちの姿を描くときの語りとは明らかに異なる。このように、読者はこの物語の中に2つの世界を見ることになるのであるが、それぞれの世界が描かれた章は明確に区別され、章によって視点も変わるために、読者は異なった人物の「目」を通してそれらを見ることになる。逃亡奴隷の追捕という、軸となるストーリーそのものの単純さにもかかわらず、この作品が多くの批評家によって高く評価されているのは、この作品の整った章構成と語りの妙ゆえであろう。本論では、この語りの技法と構成を考察し、物語におけるその効果を分析することを目的とする。
1 0 0 0 OA 現代スポーツを考える ─ スポーツ選手の入れ墨が影響するもの ─
- 著者
- 岡部 修一 Okabe Shuichi
- 雑誌
- 紀要 = Study reports of Narabunka Women's Junior College (ISSN:02862867)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.175-183, 2012-11-01
1 0 0 0 OA 寛政享和文化文政撰要目録 8巻
- 出版者
- 写
- 巻号頁・発行日
- vol.[8] 文政撰要目録 下,
1 0 0 0 環境税からゴミ問題まで国民との問題意識の共有を図りたい
1 0 0 0 IR 共有される種子 : オルタナティブな種子実践をめぐる「農民」集団のアイデンティティ的構築
- 著者
- ドゥムルナエル E. ボヌイユ C. 須田 文明[翻訳] E. Demeulnaere C. Bonneuil Fumiaki Suda 農林水産省農林水産政策研究所
- 出版者
- 岩手県立大学総合政策学会
- 雑誌
- 総合政策 = Journal of policy studies (ISSN:13446347)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.133-148, 2015-11-01
1 0 0 0 象牙質を経由した細菌性LPSの歯髄への拡散について
- 著者
- 池田 英治 プアピチャドゥムロング ピラヤ 須田 英明
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 = THE JAPANESE JOURNAL OF CONSERVATIVE DENTISTRY (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, 2004-10-18
1 0 0 0 OA 花街雀竹夜遊 前帙4巻後帙6巻
- 著者
- ラジャ アブドゥ ムフティ 鈴木 毅 吉住 優子 向阪 真理子 山内 清史 山本 葵 松原 茂樹 奥 俊信
- 出版者
- Architectural Institute of Japan
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.675, pp.979-986, 2012
- 被引用文献数
- 1
This paper analyzes an environment sharing system from a field survey of 225 <i>Bale bales</i> (Endai-like furniture) in Lae Lae isle, Makassar, Indonesia. <i>Bale bales</i> are owned by individuals and used by entire households. However, 1) <i>Bale bales</i> are sometimes moved to better environments not only by owners but also by neighbors.<br>2) Whether or not they have their own <i>Bale bales</i>, many islanders use the <i>Bale bales</i> of other families located in comfortable environments (for example, the seashore, a street corner, or a public square) far from their homes.<br>3) Not only relatives but also neighbors and visitors are permitted to use each <i>Bale bale</i> on the island.<br>By following these customs and rules, islanders can share a good environment on their high-density island.
- 著者
- 菅原 健介
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 心理學研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.134-140, 1986
- 被引用文献数
- 1 10
Public self-consciousness involves two contrasting attitudes toward self-presentation-exhibitionism and shyness. The purpose of this study was to explore the distinctive motivational states which mediate these two attitudes. This paper consists of two researches. 395 undergraduates (207 males, 188 females) participated in the former study and 452 undergraduates (288 males, 164 females) participated in the latter one. The first study employed a factor analytic technique and results pointed to the existence of the following two motivational states-(1) acquiring praise and (2) avoiding rejection-both of which were positively correlated with public self-consciousness. "Acquiring praise" was also found to be related to exhibitionism but "avoiding rejection" was not. The later was found to be related to shyness. The second study revealed that both motivational states were related to a tendency to seek out and value the experience of participating in a social group. The implications of these findings for theories of self-consciousness and self-presentation were discussed.
1 0 0 0 育児指導の効果に関する研究
- 著者
- 前田 ひとみ 岡本 淳子 寺本 淳子 山下 清香 山本 悌子 成田 栄子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.2_14-2_20, 1989
より行動化され易く、また、母親の意識を高めることの出来る保健指導を検討する為に、育児指導の内容や方法が異なる竜北町と熊本市の1才6ケ月児検診における母親の育児行動ならびに児の日常生活習慣の自立等の実態とそれまでに受けた指導とを比較した。 その結果、児の発達を追いながら個別性を考慮し、期間を区切って身近な目標を持たせるような指導は効果のあることが示唆された。そして、集団指導は効果的な指導の場となっており、加えて実習することによって母親自身に方法や知識が確実に習得されると思われる結果が得られたことから、項目によっては単に口述だけでなく、実習をまじえた指導がより効果的であると考えられた。一方、正常な発達過程や家族の生活形態や家族形態の影響を受け易い日常生活習慣については、指導の効果が現れにくいことが示唆された。
1 0 0 0 階層型マクロデータフロー処理におけるサブルーチン並列処理手法
マルチプロセッサシステムにおける従来のFortran自動並列化コンパイラではDo-allやDo-acrossなどのループ並列化のみが用いられていた.この場合,ループ以外の部分の並列性,たとえば基本プロック内部の並列性や,基本プロック,ループ,およびサプルーチン間の粗粒度並列性を利用することはできなかった.筆者らは以上のような間題を解決するため,従来よりマルチグレイン並列処理手法を提案してきた.これは,基本プロック,ループ,サブルーチンより定義される粗粒度タスク(マクロタスク)の並列処理(マクロデータフロ処理),中粒度並列処理(ループ並列化),細粒度並列処理を階層的適用した並列処理手法である.
1 0 0 0 OA 書画五拾三駅 伊勢関乳人之恩愛
- 著者
- 佐藤 純次
- 出版者
- 気象庁気象研究所
- 雑誌
- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.39-49, 1989
エア・トレーサーを有限時間に放出した中規模大気拡散実験において、トレーサープルームが風下方向に引き伸ばされる現象が観測された。このような有限長プルームの引き伸ばされた部分は、トレーサーを瞬間的に放出したパフの拡散の場合と同じであると仮定することによって<i>x</i>方向の拡散パラメータ、σ<sub><i>x</i></sub>を求めることができる。有限長プルームから求めたσ<sub><i>x</i></sub>を 「安定」、「ほぼ中立」、「不安定」 の3階級の大気安定度に分類し、他の類似した規模の拡散実験結果と比較した。安定条件ではσ<sub><i>x</i></sub>の値が僅かではあるが小さい傾向が見受けられたが、σ<sub><i>x</i></sub>の風下方向への変化に対する安定度の影響は認められなかった。<br> さらに、連続条件を満足するようにトレーサーの放出時間、サンプリング時間、トレーサープルームの長さを考慮した時間平均濃度を適正に評価する方法を検討した。この方法はいかなるサンプリングモードにも適用できる。
- 著者
- 吉村 雅仁 今泉 眞之 佐倉 保夫 唐 常源
- 出版者
- 公益社団法人 日本地下水学会
- 雑誌
- 地下水学会誌 (ISSN:09134182)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.19-40, 2003
割れ目の幾何(パターン)が岩盤の透水性や内部の物質挙動に与える影響について明らかにすることを目的とした.アクリル製の角柱ブロックを水槽内に異なるパターンで並べることによって,6種類の模擬割れ目岩盤を作り,トレーサー試験を行った.トレーサーの挙動は,最大64箇所の割れ目交差部でトレーサーの電導度を計測することによって把握した.解析の結果,割れ目パターンの違いは流路長や有効間隙率を変化させ,異なる透水性やトレーサープルームの形状を示すこと,平行板からなる割れ目内における機械的分散現象が生じていることを明らかにした.トレーサープルームの形状の成因については,交差部における流線と拡散ゾーンの概念を導入して考察した.
1 0 0 0 OA ジオパークにおける大学・博物館の役割
- 著者
- 新名 阿津子 松原 典孝
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.6, pp.841-855, 2016-12-25 (Released:2017-01-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 3
The roles of universities and museums in relation to geoparks are discussed by comparing San'in Kaigan UNESCO Global Geopark in Japan and Lesvos UNESCO Global Geopark in Greece. Bottom-up management is a key to the success of sustainable development. It is important for local people to make decisions on regional matters. Scientists who live in the territory of a geopark are also local people and play multiple roles. They usually work for universities and museums. According to the guideline of UNESCO Geopark, education is an important issue. Geoparks need to connect people with earth science. Educational activities, however, need specific times and places to be carried out. It is essential to provide high-quality educational programs continuously for learners of all kinds in the territory of a geopark. In the case of San'in Kaigan Geopark, individual actors, including administrative officers, local geo tour guides, scientists, and curators provide geopark educational programs for learners without their own geopark educational strategy, because the education committee of San'in Kaigan Geopark discusses school education only and half of the geopark staff members are transferred every year. So, it is not easy for them to take over various tasks of the geopark. This situation in San'in Kaigan keeps learners away from high-quality and continuous education. Under this situation, scientists who work for universities play multiple roles in connecting local people with earth science and other people through multi-scale geopark networks which are of global, regional, national, and local scales, although scientists tend to be rooted and the locations of universities do not necessarily commit scientists to become engaged with the geopark. On the other hand, Lesvos Geopark is a good example. It has a rational educational strategy, develops scientific educational programs combined with geotourism, and provides opportunities for education and employment to local people at the Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest. The same staff members at the museum take responsibility for management and education in the geopark. That is why they can develop Lesvos Geopark in a coherent manner.
1 0 0 0 IR 中世アル・アンダルスにおけるユダヤ系住民の社会的地位について
- 著者
- 上間 篤
- 出版者
- 名桜大学
- 雑誌
- 名桜大学紀要 (ISSN:18824412)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.1-9, 1998
本小論は、アブデラマン三世(911年~961年)の寵臣≪ハスダイ・イブン・サプル≫の幾多の卓越した功績と業績をふまえて、中世スペインのイスラム教徒社会におけるユダヤ系住民の社会的地位について考察し、当時としては超人的とも言えるハスデイの働きも究極的にはアラブ支配体制の障壁を突き崩すまでには至らなかった内実を考える。This short paper examines the social status of the Jews in Al-Andalus through the life of a distinguished Jew named Hasday Ibn Saprut, who served in numerous outstanding ways in the court of Abderraman 3(911-961). By observing various aspects of Hasday's major contributions and achievements, the paper has tried to reveal what the Jews of the time could do and what they couldn't in Al-Andalus due to their ethnic background.
1 0 0 0 OA 環境と月経・性周期との関係に関する研究
- 著者
- 犬竹 正雄
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.124-144, 1958-02-15 (Released:2009-07-10)
- 参考文献数
- 43