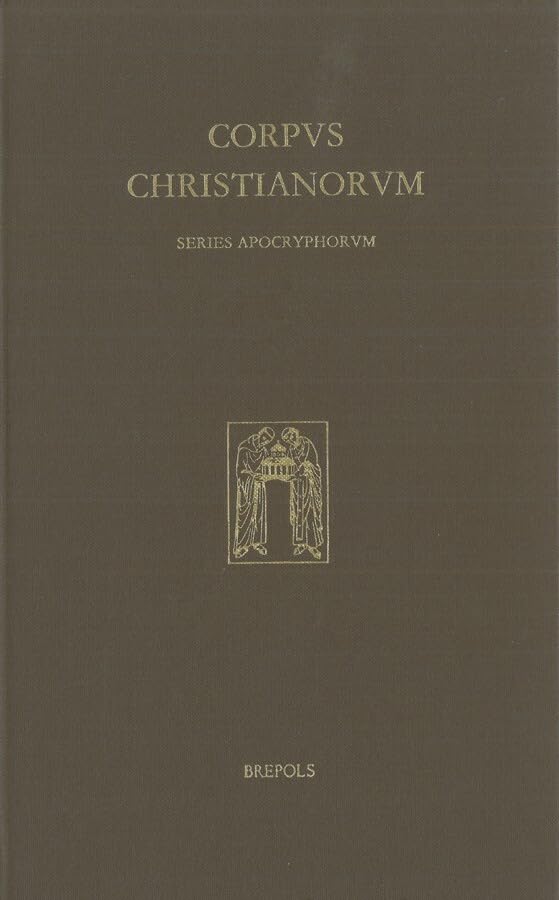1 0 0 0 Acta Philippi
- 著者
- cvra François Bovon Bertrand Bouvier Frédéric Amsler
- 出版者
- Brepols
- 巻号頁・発行日
- 1999
- 著者
- 遠藤 祐
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国文学解釈と鑑賞 (ISSN:03869911)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.12, pp.86-91, 1972-10
1 0 0 0 OA オンラインフリーマーケットを活用した起業家教育の試み
- 著者
- 中川 雅人 河野 篤 北川 博美
- 出版者
- 中部学院大学
- 雑誌
- 中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要 (ISSN:1347328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.83-89, 2006-03
電子商取引に関する技術と知識の習得を目的として、2004年度より、中部学院大学短期大学部経営学科では「ネットビジネス」という科目を新設した。本論文は、この中で実施した「オンラインフリーマーケット」という実践的カリキュラムについて述べている。商品を販売するためのホームページを制作し、電子メールで交渉を行い、代金引換で発送する仕組みを用いて、安全に「モノ」と「カネ」を交換する仕組みを学習するためのカリキュラムを開発した。
1 0 0 0 OA 青紫色半導体レーザー励起によるエネルギー移動固体色素レーザーの発振
- 著者
- 福田 将海 松浦 秀高 坂田 肇
- 出版者
- 一般社団法人 レーザー学会
- 雑誌
- レーザー研究 (ISSN:03870200)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.8, pp.614-618, 2009-08-15 (Released:2015-08-04)
- 参考文献数
- 12
We report the lasing characteristics of solid-state dye lasers that contain two mixed dyes. Pyrromethene
1 0 0 0 OA 光ファイバー上に構築された固体色素レーザーによる曲げセンサーの開発
- 著者
- 久保田 寛之 興 雄司 渡邉 博文 大海 聡一郎 楊 雨
- 出版者
- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会
- 雑誌
- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成22年度電気関係学会九州支部連合大会(第63回連合大会)講演論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.663-664, 2010 (Released:2012-02-24)
我々が開発した固体色素レーザー描画法は、描画的手法で簡易に曲面上にでもDFB色素レーザー導波路が構築可能である。今回、その特徴を利用し、マルチモードのプラスチック光ファイバーのコア表面上に複数本のレーザーを実装した。屈折率をコアよりもわずかに大きく設計すると同時に、レーザー出射部を切り落とし型の端面ではなくテーパー化することで、発振光をコア部に再度結合することが可能となる。本研究では、ファイバーの曲率によりレーザーの波長が変化することを利用して、多元曲げセンサーの観点から開発をおこなった。光ファイバーを曲げたときに内側と外側では波長の変化が異なるため、曲率や曲げた方向も判別可能となる。
- 著者
- 早川 喜郎 川名 隆広 神谷 勇一郎
- 出版者
- 日本食品工学会
- 雑誌
- 日本食品工学会誌 (ISSN:13457942)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.215-220, 2008-12
野菜・果実加工において、濃縮プロセスは、最も重要な技術の1つであり、品質・コストに大きく影響を与えている。本研究においては、多くの食品に適用が可能で、かつ多品種少量生産に適する新規の凍結濃縮技術を開発することを目的とした。この凍結濃縮技術は、界面前進凍結濃縮を原理としており、氷の生産、分離が同一容器内で可能であり、装置構成、操作が非常に簡単なシステムである。濃縮条件の最適化、製氷器の最適設計、氷に含まれる溶質成分の回収と自動化、装置の自動化などの開発を行い、小規模の界面前進凍結濃縮システムを開発した。このシステムを使用してトマトジュースの凍結濃縮試験を行った結果、Brix40%程度の高濃度濃縮が可能であり、香味に優れた濃縮品を得ることが可能であった。また、トマトジュースのように他の果汁に比較するとバルブ質を多く含んでいるジュースでも凍結濃縮が行えることが確認できた。
- 著者
- Kenji Iwaku Fumiko Otuka Matsuo Taniyama
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.335-339, 2017-02-01 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 5
The patient was 32-year-old man, who received olanzapine for schizophrenia and developed polyuria and thirst without drinking soft-drinks after 4 months. Five months after the initiation of treatment, he developed diabetic ketoacidosis (blood glucose: 490 mg/dL, HbA1c: 15.5%). He was diagnosed with type 1 diabetes (glutamic acid decarboxylase (GAD)-Ab: 5.6 U/mL, IA-2 Ab: 5.9 U/mL, fasting C-peptide: 0.12 ng/mL) and was put on intensive insulin therapy. At four months after the onset of 1A diabetes, he experienced a honeymoon phase that was sustained until the 40th month of treatment. We hypothesize that the administration of olanzapine to a patient with pre-type 1A diabetes induced marked hyperglycemia and accelerated the onset of type 1A diabetes.
1 0 0 0 オレンジ・カードの経済計算
- 著者
- からくり堂主人
- 出版者
- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会
- 雑誌
- オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 (ISSN:00303674)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.9, 1986-09-01
1 0 0 0 特集3 IP電話、コスト削減の条件
- 著者
- 坂口 裕一
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.569, pp.134-139, 2003-03-10
昨年12月13日、『日本経済新聞』の朝刊1面に掲載された記事「IP電話全面導入—東京ガス 通信コスト半分以下に」は大きな反響を呼んだ。東京ガスと、今回のネットワーク構築を手掛けるNTTデータには、記事掲載から約2カ月間で百数十件もの問い合わせが寄せられた。その中心はユーザー企業だったという。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経情報ストラテジ- (ISSN:09175342)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.172-175, 2006-04
「データセンターを捜査し、10万通のメールを分析」「経営トップのパソコンなど100台以上を押収」 2006年1月17日。新聞各紙の朝刊1面にはライブドア事件の始まりを告げる見出しが躍った。 前日夜、東京地検特捜部はライブドアの本社やデータセンターに強制捜査に入った。特捜部が不正取引の実態をつかむために注目したとみられるのは、経営陣がやり取りした数々のメール。
1 0 0 0 IR 日本軍の治安戦と三光作戦 (国際ワークショップ 日中戦争の深層(2))
- 著者
- 笠原 十九司 Kasahara Tokushi
- 出版者
- 新潟大学大学院現代社会文化研究科環日本海研究室
- 雑誌
- 環日本海研究年報 (ISSN:13478818)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.17-28, 2011-03
- 著者
- 弓削 孟文
- 出版者
- 克誠堂出版
- 雑誌
- 麻酔 (ISSN:00214892)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.Sp59-64, 1995-10
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA カキにおける新梢生長, 腋芽発育と花芽分化の関係
- 著者
- 原田 久
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.271-277, 1984 (Released:2007-07-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 6 6
カキ‘平核無’における新梢生長, 腋芽の発育と花芽分化の関係について調査した.新梢は主として節間伸長によって伸長し, 新梢茎頂で葉を分化しながら伸長するといったことはみられなかった. 新梢伸長の停止は, 新梢茎頂部が生長を止め, 枯死することによって起こった. 新梢伸長停止後, 腋芽内の葉原基数が急速に増加した. 葉原基数の増加は新梢の肥大生長の影響を受けた. 7月上旬になると, 腋芽茎頂での葉原基の分化が次第に抑えられ, それとともに葉原基の腋部分裂組織が隆起し, その後多くは花芽へと発達した. 花芽分化は腋芽の発育や腋芽の茎頂分裂組織の活性低下と密接な関係をもって起こっていると考えられた.
- 著者
- 渡辺 漸
- 出版者
- Okayama Medical Association
- 雑誌
- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.12supplement, pp.53-66, 1958 (Released:2009-08-24)
- 参考文献数
- 20
No systemic study to induce leukemia in the experimental animals with the internal irradiation with radioactive isotopes has ever been attempted. We set about experiments with this object in 1953 and succeeded in the induction of experimental leukemia in dt, ddF and ddN uniform strain mice treated with small frequent doses of P32, Sr89 and Ce144.Single dosis of the isotopes ranged from 0.03 to 0.5 μc per gram body weight twice a week was administrated to mice with the methods of intravenous injection, intraperitoneal injection, intratracheal administration and intraesophageal dripping. The total administrations of the isotopes were 7-16 times.The development of leukemia was confirmed in higher frequencies among mice which were administered with small frequent doses of P32. The highest incidence of leukemia throughout our experiments was about 42% in the experiment with P32 at 0.3-0.5 μc level.The development of leukemia remains in lower frequencies among mice which were given small frequent doses of Sr89 or Ce144. In the former cases we confirmed the higher incidence of osteogenic sarcoma. In the latter cases the aplasia of the bone marrow were easily resulted.Among the Beta-emitting radioisotopes the one which has the shorter halflife and more intensive energy such as P32 is more suitable to induce leukemia in mice so far we had experienced.The excessive and at the same time partially abnormal regeneration preceed the development of leukemia after the administrations of small frequent doses of the radioisotopes.The order of the intensity of the radioactivity in the bone after the administration of the radioisotope change from time to time. Such effect will also contribute to enforce the abnormal regeneration of the bone marrow.For the development of leukemia in mice after the administration of the frequent small doses of the radioisotope we should not overlook the most intensive regenerative hematopoietic activity in the bone marrow corresponding middle portion of the long bone such as the femur.
1 0 0 0 経済学
- 著者
- P.A.サムエルソン [著] 都留重人訳
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1974
- 著者
- 張 青華
- 出版者
- 一般社団法人中国研究所
- 雑誌
- 中国研究月報 (ISSN:09104348)
- 巻号頁・発行日
- no.493, pp.31-38, 1989-03-25
1 0 0 0 OA 日本漢語の史的音韻論的課題(<特集>借用語音韻論の諸相)
- 著者
- 高山 知明
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.44-52, 2002-04-30
The aim of this article is to emphasize the necessity for further investigation into the relationship between Sino-Japanese and Yamato, and to present a couple of topics on the historical phonology of Japanese. One of the main questions that deserves to be challenged is how the indigenous structure extended to SJ word formation, such as geminations, of which the earlier stage can be hardly attested by historical records. Another topic concerns vowel coalescence. The interesting interaction between SJ word types and Yamato accounts for these sound changes.
1 0 0 0 OA かるかんの凍結保存中における物性変化について
- 著者
- 大山 重信 立山 冬子
- 出版者
- 鹿児島県立短期大学
- 雑誌
- 鹿児島県立短期大学紀要. 自然科学篇 (ISSN:02861208)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.17-29, 1991-12-16
Karukan sample A and E were stored at-20℃ for 56 days. Thawing was made with microwave oven. Rheological properties were examined with colorimeter, rheometer, tensilon meter, and texturometer. Moisture was also determined. Moisture decreased during one week or so at the beginning of frozen storage, and whiteness decreased slightly, too. Flastic deformation values of both sample decreased by frozen storage. On the other hand, retarded elasticity and visco-elasticity remained almost unchanged (Fig.7 and 8). The values of hardness which were measured with texturometer increased at the beginning of frozen storage and the change was observed specially in the case of sample E (Fig.11 and 12). Each area of the first, second, and third peak in texture profile curve obtained on texturometer for both sample A and E increased at the biginning of frozen storage (Fig.13 and 14). It means that the work done in each chew of the samples under frozen storage is harder than that of unfrozen. Cohesiveness of sample E became larger than before freezing (Table 1). Gumminess of both sample became larger than before freezing, as well (Tabele 1). It means that more energy will be required to chew and make sample to as tate ready for swallowing. In general, the changes in properties occured during 7 days or so at the beginning of frozen strage, and the changes on sample E came out more clearly than those on sample A. Thereafter, the properties of both sample seemed to remain almost unchanged during frozen storage. The changes stated above showed the quarity of the starting samples of "Karukan" suffered deterioration more or less by frozen storage and thawing.
1 0 0 0 OA かるかんの調製について
- 著者
- 大家 千恵子 松本 エミ子
- 出版者
- 一般社団法人日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.110-118, 1986-07-20
- 被引用文献数
- 1
かるかんの材料配合, 調理手法, 米粉の粒度などが調理製品の性状に及ぼす影響を, 製品の官能検査, 物性測定, 顕微鏡観察によって調べた。1. かるかんの材料配合比は生山芋, 水, 砂糖, 米粉の比が1:1:2:1.3, 乾燥粉末山芋では1:4:2:1.3が好ましい。調理手法はすりばち-すりこぎ法で良い結果が得られた。2. かるかんは官能検査の結果から, 米粉粒度60メッシュを用いたものが好ましく, 粒度の小さいものはカステラ様の感触のものとなる。3. かるかんの顕微鏡観察で米粉粒度のちがいがみられ, また, 山芋の蓚酸カルシウム針状結晶がそのまま残存し, 完全に糊化していない山芋でんぷんも観察された。