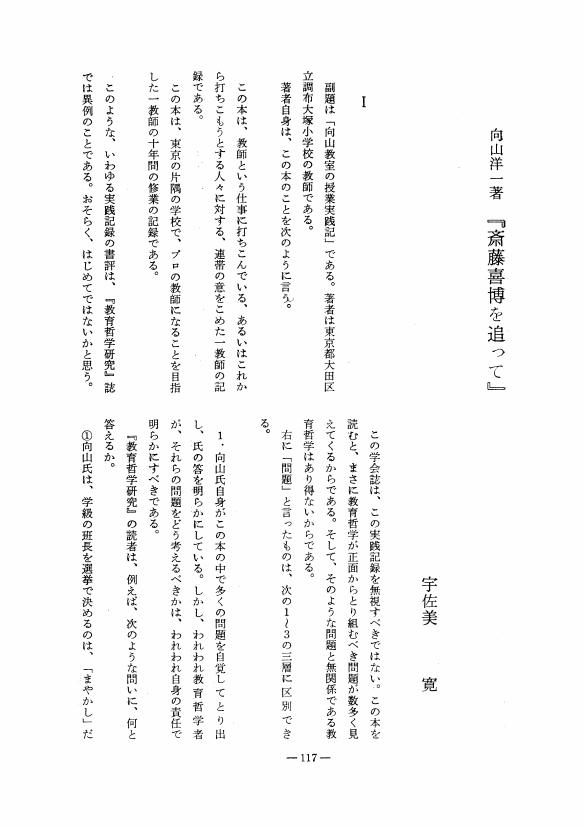- 著者
- 鈴木 大地 中村 雅俊 大箭 周平 青木 孝史 江玉 睦明
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.117-123, 2019-04-01 (Released:2019-03-16)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 2
It is well known that eccentric exercise induces muscle damage that is characterized by a prolonged decrease in muscle strength and range of motion, development of delayed onset muscle soreness, and swelling. Therefore, the present study aimed to compare the acute effects of hold-relax stretching (HRS) with those of static stretching (SS) on muscle strength and soreness. The participants comprised 28 male volunteers randomly assigned to either the HRS group (N = 14) or the SS group (N = 14). Initially, the participants of both groups performed 60 maximal eccentric contractions of the knee extensors. Two and four days after this exercise, each group performed either HRS or SS for 60 s at a time and repeated them six times for a total of 360 s. Muscle strength and soreness during stretching and contraction were measured before and immediately after HRS and SS. The results showed that the muscle soreness observed after eccentric contraction significantly decreased immediately after both HRS and SS were performed two and four days later. In addition, there were no significant changes in muscle strength immediately after both HRS and SS were performed two and four days later. The rate of change in muscle soreness after HRS was significantly higher than that after SS two days post eccentric contractions. These results suggest that while both HRS and SS can effectively decrease muscle soreness, the effect of HRS on muscle soreness was larger than the effect of SS.
5 0 0 0 OA 東日本大震災アーカイブの閉鎖:ひなぎくによる承継の試み
- 著者
- 井上 佐知子
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.155-158, 2022-11-01 (Released:2023-01-05)
- 参考文献数
- 12
東日本大震災を契機に、震災記録を収集保存するために多様な組織により多くの震災アーカイブが立ち上げられ、国立国会図書館はそれらのポータルとなる東日本大震災アーカイブを公開した。しかし、これらの震災アーカイブの維持運営には様々な課題があり、震災から10年以上が経過した現在、維持困難となって閉鎖された事例も出てきている。国立国会図書館は、閉鎖された一部の震災アーカイブの資料を承継して公開を続けており、承継に伴う権利処理など様々な課題に取り組んでいる。本稿ではその経験に基づきアーカイブの閉鎖とそれに伴う課題について述べる。
5 0 0 0 OA 総論:デジタルアーカイブの消滅と救済
- 著者
- 柴山 明寛
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.151-154, 2022-11-01 (Released:2023-01-05)
- 参考文献数
- 5
1990年頃から国内外でデジタルアーカイブ構想が活発化しはじめ、現在、博物館や図書館、教育機関などで数多くのデジタルアーカイブが構築されている。その一方で様々な理由によりデジタルアーカイブが消滅している現状がある。デジタルアーカイブが消滅する理由としては、デジタルアーカイブを運営する組織的な課題とデジタルアーカイブのシステム的な課題があると考える。そこで本総論では、デジタルアーカイブが消滅する理由について「組織的な課題」と「システム的な課題」を概説するとともに、救済方法についても概説する。
5 0 0 0 OA 大日本古文書
- 著者
- 東京帝国大学文学部史料編纂所 編
- 出版者
- 東京帝国大学
- 巻号頁・発行日
- vol.家わけ九ノ一, 1925
- 著者
- さかなクン
- 出版者
- 東洋館出版社
- 雑誌
- 初等教育資料 (ISSN:04465318)
- 巻号頁・発行日
- no.887, pp.88-92, 2012-06
- 著者
- 廣津 伸夫 長谷川 貴大 税所 優 村手 純子 池松 秀之 岩城 紀男 河合 直樹 柏木 征三郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.1, pp.117-125, 2014-01-20 (Released:2016-09-27)
- 参考文献数
- 15
発熱疾患の鑑別には末梢血検査が行われ,細菌感染においてその診断および治療効果の判定に有用な手段となっているが,ウイルス感染においてはその検討は少なく,明確な見解はない.このたび,2004/05 年度から2009/10 年度に至る発熱疾患に対するルーチンの末梢血検査(白血球数とその分画およびCRP)の蓄積を後ろ向きに検討した結果,季節性インフルエンザA 型(H3N2 及びH1N1 を含む,以下季節性A 型)614 例と2009/10 年のパンデミックインフルエンザ(H1N1)2009(以下,A/H1N1/pdm09)548 例の述べ1,162 例からインフルエンザの特徴的な所見が示され両者の違いも明らかとなった. 検討に当たっては,白血球とその分画は年齢により異なるため,全症例を一般化加法モデル(GAM,generalized additive model)を用いて年齢調整を行い,解析を実施した.インフルエンザの感染初期には顆粒球の増加,リンパ球の減少が確認され,その後顆粒球は減少,リンパ球は増加に転じることが観察された.顆粒球数では,季節性A 型に対してA/H1N1/pdm09 は,治療開始前は0.93 倍,治療後は0.82 倍とそれぞれで統計的に有意に低く推移していた.リンパ球数の比率は,治療開始前,治療後のいずれも,1.12~1.30 倍であり,統計的に有意に高い推移であった.CRP は発症後24 時間から36 時間にピークを迎え,その平均値はA/H1N1/pdm09 で0.88mg/dL,季節性A 型で1.53mg/dL であった. 末梢血は疾病の時間的経過,合併症の併発,治療による修飾,治療薬の副次作用等によって変動する.このようなインフルエンザ本来の末梢血の白血球分画の変化・動態を知ることは,診断時(特に迅速診断の要否の判断),経過中の合併症や副作用の出現を把握するために重要と考え報告する.
5 0 0 0 OA 事物知覚とエナクティヴィズム どうして物を見ることが身体的行為なのか
- 著者
- 宮原 克典
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.68, pp.200-214, 2017-04-01 (Released:2017-06-14)
- 参考文献数
- 21
This paper proposes an enactive account of thing-perception by integrating a descriptive, phenomenological analysis of thing-perception with the American philosopher John Haugeland’s account of “objective perception.” Enactive views of perception hold that perception is a form of embodied action. They apply well to the kind of perception that directly guides embodied action, but so far there is no convincing account as to how they might accommodate “thing-perception,” or the kind of perception that merely presents physical objects as things as such. Phenomenologically speaking, thing-perception is a temporally extended process of transforming an inarticulate appearance of a physical object into an articulate one. Furthermore, such transformation is shaped by embodied action guided by a normative sensitivity to the environment. Accordingly, phenomenological description suggests that ordinary thing-perception depends on the operation of bodily skills or bodily habits of certain kinds. On the other hand, Haugeland submits that our perceptual experience has the structure of objectivity by virtue of our antecedent commitment to certain constitutive standards. In particular, thing-perception is essentially dependent on our commitment to the constitutive standard for thinghood: We experience things as perceptual objects because of our preparedness to maintain in our experience a pattern of phenomena in accord with this constitutive standard. I claim that it is one and the same thing to have a commitment to the constitutive standard for thinghood and to have a bodily habit of seeing physical objects as things as such. Furthermore, I argue by thus integrating the two accounts described so far that thing-perception is essentially dependent on a form of embodied action. To have a bodily habit of seeing something as such is to have a commitment to the constitutive standard for thinghood, and the latter commitment is necessary for thing-perception to take place. Therefore, thing-perception is essentially a form of embodied action.
5 0 0 0 OA 東京湾内湾の干潟域の魚類相とその多様性
- 著者
- 加納 光樹 小池 哲 河野 博
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.115-129, 2000-11-27 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 9
A total of 61, 388 fish specimens, representing about 60 species, were collected by monthly seine-net (mesh size 0.8 mm) samplings at the seven tidelands in the inner Tokyo Bay, Pacific coast of central Japan, from April 1997 to March 1998. Two gobiid species, Acanthogobius flavimanus and Chaenogobius macrognathos, were the most abundant species, contributing 52.6 and 20.7% of the total number of fishes, followed by Chaenogobius castaneus (7.7%), Lateolabrax japonicus (6.3%) and Mugil cephalus cephalus (6.0%). Eight “estuarine” and 19 “marine” species, which occupying 99.4% of total number of fishes, were highly possibly c0onsidered to depend on tidelands for their considerable part of life history, because of the occurrence of some developmental stages. The diversity of fish community was higher in Obitsu River and Edo River than in other five sites, in the first two rivers, large tidelands having remained in spite of coastal construction since 1950's. The results of this study would indicate that the diversity of fish community at tidelands reflect more or less an impact of emvironmental changes by the reclamation of the inner Tokyo Bay.
- 著者
- Shoko Tomooka Emi Oishi Masako Asada Satoko Sakata Jun Hata Sanmei Chen Takanori Honda Kosuke Suzuki Hiroshi Watanabe Norihito Murayama Naohisa Wada Takanari Kitazono Toshiharu Ninomiya
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20220232, (Released:2022-12-24)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
Background: The association between chronic lipopolysaccharide exposure and the development of metabolic syndrome (MetS) is unclear. In this study we examined the association between serum lipopolysaccharide-binding protein (LBP) levels, an indicator of lipopolysaccharide exposure, and the development of MetS in a general Japanese population.Methods: 1,869 community-dwelling Japanese individuals aged ≥40 years without MetS at baseline examination in 2002–2003 were followed up by repeated examination in 2007–2008. MetS was defined according to the Japanese criteria. Serum LBP levels were classified into quartiles (quartiles 1–4: 2.20–9.56, 9.57–10.78, 10.79–12.18, and 12.19–24.34 μg/mL, respectively). Odds ratios (ORs) for developing MetS were calculated using a logistic regression model.Results: At the follow-up survey, 159 participants had developed MetS. Higher serum LBP levels were associated with greater risk of developing MetS after multivariable adjustment for age, sex, smoking, drinking, and exercise habits (OR [95% confidence interval] for quartiles 1–4: 1.00 [reference], 2.92 [1.59–5.37], 3.48 [1.91–6.35], and 3.86 [2.12–7.03], respectively; P for trend <0.001). After additional adjustment for homeostasis model assessment of insulin resistance, this association was attenuated but remained significant (P for trend=0.007). On the other hand, no significant association was observed after additional adjustment for serum high-sensitivity C-reactive protein (P for trend=0.07).Conclusions: In the general Japanese population, our findings suggest that higher serum LBP levels are associated with elevated risk of developing MetS. Low-grade endotoxemia could play a role in the development of MetS through systemic chronic inflammation and insulin resistance.
5 0 0 0 OA 加藤寛治大将伝
- 著者
- 加藤寛治大将伝記編纂会 編述
- 出版者
- 加藤寛治大将伝記編纂会
- 巻号頁・発行日
- 1941
5 0 0 0 OA 日本人の化粧に対する意識 ―女性の化粧義務の解消に向けて―
- 著者
- 山下 海 矢野 円郁 Umi YAMASHITA Madoka YANO
- 雑誌
- 女性学評論 = Women's Studies Forum
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.63-75, 2020-03-20
現代の日本社会では、「化粧は女性の身だしなみ」といわれ、職場などで女性にのみ化粧が課されることがある。女性に対してのみ課される「身だしな み」や服装規定は、化粧だけに限らない。仕事場で、女性のみヒールの高い靴を履かされたり、眼鏡をかけることを禁止されたりすることもある。これらの規定は、健康被害を生み、職務に支障をきたしうるものであり、世界的に、このような女性に対する理不尽な服装規定を廃止する動きが広がっているが、日本ではいまだに、「仕方がないこと」として許容する人も少なくない。化粧については、日本人女性も楽しみで行う人もいるが、女性だからしなければならないという義務感にかられてのみ化粧を行う人も少なくない。逆に、男性が化粧することに対して否定的な人もいる。男女問わず化粧をしたい人がし、したくない人に強要しない社会にするためには、人々のジェンダーステレオタイプをなくしていかなければならない。本稿では、化粧行動の歴史や化粧に対する意識についての研究を紹介しつつ、ジェンダーステレオタイプにとらわれない寛容な社会を築くために考えるべきことを議論する。
5 0 0 0 多職種協働のための共通言語としてのICFへの期待と課題
- 著者
- 中俣 恵美
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.9, pp.706-710, 2016
- 被引用文献数
- 1
医療・福祉・保健分野において,高齢化および疾病構造の変化に伴う課題解決の方策として多職種協働による地域包括ケアシステムが注目されている.これには職種間の相互理解,各々の高い専門性の追求にとどまらず,職種間の隔壁を超えた幅広い視野をもってアプローチすることが求められる.そして,これを具現化するためにはICFを共通概念,共通言語として活用することが必要である.ICFは生活機能を包括的に捉える視点と枠組みを示すものであり,これを協働のためのツールとして取り扱うことが望ましい.しかし現状では概念の取り違えやツールとしての活用に課題もある.本論ではICFの特性について再確認すると共に実践の現場での活用方法を述べる.
5 0 0 0 OA 佐世保市行政による軍港像の創出
- 著者
- 山本 理佳
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.10, pp.634-648, 2005-09-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 2
本稿は,長崎県佐世保市を事例として,地方自治体がいかなる軍事施設イメージを提示しているのかを明らかにすることを目的とした.特に軍事施設の存在が憲法第9条で明示された「平和」理念と矛盾するという点に着目し,それに対してどのように対処しようとしているのかを検討した.具体的には,そうした「平和」との矛盾を顕在化させた事象として,1960年代の米軍原子力艦艇寄港反対運動を位置づけ,これに関連する時期や場所について分析を行った,その結果,佐世保市行政は,顕在化した矛盾に抵触しないよう,さまざまなレトリックを駆使しつつ,軍事施設イメージを創り出していた状況が明らかとなった.
- 著者
- 小川 成
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.313-321, 2016-09-30 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
慢性の腰痛を併存した社交不安症に対しアクセプタンス&コミットメント・セラピー(Acceptance and Commitment Therapy: ACT)を施行した経験について報告する。クライエントは40歳代の女性である。経過の中で認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy: CBT)を施行したが改善は見られていなかった。アイフォート・フォーサイス(2012)のマニュアルに基づいた毎週1時間、計12回のACTを施行した結果、社交不安症の症状と腰痛に変化が見られた。しかし、CBTを施行されたことのあるクライエントの場合、ACTとCBTを混同する可能性があり留意すべきである。
5 0 0 0 OA 数種ゴキブリの体表ワックスの化学分類学的考察
- 出版者
- 日本環境動物昆虫学会
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.31-38, 1989 (Released:2016-08-01)
5 0 0 0 OA 向山洋一著『斎藤喜博を追って』
- 著者
- 宇佐美 寛
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1981, no.43, pp.117-122, 1981-05-10 (Released:2009-09-04)
5 0 0 0 OA ダクタイルセグメントの耐食性と耐久性に関する調査研究
- 著者
- 佐藤 宏志 渡辺 仁 品部 耕二郎 小泉 淳
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.756, pp.21-31, 2004-03-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 11
ダクタイルセグメントは使用期間が最も長いものでは約37年あまりが経過したが, 二次覆工が行われない場合も多いため, その耐食性, 耐久性が問題になると考えられるが, その実態は従来ほとんど明らかにされていなかった. 本論文は, 供用中のダクタイルセグメントの腐食に関する継続的な調査結果を分析し, ダクタイルセグメントの耐久性を考察するものである. まず, セグメントの肉厚測定の方法およびその信頼性について述べ, 次に調査の内容およびその結果を述べる. この調査結果から, ダクタイルセグメントの主要肉厚は少なくとも24年間においてほとんど減少していないことがわかり, ダクタイルセグメントは現在のところ健全性を維持しており, 今後も長期間使用できると考えられる.
5 0 0 0 OA 最重度知的障害を伴う自閉症のある成人に対する時計の読みの指導(実践研究)
- 著者
- 藤田 昌也 松見 淳子 平山 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.195-204, 2011-09-30 (Released:2019-04-06)
本研究は、最重度知的障害を伴う自閉症成人女性に対して、1時間単位の時計の読みと時系列の順序を指導した事例研究である。対象者は、28年間施設を入所利用し、)し2年から重症心身障害児施設を入所利用する41歳の最重度知的障害を伴う自閉症のある女性である。モデル提示、弁別訓練、プロンプトを用いた約30分の指導セッションを45試行、フォローアップを5試行実施した。介入の結果、アセスメントでは7以上の数字を読むことができなかった対象者が、段階的な指導を行うことにより1時間単位の時計の読みと時系列の順序を獲得することができた。3カ月半後のフォローアップでは時計の読みスキルの維持と他の時計への般化も確認された。本研究の結果から、段階的な行動的支援方法を用いることにより、最重度知的障害を伴う自閉症成人に対して、日常生活に応用可能な新たなスキルを形成できることが示された。