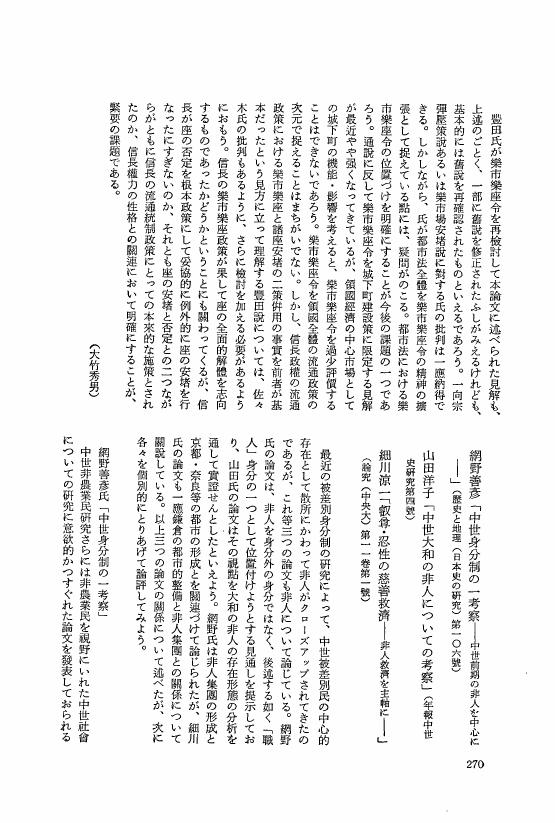- 著者
- 川端 裕人
- 出版者
- 日本視覚学会
- 雑誌
- VISION (ISSN:09171142)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.10-14, 2022
5 0 0 0 OA 寛永元年刊「大日本国地震之図」なるものについて
- 著者
- 野間 三郎
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.415-425, 1965-08-28 (Released:2009-04-28)
5 0 0 0 IR 生活保護受給者の生活満足度と関連する心理社会的要因の検討
- 著者
- 吉住 隆弘 山田 壮志郎
- 出版者
- 中部大学人文学部
- 雑誌
- 人文学部研究論集 (ISSN:13446037)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.99-109, 2012-07
生活保護受給者の支援方法については多くの議論がなされているが,心理学的側面からの検討はほとんどなされていない。そこで本研究では,生活保護受給者の生活満足度に着目し,それに影響を与える心理社会的要因について検討した。調査対象者は,現在生活保護を受給している106名(男性98名,女性8名,平均年齢57.8歳)であった。生活必需品に関する領域,社会的ネットワークに関する領域,心理的要因に関する領域に注目し,各領域に含まれる変数が,生活満足度に与える影響性について探索的に検討した。重回帰分析の結果,定職を持っている人,ケースワーカーの対応を良いと感じている人,そして余暇活動を積極的に行っている人は,生活満足度が高いことが示された。生活保護受給者のウェルビーイングの増進において,従来の就業支援に加え,余暇活動の推進やケースワーカーの対人援助スキルが重要な役割を担っていることが示された。
- 著者
- 千葉 精一
- 出版者
- 尚美学園大学芸術情報学部
- 雑誌
- 尚美学園大学芸術情報学部紀要 (ISSN:13471023)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.11-32, 2006-11
近年、音楽用CDの世界ではポップス・ロック系ジャンルを中心に音量感(ラウドネス:LOUDNESS)を上げるためのレベル競争が激しくなってきている。それらの中には音量感を上げるための処理に行き過ぎと思われるものも見受けられ、音量感は上がったものの音質劣化や楽器バランスの変化が起きているのではないかとの疑問を持つに至り、その状況を検証し適正なCD収録レベルは如何にあるべきかについて考察を試みた。また、DVD-Videoは発売当初、映画が市場の大半を占めていたが最近ではライブやプロモーション映像を収録したミュージックDVDも多くのタイトルがリリースされてきている。これらの中にCDとDVD-Videoがひとつのパッケージに同梱された商品形態があり、一部には収録音声レベルにかなり差のある商品も存在することが判明した。音声レベルにばらつきがあることはユーザーにとって「その都度ボリュームを調整せざるを得ない」という不便さを招き、また同一メディアでありながら音量にバラつきがあること自体も問題であり、実態の検証と原因、改善策などについて考察してみた。
5 0 0 0 OA 社会福祉学における参加論の系譜と利用者参加概念の発展(II)
- 著者
- 児島 亜紀子
- 出版者
- 長野大学
- 雑誌
- 長野大学紀要 = BULLETIN OF NAGANO UNIVERSITY (ISSN:02875438)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.51-59, 1998-12-26
- 著者
- 村上 正二
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 (ISSN:03869067)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.305-339, 1961-12
The Mongol term soyurqal, which meant a kind of fiefdom in Činggis Qan's Empire of the early thirteenth century, was obviously derived from the verb soyurqa-qu, 'to grant a favor'. This verb, along with its passive form soyurqaγ-da-qu, frequently occurs in the Mongolian text of the Secret History of Mongols where it is voiced reciprocally between the knight and the lord in the oath of allegiance, in a set pattern of expression. The noun soyurqal seems to have originally meant any kind of gracious deed or thing bestowed by the lord upon the knight in reward for the latter's lasting service or distinguished merits. Later it came to denote a wide range of inherited privileges conferred upon grand knights and princes, concerning their emčü irgen (subject-peoples), sometimes accompanied by the so-called darqan right, i. e. special right of tax exemption or impunity. In the early stage of the Mongol Empire, those subject-peoples, who were granted to knights or princes, mostly consisted of non-Mongolians, qari-yin irgen, or, to be more exact, natives of non-steppe areas who had been captured on the battle-field. As soyurqal was a special favor of the Qan, the recipient was excused from the duties such as taxes and corvées otherwise to be assessed upon it by the State. On the other hand, the majority of the people of the Mongol States and Empire, generally called ulus irgen or qanliγ irgen, were mainly peoples of steppe origin, who were .placed under a direct control of the central government and were imposed upon with all sorts of nomadic taxes and corvées. In contrast to the emčü irgen, the ulus irgen were portions of heritage, qubi kešig, of the common property, i. e. the Empire's peoples, divided among Činggis Qan's family members in accordance with the traditional law of succession of Mongols. In Mongolia of this stage, a Qaγan or a king of a State had a double personality, public and private; as a private person, even he could possess his own private domain in the form of an ordo with all its paraphernalia, while a prince or a knight had soyurqal instead. This was why the ulus irgen of the Empire or the States were registered in census books under an entirely different category from that of the emčü irgen of the kings or knights.
- 著者
- 前田 和哉
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.394-400, 2020-11-25 (Released:2021-02-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
Pharmacokinetic boosterは、CYP3A、P-gpの良好な基質であるために、経口投与時に血中での十分な暴露の確保が困難であったHIVプロテアーゼ阻害薬等の代謝・排出経路を強力に阻害することによって、血中暴露の劇的な改善に貢献してきた。古くは治療量よりは低投与量のリトナビルが用いられてきたが、その後、リトナビルと異なり薬効をもたず、酵素誘導能も喪失した構造類縁体のコビシスタットが純粋なboosterとして、各種薬物との配合剤として用いられるようになった。リトナビルとコビシスタットは、消化管・肝臓CYP3Aの強力な阻害を呈する一方、リトナビルは、複数の代謝酵素の誘導も引き起こすため、両者の間で処方変更があった場合、併用薬の体内動態に影響するケースがあることに留意する必要がある。
5 0 0 0 OA 平起り七言絶句転句における下三挟み平 (●○●) と四字目の孤平について
- 著者
- 鷲野 正明
- 出版者
- 国士舘大学文学部人文学会
- 雑誌
- 国士舘人文学 = Kokushikan journal of the humanities (ISSN:21876525)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.101-118, 2019-03-15
5 0 0 0 OA 哺乳類研究における非実験データセットに対する回帰分析の適用について
- 著者
- 竹下 和貴 林 岳彦 横溝 裕行
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.69-79, 2022 (Released:2022-02-09)
- 参考文献数
- 33
回帰分析は,説明変数の変動から目的変数の変動を定量的に説明しようとする統計手法である.回帰分析には,目的変数と説明変数の関係の記述,説明変数による目的変数の予測,目的変数に対する説明変数の介入効果の推定という3つの目的が存在するが,それら3つの目的の間で説明変数の選択基準が異なることに対して,国内の哺乳類研究者の理解はあまり進んでいないように思われる.また,哺乳類研究では,集団(例えば個体群)の平均だけでなく,平均から外れたもの(低順位個体など)も,重要な研究対象となり得る.しかし,これまでの国内の哺乳類研究では,目的変数の条件付き期待値に着目した回帰分析が半ば無自覚的に選択される傾向があり,それ以外の値に対する回帰分析は行われてこなかった.本稿では,記述,予測,そして介入を目的とした回帰分析における統計学的な留意点を整理するとともに,分位点回帰と呼ばれる,任意の分位点に対する回帰直線を推定することができる統計手法の導入による哺乳類研究の今後の発展性を記した.
5 0 0 0 OA 人工現実感によるシステムキッチン体験システム
- 著者
- 野村 淳二
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.1352-1355, 1991-08-05 (Released:2009-10-08)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
5 0 0 0 OA 書評:小松原織香『性暴力と修復的司法:対話の先にあるもの』
- 著者
- 品川 哲彦
- 出版者
- 関西倫理学会
- 雑誌
- 倫理学研究 (ISSN:03877485)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.146, 2019 (Released:2020-01-09)
- 著者
- 呉 祖維 野地 朱真
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.16, pp.161-162, 2012-03-09
- 参考文献数
- 5
本論文では日本の動画制作会社マッドハウスが2010年にリメイクしたアメリカスーパーヒーローアニメ作品「X-MEN」を中心にし、ストーリー設定、キャラクターデザインから作画まで、海外アニメーションと日本のアニメの違いを比較し、分析する。
5 0 0 0 OA サービスデザイン再考 ─ 相互主観性からの視座 ─
- 著者
- 山内 裕 佐藤 那央
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.64-74, 2016-01-08 (Released:2020-04-28)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
本稿では既存のサービスデザインの概念を社会科学の理論的視座から再考する。その目的は既存のサービスデザインを否定することではなく,その更なる発展のため,サービスデザインの実践研究とサービスの理論の接合を試みることにある。そこで,本稿ではサービスは相互主観性レベルの事象であるという主張を元に,サービスデザインにおける基礎的な概念である,「体験」や「共創」が孕んでいる理論的矛盾点を指摘する。具体的には,これまで利用者やステークホルダーがデザインされた,あるいはされる対象を客体として観照し体験しているという主観性の概念に依拠するのではなく,これらの人々が自分の理解をどのように示し合うのかという相互主観性の水準で議論することで,従来のデザイン方法論と比較したときのサービスデザインの独自性を明確にする。従来から議論されている方法論は主観性を基礎としている限りにおいて,相互主観性の水準で議論されるべきサービスデザインの方法論として適切ではなく,独自の方法論を探究しなければならない。
5 0 0 0 OA ストレッチャーの持ち上げ操作時における身体負荷の男女差と対策
- 著者
- 坂口 英児 安田 康晴 山本 弘二 吉川 孝次 佐々木 広一 友安 陽子 竹井 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5, pp.712-716, 2021-10-31 (Released:2021-10-31)
- 参考文献数
- 15
背景:救急活動においてストレッチャー操作は不可欠であり,とくにストレッチャーの持ち上げ操作における身体負荷は男性より女性のほうが大きいと考えられる。目的:ストレッチャー操作での男女の身体負荷を明らかにし,その対策を検討する。対象と方法:救急救命士養成課程の学生男性24名,女性5名を対象に,ダミーを乗せたストレッチャーの持ち上げ操作前後の自覚的運動強度と客観的運動強度の身体負荷をそれぞれ比較した。結果:自覚的運動強度での身体負荷は65kgの頭側と75kgの頭側,尾側で男性より女性のほうが有意に大きかった(p<0.05)。65kgの尾側では身体負荷に有意差はないものの,男性より女性のほうが身体負荷を感じていた。客観的運動強度での身体負荷は65kg,75kgともに頭側,尾側で男性より女性のほうが有意に大きかった(p<0.05)。考察:腰痛予防対策指針には重量物取扱い作業時の自動化・省力化が示されている。女性救急隊員の身体負荷の軽減や活躍できる環境を整えるために,女性がストレッチャー操作する際には頭側を避け,尾側の左右に1名ずつ配置し持ち上げ操作を行うなどの対策や,電動ストレッチャーを導入するなどの対策が必要である。
- 著者
- 松尾 剛次
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.30, pp.270-274, 1981-03-30 (Released:2009-11-16)
5 0 0 0 OA 山本信良・今野敏彦著『近代教育の天皇制イデオロギー』
- 著者
- 佐藤 秀夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.238-240, 1974-09-30 (Released:2009-01-13)
5 0 0 0 OA 軽水炉プラント―その半世紀の進化のあゆみ 第1回 原子力発電前史
- 著者
- 吉川 秀夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.9, pp.613-618, 2007 (Released:2019-04-16)
- 参考文献数
- 6
5 0 0 0 OA 社会地理学と教育社会学との接点
- 著者
- 川田 力
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.187-202, 1994-04-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 178
- 被引用文献数
- 2 1
At present, the theoretical framework and viewpoint of social geographical analyses of education are at the stage of formation, trial and error. It is important at this stage to examine the themes and results of geography and its related disciplines on education. The purpose of this paper is to identify distinctive themes of social geographical analyses of education and to examine their analytical methods, with due consideration for educational sociology, one of the nearest disciplines to social geographical analyses of education.In the field of educational sociology in Japan since the 1980's, great interest has been aroused in the structural principles of education and society as social problems. Also it has been seen as important to question the stratified society of Japan in connection with unequal chances to receive an education. So the problem of to what extent education contributes to the reproduction of an unequaly stratified social system has been dealt from the viewpoint of cultural reproduction theory. In this way, educational sociology examined facets like educational careers, stratified culture, life course and gender. It adopts four approaches: historical, quantitative, system -theoretical and hermeneutic. These approaches have been or can be developed also in geography.In contrast to educational sociology, geographical analyses of education have shown two research directions. One examines regional disparities in education and their effects on the inhabitants of that region. The other considers locational problems of educational institutions from an administrative viewpoint. In these two streams, the former is more inclined to social geographical analysis than the latter. In this case social geography encounters the problem that spatial differences in both standards of education and ability are formed by individuals or society, which is an assembly of individuals, neither by the region itself nor space. But society is inseparable from region and space. So spatially reproductive processes of regional disparities are at work with Bourdieu's cultural reproductive processes. And this furnishes an important, noticeable theme in social geographical analyses of education.To examine those processes, we are able to use approaches which have been adopted by educational sociology. Results from time-geography, which parallels the viewpoint of life course in educational sociology, and core-periphery theory will provide important suggestions for emphasizing spatial aspects.