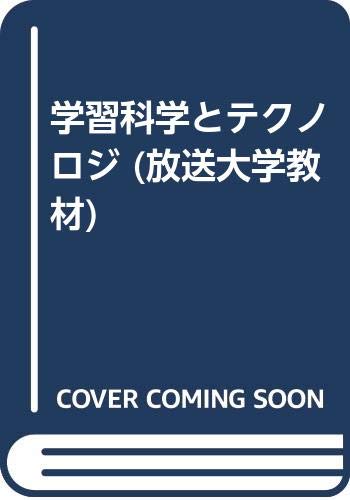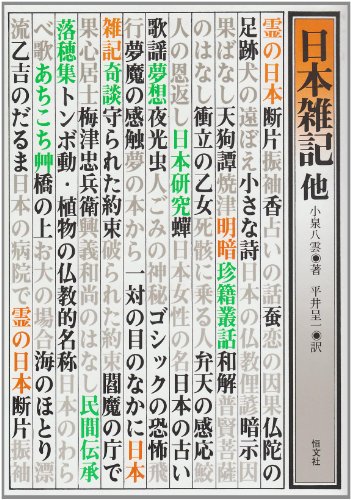1 0 0 0 OA 共生の宗教へむけて――政教分離の諸相とイスラーム的視点をめぐる地域文化研究
「宗教的近代」を疑問に付す諸現象(宗教の再活性化、保守革命、イスラーム民衆運動)に対して西洋諸社会が警戒を示すなかで、寛容を創出すべき政教分離の制度が、かえってマイノリティ抑圧へと転化する状況が見られる。本研究では、民主主義的諸価値が特定の宗教に対して動員され、グローバル化に伴う社会問題を相対化、隠蔽する様子を分析した。フランスでは、国家が対話しやすいイスラーム教を制度化するという、政教分離に矛盾する動きも見られた。他方で、ナショナル・アイデンティティとしてのライシテ(脱宗教)が、イスラーム系市民を周縁化しつつ、差別、経済格差、植民地主義的な人種主義をめぐる問題提起をむずかしくしている。
1 0 0 0 学習科学とテクノロジ
1 0 0 0 IR 「無始時来」の原語と思想--anamataggaとanadikala
- 著者
- 佐々木 現順
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.p1-15, 1978-01
- 著者
- M・A Huffman
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2004
アフリカ・アジアの大型類人猿(チンパンジー、オランウータン)、旧世界ザル(ニホンザル等)と原猿類(ワオキツネザル、ヴェローシファカ)の植物性食物の採食部位およびヒトの民間薬或いは実際に有効な天然化合物として用いられている植物を網羅し、主要な霊長類の潜在的薬用植物のデータベース作成を継続して行っている。この研究は、霊長類の採食生態学的観点から、栄養成分とそれ以外の健康管理に役立つ薬理効果をもつ成分の存在の可能性を探ることを目標としている。作成されるデータベースに基づいて今後の研究対象とすべき霊長類と植物を明らかにし、霊長類における自己治療研究に必要な領野と重点的研究項目を明確にする。本計画の2年間の成果として以下の主な実績を報告する。1)16年度の基盤C研究費でまとめた論文集「A study of primate self-medication」(1989年から2004年の間に申請者の研究グループ(CHIMPP)によって出版された48の論文等)70冊ほどを世界各地の専門家や図書館に配り、共同研究を呼びかけている。2)この出版物の内容を中心に、ウェブサイトを作成した。CHIMPPグループの設立経緯、研究の意義や目標等をまとめて、現在6カ国語(和、中、独、伊、シンハラ、英)に訳されたものを載せた(htt://www.pri.kyoto-u.ac.jp/shakai-seitai/seitai/huffman/index.html)。2006.03.22現在、既に1563ヒットを受けている。3)各霊長類種の食物データベース作成を継続している。昨年入力が終わったチンパンジー(N=550植物種)、オランウータン(N=551)、ニホンザル(N=515)、シファカ(N=242)、ホエザル(N=109)に関して、それぞれの採食植物品目に対応する民間薬・生薬・天然化合物の文献収集が進んでいる。本年度中に完成したのはチンパンジー(文献12件、36/550薬用とされた植物種)とニホンザル(文献81件、薬用とされた植物287/515種)のである。4)2度スリランカを訪問し、現地生息の野生霊長類のトクザルとハヌマンラングルを10カ所で調査し、現地の共同研究者らとの情報交換、研究打ち合わせを行った。
1 0 0 0 出版年鑑
- 著者
- 出版ニュース社出版年鑑編集部 [編集]
- 出版者
- 出版ニュース社
- 巻号頁・発行日
- 1951
1 0 0 0 OA 食品の嗜好に関する研究 I : 琉球大学男子,女子学寮生の嗜好調査(家政学科)
- 著者
- 金城 須美子
- 出版者
- 琉球大学
- 雑誌
- 琉球大学農学部学術報告 (ISSN:03704246)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.323-331, 1971-12-01
1 琉大の男子寮, 女子寮生を対象に食品の嗜好調査を行った。その結果, 肉料理, すし類, 果物, 野菜サラダの平均嗜好度は男女とも高く標準偏差も小さい。男子の肉料理に対する嗜好は女子より高い。特にビフテキは全食品中最も高い嗜好を示し偏差も1.04と非常に小さい。これは殆んどの男性が, 文句なしにビフテキを好んでいることが分る。これに対して女子は野菜サラダを最も好む食品としている。琉球料理のイリチーやチャンプルーはさ程好まれない。各食品に対する男女の嗜好の相違は顕著でないように思う。2 気候, 健康状態によって嗜好が異るかどうかを調査した。その結果, 夏と冬, それに疲れたときの食品に対する嗜好が異ることが分った。特に気候の影響が大きい。それ故, 食品の嗜好に及ぼす要因として性別よりも, むしろ季節, その他の要因が大きいと思われる。
- 著者
- 驛 賢太郎
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 神戸法學雜誌 (ISSN:04522400)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.27-80, 2013-12
1 0 0 0 OA 東アジアの自動車産業における日系・欧米系・現地企業の管理、組織、労働の比較研究
本研究は、中国、タイ、ベトナムに進出した自動車産業などの日系企業が現地で直面する管理上の諸問題について、現地企業や欧米企業と比較してどのような特徴があるかの解明に焦点を当てた。とくに、日本的経営の要をなす作業・雇用慣行、協調的な労使関係、企業間の系列関係の3点が、現地でいかなる適応を試みられているかに注目した。本研究が示したのは、製造過程に関連しては強みを生かす取組みが成果を発揮しつつあるものの、それ以外の領域では日本的手法が競争力の源泉として生かされる段階には到達できていないし、その弱点を十分克服することができていないなどの諸点である。
1 0 0 0 OA 電荷を持つ超対称性粒子の宇宙論的検証
- 著者
- 郡 和範
- 出版者
- 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-28
4年間で、関連の深い論文34本、まとめの論文を1本執筆したことが最大の成果である。2013年のヒッグス粒子発見を受け、それと無矛盾な最小超対称性理論のパラメーター領域は、厳しく制限されることとなった。そのパラメーターの範囲内で、超対称性粒子がダークマタ―になる条件と、長寿命荷電粒子がビッグバン元素合成に与える悪い影響を逃れる条件を課す場合、さらにパラメーター領域は制限される。我々はsinglinoという粒子を一つ導入することにより超対称性理論を拡張すれば、そのsinglinoがダークマタ―となり、ビッグバン元素合成でのリチウム7問題とリチウム6問題を同時に解決することを示した。
1 0 0 0 OA P10 火山爆発のシミュレーション (II) : 衝撃波の発生と光環現象
- 著者
- 高山 和喜 斎藤 務 木下 利博 藤井 直之 山岡 耕春 谷口 宏充
- 出版者
- 特定非営利活動法人日本火山学会
- 雑誌
- 日本火山学会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, no.2, 1992-11-09
1 0 0 0 A Japanese miscellany
- 著者
- by Lafcadio Hearn
- 出版者
- Little, Brown
- 巻号頁・発行日
- 1901
1 0 0 0 霊の日本 ; 明暗 ; 日本雑記
- 出版者
- 日経ホーム出版社
- 雑誌
- 日経マネー (ISSN:09119361)
- 巻号頁・発行日
- no.308, pp.30-37, 2008-07
ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)よりも、需給によって株価が動くことが多い最近の相場。うまくその波に乗るには、相場の主役である外国人の動きを知ることが重要だ。
宇宙を飛び交っている10^<15.5>eV以下の粒子(宇宙線)は、銀河系内の超新星残骸(SNR)で加速されていると信じられている。しかし、現在見つかっている~TeVまでの加速が行われているSNRは、系内のSNR 270個のうち10個程度しかなく、そのほとんどが爆発からん1000年経った若いSNRとなっている。従って、宇宙線加速とSNRの環境との関係、宇宙線加速の進化、そして宇宙線の主成分である陽子加速については未だ解明されていない。そこで私は加速源の環境と加速の進化を解明するために、(i)爆発から数万年経ったSNRから、電子加速の証拠となるシンクロトロンX線を発見すること、(ii)系内SNRのうちシンクロトロンX線が受かっているサンプルを集め、光度の時間変化を追うことの2点に着目して研究を行った。(i)については、古いSNR W28と、CTBS7Bという2つのSNRがら初めてシンクロトロンX線を発見した。次に、(ii)に述べたサンプルにW28とCTB37Bのデータを加え、光度の時間変化を見た。その結果、年齢の若いSNRはシンクロトロンX線の光度が10^<34>erg/secと明るく、古くなるにつれて光度がさがる傾向が見られた。この傾向を説明するために、我々はSNRの進化に基づいて衝撃波の速度、磁場、電子の最高エネルギーを計算し、シンクロトロンX線の半径に対する光度を求める簡単なモデルを構築した。その結果、プラズマの密度が0.01-1cm^<-3>の時に観測データを良く再現でき、密度が低い環境下にあるSNRほど高いエネルギーまで電子が加速され、加速のタイムスケールも長くなること発見した。同様のモデルを宇宙線の主成分である陽子加速にも適用した。その結果、陽子はSNRの進化の早い時期に一気に~1015eVまで加速されること、また最高到達エネルギーの密度依存性が小さいことがわかった。このように電子加速、陽子加速の進化を追った研究は世界で初めてであり、モデルを構築することによって宇宙線加速と環境の関わりを示唆できたことは、宇宙線加速解明への重要な成果であると言える。
1 0 0 0 OA 宇宙の過去を復元するデータマインニングと統計的因果推論の探求
本補助金によって、X線、電波を含む追観測が実現できた。これにより、1)多波長深宇宙探査で検出した10万個の銀河データベースを再構築をし、2)多波長スペクトル解析から赤方偏移、星質量、星形成率、ダスト量を再導出し、3)星形成と銀河中心核(AGN)の活動性を赤外線ー電波スペクトルで分離して、1000個のz<3の赤外線銀河を星形成銀河、AGN銀河、星形成+AGN銀河に再分類し、4)AGNのブラックホールへの質量膠着率を再導出し、5)z<0.8でのAGNによる星形成の抑制傾向などを明らかにした。一方、銀河の系統樹を再構築する統計的因果推論については、多波長データの誤差評価が今後の課題と残された。
1 0 0 0 OA 医学・薬学関係のダイレクトリー
- 著者
- 板橋 瑞夫
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.167-174, 1984-02-25 (Released:2011-09-21)