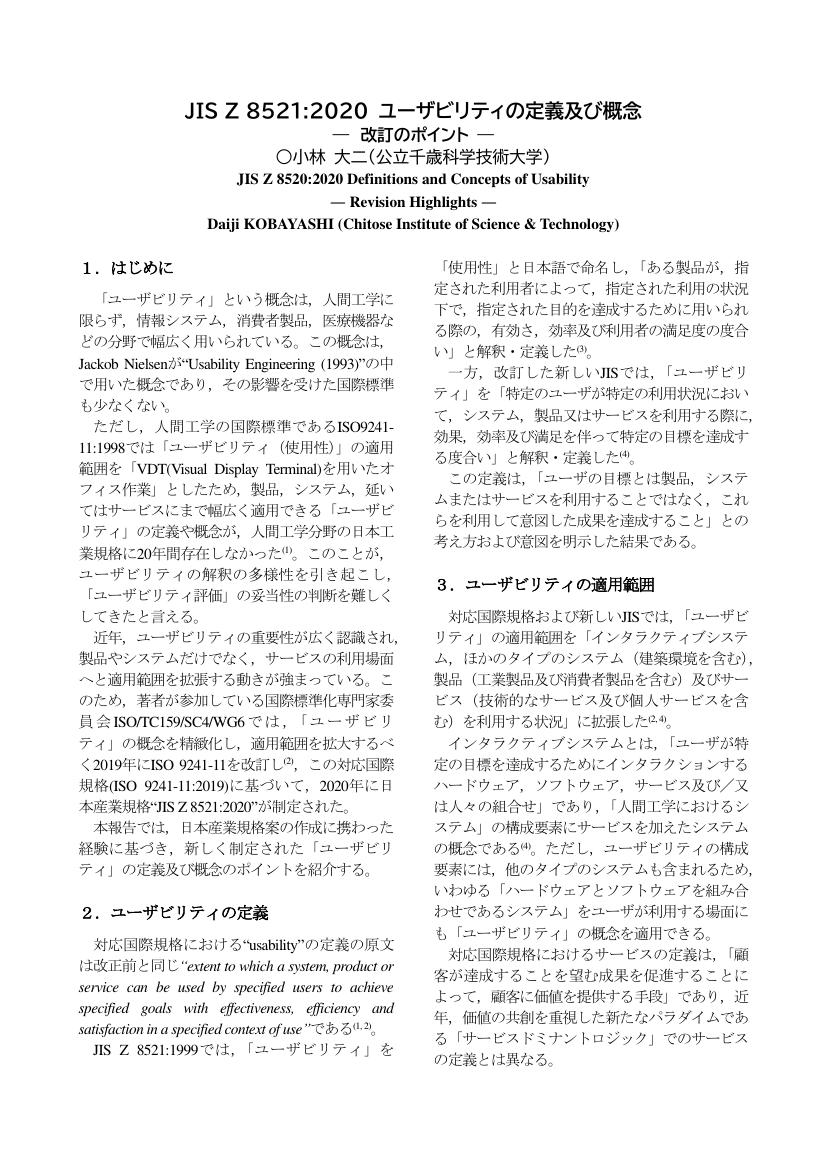2 0 0 0 OA ユリ「カサブランカ」の強い香りの抑制
- 著者
- 大久保 直美
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.102-106, 2011-03-25 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 6
強い芳香を持つユリは,狭い空間に置くとにおいが充満するため,不快に感じられることがある.強い香りを持つ花の利用を広げるため,ユリ「カサブランカ」を用いて花の香りの抑制方法を検討した.「カサブランカ」の香気成分を分析した結果,不快臭を有する成分は芳香族化合物と考えられたことから,香気成分生成抑制剤としてフェニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAL : phenylalanine ammonia-lyase)阻害剤を選択した. PAL阻害剤処理区において,香気成分量はコントロールの10〜20%程度となった.官能的にも,PAL阻害剤処理を行ったユリの香りは,無処理区に比べ弱まった.以上のことからPAL阻害剤は,「カサブランカ」の香りの抑制に利用できると考えられる.
2 0 0 0 OA 札幌からアフリカへ
- 著者
- 日野 舜也
- 出版者
- 日本アフリカ学会
- 雑誌
- アフリカ研究 (ISSN:00654140)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.86, pp.45-47, 2015-01-31 (Released:2015-05-21)
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA JIS Z 8521:2020 ユーザビリティの定義及び概念 ― 改訂のポイント ―
- 著者
- 小林 大二
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.Supplement, pp.S10-1, 2021-05-22 (Released:2021-05-22)
2 0 0 0 OA 何故Madhyamikaは「中観」と翻訳されたのか?
- 著者
- 赤羽 律
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.1229-1236, 2012-03-25 (Released:2017-09-01)
中観派という呼称は仏教を少しでも齧ったことのある人ならば誰でも知っているといってよいほど広く知られた名称である.しかし,元々サンスクリット語でMadhyamikaと呼ばれ,直訳としては「中」という意味にしかならない名称が,何故「観」の字を加えられた「中観」という呼称として翻訳されたのかについては定かではない.本稿で明らかにしようと試みたのは,まさにこの点である.中観という呼称を学派名称として初めて用いたのは義浄であるとこれまで考えられてきた.しかしこの呼称そのものは決して義浄が独自に生み出したものではない.義浄以前に,中国における中観派系統の学派である三論宗の実質的な開祖である吉蔵が,Nagarjunaの『中論』を註釈した際に,そのタイトルを『中観論疏』とし,『中論』を『中観論』と呼んだことに由来すると考えられる.この『中観論』という呼称が7世紀半以降,中国を中心に広く知られていたことは明らかであり,インドに渡る以前の義浄が知っていたと十分に考えられる.それ故に,インドにおいてNagarjunaの思想に基づく学派としてMadhyamikaという呼称を耳にした義浄の脳裏に,Nagarjunaの最も重要な論書である『中論』即ち『中観論』という名称が浮かび,それを学派名称に転用したとしても何ら不思議はないであろう.また「観」の字を加えた理由は定かではないが,吉蔵の『中観論』という名称に関する注釈に従うならば,『中論』の各章に「観」の字が付けられていることに基づいたためではないかと推察される.何れにせよ,義浄以前の7世紀に活躍し,インドの仏教事情に詳しい玄奘や,630年代初頭に『般若灯論』の翻訳を行ったインド人Prabhakaramitraといった著名な仏教僧たちが何れも,中観派という呼称を用いていないことから,恐らくこの用語を学派名称として初めて用いた人物が義浄であると想定するのが現段階では妥当であろう.
2 0 0 0 OA 長野県の郷土料理における地域的特性の比較
- 著者
- 春日 千鶴葉 柏木 良明
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2016年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100058, 2016 (Released:2016-11-09)
郷土料理は以下のように定義されている(木村,1974)。(1)ある地域に古くから行われている食形態で他地方にはみられない特色をもち、その発生が明治以前であるものである。ただし、北海道に限り明治末期までに備わった食形態を取り上げる。(2) 現在は比較的広範囲の各地の人々に食されているが、江戸時代までは限られた範囲の地域の民衆生活のみ定着していた食形態であるものである。 また、郷土料理は地方の特産品をその地方に適した方法で調理したものである(岡本,1987)。その中で、食の暮らしの知恵が育まれ、おいしく健康に良い食べ方などが工夫されている(成瀬,2009)。種類や調理方法における地域性は、地形、気候、地域ごとの生産物といった自然的要因だけでなく、地域の人々の気質、宗教、産業技術の発達状況、時代・地域社会の思潮などの人為的要因によっても形成される(石川,2000)。そして、郷土料理のタイプは(1)その土地で大量に生産される食べ物をおいしく食べようと工夫したことにより生まれたもの(2)地方の特産物を利用してできたもの(3)その地方で生産されない材料を他地域からもってきて、独自の料理技術を開発して名物料理に仕上げたものに分類される(安藤,1986)。さらに、郷土料理は伝統行事に欠かせないものにもなっている。しかし、生活様式の変容などにより、その地域性が失われつつある(成瀬,2009)。 長野県の郷土料理の一つであるおやきはもともと長野県北部の農村の発祥である。かつて、囲炉裏の灰で焼いたことから「お焼き」と名付けられた。作り方は味噌で味付けしたナスなどの野菜を餡として小麦粉の皮で包み、蒸すあるいは焼く。その後、1982年におやきが手打ちソバ、御幣餅、スンキ漬、野沢菜漬とともに「食の文化財」に指定された。現在では、長野市、小川村をはじめおやきの専門工房や販売店が県内全域の広範囲に多数存在している。その上、おやきは地域差が県全域を通じて見られ、地域性がよく見られるのも特徴である。 おやきに関する研究では、ある特定の地域における特性は明確になっているが県内全域でのおやきの実態、特性を示す研究は少ない(水谷ら,2005)。故に、長野県内の中でどのような差異や共通点があるのかも不十分であり、おやきに関する明確なデータも少ない。 そこで、本研究では長野県全域を調査地域として、各地域におけるおやきの特性について比較調査するとともに、なぜ地域差が見られるのかを明らかにする。また、考察の際に五平餅との比較も取り上げる。 結果として長野県内は北信、中信、東信、南信の4つの行政区分である。調査方法は主に文献調査、聞き取り調査(25店舗)、おやきの購入・試食、写真撮影による。 北信地方で119店舗、東信地方で27店舗、中信地方で49店舗、南信地方で20店舗、計215店舗あることがわかった。特に、北信地方だけでも全体の約5割をも占めている。東信・南信では店舗自体は非常に少ない。 おやきの製法には、蒸かし、焼き蒸かし、焼き、揚げ焼きなどの種類がある。北信では小麦粉の味を生かしたおやきで蒸かしたものが多い。しかし、長野市から離れた山村地域に行くと、ほうろくの上にのせて焼く製法が見られる。東信地方では、蒸かす製法が多い傾向にあり、主に上田市に多く店舗が集中している。中信は南北に差異があり、北側は昔ながらの焼き製法、南側は蒸かし製法で作られている。南信では生地に砂糖を入れ甘く仕上げて、ふくらし粉を使用し蒸かす。 全域を通してノザワナ、ナス、小豆あんである。また、山菜やクリなど地域でとれた素材を生かして作っている場合が多い。 考察に関して、穀物において、米は盆地の河川流域に集中している一方で長野盆地には水田地帯が少なく畑作を行う傾向にある。小麦は、松本、安曇野で最も多く、全体的に収穫量は北側に集中していることから北側を中心に小麦の文化が定着しているといえる。また、県内では穀物を粉状にして食べる工夫が自然にできる環境にあった。 北部ではおやきをお盆に食べ、南部では11月20日のえびす講で、あんこを多く入れたおやきを作って供える。このようにおやきを食べる習慣が各地域により異なる。 五平餅とは南信地域で食べられる郷土料理のことである。名前の由来は、五平が始めた、神前に供える御幣の形に似ていることなどがあげられる。作り方はうるち米のみを使用して焼く。 五平餅は、「塩の道」である伊那街道沿いの地域に分布しており、終点は塩尻で南北の分岐点となっている。それを境に、南信地方では五平餅文化が存在している。そのため、南信地域にはおやき店舗よりも五平餅店舗の方が多い。その一方で北信地方では五平餅店舗は見られない。
2 0 0 0 OA デンマーク最近の教育事情
- 著者
- 寺田 治史
- 出版者
- 学校法人 天満学園 太成学院大学
- 雑誌
- 太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.273-283, 2011 (Released:2017-05-10)
幸福度世界一のデンマ-クと同90位の日本(2006年.英レスタ-大学ホワイト教授調べ)。この違いはどこから来るのか。5度に亘るデンマ-ク訪問の結果、その底流に両国における教育の歴史に違いを見出す事が出来る。知と情と意を統合した"対話中心の教育"(筆者はこれを人間教育と称する)を貫くデンマ-クに対して日本の教育は、知育に偏しているように思われる。デンマ-クにおける調査、聞き取り、視察を通して考察した内容を提示し、わが国における今後の議論の糧となれば幸いである。
2 0 0 0 OA 組織内デジタル文化資本がICT投資効果に与える影響
- 著者
- 清水 たくみ 平野 雅章
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2020年全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.269-272, 2021-01-28 (Released:2021-01-18)
ICT投資は経済・企業成長の主要な要因としての役割を果たし続けている。マクロレベルでのICT投資の正の影響については合意が形成されつつある一方、ミクロレベルでどのような組織がICT投資を成果に結びつけているかについては統一的な見解が得られていない。そこで本研究では「デジタル文化資本」概念に着目し、ICT投資成否を左右する組織要因について明らかにする。日本企業に対する大規模サーベイ調査のパネルデータ分析を行った結果、ICT投資は組織内デジタル文化資本の高低に応じて企業業績に与える影響が変化することが示された。本研究により、ICT投資と企業業績の関係性に関する新たな理論的・実証的貢献がもたらされた。
2 0 0 0 OA モチビック・コホモロジー,その応用と重要な予想
- 著者
- ガイサ トーマス
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.225-245, 2015-07-24 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 88
- 著者
- 北川 裕子 佐々木 司
- 出版者
- 一般社団法人 日本学校保健学会
- 雑誌
- 学校保健研究 (ISSN:03869598)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.83-90, 2021-07-20 (Released:2021-08-11)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 OA 第13回臨床不整脈研究会 逆行性通常型心房粗動の心電図学的特徴 左房起源心房粗動との比較
- 著者
- 伊藤 致 深澤 浩 内藤 滋人 窪田 彰一 伊藤 幸子 平辻 知也 鶴谷 英樹 関口 誠 河口 廉 高間 典明 磯部 直樹 瀬田 享博 櫻井 繁樹 安達 仁 外山 卓二 星崎 洋 大島 茂 谷口 興一
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.Supplement5, pp.68-73, 2001-12-31 (Released:2013-05-24)
【目的】陽性F波を呈する逆行性通常型心房粗動の心電図学的特徴を検索することで,回路の推測が可能か否かを検討した.【対象】陽性F波を呈する心房粗動と診断され,心臓電気生理検査を施行,起源が逆行性通常型および左房起源型心房粗動と診断された連続17症例.【方法】興奮波が三尖弁輪部を時計方向に旋回し,冠静脈洞入口部位での心房ペーシングでconcealed entrainment現象を認めた例を逆行性通常型心房粗動(R群:13例),心内電位で冠静脈洞遠位の左房から右房側へ興奮伝幡を認め,右房ペーシングでconcealed entrainment現象を認めなかった例を,左房起源型心房粗動(LA群:4例)と診断した.これら2群でのF波を比較した.【結果】1)V1のF波は,R群で陰性F波を,LA群では陽性F波を有意に認めた(R:81.8%,LA:0%,p<0.05).2)V6のF波は,R群で陽性F波を,LA群では陰性F波を有意に認めた(0.9%,LA:25%,p<0.05).3)I誘導では両群ともすべて陽性F波を認めたが,aVL誘導では関連はなかった.4)両群のF波成分を比較したところ,F波高はR群が高い傾向(R:0.22±0.06mV,LA:0.13±0.06mV,p=0.0503)にあり,F波幅はR群が有意に長かった(R:144±36mse,LA:92±24msec,p<0.05).5)肢誘導R,S波高に両群で有意差はなかった.【結語】1)陽性F波を呈する非通常型心房粗動は,V1およびV6誘導のF波を検討することで旋回が逆方向性通常型心房粗動なのか左房起源型心房粗動なのか推測できることが示唆された.2)F波成分は,左房起源型心房粗動では波形が小さく,その上降部と下降部が左右対称であったのに対し,逆方向性通常型心房粗動では,緩徐に上がり,急峻に下がるF波が特徴であると思われた.
2 0 0 0 OA 日本で発症した人体ハエ症の再検討
- 著者
- 末吉 昌宏
- 出版者
- The Japan Society of Medical Entomology and Zoology
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.91-120, 2015-09-25 (Released:2016-03-25)
- 参考文献数
- 339
- 被引用文献数
- 4 7
Myiasis in Japan was reviewed based on the case reports published until 2014. A total of 209 cases of facultative myiases were reported and these involved more than 32 species from 11 dipteran families. Boettcherisca peregrina, Lucilia sericata, and Parasarcophaga similis were responsible for 74 of all the cases. Four foreign dipteran species were involved in 50 cases of obligatory myiasis. Dermatobia hominis imported from Central and South America dominated with 41 of these cases. Four cases of wound myiases were caused by L. sericata and L. ampullacea, and one case of ophthalmomyiasis by B. peregrina was acquired in forests or similar environments. Among the flies known as forest-dwelling species, L. ampullacea, Chrysomya pinguis, and B. septentrionalis are found to be dominant in forests. It is recommended that people visiting forests stay together and avoid exposing their skin to prevent infections from myiasis-producing flies. For development of control measures to reduce infections, it is essential to accumulate knowledge on the abundance of myiasis-producing flies in different forest environments and on smaller islands, and to collect case reports of human myiasis with reliable identifications of the fly species involved.
2 0 0 0 OA 真に必要な地方創生支援とは何か ―西粟倉村での仕事づくりの経験から―
- 著者
- 牧 大介
- 出版者
- 地域農林経済学会
- 雑誌
- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.10-16, 2016-03-25 (Released:2016-04-01)
- 著者
- 金 政芸
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.57-73, 2015-02-28 (Released:2019-05-24)
- 参考文献数
- 26
In this paper, I statistically research the effects of diversity and intimacy in social relationships on tolerance toward foreigners. To verify these effects, data from the Japanese General Social Survey conducted in 2008 (JGSS-2008) was used for analysis. I hypothesized that having diverse relationships with other people would increase tolerance toward foreigners, based on studies on generalized intergroup contact effects and other studies related to tolerance. Furthermore, I hypothesized that having intimate relationships with other people would increase tolerance toward foreigners, based on studies on the need to belong and Fromm’s study about the psychological origins of fascism. The results revealed that diversity in occupations and diversity of group affiliations, which were used to determine diversity on social relationships, have positive effects on tolerance toward foreigners. It was also found that closeness of relationships with friends, and the degree of satisfaction in relationships with family members, which are used to determine intimacy, have positive relations with tolerance toward foreigners even if they are controlled by diverse factors in relationships.
2 0 0 0 OA 自殺に用いられる薬毒物と出版物による影響に関する研究
- 著者
- 後藤 京子 杉本 侃
- 出版者
- The Japanese Society of Health and Human Ecology
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.53-64, 1996-03-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
The Japan Poison Information Center (JPIC) received 205, 199 inquiries from citizens and medical personnel for 5 years from April, 1989 to March, 1995. And, the number of inquiries concerning with suicide in those was 5, 778. In July 1993, the book named the Suicidal Manual were published in Japan and since then, the inquiries concerning with suicide attempts have increased. So, I analyzed these data about implicated products and contrasted the data received before the publication of the manual to the data received after that on purpose to make clear the affection of the Suicidal Manual. In regard to the substance that was selected in suicide attempts cases, teen-ager and the twenties tend to use medicines, especially over-the-counter drugs and older people tend to use agricultural chemicals. After the book was published, the number of inquiries about some over-the-counter drugs that were shown as appropriate way for easy and painless death in the book had increased. So, it is very important to give the young people the information of drug toxicity and appropriate management of drugs to decrease the influence of the book.
2 0 0 0 OA 1.補充療法に用いられる合成ステロイドホルモン
- 著者
- 大月 道夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.4, pp.766-771, 2008 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 10
副腎不全治療において欠落ホルモン(コルチゾール,アルドステロン,副腎アンドロゲン)に対して合成ステロイドホルモンの補充が行われる.グルココルチコイド補充には通常ヒドロコルチゾンが用いられるが,ストレス,手術などにおいて必要量が変化することに注意しなければならない.ミネラルコルチコイド補充にはフルドロコーチゾンが用いられる.副腎アンドロゲン補充は有用であると考えられるが,今後検討が必要である.
2 0 0 0 OA いま家族に何が起こっているのか 日本の家族の今を問う
- 著者
- 袖井 孝子
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.4-9,116, 1990-07-20 (Released:2009-08-04)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
Looking back to the past two seminers, the following points stand out: (1) the trend of family changes is not unilineal but multilineal, (2) families which depart from major trends are not deviant but variant, and (3) the nuclear family based on sex role differentiation seems to be losing its vital role through the change from industrial to post-industrial society. Concerning the contemporary Japanese family, some see crisis and others see stability. Such a difference seems to be derived from differences in their perspective. If we look at the national statistics, the general features of the Japanese family are quite stable, because the rates of divorce, of one-parent family, and of illegitimate children are lower than those of most industrial nations. However, if we focus on internal factors seen through case studies, we can easily find tensions and conflicts within the family. We should pay more attention to various aspects of the family which differ from the averages. Contrary to what is widely accepted, today is not a time of family crisis but a time of crisis in family sociology, which has yet to develop suitable theories in the post-industrial society.
2 0 0 0 OA 近世の日朝関係
- 著者
- 田代 和生
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.Special_Issue, pp.251-260, 2018-04-11 (Released:2018-05-23)
2 0 0 0 OA 圖版 第 IV. Pl. IV
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- ヴヰナス (ISSN:24329975)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3-4, pp.App3, 1938-12-25 (Released:2018-01-31)
2 0 0 0 OA 珍しき共棲二枚貝マゴコロ貝(遺稿)
- 著者
- 庄司 幸八
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- ヴヰナス (ISSN:24329975)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3-4, pp.119-128, 1938-12-25 (Released:2018-01-31)
2 0 0 0 OA 圖版 第 III. Pl. III
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- ヴヰナス (ISSN:24329975)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3-4, pp.App2, 1938-12-25 (Released:2018-01-31)