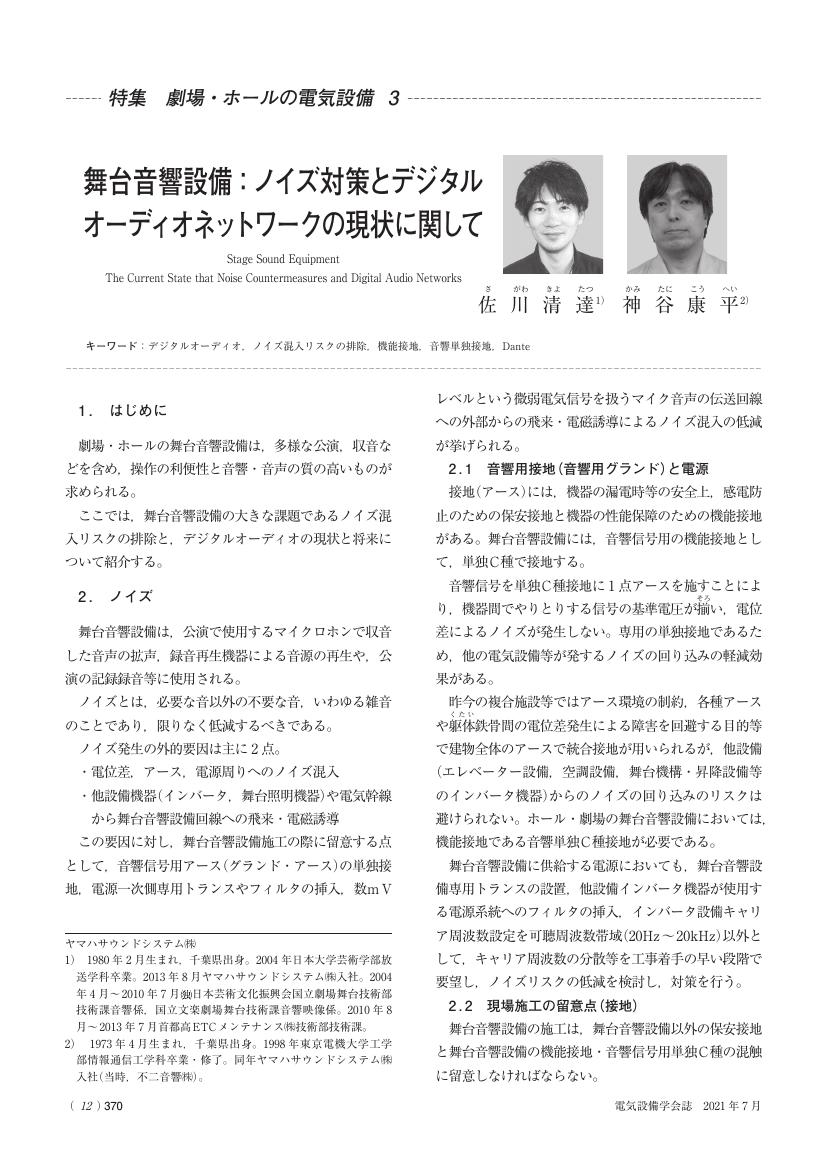4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1923年12月25日, 1923-12-25
- 著者
- 植田隆子著 国際基督教大学社会科学研究所編集 = Takako Ueta
- 出版者
- 国際基督教大学
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- 佐川 清達 神谷 康平
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.7, pp.370-373, 2021 (Released:2021-07-10)
- 参考文献数
- 3
4 0 0 0 仮想現実と「あり得たかもしれない心」
- 著者
- 鈴木 啓介
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.27-34, 2022-01-01 (Released:2022-01-01)
4 0 0 0 義足足部に吸収および放出されるエネルギー量
- 著者
- 江原 義弘 別府 政敏 野村 進 國見 ゆみ子 池田 稔 高橋 茂 丸田 耕平
- 出版者
- Japanese Society of Prosthetics and Orthotics
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 = Bulletin of the Japanese Society of Prosthetic and Orthotic Education, Research and Development (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.152-158, 2002-04-01
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 4
下腿切断者を被験者として, 16種類の足部について歩行時に足部に吸収・放出されるエネルギー量を計算した. 歩行中の関節位置と床反力データより関節モーメントを計算し, 関節角速度と体節間浸透力を考慮した新しい方式でパワーを計算した. 立脚期におけるパワーは負・正・負・正の4領域となり, おのおのの領域でパワーを積分してエネルギーを求めた. 踵部での吸収が少ない群としてはスプリングライトII, フレックスウォークII, グライジンガープラス, カーボンコピーII, 1H38, SL1020があり, 多い群としてはSACH, 1D10, SAFEIIがあった. 前足部での吸収・放出が少ない群としてはSACH, 1H38であった. 多い群はエナジーマルチ, シュアーフレックス, J-フットであった. 踵部と前足部の機能は足部を選択する場合に重要であることが示唆された.
4 0 0 0 OA 血縁なき親子関係をつくるネットワーク―NPO法人「環の会」の事例研究―
- 著者
- 樂木 章子
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.15-26, 2005 (Released:2005-08-26)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4 1
本研究は,不妊のために子どもを産むことを断念した夫婦が,血のつながらない子どもと養子縁組を通して親子関係を結んでいくプロセスにおいて,養子縁組を支援するNPOが果たす役割を検討しようとするものである。具体的には,新しい養子縁組のあり方を模索しつつ,育て親を開拓する活動を展開しているNPO法人「環の会」でのフィールド研究に基づき,夫婦が養子を迎えるまでのプロセスや,養子に関する啓発活動等の一連の活動内容とその特徴を明らかにした。その結果,産みの親の存在を積極的に組み入れ,かつ,養子を迎えた後も育て親が会の活動を支えることにより,従来の養子縁組が持つ否定的なイメージが打破されつつあることが見出された。また,育て親希望者を対象とした「育て親研修」が,まだ見ぬ養子とともに新しい人生を歩んでいくために必要な先験性を構成する場であると同時に,その先験性は,子どもを迎えた後も,「環の会」と継続的にかかわるシステムに組み込まれることによって,維持・強化されていることを考察した。
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1916年07月08日, 1916-07-08
- 著者
- 小林 将生 佐藤 みゆき 酒井 保治郎
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.489-492, 2016 (Released:2016-07-06)
- 参考文献数
- 18
〔目的〕脱神経筋に対して電気刺激を併用した自転車エルゴメーターの有用性を検討する.〔対象〕腰椎椎間板ヘルニアに対して,除圧術を施行された後に下垂足を呈した28歳男性とした.〔方法〕標準的な理学療法に加え,週に4~5回の電気刺激を併用した自転車エルゴメーターを6週間実施した.電気刺激は自転車エルゴメーターの下肢屈曲相に腓骨神経に刺激が入るよう調整した.〔結果〕介入後,前脛骨筋や腓骨筋の筋力が向上し,歩行能力の改善が認められた.〔結語〕脱神経筋に対して電気刺激を実施することは効果的であった可能性がある.
- 著者
- 大澤 隆男 古谷 純 池田 稔 熊谷 健太
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.3_33-3_42, 2019-01-31 (Released:2019-03-25)
- 参考文献数
- 16
国内電機メーカは需要の変化に伴い事業戦略の見直しが進んでおり,企業内デザイン組織はその対応からより適切なデザイン価値の提供が求められている。日立製作所デザイン本部は製品価値を高めるプロダクトデザインから,ユーザの経験価値を高めるエクスペリエンスデザインへとデザイン価値を向上させる組織改革を進めてきた。 本稿は2005年から2010年に行った日立製作所のデザイン改革を「Will:組織の思い」「Must:組織の義務」「Can:組織の技量」からなる枠組みで整理した。「Will:組織の思い」では危機意識から将来ビジョンを描き実現の行程を共有し,「Must:組織の義務」で事業ニーズと成果評価を分析しデザイン満足度を上げ,「Can:組織の技量」で経験価値を創出するデザイン基盤を整備した。これ等の活動でデザイン本部は技術ポートフォリオを変え,B2B事業の貢献を高め顧客協創によるイノベーション創出を担う組織に変貌した。本事例から電機メーカのデザイン組織改革におけるWMCモデルのフレームワークの有効性を考察した。
4 0 0 0 OA 尾張名所図会
- 著者
- 岡田啓 (文園) , 野口道直 (梅居) 著
- 出版者
- 片野東四郎
- 巻号頁・発行日
- vol.前編 巻6 知多郡, 1880
- 著者
- Ichiro KATO Ryuta SUZUKI
- 出版者
- 経営行動科学学会
- 雑誌
- 経営行動科学 (ISSN:09145206)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.301-316, 2007-12-28 (Released:2011-01-27)
- 参考文献数
- 15
The purpose of this study is to investigate how Japanese white-collar workers feel and dealwith their own careers in terms of individual career management.Recent years havewitnessed increasing discussion about how one should always be aware of career problemsand be planning and designing one's own career.Under this circumstance, how are those intheir 30's trying to develop their own careers?This paper intends to tackle this question usinga conceptual framework called Mist-Drift Matrix (MDM) developed in the Japanese context.Qualitative data were gathered through intensive interviews of eight Japanese white-collarworkers, who were around 35 years of age.Three cases, which seem to represent the typicalcoping style within the framework, are presented.Results from our analysis of these casesshow that (1) organizational influence is still an important force in in the MDM, (2) individuals show a propensity to stay in a certain domain within the MDM, and (3) there aredifferent styles of coping according to position within MDM.Practical implications are also discussed.
4 0 0 0 OA 東讃電鉄沿道名所案内
- 出版者
- 東讃電気軌道
- 巻号頁・発行日
- 1912
4 0 0 0 OA 房取り収穫が可能なブルーベリー種間雑種系統HoSp-S65G-13の貯蔵特性
- 著者
- 望月 佑哉 目黒 亜依 福岡 亜友 宮下 智人 Worarad Kanjana 井上 栄一
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.463-468, 2021 (Released:2021-12-31)
- 参考文献数
- 19
ブルーベリー果実の出荷期間を延長することを目的とし,まず,房取り収穫が可能な新系統HoSp-S65G-13の貯蔵特性を既存品種と比較した.次いで,収穫方法の違いが収穫後の果実品質に及ぼす影響について房取り収穫と個別収穫した果実を貯蔵して調査した.その結果,HoSp-S65G-13はハイブッシュブルーベリーの ‘Chandler’ およびラビットアイブルーベリーの ‘Tifblue’ と同等の貯蔵性を持つことが明らかになった.房取り収穫した果実の重量減少率は個別収穫のそれと比較し,貯蔵後2週目から有意に低かった.一方で,Brix値および酸度には収穫方法間で有意差はみられなかった.さらに,房取り収穫は貯蔵期間中の果実の腐敗発生を抑制した.貯蔵5か月後の果実を用いて官能試験を行ったところ,房取り収穫した果実は輸入生果と比較して同等であった.一方で,個別収穫した果実の評価は輸入生果と比較して有意に低かった.従って,ブルーベリー果実の房取り収穫は果実の重量減少および腐敗発生を抑制したことから,房取り収穫したブルーベリーを長期貯蔵することで出荷期間を延長できる可能性があることが示唆された.
4 0 0 0 OA 若年成人女子の人体計測データからみた体格・体型特性
- 著者
- 別府 美雪 伊藤 由美子 坂倉 園江 中保 淑子 畠山 絹江 福井 弥生 間壁 治子
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.97-104, 1997-04-15 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 2
通商産業省工業技術院により現行JISの衣料サイズが見直されている. よって, 本研究は現行JISと若年女子の身体計測値との差異をとらえ, 衣料サイズ設定の在り方について検討を行った. 被験者は18~22歳の若年女子1,634名である. 計測項目は身長, バスト, ウエスト, ヒップ, 背肩幅, 股下高, 体重, バスト/ウエスト, ヒップ/ウエスト, BMIである. 身体寸法10項目で統計処理を行い, 各項目の特性をとらえた. 結果は以下のとおりである. 1) 現行JISとの間にずれを生じている. 2) 身長は平均値で2cm高くなっている. 3) 若年女子のプロポーションは下半身型に移行している. 4) JISサイズは幅広い年代に利用されるため設計に際しては年代差が特に考慮されなければならない. 5) 現行JISは早急に再検討する必要がある. 非接触三次元計測の進歩によりサイズだけでなく体型差についても, さらなる検討が必要といえよう.
- 著者
- Kazuya Yamazaki
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-039, (Released:2021-10-20)
A novel lightweight and high-accuracy variant of the image pan-sharpening technique is designed for Himawari-8 multispectral images. This method, named Additive Template Sharpening, injects higher-wavenumber components of the highest-resolution Band 3 images into lower-resolution visible or shortwave infrared images, thereby providing multispectral high-resolution images. This injection is realized by adding inter-band differential field to the high-resolution band, making use of the specific pixel arrangement of the Himawari-8 imager for simple and accurate coordinate transformations. Both subjective inspection of RGB composite images and objective evaluation of the upsampling indicate that Additive Template Sharpening exhibits higher accuracy than existing methods for Bands 1-6 of Himawari-8. This technique not only enables operational forecasters to diagnose atmospheric conditions in more details using higher-resolution RGB composites, but also provides higher-quality true-color imagery for the public.
4 0 0 0 OA 研修医採用試験へのSPI検査導入の意義
- 著者
- 田中 篤 林田 憲明 石川 陵一 櫻井 健司
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.377-385, 2004-12-25 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 8
聖路加国際病院では研修医の採用試験として, 学科試験・面接に加え, 1998年から適性検査であるSPI検査を導入している.今回われわれは, SPI検査の結果と, 研修医の知的能力・学科試験の成績・研修中の評価との相関を解析した.SPI検査のうち, 基礎能力検査は, 知的能力とは相関するものの, 学科試験の成績とは相関しなかった.高い基礎能力・身体活動性, 外向性は2年間平均した高い評価と関連があった.一方, 思考・実践の重視, 協調性が, 1年目から2年目への高い成長と相関していた.基礎能力は成長とは関連していなかった.以上より, SPI検査の結果は研修医のさまざまな人物特性と相関があることが明らかとなった.
4 0 0 0 OA Multiple Functions of Angiotensin-Converting Enzyme 2 and Its Relevance in Cardiovascular Diseases
- 著者
- Keiji Kuba Yumiko Imai Josef M. Penninger
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.2, pp.301-308, 2013 (Released:2013-01-25)
- 参考文献数
- 93
- 被引用文献数
- 97 148
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is a negative regulator of the renin-angiotensin system, and functions as the key SARS coronavirus receptor and stabilizer of neutral amino acid transporters. ACE2 catalyzes the conversion of angiotensin II to angiotensin 1–7, thereby counterbalancing ACE activity. Accumulating evidence indicates that the enzymatic activity of ACE2 has a protective role in cardiovascular diseases. Loss of ACE2 can be detrimental, as it leads to functional deterioration of the heart and progression of cardiac, renal, and vascular pathologies. Recombinant soluble human ACE2 protein has been demonstrated to exhibit beneficial effects in various animal models, including cardiovascular diseases. ACE2 is a multifunctional enzyme and thus potentially acts on other vasoactive peptides, such as Apelin, a vital regulator of blood pressure and myocardium contractility. In addition, ACE2 is structurally a chimeric protein that has emerged from the duplication of 2 genes: homology with ACE at the carboxypeptidase domain and homology with Collectrin in the transmembrane C-terminal domain. ACE2 has been implicated in the pathology of Hartnup’s disease, a disorder of amino acid homeostasis, and, via its function in amino acid transport, it has been recently revealed that ACE2 controls intestinal inflammation and diarrhea, thus regulating the gut microbiome. This review summarizes and discusses the structure and multiple functions of ACE2 and the relevance of this key enzyme in disease pathogenesis. (Circ J 2013; 77: 301–308)
- 著者
- 渡邊 有希乃
- 出版者
- 日本公共政策学会
- 雑誌
- 公共政策研究 (ISSN:21865868)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.162-177, 2020-12-10 (Released:2021-10-02)
- 参考文献数
- 38
日本では1990年代以降,入札の競争性向上を目的とした公共調達制度改革が進行した。しかし国士交通省直轄工事入札における一件当たり応札数は減少傾向にあり,入札の顕在的競争性は低く保たれている。なぜ行政組織は,改革下でもなおこうした制度運用を行うのか。本稿では,むしろ応札数の増大に合理性を見出す多くの先行研究が問題外としてきた「制度運用の取引費用」に焦点を当てることで,手続的合理性の観点から応札数抑制の優位性を検討する。公共工事調達は,低価格・高品質の追求という目標を伴った,事業者選定を巡る行政組織の意思決定活動である。だが,これらトレードオフ関係にある二目標を同時に考慮し,両者の適切なバランスのもとに唯一最適の事業者を決定するには膨大な取引費用がかかり,現実上の行政組織がこれを負担するのは難しい。しかし,事業者の施主能力をふまえた品質判断に基づいて参入可能な事業者を限定し,それを通過した事業者間で競争入札を行わせる,つまり,まずは品質・次に価格といった形で両価値を逐次的に扱えば,意思決定にかかる取引費用は削減される。即ち応札数抑制は,低価格・高品質という目標を同時に追求することの難しさを緩和するための戦略がとられていることの表出として説明され,このとき,事業者選定の手続的合理性は向上していると推論される。なお以上の妥当性は,国士交通省直轄工事の入札結果データを用いた計量分析によって,実証された。