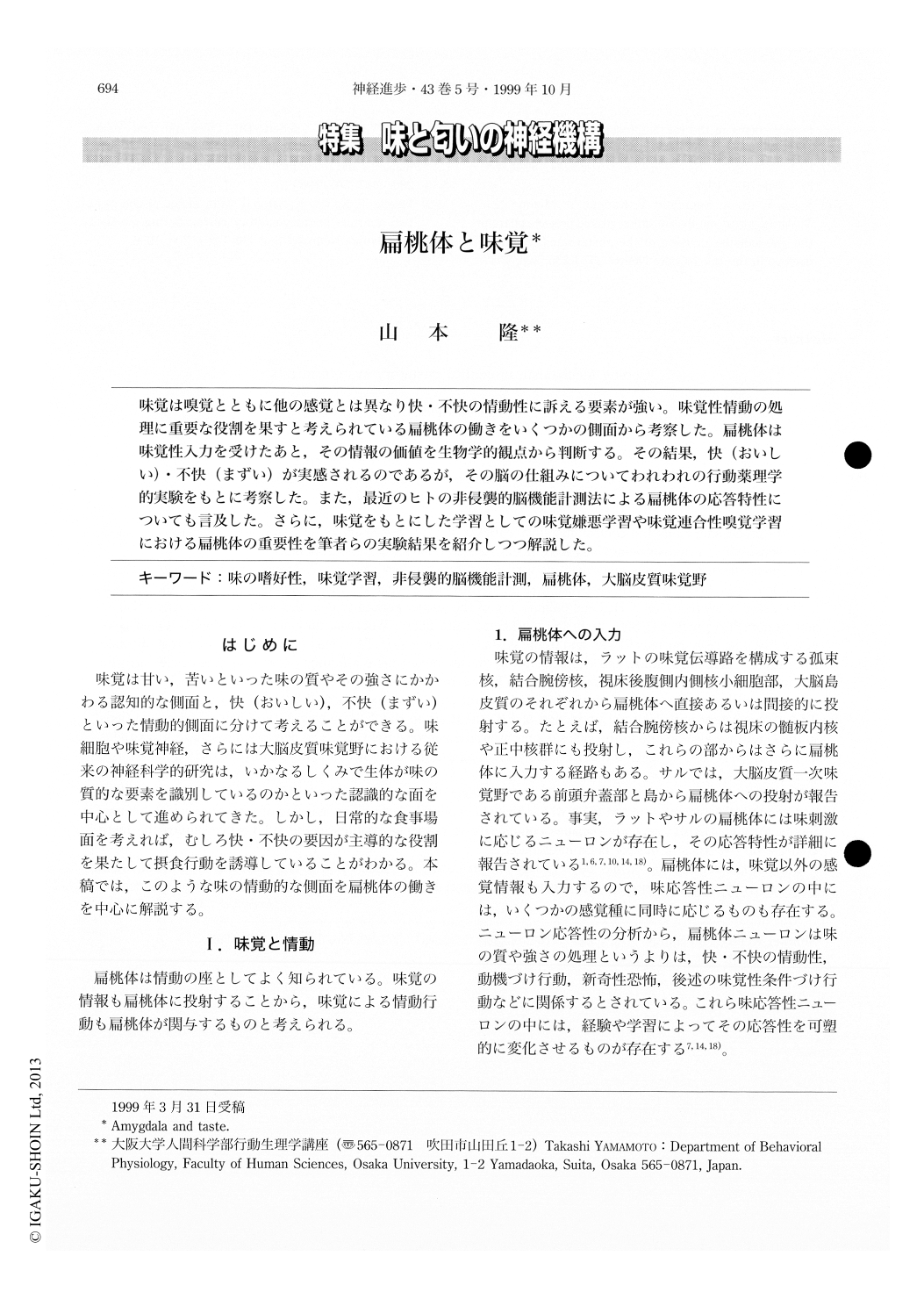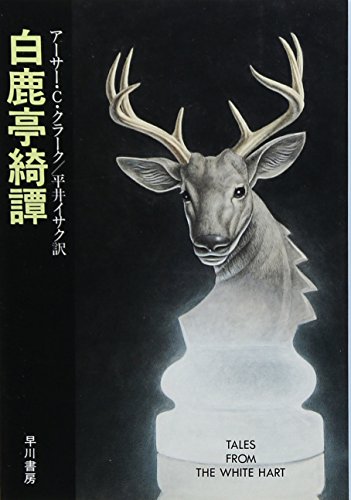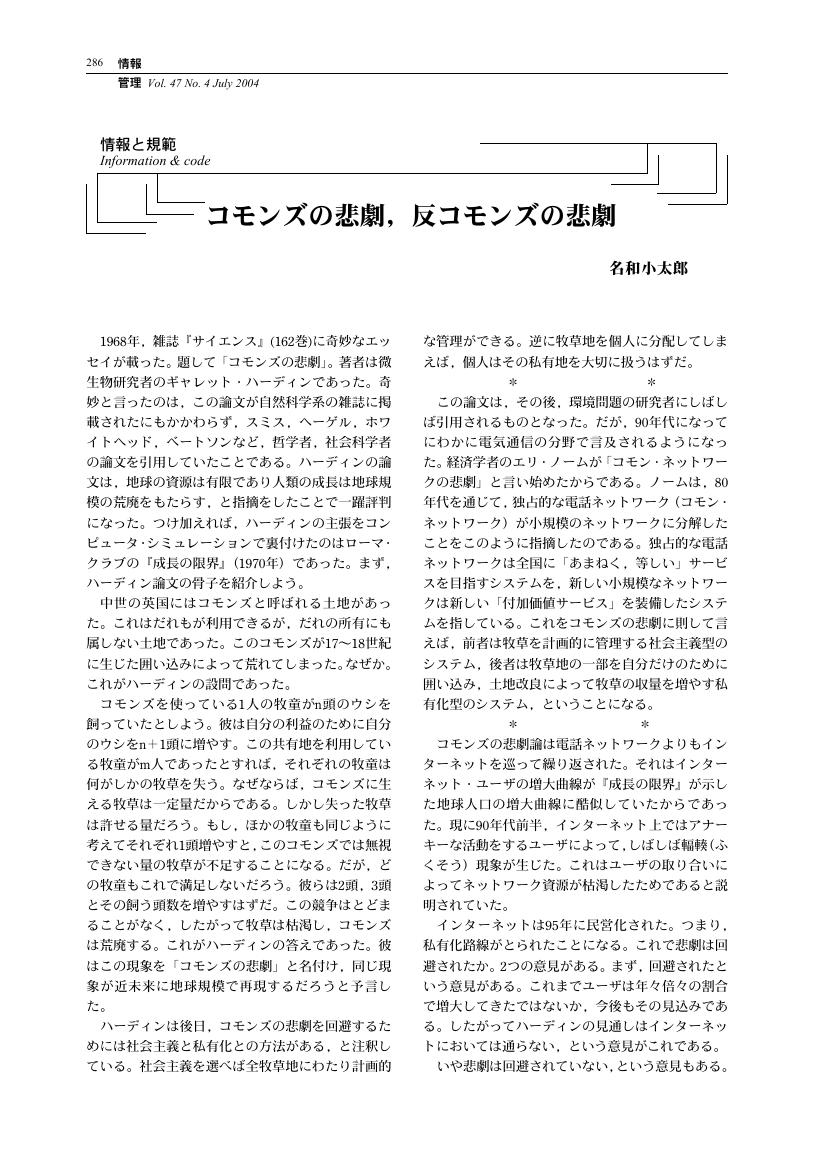4 0 0 0 IR 自然科学系の学術論文は著作物となり得るか : 自然科学系の学術論文と著作権の関係について
- 著者
- 新谷 由紀子 菊本 虔
- 出版者
- 日本知的財産協会
- 雑誌
- 知財管理 = Intellectual property management (ISSN:1340847X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.175-189, 2014-02
学術論文のうち、特に自然科学系の原著論文については、著作権の対象として保護される可能性が低く、むしろ、全体として論文の著作物性を否定するべきである。そして、当該論文の問題に関しては、裁判所の判断を求めるのではなく、学界内部にその救済機関を設置し、プライオリティの判断や著者の名誉の保護を目指すべきである。それにより論文の電子媒体等による広範な普及を図ることができ、一方、学術出版社(者)に与える影響は小さいか、ほとんどないと考えられる。また、学術研究と著作権に関連する創作性のないデータベースについてデータベースの投資者に独自の権利(sui generis right)を与えることについては、著作権類似の権利の拡充を認めるものであり、特に、学術研究に対する重大な障害になるおそれがあるので、慎重、かつ、広範な議論を要する。
4 0 0 0 扁桃体と味覚
味覚は嗅覚とともに他の感覚とは異なり快・不快の情動性に訴える要素が強い。味覚性情動の処理に重要な役割を果すと考えられている扁桃体の働きをいくつかの側面から考察した。扁桃体は味覚性入力を受けたあと,その情報の価値を生物学的観点から判断する。その結果,快(おいしい)・不快(まずい)が実感されるのであるが,その脳の仕組みについてわれわれの行動薬理学的実験をもとに考察した。また,最近のヒトの非侵襲的脳機能計測法による扁桃体の応答特性についても言及した。さらに,味覚をもとにした学習としての味覚嫌悪学習や味覚連合性嗅覚学習における扁桃体の重要性を筆者らの実験結果を紹介しつつ解説した。
4 0 0 0 OA ヨーグルト・乳酸菌飲料摂取によるアレルギーの発症抑制 : 疫学調査から
- 著者
- 榎本 雅夫 清水(肖) 金忠 島津 伸一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.1394-1399, 2006-11-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3
【背景】最近,乳酸菌の抗アレルギー作用への興味が高まりつつある.しかし,日々のヨーグルトや乳酸菌飲料の摂取によるアレルギーの発症の抑制についての報告はほとんどない.【方法】和歌山県下の中学1年生を対象に,ヨーグルトや乳酸菌飲料,納豆の摂食習慣と血清総IgE値,特異的IgE抗体量,各種アレルギー疾患の有無について調査を実施し,得られた134人の回答について解析を行った.【結果】ヨーグルトや乳酸菌飲料の摂取歴のあるものでは,血清総IgE値が有意に低値で,アレルギー疾患の有病率も有意に少なかった.しかし,納豆の摂取の有無では,これらの関係は認められなかった.【結論】アレルギー疾患の発症に乳酸菌などの腸内細菌が深く関与していることを裏付ける疫学調査の興味ある結果であった.今後,症例を増やして検討する価値のある治験であろうと考えている.
- 著者
- TAKEO WATANABE
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Mineralogical Journal (ISSN:05442540)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.6, pp.408-421, 1959 (Released:2008-03-18)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 7 10
The ore deposits of the Noda-Tamagawa mine have become famous for their wealth of mineral species, the production of high grade manganese ores, and also the recent discovery of uranium ores. More than seventy minerals have been found in this mining area including such rare minerals as pyrochroite, manganosite, vredenburgite, yoshimuraite (a new mineral of Ba, Sr, Mn, Ti-silicate), etc. The ore deposits of this mine may be classified into the following types: (A) The contact-metamorphosed bedded manganese deposits in metamorphosed roof pendant in the batholithic mass of granitic rocks. (B) (1) The uranium-bearing veins. (2) The cobalt-nickel-molybdenum-bearing uranium deposits associated with pelitic hornfels. (C) Pyrometasomatic copper-bearing pyrrhotite deposits found in limestone. (D) Gold-silver-bearing quartz-arsenopyrite veins. Among them manganese deposits are economically the most important ones. The geology and ore deposits of the mine are briefly described. The mineral parageneses of ores and country rocks are shown in Tables 1 and 2.
4 0 0 0 OA 6. 貧血領域
- 著者
- 倉賀野 隆裕 土谷 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.12, pp.758-760, 2017 (Released:2017-12-28)
- 参考文献数
- 8
4 0 0 0 OA ゲノム配列の比較から明らかになった初期生命の好熱性
- 著者
- 赤沼 哲史
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 地球化学 (ISSN:03864073)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.199-210, 2016-09-25 (Released:2016-09-25)
- 参考文献数
- 54
Understanding the origin and early evolution of life is fundamental to improve our knowledge on ancient living systems and their environments. Information about the environment of early Earth is sometimes obtained from fossil records. However, no fossil records of ancient organisms that lived more than 3,500 million years ago have been found. Instead, we can now predict the sequences of ancient genes and proteins by comparing extant genome sequences accumulated by the genome project of various organisms. A number of computational studies have focused on ancestral base contents of ribosomal RNAs and the amino acid compositions of ancestral proteins, estimating the environmental temperatures of early life with conflicting conclusions. On the other hand, we experimentally resurrected inferred ancestral amino acid sequences of nucleoside diphosphate kinase that might have existed 3,500–3,800 million years ago. The resurrected proteins are stable around 100℃, being consistent with the thermophilic ancestry of life. Our experimental data do not exclusively indicate the thermophilic origin of life; rather, our conclusion is compatible with the idea that the hyperthermophilic ancestor was selected for increased environmental temperatures of early Earth probably caused by meteorite impacts.
生物細胞が音波信号を発して同種又は異種の細胞がこれに応答すること、また多くの天然物質が赤外線等の電磁波の断続波を受けて音波を発すると、そのある周波数の音波が細胞によって受信され、細胞の増殖を促進又は抑制するように働くことを明らかにした。このような現象ははじめ細菌細胞で見出されたが、高等動植物にも存在することが分かった。本研究は以下の数項目の現象究明よりなる。1.枯草菌菌体からの音波シグナルの検出。光音響スペクトロメトリに用いるカプラーと超高感度マイクロフォン-アンプ系を転用して約50mgの枯草菌湿菌体より発する音波を捕らえ、フーリエ解析によってそのスペクトルを検出したところ、9kHzを基音とする倍音を頂点に、ややなだらかな数個のピークと、他に共鳴と思われる少数個のシャープなピークを得た。2.枯草菌と近縁のBacillus carboniphilusを音波信号の受信者とし、関数発生機に接続したスピーカより種々の周波数の単一・連続な音波・超音波を与えた時、同様に9kHzを基音とする倍音を中心にした周波数帯の音波・超音波が最もよく同菌の増殖を促進した。3.大腸菌を受信者としたときは数百ヘルツ以下の低周波帯の音波が同菌の増殖を抑制した。4.生きている細胞ばかりでなく木材、コルクや土、砂、鉱物、一部の金属等が赤外線等の断続波を受けてこれを音波に変え、B.carboniphilusやその他の類縁の細菌の増殖を促進する事を見出した。5.枯草菌、大腸菌、B.carboniphilusより音波応答に関する変異株を分離して解析した。6.めだかの受精卵の孵化を細菌、酵母、グラファイト、スピーカからの音波が抑制又は促進する事を見出し、この音波に感受性の一定の時期のあることを明らかにした。
4 0 0 0 OA 黄耆が奏功した慢性腎不全の4症例
- 著者
- 長坂 和彦 福田 秀彦 渡辺 哲郎 永田 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.98-102, 2012 (Released:2012-10-04)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 5 6
漢方薬はこれまでも腎疾患に応用されてきた。漢方薬の大黄や温脾湯には,透析導入までの期間を延ばす働きがあることが知られている。しかし,その効果は1/Cr の傾きを改善するにとどまり,Cr 自体を改善するわけではない。今回,西洋薬が無効であった慢性腎不全患者に漢方薬の黄耆が奏功した4症例を報告する。4例ともCr 値は明らかに改善し,透析導入までの期間が延長された。このうち2例は4年以上にわたり安定的に推移している。4例とも副作用は認めず,また治療前後で血清リン,カリウム,尿酸値に変化はなかった。黄耆は慢性腎不全の有力な治療薬となりうる。
4 0 0 0 OA 関東平野における過去12,000年間の環境変遷(日本列島と周辺域における環境変遷)
- 著者
- 吉川 昌伸
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.267-287, 1999-03-31
約12,000万年前以降の関東平野の層序と環境変遷史を検討し,変化期について考察した。完新世の有楽町層は,下部層は主に縄文海進期の海成層から,上部層は河成ないし三角州成堆積物から構成されるが,台地の開析谷内では上部層形成期にはふつう木本泥炭層が形成され,弥生時代以降に主に草本泥炭層に変化した。沖積低地では約4,000年前と約2,000年前には海水準の低下により浅谷が形成された。約12,000年前,冷温帯ないし亜寒帯性の針葉樹と落葉広葉樹からなる森林が,コナラ亜属を主とする落葉広葉樹林に変化した。クリは,約10,500年前以降に自然植生として普通に分布し,縄文中期から晩期(約5,000~2,150年前)には各地で優勢になった。クリ林の拡大が海退と関係することから,環境変化に起因して起こった人為的な変化と推定した。照葉樹林は,房総半島南端では約7,000年前に既に自生し,奥東京湾岸で約7,500年前に,東京湾岸地域の台地で約3,000年前に拡大したが,内陸部では落葉広葉樹林が卓越した。照葉樹林の拡大が関東平野南部から北部,沿岸域から内陸部へと認められたことから,海進による内陸部の湿潤化が関係すると考えた。スギ林は南関東では約3,000年前までに拡大し,その後北部に広がった。照葉樹林やスギ林は,弥生時代以降には内陸部の武蔵野台地や大宮台地,北関東でも拡大が認められたが,これら森林の拡大には生態系への人間の干渉も関係した。また,丘陵を主とするモミ林の拡大は古墳時代頃の湿潤化に起因して,マツ林は特殊な地域を除いては14~15世紀以降に漸増し18世紀初頭以降に卓越した。こうした関東平野の沖積低地の層序や植物化石群に基づき,約12,000年前以降にPE,HE1,HE2,HE3,HE4,HE5各期の6つの変化期を設定した。各変化期は,陸と沖積低地の双方で起こった変化であることを明らかにした。
本研究はCD147/basigin を介するTh細胞の分化制御機構と乾癬病態形成を解明する目的で計画された。CD147/basiginは解糖系の調節を介してTリンパ球の分化と活性化を制御している。すなわちCD147/basiginはモノカルボン酸トランスポーター(monocarboxylate transporter; MCT)と複合体を形成することでMCTの細胞膜への正常な発現をサポートし、解糖系の代謝産物である乳酸の細胞膜輸送を制御している。平成30年度はCD147/basiginの解糖系を介するT細胞の活性化に対する関与をin vitroの系で検討することを計画した。この検討のために野生型マウス由来のT細胞 (T-wt)とCD147/basiginノックアウトマウス由来のT細胞 (T-ko) を用いてそれぞれPMA + ionomycinあるいは固層化した抗CD3/抗TCR抗体で刺激し、MCT1, MCT4の細胞膜上の発現を観察する。平成30年度にはT細胞を刺激する実験系を確立した。ノックアウトマウスは連携研究者が保有しておりヘテロ同士を掛け合わせてホモのノックアウトマウスを得るが、CD147/basiginの機能上ホモのノックアウトマウスの産生効率が極めて低く、研究に十分な数を得るのに長期間を要することが判明した。そこでメイティングによる繁殖を進める一方で、乾癬では免疫系細胞が病態形成に重要な役割を果たしている事実に鑑み、ホモのノックアウトマウスの骨髄を用いて骨髄キメラマウスを作成する方針とした。骨髄キメラマウスはホモのノックアウトマウスが1匹得られれば作成可能である。平成30年度はキメラマウスのレシピエントマウスの繁殖を行なった。
4 0 0 0 白鹿亭綺譚
- 著者
- アーサー・C・クラーク著 平井イサク訳
- 出版者
- 早川書房
- 巻号頁・発行日
- 1980
4 0 0 0 OA 帝政期ドイツにおけるトランスナショナルな人的移動とジェンダー秩序に関する研究
4 0 0 0 OA コモンズの悲劇,反コモンズの悲劇
- 著者
- 名和 小太郎
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.286-288, 2004 (Released:2004-07-01)
4 0 0 0 OA エリファス・レヴィの隠秘思想におけるanalogie理論の考察
- 著者
- 渡邊 幹也
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- 日本フランス語フランス文学会中部支部研究報告集 (ISSN:02853795)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.73-83, 2003-03
4 0 0 0 OA 決戦下の陸上輸送対策
- 著者
- 東京急行電鉄株式会社 [著]
- 出版者
- 東京急行電鉄
- 巻号頁・発行日
- 1943
4 0 0 0 OA ケリの配偶システムと営巣場所への帰還性
- 著者
- 脇坂 英弥 脇坂 啓子 中川 宗孝 江崎 保男
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.17-23, 2015-09-30 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 12
We studied breeding ecology of the Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus by tracing nesting of 31 banded adults and their precocial chicks in Ogura-ike Farmland, Kyoto, for five breeding seasons from 2007 to 2011. From incubation to chick-rearing periods, banded males and females of seven pairs took care of their offspring cooperatively and the monogamous mating system of this species was confirmed. The pair relationship was maintained over years, notably in two pairs which remained stable for four and five years, respectively, even after failure in breeding. Thirteen birds (four males, eight females, one bird sex-unknown) returned to the study area and nested on the same block of the paddy field. Thus, nest site fidelity in this species can be strong.
4 0 0 0 OA 革新的な製品に含まれるデザイナー発の技術イノベーション
- 著者
- 吉岡(小林) 徹
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.21-37, 2018-06-30 (Released:2018-12-14)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 3
デザイナーが商品開発の上流工程から関わること,とくに,デザイナーが他の職能組織の活動に積極的に関与していくことは,製品・サービスのイノベーションの実現につながるのだろうか。本研究は,デザイナーによる他の職能組織の活動への関与の一つとして,技術開発への関与が,技術開発の質を高め,かつ,製品の質を高めているのかを,市場で成功を収めた事例の分析と,国際的なデザイン賞受賞製品90製品の調査により検証した。その結果,デザイナーの技術開発の関与は,①新たな要素技術を着想し,新規な製品コンセプトを実現する,②技術的課題を設定するか,技術開発チーム内での共有を促し,技術者の開発効率を高める,③他組織の技術を橋渡しし,新たな技術を生み出す,のいずれかの形で高い質の技術を生み,かつ,製品自体の質を高めていたことが確認できた。これらはデザイナー固有の寄与とまでは断言できないが,デザイナーの強みが生きた機能組織間連携の効果であると考えられる。
4 0 0 0 近代中東・イスラーム世界におけるプリント・メディアの歴史と構造
- 著者
- 平野 淳一
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告デジタルドキュメント(DD) (ISSN:21862583)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.9, pp.1-8, 2011-03-21
本論では,エジプトを中心とするアラブ世界やイラン,トルコにおいて,新聞や雑誌といったプリント・メディアがどのような歴史的経緯のもとに普及・発達していったのか,ヨーロッパとの国際関係,支配者の政治社会政策,知識人の文化活動などに着目しつつ明らかにする.This paper aims to reconsider a historical and theoretical process of development of the print media in the Arab world, Iran and Turkey, with special reference to their international relationships with the West and the governors' social politics and the intellectuals' cultural activities from the latter half of the 19th century to the beginning of the 20th century.
4 0 0 0 OA 埋(うず)もれた十字架 : 天正遣欧使節と黄金の十字架
- 著者
- 小西 瑞恵 コニシ ミズエ Mizue KONISHI
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学学芸学部論集
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.19-33, 2007-03-20
大阪中津にある南蛮文化館(北村芳郎館長)には、美しい黄金の十字架が保存されている。この十字架は、北村芳郎館長の解説によると、1951年に長崎県南有馬町(南島原市)の原城本丸跡から発見されたが、実は天正の遣欧少年使節がローマ教皇から託されて日本に持ち帰り、キリシタン大名有馬晴信(プロタジオ)に贈ったものであるという。この黄金の十字架について、最初に、これまで不明であった十字架発見の状況(発見者や発見場所)を初めて明らかにした。次に、文献史料(原文はイタリア語)により、これは十字架の形をした聖遺物入れであり、有馬晴信の遺品であることを確認した。天正遣欧使節については、織田信長が狩野永徳に描かせて託したローマ教皇への贈物(安土城の屏風絵)が探し求められているが、この十字架は使節が日本に持ち帰った教皇からの贈物である。なぜ島原の乱の舞台となった原城跡に、有馬晴信の遺品が埋もれていたかという問題については、同じく晴信の遺品である山梨県甲州市大和町栖雲寺蔵「伝虚空蔵菩薩画像」(最近、泉武夫氏により元末14世紀の景教聖像であることが実証された)について述べ、キリシタン大名として刑死した晴信の側近くにいた者が、島原の乱の際に原城跡で殉教したのであろうと推論した。
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1915年03月29日, 1915-03-29