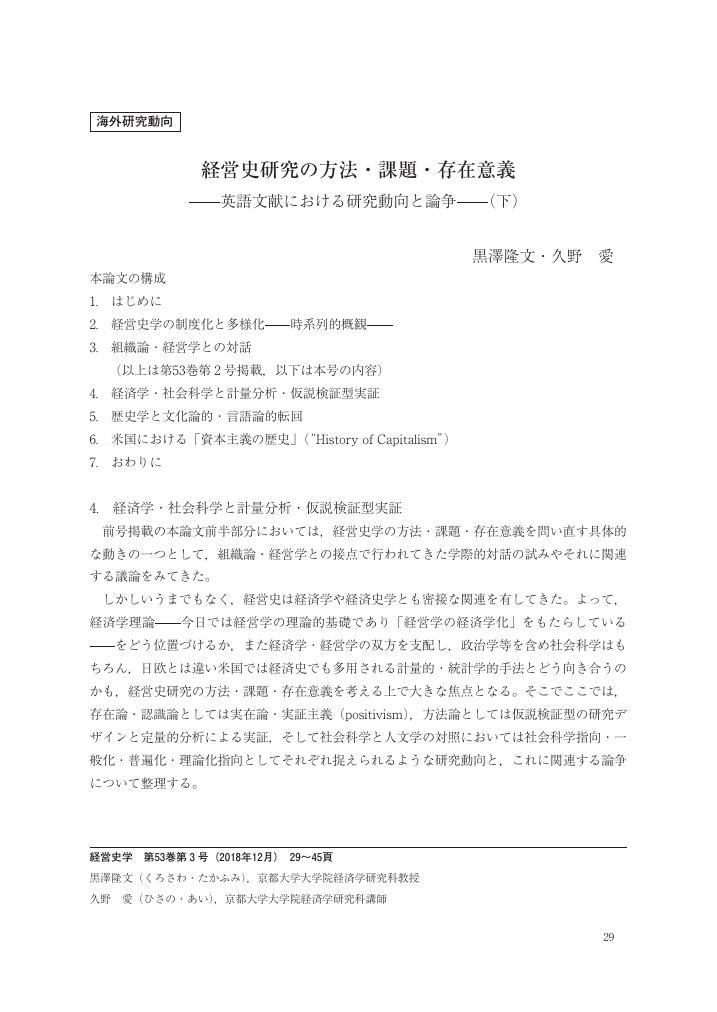3 0 0 0 OA 日本アルプスのカール内に分布する岩塊堆積地形の成因-岩石氷河説に基づく再検討
- 著者
- 青山 雅史
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.8, pp.529-543, 2002-07-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3 2
かつては日本アルプスのカール内にある岩塊堆積地形の多くがモレーンやプロテーラスランパートと考えられてきたが,その中に岩石氷河が含まれる可能性も指摘されている.この指摘の妥当性を検討するために,空中写真判読と現地調査を行った.その結果,岩石氷河と認定可能な地形が多数存在することが明らかとなった.たとえば,周縁部に切れ目のない連続性の良いリッジを持ち,その内側に同心円状の畝・溝構造を有する岩塊堆積地形や,畝・溝構造が未発達であっても前縁部のリッジが崖錐基部付近にある岩塊堆積地形は,形態と堆積物の特徴からみて,岩石氷河の可能性が高い.したがって,カール内の岩塊堆積地形を用いて氷河の消長や古環境変遷を論じる際には,あらかじめ地形の成因を十分に吟味する必要がある.
3 0 0 0 OA 2014年広島土石流災害による建物被害の立地分析
- 著者
- 田中 圭 中田 高
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.1, pp.62-78, 2018-01-01 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 16
広島市北郊で2014年8月20日未明に発生した土石流は山麓緩斜面に広がる住宅地を襲い,74名の犠牲者を伴う大災害を引き起こした.このような被害が発生した理由として,高度経済成長期における急速な宅地開発であると指摘されている.本稿では41名の犠牲者が集中した八木3丁目を対象に,撮影時期の異なる空中写真から作成したDSMを基に建物の建築時期を推定し,GISを用いて建築時期別に建物被害と土石流との関連について分析を行った.また,発災前にUAVを用いて撮影した範囲において,発災後に撮影を行い,それら画像からDSMなどを作成し,災害の状況を詳細に比較検討した.これらの分析結果から壊滅的な被害を受けた建物は,高度経済成長期以降に渓流の谷筋に建築されたものに集中したことがわかった.単純な高度経済成長期による宅地開発ではなく,土石流の発生危険度が高い地域に建物が建築され続けたことが,被害拡大の素因であることが明らかになった.
3 0 0 0 OA ニホンジカによるスギ・ヒノキ人工林剝皮害の広域分布状況
- 著者
- 幸田 良介 小林 徹哉 辻野 智之 石原 委可
- 出版者
- 地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所
- 雑誌
- 大阪府立環境農林水産総合研究所研究報告 (ISSN:21886040)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.9-13, 2015 (Released:2020-04-02)
シカによる人工林被害状況を広域的に把握するために, スギ・ヒノキ人工林において剥皮被害割合を調査し,IDW 法を用いて剥皮被害度の空間分布図を作成した.スギ林での剥皮被害度は全体的に低く,大阪府ではスギよりもヒノキの方が剥皮被害を受けやすい傾向にあると予想された.スギ林の剥皮被害度には被害地域の偏りが見られなかったのに対し,ヒノキ林での剥皮被害度は北摂の西側地域でのみ高く,被害地域の明確な偏りが見られた. 剥皮被害度の分布状況は落葉広葉樹林での下層植生衰退度の分布状況と一致せず,剥皮被害の発生にはシカ生息密度以外にも様々な環境要因が影響しているものと予想された.今後は剥皮害発生状況とシカ生息密度や様々な環境要因との関係について解析していくことが求められる.
3 0 0 0 OA 平安貴族における遅刻と時間厳守の研究
3 0 0 0 OA 『ロキフェールの戦い』における妖精モルガーヌ―「アーサー王物語」の「武勲詩」への影響―
- 著者
- 渡邉 浩司
- 出版者
- 中央大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文研紀要 (ISSN:02873877)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.321-350, 2022-09-30
「武勲詩」は,『ローランの歌』を皮切りとして11世紀後半に生まれ,12世紀中頃に初期の作品群が成立し,13世紀に₃ つの詩群が形づくられた。そして,こうした潤色過程で「アーサー王物語」の特徴的な要素を取りこみ,ジャンルの革新を行った。「ギヨーム・ドランジュ詩群」に属する『ロキフェールの戦い』の「アヴァロン・エピソード」がその典型例であり,その中ではアーサー王の異父姉妹モルガーヌが中心的な役割を演じている。現世の勇者レヌアールを異界アヴァロンへと連れ去る妖精モルガーヌは,妖女であると同時に極端な母性愛を見せる両義的な存在である。
従来の研究においては、近世儒教教育思想とその思想家の教育者としてのあり方に注目してきたのであるが、近世の教育法を現在も残していると思われるのは、伝統芸能の世界ではないかと思い至った。そこで本研究では、日本の伝統芸能の中でも、日本舞踊の世界を対象にすることとした。幼時より舞踊に関わってきたことから、外部からの客観的見方とは異なる内部的な考察が可能であると考えたのである。今日に残る日本舞踊の起源は、近世の歌舞伎舞踊であり、歌舞伎の演目の中に所作事が必ず入るところから、専門の振付師が必要となり、歌舞伎役者を兼ねた振付師が誕生した。彼らは流派を作り家元制度を作って、日本舞踊の指導を職業とした。その一人が四世西川扇蔵であり、その門弟の一人が初世西川鯉三郎である。二世西川鯉三郎は、名優六代目尾上菊五郎に丹精なる教えを受け、舞踊の才のみならず振付の才を発揮し、また弟子の指導においても、師匠ゆずりの卓抜性を示した。機会を捉えた教え方の妙味があったといえる。彼の創作舞踊は、古典の良さを基礎としながらも、能や狂言を取り入れ、現代性を加えて劇的な構成を施し、「舞踊劇」という新しいジャンルとなった。舞踊であっても単に形としての振りに終始するのでなく、文学性(ストーリー性)を重視し、菊五郎譲りの写実的で心理的な舞踊劇であった。すなわち、鯉三郎は日本舞踊の「大衆化」を最も意図したのである。しかしながら、「名人」と言われながらも、鯉三郎の芸や業績に対して、当時の社会的評価は必ずしも高かったとは言えない。真の芸術を正しく評価出来る文化的土壌や国民性を、日本はこれから育成していかなければならない。伝統芸能教育は、これからの生涯学習社会を支え、人々の失われた「感性」を養うことに、大いに力を発揮すべきものと思われるのである。
3 0 0 0 OA 後期メルロ=ポンティ哲学における可逆性と他性
- 著者
- 屋良 朝彦
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.47, pp.276-285, 1996-05-01 (Released:2009-07-23)
Merleau-Ponty qualifiait la réversibilité de «vérité ultime». «La réversibilité» exprime la fonction ontologique d'alterner les deux termes <le voyant-le visible>, <le touchant-le touché>, tout en les faisant demeurer dans la même chair. Et plus il soulignait l'importance d' «une réversibilité toujours imminente et jamais réalisée en fait». Je ne parviens jamais à me toucher touchant. Il y a quelque chose qui déborde cette réversibilité. Le but de cette essai est rechercher le sens de l'imminence de la réversibilité. Est-ce la latence de l'Être ? ou la transcendance de l'Être ? ou la transcendance même au-delà de l'Être ? La possibilité de déchirer l'ontologie de la chair serait montrée, qui est «l'impensé» dans la dernière philosophie de Merleau-Ponty.
3 0 0 0 OA 社交不安における自己注目と他者注目を脳領域と視線情報から可視化する
- 著者
- 富田 望 熊野 宏昭
- 出版者
- 日本不安症学会
- 雑誌
- 不安症研究 (ISSN:21887578)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.19-28, 2022-11-30 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 37
社交不安においては,自己注目と他者注目が症状の維持要因とされているが,社会的場面において2つの注意の偏りがどのような関係にあるのかを示した実証的研究は少ない。本稿では,自己注目や他者注目を視線や脳活動によって可視化することで,両者を比較可能な形で捉えることを目的とした,Tomita et al.(2020)とTomita & Kumano(2021;第2回日本不安症学会学術賞受賞論文)の2つの研究を紹介した。研究の結果,右前頭極と左上側頭回の過活動は対人場面で生じる自己注目や他者注目それぞれの客観的指標となることが示唆された。対人場面でこれらの脳活動をリアルタイムに測定することで,社交不安者の自己注目と他者注目の程度を,本人が自覚していない場合でも予測できることが期待される。また,自己注目と他者注目は独立した構成概念であることが脳の観点から示唆された。
3 0 0 0 OA 生物学における種の概念
- 著者
- 川原 治之助
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 鉱物学雜誌 (ISSN:04541146)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.84-90, 1977-01-30 (Released:2009-08-11)
- 参考文献数
- 3
3 0 0 0 OA ケイパビリティ・アプローチからみた未婚の女性非正規雇用者の生活課題
- 著者
- 山本 咲子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.8, pp.421-429, 2017 (Released:2017-09-06)
- 参考文献数
- 31
The purpose of this study is to clarify the life problems of unmarried women in non-regular employment. Amartya Sen's Capability Approach that provides a new way of understanding of life quality is applied in order to do so. The survey took the form of interviews which were conducted among 6 participants. The results of the survey were as follows: various social conditions that make it hard to escape non-regular employment or have stable income, such as fixed-term contracts system, unstable work environment and suspicion towards the pension system, made participants unable to think positively about the future. To resolve these life problems, I propose several measures: to secure the opportunity of stable employment for non-regular employees; to conduct a seminar that would educate people about the position of non-regular employees within the current economic structure; to introduce a policy that would improve the low wages of non-regular employees.
3 0 0 0 OA 弘前藩とベンガラ -今別町の赤根沢における赤土採掘の記録-
- 著者
- 竹内 健悟
- 出版者
- 青森大学付属総合研究所
- 雑誌
- 青森大学付属総合研究所紀要 (ISSN:24361585)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.20-29, 2022-09-30 (Released:2022-12-28)
- 参考文献数
- 5
今別町にある青森県指定の天然記念物「赤根沢の赤岩」の周辺は,縄文時代から江戸時代にかけて良質の赤土を産出した場所である.弘前藩は,役人を配置し,厳重な管理の下で赤土を採掘・精製し,赤の顔料のベンガラとして江戸幕府などに献上していた.藩では,赤土を採掘するときには,奉行を任命し,番所に役人や職人を派遣した.本稿では,当時の管理体制,作業内容,施設設備について「弘前藩庁日記」の記録から整理した.
3 0 0 0 OA 相撲の駒どり放送
- 著者
- 志村 一郎 福田 和夫 山脇 久彦 谷村 洋 佐々木 巖
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン (ISSN:18849644)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.10, pp.444-448, 1957 (Released:2011-03-14)
3 0 0 0 OA <ノート>元老の形成と変遷に関する若干の考察 : 後継首相推薦機能を中心として
- 著者
- 伊藤 之雄
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.241-263, 1977-03-01
個人情報保護のため削除部分あり
3 0 0 0 OA 経営史研究の方法・課題・存在意義 ―英語文献における研究動向と論争―(下)
- 著者
- 黒澤 隆文 久野 愛
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.29-45, 2018 (Released:2020-12-30)
3 0 0 0 OA 都市整備に伴う回遊選択の変化に応答的な土地の両面市場モデル
- 著者
- 小林 里瑳 羽藤 英二
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.524-531, 2021-10-25 (Released:2021-10-25)
- 参考文献数
- 16
本論文は,土地所有者による土地の売買と来訪者による逐次的滞在場所選択を離散的選択モデルで定義したサブモデルからなる地区スケールを対象とした土地-交通モデルを提案した.特に土地売買行動は,売手地主と買手地主それぞれの推定購入額と推定売却額を効用関数に導入することで,相互推論によるマッチング行動を仮定し,従前の土地市場モデルで扱われてきた均衡価格を明示しない取引構造の記述を試みた.構築したモデルは,2時点の実データを用いた実証分析及び構造推定を用いた推定により,計算可能であることを確認した.提案モデルは,都市開発や都市政策が歩行者の行動や土地所有者の土地取引行動に与える影響の測定やシミュレーションに応用可能性を持つと考える.
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1942年04月01日, 1942-04-01
- 著者
- 大沢 啓子 大沢 夕志
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.253-262, 2022-12-15 (Released:2022-12-15)
- 参考文献数
- 11
アブラコウモリPipistrellus abramusは,国内では北海道南部から沖縄まで,都市やその郊外で最も普通に見られる種である.原則夜行性であるが,日没前後の明るい時間にも活動するため,昼行性の捕食性鳥類の餌となることがある.我々は2012年4月から2022年5月までの埼玉県川越市にある小畔川の河岸からの710日の観察で,飛翔中のアブラコウモリに対する昼行性鳥類の捕食行動を47件観察した.捕食行動を行った鳥類にはツミAccipiter gularis,チョウゲンボウFalco tinnunculus,ハヤブサFalco peregrinus,モズLanius bucephalus,ハシボソガラスCorvus coroneが含まれる.都市近郊にすむ昼行性の捕食者の鳥にとって,アブラコウモリが潜在的な餌となりうることを示している.