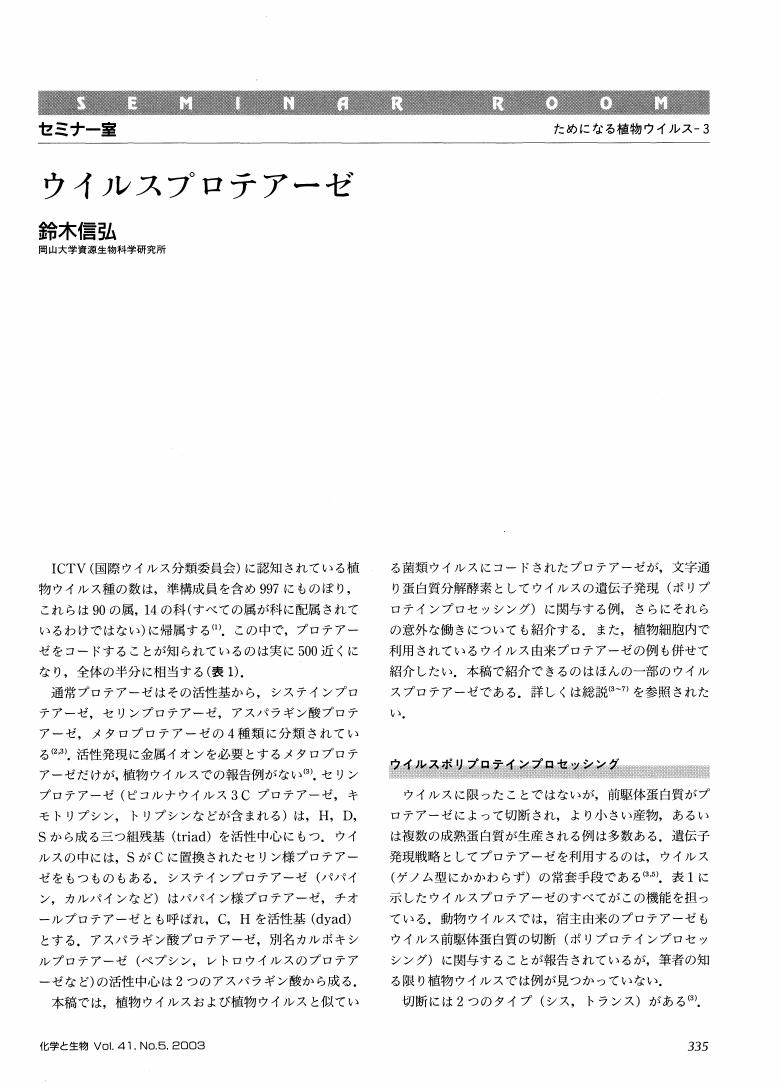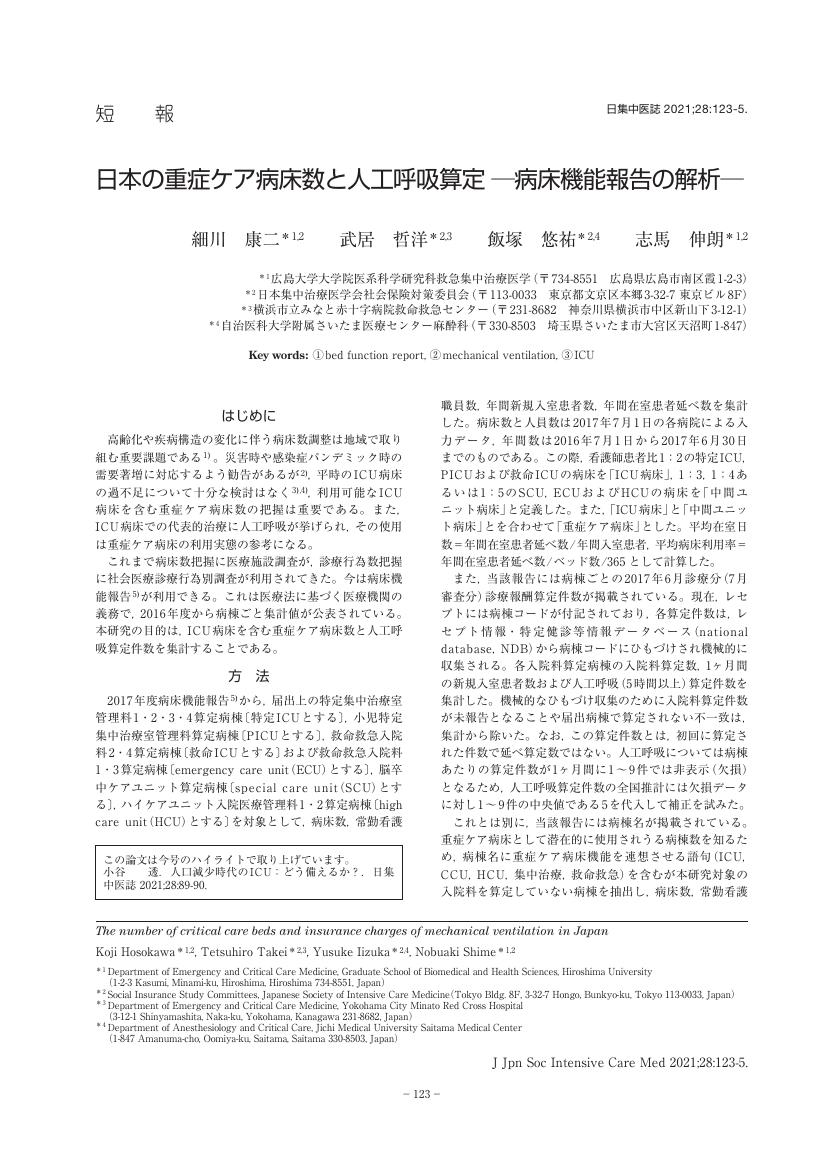3 0 0 0 IR 「もののあはれをしる」と浪漫的憧憬 (中井千之教授還暦記念号)
- 著者
- 中井 千之
- 出版者
- 上智大学ドイツ文学会
- 雑誌
- 上智大学ドイツ文学論集 (ISSN:02881926)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.p9-20, 1989
中井千之教授還暦記念号Sondernummer Zum 60. Geburtstag von Prof. Chiyuki Naiai
- 著者
- He Gong Mei Huang Zhaosheng Wang
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-027, (Released:2021-07-28)
The northern Eurasia is a region heavily affected by the Arctic polar vortex (APV). Understanding the vegetation responses to anomalous APV in this region is important for dealing with climate change. In this study, we investigated the impacts and mechanism of the anomalous APV phases on the vegetation dynamics in the northern Eurasia. The larger and smaller APV phases correspond to almost opposite atmospheric circulation patterns which result in opposite vegetation responses. The decreased (increased) solar radiation, the enhanced (weakened) northerly winds, together with the decreased (increased) water vapor divergence, caused the decreasing (increasing) of the air temperature, increasing (decreasing) of the precipitation and soil moisture in the study area during the larger (smaller) APV phase. The response of vegetation growth to the APV depends on climate change and vegetation sensitivity to it. In most parts of the study area, vegetation growth was positively associated with air temperature, and hence, vegetation was suppressed (promoted) during the larger (smaller) APV phase. In the northeast of the Caspian Sea (NCS), vegetation growth was sensitive to precipitation. Therefore, the increased (decreased) soil moisture in summer and autumn were responsible for the promoted (suppressed) vegetation growth during the larger (smaller) APV phase.
- 著者
- Tana Bao Tao Gao Banzragch Nandintsetseg Mei Yong Erdemtu Jin
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-026, (Released:2021-07-21)
- 被引用文献数
- 13
In this study, we investigated the spatiotemporal variations of border-crossing dust events (DEs), including floating, blowing dust, and dust storms between Mongolia (MG) and Inner Mongolia (IM), China using the ground-based observations from 91 synoptic stations across the Mongolian Plateau during 1977-2018. We defined the intensity of DEs (progressive and recessive) depending on the dust impact area (number of stations affected by dust) by dividing them into three categories: DEs, transported dust events (T-DEs), and severe transported dust events (ST-DEs). The results revealed that during 1977-2018, the frequency of DEs in MG was two times higher than in IM. Simultaneously, the frequency of DEs (dominated by dust storms) increased in MG, whereas IM experienced a decrease in DEs (prevalent types of blowing dust). The T-DEs occurred 2.4 times higher than the ST-DEs over Mongolian Plateau. For the border-crossing DEs, transported dust storms were the dominant type. During 1977-1999, approximately 86% of DEs in IM originated from MG; however, this was decreased to 60% in the 2000s (2000-2018). The intensity of the border-crossing DEs originated from MGand the recessive T-DEs increased significantly since the 2000s, which were more significant than the progressive type.
3 0 0 0 OA Tropical Cyclone Track Forecasts using NCEP-GFS with Initial Conditions from Three Analyses
- 著者
- Tetsuro Miyachi Takeshi Enomoto
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-025, (Released:2021-07-20)
Tropical cyclone track forecast experiments were conducted using the National Centers for Environmental Prediction Global Forecast System with the initial conditions from three numerical weather prediction centers, to distinguish between tropical cyclone track forecast errors attributable to the initial state uncertainty and those attributable to the model imperfection. The average position error was reduced by replacing the initial conditions from the European Centre for Medium-range Weather Forecasts. The northward recurvature of Lupit (2009) was not reproduced with initial conditions from the Japan Meteorological Agency. It was consistent with the preceding study, indicating sensitivity to the initial state. The sensitivity to the model and the initial state was obtained. For Parma (2009), as opposed to the conclusion of the previous study, where Parma was discovered to be insensitive to the initial state, and the error was assumed to come from the model difference. Insensitivity to the initial vortex structures in the predicted tracks for Parma indicates that the error in the steering flow formed by the environmental field around tropical cyclone contributes to the northward bias.
3 0 0 0 OA 糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告 (国際標準化対応版)
- 著者
- 清野 裕 南條 輝志男 田嶼 尚子 門脇 孝 柏木 厚典 荒木 栄一 伊藤 千賀子 稲垣 暢也 岩本 安彦 春日 雅人 花房 俊昭 羽田 勝計 植木 浩二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.7, pp.485-504, 2012 (Released:2012-08-22)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 10 1
本稿は,2010年6月発表の「糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告」以降の我が国におけるHbA1c国際標準化の進捗を踏まえて,同報告のHbA1cの表記を改めるとともに国際標準化の経緯について解説を加えたものである. 要約 概念:糖尿病は,インスリン作用の不足による慢性高血糖を主徴とし,種々の特徴的な代謝異常を伴う疾患群である.その発症には遺伝因子と環境因子がともに関与する.代謝異常の長期間にわたる持続は特有の合併症を来たしやすく,動脈硬化症をも促進する.代謝異常の程度によって,無症状からケトアシドーシスや昏睡に至る幅広い病態を示す. 分類(Table 1,2,Fig. 1参照):糖代謝異常の分類は成因分類を主体とし,インスリン作用不足の程度に基づく病態(病期)を併記する.成因は,(I)1型,(II)2型,(III)その他の特定の機序,疾患によるもの,(IV)妊娠糖尿病,に分類する.1型は発症機構として膵β細胞破壊を特徴とする.2型は,インスリン分泌低下とインスリン感受性の低下(インスリン抵抗性)の両者が発症にかかわる.IIIは遺伝因子として遺伝子異常が同定されたものと,他の疾患や病態に伴うものとに大別する. 病態(病期)では,インスリン作用不足によって起こる高血糖の程度や病態に応じて,正常領域,境界領域,糖尿病領域に分ける.糖尿病領域は,インスリン不要,高血糖是正にインスリン必要,生存のためにインスリン必要,に区分する.前2者はインスリン非依存状態,後者はインスリン依存状態と呼ぶ.病態区分は,インスリン作用不足の進行や,治療による改善などで所属する領域が変化する. 診断(Table 3~7,Fig. 2参照): 糖代謝異常の判定区分: 糖尿病の診断には慢性高血糖の確認が不可欠である.糖代謝の判定区分は血糖値を用いた場合,糖尿病型((1)空腹時血糖値≧126 mg/dlまたは(2)75 g経口糖負荷試験(OGTT)2時間値≧200 mg/dl,あるいは(3)随時血糖値≧200 mg/dl),正常型(空腹時血糖値<110 mg/dl,かつOGTT2時間値<140 mg/dl),境界型(糖尿病型でも正常型でもないもの)に分ける.また,(4)HbA1c(NGSP)≧6.5 %(HbA1c(JDS)≧6.1 %)の場合も糖尿病型と判定する.なお,2012年4月1日以降は,特定健康診査・保健指導等を除く日常臨床及び著作物においてNational Glycohemoglobin Standardization Program(NGSP)値で表記されたHbA1c(NGSP)を用い,当面の間,日常臨床ではJDS値を併記する.2011年10月に確定した正式な換算式(NGSP値(%)=1.02×JDS値(%)+0.25 %)に基づくNGSP値は,我が国でこれまで用いられてきたJapan Diabetes Society(JDS)値で表記されたHbA1c(JDS)におよそ0.4 %を加えた値となり,特に臨床的に主要な領域であるJDS値5.0~9.9 %の間では,従来の国際標準値(=JDS値(%)+0.4 %)と完全に一致する. 境界型は米国糖尿病学会(ADA)やWHOのimpaired fasting glucose(IFG)とimpaired glucose tolerance(IGT)とを合わせたものに一致し,糖尿病型に移行する率が高い.境界型は糖尿病特有の合併症は少ないが,動脈硬化症のリスクは正常型よりも大きい.HbA1c(NGSP)が6.0~6.4 %(HbA1c(JDS)が5.6~6.0 %)の場合は,糖尿病の疑いが否定できず,また,HbA1c(NGSP)が5.6~5.9 %(HbA1c(JDS)が5.2~5.5 %)の場合も含めて,現在糖尿病でなくとも将来糖尿病の発症リスクが高いグループと考えられる. 臨床診断: 1.初回検査で,上記の(1)~(4)のいずれかを認めた場合は,「糖尿病型」と判定する.別の日に再検査を行い,再び「糖尿病型」が確認されれば糖尿病と診断する.但し,HbA1cのみの反復検査による診断は不可とする.また,血糖値とHbA1cが同一採血で糖尿病型を示すこと((1)~(3)のいずれかと(4))が確認されれば,初回検査だけでも糖尿病と診断する.HbA1cを利用する場合には,血糖値が糖尿病型を示すこと((1)~(3)のいずれか)が糖尿病の診断に必須である.糖尿病が疑われる場合には,血糖値による検査と同時にHbA1cを測定することを原則とする. 2.血糖値が糖尿病型((1)~(3)のいずれか)を示し,かつ次のいずれかの条件がみたされた場合は,初回検査だけでも糖尿病と診断できる. ・糖尿病の典型的症状(口渇,多飲,多尿,体重減少)の存在 ・確実な糖尿病網膜症の存在 3.過去において上記1.ないし2.の条件がみたされていたことが確認できる場合は,現在の検査結果にかかわらず,糖尿病と診断するか,糖尿病の疑いをもって対応する. 4.診断が確定しない場合には,患者を追跡し,時期をおいて再検査する. 5.糖尿病の臨床診断に際しては,糖尿病の有無のみならず,成因分類,代謝異常の程度,合併症などについても把握するよう努める. 疫学調査: 糖尿病の頻度推定を目的とする場合は,1回の検査だけによる「糖尿病型」の判定を「糖尿病」と読み替えてもよい.この場合,HbA1c(NGSP)≧6.5 %(HbA1c(JDS)≧6.1 %)であれば「糖尿病」として扱う. 検診: 糖尿病を見逃さないことが重要で,スクリーニングには血糖値をあらわす指標のみならず,家族歴,肥満などの臨床情報も参考にする. 妊娠糖尿病: 妊娠中に発見される糖代謝異常hyperglycemic disorders in pregnancyには,1)妊娠糖尿病gestational diabetes mellitus(GDM),2)糖尿病の2つがあり,妊娠糖尿病は75 gOGTTにおいて次の基準の1点以上を満たした場合に診断する. (1)空腹時血糖値 ≧92 mg/dl (2)1時間値 ≧180 mg/dl (3)2時間値 ≧153 mg/dl 但し,上記の「臨床診断」における糖尿病と診断されるものは妊娠糖尿病から除外する.
3 0 0 0 家族と(再)分配
- 著者
- 藤谷 武史
- 出版者
- 有斐閣
- 雑誌
- 租税法研究 = Japan tax law review (ISSN:09104313)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.63-81, 2020-06
- 著者
- 田中 洋一 山川 修
- 雑誌
- 研究報告教育学習支援情報システム(CLE) (ISSN:21888620)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-CLE-25, no.1, pp.1-5, 2018-06-08
SECI モデル及び e ポートフォリオ ・ リテラシースキルを用いた授業設計について報告する.
- 著者
- 東方 孝之
- 出版者
- 京都大学東南アジア地域研究研究所
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.211-213, 2021-07-31 (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 IR 盛岡藩における巣鷹捕獲 : 三戸町小笠原家文書「巣鷹御用覚帳」の分析から
- 著者
- 中野渡 一耕
- 出版者
- 九州大学基幹教育院
- 雑誌
- 鷹・鷹場・環境研究 (ISSN:24328502)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.17-34, 2020-03-20
小稿は、盛岡藩三戸代官所(現青森県三戸町)の役人の留書から、同藩における巣鷹捕獲の実態について分析するものである。巣鷹とは、巣立ち前のタカ類の幼鳥のことで、鷹狩り用に調教するため捕獲された。盛岡藩では巣鷹を捕獲する専門の役職「巣鷹御用懸」が、藩内4か所の代官所に置かれた。巣鷹の見回りや捕獲は、巣鷹御用懸や実際に捕獲する専門の百姓のほか、肝入(村の責任者)・山守など多くの村人が動員される一大作業だった。また藩庁の指示により、捕獲の要・不要ががけ判断され、また営巣(巣懸)・孵化(貝割)・巣下げの度に代官や用人に報告させるなど、厳格な管理体制が敷かれていた。藩の権力を背最にした鷹の権威の大きさが見て取れるとともに、藩の方針に振り回される現場の様子も垣間見え、藩政と地域の結節点にあった代官所役人の業務の特性が現れている。また、巣鷹御用懸の職制と関連して、これまであまり分析されていなかった、盛岡藩の鷹匠組織や鷹の捕獲体制についても触れる。
3 0 0 0 OA ウイルスプロテアーゼ
- 著者
- 鈴木 信弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.335-344, 2003-05-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 35
3 0 0 0 IR 福井からの痘苗の伝播と鯖江藩の種痘
- 著者
- 柳沢 芙美子
- 出版者
- 福井県文書館
- 雑誌
- 福井県文書館研究紀要 (ISSN:13492160)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.53-71, 2020-03
3 0 0 0 OA キャサリン・マンスフィールドの「生」の見方 : 「園遊会」と「蝿」を通して
- 著者
- 寺本 明子
- 出版者
- 東京農業大学
- 雑誌
- 東京農業大学農学集報 (ISSN:03759202)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.5-12, 2008-06-15
キャサリン・マンスフィールド(Katherine MANSFIELD 1888-1923)は,20世紀の短編小説の基礎を築いた作家である。彼女の作品にはドラマティックなロマンスも大事件も無く,有るのはありふれた日常生活と,そこに見られる登場人物達の繊細な感情である。喜びと哀しみ,憧れと幻滅,期待と落胆,好みと嫌悪,不安と安堵,情熱と諦めなど総ての感情が彼女の小説に織り込まれ,彼女は人間の性質だけでなく,日常生活に秘められた真実への深い洞察力をも発揮する。若くしてマンスフィールドは小説家になる夢を抱き,その為には,何でも知ろうとする好奇心を持ち,幸せな女性の人生経験を積むことが大切だと考えた。しかし不幸なことに,その人生は向こう見ずな結婚,続いて流産,離婚,数々の病気へと進んで行った。一方で,愛する弟の死によって,彼女は20才で見捨てた祖国ニュージーランドについて書くことが使命だと気づいた。軽率な生活のせいで患った病気に苦しみ,彼女自身の死を身近に感じることが,「生きる」ということについて書くきっかけとなった。「園遊会」('The Garden Party')では,ローラが楽しい園遊会の正にその日に,貧しい荷馬車屋の死に出会い,死の荘厳さを知る。「蝿」('The Fly')では,ボスが,インク瓶に落ちた蝿を助けるのだが,その蝿に数滴のインクを垂らして死なせてしまう。彼は蝿に,6年前に戦死した最愛の息子の姿をだぶらせる。このように「死」に関する話題を取り上げながら,彼女はまた,日常生活の中に「生」を発見し,その発見を感覚的に捉え,小説に描く。彼女にとって人生は,何か永遠なるものにつながる喜びの瞬間で成り立っているのだ。この論文では,上記の2つの作品を精読し,マンスフィールドの「生」に対する見方を研究する。
3 0 0 0 IR 視覚表示と表現の記号論 (1) : 視覚記号の原理について
- 著者
- 雨宮 俊彦
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.89-141, 2000-09-25
本論文では,視覚記号の基本的な問題をあつかった。第1部では,視覚記号と聴覚記号の比較,音声言語と絵的記号の比較がなされた。そして,著者は,種々の視覚表示と視覚表現が,マー(1982)のとなえる視覚的情報処理における諸段階の表象と諸側面に関連して位置づけられることを指摘した。第II部では,グッドマン(1968)による記譜性にかんする記号論とデイーコン(1997)によるシンボリック・レファランスの成立についての説が,それぞれ批判的に検討された。最後に著者は,視覚記号における四種類のレファランス(外延指示、共示、例示、表現)のしくみの解明をこころみた。付録では,マンガ(日本のストーリーコミックス)表現が,音声言語表現と絵的表現の融合したものとして分析された。
3 0 0 0 近代国家の文化的アイデンティティ形成における古代表象の諸相
3 0 0 0 『諏訪大明神絵詞』外題・奥書考 (地域特集 諏訪郡)
- 著者
- 石井 裕一朗
- 出版者
- 信濃史学会
- 雑誌
- 信濃 [第3次] (ISSN:02886987)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.12, pp.923-943, 2020-12
3 0 0 0 OA 日本の重症ケア病床数と人工呼吸算定 ─病床機能報告の解析─
- 著者
- 細川 康二 武居 哲洋 飯塚 悠祐 志馬 伸朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.123-125, 2021-03-01 (Released:2021-03-01)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 石井 紀子
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.167-191, 2005-03
一八八〇年代から一九〇〇年代にかけて北中国ミッションと日本ミッションに赴任した医師の資格を持つ一人のアメリカ女性宣教師の本国宛の書簡を手がかりに、伝道地の主体性、宣教師の専門性、ジェンダーと伝道活動の相互作用を検討した。その結果、伝道活動を決定する要因として伝道地の事情が宣教師個人の専門性より優先することが明らかになった。本事例でホルブルックは中国で専門を生かして診療所開設の上、「医療バイブル・ウーマン」を養成できたのに対し、日本では女子高等教育の中の理科教育、家庭衛生教育の分野で自身の専門性を生かした。女性宣教師はジェンダーの分離を根拠に女性のための伝道を正当化していた上、海外伝道の目的として伝道と女性の地位の向上を矛盾したものとはとらえていなかったので、ホルブルックにとって二つの伝道活動は一貫していたといえる。
- 著者
- 吉田 毅
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.43-58, 2010-03-20 (Released:2016-10-05)
- 参考文献数
- 18
本稿の目的は、オリンピック金メダリストがどのような競技生活を送って金メダル獲得に至ったのか、また、金メダル獲得は金メダリストのその後の人生にどのような影響を及ぼしているのかについて、競技者のキャリア形成の視点を踏まえ解明することであった。ここでは、冬季オリンピック、ノルディック複合団体で金メダルを獲得した日本チームの1人を事例とし、ライフヒストリー法を用いて検討した。 氏は、スポーツ少年団で本格的なジャンプを、中学時代に複合を専門的に始めた。高校時代にはハードトレーニングに打ち込んだ結果、日本代表としてジュニア世界選手権に出場し、また、インターハイで優勝した。氏の競技者キャリアは、中学時代までは「導入・基礎期」、高校時代は「強化・飛躍期」、大学時代は「停滞期」、そして実業団時代が「仕上げ期」と捉えられる。これは、競技力養成という点で、早期には結果を求めるよりも基礎づくりが重要であることを示唆する1つのモデルとなり得るだろう。また、ピークに達する前段階での停滞が奏功したモデルともいえるが、氏はこの時期にもオリンピックに出場したいとの夢を保持していた。氏が金メダル獲得に至るまでには、金メダル獲得の追い風というべき運命的な要素がいろいろと見出された。おそらく金メダリストの競技者キャリアには、そうした運命的な要素を孕む金メダル獲得に至るストーリーがあるのだろう。 氏のこのストーリーには、さらに各段階の指導者、ならびに両親をはじめとした支援者と様々な他者が登場する。 氏にとって、金メダル獲得は至福の体験であり、ほとんど良い意味で氏の人生を変えるものであった。例えば、世間の注目を浴び、あらゆる面で自信を得、多額の報奨金を得た。現役引退後のセカンドキャリア形成プロセスでは、学校等からの度々の講演依頼、また複合のテレビ解説依頼があり、仕事では知名度の高さが有利に働いた。