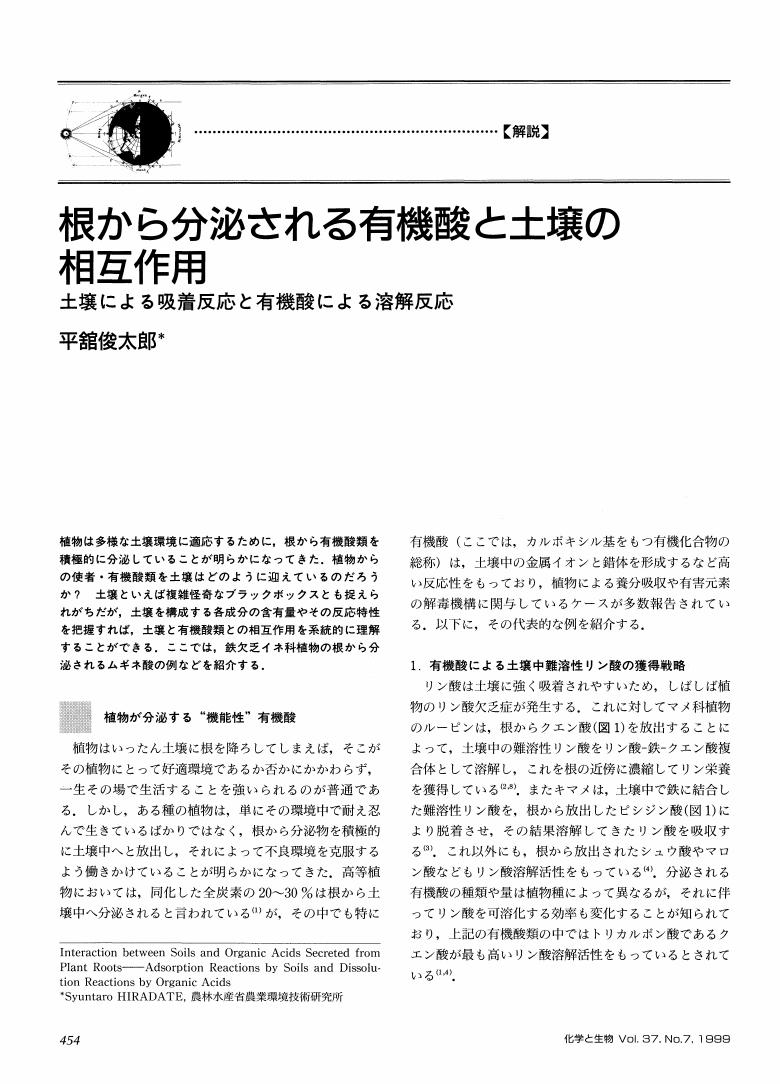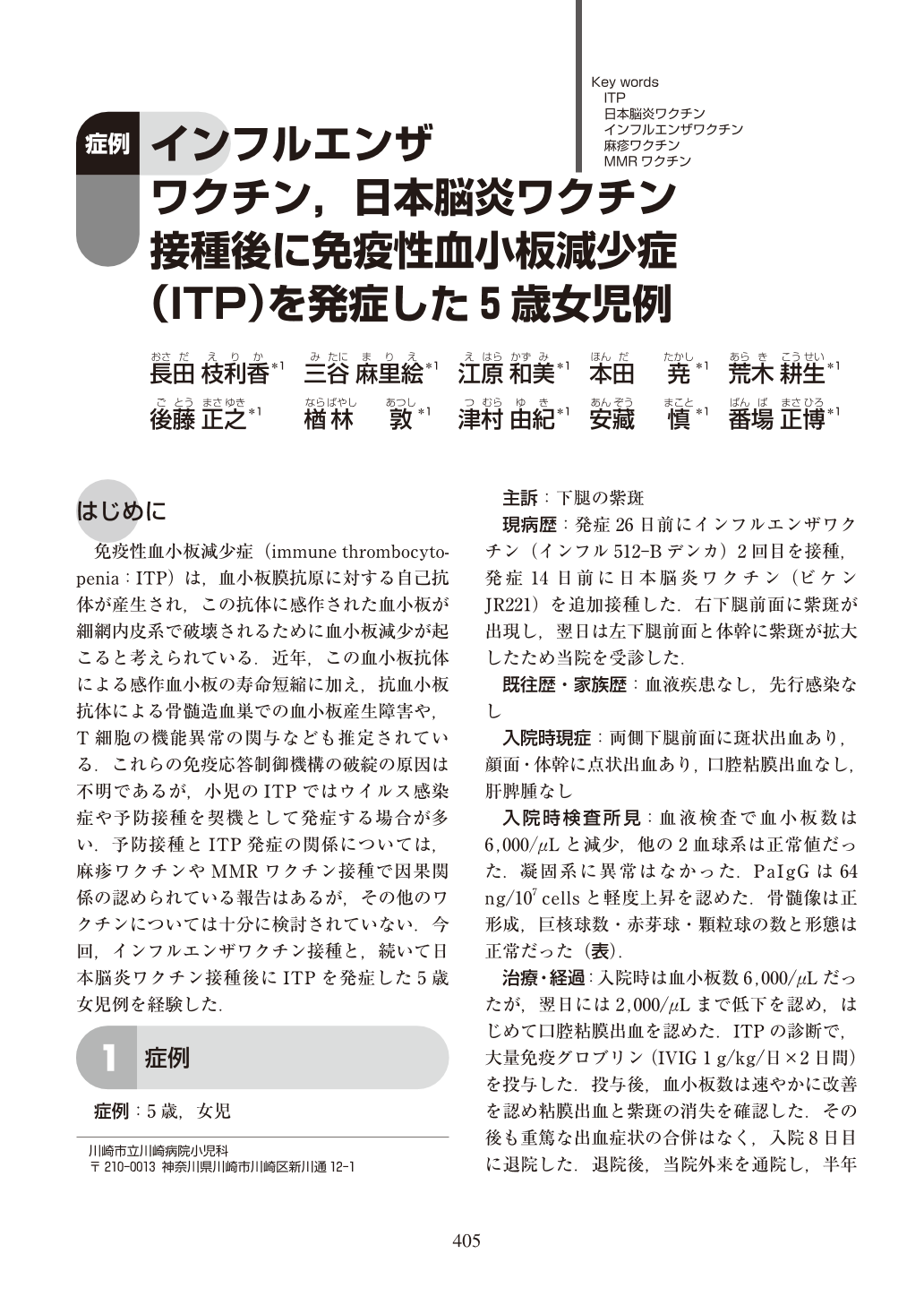3 0 0 0 (OS招待講演)ことをデザインするアプローチ
- 著者
- 須永 剛司
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.2A1OS151, 2011
<p>学際共同研究であるCRESTプロジェクトから私たちが見出したのは拡張の必要である。社会の営みに埋め込まれるシステム開発のために、技術やデザインの視野を、システムから道具へ、道具から人々のリアルな活動へ拡張すること。ここでは、生きた活動をデザインの対象問題として認識するために、「こと」という概念を提示する。「こと」は人々に経験される事態であり、私のまわりに、そのとき立ち現れる生成的な出来事である</p>
- 著者
- 武内 進一
- 出版者
- 京都大学東南アジア地域研究研究所
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.277-279, 2021-01-31 (Released:2021-01-29)
3 0 0 0 OA 河床縦断形の解析からみた養老山地東斜面における削剥と堆積
- 著者
- 大上 隆史
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2016年大会
- 巻号頁・発行日
- 2016-03-10
濃尾平野の西縁を画する養老山地,とくにその東斜面には起伏が大きい山地地形が発達している.これらは養老・桑名断層帯の活動に伴う山地の活発な隆起,および東流する河川網の下刻に伴って形成されたと考えられ,山地で生産された土砂が東麓に扇状地群を形成している.扇状地の形態に関して多くの研究が蓄積されており,扇面勾配が集水域面積(≒河川流量)と負の相関を持つことが広く認識されている.さらに,扇面勾配の大きさが土砂流量/河川流量と相関関係を持つことが地形実験によって示されており(Whipple et al., 1998),実際の扇状地においても扇面勾配が河川流量に加えて集水域の削剥速度にコントロールされている可能性が高い.しかし,それらの関係を具体的に検討するためには,集水域の平均削剥速度や扇状地における堆積速度を定量化する必要がある.それらの値を直接得ることは一般に難しいため,集水域における削剥速度の指標として斜面傾斜や起伏比が計測されてきた.ところが,“Threshold Hillslope(限界傾斜)”を獲得するような険しい流域では削剥速度は斜面傾斜と無関係となることが示されており(Burbank et al., 1996),起伏比は集水域面積と負の相関をもつ場合が多いため河川流量と切り分けた議論が困難である.一方で,ストリームパワー侵食モデルにもとづいて“平衡状態にある”岩盤河川の河床縦断形の解析手法が発展しつつあり,隆起速度と岩盤の抵抗性に依存する流路の「Steepness(急峻さ)」の概念が導入されている(Wobus et al., 2006).岩盤強度が一様であれば,“平衡状態にある”河川のSteepnessは隆起速度(≒侵食速度)の関数となることが期待されており,近年ではSteepnessと侵食速度の関係が実際に検討されつつある(DiBiase et al., 2010).特に限界傾斜を獲得するような山地では,Steepnessが岩盤河川の下刻速度を表し,河川の下刻速度が山地の削剥速度を規定している可能性がある.そこで,養老山地東斜面の河川群における河床縦断形から流路のSteepnessを試算するとともに,それらと扇面勾配との関係を検討した. 養老山地の東斜面を流下する河川群のうち,養老山地の中央分水嶺に谷頭を持つ25流域を研究対象とした.国土地理院が公開している5 mメッシュ数値標高データにもとづき直交座標系(UTM53N)における10 mグリッドのDEMを発生させ,これを用いて集水域解析を行った.谷頭を起点とする河床縦断形を作成し,それらをχ−標高プロット(Perron and Royden, 2013)に変換した.χ−標高プロットが直線回帰されるとき,その河床縦断形は“平衡状態にある”とみなせる.また,χ−標高プロットの勾配は「Steepness」を表す.流路距離および集水域面積を用いてχを計算するのにあたり,A0=10 km2とし,定数m/n=0.5を採用した.χ−標高プロットにもとづき,流路は大きく3つのセグメントに分けられる.最上流部におけるχ−標高プロットの勾配は比較的小さく,これらの流路の集水域は<0.1 km2程度である(最上流セグメント).集水域面積>0.1 km2程度の山地河川の流路ではχ−標高プロットの勾配は大きくなり,その勾配はほぼ一定で直線回帰される(上流セグメント).上流セグメントはχ−標高プロットで直線回帰されるため“平衡状態にある”流路とみなせる.下流部の堆積域ではχ−標高プロットの勾配は小さくなっている(下流セグメント).養老山地東斜面の山地における河川網の大部分は上流セグメントに属する.そのため,各集水域の流路のSteepnessを,本流の上流セグメントにおけるχ−標高プロットの勾配とした.本発表ではχ−標高プロットの勾配をそのままSteepnessとした. 対象河川の集水域面積は0.15−5.09 km2であり,それらの平均傾斜は36−44°,起伏比は0.09−0.45である.Steepnessは35.2−89.6×10-3の値をとる.これらの集水域の地形量のうち,起伏比は集水域面積と負の相関関係を示すが,その他は明瞭な相関関係が認められない.ただし,起伏比とSteepnessの関係に着目すると,同程度の集水域面積のクラスター毎に概ね正の相関がある.扇頂から下流に連続する直線的な河床勾配(以下では堆積勾配と呼ぶ)は0.024−0.338であり,これらはよく知られているように集水域面積と負の相関関係を示す.Steepnessと堆積勾配の関係を見ると,同程度の集水域面積のクラスター毎に正の相関関係があるとみなせる.このことは,堆積勾配が集水域面積とSteepnessによって規定されていることを意味する.また,Steepnessが流域の削剥速度を表していることを間接的に示し,養老山地東斜面における削剥プロセスは“Threshold Slope”パラダイムにもとづく侵食モデル,つまり岩盤河川の下刻速度が流域の削剥速度を律するモデルによって説明できる可能性が高いことを示唆する.すなわち,集水域における土砂生産速度と集水域面積(≒河川流量)が扇状地の扇面勾配にあらわれていると解釈できる.引用文献:Whipple et al., 1998. Journal of Geology 106. Burbank et al., 1996. Nature 379. DiBiase et al., EPSL 289. Wobus et al., 2006. GSA Spec. Pap. 398. Perron and Royden, 2013. EPSL 38.
3 0 0 0 OA 不感症と早漏の素人療法
3 0 0 0 OA 主観的な睡眠の質と身体活動および心理的適応との関連
- 著者
- 荒井 弘和 中村 友浩 木内 敦詞 浦井 良太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.7, pp.667-676, 2006-07-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4
本研究の目的は,主観的に評価された睡眠の質と,身体活動および心理的適応(不安・抑うつ)との関連を検討することであつた.本研究の対象者は,夜間部に通う大学1年生の男子186名であつた.測定尺度にはPittsburgh Sleep Quality Indexの日本語版(PSQI-J),身体活動評価表(PAAS),Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)日本語版を用いた.本研究は,横断的研究デザインであつた.相関分析の結果,運動や日常身体活動を行つていない者ほど,睡眠時間が長く,眠剤を使用していた.また,日常身体活動を行つている者ほど,睡眠困難や日中覚醒困難を感じていないことが明らかになった.次に,階層的重回帰分析を行つた結果,運動の実施はPSQI得点を予測していなかつたが,日常身体活動の実施は睡眠時間,睡眠効率,睡眠困難,および日中覚醒困難を予測することが明らかになつた.結論として,本研究は,身体活動が主観的な睡眠の質と部分的に関運することを支持した.
3 0 0 0 IR 石ノ森章太郎の運動表現/加速と停滞、二つのモード
- 著者
- 山本 忠宏 大塚 英志 橋本 英治 泉 政文 Tadahiro YAMAMOTO Eiji OHTSUKA Eiji HASHIMOTO Masafumi IZUMI
- 出版者
- 神戸芸術工科大学
- 雑誌
- 芸術工学2012
- 巻号頁・発行日
- 2013-11-25
本研究では、石ノ森章太郎のまんが作品を対象として、写真や映画における運動表現を対置しながら石ノ森章太郎の運動表現の分析を行うことを目的とする。分析対象としては、1971 年に『少年マガジン』において、TV シリーズとのタイアップで1 年間連載された『仮面ライダー』を取り上げる。石ノ森章太郎はこの作品の直前に『ジュン』(1967)や「神々との戦い編」『サイボーグ009』(1969)において実験的な表現を行っている。そこには、特定の主人公に感情移入させる物語を語ることに縛られない表現が見受けられ、その方法は『仮面ライダー』の運動表現において「加速と停滞」という役割として顕著に見られる。石ノ森章太郎の運動表現における「加速と停滞」という要素を検証しながら、物語を語ることと共に作品内において二つのモードの形成について考察する。This study analyzes the motion representation of Shotaro Ishinomori comic works, comparing the motion representation in photography and early film. The analysis object is "Kamen Rider"(1971) was serialized in "Shonen Magazine" tie-up with the TV series. Ishinomori have done an experimental representation just before, in "Jun"(1967), "Kamigamitonotatakai-hen" of "Cyborg 009"(1969). This representation is not related storytelling and the factor of stagnation and acceleration in the motion representation of "Kamen Rider".We consider the two modes of the storytelling and the motion representation, analyzing the factor of stagnation and acceleration in the motion representation of Shotaro Ishinomori.
3 0 0 0 OA 戦後沖縄の米兵向けバーに関する研究-女性従業員の生活史を中心に-
- 著者
- 鈴木 亘
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.13, 2017 (Released:2019-01-02)
One of Jacques Rancière’s contributions to aesthetics is his re-reading of the history of aesthetics. Rancière refers to the regime that has identified art as “art” since the end of the 18th century as “the aesthetic regime of art.” Against the short divisions of art history by modernism or postmodernism, he seeks to describe the long term. For Rancière, ideas of “modernism” and “postmodernism” need critique because the two cannot treat general transformations in the aesthetic regime of art. We will explain how his thinking can renew the discourses of modernism and postmodernism. This essay first examines the pre-existing modernist and postmodernist thinking that Rancière criticizes. It then deals with his view of the history of art history by reading Le partage du sensible. This reading aims to emphasize the work’s originality with regard to modernist and postmodernist thinking. We finally investigate his analysis of political art in Malaise dans l’esthétique, whose arguments offer us a new point of view fot reconsidering contemporary political art. We conclude this essay by stating that Rancière recognizes the political effectiveness of the “mixtures” of the heterogeneous that fundamentally characterize the aesthetic regime.
- 著者
- 中川 拓也 井上 さゆり 横畑 泰志 佐々木 浩 青井 俊樹 織田 銑一
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.13-20, 2012 (Released:2012-08-23)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 1 1
日本の中央部および西部で1982~2002年に収集された70頭のニホンイタチ(Mustela itatsi)および12頭のタイリクイタチ(M. sibirica)の寄生蠕虫類を調査した。吸虫1種(浅田棘口吸虫Isthmiophora hortensis(Asada, 1926)),線虫3種(日本顎口虫Gnathostoma nipponicum Yamaguti, 1941,Sobolyphyme baturini Petrow, 1930および腎虫 Dioctophyme renale(Goeze 1782))がそれぞれ岐阜および愛知県,兵庫県,石川および福井県および京都府,兵庫県産のニホンイタチから得られた。 鉤頭虫の1種,イタチ鉤頭虫 Centrorhynchus itatsinis Fukui, 1929が東京都および静岡,石川,福井,岐阜,三重,滋賀および鹿児島の各県産のニホンイタチおよび三重および滋賀県産のタイリクイタチから検出された。今回のS. baturiniの検出は,本種のニホンイタチからの,また中部および西日本からの初記録となった。他の種については新しい産地の報告となった。
- 著者
- ミラー ラッシュ・G ショットランダー ブライアン ジョーダン ジェイ 平原 禎子 廣瀬 絵里子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.33-39, 2012
紀伊國屋書店では,2007年より毎年海外から講師を招致し,大学図書館経営層の方々を対象とした国際ラウンドテーブルを開催している。5回目となる2011年はその規模を拡大し,OCLCとの共催で,広く図書館関係者に向けたセミナーを催すこととなった。ピッツバーグ大学図書館長のRush G.Miller氏,カリフォルニア大学サンディエゴ校図書館長のBrian E.C.Shottlaender氏,そしてOCLC会長兼CEOのJay Jordan氏を講師にお迎えし,早稲田大学図書館の後援を得て,同大学大隈記念講堂にて講師3名の講演およびパネルディスカッションが行われた。本稿は,講師3名の講演内容をそれぞれ和訳し要約したものである。
3 0 0 0 OA 根から分泌される有機酸と土壌の相互作用
- 著者
- 平舘 俊太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.454-459, 1999-07-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA 日本在来馬のミトコンドリアDNA多型
- 著者
- 川嶋 舟 颯田 葉子 Schu Kawashima Yoko Satta
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.211-213,
日本在来馬8馬種(北海道和種馬,木曽馬,野間馬,対州馬,御崎馬,トカラ馬,宮古馬,与那国馬)のミトコンドリアDNAコントロール領域の多型解析を行なった。その結果,8馬種で14ハプロタイプが認められた。系統樹解析の結果,14ハプロタイプ間に明確な遺伝的差異は認められず,日本在来馬の単一起源説を支持するものであった。各馬種のハプロタイプ構成を比較した結果,遺伝的多様性が維持されている馬種や失いつつある馬種の存在が明らかとなった。また,8馬種は互いに明確に異なるハプロタイプ構成を保有することが明らかとなった。これは,各飼養地域内で長期間維持されてきたため,各馬種で固有のハプロタイプ構成を持つに至ったと考えられた。
3 0 0 0 OA ソーシャル・メディアと集合的沸騰
- 著者
- 遠藤 薫
- 出版者
- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)
- 雑誌
- 横幹連合コンファレンス予稿集 第3回横幹連合コンファレンス
- 巻号頁・発行日
- pp.72, 2009 (Released:2010-04-05)
This paper makes clear differences between the fads in former times and the internet fads mediated by social media today. Then, it points out that various fads or collective effervescences have been triggers of big social changes, or rather the triggers of social formation. Finally, it discusses that in today's world, which can be called as "inter-media" society because multi-layered media including social media are embedded, collective effervescences are easy to be caused.
3 0 0 0 OA アメリカの著名な食行動心理学研究者の論文撤回事件および辞職事件と研究倫理
- 著者
- 林 昭志
- 出版者
- 上田女子短期大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:21883114)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.7-19, 2021-01-31
本研究ではアメリカで著名な研究者ブライアン・ワンシンク博士(Dr. Brian Wansink)の論文撤回と大学辞職事件を解説した。ワンシンク氏はイグノーベル賞を授賞したり、アメリカ政府の栄養政策のトップに就いたり、メディアに数多く出演するなど著名な食心理学研究者だった。しかし論文の記述の誤り、不適切な分析方法、不適切なオーサーシップなどだけではなく、ローデータの有無・保管が問題とされて、一流ジャーナルの論文撤回が決定的な原因となり辞職した。この事件はアメリカでは注目されたが日本では注目されなかった。最後に研究不正防止・研究倫理のために必要な内容を考察した。
3 0 0 0 OA 心肥大と心拡張―その形態について
- 著者
- 金井 孝夫
- 出版者
- 日本獣医循環器学会
- 雑誌
- 動物の循環器 (ISSN:09106537)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.39-42, 1996 (Released:2009-09-17)
- 著者
- 長田 枝利香 三谷 麻里絵 江原 和美 本田 尭 荒木 耕生 後藤 正之 楢林 敦 津村 由紀 安藏 慎 番場 正博
- 出版者
- 金原出版
- 巻号頁・発行日
- pp.405-408, 2016-04-01
症例は5歳女児で、26日前にインフルエンザワクチン2回目を接種、14日前に日本脳炎ワクチンを追加接種した。右下腿前面に紫斑が出現し、翌日は左下腿前面と体幹に紫斑が拡大した。血液検査で血小板数は6000/μLと減少、他の2血球系は正常値であった。凝固系に異常はなかった。PaIgGは軽度上昇を認めた。骨髄像は正形成、巨核球数・赤芽球・顆粒球の数と形態は正常であった。血小板数は、翌日には2000/μLまで低下を認め、はじめて口腔粘膜出血を認めた。免疫性血小板減少症(ITP)の診断で、大量免疫グロブリンを投与した。血小板数は速やかに改善を認め、粘膜出血と紫斑の消失を確認した。その後も重篤な出血症状の合併はなく、入院9日目に退院した。退院後、外来で通院し、半年後の血小板数は17万/μLを維持している。