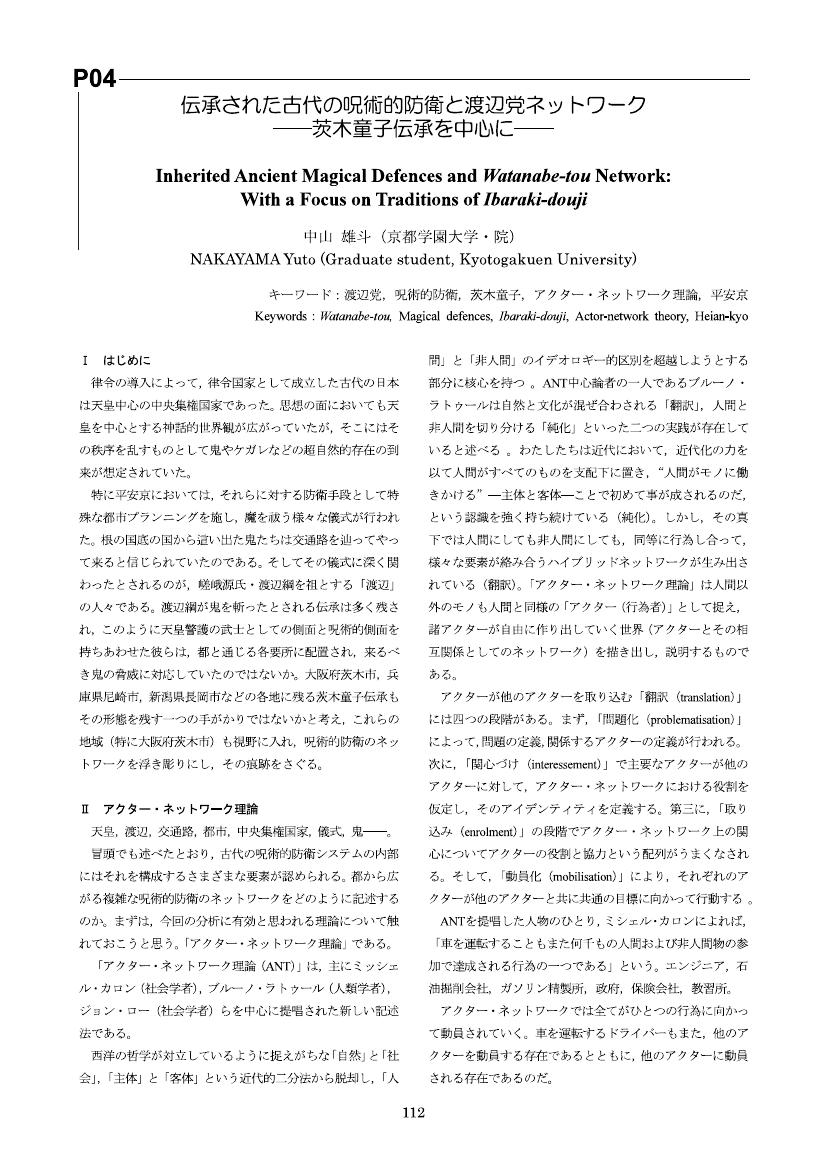- 著者
- 細井 浩一 中村 彰憲
- 出版者
- 立命館大学映像学会
- 雑誌
- 立命館映像学 (ISSN:18829074)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.123-146, 2023-03
- 著者
- 原田 春美 小西 美智子 寺岡 佐和 浦 光博
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.72-83, 2009 (Released:2009-08-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 3
本研究の目的は,支援という枠組みにおける保健師と精神障害者や彼らにとっての重要他者との相互作用について,保健師が用いた人間関係形成の方法に焦点をあて,その特徴とプロセスを明らかにすることであった。対象は市町村に所属する保健師12名であった。データ収集は半構成的面接法を用いた。分析は,面接内容の逐語録をデータとし,Modified Grounded Theory Approachを用いて質的・帰納的に行った。分析の結果抽出された29の概念から,【温かで人間的な関係の結び方】【冷静で客観的な関係の結び方】【他者との関係の取り持ち方】【適切な心的距離で関係を維持する方法】という4つのカテゴリが生成された。支援場面における相互作用は,保健師が精神障害者と良好な関係を形成し,その関係が途絶えることの無いように適度な距離を保ちながら,さらに精神障害者と彼らを取り巻く地域の人々との関係形成とその維持を支援しようとするプロセスであった。同時に,その関係性の中で,個々の精神障害者のための支援の仕組みを作り,精神障害者が主体的にその仕組みを活用しながら地域で暮らし続けることを目指すものであった。
2 0 0 0 惑星アエロブレーキ基礎技術の研究
惑星探査機の搭載機器能力を大きく向上させる方式として、惑星周回軌道に投入する際にアエロブレーキを用いることを目的とし、その基本技術として、地球周回軌道で小型人工衛星を用いた実証をすること、水素を主成分とする惑星大気の力学を極めることを柱として研究を行ってきた。最終年度には、地球周回実証機の打ち上げ機会が得られなかったので、フライトモデルにプログラム書き換え機能を付与すること、ユニットの統合などによる軽量化を計ることなどの高機能化を行った。非火薬分離機構の研究では、切り離し実験を進め、実用システムとしての可能性を見出した。釣竿を利用した伸展ロッドは環境試験を実施して実用の確認をした。姿勢・軌道の制御ではテザーの運動を利用して効果的な軌道制御を実現する理論を確立した。気体力学では、水素極超音速希薄流の解析を行い、水素分子の回転緩和、振動緩和、解離反応を考慮し、木星大気を対象としたエアロキャプチャーが実現できる見通しを得た。実験的にはデトネーション駆動型イクスパンションチューブを用いて水素極超音速流の発生を試み、8km/sを達成した。また、炭素系アブレータをアーク加熱空気流に曝し、分光分析によりCN Violet、C_2 SWANバンドをアブレータの上流側で観測し、スポーレーションの発生を確認した。さらに、惑星大気に突入したときの強い衝撃波を含む非定常大規模乱流を解明するため、精度向上を達成できるLES/RANSハイブリッド乱流モデルを検討し、新たなモデル表式を確立した。
2 0 0 0 OA インターネットから“抜け出せない”うつと不安をかかえる大学生の事例
- 著者
- 小林 絵理子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.206-207, 2017-09-30 (Released:2017-10-31)
- 著者
- 鈴木 健介 原田 諭 須賀 涼太郎 土肥 莉里香 中澤 真弓 小川 理郎 横田 裕行
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅救急医学会
- 雑誌
- 日本在宅救急医学会誌 (ISSN:2436066X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.21-24, 2022-03-31 (Released:2022-07-03)
- 参考文献数
- 8
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年5月からMicrosoft Teamsを活用し、チャンネル機能を活用し8~10名に1名の教員を配置した遠隔実習を行った。同年8月から、補講という位置づけで対面実習を行った。50~100名教室に8~10名の学生、1名の教員を配置し、シミュレーター人形を用いて実習を行った。感染対策として、2週間前からの行動記録と体温管理、当日の検温、手袋、ゴーグル、不織布マスク、アルコール消毒液、大型扇風機による換気、高濃度次亜塩素酸水による機材の消毒を行った。検温にて体温が高い場合は、医療機関受診を促し、PCR検査等陽性の場合は、積極的疫学調査を独自で行い濃厚接触者を1時間以内に特定できるようにした。同年9月より、後学期の講義や実習が開始され、各学年週に1回は対面で実習ができる教育環境が構築できた。 2021年4月から、前述した感染対策に加えて、CO2濃度を測定した。「CO2が800ppmを超えたら強制的に換気を行う」を感染対策に加えた。同年6月下旬より職域接種を行った。実習では、virtual reality(以下、VR)視聴とシミュレーション実習を行うだけでなく、学生の目線と定点の2つのカメラで撮影し、映像を用いたフィードバックを実践した。2022年1月からオミクロン株による第6波の影響により、積極的疫学調査による早期隔離、濃厚接触者と感染経路の特定を行った。 コロナ禍において、新型コロナウイルス感染対策に関する最新の医学的知識を学び、感染対策を教職員が学生と一丸となって実施した結果、VRを用いたシミュレーション教育が実施できた。
2 0 0 0 梶井基次郎「ある心の風景」論--<想念>と<現実>
- 著者
- 石谷 春樹
- 出版者
- 皇学館大学人文学会
- 雑誌
- 皇学館論叢 (ISSN:02870347)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.p48-66, 1995-04
2 0 0 0 OA 『ハリー・ポッター』におけるクィディッチ : 学校物語のスポーツについての一考察
- 著者
- 桑野 久子
- 雑誌
- 流通経済大学スポーツ健康科学部紀要 = The journal of Ryutsu Keizai University, the Faculty of Health & Sport Science
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.59-74, 2017-03-10
2 0 0 0 OA 後鳥羽院筆「熊野懐紙」の字母について
- 著者
- 吉田 智美
- 出版者
- 日本大学大学院文学研究科国文学専攻
- 雑誌
- 日本大学大学院国文学専攻論集 (ISSN:02863464)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.70-91, 2013-09-30 (Released:2022-11-24)
2 0 0 0 遡行する身体 : 『痴人の愛』の文化批判
- 著者
- 柴田 勝二
- 出版者
- 東京外国語大学
- 雑誌
- 東京外国語大学論集 (ISSN:04934342)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.[150]-135, 2003
- 著者
- Naoya Masumori Mikiya Nakatsuka
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-23-0021, (Released:2023-03-28)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 10
Gender-affirming hormone treatment generally by cross-sex hormones is an important strategy for transgender people to achieve the physical features affirming their experienced gender. Estrogens and androgens are administrated, usually for a long time, to transgender women and transgender men who would like to physically achieve feminization and masculinization, respectively. Several harmful adverse events have been reported in the literature following the administration of gender-affirming hormones, including worsening of lipid profiles and cardiovascular events (CVE) such as venous thromboembolism, stroke, and myocardial infarction, but it remains unknown whether the administration of cross-sex hormones to transgender people increases the subsequent risk of CVE and death. Based on the findings of the present narrative review of the recent literature, including meta-analyses and relatively large-scale cohort studies, it is likely that estrogen administration increases the risk of CVE in transgender women, but it remains inconclusive as to whether androgen administration increases the risk of CVE in transgender men. Thus, definitive evidence guaranteeing the long-term safety of cross-sex hormone treatment on the cardiovascular system is insufficient because of lack of evidence from well-organized, high-quality, and large-scale studies. In this situation, as well as considering the proper use of cross-sex hormones, pretreatment screening, regular medical monitoring, and appropriate intervention for risk factors of CVE are necessary to maintain and improve the health of transgender people.
- 著者
- 石垣 智也 尾川 達也 宮下 敏紀 平田 康介 岸田 和也 知花 朝恒 篠宮 健 市川 雄基 竹村 真樹 松本 大輔
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.261-270, 2021 (Released:2021-06-18)
- 参考文献数
- 24
【目的】在宅環境での2 ステップテストの信頼性と妥当性の検討を行い,歩行自立の基準値を見出すこと。【方法】訪問リハビリテーション利用者を対象とした横断調査のデータベース(10 施設226 名)から,目的別にデータを抽出した(信頼性98 名,妥当性117 名,基準値209 名)。調査項目は基本情報と膝伸展筋力,歩行能力として2 ステップテストによる2 ステップ値や歩行自立度などとした。歩行手段と距離により屋内杖歩行から屋外独歩800 m 以上と12 種の歩行自立条件を設定し,各自立を判別するカットオフ値を検討した。【結果】2 ステップテストの検者内信頼性は良好であり,固定誤差は認めないが比例誤差が示された。2 ステップ値は膝伸展筋力より歩行能力との相関係数が高く,歩行自立条件に応じた段階的なカットオフ値が設定できた。【結論】2 ステップテストは在宅環境でも信頼性と妥当性があり,歩行自立に対する基準値を有する歩行能力評価である。
- 著者
- Shinji Fujii Nobuhira Kurosaki
- 出版者
- The Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.1, pp.17-27, 2023-02-28 (Released:2023-03-15)
Carex planata has been treated as comprising three varieties: var. planata, var. angustealata, and var. remotiuscula. To evaluate this treatment, characteristics of the inflorescences, spikes, utricles, and achenes of both herbarium specimens and growing plants in the field were examined. Principal component analysis (PCA) revealed two distinct groups within C. planata, one of which was identical to var. angustealata and the other to var. planata; var. remotiuscula could not be distinguished from var. planata. Variety remotiuscula was confirmed to be a synonym of var. planata. Variety angustealata of western Japan grows in flood plains along rivers. The results from PCA and information from distribution and habitat led to the conclusion that var. angustealata should be treated as a distinct species: C. angustealata, characterized by ascendant utricles and a greater number of spikes (≥ 9) on well-grown plants. Smaller achenes in proportion to the utricles also distinguish C. angustealata from C. planata. Detailed descriptions of both C. angustealata and C. planata based on the numerical survey are presented. Lectotypes of var. angustealata Akiyama and var. remotiuscula Akiyama are designated.
2 0 0 0 OA 伝承された古代の呪術的防衛と渡辺党ネットワーク ー茨木童子伝承を中心にー
- 著者
- 中山 雄斗
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2018年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.112-113, 2018 (Released:2020-06-13)
2 0 0 0 「現在」という水源--永井荷風『すみだ川』私論
- 著者
- 中村 良衛
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.56-69, 1999-05
2 0 0 0 OA ストーカー対応の現状と課題 司法臨床の展開(第五報)
2 0 0 0 OA 野菜のブランチングに関する資料紹介
- 著者
- P.J. VELASCO J.R. WHITAKER A. CHEN J.R. HITAKER
- 出版者
- 日本食品保蔵科学会
- 雑誌
- 食品と低温 (ISSN:02851385)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2-3, pp.85-92, 1982-09-25 (Released:2011-05-20)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
ブランチングは野菜凍結の重要な前処理工程となっているが, これについての基礎的知識はまだ十分でないように思われる。今回これに関する次の3つの資料を訳出紹介する。(1) パーオキシダーゼ-その熱変性と再生について-(2) 食品中のカタラーゼ(3) 野菜ブランチングの必要性アメリカ冷凍食品協会 (AFFI) では, カリフォルニア大学デイビス分校 (U.C.D.) のJ.WHITAKER博士らに, 1980年9月来野菜のブランチングについて研究を委託している。その目的は, この問題に関与する酵素系についての知識を深め, 不活性化にもっとも適した方法を開発し, また酵素再活性化の重要さを知ることにあるという。ここに訳出した資料中, (1) および (2) は上記プロジェクトの一環としてAFFIに提出された報告である。また (3) は, 野菜のノーブランチング凍結について, かつてQ.F.F.誌上に解説されたもので, 興味ある関係資料として併せて要点を訳出したものである。大方の参考になれば幸いである。
2 0 0 0 OA 深海からのメタンハイドレート回収技術
- 著者
- 松隈 洋介 濱口 涼吉 峯元 雅樹
- 出版者
- 日本混相流学会
- 雑誌
- 混相流 (ISSN:09142843)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.398-406, 2022-12-15 (Released:2023-01-13)
- 参考文献数
- 4
A system for recovery of methane hydrate from the deep ocean floor has not been established. As one possible recovery system, a gas-lift system was investigated. Experiments were performed with a gas-lift system of 5 m height and 100 mm in diameter to determine the relationship between injected gas quantity and pumped water quantity. Vertical flow in the gas-lift pipe was calculated with a compressible one-dimensional two-fluid model to analyze flow in the recovery pipe of methane hydrate from the deep ocean floor. Basic equations were mass conservation equations and momentum conservation equations of each phase, the relation of volume fractions and the state equation of the gas phase. The calculation showed that optimal gas injection depths exist. Thus, the gas-lift system can be economically effective the recovery of methane hydrate from the deep ocean floor.
2 0 0 0 OA 19世紀アメリカ西部河川輸送に関する一考察
- 著者
- 加勢田 博
- 出版者
- 關西大学經済學會
- 雑誌
- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.17-31, 2002-06-01
19世紀のアメリカにおける交通・輸送の発展は、世紀前半においては、河川や運河の航行改良によって、また世紀後半には鉄道によって、工業成長に伴う著しい輸送需要の増大に対応することができた。本論文では、河川輸送が鉄道時代の到来とともにその役割をどのように変化させていったのかを概観する。