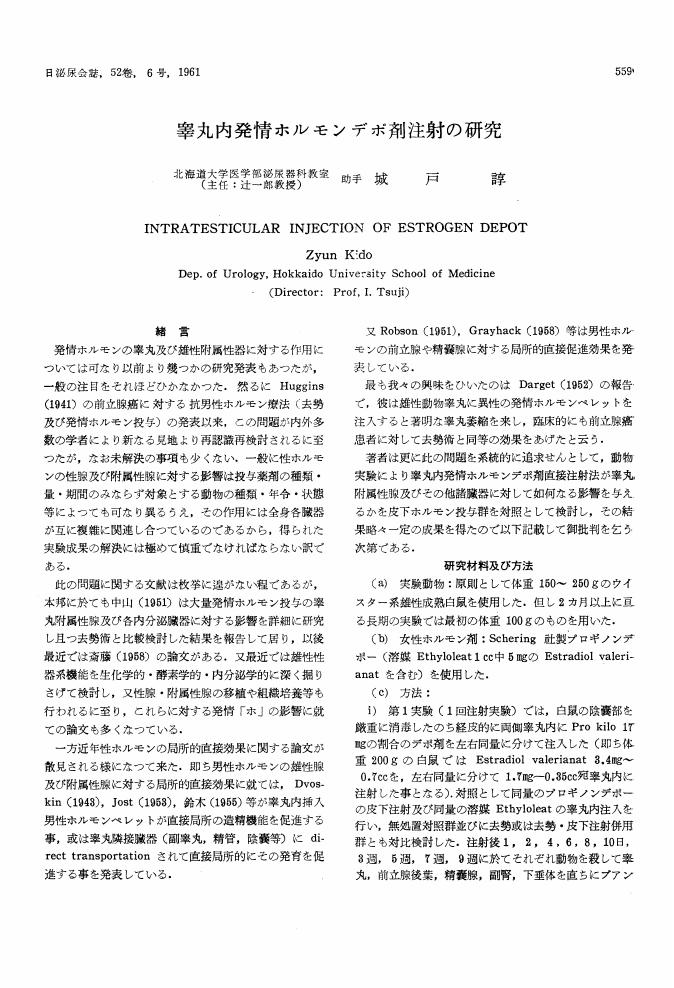2 0 0 0 OA ヘビの神経毒
- 著者
- 林 恭三
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.12, pp.817-820, 1973-12-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 食物連鎖による魚貝類の毒化
- 著者
- 橋本 芳郎 神谷 久男
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.425-434, 1970-04-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 2 5
- 著者
- 森 修一 石井 則久
- 出版者
- 日本ハンセン病学会
- 雑誌
- 日本ハンセン病学会雑誌 (ISSN:13423681)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1, pp.69-90, 2017 (Released:2017-08-18)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1
日本のハンセン病政策は1907年の 「癩 (らい) 予防ニ関スル件」 の施行に始まるが、患者隔離は1909年の連合府県立 (国立) ハンセン病療養所 (以下、療養所) の開設からであった。本政策は1996年の 「らい予防法」 廃止まで継続され、約35,000人 (実数、推測値) が隔離を受けたが、その入退所動向の全容は未だ明らかではない。本研究では国立療養所の入退所動向を解析し、日本のハンセン病政策の実態を明らかとすることを目的とし、1909年から2010年まで102年間の入退所者数とその内訳を各国立療養所の年報や内部資料を収集し、内容を検討し、項目などを統一した上で、年次ごと、ハンセン病に関するそれぞれの法律の施行されている期間ごとにその内訳を集計した。その結果、102年間の総入所者数 (入所、再入所、転入を延べ数として集計した) 56,575人、総退所者数 (転所、軽快退所、自己退所、ハンセン病でない、その他を延べ数として集計し、死亡者数を加えた数) 54,047人 (死亡 : 25,200人、転所 : 4,350人、軽快退所 : 7,124人、自己退所 : 12,378人、ハンセン病でない : 310人、その他 : 4,685人) であった。法律ごとの内訳は、 「癩予防ニ関スル件」 (1907年―1931年) では総入所者数12,673人、総退所者数9,070人 (死亡 : 3,496人、転所 : 197人、軽快退所 : 79人、自己退所 : 4,824人、ハンセン病でない : 55人、その他 : 419人) 、 「癩予防法」 (1931年―1953年) では総入所者数31,232人、総退所者数23,354人 (死亡 : 11,559人、転所 : 488人、軽快退所 : 2,087人、自己退所 : 5,848人、ハンセン病でない : 247人、その他 : 3,125人)、 「らい予防法」 (1953年―1996年) では総入所者数12,098人、総退所者数18,159人 (死亡 : 7,654人、転所 : 3,450人、軽快退所 : 4,412人、自己退所 : 1,558人、ハンセン病でない : 8人、その他 : 1,077人)、 「らい予防法廃止に関する法律」 (1996年―2009年) では総入所者数572人、総退所者数3,464人 (死亡 : 2,491人、転所 : 215人、軽快退所 : 546人、自己退所 : 148人、ハンセン病でない : 0人、その他 : 64人) であった。今回の研究から日本の隔離政策下での入退所動向の全容がはじめて明らかとなった。
- 著者
- 中井 悠貴
- 出版者
- 立命館大学人文科学研究所
- 雑誌
- 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, pp.175-207, 2022-12
2 0 0 0 IR 吉原における客の身分 : 遊女評判記を中心に
- 著者
- 高木 まどか
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 常民文化 = Jomin bunka (ISSN:03888908)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.180-154, 2015-03
This study examines the discourse that visitors' social position did not make sense in Yoshiwara of Edo, using Yujo hyoban-ki, which is one of the classifications of a story book Kanazoshi, in this paper. In the Edo period, there were some districts of licensed brothels, such as Shinmachi in Osaka, Shimabara in Kyoto, and Yoshiwara in Edo. Previous studies often explained that these brothel districts were places beyond the social order that visitors' social statuses did not make sense. Although there were also some positions contrary to such explanation, the dispute in a scientific meaning has not arisen between different positions. Moreover, each dispute does not show clear basis and is not necessarily an empirical discussion. In this paper, I focus on the difference in positions and the insufficient demonstration in such previous studies. Then, I'll consider why the opinions about the treatment of a visitor's status in brothel districts are divided, and how the visitor's status was in fact treated in brothels. In considering these, I use Yujo hyo-banki, which is one of the classifications of Kanazoshi, as the primary historical sources. Although Yujo hyo-banki is a document which describes the reputation of each prostitute, there are some description of visitors' aspects finely, which observe visitors' actual conditions in brothels. In this paper, I verify how visitors' social positions in brothel districts are treated, by mainly focusing on Yoshiwara from the second half of the 17th century to the middle of the 18th century, when many description about visitors to the brothels are seen in Yujo hyo-banki.This study examines the discourse that visitors' social position did not make sense in Yoshiwara of Edo, using Yujo hyoban-ki, which is one of the classifications of a story book Kanazoshi, in this paper. In the Edo period, there were some districts of licensed brothels, such as Shinmachi in Osaka, Shimabara in Kyoto, and Yoshiwara in Edo. Previous studies often explained that these brothel districts were places beyond the social order that visitors' social statuses did not make sense. Although there were also some positions contrary to such explanation, the dispute in a scientific meaning has not arisen between different positions. Moreover, each dispute does not show clear basis and is not necessarily an empirical discussion. In this paper, I focus on the difference in positions and the insufficient demonstration in such previous studies. Then, I'll consider why the opinions about the treatment of a visitor's status in brothel districts are divided, and how the visitor's status was in fact treated in brothels. In considering these, I use Yujo hyo-banki, which is one of the classifications of Kanazoshi, as the primary historical sources. Although Yujo hyo-banki is a document which describes the reputation of each prostitute, there are some description of visitors' aspects finely, which observe visitors' actual conditions in brothels. In this paper, I verify how visitors' social positions in brothel districts are treated, by mainly focusing on Yoshiwara from the second half of the 17th century to the middle of the 18th century, when many description about visitors to the brothels are seen in Yujo hyo-banki.
2 0 0 0 OA 2)パーキンソン病の治療:過去・現在・未来
- 著者
- 服部 信孝 常深 泰司
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.9, pp.1923-1929, 2017-09-10 (Released:2018-09-10)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 江戸時代後期の『鳥獣図』に描かれたペンギン図
- 著者
- 福田 道雄
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.91-95, 2020-04-23 (Released:2020-05-16)
- 参考文献数
- 32
日本では,現在非常に多数のペンギンが飼育されている.このような状態になった理由を解明するため,ペンギンの渡来史を調べた.『禽譜』によれば,ペンギンの全身と部分の皮が,江戸時代の享保年間(1716–1736)と1821年に渡来し,どちらの種もキングペンギンAptenodytes patagonicusであった.筆者は,貴志孫太夫が転写したと考えられる『鳥獣図』に描かれたフンボルトペンギンSpheniscus humboldtiの図を見つけた.そして,その原図で写生されたフンボルトペンギン標本の渡来時期は,貴志忠美が没した1857年以前と推定できた.
2 0 0 0 OA <ニュー・ジャーマン・シネマ>とは何だったか
- 著者
- 瀬川 裕司
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国立大学人文紀要. 第二類, 語学・文学 (ISSN:0513563X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.155-168, 1992-10-30
2 0 0 0 OA 睾丸内発情ホルモンデポ剤注射の研究
- 著者
- 城戸 諄
- 出版者
- 社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.6, pp.559-580, 1961-06-20 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 82
2 0 0 0 OA 環太平洋連帯構想の展開とPECCの設立 : 外相大来佐武郎の役割に焦点を当てて
- 著者
- 井本 将来 Masaki Inomoto
- 出版者
- 同志社法學會
- 雑誌
- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.6, pp.2221-2271, 2022-11-30
研究ノート(Note)
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1945年05月22日, 1945-05-22
2 0 0 0 栃木県教育史
- 著者
- 栃木県教育史編さん委員会編
- 出版者
- 栃木県連合教育会
- 巻号頁・発行日
- 1990
2 0 0 0 OA 火山フロントと梢深発地震活動(第2報) : 関東および北海道
- 著者
- 吉田 明夫 細野 耕司
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.727-738, 2003-01-08 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 28
We investigated how the intermediate-depth seismicity changes with depth in the Pacific slab beneath Hokhaido and the Kanto district using JMA data since Oct. 1997. We found that seismicity in the upper seismic plane decreases noticeably at about the depth of 100 km and on its deeper side both in Hokkaido and the Kanto district. In Hokkaido the volcanic front is located nearly above the line where the seismicity in the upper seismic plane starts to decrease (the D line). This feature is the same as that seen in the Tohoku district (Hosono and Yoshida, 200la). In the Kanto region, however, the D line is located several tens km to the east of the volcanic front, the cause of which may be attributed to the subduction of the Philippine Sea plate above the Pacific plate. We think the noticeable decrease of seismicity in the upper seismic plane at about the depth of 100 km which is commonly observed in the Pacific slab beneath Japan and the correspondence between the location of the D Iine and the volcanic front in Hokkaido and the Tohoku district indicate that the decrease of seismicity in the upper seismic plane may be related to the genetic process of magmatic bodies in the subduction zone.
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1945年03月06日, 1945-03-06
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1941年11月22日, 1941-11-22
2 0 0 0 OA 擬似的に小胸筋短縮位にした状態が呼吸時の肋骨移動に及ぼす影響
- 著者
- 田野 聡 鶯 春夫 高岡 克宜 松村 幸治 田岡 祐二
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.Da0983, 2012 (Released:2012-08-10)
【目的】 小胸筋は,第2~5肋骨前面から起こり肩甲骨烏口突起に停止する。筋機能としては,肩甲骨の前傾,下方回旋の他に,吸気補助筋としての作用もある。臨床現場では,姿勢不良や肩こり,また呼吸器疾患においても,小胸筋の短縮または過緊張が認められる場合がある。このことから小胸筋の短縮が,肋骨の位置に影響を及ぼす可能性があると考えられる。そこで本研究では,擬似的に小胸筋短縮位にした状態(以下,小胸筋短縮位)での呼吸時の肋骨の動態を,超音波画像を用いて検討することを目的とした。【方法】 対象は,健常男性13名(年齢25.9±5.1歳)とした。超音波画像は,超音波画像診断装置(東芝,SSA-660A)とリニアプローブ(東芝,PLT-704AT,7.5MHz)を用い,Bモード法により表示した。リニアプローブは,右第4肋骨を標識とし乳頭ライン上に縦方向に置いた。測定肢位は座位で,上肢下垂位を基準肢位(以下,基準肢位)とし,小胸筋短縮位は自動運動にて肩関節を伸展,内転,内旋させることにより,肩甲骨前傾位とした。測定1:基準肢位と小胸筋短縮位での,肋骨の位置の相違をみる目的で,安静呼吸の吸気時と呼気時にそれぞれ分け,その位置を測定した。具体的な方法は,基準肢位における吸気時の第4肋骨の位置と,小胸筋短縮位における吸気時の第4肋骨の位置を比較した。呼気時も同様に実施した。測定2:安静呼吸の呼気時から吸気時までの肋骨の移動範囲をみる目的で,基準肢位と小胸筋短縮位で呼気時から吸気時までの第4肋骨の移動距離をそれぞれ測定した。また,その移動距離を比較検討した。測定3:深呼吸の最大呼気時から最大吸気時までの肋骨の移動範囲をみる目的で,基準肢位と小胸筋短縮位で最大呼気時から最大吸気時までの第4肋骨の移動距離をそれぞれ測定した。また,その移動距離を比較検討した。統計処理はt検定を用い,有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮,説明と同意】 対象者には,本研究の主旨および内容を説明し,同意を得てから研究を実施した。【結果】 測定1:小胸筋短縮位の吸気時では,基準肢位吸気時より頭側に5.9±2.5 mm移動した。また,小胸筋短縮位の呼気時では,基準肢位呼気時より頭側に4.4±1.8mm移動した。測定2:基準肢位での肋骨の移動距離は3.2±1.2mmであった。小胸筋短縮位での肋骨の移動距離は2.0±1.1mmであった。小胸筋短縮位は基準肢位に比べ, 肋骨の移動距離は有意に小さかった(P<0.01)。測定3:基準肢位での肋骨の移動距離は8.5±5.4mmであった。小胸筋短縮位での肋骨の移動距離は5.7±4.3mmであった。小胸筋短縮位は基準肢位に比べ, 肋骨の移動距離は有意に小さかった(P<0.05)。【考察】 今回,擬似的な小胸筋短縮位では,測定1の結果より,吸気時,呼気時ともに肋骨が挙上した。小胸筋の短縮により,胸郭と肩甲骨の位置関係に影響を与え,烏口突起に付着する小胸筋を介して,肋骨の挙上変位が起こったと考える。また,測定2,3の結果より,小胸筋短縮位では,安静呼吸時と深呼吸時ともに,肋骨の移動距離は低下した。通常,肋骨は吸気時に挙上し,呼気時には挙上位から下制する。今回,吸気時に肋骨が挙上した後,呼気時において下制の移動が少なかったことにより,肋骨移動範囲が狭くなったと考える。小胸筋は,吸気補助筋として肋骨を挙上させることにより,胸郭を拡張させるといわれている。しかし,常時,小胸筋が短縮した場合,吸気時,呼気時ともに肋骨が挙上した状態であるため,胸郭の拡張は起こりにくくなるのではないかと考える。【理学療法学研究としての意義】 小胸筋に関しては,胸郭出口症候群や不良姿勢の際に重要視されているが,呼吸に関連した報告は少ない。今回,臨床で遭遇する小胸筋の短縮に対し,呼吸の観点より,その影響を超音波画像を用いて検証した。本研究の結果により,小胸筋短縮が,肋骨挙上を引き起こし,胸郭拡張が制限されると推察された。この結果は,臨床的有用性が高く,理学療法の治療にも反映するため,本研究の意義は大きいと考える。
2 0 0 0 IR 媽祖と観音--中国母神の研究-2-
- 著者
- 平木 康平
- 出版者
- 大阪府立大学
- 雑誌
- 大阪府立大学紀要 人文・社会科学 (ISSN:04734645)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.p43-57, 1984
2 0 0 0 OA 市販DLPプロジェクターを用いた低コストマスクレス露光装置の検討
- 著者
- 馬場 岳斉 工藤 幸寛 高橋 泰樹
- 雑誌
- 2015年 第76回応用物理学会秋季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2015-07-17
2 0 0 0 OA わさびおよび加工わさび製品中の6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート含量
- 著者
- 村田 充良 宇野 みさえ 永井 陽子 中川 多世 奥西 勲
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.9, pp.477-482, 2004-09-15 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 5 7
機能性成分である6-MSITCの,各種わさび及び加工わさび製品における含量を分析した.本ワサビ5品種の6-MSITC含量を部位別に測定した結果,いずれの品種も根茎における含量が最も高く,次いで根,茎,葉の順であった.一方,西洋ワサビの6-MSITC含量は低かった.本ワサビ根茎の6-MSITC含量が最も高かった品種はみつきであり,最も含量の低かった品種との間には約1.6倍の差があった.みつきは収穫量も高く,優れた品種であることがわかった.加工わさび製品25種類の6-MSITC含量を分析した結果,メーカーや製品の種類によって,大きな差があった.6-MSITC含量には本ワサビ原料,特に根茎の配合率が大きく関与していることが明らかになった.以上のことより,食事の中で効率よく6-MSITCを摂取するためには,本ワサビ根茎を食べるのがもっとも望ましく,また,加工わさび製品でも,本ワサビ根茎が多く配合されている製品を選ぶことが重要であると考えられた.
- 著者
- 渡邊 三津子 遠藤 仁 古澤 文 藤本 悠子 石山 俊 Melih Anas 縄田 浩志
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.265, 2020 (Released:2020-03-30)
1. はじめに 近年,大野盛雄(1925〜2001年),小堀巌(1924〜2010年),片倉もとこ(1937〜2013年)など,日本の戦後から現代にいたる地理学の一時代を担った研究者らが相次いで世を去った。彼らが遺した貴重な学術資料をどのようにして保存・活用するかが課題となっている。本発表では,故片倉もとこが遺したフィールド資料の概要を紹介するとともに,彼女がサウディ・アラビアで撮影した写真の撮影場所を同定する作業を通して,対象地域の景観変化を復元する試みについて紹介する。2. 片倉もとこフィールド資料の概要 片倉が遺した研究資料は,フィールド調査写真,論文・著作物執筆に際してのアイデアや構成などを記したカード類,フィールドで収集した民族衣服,民具類など多岐にわたる。中でも,写真資料に関しては,ネガ/ポジフィルム,ブローニー版,コンタクトプリントなど約61,306シーンが確認できている(2018年12月現在)。本研究では,片倉が住み込みで調査を実施した経緯から,写真資料が最も多く,かつ論文・著作物における詳細な記述が遺されているサウディ・アラビア王国マッカ州のワーディ・ファーティマ(以下,WF)地域を対象とする。3. 片倉フィールド調査写真の撮影地点同定作業 本研究では,以下の手順で撮影地点の同定をすすめた。1) 調査前の準備(写真の整理と撮影地域の絞り込み) まず,写真資料が収められた収納ケース(箱,封筒,ファイルなど)や,マウント,紙焼き写真の裏などに書かれたメモや,著作における記述を参考に,WF地域およびその周辺で撮影されたとみられる写真の絞り込みを行った。次いで,WF地域で撮影されたとみられる写真の中から,地形やモスクなどの特徴的な地物,農夫などが写り込んでいる写真を選定し,現地調査に携行した。2) 現地調査 2018年4〜5月,2018年12月~2019年1月,2019年9月の3回実施した現地調査では,携行した写真を見せながら,現地調査協力者や片倉が調査を行った当時のことを知る住民に,聞き取り調査を行った。 次に,撮影地点ではないかと指摘された場所を訪れ,背景の山地,モスクや学校などの特徴的な地形や地物を観察するとともに,周辺の住民にさらなる聞き取りを行った。 聞き取りや現地観察を通して撮影地点が特定できた場合には,できるだけ片倉フィールド調査写真と同じ方向,同じアングルになるように写真を撮影するとともにGPSを用いて緯度・経度を記録した。なお,新しい建築物ができるなどして同じアングルでの撮影が難しい場合には,可能な限り近い場所で撮影・記録を行った。3) 現地調査後 調査後は,調査で撮影地点が同定された写真を起点として,その前後に撮影されたとみられる写真を中心に,被写体の再精査を行い,現地調査で撮影地点が同定された写真と同じ人物,建物,地形などが写り込んでいる写真を選定し,撮影同定の可能性がある写真の再選定を行った。一連の作業を繰り返すことで,片倉フィールド調査写真の撮影地点の同定をすすめた。4. 写真の撮影地点の同定作業を通した景観復元の試み 撮影地点が同定された片倉のフィールド調査写真と、現在の状況との比較,および1960年代以降に撮影・観測された衛星画像との比較を通して,およそ半世紀の間におこった変化の実情把握を試みた。例えば衛星画像からは、半世紀前にはワーディに農地が広がっていたのに対して,現在では植生が減少していることなどを読み取ることができる。一方で,集落では住宅地が拡大し,道路が整備された。このような変化の中、地上で撮影された写真からは,以下のような変化を読み取ることができる。例えば,1960年代の集落には,日干しレンガの平屋が点々とあるだけであったが,現在は焼成レンガやコンクリートを使った2階建以上の建物が増えた。一方で,集落内のどこからでも見えた山はさえぎられて見えなくなった。また,次第に電線が張り巡らされ,1980年代以降電化が進んだ。また,1960年代当時は生活用水をくむために欠かせなかった井戸は,配水車と水道の普及により次第に使われなくなった。発表では,実際の写真を紹介しながら,フィールド写真を用いた景観変化復元の試みについて紹介する。 本研究はJSPS科研費16H05658「半世紀に及ぶアラビア半島とサハラ沙漠オアシスの社会的紐帯の変化に関する実証的研究」(研究代表者:縄田浩志),国立民族学博物館「地域研究画像デジタルライブラリ事業(DiPLAS)」,大学共同利用機関法人人間文化研究機構「現代中東地域研究」秋田大学拠点の研究成果の一部である。また,アラムコ・アジア・ジャパン株式会社と片倉もとこ記念沙漠文化財団との間で締結された協賛金事業の一環として事業の一環として行われたものである。