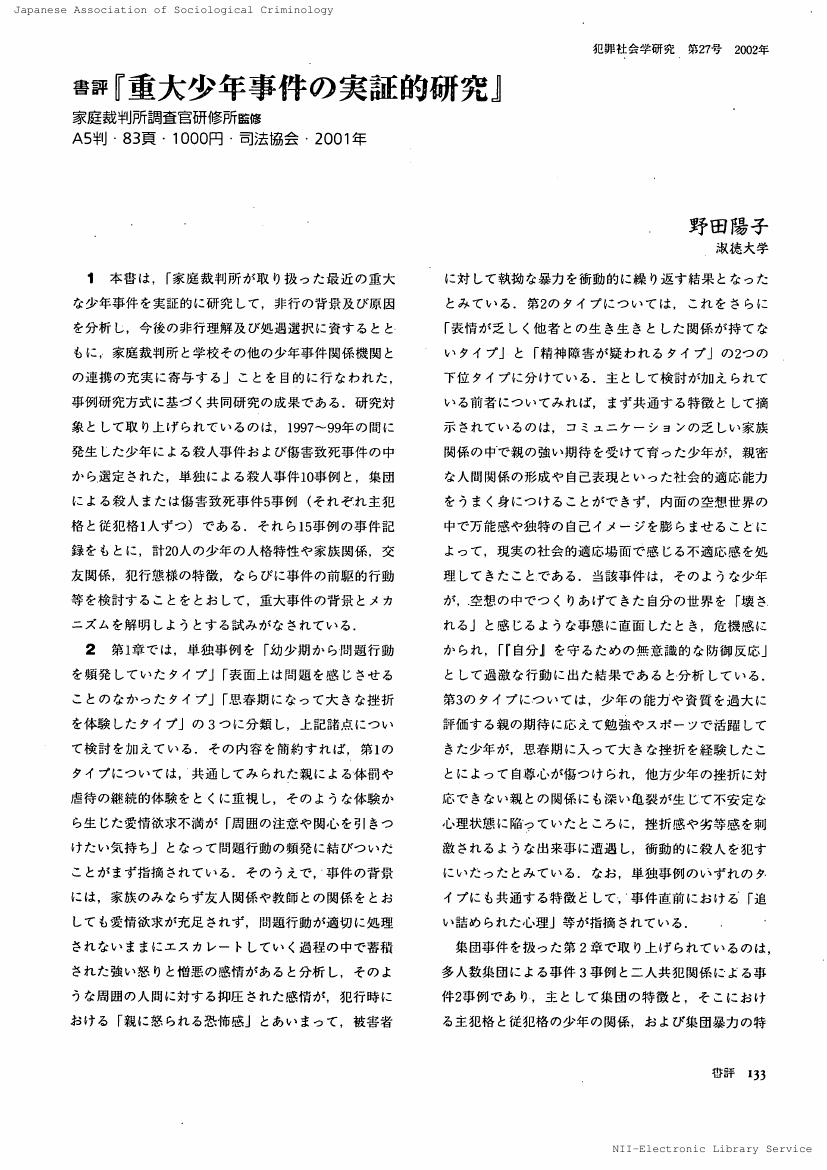2 0 0 0 OA 日本・ベルギー関係史の一断面:第一次世界大戦期における資料
- 著者
- 櫻井 良樹
- 出版者
- 麗澤大学
- 雑誌
- 麗沢大学紀要 (ISSN:02874202)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.169-178, 2009-12-20
- 著者
- 後藤 史与
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学大学院論集 (ISSN:18845428)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.169-187, 2010-03
2 0 0 0 OA 明治・大正時代における日本のベルギー認識
- 著者
- 黒沢 文貴
- 出版者
- 東京女子大学
- 雑誌
- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.85-114, 2007-09
In the Meiji period, Japan looked to Western powers for a model of modernization, and many reports on things Western were published. Some were reports by government-funded survey missions, and others were travel accounts by private individuals who had gone overseas. Regardless of the type of writing, each work reflected the image of "a model, modern nation" as seen by its author. In this essay, I will discuss several representative writings that helped shape Japanese perceptions of Belgium in the Meiji-Taisyo period.
- 著者
- 戸谷 浩
- 出版者
- 明治学院大学
- 雑誌
- 明治学院論叢 (ISSN:09189858)
- 巻号頁・発行日
- no.621, pp.27-45, 1999-01
- 著者
- 梶原 克彦
- 出版者
- 愛媛大学法学会
- 雑誌
- 愛媛法学会雑誌 (ISSN:03898571)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.41-66, 2017-08
2 0 0 0 スウェーデンにおける俳句受容
- 著者
- 児玉 千晶
- 出版者
- 北ヨーロッパ学会
- 雑誌
- 北ヨーロッパ研究 (ISSN:18802834)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.33-45, 2008
海外での俳句受容は明治初期に来日したイギリス、フランス、ドイツの外交官及び御雇外国人らによる、俳句の翻訳と解説から始まった。スウェーデンの俳句受容はアメリカでの受容より少し遅れ、1933年に初めて新聞紙上において俳句が紹介された。1999年にはスウェーデン俳句協会が設立され、季語・定型に拘らないことを基本としながらも、古典俳句を手本とし、俳句の本質を追究する姿勢で俳句集の出版、協会誌の発行、句会・講座等の活動を行っている。スウェーデン人の自然観はドイツ人などと比べ、自然に対しての共存意識や一体感があるため、自然を軸とした俳句への理解・共感を持ち易かったと思われる。また、一句の中に対立する季節の季語が同時に現われやすいのは、四季の長さがほぼ等分の日本と違って、スウェーデンでは夏と冬(光と闇) のコントラストが大きく、双方が常に人々の意識から消えないためと考えられる。
2 0 0 0 IR 世紀の終りと「黄禍」の誕生 : カイザーとその寓意画,および三国干渉
- 著者
- 飯倉 章
- 出版者
- 城西大学国際文化研究所
- 雑誌
- 国際文化研究所紀要 (ISSN:13412663)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.1-23, 1997-07
The phrase "Yellow Peril" became popular because it summed up the idea that the rise of the yellow race was a danger to the white race. It was the German Kaiser, Wilhelm II, and his cartoon that propagated the Yellow Peril idea around the world and popularized it in the Western political arena. There are, however, some misunderstandings over the Kaiser's role in the Yellow Peril. First, this essay attempts to clarify the genesis of the phrase "Yellow Peril" and its relation to the Kaiser's cartoon embodying his idea of the Yellow Peril. Although the Kaiser seems to have believed himself to be the inventor of the phrase, there is no evidence proving this. There is also no evidence that the Kaiser's cartoon was originally entitled "the Yellow Peril," although this belief has been widely held. Next, this essay considers the effect which the Kaiser's idea of the Yellow Peril had on the decision-making process of the Triple Intervention of 1895, the intervention by the three powers, Russia, Germany and France, which forced Japan to renounce the possession of the Liaotung Peninsula. As the Kaiser sent the cartoon to his cousin, Tsar Nicholas II, and propagated the Yellow Peril idea just after the intervention, it has been argued that the fear aroused by the Yellow Peril played a major role in the intervention. The fact is, however, that the Kaiser used the fear mainly as a means of justifying the intervention. Lastly, this essay examines the contemporary reaction to the cartoon. Admittedly, it caused a mild sensation in the Western political arena. However, it also became a subject of amusement. In fact, some ridiculed the cartoon as much as they did the Kaiser's idea of the Yellow Peril itself.
2 0 0 0 OA 小学校理科における水の沸騰の実験に関する教師の認識に関する一考察
- 著者
- 中山 雅茂 境 智洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.180-186, 2019 (Released:2019-07-05)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
This research focuses on an experiment in boiling water in grade 4 Japanese elementary school science class. A questionnaire answered by 111 Japanese school teachers revealed that only few teachers understood that the cooler air around the thermometer prevents it from reaching the exact boiling point of water. Teachers want the children to obtain the boiling point of water at 100°C, yet in actual experiments it is difficult to measure it precisely. In order to avoid this situation in the classroom, it is necessary for the teacher to understand the characteristics of and master the rod thermometer.
2 0 0 0 OA 草の葉
- 著者
- ワルト・ホイットマン 原著
- 出版者
- 富岳本社
- 巻号頁・発行日
- vol.[本編], 1947
2 0 0 0 OA 医療的ケアを継続しながら在宅療養へ移行した先天異常のある子どもの母親のレジリエンス
- 著者
- 山岡 愛 吾妻 知美
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.151-159, 2018 (Released:2018-11-13)
- 参考文献数
- 22
目的:医療的ケアを継続しながら在宅療養へ移行した先天異常のある子どもの母親の経験や思いから,母親のレジリエンスの一端を明らかにする.方法:在宅療養中の先天異常のある子どもの母親7人に感情浮沈図を用いて半構造化面接を行った.データは内容分析の手法を用いて分析し,母親のレジリエンスについてカテゴリー化した.結果:母親のレジリエンスとして【退院への意志】【ネガティブ感情に負けない力】【夫の存在】【信頼できる医療者の存在】【子どもの生命力】【家族の存在】【妊娠と出産のポジティブな思い】【同じ境遇の母親の存在】【母親としてのプライド】【ソーシャルサポート】が抽出された.結論:医療的ケアを継続しながら在宅療養へ移行した先天異常のある子どもの母親のレジリエンスは,退院への意志,母親の性格,周囲の人々との信頼関係や支援,子どもの生命力,子どもとの相互作用によって培われた母親としての思いであった.出産前からの計画的な支援,母親と子どもの相互作用に着目した支援,在宅療養への段階的な支援が重要であることが示唆された.
2 0 0 0 OA 泡沫の三十五年 : 外交秘史
- 著者
- 佐藤 正惠
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.128-132, 2022-04-01 (Released:2022-04-01)
2020年3月にパンデミックが宣言されたCOVID-19感染症は,2022年1月現在もウイルス変異により猛威を振るい続けており,社会生活は大きく変貌した。医療体制,ワクチン接種等をめぐり,根拠の不確かなニュースが氾濫するインフォデミックが危惧される状況となっている。本稿は,主に公共図書館における情報の吟味と提供を考える。疑問の定型化,エビデンス・ピラミッドや6Sピラミッドと情報検索,フェイクニュースへの海外の対応について述べる。さらに医療・健康に関する報道について質の向上を目指すメディアドクター研究会の活動を紹介し,メディアリテラシーについての話題を提供する。
2 0 0 0 OA 先史スラヴ文化におけるエンバクの語彙的証拠
- 著者
- 佐藤 規祥
- 出版者
- 愛知淑徳大学交流文化学部
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集. 交流文化学部篇 (ISSN:21860386)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.93-107, 2021-03-16
2 0 0 0 OA 木津用水の歴史とその役割について
- 著者
- 中屋 俊満
- 出版者
- 公益社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業農村工学会誌 (ISSN:18822770)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.7, pp.571-574,a2, 2015 (Released:2021-01-14)
- 参考文献数
- 7
愛知県濃尾平野北部に位置する木津用水は今から約370年前,尾張藩の直轄事業として開削された。木津用水の開削は尾張藩の財政を支え,その後何回かの災害を受けながらも復旧を行ってきた。明治時代には木曽川から名古屋を結ぶ舟運にも利用されながら現在まで用水路として水を配り続けてきた。しかしながら,都市化の進行により背後地などからの排水量の増大により機能に支障が出始めたことから,国営総合農地防災事業として改修を行うことになった。同用水の地下水涵養機能などに着目し,今後の用水供給の継続と土地改良区の役割などについて筆者の考えをまとめた。
2 0 0 0 OA ADHD スペクトラム? ―岡崎論文へのコメント―
- 著者
- 室橋 春光
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.73-75, 2011 (Released:2018-08-18)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 胸部大動脈に病変を有する炎症性大動脈瘤の一例
- 著者
- 仁科 有美子 土屋 貴彦 青木 正紀 山上 賢治 早川 純子 金子 菜穂 西成田 進
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.169-173, 2009-06-30 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 11
We report a case of 79-year-old woman with an inflammatory aneurysm occurred in a thoracic aorta. The patient was admitted to our medical center because of continuous pyrexia of unknown origin. A marked elevation of serum C-reactive protein level was observed. Infections, collagen vascular diseases and neoplastic disease including malignant lymphoma were found to be unlikely by hematologic, serologic and radiographic examinations. Autoantibodies including antineutrophil antibodies were undetectable. Only enhanced-computed tomography revealed an abnormal finding, so-called mantle core sign, in thoracic aorta, which is specific for inflammatory aortic aneurysm. In general, the disease occurs in abdominal aorta, and the involvement of thoracic aorta like this case is rare. Usually, an aortic aneurysm occurs based on atherosclerotic change of blood vessels, and the aspects of an inflammation of large vessels have been focused recently at the pathological findings, the cytokine profiles and the immunological abnormalities. Thus, the differential diagnosis of the disease from Takayasu arteritis, a prototype of a large vessel vasculitis, is often difficult. The diagnostic procedure to differentiate from the other large vessel vasculitis, Takayasu arteritis and atherosclerotic diseases in abdominal aorta, is discussed. The patient was given oral prednisolone which lead to favorable outcome.
- 著者
- 野田 陽子
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.133-135, 2002-10-26 (Released:2017-03-30)