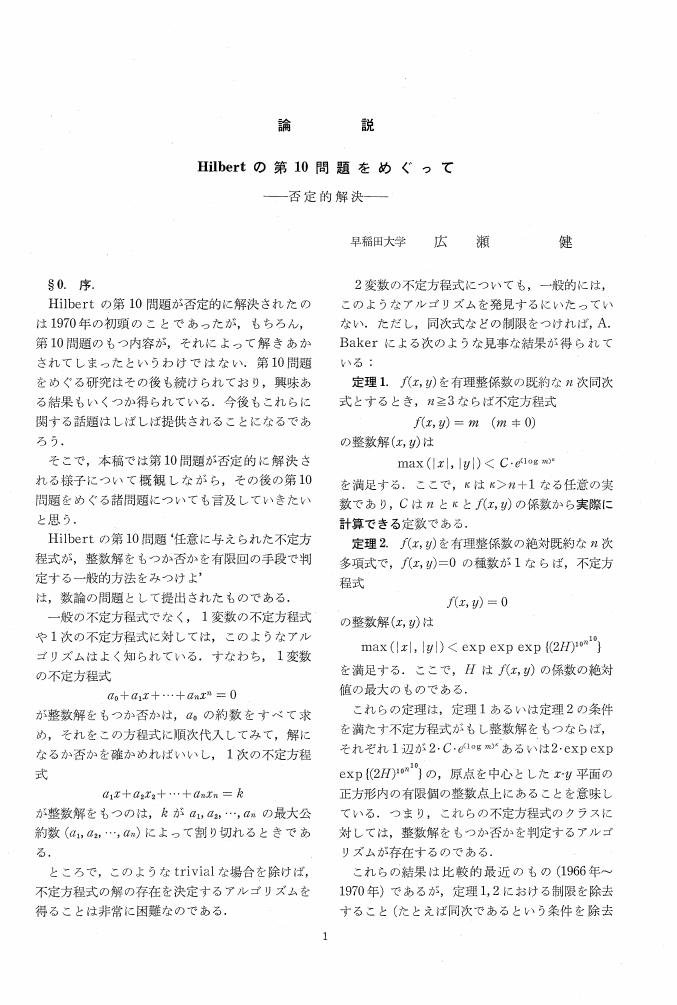2 0 0 0 OA カダヤシの塩分の上昇に対する馴致
- 著者
- 伊藤 寿茂
- 出版者
- 日本陸水学会
- 雑誌
- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.219-222, 2006-12-01 (Released:2008-03-21)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3 4
日本に帰化した淡水魚カダヤシGambusia affinis の塩分耐性を水槽内で調べた。飼育水の塩分を様々な上昇幅で24時間毎に上げていき, その生残率を調べた。1日で海水濃度まで上げた水槽では, 殆どの個体が死亡したが, 3日以上かけて徐々に塩分を上げた水槽では, その生残率は大幅に高まり, 海水に高い適応性のある魚種であることが確認できた。カダヤシは汽水域や海水域を一時的に生活場所と出来, 海水域を介して分布を拡大する可能性が示された。
2 0 0 0 沼田の湯立神楽 : 国記録選択無形民俗文化財調査報告書
- 著者
- 静岡県教育委員会文化財保護課編集
- 出版者
- 静岡県教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 2016
2 0 0 0 OA 原発性虫垂癌13例の臨床病理学的検討
- 著者
- 宇高 徹総 山本 澄治 中村 哲也 黒川 浩典 宮谷 克也
- 出版者
- 日本外科系連合学会
- 雑誌
- 日本外科系連合学会誌 (ISSN:03857883)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.738-742, 2016 (Released:2017-10-30)
- 参考文献数
- 9
1990年1月から2013年12月までに当院で切除した原発性虫垂癌13例について臨床病理学的特徴,術前・術中診断,術式,化学療法,転帰について検討した.男性6例,女性7例で,平均年齢は73.4歳(56~94歳)であった.術前診断で虫垂癌の確定診断が得られたのは1例のみで,術中にあらたに6例に診断ができ,残りの6例は術後の病理で診断できた.術式は結腸右半切除術5例,回盲部切除術6例,盲腸部分切除術1例,虫垂切除術1例であった.組織型は高分化型腺癌9例,中分化型腺癌3例,乳頭腺癌1例で,深達度はT2が1例.T3が5例,T4が7例,進行度はStage Ⅱが6例,Stage Ⅲaが4例,Stage Ⅲbが1例,Stage Ⅳが2例であった.術後観察期間中央値は43カ月(2~169カ月),転帰は無再発生存5例,無再発他病死3例,腹膜播種による原癌死3例,肝転移による原病死が1例,切除断端再発よる原病死が1例であった.累積5年生存率は51.9%であった.手術時にはすでに進行しており腹膜播種再発の頻度が高い傾向があるため,術後化学療法などの集学的治療が重要と思われた.
2 0 0 0 OA 運動後のグルタミン投与は筋肉グリコーゲンの蓄積を促進する
- 著者
- 伏木 亨
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.7, pp.463-464, 1996-07-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 地震とめまい —東日本大震災直後2週間の東京でのアンケート調査とその分析—
- 著者
- 二木 隆 深谷 卓
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.456-465, 2012 (Released:2013-02-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2
Many patients who have been receiving treatment for dizziness in our clinic complained of some worsening of their symptoms or changing of their usual problems after the “Mega-quake” of 11, Mar. 2011, i.e. the Higashi-Nihon Daishinsai earthquake (Magnitude: 9.0). In order to elucidate the influence of the Mega-quake on patients with dizziness, we assessed 235 subjects within 2 weeks after the `quake' with a questionnaire. The number of new patients within the 2 weeks before and after the earthquake rose from 19 to 29. The response rate from the questionnaire was 59%, and the three most serious symptoms were as follows, “horizontal swinging of the earth”, “vertical movement of the earth”, “nausea sensation similar to motion sickness”, rather than the usual symptoms such as vertigo or blackouts. As objective findings, spontaneous and positional nystagmus was encountered 27% of the respondents and one in 5 patients showed a larger area of body sway in the Gravicorder Recording. Some of the neurological considerations were discussed based on the results of our investigation regarding the earthquake and body equilibrium.
2 0 0 0 OA 制振材料に関する一般知識と材料データ
- 著者
- 竹内 文人
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.8, pp.249-253, 2016 (Released:2016-10-05)
- 参考文献数
- 5
This article gives an overview of the fundamentals of polymeric materials for vibration damping. Based on vibration transmissibility of single degree of freedom systems, the differences between vibration isolation and vibration damping are described. Mechanism and materials design of the vibration damping materials are outlined with viscoelastic properties and those structures. As an example of controlling loss factor in viscoelastic properties, the formulations of EPDM with carbon black are described.
2 0 0 0 OA 利他的行動と再帰的他者推定
- 著者
- 牧野 貴樹 滝 久雄 合原 一幸
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.259-265, 2010-05-01 (Released:2010-09-22)
- 参考文献数
- 10
試行錯誤を通して学習するエージェントが利他的行動を獲得するために必要な他者モデルの要素を,繰り返し囚人のジレンマゲームの計算機シミュレーションにより調べた。実験の結果,他者モデルを持たないエージェントや,予測した他者の行動だけを参照するエージェントよりも,推定した他者の内部状態に基づいて行動決定するエージェントのほうが,高確率で相互協調に至ることが明らかになった。また,再帰的な推定構造をもつ他者モデルや,自己と他者の相互の入れ子構造を有する他者モデルを利用すると,相互協調に至る確率がさらに高まった。
2 0 0 0 OA 9.家族性地中海熱の診断と治療
- 著者
- 右田 清志 古賀 智裕 川上 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.9, pp.1918-1925, 2019-09-10 (Released:2020-09-10)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA 明治初期大阪におけるアメリカ人医療宣教師と医学教育
- 著者
- 藤本 大士
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.292, pp.318-333, 2020 (Released:2020-04-22)
In 1859, some American Protestant denominations started medical missions in Japan. The medical missionaries tried to eliminate the Japanese people’s prejudice against Christianity by offering medical care and education to the local communities. In the 1870s, several young medical students and ambitious medical practitioners asked the American medical missionaries for instruction about Western medicine. The current scholarship has overlooked the work of these American medical missionaries and has narrowed its focus to the German physicians who worked at the University of Tokyo and influenced the Japanese physicians with German medicine. This paper aims to demonstrate how the American medical missionaries were appreciated in early Meiji Osaka. First, I outline the background of the American Protestant missions, which dispatched many medical missionaries in the 1870s. Second, I describe the activities of the American medical missionaries in Osaka from the 1870s until the mid- 1880s, focusing on Arthur H. Adams and Wallace Taylor from the American Board of Commissioners for Foreign Missions and on Henry Laning from the Protestant Episcopal Church in the United States of America. Finally, I examine how these medical missionaries were engaged in the medical education of both medical students and physicians.
2 0 0 0 OA 漢字のとめはねの丁寧さはテストにおいてどのように評価されるのか
- 著者
- 関口 あさか 平林 ルミ 高橋 麻衣子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, pp.99-100, 2018 (Released:2019-12-05)
2 0 0 0 OA ドーパミンによる可塑性と学習の制御機序
- 著者
- 柳下 祥
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3-4, pp.144-151, 2020-12-05 (Released:2021-01-08)
- 参考文献数
- 34
報酬による学習においてドーパミンは主要な役割を担う.特に近年の光遺伝学を始めとした神経回路操作技術や遺伝子コードされるプローブを利用した神経活動の観察技術の進展により,ドーパミンが報酬予測誤差信号として学習を制御する実態がわかってきた.一方,ドーパミンがどのように学習の基盤となる神経回路の変化を起こすかについては不明な点が多かった.そこで,筆者らは光遺伝学によるドーパミン神経操作に加えてケイジド・グルタミン酸の2光子刺激による単一スパイン・シナプスでのグルタミン酸シグナルの操作技術を駆使しこの問題に取り組んだ.結果,学習に関わるドーパミン一過性変化が側坐核のD1受容体およびD2受容体発現細胞のスパイン・シナプスの可塑性を制御する機序を世界に先駆けて明らかにした.このシナプス細胞基盤の知見を元に,条件づけ学習を詳細に検討したところ,D1受容体発現細胞は汎化学習・D2受容体発現細胞は弁別学習を担うことがわかった.一方,消去学習はこれらの機序では説明がつかなかった.このようにドーパミン報酬予測誤差信号が側坐核のシナプスを介して制御する学習の実態の解明に近づいた.また,統合失調症とD2受容体の関連は古くから知られていたが,この関係をD2受容体発現細胞の機能低下と弁別学習障害により妄想の基盤となるサリエンス障害が生じるのではないかという仮説を提唱するに至った.このようにシナプス可塑性・学習により環境構造を内在化する機能を詳細に理解した上で,現在はさらに脳が社会環境と相互作用することが精神疾患理解に新たな道を拓くのではないかと考え,研究を進めている.
2 0 0 0 OA 刀剣講話
- 著者
- 別役成義, 今村長賀 述
- 出版者
- [ ]
- 巻号頁・発行日
- vol.3, 1903
2 0 0 0 OA 租税法律主義と「遡及立法」
- 著者
- 渕圭吾
- 出版者
- 財務省
- 雑誌
- フィナンシャル・レビュー
- 巻号頁・発行日
- no.129, 2017-03
- 著者
- Albert Youngwoo Jang Minsu Kim Pyung Chun Oh Soon Yong Suh Kyounghoon Lee Woong Chol Kang Ki Hong Choi Young Bin Song Hyeon-Cheol Gwon Hyo-Soo Kim Woo Jung Chun Seung-Ho Hur Seung-Woon Rha In-Ho Chae Jin-Ok Jeong Jung Ho Heo Junghan Yoon Soon Jun Hong Jong-Seon Park Myeong-Ki Hong Joon-Hyung Doh Kwang Soo Cha Doo-Il Kim Sang Yeub Lee Kiyuk Chang Byung-Hee Hwang So-Yeon Choi Myung Ho Jeong Chang-Wook Nam Bon-Kwon Koo Seung Hwan Han
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.9, pp.1365-1375, 2022-08-25 (Released:2022-08-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
Background: Differences in the impact of the 1- or 2-stent strategy in similar coronary bifurcation lesion conditions are not well understood. This study investigated the clinical outcomes and its predictors between 1 or 2 stents in propensity score-matched (PSM) complex bifurcation lesions.Methods and Results: We analyzed the data of patients with bifurcation lesions, obtained from a multicenter registry of 2,648 patients (median follow up, 53 months). The patients were treated by second generation drug-eluting stents (DESs). The primary outcome was target lesion failure (TLF), composite of cardiac death, target vessel myocardial infarction (TVMI), and ischemia-driven target lesion revascularization (TLR). PSM was performed to balance baseline clinical and angiographic discrepancies between 1 and 2 stents. After PSM (N=333 from each group), the 2-stent group had more TLRs (hazard ratio [HR] 3.14, 95% confidence interval [CI] 1.42–6.97, P=0.005) and fewer hard endpoints (composite of cardiac death and TVMI; HR 0.44, 95% CI 0.19–1.01, P=0.054), which resulted in a similar TLF rate (HR 1.40, 95% CI 0.83–2.37, P=0.209) compared to the 1-stent group. Compared with 1-stent, the 2-stent technique was more frequently associated with less TLF in the presence of main vessel (pinteraction=0.008) and side branch calcification (pinteraction=0.010).Conclusions: The 2-stent strategy should be considered to reduce hard clinical endpoints in complex bifurcation lesions, particularly those with calcifications.
2 0 0 0 OA タービン翼列の二次流れと損失の発生メカニズム
- 著者
- 山本 孝正
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.234-241, 1986-04-10 (Released:2011-07-11)
- 参考文献数
- 36
2 0 0 0 OA 鼻腔由来一酸化窒素 (NO) に及ぼすα1およびβ2刺激剤局所投与の影響
- 著者
- 甲斐 智朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.7, pp.898-906, 1999-07-20 (Released:2010-10-22)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
(目的) 鼻粘膜の血管収縮・拡張が鼻腔由来の一酸化窒素 (NO) 濃度に及ぼす影響を局所への薬剤投与により検討した.(対象) アレルギー性鼻炎以外に特に鼻副鼻腔疾患を有しない健常人24名.(方法) 安静座位における鼻腔由来のNO濃度および鼻腔抵抗, 最小鼻腔断面積, 鼻腔容積を測定した後, 前者12名には血管収縮剤として硝酸ナファゾリン, 後者12名にはNO-cGMP系を介さない血管拡張剤として硫酸サルブタモールをそれぞれ定量噴霧器を用いて両側鼻腔内に投与し, それぞれの計測値の変化を測定した. NOの測定には, chemiluminescence法によるNOアナライザーを用いた. 鼻腔抵抗の測定は鼻腔通気度計を用いてアンテリオール法により, 更に最小鼻腔断面積と鼻腔容積の測定はアコースティックライノメトリーにより行った.(結果) 硝酸ナファゾリンの投与によりNO濃度は有意に低下し, 鼻腔抵抗は有意に減少した. 更に鼻腔容積は有意に増大した.硫酸サルブタモール投与により, NO濃度は有意に上昇し, 鼻腔抵抗も有意に上昇した. 更に最小鼻腔断面積および鼻腔容積は有意に減少した.(考察) 鼻腔抵抗および最小鼻腔断面積, 鼻腔容積の変化から, 各薬剤により鼻粘膜が収縮・拡張していることが示された. 硝酸ナファゾリンはα1レセプターを介して血管を収縮させ, また血管拡張作用を示した硫酸サルブタモールはβ2刺激剤であり, この血管拡張作用はNOを介さないことから, 鼻腔由来のNO産生量は, 血管の収縮・拡張に伴う基質の供給量の変化に影響される可能性が示唆された.(結論) 血管収縮・拡張剤により, 鼻腔由来のNO濃度は有意に減少・増加し, これは基質の供給量の変化に基づいている可能性があると考えられた.
- 著者
- 岩本 宗大 大西 鮎美 寺田 努 塚本 昌彦
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.10, pp.1574-1582, 2022-10-15
フィールドホッケーは,スティックと硬球を使って行う世界的に人気のあるスポーツである.フィールドホッケーの動作の中で,チームメイトへのパスとして最も基本的で一般的に使われる動作のうちの1つにプッシュという動作がある.プッシュ動作中,スティックにボールが接触してからリリースされるまでスティックがボールと接触している距離が長いと強くて速いプッシュを打てる.しかし,初心者が自分でスティックの接触点を知覚することは難しい.本研究では,プッシュの技術向上のためにスティックにボールが接触する位置の移動経路をリアルタイムに聴覚フィードバックするシステムを提案する.提案システムは,圧力センサの接触位置に応じてピッチの異なるフィードバック音を圧電スピーカによりリアルタイムで発生させる.2カ月間行った評価実験の結果,スティック上のボールの移動経路の平均距離は,聴覚フィードバックを行ったほうが,行わなかった場合よりも有意に長くなった.これにより,提案システムによる聴覚フィードバックの有効性を確認した.
2 0 0 0 OA BMI>90の超高度肥満患者の人工呼吸器離脱経験
- 著者
- 小林 朋恵 大塲 瑠璃 佐藤 麻理子 安達 厚子 桜田 幽美子 袖山 直也 安藤 幸吉 山内 正憲
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.552-553, 2021-11-01 (Released:2021-11-01)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 穿通枝の外科解剖—ICG videoangiographyと神経内視鏡の有用性—
- 著者
- 片岡 大治 飯原 弘二
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.12-18, 2015 (Released:2015-01-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
穿通枝障害は重篤な神経症状を生じることが多いため, その外科解剖を理解することは脳神経外科顕微鏡手術においてきわめて重要である. 特に, 脳動脈瘤クリッピング術の際は, 穿通枝の解剖学的バリエーションと脳動脈瘤との関係について理解しておく必要がある. 前脈絡叢動脈は, 動脈瘤のドームから起始することもあり, また2~4本存在することがあるため, そのような場合には注意が必要である. レンズ核線条体動脈は通常中大脳動脈水平部 (M1部) の後壁から分岐するが, 時としてM1-2分岐部やM2から起始する. 視床下部動脈は前交通動脈の後面から起始するため, pterional approachでは確認することが困難である. 穿通枝の温存のためには, 動脈瘤周囲の穿通枝をすべて確認することが必要で, 神経内視鏡は顕微鏡の死角となる部分の観察に有用である. 穿通枝の血流を温存するようにクリップをかけ, クリッピング後はドップラー超音波流量計, ICG蛍光血管造影, 運動誘発電位などの神経生理学的モニタリングなどの術中モニタリングで穿通枝の温存を確認する. それぞれのモニタリングには偽陰性が生じ得るため, 複数のモニタリングを組み合わせて使用することが重要である.
2 0 0 0 OA Hilbertの第10問題をめぐって
- 著者
- 広瀬 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.1-9, 1973-01-30 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 13