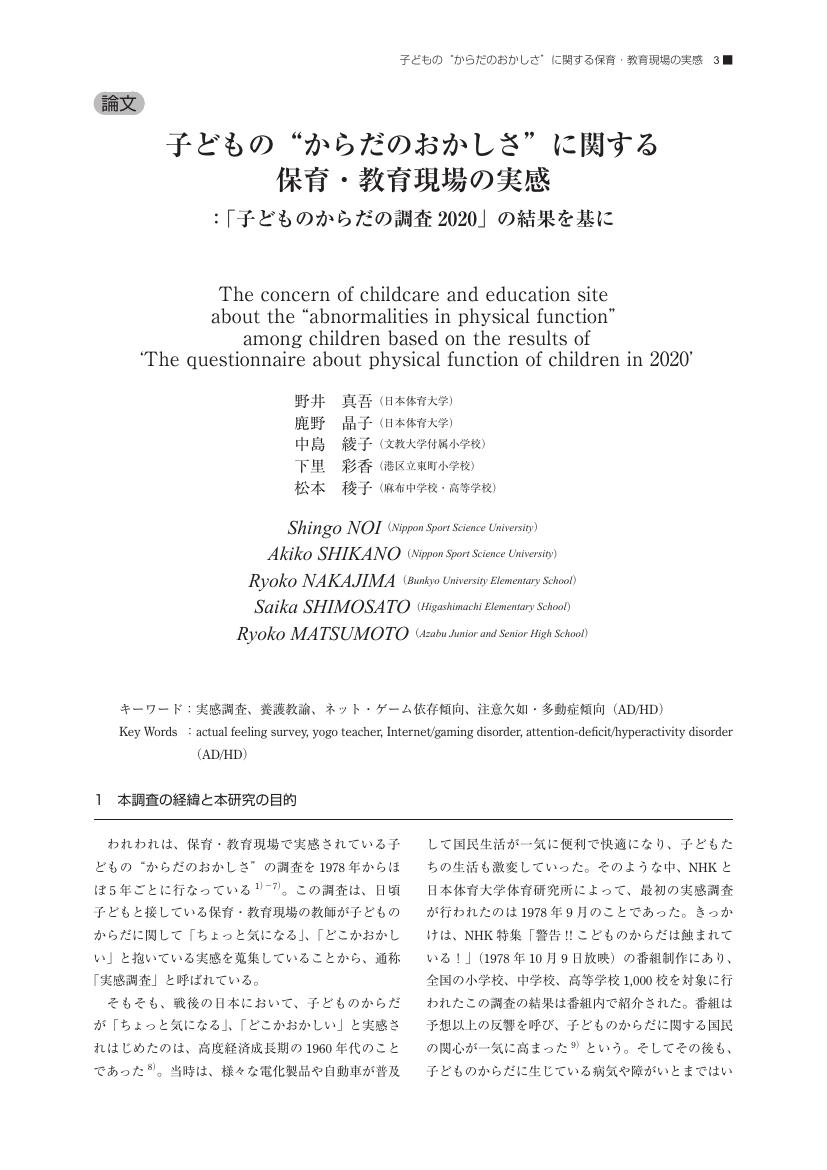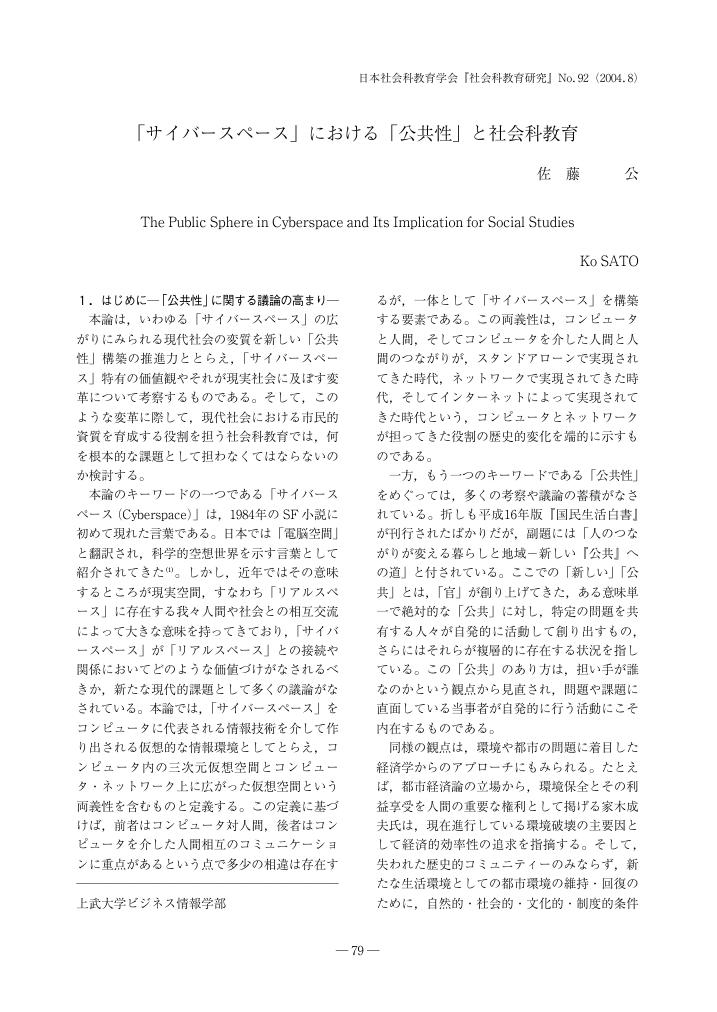2 0 0 0 OA 新型コロナ対策専門家Twitterアカウントにおけるツイートの特徴と情報発信内容
- 著者
- 古口 凌太郎 石橋 由基 田谷 元 安保 悠里子 伊豆藏 栞 奈良 由美子 堀口 逸子
- 出版者
- 一般社団法人 日本リスク学会
- 雑誌
- リスク学研究 (ISSN:24358428)
- 巻号頁・発行日
- pp.SRA-0383, (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 22
In 2020, COVID-19 had a huge impact worldwide. The Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan organized a “cluster countermeasure group” comprising public health and infectious diseases experts. They provided information about COVID-19 on Twitter. In this study, the text analysis software “KH Coder” was used to confirm the kind of information posted by these experts on the Twitter account. Scientific information, such as explanations of terms, future predictions of the spread of infection, and public health measures, were provided. Twitter account had played a role in providing scientific information. That is, we practiced risk communication. It helped to increase the trust of the account by receiving genuine certification from Twitter Inc. Text analysis helped assess risk communication.
- 著者
- 野井 真吾 鹿野 晶子 中島 綾子 下里 彩香 松本 稜子
- 出版者
- 日本教育保健学会
- 雑誌
- 日本教育保健学会年報 (ISSN:18835880)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.3-17, 2022-03-01 (Released:2022-06-04)
2 0 0 0 OA 花見における民衆の変身と笑いについて
- 著者
- 小野 佐和子
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.93-103, 1984-10-15 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
近世都市における住民のレクリェーション研究のひとつとして幕末の江戸で行われた花見のあり方を考察した。その結果, 下層町人を主体とする行列・仮装・滑稽劇をその特徴に認め, 当時の花見が, 演劇的装いのもとに笑いを通じて民衆の想像力を解放する働きを有しており, 花見の場が民衆の笑いと変身の空間であるとする知見を得た。
- 著者
- 山勢 善江 山勢 博彰 明石 惠子 浅香 えみ子 木澤 晃代 剱持 功 佐々木 吉子 佐藤 憲明 芝田 里花 菅原 美樹 中村 美鈴 箱崎 恵理 増山 純二 三上 剛人 藤原 正恵 森田 孝子
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急看護学会
- 雑誌
- 日本救急看護学会雑誌 (ISSN:13480928)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.37-47, 2021 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 20
2019年11月に中国で発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、わが国でも全国に拡大し、2020年4月には第一波、夏に第二波、そして11月には第三波が到来した。 本学会では、COVID-19緊急事態宣言下での救急看護の実態と課題を明らかにすることを目的に、学会ホームページを通じて、本学会員を中心にWebアンケート調査を実施した。調査内容は、COVID-19患者への所属施設の対応、具体的対応、感染防止策、看護師の認識や思い等である。調査には425名が回答した。 多くの施設で、待合室や診察室として「新設の専用エリア」や「陰圧室」を使用していたが、「他患者と同じエリア」を使用していた施設もあり、ハード面の迅速な設置の困難さが明らかになった。また、半数以上の者が、感染防護具、看護師の不足を感じていた。さらに、救急看護師は未知の感染症への対応で、自分自身や家族への感染の恐怖、行政や所属施設、上司への不満などネガティブな感情をもつ者が多く、調査時点で心理的不安定を経験していた看護師は29.6%いた。 今後の医療の課題と対策には、感染対策指針やマニュアルの整備、検査体制の強化、ワクチンや治療薬の開発促進、専門病院の整備、専門的スタッフの配置、日本版CDCの設置、医療者への報酬増額があった。
2 0 0 0 OA 東京市商工名鑑
- 著者
- 東京市 編
- 出版者
- ジャパン・マガジーン社
- 巻号頁・発行日
- vol.第5回, 1935
2 0 0 0 OA 江戸初期能番組7種 : 番組要綱と曲名・演者名索引(1)
- 著者
- 演能記録調査研究グループ
- 雑誌
- 能楽研究 : 能楽研究所紀要 (ISSN:03899616)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.302-212, 1994-03-30
2 0 0 0 OA 「サイバースペース」における「公共性」と社会科教育
- 著者
- 佐藤 公
- 出版者
- 日本社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.92, pp.79-94, 2004 (Released:2016-12-01)
- 著者
- 遠藤 伸太郎 矢野 康介 大石 和男
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.657-672, 2022 (Released:2022-08-17)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
Restrictions on going out due to the novel coronavirus (COVID-19) pandemic have caused various psychological problems in many Japanese elementary school students, such as stress, anxiety, fear, helplessness, and anger. In this context, promotion of nature experience activities has been advocated, and have been reported to improve mental health. In addition, since a decrease in daily physical activity/exercise level is reportedly associated with a deterioration in mental health, the level of physical activity/exercise should be taken into account when evaluating the effects of nature experience activities. The purpose of this study was to examine the longitudinal effects of nature experience activities on the mental health of elementary school children during the COVID-19 pandemic, taking into consideration the daily level of physical activity/exercise. The participants were 130 fifth and sixth grade elementary school students (60 boys and 70 girls). The survey was conducted at 3 time points: just before the nature experience (pre-survey), just after the experience (post-survey), and 1 month after the experience (follow-up survey). Participants were asked to complete a questionnaire that assessed: 1) the degree of anxiety and limitation of activities related to COVID-19, 2) daily exercise level (hours), 3) social support level, 4) mental health level, 5) content of experiences in nature experience activities, 6) stress level. The participants were divided into high- and low-exercise groups according to their median scores. In the high-physical activity group, the pre-survey anger score (a component of mental health) was significantly higher than the scores for the post- and follow-up surveys. In addition, the self-confidence score (a component of mental health) for the postand follow-up surveys were significantly increased from the pre-measurement score, regardless of exercise hours. Therefore, it was shown that nature experience activities, while considering the influence of daily exercise, may be important for retaining calmness and confidence in daily life, even during the COVID-19 pandemic. However, there was no significant relationship between mental health and the content of nature experience activities. Therefore, it will be necessary to examine such content, which is closely connected with improvement in mental health.
2 0 0 0 OA 西洋占星術に見る人の生死と運命
Beliefs in the power of celestial bodies and ways of interpreting their meaning are found throughout the world. In this paper, traditional Western astrology is taken as an object of study and its relationship with quality of life, death, and destiny are explored. First, the historical process and environment in which Western astrology was formed are surveyed. Second, the basic theory of Western astrology is viewed through Ptolemy’s Tetrabiblos, which is regarded as the standard textbook of astrology from ancient times. Finally, the ethical and religious problems that the materialism of Western astrology has caused are discussed, such as the freedom of God and human beings, astrological fatalism, and the meaning of life.The horoscope of Western astrology, which is the birth chart of each person, has three fundamental components: planet, sign, and house. These three components determine all the dimensions of the life of that person. “Planet” includes the sun and moon, and it is said that these seven planets have productive or destructive power according to the mythological characters they are named after. “Sign” and “house” are particular areas of the zodiac and are derived by dividing the zodiac into twelve parts. Sign is the fixed area that starts from the spring equinoctial point, but house is the fluid area that starts from the ascendant, which is the rising point of the sun and changes everyday. It is believed the power of one’s planet adjusted by sign and house flows into each person and forms his or her whole life: parents, siblings, marriage, children, welfare, death, and length of life.
- 著者
- Ryutaro SHIMAZAKI Kohji KUSANO
- 出版者
- Catalyst Unit
- 雑誌
- Translational and Regulatory Sciences (ISSN:24344974)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.122-124, 2021 (Released:2021-12-24)
- 参考文献数
- 12
Sendai virus (SeV) vectors are able to infect a diverse range of cells. They have a high affinity for epithelial cells in the respiratory tract, which provides advantageous properties for intranasal inoculation. Vaccination of the respiratory tract, the main route of infection for Coronavirus (COVID-19), can strongly induce mucosal immunity, which is difficult to induce through injected vaccines, in addition to systemic immunity in a manner similar to innate immunity. A SeV vector vaccine carrying part of the SARS-CoV-2 spike-protein gene showed high immunogenicity in pharmacological studies using intranasally inoculated rodents and is a promising next-generation vaccine.
2 0 0 0 OA 富山平野における隆起扇状地の水田造成と灌漑について
- 著者
- 竹内 常行
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.216-237, 1977-04-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 2
富山平野の山麓にはかなり広い隆起扇状地が発達しているが,これらの隆起扇状地にも古くから水田が広く拓かれている.このことは天竜川,相模川,荒川や松本平その他の隆起扇状地と較べて著しい特色である.この理由を明らかにするために,隆起扇状地が2段以上発達している,小矢部川から黒部川に至る8河川の隆起扇状地が,どのような用水路によって拓かれてきたか,また各河川の灌瀧区域の用水事情はどのようであったかを調査した.その結果,用水源である河川の本流あるいは支流の集水面積が,灌概区域に対して広い神通川を除いて,必ずしも集水面積は広くはないが,多雪地帯であるために,最多要水期に雪解水が豊富であることと,各河谷の勾配が急で,比較的短い距離で導水できることなどの有利さが,加賀藩の政策と相侯って,広く水田開発を可能にしたことがわかった.しかし,大部分の地域が夏期の渇水期の水不足に苦しんだ実情をも明らかにして,近年の合口事業やダム建設の効果にも論及した.
2 0 0 0 OA アニムス再考ー変容する力としてー
- 著者
- 山口 素子 Motoko YAMAGUCHI
- 雑誌
- 心理相談研究
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.3-10, 2009-03-31
2 0 0 0 OA Supplemental PN の意義
- 著者
- 井上 善文
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.303-308, 2017 (Released:2018-05-22)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA 第二次世界大戦後の香港左派の発展 学友社の事例
- 著者
- 谷垣 真理子
- 出版者
- 日本華南学会『華南研究』編集委員会
- 雑誌
- 華南研究 (ISSN:21884846)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.5-23, 2019 (Released:2020-06-01)
2 0 0 0 OA 生体電気計測の基礎
- 著者
- 神保 泰彦
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.11, pp.1204-1207, 2007 (Released:2009-12-11)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 『韃靼漂流記』にみる弓馬の意義
- 著者
- 小林 寛 金 河守 Hiroshi Kobayashi Ha-soo Kim
- 雑誌
- 研究紀要 = Bulletin of Tsukuba International University (ISSN:13412382)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.63-76, 2014
2 0 0 0 OA 雌性発生キンブナにおける精子核導入による四倍体の作出
- 著者
- 間田 康史 宮川 真紀子 林 大雅 海野 徹也 荒井 克俊
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.103-112, 2001-03-20 (Released:2010-10-28)
- 参考文献数
- 29
雌性発生により繁殖している三倍体ギンブナの卵をキンギョ精子で受精後,様々な条件で低温あるいは高温処理を施すことにより,四倍体あるいは四倍体-三倍体モザイクが作出できた。40℃,60秒間の高温処理では受精後5分に処理を開始した群で四倍体の出現率が高かった(67~100%)。DNAフィンガープリント分析とRAPD-PCR分析から,四倍体は父親キンギョ由来のDNA断片を示すことから,精子核ゲノムが取り込まれて作出されることが判明した。高温処理(40℃,60秒間,受精後5分)を施した受精卵の細胞学的観察から,三倍体では本来膨潤しないはずの精子核が雄性前核となり,三倍体雌性前核あるいは二細胞期の割球の核と融合することにより四倍体核が形成されることが判った。同一水槽で三倍体と四倍体を飼育した場合,12月齢魚では成長に差は見られなかった。これらの三倍体は全雌であったが,四倍体では17個体中10個体が雌で,残りの7個体は性的に未分化であった。
2 0 0 0 OA 石原莞爾の対中国観を追う ―満洲事変から東亜聯盟への軌跡―
- 著者
- 浜口 裕子
- 出版者
- 拓殖大学政治経済研究所
- 雑誌
- 拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 = The review of Takushoku University : Politics, economics and law (ISSN:13446630)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.1-24, 2018-09-30
本稿は関東軍参謀として満洲事変を画策したことで知られる石原莞爾の対中国観を追う。石原は満洲事変を起こしたものの,後の日中戦争勃発にあたっては,陸軍参謀本部作戦部長という要職にあったにもかかわらず「不拡大」の立場で,その収拾あたった。そこに至る彼の思想的変遷を,特に対中国観という面から跡づける。若き頃より中国に対して並々ならぬ関心を抱いていた石原は,辛亥革命勃発の際にはその前途に希望を持ち,大きな喜びに震えた。ところがその後軍閥間の抗争に明け暮れる中国に失望し,中国人の政治能力に疑問を抱く。満洲事変直前には,来たるべき日米間の世界最終戦争の準備が必要で,日本が満蒙を領有し,その治安を守る,といった考えを構築する。満洲事変・満洲国建国の過程で,石原の中国人の政治能力に対する懐疑は解け,満蒙独立論に転化,日中平等の民族協和国家の建国を推進する。この民族協和政治の実現は協和会に期待し,満洲を去り参謀本部で自らの構想を提唱するが必ずしも理解されない。「日支平等」の考えを成長させ,東亜聯盟を提唱していく一方で,参謀本部作戦課長や戦争指導課長としてソ連の脅威にどう対処するかを考えざるを得ず,満洲国構想も東亜聯盟論もこの点で意味づけられた。すなわち満洲国-東亜聯盟を完成させ,国防を充実させソ連に対抗し,また日本国内の改造(昭和維新)が必要である,という方向へ向かうのである。