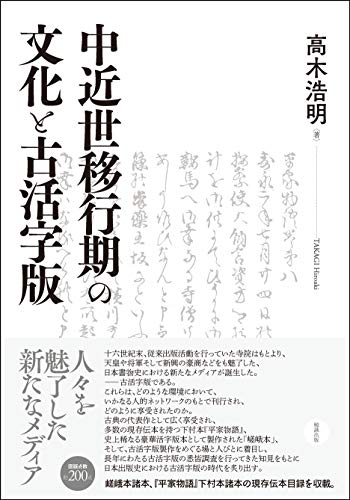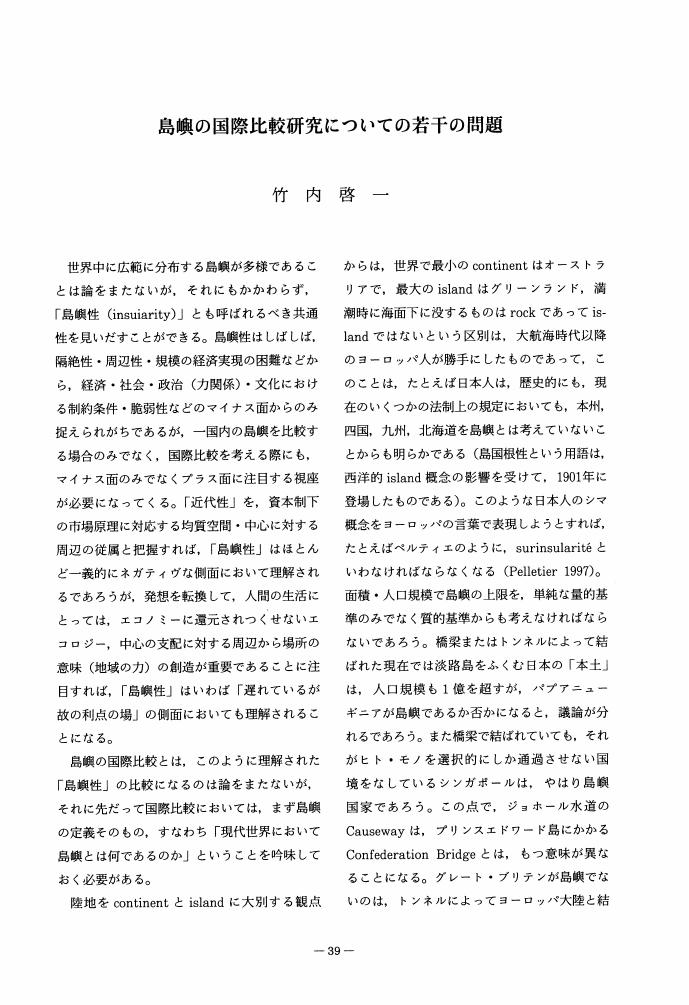2 0 0 0 IR 開かれた「窓」への感謝とともに : 法学部・市民講座・『更級日記』
- 著者
- 和田 律子
- 雑誌
- 流経法學 = Journal of the Faculty of Law, Ryutsu Keizai University
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.19-28, 2021-03-10
- 著者
- 金森 紀博 小泉 雅大 野嶋 栄一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.299-308, 2014-12-25 (Released:2016-08-11)
一人一台の学習端末における繰り返し学習はCAIから始まり,eラーニングまで続いているが,単なるドリル学習ではモチベーション維持が難しかった.本研究では,「見えないライバル」とネットワーク上でリアルタイムに対戦できる「つながる学習システム」を開発し,実証実験を行った.同程度のレベルのグループに分けられることにより,競争への意識が高まり,計算,算数への肯定感だけではなく,家庭学習の習慣にも好影響があることがわかった.8ヶ月にわたる実証実験の結果,本システムを利用した児童は,利用しない児童に比べ比較的短期間で計算力が向上することを実証した.また,計算力向上がみられる伝統的な習い事と比較しても同程度以上の効果があげられ,特に低学力層への効果が高いことがわかった.
2 0 0 0 OA 日本におけるおっとせい研究の現状
- 著者
- 和田 一雄
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.2_7-13, 1965 (Released:2008-12-17)
2 0 0 0 IR 犬吠埼温泉の有用性 : 成分分析と保湿効果検証
- 著者
- 平尾 哲二 手束 聡子 鈴木 真綾 木村 美沙季 山下 裕司
- 出版者
- 千葉科学大学
- 雑誌
- 千葉科学大学紀要 (ISSN:18823505)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.15-22, 2017-02
犬吠埼温泉は銚子市の観光資源の一つである。本研究では、犬吠埼温泉の有用性について科学的データ取得を目的として、3種類の源泉について成分分析するとともに、保湿効果について検討した。各源泉に含まれる主要元素についてICP発光分光法により調べたところ、いずれもClとNaを多く含むものの、それらの濃度やその他の元素濃度に差異が認められた。また、浮遊物質濃度の挙動などの特性値についても各源泉により違いが認められた。皮膚保湿試験は、実際の入浴シーンに近い足湯への入浴試験と、前腕に温泉試料を塗布する2種類の試験を実施した。皮膚保湿試験においては、千葉科学大学倫理委員会による承認を得た上で、被験者の同意を得て試験を実施した。犬吠埼ホテル足湯入浴後の角層水分量を足甲と下腿部で経時的に測定したところ、足湯入浴後は徐々に角層水分量は低下するが、その低下は対照であるお湯に比較して緩やかで、有意な保湿効果が認められた。また、前腕に3種類の源泉あるいは水を塗布して角層水分量を経時的に測定したところ、対照である水塗布に比較して、犬吠埼ホテルおよび犬吠埼観光ホテルの源泉では角層水分量が高く維持され、保湿効果が検証されたが、太陽の里の源泉では、今回の試験条件では、保湿効果は検証できなかった。これらの挙動は、各温泉に含まれるミネラル成分の多寡と比較的よく一致していた。源泉成分の特性解析や保湿効果の作用機序については未解明であり、今後の研究発展によりさらに犬吠埼温泉の有用性に関するエビデンス蓄積が期待される。
2 0 0 0 中近世移行期の文化と古活字版
2 0 0 0 OA 島嶼の国際比較研究についての若干の問題
2 0 0 0 IR 中国に帰ったタイ華僑共産党員-欧陽恵氏のバンコク、延安、大連、吉林、北京での経験-
- 著者
- 村嶋 英治 鄭 成
- 出版者
- 早稲田大学アジア太平洋研究センター
- 雑誌
- WIAPSリサーチ・シリーズ (ISSN:2185131X)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.1-241, 2012-12-15
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1919年03月07日, 1919-03-07
2 0 0 0 OA ソフトウェア設計の分析・原理・論理
- 著者
- 日野克重
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告ソフトウェア工学(SE)
- 巻号頁・発行日
- vol.1984, no.64(1984-SE-040), pp.73-78, 1985-02-07
- 著者
- 大塚 明子 森 恭子 秋山 美栄子 星野 晴彦
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.41-52, 2015-03-01
本稿では「価値観 ・ 労働観 ・ ライフスタイル等に関する日本と北欧の比較調査研究」の第一次量的調査で取り上げた設問のうち、自尊感情 ・ 対人信頼感 ・ 文化的自己観の3つの心理尺度に焦点を当て、第二次質的調査のインタビューによってその解釈を深めることを試みた。共通して伺えたのは、スウェーデン人が自己及び周囲との相互作用というミクロな焦点化をおこなうのに対し、日本人は一般的な社会というマクロな視点から俯瞰する、という傾向であった。第一次量的調査ではスェーデン人の相互独立性と評価懸念の両立という、文化的自己観に関する先行研究と異なる結果が得られたが、それを整合的に解釈することができたのが最大の成果の1つと考える。なぜ社会人と比べて大学生の方がより「日本人らしさ」、つまり低い自尊感情 ・ 対人信頼感 ・ 相互独立性+高い相互協調性を示すのかについても、社会的に不利な立場が大きな要因であることが示唆された。
- 著者
- Kenta Hirai Kei Nagai Takashi Ono Masayuki Nakajima Tomohiro Hayakawa Yoshinori Sakata Yoshiharu Nakamura
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- Journal of Rural Medicine (ISSN:1880487X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.47-51, 2021 (Released:2021-01-05)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
Objective: Most cases of severe metabolic alkalosis have many causes that may result in renal failure and death. Therefore, these should be treated promptly for successful recovery.Patient: A 61-year-old man was hospitalized due to an acute kidney injury (creatinine level of 4.36 mg/dL) after a 3-month history of anorexia and recurrent vomiting. He had been treated for tuberculosis in the past.Results: Blood gas analysis revealed severe metabolic alkalosis with pH=7.66, HCO3=94 mmol/L, and pCO2=82.0 mmHg. Routine biochemical examination revealed severe hypokalemia (K 2.9 mEq/L) that was associated with prolonged QTc interval (0.52 seconds) on the electrocardiogram. Gastrofiberscopic examination also revealed severe stenosis and ulcerated scarring of the gastric pylorus and severe esophagitis. Intravenous hydration and correction of hypokalemia improved renal function and resolved metabolic alkalosis. An investigation that was repeated after 6 days revealed a creatinine level of 1.58 mg/dL, pH=7.47, HCO3=23.4 mmol/L, K=3.6 mEq/L, and QTc of 0.45 seconds. The patient underwent gastrectomy and adenocarcinoma was observed.Conclusion: We described a resolved case of severe metabolic alkalosis and acute kidney injury in a rural medical setting following conservative management.
2 0 0 0 IR 近藤重蔵論ノート(2)
- 著者
- 梅澤 秀夫 ウメザワ ヒデオ Hideo UMEZAWA
- 出版者
- 清泉女子大学人文科学研究所
- 雑誌
- 清泉女子大学人文科学研究所紀要 (ISSN:09109234)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.69-93, 2014
本稿は、近藤重蔵の思想と行動を、歴史の中にいかに位置づけるかを考えることを課題としている。今回は、まず学問吟味で優秀な成績を収めた近藤重蔵が、寛政七(一七九五)年から九年にかけて、長崎奉行に任命された中川忠英の手附出役(奉行補佐官)として、長崎で勤務した時期の活動について考察した。次に、中川が勘定奉行に転じ、重蔵も江戸に戻って勘定所の支配勘定となり、海防および蝦夷地問題についての意見書を幕府に提出した時期をとりあげ、重蔵の思考と活動について考察した。長崎での活動については、『清俗紀聞』の編纂を中心に、当時幕府が進めつつあった書物編纂事業の一環として考えられること、及び重蔵の考証学者としての能力が最初に活用された事例であることを指摘した。次に、重蔵と蝦夷地との関わりについて考察する前提として、中世以来、蝦夷地がたどった歴史的経緯と近世国家体制に組み込まれてゆくプロセスをおおまかに検討した。それを踏まえ、十八世紀以降、北方地域にロシア勢力が出現し、その脅威に対処するために、幕府内に蝦夷地の直轄・開発を唱える改革派グループが形成され、勢力を拡大していくが、その政策が江戸初期以来の幕府の蝦夷地政策を大きく変更するものであることを指摘した。次に、寛政期における松平定信と改革派との関係、幕府内における強力な反対派勢力の存在を藤田覚氏の研究に依拠しながら、確認した。そして、定信退陣後にプロビデンス号来航を契機として直轄・開発派が、蝦夷地直轄に向けて動き出している状況の中で、重蔵等が江戸に帰着し、重蔵の意見書が提出されており、重蔵はこの幕府内の政治的対立の渦中に自らの意志で身を投じていったことを、重蔵が提出した意見書を検討しながら指摘した。なお、重蔵が寛政十年に幕府の大規模な蝦夷地調査団の一員として派遣され、蝦夷地で見聞・経験した諸問題については、次回にとりあげ、考察する予定である。 This is the second in a series of articles about the position and the role of Kondô Jûzô in Tokugawa intellectual history. This particular paper focuses on his thoughts and activity in the late eighteenth century, from 1795 to 1798 in particular, when he was in his late twenties. In 1795 Nakagawa Tadahide, the newly appointed magistrate of Nagasaki, recruited Kondô Jûzô as one of his assistants since he had been impressed by the remarkable scholarly ability of the young man. When Nakagawa was given a promotion and appointed as a magistrate in charge of the bakufu finance in two years, he took Kondô back to Edo with him and arranged for the latter's appointment as a junior official working for his office. This paper takes up the edition of Shinzoku Kibun, a book on customs and folk culture of Qing (Shin) China, carried out under the supervision of Nakagawa. This paper points out that Kondô played a major role in editing the book, making full use of his knowledge and ability in Chinese studies. It also points out that the edition of the book could be viewed as a part of a project of editing various books that the bakufu was carrying out at the time. Next, the paper sketches the history of Ezochi, the northern boundary area where Ainu people were living, and the developments and changes in the bakufu's policies about the management of the area from the early Tokugawa period on. Then it focuses on the argument exchanged between groups of bakufu officials in the late eighteenth century about how to deal with the people and the land of the area. One of the groups of officials, who were on alert against Russian policies of extending its territory into north-east Asia, made a plan to put Ezochi under the bakufu's direct control and develop agriculture and other industries there. This paper points out that such a plan was in conflict with the bakufu's traditional policy of dealing with the land of Ainu separately from the other parts of Japanese territory, and that the group of officials were inevitably oriented toward the reform of the traditional policy. The news about the incursion of the Providence, a British warship, into the Funkawan Bay of Ezochi, in 1796 encouraged this group of officials to promote a movement aiming at the realization of their plan. At the time Matsudaira Sadanobu, who had kept the group not to be too radical, had already resigned from the office of the senior councilor. According to the research of Fujita Satoshi on the bakufu's politics of this period, those bakufu officials who opposed to such a reforming policy banded together and tried to disturb the movement of the reformers. Against such controversy between groups of the bakufu officials as the backdrop, this paper analyzes a written proposal that Kondô submitted to the bakufu councilors at the time and points out that he intentionally participated in the argument on the side of the reformers.
2 0 0 0 身体化の意識性と共感性の関係
- 著者
- 大藤 弘典
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.84, pp.PM-039-PM-039, 2020
<p>シミュレーション理論によると,他者の心を理解し共有する共感の過程では,相手の心の状態を心内で真似る処理が行われていると考えられており,そのために必要な能力として,他者の身体を自分の身体のように認識する身体化が想定されている。こうした「意識的な身体化」の能力が高い者は,物語を読むといった想像場面において,登場人物の体験を感覚的に捉えることで,その人物の感情を理解することにも優れると考えられる。だが,他者の涙を見てもらい泣きをする場合のように,共感に関わる身体化は意識的に行われるだけでなく,無意識にも起こり得る。本研究では,身体化能力の意識性と共感力の関係を明らかにすることを目的として,(1)意識的な身体化能力と無意識的な身体化能力の間に関連がある,および(2)場面(想像的 vs 知覚的)に応じて2種類の身体化が共感過程に選択的に関与する,という2つの仮説を検証した。検証の結果,両仮説とも支持されなかった。一方で,補足分析から身体化を通した共感の過程で性差が示唆された。</p>
2 0 0 0 伊能忠敬全国測量の諸問題
- 著者
- 星埜 由尚
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.2, pp.227-240, 2020
- 被引用文献数
- 4
<p> The map of Japan drafted by Inoh Tadataka is considered to be the earliest produced from a scientific survey. The descriptions of longitude and latitude are based on astronomical observations, and Inoh's nationwide survey has been considered to be the origin of modern surveys in Japan. However, he did not succeed in determining longitude. Although he had knowledge of a spherical earth, the results of his survey were projected on a plane, not on a spherical surface. The parallels of latitude drawn on his maps are based on an accurate astronomical survey he carried out, but the meridians on his maps are absolutely inconsistent. His survey method also combined traverse and intersection surveys without control points. Therefore, his nationwide survey cannot be considered to be representative of a survey carried out in the modern period. There are many open traverse lines on his maps. These lines generally extend to temples and shrines, although they are not effective for improving the accuracy of the survey. Because temples and shrines might have been important public facilities at that time, the Tokugawa shogunate government probably requested information concerning their locations. He carried out a nationwide survey ten times, but he could not survey the northern half of Ezo island (Hokkaido). It is said that Mamiya Rinzo, who studied survey technology under Inoh Tadataka, surveyed Ezo island and submitted his survey data to Inoh Tadataka, therefore, Inoh's map of Ezo island might be entirely based on Mamiya's data. Further studies are necessary because Mamiya's survey has not been clarified.</p>
2 0 0 0 OA 秦檜の講和政策をめぐって
- 著者
- 衣川 強
- 出版者
- 京都大學人文科學研究所
- 雑誌
- 東方學報 (ISSN:03042448)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.245-294, 1973-09-20
2 0 0 0 OA 福井藩医師岩佐純及び橋本綱常履歴書
- 著者
- 保科 英人
- 雑誌
- 福井大学医学部研究雑誌 (ISSN:13488562)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.1-10, 2017-12-26
2 0 0 0 OA 乳腺Ki-67 計測定量化のための全自動画像解析システムの開発
- 著者
- 山下 慶子 喜友名 朝春 山口 雅浩
- 出版者
- 日本医用画像工学会
- 雑誌
- Medical Imaging Technology (ISSN:0288450X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.124-132, 2015 (Released:2015-05-26)
- 参考文献数
- 17
免疫染色を用いた病理診断において,Ki-67陽性率は良性・悪性の鑑別,悪性度や予後の推定などの目的で広く用いられている.免疫染色画像における細胞核を解析するシステムとして,whole slide image(WSI)の解析を人手を介することなく,自動で解析領域を選択し,画像パターンごとに検出条件設定を必要としない方法を提案する.提案手法を組み込んだ免疫染色画像計測システムを開発し,本システムによって算出されたKi-67陽性率は,目視カウントによる計測と相関が高く,解析法として有効であることが示された.
2 0 0 0 IR <研究ノート>恋歌の消滅 : 『百人一首』の近代的特徴について
- 著者
- 岩井 茂樹
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.215-237, 2003-03-31
『百人一首』の研究は近年盛んになりつつあるが、近代(明治時代以降)の享受の実態についてはほとんど行われていない状態である。本論稿は、近代に特徴的に見られる『百人一首』の恋歌に対する非難の実態と、そのような論調により作り変えられた恋歌を排除した『百人一首』に関するものである。加えてその原因について考察を行った結果、①百人一首歌留多の興隆と受容形態の変化、②旧派歌人を中心とした恋歌の消滅、がその背景にあることがわかった。
2 0 0 0 IR 恋歌の歴史--江戸時代を中心に
- 著者
- 岩井 茂樹 Iwai Shigeki イワイ シゲキ
- 出版者
- 総合研究大学院大学文化科学研究科
- 雑誌
- 総研大文化科学研究 (ISSN:1883096X)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.5-41[含 抄録], 2005-08