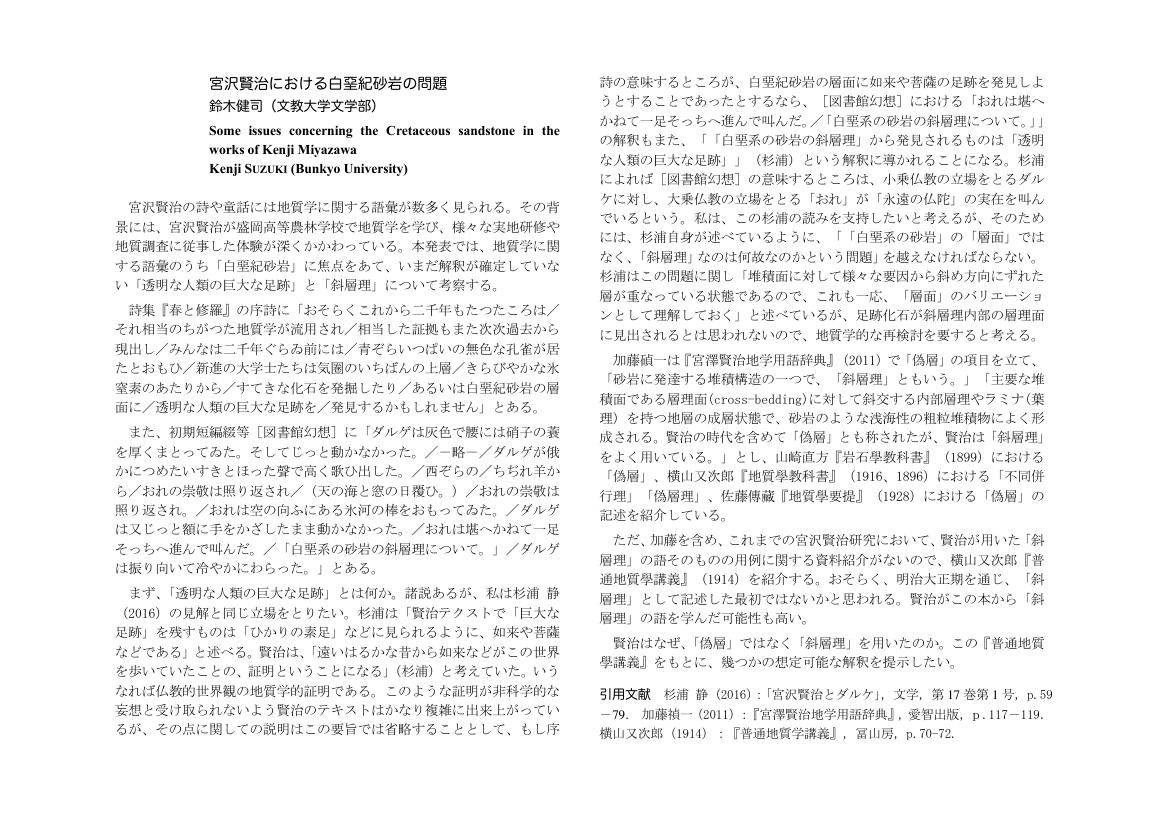2 0 0 0 OA 携帯電話GPS端末を利用したアライグマの行動追跡の実用性について
- 著者
- 山﨑 晃司 佐伯 緑
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.47-54, 2012 (Released:2012-07-18)
- 参考文献数
- 6
GPS機能付き携帯電話(FOMA)端末に増設バッテリーパックを接続した上で首輪ベルトに包埋を行い,定置試験と共に,アライグマ野生個体への装着を行った.首輪システムの総重量は215 gで,VHF発信器を加えた場合のシステム総重量は300 gであった.定置試験(n=3)での測位データ送信のための通信成功率は99.5~100%で,測位誤差は12.0~16.5 mであった.野生個体への装着例(n=7)では,電池充電が適正に行われた場合の平均稼働日数で25.3日間であったが,計算上より短かった.通信成功率は夜間(59.9%)と日中(38.0%)で有意に差があった.夜行性のアライグマは,昼間は遮蔽物(樹洞,土穴,人家屋根裏)で休むため,通信圏外の状態になる割合が高くなることが考えられた.ただし夜間でも,通信成功率は定置試験に比較して低かった.アライグマ首高の地表付近では,携帯通信網の電波状態が安定しない可能性が考えられた.
2 0 0 0 OA 上海の日本食文化 : メニューの現地化に関するヒアリング調査報告
- 著者
- 岩間 一弘 イワマ カズヒロ Kazuhiro IWAMA
- 雑誌
- 千葉商大紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.1-54, 2013-09
2 0 0 0 OA 連帯の規範と<重度知的障害者> : 正義の射程から放逐された人々
- 著者
- 田中 耕一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.82-94, 2009-05-31 (Released:2018-07-20)
本稿では,<重度知的障害者>を包摂する連帯規範の理論的探究に向かうため,(1)福祉国家の理論的基礎を支えてきたリベラリズムの規範理論において,<重度知的障害者>がなぜ,どのように,その理論的射程から放逐されてきたのかを,リベラリズムにおける市民概念の検討を通して考察し,(2)連帯規範の再検討における<重度知的障害者>という視座の意義について検討を加え,(3)<重度知的障害者>という視座における連帯規範の再検討によって,どのような理論的課題が浮上するのか,を検討した.リベラリズムがその理論的射程から放逐してきた<重度知的障害者>を連帯規範の再検討のための視座におくことには,それがリベラリズムの規範理論の限界点と課題を照射しつつ,連帯規範をめぐる新たな公共的討議の可能性を開示する,等の意義を見いだすことができる.また,この<重度知的障害者>という視座による連帯規範の問い直しの作業は,リベラリズムの市民資格の限定解除を求めつつ,現代の政治哲学における「ケアと正義」の接合,併存をめぐる理論的課題に逢着することになるだろう.
2 0 0 0 腹部脂肪吸引術後に脂肪塞栓症候群を発症した 1 例
- 著者
- 佐々木 誉詩子 内 博史 古江 増隆
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.5, pp.459-462, 2017-10-01 (Released:2017-11-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
29 歳,女性。初診 13 日前に両側腹部脂肪吸引術を受けた。初診 4 日前に発熱,両側腹部の発赤で蜂窩織炎と診断された。初診 3 日前に同部位に水疱が出現し急激に拡大した。初診前日,咳嗽が出現し,当日,呼吸困難感を訴え,肺塞栓症疑いで当院に救急搬送となった。初診時,バイタルサインの異常と両側腹部に手拳大の壊死組織を認めた。血液検査では白血球・CRP 上昇,Hb 低下,凝固異常などがみられた。心エコーで肺動脈が拡張していたが CT で明らかな血栓はなく,経過からは脂肪塞栓による肺塞栓症と考えた。敗血症性ショックを疑い腹部の緊急デブリードマンを行ったが,塗抹・培養とも菌は検出されなかった。肺高血圧は軽減し経過観察していたが,その後急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) を発症し,凝固障害とともに治療し軽快した。脂肪塞栓症候群は脂肪吸引術後にもまれに起こる重大な合併症であり,処置後の患者は注意深く観察し,発症の際は速やかな診断・治療が必要となる。
2 0 0 0 OA 繊維製品の耐用年数に関する研究
- 著者
- 安田 武 山階 克子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.5, pp.278-287, 1968-07-15 (Released:2010-09-30)
消費財の耐用年数については, 主として営業用の減価償却の都合上, 国税局によって規定されたものがある.また, 銀行や火災保険会社などでその業務の都合上調査した資料があるが, これらに繊維製品は数点しか含まれておらず, それ以外に公表されたものはほとんど見当らない.特に戦後の消費ムードによって国民の消費財の耐用に関する考え方が変化しつつあるので, 最近の繊維製品の耐用年数についてその実態を明らかにすることは非常に重要であると思われる.著者らは, 本学学生およびその家族を対象に, 調査人員623名について, 家庭で実用する131品種の繊維製品の平均耐用年数, 実際に使用する日数, 使わなくなる理由を調査した.繊維製品の耐用年数は, 短かいものでストッキングの2~3週間から長いものでは蚊帳の12.6年に到るまで, はなはだ広範囲にわたっている.消費ムードによって全体的にこれらの耐用年数が短かくなる傾向はあるとしても, このような品種別の大きい開きは無視できないと考えられる.消費科学の研究課題として, 強さ, 変色など種々の特性がとりあげられているが, 耐用年数に着目して繊維製品の消費特性を考えてみると, 品種によって強さの要求されるもの, あるいは変色しないことを要求されるものなど非常に特徴的な傾向がみられる.さらに, 科学的特性がいかにそなわっていても, 型の陳腐化によって耐用年数の決定される品種もはなはだ多い.
- 著者
- Satoshi Yamagishi
- 出版者
- Yamashina Institute for Ornitology
- 雑誌
- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2-3, pp.96-102, 1982-12-20 (Released:2008-11-10)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 5 10
A total of 197 Bull-headed Shrikes Lanius bucephalus were examined for this study. Out of 756 nestlings banded for a population study, 38 were re-captured more than once and examined. Their plumage was checked for the presence of buff-tipped greater primary upper coverts (BTGPUCs), and the process of replacement of the buff-tipped coverts was followed. Similar examinations of BTGPUCs were also made on 6 juveniles and on 153 other captured birds whose age could not be established. At least some proximal juvenal BTGPUCs, almost without exception, were retained until the second fall molt. Thus, the presence of these juvenal feathers in the greater primary upper covert (GPUC) series is a reliable criterion for designating first-year birds in this species.
2 0 0 0 OA 航路標識の歴史
- 著者
- 石坂 幸夫
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.4, pp.176-179, 1992-04-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 説明実践を支える教授・学習研究の動向
- 著者
- 山本 博樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.46-62, 2017-03-30 (Released:2017-09-29)
- 参考文献数
- 85
- 被引用文献数
- 3
本稿の目的は,2015年7月から2016年6月末までの1年間を中心に,教授・学習研究の動向を概観し,今後の展望を考察することである。授業の中ではたくさんの教師が説明実践に本質的な問題を抱えていることに加えて,説明実践にかかわる問題が教授・学習領域に要請された重要な研究課題となっている。それ故,説明実践に焦点をあてて,説明実践の支えになると考えられる教授・学習領域の1年間の動向を概観する。概観にあたっては,説明実践を支援モデルの観点から捉えて,次の5つの節に分けて検討したい。それらは,1) 授業での説明の役割,2) 授業中の理解不振・学習不適応,3) 説明方略・理解方略,4) 教科に即した説明実践,5) 説明力の育成,である。これらの概観を過去30年にわたる研究動向の中に意味づけた上で,今後の展望を示す。最後に,説明の原点に立ち返り,説明実践が抱える難題を示し,この解決に資する研究推進上の原則を示したい。本稿を通して,教授・学習研究が説明実践の支えになるという可能性を提示する。
2 0 0 0 OA 諸国名所百景 尾州名古屋真景
2 0 0 0 OA 超音波照射が干し椎茸の水戻しに及ぼす影響
- 著者
- 木村 友子 菅原 龍幸 福谷 洋子 加賀谷 みえ子
- 出版者
- 社団法人日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.585-593, 1994-07-15
- 被引用文献数
- 7
Dried shiitake mushrooms were rehydrated with ultrasonic-irradiation in search for rational rehydration methods. Its effects on the texture properties and the preference test were studied. The following results were obtained ; water absorption by the shiitake mushrooms, the color of yellowing of the rehydration liquid and its browning were greater with ultrasonic-irradiation than in the control without the irradiation. The irradiated shiitake mushrooms had less hardness and gumminess and were softer. Irradiation time was 20 min and total immersion time was 2h for Jyodonko adn 1h for Jyokoshin at 5℃ and 25℃ which are within a suitable rehydration range. Under these conditions, water absorption reached 90% of the maximum and the shiitake mushrooms scored high preference points in such properties as softness and gumminess. Irradiation slightly affected on the content of RNA and the composition of 5'-GMP, 5'-AMP, 5'-UMP, 5'-CMP and free amino acids in steam-cooked shiitake mushrooms.
- 著者
- 山口 紀子
- 出版者
- お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科
- 雑誌
- 人間文化創成科学論叢
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.115-124, 2019-03-31
The Kyrgyz Republic is regarded as "the Isolated Learning Japanese Circumstance" since it has few chance of human and economic interaction with Japan. In that situation, it is challenging to get the pragmatic opportunities to study or work using Japanese for most of Japanese learners. Also, it seems difficult to continue to learn and hesitate from having education of Japanese language in Kyrgyz. This survey investigated motives for learning Japanese and elements affected to sustainable motivation of life-long learners. The results of factor analysis suggested that (a) they have five types of motives for learning such as 〈desires for living in abroad〉〈interests in Japanese language and culture〉〈self-esteem and selfimprovement 〉〈development personal relationship and challenges to new domain〉and〈hobby and entertainment〉, (b) the lack of pragmatic opportunities and difficulties to study the language may affect to motivation low. On the other hand, the results of covariance structure analysis shows that (c) not only pragmatic motives such as〈desires for life abroad〉 but also non-pragmatic motives such as 〈development personal relationship and challenges to new domain〉affects to sustainable motivation high. It suggests how teachers can support learners' sustainable motivation in" Isolated Circumstances".
2 0 0 0 OA 酩酊症を呈した胃カンジダ症の1例
- 著者
- 施 清源 杉山 貢 衛藤 俊二 土屋 周二 長岡 英和
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.6, pp.1318-1321, 1982-06-05 (Released:2007-12-26)
- 参考文献数
- 19
2 0 0 0 OA 宮沢賢治における白堊紀砂岩の問題
- 著者
- 鈴木 健司
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第123年学術大会(2016東京・桜上水) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.085, 2016 (Released:2017-04-25)
2 0 0 0 OA 高頻度抗原KANNOに対する同種抗体の血清学的性状と臨床的意義
- 著者
- 川畑 絹代 安田 広康 土田 秀明 伊藤 正一 菊地 正輝 常山 初江 内川 誠 大戸 斉
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.478-483, 2011 (Released:2012-01-06)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
抗KANNOは1991年に福島医大病院で遭遇した高頻度抗原に対する抗体で,既知の抗体にはその反応性が一致するものが無かった.発端者に因み,この抗体を抗KANNO,対応抗原をKANNO抗原と名付けた.KANNO抗原発見に関わった福島医大病院2症例と山形県および宮城県赤十字血液センターで同定した抗KANNO 12例,計14例について反応性,臨床的意義を検討した. 抗KANNOを保有する14例のうち13例が妊娠歴のある女性であり,輸血よりも妊娠によって産生されやすい抗体であると考えられる.抗KANNOは高力価低親和性(HTLA)抗体の特徴を示し,類似した反応性を持つ抗JMHとは,AET処理赤血球と反応する点で鑑別できる.現在まで,抗KANNOによる溶血性輸血副作用(HTR)や胎児・新生児溶血性疾患(HDFN)の報告はなく臨床的意義は低いと考えられるが,さらに症例を蓄積する必要がある.
- 著者
- Young-In Hwang Ki-Song Kin
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.82-85, 2018 (Released:2018-01-27)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3
[Purpose] The purpose of this study was to investigate the effect of pelvic tilt angles and lung function in participants performing pelvic tilts on a ball. [Subjects and Methods] Eighteen subjects participated in this study. While they performed pelvic tilt on sitting at a ball, the peak expiratory flow (PEF) and forced expiratory volume in one second (FEV1) were measured at 10 degrees of anterior and posterior pelvic tilt, respectively, and neutral position. The repeated measure ANOVA was performed, and the Bonferroni correction was used for post-hoc analysis. [Results] The PEF of the participants was significantly higher at neutral position, compared with an anterior pelvic tilt at 10 degrees. The FEV1 was also higher in neutral position, compared with anterior and posterior pelvic tilt. [Conclusion] This study underlines the need for the standardization of the FVC testing protocol for positioning the pelvic angle in a neutral position in patients with respiratory disorders to promote reliable interpretation of intervention outcomes.
2 0 0 0 OA 「帝国」概念の思想史的研究
本研究の目的は、18世紀末から19世紀中葉にかけて「帝国」ということばを用いた日本知識人における自他認識の転回に光をあてることである。「帝国」は古典的な漢語ではなく、18世紀末に蘭学者が、オランダ語keizerrijkから翻訳した新しいことばである。日本知識人の多くは、「帝国」のステータスを、「王国」や「公侯国」といった他のいかなる君主国よりも優越していると考えた。儒学的教養を身につけたこれら知識人は、「皇帝」が他の君主たちよりも優越していることを知っていたので、彼らは、中国古典に見いだせないこの新奇なことばを、たやすく受け容れることができたのである。彼らにとって幸いであったのは、ヨーロッパにおいて刊行された多くの地理書が、「日本は帝国である」と叙述していたことである。翻訳書を含むこれらの書籍おいて、こうした記載を読んだ日本知識人は、日本の優越性と独立性を確信するようになった。日本排外主義が、海外の書籍によって形成されたことは、まことに皮肉であったと言える。
2 0 0 0 OA 『日本書紀』仏教伝来記事と末法思想(その二)
- 著者
- 吉田 一彦
- 雑誌
- 人間文化研究 (ISSN:13480308)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.186-175, 2008-06-25
2 0 0 0 OA 霜田史光研究落穂拾い(その1)
- 著者
- 竹長 吉正
- 雑誌
- 白鴎大学論集 = Hakuoh Daigaku ronshu : the Hakuoh University journal (ISSN:09137661)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1/2, pp.63-101, 2015-03-01
2 0 0 0 IR ケータイ小説における作者と読者の関係性 : ケータイ小説が生まれる空間の考察
- 著者
- レバリアーティ ガブリエレ
- 出版者
- 青山学院大学
- 雑誌
- 青山社会情報研究 (ISSN:18837638)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.9-23, 2014
The main purpose of this paper is to investigate a possible scenario in the relationship between the author and reader in the digital era using Japanese mobile novels as a concrete example. With the ongoing debate over the increasing popularity of the digitization of books, an analysis of the phenomenon of mobile novels (keitai shosetsu) in Japan may help to broad our understanding of the future of book publications, and of the literature, in general, during this era of new media. The important changes occurring in the relationship between authors and readers are also investigated.