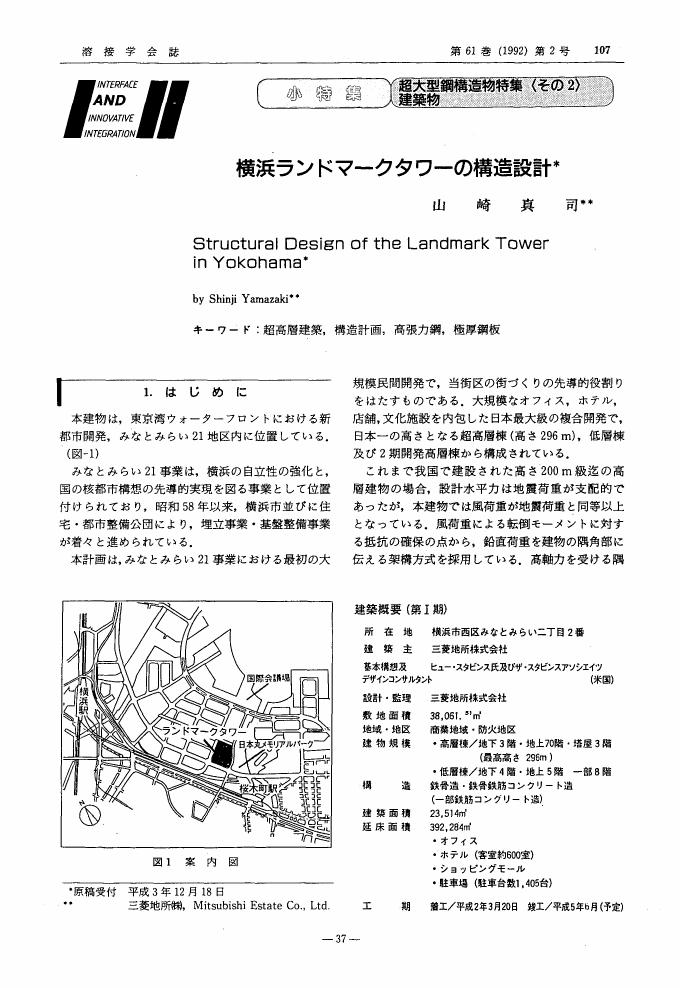- 著者
- 伊藤 結香 山崎 真湖人
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究. 研究発表大会概要集 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.94-95, 2007-06-20
This paper explains a method of contextual research which professional designers can easily apply. We designed a set of worksheets based on the method of Contextual Design, in order to provide framework for the research and a common basis of the collaborative analysis. We tested the worksheets in a workshop, in which participants with different backgrounds researched a coffee shop and created design ideas, inspired by what they found in the research. In the workshop, it was suggested that the worksheets facilitate the designers in the process of research and ideation, and that we can obtain the seed of design idea through the contextual research and transfer it onto a different area of application.
- 著者
- 山崎 真理子 水野 邦夫 青山 謙二郎
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.173-180, 2007
The modeling effect on eating means that the more models eat the more participants eat. Herman, Polivy, & Roth (2003) proposed that participants make the amount of food they consume conform to the consumption of others in order to avoid being seen by others as eating excessively. In this study, in order to create a situation in which participants believe no one can know how much they eat, we did not use the usual model. Instead, feigned leftover food was shown to participants before the tasting test. This leftover food (in amounts large or small) was expected to give participants information on how much other participants had eaten. In one condition, participants were misled to believe that the experimenter could not find out how much food the participants had consumed; in another condition, they were not misled. In the former condition, regardless of how much others eat, participants should eat as much as they like, believing that no one can learn of the amount, they consume. Contrary to the prediction, the modeling effect arose in both conditions. These results indicate that the modeling effect cannot be explained entirely by self-presentational concern regarding others.
- 著者
- 大塚 泰介 山崎 真嗣 西村 洋子
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.167-177, 2012-07-30
- 被引用文献数
- 2
水田の多面的機能は、そこに生息する生物間の相互作用に負うところが大きい。水田にキーストーン捕食者である魚を放流して魚を放流しない水田と比較すれば、対照区つきの隔離水界実験(メソコスム実験)になり、水田の生物間相互作用を解明する上で有効である。水田にカダヤシを放流しても、カに対する抑制効果が見られないことがある。カダヤシはカの幼虫・蛹のほかに、その捕食者や競争者も食べるので、捕食による効果の総和が必ずしもカを減らす方向に働かないためである。メコン川デルタの水田に3種の魚を放し、魚を放さない水田と生物群集を比較した実験では、ミジンコ目が減少し、原生動物とワムシが増加し、水中のクロロフィルa濃度が増加するという結果が得られている。水田にニゴロブナの孵化仔魚を放流した私たちの実験でも、これと類似の結果が得られた。ニゴロブナの後期仔魚および前期稚魚はミジンコ目を選択的に捕食し、ほぼ全滅させた。すると放流区では対照区よりも繊毛虫、ミドリムシなどが多くなった。また放流区では、ミジンコ目の餌サイズに対応する植物プランクトン、細菌、従属栄養性ナノ鞭毛虫などの数も増加した。メコン川デルタと私たちの結果は、ともに典型的なトップダウン栄養カスケードとして説明できる。また、魚の採食活動が、底泥からの栄養塩のくみ上げや底生性藻類の水中への懸濁を引き起こしたことも示唆される。これとは逆に、コイの採食活動によって生じた濁りが、水田の植物プランクトンの生産を抑制したと考えられる事例もある。こうした実験の前提となるのは、魚が強い捕食圧を受けていないことである。魚に対する捕食圧が大きい条件下での水田生物群集の動態は、今後研究すべき課題である。
4 0 0 0 OA 「大学の自治」の思想と慣行
- 著者
- 山崎 真秀
- 出版者
- The Japanese Association of Sociology of Law
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.1966, no.18, pp.51-85,226, 1966-04-20 (Released:2009-04-03)
- 参考文献数
- 57
After the war, Japanese universities were reorganized into an institution not only for prosecuting academic researches as before but also for giving the people higher education in order to bring up “citizens”, and the number of universities has remarkably increased as compared with prewar days. In particular, recent economic development of our country has brought the growing attention of the people to university and the growing number of high school graduates who go on to universities. This tendency is also under the influence of the constitutional guarantee of the right to receive education. Likewise, the government has adopted, as one of its main policies, the policy of promoting the scientific technique and cultivating the people's ability, so that the problems of university system and education have often aroused public attention and discussion. Under such social condition, a matter which is always and hotly discussed is “university autonomy”.“University autonomy” in Japan had developed as a “custom” at the prewar Imperial Universities, the basic idea of which gave the faculty meeting an autonomy as to its human affairs, so as to maintain freedom of research. But after the Taisho era, when reformative thoughts such as socialism developed, the government authority hand in hand with the militarists exerted pressure upon the thoughts and opinions of progressive scholars, and by so doing frequently violated “university autonomy” as well as “academic freedom”.Through such experience before the war, we acquired after the war the constitutional guarantee of “academic freedom” and legal guarantee for the university's control over the human affairs of its teaching staff. However, “university autonomy” remains to be and is prevailingly considered to be a “custom” which has been practiced from the prewar days.Now, what is the reason why many troubles have happened in succession over this “university autonomy”, in spite of the constitutional guarantee of “academic freedom” and partial legal guarantee of “university autonomy”? It is worthy of discussion. Although many reasons may be pointed out, the author thinks the main reason may be found in the fact that the “university autonomy” has seldom become an object of scientific study because it has been a “custom” in the exact meaning, and that we have lacked in historical studying about the “Imperial Universities” which established the “custom”.On this hypothesis, the author discussed the development of the thought and custom of “university autonomy” in Japan before the war and the historical function of the Imperial Universities as the source of such thought and custom. The summary of the article is as follows.Section I. To make out the meaning and the background of the subject, the author explains the transition from the constitution and the underlying principle of it under the prewar Meiji Constitution to those under the postwar Constitution of Japan, and the difference of the constitutional guarantee and treatment of “academic freedom” and “university autonomy” under those two Constitutions.Section II. The birth of the University of Tokyo as the first modern university in Japan; its reorganization into the “Imperial University” by the first Education Minister, Arinori Mori, in 1886 when the Ordinance of Imperial University and other school ordinances were framed; the process in which this “Tokyo Imperial University” came to be established as a model to subsequent Japanese universities and university institution; these matters are sketched.
4 0 0 0 OA 融雪剤中毒が疑われた2005-2006年冬季北海道における野鳥の大量死(病理学)
- 著者
- 田中 智久 田上 銀平 山崎 真大 高島 郁夫 迫田 義博 落合 謙爾 梅村 孝司
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.6, pp.607-610, 2008-06-25
- 被引用文献数
- 1 2
2005年度冬季に北海道で大量死した野鳥のうちの13羽について,病理検査とインフルエンザ,ウエストナイル両ウイルスの検出を行った.病理検査では全身性の急性循環障害が共通して認められ,ウイルス検出は陰性であった.これら検査結果,冬季限定の発生状況および文献検索から,融雪剤中毒の可能性が高いと考えられた.また,融雪剤を投与した鶏雛は急性経過で死亡し,野鳥と類似の病変を示した.鶏雛で血漿Na濃度の上昇があったことから,野鳥の死因の確定には罹患症例の電解質検査が必要と考えられた.
3 0 0 0 OA 横浜ランドマークタワーの構造設計
- 著者
- 山崎 真司
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.107-112, 1992-03-05 (Released:2011-08-05)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 山崎 真治 藤田 祐樹 片桐 千亜紀 黒住 耐二 海部 陽介
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.1, pp.9-27, 2014
- 被引用文献数
- 2
2012~2013年に沖縄県南城市サキタリ洞遺跡調査区IのII層(約16400~19300 BP[未較正])を発掘し,人骨2点(臼歯1点と舟状骨1点)とともに39点の断片化した海産貝類を検出した。先に報告したI層出土のものと合わせ,計47点にのぼる海産貝類は,人為的に遺跡近辺に運搬され,埋没したものと考えられる。II層由来のマルスダレガイ科(マツヤマワスレ[<i>Callista </i><i>chinensis</i>]・ハマグリ類[<i>Meretrix</i> sp. cf. <i>lusoria</i>]),クジャクガイ[<i>Septifer bilocularis</i>],ツノガイ類["<i>Dentalium</i>" spp.]について組成や形状,割れ方について記載するとともに,微細な線条痕および摩滅・光沢を観察したところ,マルスダレガイ科の破片には定型性が認められ,二次加工と考えられる小剥離痕が高い頻度で見られた。また,特定の部位に使用痕や加工痕と推定できる摩滅・光沢や線条痕が観察できることから,少なくともその一部は利器として使用されたと考えられる。また,クジャクガイの一部にも,使用痕と見られる線条痕や損耗が観察できた。ツノガイ類は,産状から装飾品(ビーズ)として用いられた可能性が高く,その一部には人為的な線条痕が観察できた。以上のことから,II層出土の海産貝類の少なくとも一部は,利器・装飾品を含む道具(貝器)として使用されたものと考えられる。II層出土の人骨と合わせて,こうした貝器の存在は,サキタリ洞での人類の活動痕跡が,少なくとも16400~19300 BP にまで遡ることを示している。
3 0 0 0 OA 統合メタボロミクスによる有用植物資源の開発
- 著者
- 中林 亮 浅野 孝 山崎 真巳 斉藤 和季
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.5, pp.313-320, 2014-05-01 (Released:2015-05-01)
- 参考文献数
- 23
2 0 0 0 OA RNA分解酵素 生理的役割を中心として
- 著者
- 山崎 真狩
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.9, pp.555-564, 1975-09-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 48
- 著者
- 山崎 真悟 中川 洸志 植田 広樹 田中 秀治
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.577-584, 2023-10-31 (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 13
目的:横須賀市の病院外心停止(以下OHCA)傷病者に対する,現場出発前後のアドレナリン(以下ADR)投与のタイミングと自己心拍再開(以下ROSC)の関連を検討すること。方法:横須賀市消防局のウツタインデータを用い,2013年1月1日〜2022年4月30日までのOHCAでADRを投与された傷病者を対象とした。ADR投与のタイミングを現場出発前投与群(以下,現発前群)と現場出発後投与群(以下,現発後群)の2群に分類し,多変量ロジスティック回帰分析によりADR投与のタイミングとROSCの関連を推定した。結果:対象のOHCA傷病者は1,122例,現発前群は483例,現発後群は639例であった。多変量ロジスティック回帰分析の結果,現発前群は現発後群と比較しROSCと有意な関連を示した(AOR 2.03,95%CI 1.31-3.16)ほか,現場滞在時間が4分延長していた。結論:現発前の早期ADR投与は早期ROSCにつながる一方で現場滞在時間の延長も示した。MC協議会は救急隊員に対して早期ADR投与の重要性について教育が必要である。
2 0 0 0 OA 精神科診断において操作的診断基準は信頼性問題を解決したか
- 著者
- 山崎 真也
- 出版者
- 日本医学哲学・倫理学会
- 雑誌
- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.79-88, 2009-10-01 (Released:2018-02-01)
In this article, I examine why disagreements of diagnosis are likely to occur in psychiatric diagnosis. This problem (which I call the "reliability problem") raises the question of whether psychiatry might have real objectivity. If psychiatric doctors (specialists) give different diagnoses to the same patient, the patient would justly doubt the objectivity of the diagnoses. In addition, our expectation that psychiatry and its classification system relates to the objective world would be undermined, since the standard of classification seems to be liberally interpreted by each diagnostician. This problem has been addressed by the employment of so-called "operational diagnostic criteria." However, the following problems remain: (a) there are different operational criteria systems; (b) if several different operational criteria systems are at once applied to the same patients group, the proportions of patients with a disease vary depending on the criteria systems; and (c) because it is not shown that a particular criteria system has an advantage and validity over other criteria systems, there is no rationale for regimenting a particular criteria system. In other words, only one operational criteria system must be used uniformly by all diagnosticians before the reliability problem can be truly resolved, but this is not realistic at present. Since each diagnostician can choose any criteria system according to their preference, the reliability problem reoccurs regardless of the introduction of operational criteria. We need to continue to inquire into the reliability problem and the objectivity of psychiatry.
2 0 0 0 OA 急速経口免疫療法を施行した鶏卵アレルギーの成人例
- 著者
- 山崎 真弓 磯崎 淳 田中 晶 安藤 枝里子 中村 陽一 栗原 和幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.1181-1184, 2017 (Released:2017-11-11)
- 参考文献数
- 17
症例は26歳,女性.幼少期より,鶏卵の誤食による誘発症状を認めていた.治療の希望があり,急速経口免疫療法の目的で当院に入院した.二重盲検負荷試験で陽性を確認し,オープン法による閾値決めを行った.生卵白乾燥粉末を症状誘発閾値の1/10量(3.0mg)より1.2倍ずつ増量し,5回/日で摂取した.1gに達したところでスクランブルエッグ8gに変更し,その後は1.5倍ずつ増量した.治療18日目に目標の鶏卵1個分(60g)に達した.治療中に蕁麻疹や軽い呼吸困難などの誘発症状を2回認めたが,抗ヒスタミン薬を内服して症状は消失した.鶏卵摂取後の運動誘発試験は陰性,鶏卵入りの加工品を摂取しても誘発症状は認めなかった.現在,1日に鶏卵1個を摂取する維持療法を継続中であり,2年の経過で誘発症状を認めていない.小児期に耐性獲得できない成人に対しての急速経口免疫療法は,選択肢として考慮される治療法である.
2 0 0 0 植物二次代謝のゲノム進化に学ぶ生合成デザイン
- 著者
- 山崎 真巳
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.7, pp.671-673, 2019 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 8
最近急速に進んだゲノム科学技術の発展により、植物における有用アルカロイド生合成についても、その特異な物質代謝がどのように進化してきたかに関するゲノムレベルでの解明が進んでいる。筆者らが明らかにしてきたアルカロイド生産の方向決定ステップを触媒する酵素の分子進化、ならびに毒性アルカロイドを生産する植物の自己耐性の分子進化について紹介し、今後の新しい生合成のデザインを目指した展開について説明する。
2 0 0 0 IR 『平家物語』における物語の変容と和歌の多義性 - 「日本文学概論」での実践報告 -
- 著者
- 山崎 真克
- 出版者
- 比治山大学・比治山大学短期大学部
- 雑誌
- 比治山大学・比治山大学短期大学部教職課程研究
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.111-117, 2019-03
2 0 0 0 OA 児童虐待の歴史的背景と定義
本稿は,児童虐待の歴史的な変遷および児童虐待の定義について概観する.児童虐待は,わが国においても1990年代以降は特殊な家族環境で発生する問題ではないことが広く認識されるようになった.児童虐待問題は,歴史的な変遷を経て関連法が大きな変革期を迎えている.児童虐待は諸外国ではChild AbuseとChild Maltreatmentの両者の用語が用いられているが,Child Maltreatmentは80年代に生態学的な観点から児童虐待を捉えることが提唱された用語でChild Abuseより広く使われている.子どもの心理社会的な発達は,親だけではなく子どもの取り巻く環境からの影響は大きく,今後はChild Maltreatmentの概念の導入や生態学的な研究が児童虐待問題に必要となってくると考えられる.
1 0 0 0 OA 北海道新産のゴハリマツモ(マツモ科)と道内におけるマツモ属の極めて稀な結実記録
- 著者
- 山崎 真巳
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.1, pp.47-56, 2002-01-01 (Released:2003-02-13)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 2 2
A molecular biological approach was applied to the study of diversity and regulation of secondary metabolism in medicinal plants at various levels. For the inter-species diversity, RFLP (restriction fragment length polymorphysm) and RAPD (random amplified polymorphic DNA) analyses of genomic DNA were performed on the plants, belonging to the same genus or family and containing related compounds. Phylogenetic trees of lupin alkaloid containing plants and other medicinal plants, based on RFLP and/or RAPD profiles, showed the relationship between the diversities in genomes and secondary metabolisms. The chemotypes regarding anthocyanin production in Perilla frutescens var. crispa, were subjected to the study on intra-species diversity. The structural genes and the regulatory genes involved in anthocyanin biosynthesis were isolated and their expression in red and green forms was determined by Northern blot analysis. The expression of all structural genes examined was co-ordinately regulated in form-specific manner and by light illumination. The anthocyanin production was enhanced in transgenic plants over-expressing Myc homologue genes from perilla. These results suggested that a protein complex including bHLH factors might regulate the expression of a series of structural genes. Additionally, cDNAs coding anthocyanin 5-O-glucosyltransferase and anthocyanidin synthase were isolated and characterized using recombinant proteins for the first time. In conclusion, it was indicated that the molecular biological techniques are powerful tools for the investigation of diversity and regulation of and for the genetic engineering of secondary metabolism in medicinal plants.
1 0 0 0 OA 沖縄本島サキタリ洞遺跡の調査
- 著者
- 山崎 真治
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.2_42-2_47, 2020-02-01 (Released:2020-06-26)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 広島大学における大学改革の思想と現状 教養部改革案を中心として
- 著者
- 山崎 真秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.319-330, 1970-01-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 ウマの情動をその表情から推察するアンケート調査
- 著者
- 青山 真人 山崎 真 杉田 昭栄 楠瀬 良
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産學會報 = The Japanese journal of zootechnical science (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.8, pp.J256-J265, 2001-04-25
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
馬術愛好家や職業として日頃ウマに接している人達はウマの表情からその情動をどの程度推察できるか,また,彼らはウマの顔のどの部位を手がかりとしてその情動を判断しているのかを調査した.調査は,ウマの顔の写真のみからその置かれている状況を推察し,さらに顔のどの部位を手がかりとしてその判断を下したかを答えるアンケート形式で行った.その結果,日頃ウマに接している人達143名の平均点は53.5点(全問正解の場合100点)であり,ウマに接する機会が少ない人達111名の平均点(39.4点)よりも有意に高かった.このことから,日頃ウマに接している人達は,ウマの顔の写真のみからその置かれている状況をある程度推察できるものと考えられた.ウマに接している人達が,状況を推察する際に手がかりとしてもっとも多く観察していたのは耳であり,さらに,高い正解率(55点以上)であったグループは正解率の低いグループ(55点未満)と比較して,耳を観察した回数が有意に多かった.これまでの文献から,耳はウマの感情がもっとも顕著に現れる部位とされているが,日頃ウマに接している人達は経験からそのことを知っていることが示された.しかしながら,異なる状況下であっても,ウマの耳の向きや角度が類似していたり,ほとんど同じである場合もあり,耳のみからでは正確な判断が難しい状況があることも示された.その場合には耳に注目すると同時に,他の部位やそのウマに関わっている他のウマの表情など,別の手がかりをあわせて指標とし,総合的に判断することが有効であると考えられた.