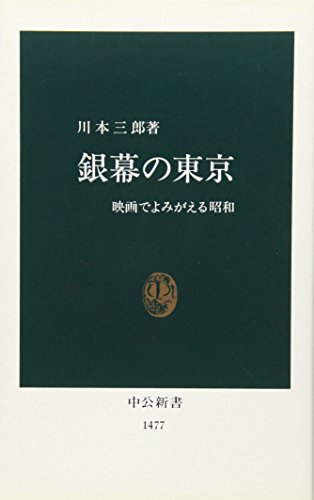1 0 0 0 日露戦争国民的後援演説集
- 著者
- [堀口多翀著] . [橋本宗吉著] . [川本幸民著] . [山本錬三郎著]
- 出版者
- 恒和出版
- 巻号頁・発行日
- 1978
1 0 0 0 OA 研究者の科学コミュニケーションに関する意識差と環境差
- 著者
- 川本 思心
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 巻号頁・発行日
- 2014-09 (Released:2015-07-01)
1 0 0 0 近赤外分析法を用いた暖地型牧草ブラキアリアグラスの飼料成分推定
- 著者
- 安里 直和 幸喜 香織 蝦名 真澄 甘利 雅拡 大森 英之 川本 康博 島袋 宏俊
- 出版者
- 日本草地学会
- 雑誌
- 日本草地学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.148-153, 2017
<p>近赤外分析法を用いて,ブラキアリアグラス(8品種,192点)の飼料成分について検量線を作成した。192点のサンプルのうち,128点のサンプルを検量線作成用試料,残りの64点を検定用試料とした。作成した検量線の精度は,相関係数(r),推定誤差の標準偏差(SDP)およびEI値を用いて評価を行った。部分最小二乗法(PLSR)における,水分,粗タンパク質(CP),粗繊維(CF),中性デタージェント繊維(NDFom),酸性デタージェント繊維(ADFom),酸性デタージェントリグニン(ADL)および乾物消化率(IVDMD)のrは0.91-0.99と高く,SDPについては,0.25-2.38と低かった。また,EI値については,水分およびCPについてAランク,その他の成分についてはBランクと良好な結果が得られた。以上のことより,ブラキアリアグラスの飼料成分およびIVDMDについて,近赤外分析法にて迅速かつ精度高く推定できる結果となった。</p>
1 0 0 0 亜熱帯地域における褐毛和種去勢牛周年放牧肥育に関する環境影響評価
<p>亜熱帯地域における周年放牧肥育生産システムに対して、ライフサイクルアセスメント(LCA)による環境影響評価を実施した。沖縄県石垣地域で行われた集約輪換放牧による褐毛和種去勢肥育生産を評価対象とし、補助飼料として、国内産副産物飼料(ビール粕・砕米)を活用した完全混合飼料(TMR)を給与した生産システムを想定した。機能単位は増体重1 kg あたりとし、エネルギー消費、地球温暖化、酸性化、富栄養化への影響を算出した。評価の結果、想定した生産システムにおいて、副産物飼料の利用により飼料生産・飼料輸送による環境影響を軽減できる一方、放牧地管理がいずれの環境影響項目においても環境影響の大きな割合を占めるということが示唆された。これは、肥育を目的として高生産性を目指した放牧地への多大な施肥により、環境影響が増大したためであると考えられた。副産物飼料からの環境影響の扱い方として、経済アロケーションまたは重量アロケーションを用いた場合、および廃棄物とみなした場合の3 通りを検討した結果、重量アロケーションを用いた場合では、経済アロケーションおよび廃棄物とみなした場合より、エネルギー消費が大きい結果となった。</p>
- 著者
- 織井 弘道 森谷 良智 難波 幸一 海老原 直樹 川本 和弘 伊藤 公一 村井 正大
- 出版者
- 特定非営利活動法人日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.495-502, 1997-12-28
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
本研究は,チタン製インプラントにプラークや歯石が付着した場合を想定し,日常臨床で用いられている種々の清掃法によってチタン表面を処理し,それが培養細胞の初期付着に対してどのような影響を及ぼすのかについて検討したものである。実験材料として,チタンを99.5%以上含むチタン板を実験に供試した。チタン表面にプラークや歯石が付着したことを想定し油性マジックを塗り,それを手用キュレット型スケーラー(HSc),超音波スケーラー(USc),歯面研磨装置(QJ),ラバーカップ(RC:歯面研磨剤を併用),プラスチックスケーラー(PSc)で除去した後の表面粗さ(中心線平均粗さ)を計測した。なお,未処理のチタン板をコントロール(C)とした。次に,そのチタン板を滅菌後,チタン表面にヒト歯槽骨由来骨芽細胞およびヒト歯肉線維芽細胞を播種し,通法に従い3, 6, 12および24時間培養を行い,走査電子顕微鏡により付着細胞数のカウント,細胞形態の観察を行った。その結果,チタン板の表面粗さには,HSc-QJ, HSc-RC, HSc-PSc, HSc-C, USc-QJ, USc-RC, USc-PSc,およびUSc-C間において統計学的有意差が認められた(p<0.05)。走査電子顕微鏡観察によると,HSc, UScによって処理したチタン板上の細胞はCと比較して発育が悪く,付着細胞数も減少傾向にあった。QJでは付着細胞数において減少傾向が見られたが,細胞形態自体にはさほど影響は見られなかった。RC, PScでは細胞形態,付着細胞数ともに良好な結果が得られた。よって,in vitroにおいて,培養細胞の付着様相は粗いチタン表面よりも,平滑なチタン表面のほうが良好であることから,チタン表面がプラークで汚染された場合の清掃法として,プロフィーペーストとラバーカップの併用あるいはプラスチックスケーラーによる方法は,有効であることが示唆された。
1 0 0 0 IR 情報リテラシー教育におけるWebテキストの導入効果について
- 著者
- 川本 勝 Masaru KAWAMOTO 尚美学園大学総合政策学部非常勤
- 雑誌
- 尚美学園大学総合政策研究紀要 = Bulletin of policy and management, Shobi University (ISSN:13463802)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.127-158, 2013-03-31
教科書の補足に大学のGoogle サイトにWebページで制作したWebテキストを用いてハイブリッドな授業を行った。その結果、以下の事が判った。受講生のWebテキストへの評価は良好である。特に、「いつでも、家でも、何度でも、自分のペースで見る事が出来る」事を評価している。そして、授業はWebテキストだけでも良いと認めている。授業が難しいと感じている受講生は、Webテキストがとても良いと感じている。しかし、課題量が多いと感じている受講生は、Webテキストがそれ程良いとは感じておらず、課題点も良くない。従って、Webテキストで、WORD文書の編集機能と課題の説明をより充実させる事が求められている。以上の結果から、Webテキストの利用は学生にも好評で、その内容をより充実させればより大きな効果が得られる事が判った。A hybrid class is performed by using a Web-text for the supplement of the textbookwhich is maked by the Web-page on the Google-site of our university. As the results, the follows are resolved. The evaluation of students about the Web-text is good. Especially,it is recognized that the Web-text is able to be looked again and again anytime at own pace, also in each home by them. And, they recognize that it is enough for the class to use only the Web-text. The student who feels that the class is difficult also feels that theWeb-text is very good. But, the student who feels that there is much quantity of problemdoes not feel the same, and, can not get good results.So, further more explanations in the details about the editing functions of the WORD document and about the problems are required in the Web-text. From the above results, it is resolved that the use of the Webtextis popular with my students and a bigger effect will be provided, if the contents ofthe Web-text are developed more.
1 0 0 0 IR 日本語の象徴語の語源--特に南島諸語に関連して-2-
- 著者
- 川本 崇雄
- 出版者
- 奈良教育大学
- 雑誌
- 奈良教育大学紀要 人文・社会科学 (ISSN:05472393)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.p1-16, 1975-11
Some of the most interesting etymologies in this part may be the following: kaka IV kaQ '(fly) into a rage', kaQkaQ, kaNkaN'(of the sun) exceedingly bright, (of a person) in a rage, (of charcoal) red-hot', hoka-hoka, poka-poka 'pleasantly warm', maQka, maQkaQka 'bright red', aka 'red' ; OJp. kaka-yaku 'to shine brightly' : -PJp. (k)AKA 'red-hot' PEOka, kaka, pukaka'red-not' : Ma. ka 'to burn, to take fire', kaka 'red-hot', Fu. kaka 'to shine', Mar.kaka 'yellow, red', To. kakaha 'to glow with heat,to be red-hot, (of anger) to flare up', Sa., Ma. pukaka, pokaka 'hot' pai pai-pai, oQpai 'the breast', OJp. FaFa 'mother' < *papai : PJp. PAYL 'motherhood' PAN bayi 'Mutter' : Tg. babayi 'Frau, Weiblichsein' ; Ja. bayi 'Saugling' sio sio-sio (OJp. siFo-siFo) 'in low spirits, sadly', siQpori 'pleasantly wet', siwo-reru, sibo-mu 'to wither', OJp. niFo-dori'grebe (=a diving bird)', simo 'lower part ', nisi 'west'(prena salized) *sisi(po) : -PJp. SI(M)PO, SIMO, NIPO, NISI 'down into water' PEO (n)sipo, sisipo 'down, to bow down, (of the sun) to set,to go into the water, west, unfortunate'. [N.B. PJp. saku 'to bloom', sakayu 'to prosper', sakari 'the prime' , saki 'happiness' and PJp. agu 'to lift, to get out of water', Okinawa agari 'east' correspond to PEO (n)sake 'up, to lift, to go up from the sea, (of the sun) to rise, to elevate in rank of power or dignity, east'. ]
1 0 0 0 1132507 走り高跳び学習の適時期に関する研究
1 0 0 0 OA 生物が関与して生成した鉄鉱石:群馬鉄山産鉄鉱石(goethite)のTEM観察
- 著者
- 赤井 純治 川本 光基 赤井 くるみ
- 出版者
- 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 鉱物学雜誌 (ISSN:04541146)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.93-97, 1996-05-31 (Released:2009-08-11)
- 参考文献数
- 11
Iron ores and mineral spring water from Gumma Iron Mine were examined mainly by TEM. Biomineralization was found on diatom and bacteria in the spring water, and also on living moss. Aggregates of cyanobacteria-like fossils were found in some iron ore which is composed of goethite and jarosite. They were examined by EPMA and TEM (lattice imaging). The formation mechanism of iron ore was discussed and biogenic contribution to the ore formation was suggested.
1 0 0 0 アカデミー賞 : オスカーをめぐる26のエピソード
1 0 0 0 銀幕の東京 : 映画でよみがえる昭和
1 0 0 0 OA 文化財の修復に用いられる接着剤の劣化
- 著者
- 植田 直見 川本 耕三
- 出版者
- マテリアルライフ学会
- 雑誌
- マテリアルライフ学会誌 (ISSN:13460633)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.89-93, 2005-07-31 (Released:2011-04-19)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA CFD解析を用いた超音速風洞流路流れの可視化
- 著者
- 野村 陵 川本 英樹 吉田 秀則 米田 武史 青木 茂
- 出版者
- 社団法人 可視化情報学会
- 雑誌
- 可視化情報学会論文集 (ISSN:13465260)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.10, pp.72-77, 2005 (Released:2005-10-31)
- 参考文献数
- 10
高解像度圧縮性CFD解析コードを用いて超音速風洞流路流れの可視化を行った.CFD解析結果の可視化は,流れ方向の気体の密度勾配分布に基づいた仮想的なシュリーレン光学画像処理手法を用いて行った.ここでは,以前に考案した超音速風洞流路流れの特性を利用した最適化手法によるノズル形状の最適化結果を例として,最適化前後のCFD解析結果を可視化し,風洞測定部の気流の変化を確認した.可視化によって,風洞流路内の一様流れ中に発生する微小な圧力波を良く捉えることができ,最適化による風洞測定部の圧力波のわずかな変化を確認することができた.このような可視化手法が微小な圧力波を評価する上で有効な手法であることが判明した.
1 0 0 0 女性のVDT作業姿勢に対応したむくみ軽減オフィスチェア
- 著者
- 川上 慶 川本 貴志 山崎 信寿
- 出版者
- 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 = The Japanese journal of ergonomics (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.252-260, 2007-10-15
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 高温高圧実験による沈み込むスラブ由来流体の化学組成の理解
1 0 0 0 OA 多数の円形高エコー病変を肝内に認めた晩発性皮膚ポルフィリン症の1例
- 著者
- 川本 智章 井戸 健一 人見 規文 磯田 憲夫 大谷 雅彦 木村 健 望月 真 広田 紀男 近藤 雅雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.241-246, 1989-02-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2 3
症例は49歳,男性.昭和58年,肝機能障害を指摘された.昭和62年4月,当科を受診し,多発性の高エコー病変を指摘され入院.既往歴として25歳時,輸血歴がある.39歳より糖尿病を指摘され,Glibenclamideを内服している.飲酒歴はビール1本/日,30年間.入院時,皮膚症状はなく,軽度の肝機能障害を認めた.腹腔鏡検査では軽度の白色紋理と小陥凹を認め,多数の円形~地図状の暗紫青色病変がみられた.超音波腹腔鏡にて同病変は高エコーに描出された.紫外線照射により,生検標本の暗紫青色部に,淡い赤色蛍光がみられた.生検組織像はchronic persistent hepatitisであり,暗紫青色部には脂肪変性を認めた.ポルフィリン体の分析では,尿中ウロポルフィリン,及び7-カルボキシルポルフィリンの増加を認め,皮膚症状を欠く晩発性皮膚ポルフィリン症と診断された.本症例の確定診断には,腹腔鏡検査,及び超音波腹腔鏡画像誘導下の狙撃生検法が極めて有効であった.
1 0 0 0 IR 遼金における正統観をめぐって--北魏の場合との比較
- 著者
- 川本 芳昭
- 出版者
- 九州大学大学院人文科学研究院
- 雑誌
- 史淵 (ISSN:03869326)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, pp.77-102, 2010-03
1 0 0 0 IR 前近代における所謂中華帝国の構造についての覚書 : 北魏と元・遼、および漢との比較
- 著者
- 川本 芳昭
- 出版者
- 九州大学大学院人文科学研究院
- 雑誌
- 史淵 (ISSN:03869326)
- 巻号頁・発行日
- vol.151, pp.1-40, 2014-03
1 0 0 0 維新東遊期における潘佩珠の思想--ヴェトナム民族運動の起点
- 著者
- 川本 邦衛
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 思想 (ISSN:03862755)
- 巻号頁・発行日
- no.584, pp.140-154, 1973-02