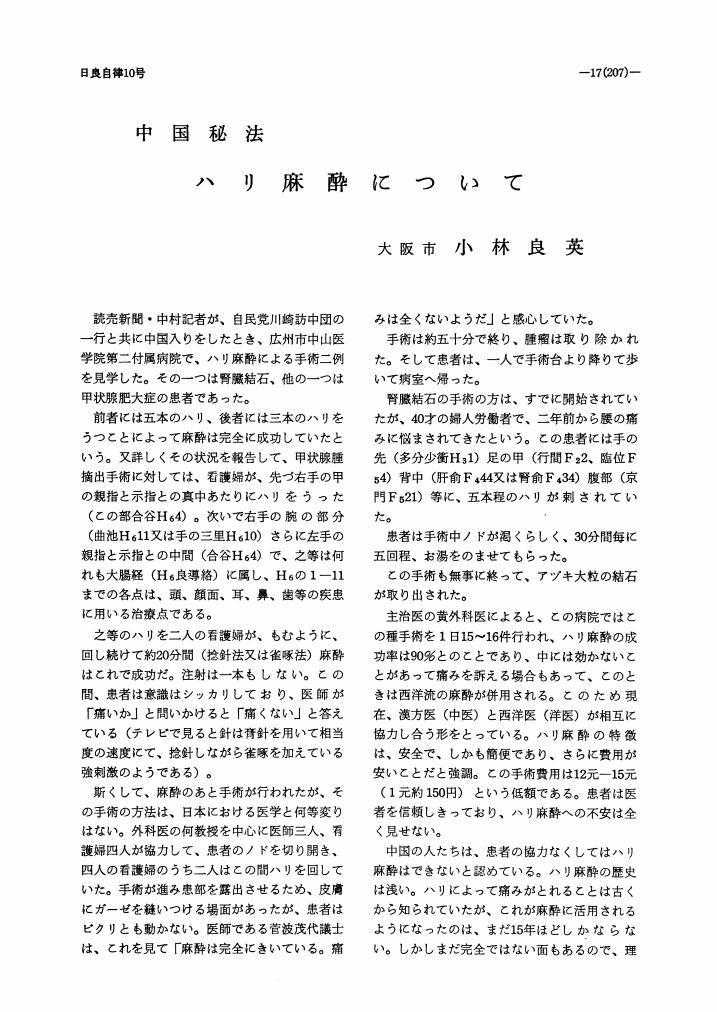- 著者
- 林 良太 黒田 健治 田中 宏明 稲富 宏之
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.231-238, 2020-04-15 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 14
本報告の目的は,自傷行為を繰り返すうつ病患者に対して,多職種協働の中でストレス対処行動獲得のために実施された作業療法の効果を検討することである.症例はうつ病患者で,自傷行為がストレス対処行動として用いられていると考えた.多職種協働の介入目標を「自傷行為の減少」として,作業療法では,新しいストレス対処行動の獲得,ストレス要因の改善,ストレス要因に対する症例のとらえ方に介入した.その結果,自傷行為は減少し,新しいストレス対処行動の獲得を認めた.多職種協働の中で,ストレス対処行動の形成化,ストレス要因の改善,認知的柔軟性を獲得し,日常的に実践可能となるような介入により自傷行為の減少に繋がる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 他出子との共同による農山村集落維持活動の実態
- 著者
- 小林 悠歩 筒井 一伸
- 出版者
- 農村計画学会
- 雑誌
- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.320-327, 2018-12-30 (Released:2019-12-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3
The purpose of this study is to reveal the characteristics of activities for maintaining rural community by collaboration with non-residents of family members by focusing on the case of Nishiotaki, Iiyama City, Nagano Prefecture. As a result of our survey, it was revealed that there are three types of way non-residents of family members are involved with community activities: participation in only recreational activities; participation in only required activities; and participation in both recreational and required activities. It was also found that year after year, the number of the non-residents who are involved with community events or associations has increased, but the number of them is limited, because some of them have more than one role in the community and all of them are not interested in the community activities. Therefore, it is necessary to think to involve non-residents who are not family members in the community activities.
- 著者
- 竹林 尚恵 谷口 としえ 端 千づる
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.315-321, 2020 (Released:2020-06-01)
- 参考文献数
- 11
咀嚼・嚥下が困難な入院患者、老人福祉施設・介護保険施設療養者に対応した食種名と形態の実態について調査するため、福井県内の病院114カ所、老人福祉施設・介護保険施設181カ所の管理栄養士を対象に、質問紙票による調査を実施した。質問紙票では提供可能な主食の形態と名称、咀嚼・嚥下困難な患者・療養者に対応した食種(副食)の名称と形態を尋ねた。形態については食事形態スケールとしてIスケールを用い、その中からの選択とした。回答が得られた159カ所のうち、咀嚼・嚥下に対応した食事が必要な対象者がいないと回答した施設を除いた148カ所を解析対象とした。病院・施設での咀嚼・嚥下困難な患者・療養者に対応した食事は、主食、副食共にさまざまな名称が使用されていた。特に副食については、名称が主食に比べて多様であった。そのため、同一の名称が異なる形態を表している場合があること、病院と施設間で使用している名称のずれが大きいことが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 固体電解質LixLa(1-x)/3NbO3のバルク単結晶
- 著者
- 藤原 靖幸 太子 敏則 干川 圭吾 小浜 恵一 胡 肖兵 小林 俊介 幾原 裕美 Craig Fisher 幾原 雄一 射場 英紀
- 出版者
- 日本結晶成長学会
- 雑誌
- 日本結晶成長学会誌 (ISSN:03856275)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.46-1-04, 2019 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 22
Bulk single crystals of the perovskite LixLa(1-x)/3NbO3, which is one of the materials used as the solid electrolyte in all-solid lithium-ion batteries, have been grown for the first time by the directional solidification method. The ionic conductivity measured in the growth direction of the single crystal wafer of LixLa(1-x)/3NbO3 and the anisotropy of ionic conduction in solid electrolyte were experimentally confirmed for the first time by using LixLa(1-x)/3NbO3 single crystals. Here, the results of four experiments on LixLa(1-x)/3NbO3 bulk single crystals are presented: (1) growth of solid electrolyte LixLa(1-x)/3NbO3 bulk single crystals, (2) ionic conduction in LixLa(1-x)/3NbO3 single crystal, (3) anisotropy of ionic conduction in LixLa(1-x)/3NbO3 single crystal and (4) microstructure analysis of LixLa(1-x)/3NbO3 single crystal.
1 0 0 0 OA Empathizing-Systemizing モデルによる性差の検討
- 著者
- 若林 明雄 バロン-コーエン サイモン ウィールライト サリー
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.3, pp.271-277, 2006-08-25 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 15 27
Empathizing is a drive to identify another person's emotions and thoughts and respond to them appropriately. Systemizing is a drive to analyze systems or construct systems. The Empathizing-Systemizing (E-S) model suggests that these are major dimensions in which individuals differ from each other, and women being superior in empathizing and men in systemizing. In this study, we examined new questionnaires, the Empathy Quotient (EQ) and the Systemizing Quotient (SQ). Participants were 1 250 students, 616 men and 634 women, from eight universities, who completed both the EQ and SQ. Results showed that women scored higher than men on the EQ, and the result was reversed on the SQ. Results also showed that humanities majors scored higher than sciences majors on the EQ, and again the result was reversed on the SQ. The results were discussed in relation to the E-S theory of gender differences.
1 0 0 0 OA グリセリン浣腸により直腸穿孔と溶血をきたした一症例
- 著者
- 島田 能史 松尾 仁之 小林 孝
- 出版者
- 新潟医学会
- 雑誌
- 新潟医学会雑誌 = 新潟医学会雑誌 (ISSN:00290440)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.1, pp.17-20, 2004-01
症例は60歳女性.右乳癌の診断にて入院した.手術当日グリセリン浣腸施行中に強い疼痛を訴え,その後も強い肛門部痛と嘔吐が持続した.臀部は腫脹し,肛門内から少量の出血を認めた.直腸診で直腸粘膜の欠損を触知し,浣腸時の直腸穿孔およびグリセリン液の管腔外注入が考えられた.浣腸後から自尿は無く,約10時間後の導尿では少量の血尿が得られた.補液と強制利尿にも反応無く,翌日急性腎不全と診断し,血液透析を開始した.計3回の血液透析で,腎機能は利尿期を経て約2週間後に正常に回復した.臀部の発赤,腫脹も受傷10日目には自然に消失し,直腸周囲での膿瘍形成も無かった.本症例は高濃度のグリセリン液が血中に入ったことにより,赤血球の膜障害と溶血が起こり,急性腎不全を引き起こしたと考えられた.以前より高濃度のグリセリンが血中に入ると溶血を起こすことは広く知られている.グリセリンが溶血を起こす機序については,赤血球の膜障害による高度の溶血が原因として推測されている.溶血が起こると大量の遊離ヘモグロビンが発生し,尿細管上皮内に再吸収されヘムとグロビンに分解される.ヘムは細胞毒として作用するため腎不全が発生するとされている.腎不全発生を予防するためには,遊離ヘモグロビンの除去が重要とされる.遊離ヘモグロビンは大分子物質であるため,その除去には血漿交換が有効と考えられている.また,遊離ヘモグロビンと結合し肝臓に運び処理するハプトグロビン投与も有効とされている.グリセリン浣腸時に患者が疼痛や気分不快および強い疼痛等を訴えた場合には,浣腸による直腸粘膜の損傷や穿孔の可能性がある.さらに腸管外へのグリセリン液注入は溶血から急性腎不全を発症する場合もあり,注意深い観察と迅速な対応が必要である.
1 0 0 0 OA 呼吸器疾患の理学療法
- 著者
- 林 積司 上西 啓裕 吉富 俊行 成川 臨
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法のための運動生理 (ISSN:09127100)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.209-216, 1989 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 10
胸部外科における心肺疾患患者の肺理学療法目的は、術前、術後の呼吸機能低下が原因で出現する種々の合併症予防と換気効率低下改善にある。術前において最も重要なことは、患者及び家族教育であり、呼吸訓練の重要性を理解してもらうことは肺理学療法の目的達成のポイントとなり得る。次は、術前、術後の全身状態が非常に異なることを念頭に置き、患者が普段から意識しなくても腹・胸式呼吸パターンが行える様に指導する。最後に、術前、術後の呼吸音を聴診することで、これは術後背臥位期間中の外側肺底区・後肺底区の聴診は異常呼吸音の早期発見につながるからである。
1 0 0 0 つわりの症状と栄養摂取および妊娠中体重増加量との関連
- 著者
- 阿部 惠理 小林 実夏
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.30, pp.380-384, 2020
- 被引用文献数
- 1
<p> 妊娠期は母子の健康のために適切な食生活を営み体重増加量を管理しなければならない.つわりは妊娠期の食生活に影響を与える要因のひとつである.母子の健康の観点からは食事摂取量の減少やつわりの悪化した妊娠悪阻に注意が払われる.しかし,吐き気を緩和させるために食事を頻回摂取するいわゆる食べつわりの症状に着目した報告は少ない.本研究では食べつわりも含めたつわりの症状と栄養摂取および妊娠中体重増加量との関連を明らかにすることを目的とした.</p><p> 対象の日本人妊産婦154名(35.2±3.7歳,妊娠前BMIは20.1±2.3)をつわりの症状別に食べつわり群,変化なし群,吐きつわり群の3群に分類した.各群の妊娠初期・中期の栄養摂取状況,および妊娠中体重増加量を比較した.その結果食べつわり群は他の2群と比較し,妊娠中体重増加量が有意に多かった.妊娠初期における3群のエネルギー摂取量は吐きつわり群が少なく有意差があった.妊娠中期には吐きつわり群のエネルギー摂取量は初期と比較し有意に増加し,3群間の有意な差はなかった.</p><p> つわりは生理的な現象であり悪阻以外は臨床的に重要視されにくいが,つわりの影響で妊娠初期の段階で食事摂取量が増した者はその後の体重管理に注意を払う必要性があると示唆された.</p>
1 0 0 0 OA 韓国の鉄スクラップ需要予測
- 著者
- 玉城 わかな 五十嵐 佑馬 藤巻 大輔 林 誠一 友田 陽 松野 泰也 長坂 徹也
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.5, pp.340-345, 2006-05-01 (Released:2009-06-19)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 6 6
1.91 milliont of steel scrap was exported from Japan to Korea in 2003, which accounted for more than 30% of the total steel scrap exported to other countries from Japan. Change in steel scrap demand in Korea in the future will make a great influence on the amount of Japan's steel scrap domestic consumption and export. In this work, quantitative data about the steel production, steel scrap demand and consumption during 1977-2003 in Korea were collected to analyze the amounts of inhouse, industrial and obsolete scrap generation, and total steel accumulation in Korea. Then, the steel scrap demand in Korea in the future was estimated. The total accumulation of steel in Korea was estimated as 380 million t in 2003 and 548 million t in 2010, respectively. The amount of obsolete scrap generation in Korea was 7.1 million t in 1996 and 9.0 million t in 2003, which was about 3.0% and 2.4% of the total steel accumulation in each year. Supposing that the amount of crude steel production, scrap consumption percentages in B.O.F and E.A.F will be stable, the obsolete scrap generation in Korea in 2010 were estimated as 13-17 million t. This significant increase in obsolete scrap generation in Korea could exceed the current amount of the scrap import. So, self-sufficiency of steel scrap could be achieved in around 2010 in Korea.
1 0 0 0 マリコのゲストコレクション(836)宇都宮健児 弁護士
1 0 0 0 OA ハリ麻酔について
- 著者
- 小林 良英
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本良導絡自律神経雑誌 (ISSN:05575729)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.10, pp.207-209, 1971-10-30 (Released:2011-10-18)
1 0 0 0 OA 経鼻胃管挿入時に徐脈をきたした1症例
- 著者
- 藤原 勇太 岸本 朋宗 平林 政人 土井 克史
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.21-24, 2017-01-15 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 10
症例は83歳の男性で,盲腸腫瘍の診断にて腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術が予定された.既往に両側緑内障があり,右眼は失明していた.麻酔導入はフェンタニル200μg,プロポフォール50mg,ロクロニウム40mgで急速導入し,経口挿管を行った.その後,経鼻胃管を鼻腔内に挿入すると心拍数50/minから15/minへと高度の徐脈となり,挿入操作中止すると心拍数42/minに回復した.本症例では三叉神経-心臓反射(trigemino-cardiac reflex:TCR)の可能性が考えられた.経鼻胃管挿入時には,TCRにより徐脈をきたす可能性があることを念頭に置くことが重要である.
- 著者
- 小林 茂樹
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.134-142, 2012 (Released:2012-05-30)
- 参考文献数
- 22
Many drugs for glaucoma treatment have recently been developed, but prostaglandin (PG) analogs, which are PGF2α derivatives, are used most frequently. In particular, PG analogs with a stem name of "-prost" have become first-line therapies. When using PG analogs, it is important to understand their chemical structures and characteristics. These PG analogs are biologically active in carboxylate forms and are formulated as prodrugs by esterifying the terminal carboxyl to reduce side effects. The effect of PG analogs on glaucoma is determined by the degree of affinity to prostaglandin FP receptors. the structural formulae of PG analogs and our experimental results suggest that a 15-difluoro PG analog (tafluprost), which has a 13, 14 double bond, would have greater affinity for prostaglandin FP receptors and greater stability than 15-hydroxy PG analogs. Furthermore, 15-difluoro PG analogs containing a 13, 14 double bond were effective in clinical studies. Experimental results have shown that 15-difluoro PG analogs could help improve blood flow in the eye and might reduce the side effect of pigmentation. Tafluprost has been considered the best PG analog for first-line therapy, but a series of new glaucoma eye drops containing 2 active ingredients were launched in Japan in 2010. Each eye drop has advantages and disadvantages, and further studies are necessary to evaluate their clinical usefulness.
1 0 0 0 OA レストランにおける受動喫煙に関する基礎的研究
- 著者
- 坂口 淳 赤林 伸一 鍛冶 紘子 都丸 恵理
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.635, pp.39-45, 2009-01-30 (Released:2009-11-02)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 5
This paper described the distribution of contaminants (fine particle and bad smell from tobacco smoking) in the restaurant where the smoking seat and the non-smoking seat are arranged in the same space. The results are as follows; (1)When the smoking seats are in close formation near the exhaust outlet, the fine particle concentration from tobacco smoking is the lowest. (2) It is very difficult to reduce bat smell intensity to the comfortable level, where smoking seats and non-smoking seats are arranged in the same space.
1 0 0 0 OA 足趾エクササイズが足内側縦アーチに及ぼす影響について
- 著者
- 城下 貴司 福林 徹
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.397-400, 2012 (Released:2012-09-07)
- 参考文献数
- 22
〔目的〕足趾機能は重要とされているが未知な部分も多い.我々は足趾機能の臨床研究や筋電図解析を行ってきた.しかしながら足趾機能と足内側縦アーチ(MLA)の関係はわかっていない.本研究の目的は足趾エクササイズとMLAの関係を検討することである.〔対象〕健常者20名,20足,平均年齢22.5±3.6歳とした.〔方法〕被験者にはタオルギャザリングエクササイズ(TGE)と3種類の足趾エクササイズ(母趾底屈エクササイズ,2から5趾底屈エクササイズ,3から5趾底屈エクササイズ)をランダムに行い,各々の足趾エクササイズ前後にNavicular Drop (ND)を計測し比較した.〔結果〕介入前NDは4.34 mmであった,TGE後NDは4.94 mmで有意差を示さなかったが,母趾底屈エクササイズ後NDは5.25 mmで有意に低下した.2から5趾底屈エクササイズ後NDは3.07 mm,3から5趾底屈エクササイズ後NDは3.32 mmとなり各々有意にNDは低下しなかった.〔結語〕母趾底屈エクササイズはMLAを低下させた.TGEは特に変化を示さなかった.しかしながらその変化は母趾底屈エクササイズに類似した.一方で2から5趾底屈エクササイズ,3から5趾底屈エクササイズはMLAを高くする効果を示しMLAとの関係性を示した.
1 0 0 0 OA 高校野球選手の肩内外旋筋力と投球障害の関係
- 著者
- 林田 賢治 中川 滋人
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.651-654, 2005-08-10 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4
The aim of this study was to elucidate the relationbetween internal (IR) and external rotations (ER) strength of the shoulder and shoulder pain during throwing in high school baseball pitchers. Internal and external rotation strength of the shoulder were measured in 401 high school pitchers, who had attended the national inter high school baseball tournament in Japan, and the influence of internal and external rotation strength of shoulder on shoulder pain during the throwing were assessed. The average IR and ER strength were 105.3+/-32.2N and 93.1+/-28.3N. The average IR. ER, and ER/IR ratio were 1.18+/-0.22,0.98+/-0.14, and 0.92+/-027, respectively, in all pitchers. All pitchers were classified into two groups. The pain experienced group (P group), which involved the pitchers who had experienced shoulder pain during throwing prolonged more than one month within the year, included 40 pitchers, and the other group (NP group) included 361 pitchers. The IR, ER, IR ratio, ER ratio, and ER/IR ratio were compared between both groups. The ER/IR ratio of the P group was lower than that of the NP group, with a statisticaldifference by unpaired student t-test (p=0.02). Pitchers with a low ER/IR ratio tend to injure their throwing shoulder and proper ER/IR ratio could be one of important condition for throwing shoulders.
1 0 0 0 OA 五十町歩以上ノ耕地ヲ所有スル大地主ニ関スル調査
1 0 0 0 OA 歩行速度の変化と足部ウィンドラス機構の関連性について
- 著者
- 高林 知也 江玉 睦明 稲井 卓真 横山 絵里花 徳永 由太 久保 雅義
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0386, 2015 (Released:2015-04-30)
【はじめに,目的】歩行速度は,運動機能を推測するための‘バイタルサイン'とされており,歩行における重要な評価指標である。先行研究では,多くの整形疾患で歩行速度が低下することや,認知機能との関連性があることも指摘されている。さらに,Winterらは片麻痺患者を対象に歩行速度を検証し,屋外および屋内歩行レベルは歩行速度により決定されると報告した。したがって,歩行速度の低下は社会参加制約に直結する因子である。歩行速度に関与する足部機能のひとつに,ウィンドラス機構(WM)がある。WMとは,足指背屈により内側縦アーチが拳上し,蹴り出し時の推進力を生み出す機構である。しかし,歩行速度の変化とWMの関連性については現在まで検証されていない。その要因として,足指角度や内側縦アーチ挙上角度(MLAEA)の動的な定量化が困難であり,詳細な足部評価が確立していないことが挙げられる。そこで,本研究は足指角度とMLAEAを動的に評価できる3DFoot modelを用いて,歩行速度の変化とWMの関連性について明らかにすることを目的とした。【方法】対象者は健常成人男性6名とした(年齢23.5±3.8歳,身長171.2±4.6 cm,体重60.0±5.5 kg)。課題動作は通常歩行(NG:4.8 km/h),低速歩行(SG:2.9 km/h),超低速歩行(VSG:1.0 km/h)の3条件とした。歩行速度は先行研究に準じ,SGは脳卒中患者の屋外歩行,VSGは脳卒中患者の屋内歩行レベルに規定した。トレッドミル(AUTO RUNNER AR-100)にて歩行速度を設定し,課題動作を実施した。課題動作の順序は無作為に実施し,各条件で10回の成功試行を計測した。動作解析には赤外線カメラ11台を含む3次元動作解析装置(VICON MX)を使用し,サンプリング周波数100Hzにて右下腿と足部に貼付した15個の反射マーカーを計測した。データ解析にはScilab(5.5.0)を使用し,計測した反射マーカーに対し遮断周波数6Hzの2次Zero-lag butterworth low pass filterを施した。その後,足指角度とMLAEAを評価可能な3DFoot modelを構築した。母趾は足指の中でWMに最も関与するとされているため,母趾背屈角度(HDFA)とMLAEAを算出し,WMの指標とした。なお,3DFoot modelで算出されるMLAEAは低値であるほど高アーチを示す。解析区間である踵接地から爪先離地(TO)までの立脚期を100%正規化し,各被験者で課題条件毎に解析項目を加算平均した。統計は,TO時におけるHDFAとMLAEAの平均値に対し,課題条件を因子としたフリードマン検定,事後検定としてSteel-Dwass法にて解析した。また,HDFAとMLAEAの関連性を相関係数にて検証した。有意水準は5%とし,統計ソフトstatics R(3.0.0)を用いた。【結果】HDFAとMLAEAの相関関係において,NGでは強い負の相関を示し(r=-0.91),SGおよびVSGでは中等度の負の相関を示した(r=-0.50,-0.57)。TO時のHDFAにおいて,NG(34.5±5.7°)はVSG(8.0±6.7°)と比較して有意に高値を示したが(p<0.05),SG(23.1±5.0°)はNGおよびVSGと比較して有意差を示さなかった。TO時のMLAEAは課題条件間にて有意差を示さなかったが,歩行速度増加に伴い高アーチの傾向を示した(NG:159.2±3.8°,SG:164.5±4.9°,VSG:167.1±6.3°)。【考察】本研究において,歩行速度の変化とWMの間には高い関連性が存在していることが示唆された。WMは足指背屈により生じるため,足指の動きがWMのトリガーの役割を担っている。また,内側縦アーチの低下はWMが破綻するとされているため,MLAEAもWMに関与する重要な因子である。本研究において,NGのHDFAはVSGと比較して有意に増加し,MLEAは歩行速度の増加に伴い高アーチの傾向を示した。さらに,HDFAとMLAEAの相関関係は,NGにおいて強い負の相関を示した。そのため,NGはWMがより働き,SGとVSGはWMへの関与が少ない可能性が考えられた。課題条件で用いたSGとVSGは,脳卒中患者の歩行レベルに準じて規定した。本研究結果より,脳卒中患者の歩行速度を通常歩行レベルに向上させるためには,WMを考慮する必要性が示唆された。なお,本研究で用いた3DFoot modelは,他のMulti-segment foot modelと比較して再現性が高いことが確認されている。また,算出したHDFAとMLAEAは,3DFoot modelを報告した先行研究と類似した波形パターンと値を示したため,本研究結果は妥当性が高いと考えられた。【理学療法学研究としての意義】理学療法において歩行速度を向上させることは,実用的および効率的な歩行を実現するために重要な課題である。本研究の知見は,歩行動作にアプローチする上で有益な基礎情報に成り得る。