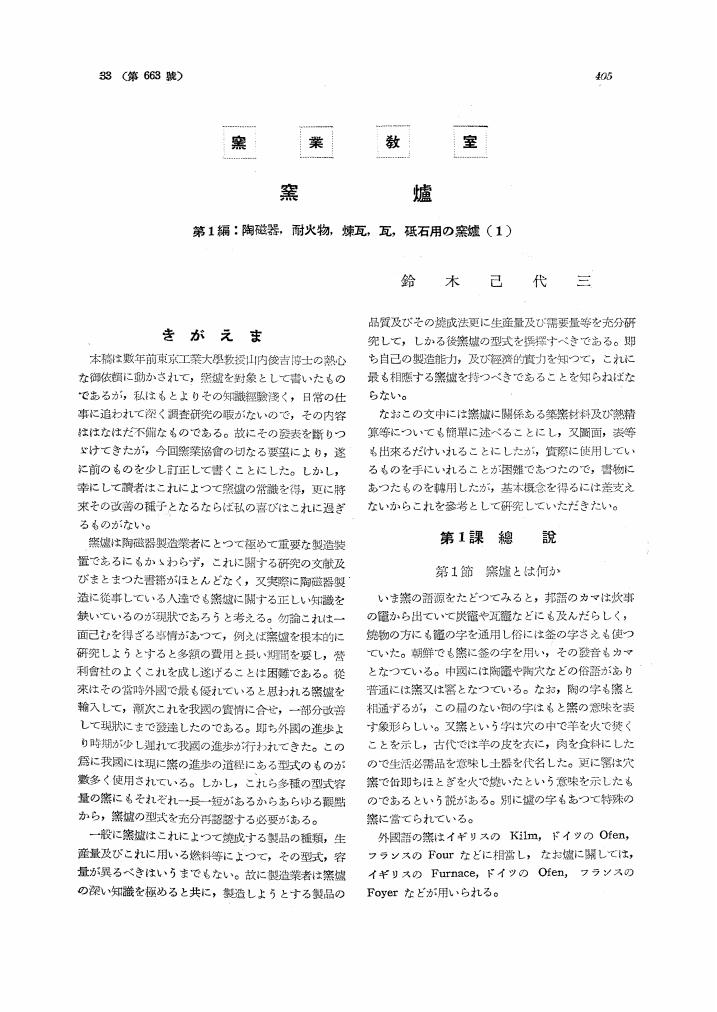1 0 0 0 OA 脊髄の運動制御機構
- 著者
- 鈴木 俊明
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-9, 2005 (Released:2006-01-26)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4
Understanding the spinal neural function is important in physical therapy for patients with neurological disease, especially the control of spasticity. We introduce our research and that of others about the spinal neural function for motor control using evoked EMG. The excitability of the spinal neural function, especially that of the spinal reflex is influenced by central and peripheral nerve function due to muscle contraction and muscle stretching at different parts. In this report, we introduce researches into the spinal reflex rearding: 1) Presynaptic inhibition in healthy and neurological diseases; 2) Excitability of the spinal neural function of an affected arm with muscle contraction of the leg in patients with cerebrovascular diseases (CVD); 3) Excitability of the spinal neural function of an affected arm at the distal part with muscle stretching of the affected arm at proximal parts in patients with CVD; and 4) Excitability of the spinal neural function of an affected arm with direct muscle stretching in patients with CVD. From these reports, it is suggested that the excitability of the spinal neural function is changed by several factors: muscle contraction, muscle stretching and others of the affected muscle and different parts.
- 著者
- 三宅 弘治 鈴木 靖夫 森田 幽
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.8, pp.680-681, 1973
- 著者
- 山寺 博史 中村 秀一 鈴木 英朗 遠藤 俊吉
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.53-56, 1997
- 被引用文献数
- 1
We experienced a 49 years old female SAD patient who showed a good response the next day after alprazolam 1.2 mg administration. The back ground EEG of the patient showed a abnormal EEG with slow waves. The personality was colored with histerical features. The nadir of body core temperature from rectum slightly delayed in remission phase compared with depressive phase. The patient became hypomania and calmed down gradually. Alprazolam tratment is seemed to be available for SAD patients. (J Nippon Med Sch 1997; 64: 53-56)
- 著者
- 鈴木 正泰 内山 真
- 出版者
- アークメディア
- 雑誌
- 臨床精神医学 (ISSN:0300032X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.7, pp.849-855, 2013-07
- 著者
- 小泉 麗 鈴木 明由実 出野 慶子 大木 伸子 本間 照子
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児看護学会
- 雑誌
- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.17-24, 2007
- 参考文献数
- 5
小児看護学実習において学生が体験した「ヒヤリハット」の場面と、学生が認識したその要因を明らかにし、小児看護学実習での事故防止に関する指導を検討することを目的に、学生107名を対象に調査を行った。その結果、学生の「ヒヤリハット」の場面は[ベッドからの転落の危険性][その他の転倒転落の危険性][外傷の危険性][ルートトラブルの危険性][状態悪化の危険性][誤飲の危険性]に分類された。また、学生が認識した要因は<安全に対する注意の欠落><安全に対する認識の甘さ><患児の精神面の影響><技術不足><運動発達の特性の認識不足><設備上の問題>に分類された。学生の過度な緊張や気の緩み、小児についての理解不足が「ヒヤリハット」の場面につながっており、学生が適度な緊張感を維持できるよう援助することや、学生が早期に患児の全体像を把握し、個別性を考慮した事故防止対策を行えるように関わることの必要性が示唆された。
1 0 0 0 小児の気道異物の取り扱い:耳鼻咽喉科の立場から
- 著者
- 鈴木 幹男
- 出版者
- 日本小児耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.22-26, 2020
<p>小児の気道異物は呼吸状態が急変することがある。搬送中に死亡する例もあり速やかな対応が必要である。小児の気道異物は0歳から3歳までに多く,ピーナッツなどの豆類が主である。誤嚥のエピソードがはっきりしておれば精査できるが咳嗽のみの症状で発見までに時間を要することがある。さらに食物異物では放射線透過性のことが多いため,原因不明の慢性咳嗽と扱われることもある。診断では,エピソードから異物を疑い,聴診や画像検査を行う。異物摘出では軟性ファイバースコープを用いて気管・気管支内の異物の位置,状態を確認してから硬性気管支鏡を挿入して摘出を行う。摘出終了後,再度軟性ファイバースコープを用いて気道内を観察し,異物断片の残存を確認する。術前の状態,術中の状況により気管切開,体外循環を用いた呼吸管理が必要な時もあるが,できるだけ低侵襲な手術操作を行うことが重要である。</p>
1 0 0 0 OA マイクロフォンアレイとロボット聴覚を用いた野鳥の歌行動観測と生態理解への試み
本研究は、マイクロフォンアレイとロボット聴覚を用いて鳥類の歌コミュニケーションを自動観測し、歌の種類と位置情報から鳥個体間で行われる歌を介した相互作用を明らかにすること、そしてその知見を野鳥の生態理解へ応用することを目的とした。当該システムの活用により、森林と草原という異なった自然環境下で、これまでの観測手法では容易に得られなかった位置情報付きの音声データの収集が実現した。さらに鳥類の音声データの収集やその解析効率、再現検証性が向上した。またこれらの音声データの解析により、観測対象種の個体間において、各個体が同時に鳴くことを避ける時間的重複回避行動が明らかになった。
1 0 0 0 OA 北海道苫小牧市を中心とせる海濱砂鐵鑛床について (I)
- 著者
- 大町 北一郎 鈴木 淑夫 早川 彰
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.154-166, 1955-08-01 (Released:2008-03-18)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 1
The field investigations of the iron beach sand deposits along the coast of the Pacific ocean from Mukawa to Horobetsu were carried out in the autumn of 1954. The iron placers occur along many shores and often produce by concentration from an elavated beach. More or less of the iron sands are seen all along many shores of the coast in the district, but the comparatively rich layers have only limited development being restricted mainly to the vicinities of Mukawa, Tomakomai, Shiraoi, Ponayoro, Noboribetsu and Horobetsu in where the last one is noteworthy and is now mined. In general the thickness of iron sand rich layers varies from 5 to 30cm, though that of the layer at Horobetsu reaches 50cm. The size of the magnetite grains is about 0.03mm in average, and the general contents of Fe and TiO2 in the iron sands are 25-45% and 2-5% respectively. The mineral and rock grains associated with the magnetite sand are hypersthene, augite, olivine, hornblende, plagioclase, biotite, quartz, garnet, ilmenite, chromite, andesite, hornfels, radioralian chert, etc. The parent source of these sand garins is probably in the adjacent volcanic rocks though some of them may be ordinarily derived from the older rock series in the Hidaka district.
1 0 0 0 IR リハビリテーション施行基準の導入 (第112回成医会葛飾支部例会)
- 著者
- 南本 新也 武石 英晃 梶原 一輝 加藤 正高 荒井 隆雄 長島 弘泰 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 又吉 由紀子 鈴木 禎 ミナミモト シンヤ タケイシ ヒデアキ カジワラ イッキ カトウ マサタカ アライ タカオ ナガシマ ヒロヤス リガクリョウホウシ サギョウリョウホウシ ゲンゴチョウカクシ マタヨシ ユキコ スズキ タダシ Minamimoto Shinya Takeishi Hideaki Kajiwara Ikki Kato Masataka Arai Takao Nagashima Hiroyasu Rigakuryohoshi Sagyoryohoshi Gengochokakushi Matayoshi Yukiko Suzuki Tadashi
- 雑誌
- 東京慈恵会医科大学雑誌 (ISSN:03759172)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.5, pp.146, 2015-09-15
1 0 0 0 OA 家族性海綿状血管腫の臨床像と予後
- 著者
- 堤 佐斗志 荻野 郁子 近藤 聡英 宮嶋 雅一 野中 宣秀 鈴木 隆元 石井 尚登 伊藤 昌徳 安本 幸正 新井 一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本脳神経外科救急学会 Neurosurgical Emergency
- 雑誌
- NEUROSURGICAL EMERGENCY (ISSN:13426214)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.14-19, 2019 (Released:2019-04-03)
- 参考文献数
- 20
脳海綿状血管腫(Cerebral cavernous malformation: CCM)は過誤腫的な血管奇形である.多くは孤発性に発生するが,一部は家族性に発症し遺伝性疾患に分類される.本研究の目的は日本人における家族性CCMの臨床像と予後を検討することである.2006年から2017年の間に当院を受診,最終的に遺伝子解析まで行い家族性CCMの診断が確定した日本人12家系,計18例の家族性CCM患者を対象とした.詳細な病歴聴取,SWIまたはT2*画像による多発CCMs確認後ELISA法を用いて遺伝子解析を行った.計18例の初発症状は頭痛5(28%),けいれん発作4(22%),感覚障害3(17%),片麻痺2(11%),構語障害1(6%),水頭症1(6%),無症候2(11%)であった.画像上CCMの多くは脳実質内の境界明瞭な低輝度多発病変として描出された.18例中11例(61%)においてCCMsは両側大脳半球,両側小脳半球,および脳幹部を含み脳実質内にびまん性に発現していた.脊髄を撮像した8例中4例で多発性CCMsを髄内に認めた.遺伝子解析の内訳は8人(44%)がCCM1変異,6人(33%)がCCM2変異,1人(6%)がCCM3変異であった.残り3人(17%)においてはCCM1, 2, 3変異のいずれも同定されなかった.変異型とCCMsの大きさ,個数の間には一定の関連はみられなかった.平均7.5年の経過観察期間中,17例に神経症状の増悪,MRI上の新規病変出現はみられなかった.家族性CCMは多くの場合良好な予後が期待できる.家族性CCMの更なる理解のためには全塩基配列を対象とした包括的遺伝子解析が必要である.
- 著者
- 鈴木 亜由子 長谷川 奉延
- 出版者
- 日本臨床社
- 雑誌
- 日本臨床 (ISSN:00471852)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.157-162, 2008-01
1 0 0 0 再発性多発軟骨炎と骨髄異形成症候群を合併した Sweet 病
- 著者
- 田﨑 典子 鍬塚 大 東 美智子 鍬塚 さやか 鈴木 貴久 波多 智子 宇谷 厚志
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.19-23, 2017
71 歳,男性。2010 年 7月,再発性多発軟骨炎を発症し,内科でプレドニゾロン 20 mg/day の内服治療が開始された。2012 年 3 月,<i>Mycobacterium intracellulare</i> による肺非結核性抗酸菌症を発症し,プレドニゾロンに加え,3 剤併用療法が開始された。2013 年 8 月,発熱と皮疹が出現し皮膚科を紹介された。皮疹は無痛性の 2 cm までの紅色結節で,頚部,上肢,体幹に散在していた。病理組織で真皮浅層から脂肪織にかけ好中球を主体とする密な細胞浸潤を認めた。一般細菌培養,真菌培養,抗酸菌培養はすべて陰性であった。以上より皮疹は Sweet 病と診断した。貧血と血小板減少のために行った骨髄穿刺にて骨髄異形成症候群も同定され,最終的に再発性多発軟骨炎と骨髄異形成症候群を合併した Sweet 病と診断した。 プレドニゾロンを増量,ステロイドミニパルスを行うも効果は一時的で浸潤性紅斑,結節の出没を繰り返し,2014 年 1 月に永眠した。本症例では約 4 カ月の間に臨床的には多彩な皮疹が出現したが,病理組織像はいずれも真皮から脂肪織に至る好中球浸潤であった。このように再発性多発軟骨炎,骨髄異形成症候群,Sweet 病の 3 者を合併する症例は過去にも報告されており,これらの症例につき文献的考察を行った。
- 著者
- 鈴木 博志 宮崎 幸恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.53-62, 1995
以上の結果は, 次のように要約される.<BR>(1) 単身世帯の男女とも, 年齢層が高くなると住宅水準の高い [マンション] や [鉄賃アパート] への住み替えが進むが, その一方で [木賃アパート] の「沈殿層」が一定程度析出されている.この「沈殿層」は, 「50歳以上」の女性に多いとみられる.若年層から高年層まで, 女性は男性より水準の高い [マンション], [鉄賃アパート] の居住が多い.いずれの住宅型でも女性の平均収入は男性より低いが, 逆に畳数水準は高く, 女性の住宅への関心の高さが伺われる.また, 長期居住による住居費の低廉化は, 高年層の女性に多く寄与している.<BR>(2) 単身世帯の現住宅に対する不満度は, 総合評価で44%と高い.各評価項目別の不満度についても同様に高いが, とくに住宅の居住空間より設備・性能に関する項目の不満度が高い.全体に女性の不満度は男性より低いが, これは現住宅の居住水準が高いことの反映でもある.住宅の評価を具体的な客観的指標 (規模, 日照, 設備水準) と照合してみると, 住宅水準が低下すると不満度が高くなる傾向が読み取れる.他方, 単身世帯の住環境に対する不満度は, 総合評価で27%と低い.各評価項目別では, 中央線沿線の立地, イメージの良さから男女とも立地の利便性や地域イメージに関する項目の不満度は低い. しかし, 居住地の安全性やアメニティに関する項目の評価では, 不満度が高く表れている.<BR>(3) 単身世帯の現住宅選択理由は, 「通勤・通学の利便性」が圧倒的に多い.二義的選択理由として, 男性は「価格・家賃が適当」の経済重視が多いが, 女性は「買物などに便利」とする日常生活の利便性を重視する傾向に分かれる.今後の住宅選択の重視項目では, 全体に「通勤・通学の便利さ」の利便性以上に, 「家賃・価格の安さ」の経済性を重視する傾向にある. [~29歳], [30歳代] では, 男女とも「通勤・通学の利便性」, 「家賃・価格の安さ」が重視されるが, [40歳代] では, 「日常生活の便利さ」, 「住宅の広さ」の比重が高くなる.高年層になると, 男性は「家賃・価格の安さ」の経済性が依然として多いが, 女性は「日常生活の便利さ」, 「住宅の設備・性能」など日常生活のしやすさを重視する傾向が強くなる.<BR>(4) 単身世帯の定住希望は, 全体で61%を占める.性別では女性の方が高い.定住希望の高い年齢層は, 男性では若年層だけであるが, 女性では若年層と高年層の両極で高い.<BR>(5) 単身世帯の住宅関連設備の要求では, 男女とも「専用の風呂」や「専用のトイレ」と最も基本的な要求であり, 「独立のキッチン」や「エアコン (冷暖房用) 」は, それにつぐ高い要求とされる。女性は, とくに住宅の安全性や生活の便利さに配慮した要求内容が多い.また, 男女とも年齢が高い層に「エレベーター装置」, 「住棟内トランクルーム」, 「衣類乾燥機付浴室」の要求がやや多い.単身世帯の住宅関連サービスの要求については, 「ゴミ処理サービス」や「セクレタリーサービス」が最も多い.「セキュリティサービス」など住宅の安全性は, 女性では若年層から高年層まで共通して多い.男女とも「ケアサービス」は, その必要性の認識が高くなる高年層に多い.
1 0 0 0 OA 窯爐 第1編: 陶磁器, 耐火物, 煉瓦, 瓦, 砥石用の窯爐 (1)
- 著者
- 鈴木 己代三
- 出版者
- 公益社団法人 日本セラミックス協会
- 雑誌
- 窯業協會誌 (ISSN:00090255)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.663, pp.405-409, 1951-09-01 (Released:2010-04-30)
1 0 0 0 IR Cherubism患児に対する口腔管理の1例
1 0 0 0 テレビの時間、元号の時間 (特集 「時間の社会学」の現代的展開)
- 著者
- 鈴木 洋仁
- 出版者
- 神戸大学社会学研究会
- 雑誌
- 社会学雑誌 (ISSN:02895374)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.159-174, 2020
1 0 0 0 OA 糖尿病患者における特異的PCR増幅法によるミトコンドリアDNA変異の検出
- 著者
- 谷山 松雄 鈴木 吉彦 榎本 詳 佐藤 温 杉田 江里 杉田 幸二郎 渥美 義仁 松岡 健平 伴 良雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.401-404, 1995-05-30 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 9
The substitution of guanine (G) for adenine (A) at positioln 3243 of mitochondrial DNA, first demonstrated in MELAS patients, has been found in some diabetics, and this mutation seems to be one of genetic factors for diabetes mellitus. Because mutational mitochondria coexist with normal mitochondria (heteroplasmy), conventional PCR-RFLPm methods may not detect a mutation When a majority of the mitochondrial DNA in leukocytes is normal. We tested the efficacy of specific PCR amplification in detecting the 3243G mutation using a primer whonse 3' base was complementary to the mutational base. This mutation-specific PCR amplification method permitted detection of the mutation in 2 patients with MELAS and in a diabetic patient whose mutation was detected by the PCR-RFLP method in biopsied muscle but not in peripheral leukocytes, and in two other diabetic patients.Specific PCR amplification for detection of the 3243G mutation is a simple and senisitive method and is useful inevaluating this mutation in diabetes mellituls.
1 0 0 0 岡田豊日先生を偲ぶ
- 著者
- 鈴木 邦雄
- 出版者
- 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.27-29, 2000
1 0 0 0 IR 環状3番染色体を持つ女性の妊娠の1例
- 著者
- 江藤 千佳 矢田 大輔 松本 雅子 飯田 瀬里香 小田 智昭 成味 恵 幸村(小林) 友希子 磯村 直美 内田 季之 鈴木 一有 伊東 宏晃
- 出版者
- 静岡産科婦人科学会
- 雑誌
- 静岡産科婦人科学会雑誌 (ISSN:21871914)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.131-136, 2019
環状第3染色体は稀な様々な表現形を呈する染色体異常であり、これまでの報告例は13例である。症例は30歳、1妊0産、身長137cm。3歳で低身長を主訴に小児科を受診し、環状3番染色体の指摘を受けた。妊娠22週に頸管無力症に対し頸管縫縮術(マクドナルド法)を行った。その後、腸閉塞、尿路外溢流を発症し、妊娠23週に皮膚腸管瘻形成術、尿管ステント挿入術を施行した。妊娠30週に陣痛発来し、妊娠30週1日、体重1726g 41cmの男児を経腟分娩した。本症例では、腸閉塞と尿路外溢流の発症の原因は妊娠子宮の圧迫であったと考えられた。低身長の妊婦が正常発育の胎児を妊娠した場合、妊娠子宮の圧迫症状のリスクに留意する必要がある。本症例が環状3番染色体を持つ女性の初めての妊娠、出産報告である。